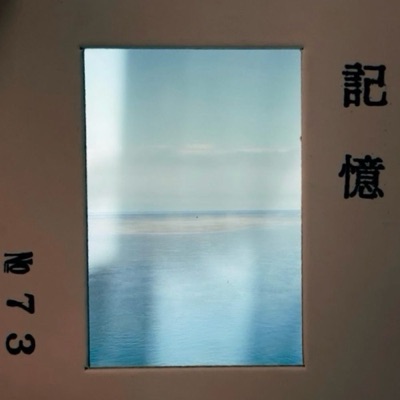他者といる技法 ――コミュニケーションの社会学 (ちくま学芸文庫)

12件の記録
 いるかれもん@reads-dolphin2025年9月27日読み終わったまた読みたいうまくまとめられないけれど面白かった。 序章で書かれている通り「他者といる技法」について、第1章では「思いやりとかけぐち」、第2章は「子の存在によって母は初めて母になる」といった相互の存在証明、第3章は外国人、第4章はリスペクタビリティ、第5章は自己啓発セミナーとそれを非難する語彙といったさまざまな観点から論じている。それぞれ独立しているので気になった論考から読んでも面白い。そして第6章は「他者を理解する」ということの葛藤について述べてまとめられている。初めて社会学という分野の本を読んだけれど、身の回りの事象を丁寧に考察していき理論を立てていく流れが読んでいてとても楽しかった。私の好きな学問かもしれない。最後の解説で各章の内容がまとめられているのでそこを立ち読みしてもらってもいいかもしれない。
いるかれもん@reads-dolphin2025年9月27日読み終わったまた読みたいうまくまとめられないけれど面白かった。 序章で書かれている通り「他者といる技法」について、第1章では「思いやりとかけぐち」、第2章は「子の存在によって母は初めて母になる」といった相互の存在証明、第3章は外国人、第4章はリスペクタビリティ、第5章は自己啓発セミナーとそれを非難する語彙といったさまざまな観点から論じている。それぞれ独立しているので気になった論考から読んでも面白い。そして第6章は「他者を理解する」ということの葛藤について述べてまとめられている。初めて社会学という分野の本を読んだけれど、身の回りの事象を丁寧に考察していき理論を立てていく流れが読んでいてとても楽しかった。私の好きな学問かもしれない。最後の解説で各章の内容がまとめられているのでそこを立ち読みしてもらってもいいかもしれない。




 いるかれもん@reads-dolphin2025年8月12日読み始めた学び!「私は「病理」や「弱者」を生む「社会」のなかにいて居心地の良さも悪さも両方感じており、その「社会」から「私」をぽっかり抜いて私がいない「社会」を問うというふるまいが、ひとつには、「私」と「社会」の絡み合った関係を誠実に問うておらず、もうひとつには、それを問わないことには、私がいま苦しんいる微妙な苦しみにとってなんら有効な答えが得られない、このふたつのことをよく知っているのだ。 「改革者」でも「弱者」でもない立場にいる人々に有効な「社会学」。私は、このような立場から出発する「社会」への問いを構想しなければならないと考える。「社会」から利益も違和よ受け取っている人々の現実を切り捨ててしまわないような問い。そのような立場の人々が感じる違和(と利益)をていねいに言葉にするような問い。」 自分が疑問に思っていたことを、とても鋭くストレートに言語化されてしまった。私にとってこの問題は雲を掴むようなものであるけれど、それを丁寧に、時に鋭く掬い取ってくれるような期待感がある。にしてもカッコで囲まれた言葉が多い。この一つ一つをこれから疑っていくのかと思うと、なかなか熱い展開になりそうな予感。読み応えありそう。読み進めるの楽しみ。
いるかれもん@reads-dolphin2025年8月12日読み始めた学び!「私は「病理」や「弱者」を生む「社会」のなかにいて居心地の良さも悪さも両方感じており、その「社会」から「私」をぽっかり抜いて私がいない「社会」を問うというふるまいが、ひとつには、「私」と「社会」の絡み合った関係を誠実に問うておらず、もうひとつには、それを問わないことには、私がいま苦しんいる微妙な苦しみにとってなんら有効な答えが得られない、このふたつのことをよく知っているのだ。 「改革者」でも「弱者」でもない立場にいる人々に有効な「社会学」。私は、このような立場から出発する「社会」への問いを構想しなければならないと考える。「社会」から利益も違和よ受け取っている人々の現実を切り捨ててしまわないような問い。そのような立場の人々が感じる違和(と利益)をていねいに言葉にするような問い。」 自分が疑問に思っていたことを、とても鋭くストレートに言語化されてしまった。私にとってこの問題は雲を掴むようなものであるけれど、それを丁寧に、時に鋭く掬い取ってくれるような期待感がある。にしてもカッコで囲まれた言葉が多い。この一つ一つをこれから疑っていくのかと思うと、なかなか熱い展開になりそうな予感。読み応えありそう。読み進めるの楽しみ。




 川@river12162025年4月17日じゅうぶん読んだ再読。おもしろいし、真っ当な「技法」そのものを教えてくれる本ではあるけれど、ときにはなぐりあったり理解の過剰/過小に苦しんだりするのも含めてコミュニケーションなんじゃないですかね、むしろそれやろうよ、とも思ってしまう。
川@river12162025年4月17日じゅうぶん読んだ再読。おもしろいし、真っ当な「技法」そのものを教えてくれる本ではあるけれど、ときにはなぐりあったり理解の過剰/過小に苦しんだりするのも含めてコミュニケーションなんじゃないですかね、むしろそれやろうよ、とも思ってしまう。