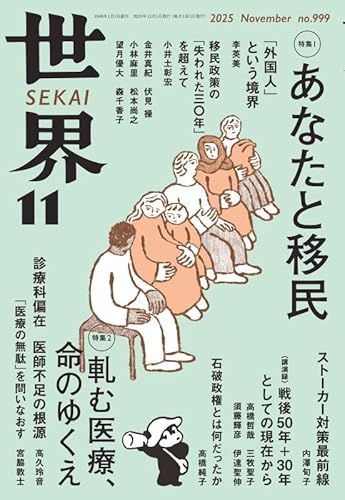ごとう
@goto
新書、話題の小説、有名な小説を中心に読みます。
- 2025年11月23日
 「倫理の問題」とは何か佐藤岳詩読み終わった「自分が良いことであってほしい」という内面的な願いと、それを「同じように考える他者と共有する」というプロセスから生まれるものとして捉えた。 つまり、倫理的な規範とは、仲間と共に築き上げていく「自分たちのルール」。 このルールの正しさを判断する基準は、まず「自分自身が重要と考えること」と「自分の考えとの一貫性」という、個人の納得感にある。 このルールが偏ったものにならないよう、自己の内省(反省)に加え、外部の規範との比較を通じて、より良いものへと絶えず改善・進化させていくことを重視する。
「倫理の問題」とは何か佐藤岳詩読み終わった「自分が良いことであってほしい」という内面的な願いと、それを「同じように考える他者と共有する」というプロセスから生まれるものとして捉えた。 つまり、倫理的な規範とは、仲間と共に築き上げていく「自分たちのルール」。 このルールの正しさを判断する基準は、まず「自分自身が重要と考えること」と「自分の考えとの一貫性」という、個人の納得感にある。 このルールが偏ったものにならないよう、自己の内省(反省)に加え、外部の規範との比較を通じて、より良いものへと絶えず改善・進化させていくことを重視する。 - 2025年11月20日
- 2025年11月17日
- 2025年11月16日
- 2025年11月14日
 プライドが高くて迷惑な人片田珠美読み終わったプライドが高くて迷惑な人は、実は満たされぬ現実に欲求不満を抱いていて、自尊心を保つのに苦労していることが多いからである。 裏返せば、それだけ自己愛が傷つくことを恐れているわけで、自慢したり、特別扱いを要求したり、他人を支配しようとしたりするのも、自己愛の傷つきから身を守るための防衛にほかならない。
プライドが高くて迷惑な人片田珠美読み終わったプライドが高くて迷惑な人は、実は満たされぬ現実に欲求不満を抱いていて、自尊心を保つのに苦労していることが多いからである。 裏返せば、それだけ自己愛が傷つくことを恐れているわけで、自慢したり、特別扱いを要求したり、他人を支配しようとしたりするのも、自己愛の傷つきから身を守るための防衛にほかならない。 - 2025年11月13日
 平成時代吉見俊哉読み終わった平成は、終わりの時代であり、始まりの時代であった。終わりというのは、人口増加の終わり、経済成長の終わり、総中流化の終わりである。裏を返せば、人口が縮減し、経済が長期的に停滞し、社会が分裂していく時代の始まりだった。
平成時代吉見俊哉読み終わった平成は、終わりの時代であり、始まりの時代であった。終わりというのは、人口増加の終わり、経済成長の終わり、総中流化の終わりである。裏を返せば、人口が縮減し、経済が長期的に停滞し、社会が分裂していく時代の始まりだった。 - 2025年11月8日
- 2025年11月6日
- 2025年11月5日
 独身・無職者のリアル~果てしない孤独~藤原宏美,関水撤平読み終わった人が求める安心感とは、単に仕事やお金、生活上の安定だけではありません。 「人に受け入れてもらえる安心感」、「ありのままの自分が愛されている安心感」、「自分がここにいてもいいんだと思える安心感」、こういった目に見えない力こそが、社会からの孤立を遠ざけて次への意欲につながる原動力になるのです。
独身・無職者のリアル~果てしない孤独~藤原宏美,関水撤平読み終わった人が求める安心感とは、単に仕事やお金、生活上の安定だけではありません。 「人に受け入れてもらえる安心感」、「ありのままの自分が愛されている安心感」、「自分がここにいてもいいんだと思える安心感」、こういった目に見えない力こそが、社会からの孤立を遠ざけて次への意欲につながる原動力になるのです。 - 2025年11月3日
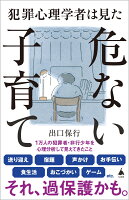 犯罪心理学者は見た危ない子育て出口保行読み終わった子どもの成長も、子育て自体も、理屈通りにはいかないもの。 一応の仮説を立てて、やりながら修正をしていくのが一番。 常に子どもの反応というフィードバックがあるから、それを見て修正する。
犯罪心理学者は見た危ない子育て出口保行読み終わった子どもの成長も、子育て自体も、理屈通りにはいかないもの。 一応の仮説を立てて、やりながら修正をしていくのが一番。 常に子どもの反応というフィードバックがあるから、それを見て修正する。 - 2025年11月3日
- 2025年11月3日
- 2025年11月2日
- 2025年11月1日
 文化が違えば,心も違う?北山忍読み終わった歴史的・地理的・社会環境によって形成された文化が、心という認知・感情・動機づけといった心理機能と、そこから成り立つ人の主体を形作る。一方で、心によって文化が動かされる。
文化が違えば,心も違う?北山忍読み終わった歴史的・地理的・社会環境によって形成された文化が、心という認知・感情・動機づけといった心理機能と、そこから成り立つ人の主体を形作る。一方で、心によって文化が動かされる。 - 2025年11月1日
- 2025年10月29日
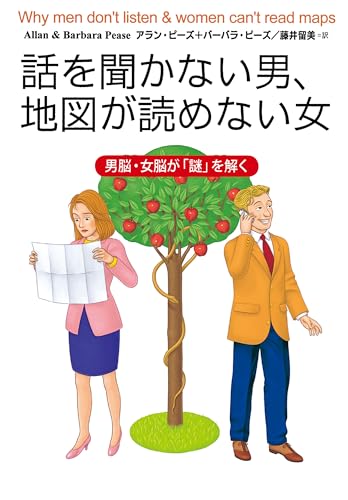 話を聞かない男、地図が読めない女アラン・ピーズ,バーバラ・ピーズ,藤井留美読み終わった女は空間能力の担当部分が脳の左右両方にあるために、それを活用するときは発話機能がお留守になる。だから市街地図を与えられた女は黙りこみ、地図を回転させるのだ。 男がナビゲーター役を女に頼むのをやめる──こうすればみんな末永く幸せに暮らせるはずだ。
話を聞かない男、地図が読めない女アラン・ピーズ,バーバラ・ピーズ,藤井留美読み終わった女は空間能力の担当部分が脳の左右両方にあるために、それを活用するときは発話機能がお留守になる。だから市街地図を与えられた女は黙りこみ、地図を回転させるのだ。 男がナビゲーター役を女に頼むのをやめる──こうすればみんな末永く幸せに暮らせるはずだ。 - 2025年10月27日
- 2025年10月26日
- 2025年10月25日
- 2025年10月16日
読み込み中...