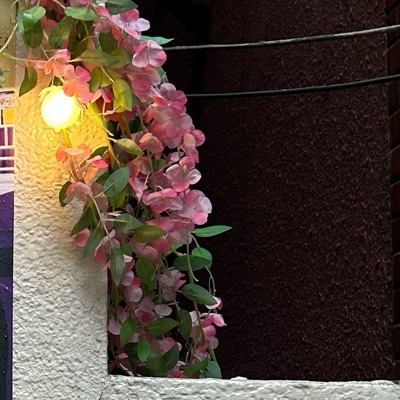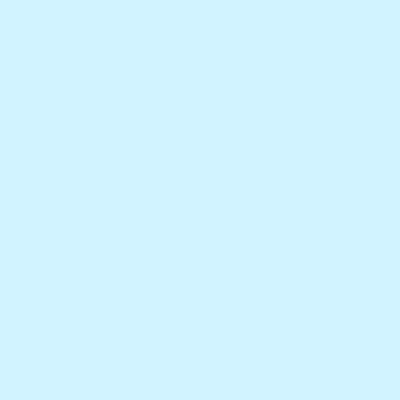ケアの物語 フランケンシュタインからはじめる

128件の記録
 隅田川@202506282026年2月23日かつて読んだaudiobook「はじめに」より だからこそ、「「今、ここ」で困っている人に手を差し出せる人は、太陽や空気や地面と同じように、この世界をどうにか存続させている基底的な条件である」(『ケアと編集』)。こう語るのは、長年にわたり医学書院の「シリーズケアをひらく」を手がけてきた編集者、白石正明である。この言葉はケアの本質を突いている。 文学は空想の産物、あるいは単なる現実逃避の手段であると考える読者はいるだろう。しかし、読書の実践は本の世界では終わらない。文学作品を読み解く力は、現実を組み替える力に変えていくことができる。本書では、メアリ・シェリーの『フランケンシュタイン』を起点にして、その実験を行なってみたい。
隅田川@202506282026年2月23日かつて読んだaudiobook「はじめに」より だからこそ、「「今、ここ」で困っている人に手を差し出せる人は、太陽や空気や地面と同じように、この世界をどうにか存続させている基底的な条件である」(『ケアと編集』)。こう語るのは、長年にわたり医学書院の「シリーズケアをひらく」を手がけてきた編集者、白石正明である。この言葉はケアの本質を突いている。 文学は空想の産物、あるいは単なる現実逃避の手段であると考える読者はいるだろう。しかし、読書の実践は本の世界では終わらない。文学作品を読み解く力は、現実を組み替える力に変えていくことができる。本書では、メアリ・シェリーの『フランケンシュタイン』を起点にして、その実験を行なってみたい。 kirakira30@kirakira302026年2月13日読み始めた〈文学は空想の産物、あるいは単なる現実逃避の手段であると考える読者はいるだろう。しかし、読書の実践は本の世界では終わらない。文学作品を読み解く力は、現実を組み替える力に変えていくことができる。〉II
kirakira30@kirakira302026年2月13日読み始めた〈文学は空想の産物、あるいは単なる現実逃避の手段であると考える読者はいるだろう。しかし、読書の実践は本の世界では終わらない。文学作品を読み解く力は、現実を組み替える力に変えていくことができる。〉II
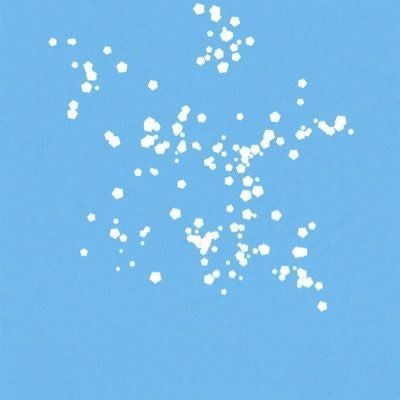 うさき@usaki_zu2026年1月31日読み終わったこれは明確に私の話だ!となる部分と今の私には理解が難しいぜ!という部分があったのだけど、とりあえず私がASDであり統合失調でありレズビアンであり虐待サバイバーでありIQ71であるものとして語ったり学問をすることには意味があるのだろうなと思った、そして左派的な"正しさ"やマイノリティのマッチョイズムにいつも置き去りにされている私のような存在に光を当てるにあたってこのようなことを学び深めていくことにもまた意味があるのだろうと思う、やるぞ、学ぶぞ、本読むぞ
うさき@usaki_zu2026年1月31日読み終わったこれは明確に私の話だ!となる部分と今の私には理解が難しいぜ!という部分があったのだけど、とりあえず私がASDであり統合失調でありレズビアンであり虐待サバイバーでありIQ71であるものとして語ったり学問をすることには意味があるのだろうなと思った、そして左派的な"正しさ"やマイノリティのマッチョイズムにいつも置き去りにされている私のような存在に光を当てるにあたってこのようなことを学び深めていくことにもまた意味があるのだろうと思う、やるぞ、学ぶぞ、本読むぞ かくり@kakuri0002025年12月21日図書館で借りた一切読めてない。SNS見るのをやめなければ一生読めないのでは… でも今は時期的にも色んな作品の一挙無料がたくさんあり、ついついそっちを優先してしまう
かくり@kakuri0002025年12月21日図書館で借りた一切読めてない。SNS見るのをやめなければ一生読めないのでは… でも今は時期的にも色んな作品の一挙無料がたくさんあり、ついついそっちを優先してしまう いずみ@moritaizumi2025年12月17日読み終わった2025年12月読了本「フランケンシュタイン」の副題「現代のプロメテウス」を、私はフランケンシュタインのことと思って読んだのだが、本書ではクリーチャーを指すとあって、そういう読み方もあるのかと驚いた。
いずみ@moritaizumi2025年12月17日読み終わった2025年12月読了本「フランケンシュタイン」の副題「現代のプロメテウス」を、私はフランケンシュタインのことと思って読んだのだが、本書ではクリーチャーを指すとあって、そういう読み方もあるのかと驚いた。

- シャガ@filifjonka2025年12月2日買った読み終わったフランケンシュタインも読みたいんだよな〜と思いながら手に取った本ながら、思いがけず進撃の巨人や僕のヒーローアカデミアなどの話題作のあらすじにも触れることができた。

- シャガ@filifjonka2025年11月17日買った読み始めた読み始め。フランケンシュタインも読んでみたいな、スキローにも取り上げられていたし。そういう、「いつか読んでみたいなあ」といった「積ん読未満」みたいな本って、振り返るとどれくらいあるんだろう。
 ごとう@goto2025年10月27日読み終わったケアを与えるという能力は、生来的に備わっていたものではなく、何代にもわたって継承されてきたものであり、努力によって自分のものにしていかなければならない
ごとう@goto2025年10月27日読み終わったケアを与えるという能力は、生来的に備わっていたものではなく、何代にもわたって継承されてきたものであり、努力によって自分のものにしていかなければならない
 いちこ@ichinics2025年10月19日2025年読了本フランケンシュタインを中心に、様々な物語についてケアの側面から読み解いていく…という本で、さまざまな物語の紹介として読むのも面白かった。 ただ「ケア」について解説する本ではないので、この本ではケアをどのように捉えているのか…という部分を探りつつ読むみたいなところもあった。
いちこ@ichinics2025年10月19日2025年読了本フランケンシュタインを中心に、様々な物語についてケアの側面から読み解いていく…という本で、さまざまな物語の紹介として読むのも面白かった。 ただ「ケア」について解説する本ではないので、この本ではケアをどのように捉えているのか…という部分を探りつつ読むみたいなところもあった。- citizen_one@citizen_one2025年10月13日読み終わったいま流行りの本。思ったより読み終わるのに時間がかかった。 著者は英文学者なので古典などに詳しいが、同時にサブカルにもかなり詳しくていったいいつ漫画など読んでいるんだろうかと不思議になった。 最近は学術✖️サブカルというテーマの本がよく売れている気がする。


 buch@wk_bucher_2552025年10月6日読んでる「〈ケアの論理〉で誤解されてきたのは、おそらくこの部分である。自分自身に対するセルフケアもケアの一環であるにもかかわらず、ケア=自己犠牲あるいは無私と考えられてきた」 224頁 身近な作品に滲むケア思想を解いていく。よみやすい
buch@wk_bucher_2552025年10月6日読んでる「〈ケアの論理〉で誤解されてきたのは、おそらくこの部分である。自分自身に対するセルフケアもケアの一環であるにもかかわらず、ケア=自己犠牲あるいは無私と考えられてきた」 224頁 身近な作品に滲むケア思想を解いていく。よみやすい はな@hana-hitsuji052025年10月4日読み終わった図書館本図書館で借りた予約待ちの本だったので少し急いで読んで返したからまた少し時間を置いて読み直したい。この本は少し前から気になってた「世界」という雑誌に掲載されたとあって、また手に取りたくなる。 トーンポリシングについて考えてる。 ただでさえ声が届きにくいために大声を出すと、声が大きいみたいにたしなめられる?の、なんだろうな。ちょっと裸の王様みたい。みんなが薄々思ってることを言ったらシー! ジェンダーギャップ指数15年1位のアイスランドで起きた「女性の休日」ウィメンズストライキの映画は私の住む街では上映なし。 観たかった!
はな@hana-hitsuji052025年10月4日読み終わった図書館本図書館で借りた予約待ちの本だったので少し急いで読んで返したからまた少し時間を置いて読み直したい。この本は少し前から気になってた「世界」という雑誌に掲載されたとあって、また手に取りたくなる。 トーンポリシングについて考えてる。 ただでさえ声が届きにくいために大声を出すと、声が大きいみたいにたしなめられる?の、なんだろうな。ちょっと裸の王様みたい。みんなが薄々思ってることを言ったらシー! ジェンダーギャップ指数15年1位のアイスランドで起きた「女性の休日」ウィメンズストライキの映画は私の住む街では上映なし。 観たかった!









 りら@AnneLilas2025年9月29日ちょっと開いた図書館本「はじめに」、「あとがき」、『哀れなるものたち』(マンスプレイングの章)のくだりのみ走り読み。 今流行りの「ケア」論の視点からの『フランケンシュタイン』読み直しの試みで、テーマごとに東西のあらゆる作品や批評等が取り上げられているものの、俎上に載せられているそれらの題材(スピヴァク、ジュディス・バトラーから、鬼滅や中居の性加害まで)があまりに多岐にわたっていて、とっ散らかっている印象が否めない。 そもそも再評価著しいメアリー・シェリーの生涯やその過小評価され続けてきた功績と「ケア」との関連については納得できるものの、『フランケンシュタイン』はそもそも「ケアの欠落」した物語(はじめに)であり、そこはちょっと読んだだけの現時点ではこじ付けに思えてしまう。 以上、通読できたらよかったのだけど、返却が迫っているため備忘録。
りら@AnneLilas2025年9月29日ちょっと開いた図書館本「はじめに」、「あとがき」、『哀れなるものたち』(マンスプレイングの章)のくだりのみ走り読み。 今流行りの「ケア」論の視点からの『フランケンシュタイン』読み直しの試みで、テーマごとに東西のあらゆる作品や批評等が取り上げられているものの、俎上に載せられているそれらの題材(スピヴァク、ジュディス・バトラーから、鬼滅や中居の性加害まで)があまりに多岐にわたっていて、とっ散らかっている印象が否めない。 そもそも再評価著しいメアリー・シェリーの生涯やその過小評価され続けてきた功績と「ケア」との関連については納得できるものの、『フランケンシュタイン』はそもそも「ケアの欠落」した物語(はじめに)であり、そこはちょっと読んだだけの現時点ではこじ付けに思えてしまう。 以上、通読できたらよかったのだけど、返却が迫っているため備忘録。 はな@hana-hitsuji052025年9月28日読んでる図書館本図書館で借りたちょいちょいシレッと全く読めない単語が出てきて手がかりないから調べられず気になって仕方ない。 あと「知ってるよね」というテイでカタカナの人名や海外の文学作品についての情報が前後ランダムにポコポコ出てくるので、食らいつかないと置いていかれる時の授業みたいでエキサイティング。(褒めてる 内容はとても興味深くて、各章で繰り返されるメッセージやキーワードがリフレインしているみたいで好き。 昔、観た映画カラーパープルのことを思い出したり、気になっているのに謎に観ていなかった2作品もこの本がきっかけとなりそう。 よく黒人やアジア人が人種差別を訴えている場面で「でも黒人男性やアジア人男性は、同じ人種の女性や子どもに酷いことしてるじゃんか」と思ったのはカラーパープルの記憶なんだと思う。
はな@hana-hitsuji052025年9月28日読んでる図書館本図書館で借りたちょいちょいシレッと全く読めない単語が出てきて手がかりないから調べられず気になって仕方ない。 あと「知ってるよね」というテイでカタカナの人名や海外の文学作品についての情報が前後ランダムにポコポコ出てくるので、食らいつかないと置いていかれる時の授業みたいでエキサイティング。(褒めてる 内容はとても興味深くて、各章で繰り返されるメッセージやキーワードがリフレインしているみたいで好き。 昔、観た映画カラーパープルのことを思い出したり、気になっているのに謎に観ていなかった2作品もこの本がきっかけとなりそう。 よく黒人やアジア人が人種差別を訴えている場面で「でも黒人男性やアジア人男性は、同じ人種の女性や子どもに酷いことしてるじゃんか」と思ったのはカラーパープルの記憶なんだと思う。









 修二@shu_22025年9月24日読み終わった進撃の巨人や虎に翼といった名作を、「ケア」の視点から見る。 上記2作は私も大好きな作品なのだが、この他にも「この作品にもケアが?」「この作品、こんな見方ができたのか!」という発見が多かった。 あまり多くは言えないが、本当にひらめきが多いので、ぜひいろんな人に手に取ってほしいと思う。
修二@shu_22025年9月24日読み終わった進撃の巨人や虎に翼といった名作を、「ケア」の視点から見る。 上記2作は私も大好きな作品なのだが、この他にも「この作品にもケアが?」「この作品、こんな見方ができたのか!」という発見が多かった。 あまり多くは言えないが、本当にひらめきが多いので、ぜひいろんな人に手に取ってほしいと思う。







 ヒ@HikariKomiyama2025年9月10日読み終わった夫の本棚『ケアの倫理』を読んだあとで気になり、パートナーの本棚から拝借して読んだ 雑誌世界の連載をまとめたものだそうで、かなり多くのトピックが詰め込まれているし、文学や研究だけでなく漫画や映画の登場人物やセリフを細かに引用していてすごい! たくさんの引用のなかで、それをつなぎあわせるのは無理があると感じる部分もあったけど、やっぱり専門なだけあってメアリ・シェリーが絡むと内容が濃くなりおもしろかった お母さまの介護をされながら書いたということだと思うので 本当に忙しかっただろうな
ヒ@HikariKomiyama2025年9月10日読み終わった夫の本棚『ケアの倫理』を読んだあとで気になり、パートナーの本棚から拝借して読んだ 雑誌世界の連載をまとめたものだそうで、かなり多くのトピックが詰め込まれているし、文学や研究だけでなく漫画や映画の登場人物やセリフを細かに引用していてすごい! たくさんの引用のなかで、それをつなぎあわせるのは無理があると感じる部分もあったけど、やっぱり専門なだけあってメアリ・シェリーが絡むと内容が濃くなりおもしろかった お母さまの介護をされながら書いたということだと思うので 本当に忙しかっただろうな

 Sanae@sanaemizushima2025年9月1日読み終わったケアという言葉の意味を考え直す機会となった本だった。いろんな場面から「ケア」の言葉の持つ意味が広がり、温かい気持ちになった。 他者に対して開かれた「多孔的な自己」という言葉をこの本を通じて知る。 10ある章の中で、思い当たる自分の無力さを感じた場面を思い出す。例えば2章「論破と対話」、4章「マンスプレイニング」。 そして5章「レイシズム」、6章「インターセクショナティ」は交差性という意味の通り、マイナス面が加算されるのではない、ということ。 女性、非白人、障がいがあったりする場合、それぞれを複合的に捉えるべきだということに気付かされた。 7章「愛」は個人的にとても勇気づけられるものだった。これからの生き方に役立ちそう。
Sanae@sanaemizushima2025年9月1日読み終わったケアという言葉の意味を考え直す機会となった本だった。いろんな場面から「ケア」の言葉の持つ意味が広がり、温かい気持ちになった。 他者に対して開かれた「多孔的な自己」という言葉をこの本を通じて知る。 10ある章の中で、思い当たる自分の無力さを感じた場面を思い出す。例えば2章「論破と対話」、4章「マンスプレイニング」。 そして5章「レイシズム」、6章「インターセクショナティ」は交差性という意味の通り、マイナス面が加算されるのではない、ということ。 女性、非白人、障がいがあったりする場合、それぞれを複合的に捉えるべきだということに気付かされた。 7章「愛」は個人的にとても勇気づけられるものだった。これからの生き方に役立ちそう。


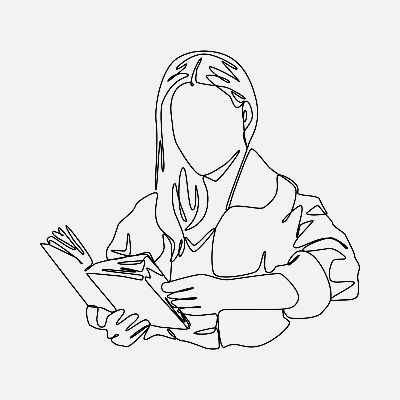 もくせいそう@mokuseisou_972025年8月29日読み終わった本格的に『フランケンシュタイン』を読んだことなくても読み進められる。現代の様々な問題にまつわる「ケア」を物語や作品を通して理解を深める本。
もくせいそう@mokuseisou_972025年8月29日読み終わった本格的に『フランケンシュタイン』を読んだことなくても読み進められる。現代の様々な問題にまつわる「ケア」を物語や作品を通して理解を深める本。

 amy@note_15812025年7月25日読み終わった感想ジェンダーヒロアカが取り上げられているとのことで読んだ 小川公代さん、もちろんお仕事のためもあると思うが映画や文学だけではなくて「鬼滅の刃」や「僕らのヒーローアカデミア」とか少年漫画も論考に入れられるぐらい読み込んでるのすごいな…。射程範囲の広さよ…数巻だけじゃなくてかなりの巻数なんだけどな… そして最後の10章「アンチ・ヒーロー」で「僕らのヒーローアカデミア」からトガヒミコと麗日お茶子の関係性に着目していて、これは二人のことが好きな人にはぜひ読んでほしいと思ってしまった 「僕らのヒーローアカデミア」の内容をすべて肯定するわけではないけれど、トガヒミコの帰結が麗日お茶子との友情からなる対話に帰結したところはとても好きなので、そのことをこうして論考として残してくれることはとてもうれしかったし、読んでいてトガヒミコの今までを考えると泣けてきてしょうがなかった 新書を読んで泣くというのは初めての経験かもしれない。 そして『虎に翼』!放送以降、小川さんのご著書で毎回見る気がするな…。でもそれだけ『ケア』や『ジェンダー』をはじめ、その社会で包摂されるべきマイノリティたちの話が展開できる作品だというわけでもある 私は『虎に翼』でケアの担い手であった花江ちゃんが大好きなので、ここでも取り上げられていてうれしい 主体的にケアを施すこととケアの役割を強いられることはまるで違うし、あたかも女性はケアが得意で好きでやっていることだといまだに思われることがある 様々な作品のなかにある『ケア』はどのように行われてきたか、それにより今を生きる私たちはこの社会を生きていくために不可欠な『ケア』をどう取り扱っていけばいいのか そのヒントがたくさん盛り込まれている本だった
amy@note_15812025年7月25日読み終わった感想ジェンダーヒロアカが取り上げられているとのことで読んだ 小川公代さん、もちろんお仕事のためもあると思うが映画や文学だけではなくて「鬼滅の刃」や「僕らのヒーローアカデミア」とか少年漫画も論考に入れられるぐらい読み込んでるのすごいな…。射程範囲の広さよ…数巻だけじゃなくてかなりの巻数なんだけどな… そして最後の10章「アンチ・ヒーロー」で「僕らのヒーローアカデミア」からトガヒミコと麗日お茶子の関係性に着目していて、これは二人のことが好きな人にはぜひ読んでほしいと思ってしまった 「僕らのヒーローアカデミア」の内容をすべて肯定するわけではないけれど、トガヒミコの帰結が麗日お茶子との友情からなる対話に帰結したところはとても好きなので、そのことをこうして論考として残してくれることはとてもうれしかったし、読んでいてトガヒミコの今までを考えると泣けてきてしょうがなかった 新書を読んで泣くというのは初めての経験かもしれない。 そして『虎に翼』!放送以降、小川さんのご著書で毎回見る気がするな…。でもそれだけ『ケア』や『ジェンダー』をはじめ、その社会で包摂されるべきマイノリティたちの話が展開できる作品だというわけでもある 私は『虎に翼』でケアの担い手であった花江ちゃんが大好きなので、ここでも取り上げられていてうれしい 主体的にケアを施すこととケアの役割を強いられることはまるで違うし、あたかも女性はケアが得意で好きでやっていることだといまだに思われることがある 様々な作品のなかにある『ケア』はどのように行われてきたか、それにより今を生きる私たちはこの社会を生きていくために不可欠な『ケア』をどう取り扱っていけばいいのか そのヒントがたくさん盛り込まれている本だった





 らこ@rakosuki2025年7月25日読み終わったケアの視点による物語分析で、『フランケンシュタイン』を中心に、さまざまな作品を、戦争、親ガチャ、マンスプレイニング、レイシズム、インターセクショナリティ、愛、エコロジーなどのテーマから論じている。『虎に翼』や『バービー』、『哀れなるものたち』など、観たことのある作品もいくつか取り上げられており、新しい見方に出会うことができた。 『哀れなるものたち』を観た際に、この作品が『フランケンシュタイン』の作者であるメアリー・シェリーとその母メアリー・ウルストンクラフト、父のウィリアム・ゴードンを意識した内容になっていると知った。それから『フランケンシュタイン』をいつか読んでみようと思いつつそのままになっていたが、この本を読んだことでさまざまな視点から物語を捉えられるかもしれない。近いうちに挑戦してみたい。 世間に流布している大きな物語だけでなく、埋もれがちな小さな物語に目を向けることの大切さを知れた。 また、周りの人や自分自身へのケアも、自分をケアしてくれている人のことも、もっと大切にしていきたいと思った。
らこ@rakosuki2025年7月25日読み終わったケアの視点による物語分析で、『フランケンシュタイン』を中心に、さまざまな作品を、戦争、親ガチャ、マンスプレイニング、レイシズム、インターセクショナリティ、愛、エコロジーなどのテーマから論じている。『虎に翼』や『バービー』、『哀れなるものたち』など、観たことのある作品もいくつか取り上げられており、新しい見方に出会うことができた。 『哀れなるものたち』を観た際に、この作品が『フランケンシュタイン』の作者であるメアリー・シェリーとその母メアリー・ウルストンクラフト、父のウィリアム・ゴードンを意識した内容になっていると知った。それから『フランケンシュタイン』をいつか読んでみようと思いつつそのままになっていたが、この本を読んだことでさまざまな視点から物語を捉えられるかもしれない。近いうちに挑戦してみたい。 世間に流布している大きな物語だけでなく、埋もれがちな小さな物語に目を向けることの大切さを知れた。 また、周りの人や自分自身へのケアも、自分をケアしてくれている人のことも、もっと大切にしていきたいと思った。


 りなっこ@rinakko2025年7月7日読み終わった『フランケンシュタイン』を取っ掛かりに、ケアの観点から様々な物語が読み解かれる。映画『バービー』や『バグダードのフランケンシュタイン』『鬼滅の刃』『オーランドー』『虎に翼』…と作品も多岐にわたり、そこで繋がるのかという驚きも楽しい 見落とされ軽視されてきた〈小さな物語〉が、10のテーマ(戦争、論破と対話、マンスプ…)の中で取り上げられる。なぜケアは必要で、非暴力の可能性を探求しなければならないのか。自分をも含めた人の “傷つきやすさ” とどう向き合っていけばいいか…という課題も響いた。
りなっこ@rinakko2025年7月7日読み終わった『フランケンシュタイン』を取っ掛かりに、ケアの観点から様々な物語が読み解かれる。映画『バービー』や『バグダードのフランケンシュタイン』『鬼滅の刃』『オーランドー』『虎に翼』…と作品も多岐にわたり、そこで繋がるのかという驚きも楽しい 見落とされ軽視されてきた〈小さな物語〉が、10のテーマ(戦争、論破と対話、マンスプ…)の中で取り上げられる。なぜケアは必要で、非暴力の可能性を探求しなければならないのか。自分をも含めた人の “傷つきやすさ” とどう向き合っていけばいいか…という課題も響いた。




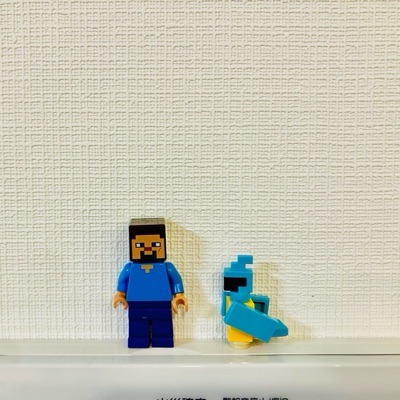 さおり@prn9909082025年7月6日読み終わったきっとどの物語にも「ケア」は描かれていてこれまではそこに光が当てられていなかっただけなんだと思う.そしてその物語のケアが実を結ばれたと思えるときにわたしはジーンとしたりなにか温かいものがこみあげてくるのを感じていたんだろうなと思ったしそれが(物語のなかではあえて)無視されたりもしくは裏切られたりしたときに、悲しくなったり寂しさを覚えていたりしたんだろうと思う.とりあげられているどの物語についての視点もその作品への敬意に満ちていて「伝えたい」という気持ちが伝わってきて、とてもアツい本だった.
さおり@prn9909082025年7月6日読み終わったきっとどの物語にも「ケア」は描かれていてこれまではそこに光が当てられていなかっただけなんだと思う.そしてその物語のケアが実を結ばれたと思えるときにわたしはジーンとしたりなにか温かいものがこみあげてくるのを感じていたんだろうなと思ったしそれが(物語のなかではあえて)無視されたりもしくは裏切られたりしたときに、悲しくなったり寂しさを覚えていたりしたんだろうと思う.とりあげられているどの物語についての視点もその作品への敬意に満ちていて「伝えたい」という気持ちが伝わってきて、とてもアツい本だった.


 ゆう@suisuiu2025年6月5日気になる卒論本15年くらい前、苫小牧行きのフェリーで卒論のために『フランケンシュタイン』を読んでいた。飛行機に乗れたらよかったけどお金がなかったので、一番やすい等級の船底の客席。海をダイレクトに感じるとてつもない揺れ。ダニの皆さんがいっぱい住んでそうな毛布。修行中のような枕。なんでこんなにお金がないんだろうと情けない気持ちになりながら、でも「ひとりで(それも年数回ずつ)フェリーに乗る女」ってきっといつまでも思い出&ネタになるとどこかしぶとく感じてもいた。だってなんだか演歌みたい。その頃の私は演歌番組のアシスタントディレクターのアルバイトをしていた。うねる声、くねる身体。 それで『フランケンシュタイン』。ホモソーシャルとかミソジニー、フェミニズムをテーマに書いた。断片的な知識すぎる、学部生だからこそののびのび感のあった卒論だろうと思うけど、なんにせよなんだか元気でいいテーマだ。それでここ数年なんとなくフランケンシュタイン的なものがまた目につくようになっている気がして、だからこの本はやっぱり気になる。でも昨日夫とこの物語の舞台について話した時、堂々と「ロンドンでしょ」とか言ったけどジュネーブだった。そうだ。 一番好きなシーンは、怪物がさまよっていた森の中でそこに棲む植物や生きもの、川の流れとたわむれ、命のかがやきみたいなものとダンスするシーン。でもこれも妄想かもしれない。
ゆう@suisuiu2025年6月5日気になる卒論本15年くらい前、苫小牧行きのフェリーで卒論のために『フランケンシュタイン』を読んでいた。飛行機に乗れたらよかったけどお金がなかったので、一番やすい等級の船底の客席。海をダイレクトに感じるとてつもない揺れ。ダニの皆さんがいっぱい住んでそうな毛布。修行中のような枕。なんでこんなにお金がないんだろうと情けない気持ちになりながら、でも「ひとりで(それも年数回ずつ)フェリーに乗る女」ってきっといつまでも思い出&ネタになるとどこかしぶとく感じてもいた。だってなんだか演歌みたい。その頃の私は演歌番組のアシスタントディレクターのアルバイトをしていた。うねる声、くねる身体。 それで『フランケンシュタイン』。ホモソーシャルとかミソジニー、フェミニズムをテーマに書いた。断片的な知識すぎる、学部生だからこそののびのび感のあった卒論だろうと思うけど、なんにせよなんだか元気でいいテーマだ。それでここ数年なんとなくフランケンシュタイン的なものがまた目につくようになっている気がして、だからこの本はやっぱり気になる。でも昨日夫とこの物語の舞台について話した時、堂々と「ロンドンでしょ」とか言ったけどジュネーブだった。そうだ。 一番好きなシーンは、怪物がさまよっていた森の中でそこに棲む植物や生きもの、川の流れとたわむれ、命のかがやきみたいなものとダンスするシーン。でもこれも妄想かもしれない。









 りら@AnneLilas2025年5月25日気になるふと、長年積読してる中公新書の廣野由美子『批評理論入門』も副題が「『フランケンシュタイン』解剖講義」だから思い切り被ってるな…と。 どちらも気になりつつも、そして色々な面で重要な作品であることは重々承知しているけれども、昔一読しただけの『フランケンシュタイン』にそこまで思い入れないしねえ、とぐぬぬとなっている。
りら@AnneLilas2025年5月25日気になるふと、長年積読してる中公新書の廣野由美子『批評理論入門』も副題が「『フランケンシュタイン』解剖講義」だから思い切り被ってるな…と。 どちらも気になりつつも、そして色々な面で重要な作品であることは重々承知しているけれども、昔一読しただけの『フランケンシュタイン』にそこまで思い入れないしねえ、とぐぬぬとなっている。