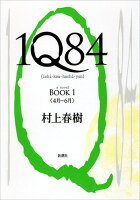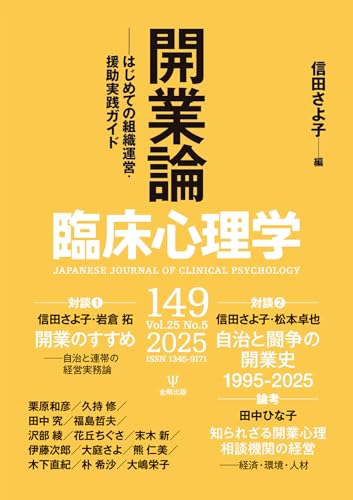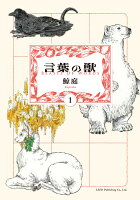Ryota.T
@ausryota
哲学を学びながら、哲学することについて試みています
- 2025年9月23日
- 2025年9月23日
- 2025年9月17日
- 2025年9月13日
- 2025年9月13日
- 2025年9月11日
- 2025年9月11日
 借りてきた「やる気か?」「もちろんガチで」 負けるのは怖い。だから、会社を辞めて、評価の外にある海外へ飛び、ウィーン大学に行った。まだ日本人じゃ真剣には誰もやってない、哲学相談を始めた。そこには競争がなく、負けることがないから。でもライバルが現れた。阪大の同い年の博士学生。論文を書き、講師として教壇に立ち、対話も相談役にも挑む彼に勝てない、と思った。読んでる量が違う、と思った。 この夏、腹の調子が悪かったのは、ヨーロッパの記録的な猛暑ばかりではない。彼から、哲学から、逃げられないと思ったからだ。京都の研究者に、哲学をやるというのが、過去から学ぶことなしに、もしくは弛まぬ精神の鍛錬なしになし得ないことを突きつけられたからだ。文献を読んで書いたものを発表すること。自分のやった対話を専門家に見てもらうこと。格上の実践者の背中を見て学ぶこと。どれもこれも、震えが止まらなかった。自分が否定されるのが怖かった。 でも、真剣勝負なんだ。負けるかもしれない怯えも、否定されるかもしれない恐怖も含めての、本気の高揚と競争の昂奮なんだ。俺も、全力疾走しようとしてるんだ。 彼に勝ちたい。研究者をギャフンと言わしてやりたい。哲学することを試みるというのは、論理の展開(アーギュメント)なんかじゃなしに、真であるものを捉え、語ろうとする勇気であり、真であるものは出来事として、隠された状態から姿を現すのだと言いたい。 ああ、全力疾走したくないな。疲れるから。負けたら嫌だし、色々恥かくし……ああ、全力疾走したくないな。 「やる気か?」「もちろんガチで」
借りてきた「やる気か?」「もちろんガチで」 負けるのは怖い。だから、会社を辞めて、評価の外にある海外へ飛び、ウィーン大学に行った。まだ日本人じゃ真剣には誰もやってない、哲学相談を始めた。そこには競争がなく、負けることがないから。でもライバルが現れた。阪大の同い年の博士学生。論文を書き、講師として教壇に立ち、対話も相談役にも挑む彼に勝てない、と思った。読んでる量が違う、と思った。 この夏、腹の調子が悪かったのは、ヨーロッパの記録的な猛暑ばかりではない。彼から、哲学から、逃げられないと思ったからだ。京都の研究者に、哲学をやるというのが、過去から学ぶことなしに、もしくは弛まぬ精神の鍛錬なしになし得ないことを突きつけられたからだ。文献を読んで書いたものを発表すること。自分のやった対話を専門家に見てもらうこと。格上の実践者の背中を見て学ぶこと。どれもこれも、震えが止まらなかった。自分が否定されるのが怖かった。 でも、真剣勝負なんだ。負けるかもしれない怯えも、否定されるかもしれない恐怖も含めての、本気の高揚と競争の昂奮なんだ。俺も、全力疾走しようとしてるんだ。 彼に勝ちたい。研究者をギャフンと言わしてやりたい。哲学することを試みるというのは、論理の展開(アーギュメント)なんかじゃなしに、真であるものを捉え、語ろうとする勇気であり、真であるものは出来事として、隠された状態から姿を現すのだと言いたい。 ああ、全力疾走したくないな。疲れるから。負けたら嫌だし、色々恥かくし……ああ、全力疾走したくないな。 「やる気か?」「もちろんガチで」 - 2025年9月9日
- 2025年9月6日
- 2025年9月2日
- 2025年9月2日
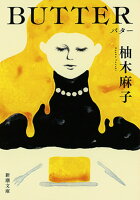 BUTTER柚木麻子読み終わった展開が面白くて徹夜で読もうとしたが、圧巻のボリュームで読みきれず、2日かけて読んだ。社会批評の鍋のようで、多くの具材をまだ消化できないでいる。 家族は円満であるべき。女は男を支えてケアするべき。誰もが一人で自立してやっていくべき。娘は父の期待に応えるべき。女は痩せた身体を保つべき。俺たちは、いつまでこのような「べき」に従い続けるんだろう。 公の秩序を保つため?各人が義務を果たすため?毒のある「べき」からは手を洗いながら、同時に、自分とは違うこだわりがあり、一瞬一瞬変わっていく、手のつけられない他者とともに生きていく方法を探したいと思った。 * 男として生まれて、性自認も男で、異性愛者の立場で、高校のときから変わらず痩身でいる私がこれを読むことはすこし変わった体験だった。 時折俺は、性欲でひとを見てしまうことがある。性愛がその人への愛を凌駕してしまうことがある。 けれども、その人を見ようとしなくなると、関係はすぐに歪んでしまう。その人がのびのび変わっていくことを求めるような動的な関係を求めるのではなくて、変わらないでいて欲しい、自分の言うことを聞いて欲しい、こだわりや自己主張は控えて欲しい、と思ってしまう。このような時、自分がその人を人間として見ていなくてぞっとする。静的な関係を求め始めたら赤信号だと思う。 社会に潜む毒のある義務はすべて、人間を、もしくは関係を静的なものへと固定しようとするエゴでできている。そのエゴは俺のなかにもある。村上春樹作品が醸し出すような男性性は俺ももっている。 * エゴと縁を切るには、自分を正しく満たす必要がある。仕事で自分の能力を発揮する。深夜にバター醤油ご飯を食べる。好きなひとの肌を求めてベッドに誘う。友達と対等に悩みを分かち合う。 ここには原初的な喜びだけがあり、毒のある「べき」も勝ち負けを決める競争もない。人間関係を我が物とするような邪念もここにはない。 すぐにはそれらが叶わなくても、自分がこれが最善と思ったことを諦めまいと意志するとき、自分を正しく愛することができる。自分を正しく愛するために必要なのは、容姿でもお金でもステータスでもない。 * ひとは原初的な喜びを味わうことでしか、自分の幸福の適量を見つけられない。俺は哲学とバレーと好きなひとさえいれば、幸せだとわかりつつある。 他者もまた、自分の幸福の適量を探している。他者に敬意を払うというのは、他者が原初的な喜びを得ようとすることを、自分と同じ強度で認めること。 他者は、自分の思い通りには動かない。付き合ったとしても、結婚したとしても、お互いが変わっていくなかで交わり続けることを願うくらいしか、できないんだろうな。 それをすこしさみしい気もするけど、そうやってひとを曖昧に好きでいたい。それに、二人でいれば「見えないものが見えるようになる」関係、互いを失いたくないと思う関係は素敵だなと思った。性愛なしでも隣に入れるのは息がしやすい。美しいシスターフッドを見させてもらった。
BUTTER柚木麻子読み終わった展開が面白くて徹夜で読もうとしたが、圧巻のボリュームで読みきれず、2日かけて読んだ。社会批評の鍋のようで、多くの具材をまだ消化できないでいる。 家族は円満であるべき。女は男を支えてケアするべき。誰もが一人で自立してやっていくべき。娘は父の期待に応えるべき。女は痩せた身体を保つべき。俺たちは、いつまでこのような「べき」に従い続けるんだろう。 公の秩序を保つため?各人が義務を果たすため?毒のある「べき」からは手を洗いながら、同時に、自分とは違うこだわりがあり、一瞬一瞬変わっていく、手のつけられない他者とともに生きていく方法を探したいと思った。 * 男として生まれて、性自認も男で、異性愛者の立場で、高校のときから変わらず痩身でいる私がこれを読むことはすこし変わった体験だった。 時折俺は、性欲でひとを見てしまうことがある。性愛がその人への愛を凌駕してしまうことがある。 けれども、その人を見ようとしなくなると、関係はすぐに歪んでしまう。その人がのびのび変わっていくことを求めるような動的な関係を求めるのではなくて、変わらないでいて欲しい、自分の言うことを聞いて欲しい、こだわりや自己主張は控えて欲しい、と思ってしまう。このような時、自分がその人を人間として見ていなくてぞっとする。静的な関係を求め始めたら赤信号だと思う。 社会に潜む毒のある義務はすべて、人間を、もしくは関係を静的なものへと固定しようとするエゴでできている。そのエゴは俺のなかにもある。村上春樹作品が醸し出すような男性性は俺ももっている。 * エゴと縁を切るには、自分を正しく満たす必要がある。仕事で自分の能力を発揮する。深夜にバター醤油ご飯を食べる。好きなひとの肌を求めてベッドに誘う。友達と対等に悩みを分かち合う。 ここには原初的な喜びだけがあり、毒のある「べき」も勝ち負けを決める競争もない。人間関係を我が物とするような邪念もここにはない。 すぐにはそれらが叶わなくても、自分がこれが最善と思ったことを諦めまいと意志するとき、自分を正しく愛することができる。自分を正しく愛するために必要なのは、容姿でもお金でもステータスでもない。 * ひとは原初的な喜びを味わうことでしか、自分の幸福の適量を見つけられない。俺は哲学とバレーと好きなひとさえいれば、幸せだとわかりつつある。 他者もまた、自分の幸福の適量を探している。他者に敬意を払うというのは、他者が原初的な喜びを得ようとすることを、自分と同じ強度で認めること。 他者は、自分の思い通りには動かない。付き合ったとしても、結婚したとしても、お互いが変わっていくなかで交わり続けることを願うくらいしか、できないんだろうな。 それをすこしさみしい気もするけど、そうやってひとを曖昧に好きでいたい。それに、二人でいれば「見えないものが見えるようになる」関係、互いを失いたくないと思う関係は素敵だなと思った。性愛なしでも隣に入れるのは息がしやすい。美しいシスターフッドを見させてもらった。 - 2025年8月30日
- 2025年8月18日
- 2025年8月18日
- 2025年8月15日
 メルロ=ポンティ 可逆性鷲田清一読んでる身体性があなたの人生において果たした役割とは何か?というエッセイを書かなくてはいけなくなり、慌てて読んだのだが、鷲田清一のメルロ=ポンティを読む手捌きに惚れ惚れする。 メルロ=ポンティ、とんでもないな。哲学者って、どっひゃ〜!っていう世界をみる真摯さみたいなものがあって、こと身体に関しては、メルポンに度肝抜かれた。いまだに意味がよくわかってないのだが、世界が昨日とは違って見えてくる。
メルロ=ポンティ 可逆性鷲田清一読んでる身体性があなたの人生において果たした役割とは何か?というエッセイを書かなくてはいけなくなり、慌てて読んだのだが、鷲田清一のメルロ=ポンティを読む手捌きに惚れ惚れする。 メルロ=ポンティ、とんでもないな。哲学者って、どっひゃ〜!っていう世界をみる真摯さみたいなものがあって、こと身体に関しては、メルポンに度肝抜かれた。いまだに意味がよくわかってないのだが、世界が昨日とは違って見えてくる。 - 2025年8月13日
 生の短さについて 他二篇セネカ,大西英文読んでるざっくり言うと、時間を大切に、外部や他の誰かへ簡単に譲り渡すことなく、自分の生を存分に味わって生きよう、ということなのだけど、セネカ先生の文章は切れ味が鋭くて気持ちがいい。 おかげで、失礼な人のメールをきっぱりと断り、毒のある人間関係も距離を置くことができた。やさしいだけでは、本当に大切にしたいことを大事にできない。
生の短さについて 他二篇セネカ,大西英文読んでるざっくり言うと、時間を大切に、外部や他の誰かへ簡単に譲り渡すことなく、自分の生を存分に味わって生きよう、ということなのだけど、セネカ先生の文章は切れ味が鋭くて気持ちがいい。 おかげで、失礼な人のメールをきっぱりと断り、毒のある人間関係も距離を置くことができた。やさしいだけでは、本当に大切にしたいことを大事にできない。 - 2025年7月28日
 世界の手触り佐藤知久ほかじゅうぶん読んだ鷲田の対談のところだけ読んだ。 1現象学っておもしろい 自分を外した、客観的な目線、上空飛翔的な目線じゃなしに、内側から探していこうとする。ぐらぐらと地盤が揺れながら、でも「このわたし」が見たり、聞いたり、感じたりしているところを頼りに探そうとする。現象学っておもしろい。 2生成 たまたまの下地の黄色から、色を塗り、筆を走らせ、絵の具をのせて、絵を生成する。人間も偶然から始まるんだけど、生成は理解可能だったりする。 3ことばのきめ テクストとしてのことばとテクスチャーとしてのことはがある。そうだな、と思った。聞かなくても伝わる、聞くとほっとする、聞いてもらえてる感じがしない、など。俺もテクスチャーを聞けるようになりたい。 4臨床哲学 鷲田は生活の場に赴くことを臨床として重視した。果たしてそうだろうか。外部の人間じゃなく、ともに生きる仲間として関わる方がよほど重要じゃないかと思う。インタビュアーで哲学ができるとは思えない。
世界の手触り佐藤知久ほかじゅうぶん読んだ鷲田の対談のところだけ読んだ。 1現象学っておもしろい 自分を外した、客観的な目線、上空飛翔的な目線じゃなしに、内側から探していこうとする。ぐらぐらと地盤が揺れながら、でも「このわたし」が見たり、聞いたり、感じたりしているところを頼りに探そうとする。現象学っておもしろい。 2生成 たまたまの下地の黄色から、色を塗り、筆を走らせ、絵の具をのせて、絵を生成する。人間も偶然から始まるんだけど、生成は理解可能だったりする。 3ことばのきめ テクストとしてのことばとテクスチャーとしてのことはがある。そうだな、と思った。聞かなくても伝わる、聞くとほっとする、聞いてもらえてる感じがしない、など。俺もテクスチャーを聞けるようになりたい。 4臨床哲学 鷲田は生活の場に赴くことを臨床として重視した。果たしてそうだろうか。外部の人間じゃなく、ともに生きる仲間として関わる方がよほど重要じゃないかと思う。インタビュアーで哲学ができるとは思えない。 - 2025年7月25日
- 2025年7月25日
- 2025年7月17日
 ニコマコス倫理学(下)アリストテレス,渡辺邦夫読んでるフロネーシス(思慮深さ)について知りたくて読んだのだが、おもろすぎて、上巻から読み直している。 アリストテレスとんでもないな、というのが第一印象。どこまであなたの思想は奥行きのあるものなんでしょうね、と美しい論理の運び方にため息が出る。素晴らしい筆致、訳者に感謝。ギリシャ語の概念は、真理、幸福、愛、日常的に使われる曖昧な言葉のオルタナティブを提示してくれる。え、そうじゃないのも全然あり得たのね、と目から鱗が落ちる。 哲学への入門として、ソクラテスの弁明とかクリトンとか、対話篇を読んでほえ〜となったら、ニコマコス倫理学で体系を見るのが黄金ルートだと思う。 自分の経験を照らし合わすことで完成する本。生きれば生きるほど、アリストテレスに近づけるとも言える。
ニコマコス倫理学(下)アリストテレス,渡辺邦夫読んでるフロネーシス(思慮深さ)について知りたくて読んだのだが、おもろすぎて、上巻から読み直している。 アリストテレスとんでもないな、というのが第一印象。どこまであなたの思想は奥行きのあるものなんでしょうね、と美しい論理の運び方にため息が出る。素晴らしい筆致、訳者に感謝。ギリシャ語の概念は、真理、幸福、愛、日常的に使われる曖昧な言葉のオルタナティブを提示してくれる。え、そうじゃないのも全然あり得たのね、と目から鱗が落ちる。 哲学への入門として、ソクラテスの弁明とかクリトンとか、対話篇を読んでほえ〜となったら、ニコマコス倫理学で体系を見るのが黄金ルートだと思う。 自分の経験を照らし合わすことで完成する本。生きれば生きるほど、アリストテレスに近づけるとも言える。
読み込み中...
![Tarzan(ターザン) 2025年8月28日号 No.908 [休む技術。]](https://m.media-amazon.com/images/I/41mJEg8Z2yL._SL500_.jpg)