

Eukalyptus
@euka_inrevarld
抽象画家、作曲家、哲学者。
人文書と理系の本が好きです。
哲学や自然科学、生物系を主に。
装丁や出版社もこだわりながら選びます。
- 2026年2月12日
 責任と物語戸谷洋志読み終わった自身が「責任」について思考している身として、本書は避けては通れないだろうと思い、通読。 私自身が、「強い」責任論から「弱い」責任論へと考えが移行している感覚があったので、親和性の高い本であると感じた。 ただし、星の王子さまの良さを1ミリもわからない自身にはあまりピンと来ないことも少しあった。
責任と物語戸谷洋志読み終わった自身が「責任」について思考している身として、本書は避けては通れないだろうと思い、通読。 私自身が、「強い」責任論から「弱い」責任論へと考えが移行している感覚があったので、親和性の高い本であると感じた。 ただし、星の王子さまの良さを1ミリもわからない自身にはあまりピンと来ないことも少しあった。 - 2026年2月9日
- 2026年2月7日
 BLが開く扉ジェームズ・ウェルカー読み終わった『クィアな変容・変貌・変化ーアジアにおけるボーイズラブ(BL)メディアに関する国際シンポジウム』にて発表されたアジア圏におけるBLとBLを好む層への学術的なアプローチについての書籍。 いやはや、元職場でこんな素晴らしい会が開かれていたこと、著者は現に本大学の教授でいらっしゃることから、その大学の開かれた姿勢にも脱帽。良いところと縁があったなと思います。 本書はかなり重要な本でして、以降刊行された関連書籍でも参考文献として引用がされています。そちらを先に読んでいたりするので、どこを引用したのか、などがわかって楽しかったです。 BLというのは、社会的に抑圧されたり、偏見を向けられたり、迫害を受ける人々にとっての解放の契機となり得るというのを感じました。私自身の経験からもいえますが、本書より、BLは個人的であり、政治的であるというのが言い得て妙だと思っています。
BLが開く扉ジェームズ・ウェルカー読み終わった『クィアな変容・変貌・変化ーアジアにおけるボーイズラブ(BL)メディアに関する国際シンポジウム』にて発表されたアジア圏におけるBLとBLを好む層への学術的なアプローチについての書籍。 いやはや、元職場でこんな素晴らしい会が開かれていたこと、著者は現に本大学の教授でいらっしゃることから、その大学の開かれた姿勢にも脱帽。良いところと縁があったなと思います。 本書はかなり重要な本でして、以降刊行された関連書籍でも参考文献として引用がされています。そちらを先に読んでいたりするので、どこを引用したのか、などがわかって楽しかったです。 BLというのは、社会的に抑圧されたり、偏見を向けられたり、迫害を受ける人々にとっての解放の契機となり得るというのを感じました。私自身の経験からもいえますが、本書より、BLは個人的であり、政治的であるというのが言い得て妙だと思っています。 - 2026年2月5日
 メタモルフォーゼの哲学エマヌエーレ・コッチャ,宇佐美達朗,松葉類読み終わった表紙に惹かれ、内容に惹かれ、読み始めた。 思いの外読みやすいが割とふわふわしているのかも。中身が無いというわけでは全く無く。 非常に興味深い概念であり、世界だった。中でも、その種がその種以外によって成り立ちうるという考えには脱帽した。 植物がヒトを学者や農家にするように、昆虫を生存のための役割にさせたりといった視点が本当に面白かった。
メタモルフォーゼの哲学エマヌエーレ・コッチャ,宇佐美達朗,松葉類読み終わった表紙に惹かれ、内容に惹かれ、読み始めた。 思いの外読みやすいが割とふわふわしているのかも。中身が無いというわけでは全く無く。 非常に興味深い概念であり、世界だった。中でも、その種がその種以外によって成り立ちうるという考えには脱帽した。 植物がヒトを学者や農家にするように、昆虫を生存のための役割にさせたりといった視点が本当に面白かった。 - 2026年2月3日
 ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のことアンジェラ・チェン,羽生有希読み終わった『私自身が性的惹かれを経験することはないものの、他者には私に対する欲望を持って欲しかったのだ。』 『ACEアセクシュアルから見たセックスと社会のこと』315p.3 アセクシュアルの中にもスペクトラムがあって、性的惹かれを経験しない、しにくいとしても人との関わりが要らないわけではないし、誰かを好きになる事だってある。 そんな多様な在り方について、さまざまな視点から書かれたルポ。アセクシュアルの本はなかなか濃い内容のものが無い。入門書や浅い本であって専門書は無いから、こういう本が実は元祖だったりする。 類書がこれから増えると良いな、本当に、新書とかじゃなくて単行本で。
ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のことアンジェラ・チェン,羽生有希読み終わった『私自身が性的惹かれを経験することはないものの、他者には私に対する欲望を持って欲しかったのだ。』 『ACEアセクシュアルから見たセックスと社会のこと』315p.3 アセクシュアルの中にもスペクトラムがあって、性的惹かれを経験しない、しにくいとしても人との関わりが要らないわけではないし、誰かを好きになる事だってある。 そんな多様な在り方について、さまざまな視点から書かれたルポ。アセクシュアルの本はなかなか濃い内容のものが無い。入門書や浅い本であって専門書は無いから、こういう本が実は元祖だったりする。 類書がこれから増えると良いな、本当に、新書とかじゃなくて単行本で。 - 2026年1月28日
 ひとり出版入門宮後優子読み終わったいや〜良い意味で出版業向いてなさそうと思った! 翻訳本などをいつかは出してみたいとも思ったけど、明確に出版業界に就職したいと言う願望もないのでその経験なしに飛び込むのは本当にやばそうだと感じた。 私に向いているのは同人みたいです。ISBNの無い本にも魅力はありますからね。
ひとり出版入門宮後優子読み終わったいや〜良い意味で出版業向いてなさそうと思った! 翻訳本などをいつかは出してみたいとも思ったけど、明確に出版業界に就職したいと言う願望もないのでその経験なしに飛び込むのは本当にやばそうだと感じた。 私に向いているのは同人みたいです。ISBNの無い本にも魅力はありますからね。 - 2026年1月20日
 クリトリス革命カロリーヌ・ミシェル,アレクサンドラ・ユバン,永田千菜読み終わった買った勁草書房の新刊案内で『哲学者、女性のオーガズムの進化にいどむ』の関連書籍にその名が記載されていて、思わず惹かれてしまってすぐ読んでしまった。 あの勁草書房が引っ張ってきた本だから中身の担保はあると認識している。。。 正直買ってよかったし読んでよかったと思っている…。太田出版だなーとも思うけど、よくぞ出してくれましたわ…。
クリトリス革命カロリーヌ・ミシェル,アレクサンドラ・ユバン,永田千菜読み終わった買った勁草書房の新刊案内で『哲学者、女性のオーガズムの進化にいどむ』の関連書籍にその名が記載されていて、思わず惹かれてしまってすぐ読んでしまった。 あの勁草書房が引っ張ってきた本だから中身の担保はあると認識している。。。 正直買ってよかったし読んでよかったと思っている…。太田出版だなーとも思うけど、よくぞ出してくれましたわ…。 - 2026年1月20日
 ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のことアンジェラ・チェン,羽生有希買った読み始めた
ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のことアンジェラ・チェン,羽生有希買った読み始めた - 2026年1月20日
 責任と物語戸谷洋志買った
責任と物語戸谷洋志買った - 2026年1月20日
 美の哲学論考倉石清志買った
美の哲学論考倉石清志買った - 2026年1月20日
 ハチは心をもっているラース・チットカ,今西康子,小野正人買った
ハチは心をもっているラース・チットカ,今西康子,小野正人買った - 2026年1月20日
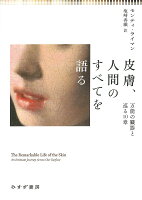 皮膚、人間のすべてを語るモンティ・ライマン,塩崎香織買った
皮膚、人間のすべてを語るモンティ・ライマン,塩崎香織買った - 2026年1月20日
 うつむく眼〈新装版〉マーティン・ジェイ,亀井大輔,佐藤勇一,小林琢自,田邉正俊,神田大輔,青柳雅文買った
うつむく眼〈新装版〉マーティン・ジェイ,亀井大輔,佐藤勇一,小林琢自,田邉正俊,神田大輔,青柳雅文買った - 2026年1月20日
 問題=物質となる身体ジュディス・バトラー,佐藤嘉幸,竹村和子,越智博美買った
問題=物質となる身体ジュディス・バトラー,佐藤嘉幸,竹村和子,越智博美買った - 2026年1月20日
 ひとり出版入門宮後優子買った
ひとり出版入門宮後優子買った - 2026年1月20日
 メタモルフォーゼの哲学エマヌエーレ・コッチャ,宇佐美達朗,松葉類買った
メタモルフォーゼの哲学エマヌエーレ・コッチャ,宇佐美達朗,松葉類買った - 2026年1月20日
 BLが開く扉ジェームズ・ウェルカー買った
BLが開く扉ジェームズ・ウェルカー買った - 2026年1月20日
 ミクロの森デヴィッド・ジョージ・ハスケル,三木直子買った
ミクロの森デヴィッド・ジョージ・ハスケル,三木直子買った - 2026年1月20日
 哲学者、女性のオーガズムの進化にいどむエリザベス・ロイド,網谷祐一買った
哲学者、女性のオーガズムの進化にいどむエリザベス・ロイド,網谷祐一買った - 2026年1月20日
 フェミニスト現象学中澤瞳,宮原優,川崎唯史,稲原美苗買った
フェミニスト現象学中澤瞳,宮原優,川崎唯史,稲原美苗買った
読み込み中...
