
天果
@melon-rice
言葉と、物語を摂取して暮らします。
- 2025年11月25日
 買った読んだ個人ブログ「ゲムぼく。」の管理人によるエッセイ本。文章が面白いので買った。 ゲムぼく。は特にテーマを定めることなく綴られているブログで、10年の歴史があり、ときおり企画が大きく話題になる。コンビニの大盛りキャンペーンの検証企画や、USJ旅行に掛かった全費用検証企画などで知ったひともいるかも知れない。 ブログではよくむちむちの太ももが登場するゲームについても書かれているので、ともすれば下品にも思われがちだけど、本書を読む限り、著者の方はけっこう上品だと感じる。 下品さには下ネタ系と悪口・誹謗系があり、ゲムぼく。さんは後者から意識的に距離を置いていることが明示されているからだ。 本書では「〝伝えたくなる日々〟を手に入れる方法」として面白さの見つけ方、深め方、形への仕方、楽しみ方が語られる。 もちろんそれらの内容自体も意義深いけれども、それ以上に軽快でユーモラスな筆致が心地良い。「役に立つから読むべき」本じゃなく、シンプルに読んでいて面白いから読みたい本。 そんな本書は、ゲムぼく。の記事が楽しめた方ならたぶん相性バッチリだ。
買った読んだ個人ブログ「ゲムぼく。」の管理人によるエッセイ本。文章が面白いので買った。 ゲムぼく。は特にテーマを定めることなく綴られているブログで、10年の歴史があり、ときおり企画が大きく話題になる。コンビニの大盛りキャンペーンの検証企画や、USJ旅行に掛かった全費用検証企画などで知ったひともいるかも知れない。 ブログではよくむちむちの太ももが登場するゲームについても書かれているので、ともすれば下品にも思われがちだけど、本書を読む限り、著者の方はけっこう上品だと感じる。 下品さには下ネタ系と悪口・誹謗系があり、ゲムぼく。さんは後者から意識的に距離を置いていることが明示されているからだ。 本書では「〝伝えたくなる日々〟を手に入れる方法」として面白さの見つけ方、深め方、形への仕方、楽しみ方が語られる。 もちろんそれらの内容自体も意義深いけれども、それ以上に軽快でユーモラスな筆致が心地良い。「役に立つから読むべき」本じゃなく、シンプルに読んでいて面白いから読みたい本。 そんな本書は、ゲムぼく。の記事が楽しめた方ならたぶん相性バッチリだ。 - 2025年10月11日
 遺失物統轄機構ほし買った読んだ“存在しないゲーム” の攻略本という体裁をとったビジュアルブック。ゲームの進行に沿った画像や解説、キャラクター設定、攻略チャートなどが収録されている。 その昔、ネットの攻略サイトが広まる前は、各社から攻略本が出ていた(あまりゲームそのものをやらなくなってしまったので、今でも出ているのかはわからない)。アルティマニアをはじめとする分厚い攻略本に親しんだひとも多いんじゃないか。 あの頃はたとえゲーム本体をプレイしなくても、攻略本を読むだけでワクワクした。その時の気持ちが蘇るような本なのだ、本書は。 扱われているゲームを実際に作ってほしい、という感想も見かけたけれど、個人的には架空のゲームだからこそ、本の断片的な情報から想像が広がるのも趣があっていいんじゃないかと思う。 また、実際にゲーム本体をプレイしないでその辺縁を楽しむという楽しみ方は、昨今のゲーム実況動画にも通じるところがあるような気がした。その意味で、懐かしくも新しい魅力がある作品だ。 プレイとは別に攻略本そのものが好きというひとや、限られた情報から空想を膨らませて一層楽しめるひとにおすすめできる。
遺失物統轄機構ほし買った読んだ“存在しないゲーム” の攻略本という体裁をとったビジュアルブック。ゲームの進行に沿った画像や解説、キャラクター設定、攻略チャートなどが収録されている。 その昔、ネットの攻略サイトが広まる前は、各社から攻略本が出ていた(あまりゲームそのものをやらなくなってしまったので、今でも出ているのかはわからない)。アルティマニアをはじめとする分厚い攻略本に親しんだひとも多いんじゃないか。 あの頃はたとえゲーム本体をプレイしなくても、攻略本を読むだけでワクワクした。その時の気持ちが蘇るような本なのだ、本書は。 扱われているゲームを実際に作ってほしい、という感想も見かけたけれど、個人的には架空のゲームだからこそ、本の断片的な情報から想像が広がるのも趣があっていいんじゃないかと思う。 また、実際にゲーム本体をプレイしないでその辺縁を楽しむという楽しみ方は、昨今のゲーム実況動画にも通じるところがあるような気がした。その意味で、懐かしくも新しい魅力がある作品だ。 プレイとは別に攻略本そのものが好きというひとや、限られた情報から空想を膨らませて一層楽しめるひとにおすすめできる。 - 2025年9月14日
 イリュージョン (集英社文庫)リチャード・バックいただいたかつて読んだ買って手元にある本、かつ読み終えた本に限定して追加しようと思うと、図書館本や気になる段階での未読本が除外されるので、なかなか悩ましい。 そこで、少し自分の中の範囲を広げて、いただいた本も出すことにした。 この『イリュージョン』は従姉妹からのいただきもの。自分だけでは選ばない、アンテナが向いていない本にも触れられるところが贈り物の素敵な点だなと思う。 小説ではあるけれど、その物語を説明しようとすると、けっこう難しい。ただ、上手く言葉に表せないお話こそが心に響くことは往々にしてある。この物語もそうした類のものだ。 話の筋だけをざっくりと示すなら、救世主と飛行機乗り(幾らかのお金と引き換えに人びとへ飛行体験を提供するお仕事)があちこちを旅するというもの。 けれども、そこで描かれているのは「自由」ということについてなのだと思う。人は思い込みによって自分を縛り付けている。何かを想像し、それができると信じれば、誰もがそれをできるのだ。 解説にもあるように、読み終えたら少しのあいだ放心し、それから遥かな空を感じさせてくれるようなお話だと思う。
イリュージョン (集英社文庫)リチャード・バックいただいたかつて読んだ買って手元にある本、かつ読み終えた本に限定して追加しようと思うと、図書館本や気になる段階での未読本が除外されるので、なかなか悩ましい。 そこで、少し自分の中の範囲を広げて、いただいた本も出すことにした。 この『イリュージョン』は従姉妹からのいただきもの。自分だけでは選ばない、アンテナが向いていない本にも触れられるところが贈り物の素敵な点だなと思う。 小説ではあるけれど、その物語を説明しようとすると、けっこう難しい。ただ、上手く言葉に表せないお話こそが心に響くことは往々にしてある。この物語もそうした類のものだ。 話の筋だけをざっくりと示すなら、救世主と飛行機乗り(幾らかのお金と引き換えに人びとへ飛行体験を提供するお仕事)があちこちを旅するというもの。 けれども、そこで描かれているのは「自由」ということについてなのだと思う。人は思い込みによって自分を縛り付けている。何かを想像し、それができると信じれば、誰もがそれをできるのだ。 解説にもあるように、読み終えたら少しのあいだ放心し、それから遥かな空を感じさせてくれるようなお話だと思う。 - 2025年3月23日
 夜市恒川光太郎買ったかつて読んだ読み返したフォロワーの方が挙げてらしたので、久々に読み返し。本書では、表題作もさることながら、書き下ろしの収録作「風の古道」が好きだ。 ひとならぬものたちが行き来する古道に入り込んだ少年の語りで展開する物語で、心細さ、奇妙さ、そしてわくわく感が絶妙に混ざり合った雰囲気が、なんかこう、怪しげなる想像を喚起してくれる。 シーンとしては古道の途中にある茶店で一夜を過ごすくだりが好くて、異界での修学旅行の夜みたいな感じがたまらない。もっとここを膨らませて書いてほしいくらいだ。 終わりはどこか、ウェルズの「塀にある扉」にもかすかに通じるような香りで、豊かな寂しさがある。
夜市恒川光太郎買ったかつて読んだ読み返したフォロワーの方が挙げてらしたので、久々に読み返し。本書では、表題作もさることながら、書き下ろしの収録作「風の古道」が好きだ。 ひとならぬものたちが行き来する古道に入り込んだ少年の語りで展開する物語で、心細さ、奇妙さ、そしてわくわく感が絶妙に混ざり合った雰囲気が、なんかこう、怪しげなる想像を喚起してくれる。 シーンとしては古道の途中にある茶店で一夜を過ごすくだりが好くて、異界での修学旅行の夜みたいな感じがたまらない。もっとここを膨らませて書いてほしいくらいだ。 終わりはどこか、ウェルズの「塀にある扉」にもかすかに通じるような香りで、豊かな寂しさがある。 - 2025年3月21日
 絶叫委員会穂村弘買ったかつて読んだ本書が初めての穂村さん本だったと思う。『ダ・ヴィンチ』経由で知ったのだったかな。あれから、何冊かを買って読んだ。 日常生活でふと出会うような印象的な言葉たちについて綴られたエッセイで、読んでいて楽しい。どこか『VOW』や『言いまつがい』にも似た雰囲気を感じる。 本書で好いなと思った点を抜き出してこようとするとキリがないけれど、とりわけ感じ入ったのは「直球勝負・その2」にあった、言葉が他者の心を貫くストレートにになるには「翼」をもたねばならない、というくだり。 直接的な言い方をするだけなら単なる棒球で、自己と世界との間に横たわる絶対的な亀裂を越えられないのだという。 言葉と翼といえば、新潮新書の『翼のある言葉』(紀田順一郎)も思い出す。これは独語の「時・場所を超えて胸に届く言葉」を表すフレーズから付けられたタイトルとのことで、別の著者の手になる無関係の本の内容がつながるように感じられ、趣深かった。 ある種の詩や現代短歌などがそうであるように、言葉の羽ばたきは、自分の胸に新鮮な空気を吹き込んでくれる。 それによって生きながらえているみたいな感覚がある。
絶叫委員会穂村弘買ったかつて読んだ本書が初めての穂村さん本だったと思う。『ダ・ヴィンチ』経由で知ったのだったかな。あれから、何冊かを買って読んだ。 日常生活でふと出会うような印象的な言葉たちについて綴られたエッセイで、読んでいて楽しい。どこか『VOW』や『言いまつがい』にも似た雰囲気を感じる。 本書で好いなと思った点を抜き出してこようとするとキリがないけれど、とりわけ感じ入ったのは「直球勝負・その2」にあった、言葉が他者の心を貫くストレートにになるには「翼」をもたねばならない、というくだり。 直接的な言い方をするだけなら単なる棒球で、自己と世界との間に横たわる絶対的な亀裂を越えられないのだという。 言葉と翼といえば、新潮新書の『翼のある言葉』(紀田順一郎)も思い出す。これは独語の「時・場所を超えて胸に届く言葉」を表すフレーズから付けられたタイトルとのことで、別の著者の手になる無関係の本の内容がつながるように感じられ、趣深かった。 ある種の詩や現代短歌などがそうであるように、言葉の羽ばたきは、自分の胸に新鮮な空気を吹き込んでくれる。 それによって生きながらえているみたいな感覚がある。 - 2025年3月19日
 少年の日の思い出 ヘッセ青春小説集ヘルマン・ヘッセ買ったかつて読んだヘッセの「少年の日の思い出」は中学の国語の教科書にも載っている、ある意味で国民的名作だ。 「そうか、そうか、つまりきみはそんなやつなんだな」というエーミールのセリフを覚えているひとは多いだろう。自分も久々にそのくだりを読み返したくなって本書を買った(本書の訳し方はちょっと異なっていたけれど)。 本作はタイトルに反してというか、少年の日からの脱却を読者にもたらすようなところがあると思っていて、それがインパクトの強さとなっているんじゃないか。 つまり、いわゆる「子供向け」の物語は多くが道徳的で、悪いことをしても悔いて謝れば許してもらえるような筋立てになっている。 たしかに幼い子供への情操教育としてそれは間違いではないと思うけれど、小学生を6年もやっていれば、世の中そんな都合よくいかないことくらいはわかるし、道徳的なお話を綺麗事のようにも感じるだろう。 そういう時に、「謝っても許してもらえないことがあるのだ」という現実をドンと突き付けてくるのが本作だ。しかも、それが教科書に載っている。 ご本というのは綺麗事ばかりじゃないんだ、と積極的には本を読んでこなかった子供にも知らしめてくれるような衝撃が、本作の意義の一つであるような気がする。 実際、エーミールが作中の語り手を許していたとしたら、このお話はここまで印象に残っただろうか?
少年の日の思い出 ヘッセ青春小説集ヘルマン・ヘッセ買ったかつて読んだヘッセの「少年の日の思い出」は中学の国語の教科書にも載っている、ある意味で国民的名作だ。 「そうか、そうか、つまりきみはそんなやつなんだな」というエーミールのセリフを覚えているひとは多いだろう。自分も久々にそのくだりを読み返したくなって本書を買った(本書の訳し方はちょっと異なっていたけれど)。 本作はタイトルに反してというか、少年の日からの脱却を読者にもたらすようなところがあると思っていて、それがインパクトの強さとなっているんじゃないか。 つまり、いわゆる「子供向け」の物語は多くが道徳的で、悪いことをしても悔いて謝れば許してもらえるような筋立てになっている。 たしかに幼い子供への情操教育としてそれは間違いではないと思うけれど、小学生を6年もやっていれば、世の中そんな都合よくいかないことくらいはわかるし、道徳的なお話を綺麗事のようにも感じるだろう。 そういう時に、「謝っても許してもらえないことがあるのだ」という現実をドンと突き付けてくるのが本作だ。しかも、それが教科書に載っている。 ご本というのは綺麗事ばかりじゃないんだ、と積極的には本を読んでこなかった子供にも知らしめてくれるような衝撃が、本作の意義の一つであるような気がする。 実際、エーミールが作中の語り手を許していたとしたら、このお話はここまで印象に残っただろうか? - 2025年3月14日
 図南の翼 十二国記 (講談社文庫)小野不由美買ったかつて読んだようやく自分の読んだ講談社文庫版が登録できるようになったので。 「十二国記」シリーズの中で一番自分が好きなのが、この『図南の翼』。 いろいろ好い要素があって挙げていくと長くなりそうだけど、作者はとにかくこまっしゃくれたというか、頭が良くて生意気な子供を描くのがめちゃくちゃ巧いと思った。 個人的に、子供の頭の良さというのは大人のそれとは異なる部分が大きく、また大人の賢さの劣化品でもないと思う。ただ、その違いを表現できているひとはあまり多くなくて、単に「小さい大人」になってしまっているような造形も見られるところ。 本作の主人公はその点、まさに賢い子供として描かれていて、素晴らしい。 あと、シーンごとのロジックに二段階の捻りを入れてくるのも痺れる。 たとえば、騎獣に名付けないこと。大切な騎獣なら名前を付けるだろう、というのが前提で、見捨てざるを得ない状況に備え、敢えて名前を付けないのだ、というのが一段階目の捻り。ここまでのロジックなら他作品でも見た覚えがあったけれど、本作ではもう一段階捻ってきていて、そこが感動を呼ぶ。 ほかにも、「本質を理解せずに形だけ真似るひと」みたいな人物のエピソードも、上手い具合に世界観に落とし込まれていて、読んでいて面白い。 ラストシーンの手前のやり取りも本当にグッとくるもので、いやこれネタバレしていいのかどうかわからないからとりあえず伏せるけれど、とにかく好いものだ。うん。
図南の翼 十二国記 (講談社文庫)小野不由美買ったかつて読んだようやく自分の読んだ講談社文庫版が登録できるようになったので。 「十二国記」シリーズの中で一番自分が好きなのが、この『図南の翼』。 いろいろ好い要素があって挙げていくと長くなりそうだけど、作者はとにかくこまっしゃくれたというか、頭が良くて生意気な子供を描くのがめちゃくちゃ巧いと思った。 個人的に、子供の頭の良さというのは大人のそれとは異なる部分が大きく、また大人の賢さの劣化品でもないと思う。ただ、その違いを表現できているひとはあまり多くなくて、単に「小さい大人」になってしまっているような造形も見られるところ。 本作の主人公はその点、まさに賢い子供として描かれていて、素晴らしい。 あと、シーンごとのロジックに二段階の捻りを入れてくるのも痺れる。 たとえば、騎獣に名付けないこと。大切な騎獣なら名前を付けるだろう、というのが前提で、見捨てざるを得ない状況に備え、敢えて名前を付けないのだ、というのが一段階目の捻り。ここまでのロジックなら他作品でも見た覚えがあったけれど、本作ではもう一段階捻ってきていて、そこが感動を呼ぶ。 ほかにも、「本質を理解せずに形だけ真似るひと」みたいな人物のエピソードも、上手い具合に世界観に落とし込まれていて、読んでいて面白い。 ラストシーンの手前のやり取りも本当にグッとくるもので、いやこれネタバレしていいのかどうかわからないからとりあえず伏せるけれど、とにかく好いものだ。うん。 - 2025年3月10日
 悪童日記アゴタ・クリストフ,堀茂樹買ったかつて読んだまだまだ検索で出てこない書籍が多いけれど、そのうち登録できるようになればいいな。ここに置いておきたいタイトルもいろいろとあるから。 何かを読むとき、読んでいてハッとさせられる作品は印象に残るもので、自分の場合、それは抒情的なシーンというより論理的構造というか、構成について「そうきたか……!」という不意打ち感を与えてくれる物語であることが多い。 本作もその一つで、とりわけ「精神を鍛える」にはやられた。 疎開という辛い境遇に立ち向かうため、精神修養としてお互いに厳しい言葉を投げかけ合うというのはわかる。ある意味で子供らしい対処法でもあるし、思い浮かびやすいアイディアだ。そうしてふたりは街のひとびとからの罵声にも動じない心を身につける。 だけど、そのあとに語られるもう一つの対処法は遥かに哀しくて残酷だ。 それゆえ、今なお強く印象に残っている。
悪童日記アゴタ・クリストフ,堀茂樹買ったかつて読んだまだまだ検索で出てこない書籍が多いけれど、そのうち登録できるようになればいいな。ここに置いておきたいタイトルもいろいろとあるから。 何かを読むとき、読んでいてハッとさせられる作品は印象に残るもので、自分の場合、それは抒情的なシーンというより論理的構造というか、構成について「そうきたか……!」という不意打ち感を与えてくれる物語であることが多い。 本作もその一つで、とりわけ「精神を鍛える」にはやられた。 疎開という辛い境遇に立ち向かうため、精神修養としてお互いに厳しい言葉を投げかけ合うというのはわかる。ある意味で子供らしい対処法でもあるし、思い浮かびやすいアイディアだ。そうしてふたりは街のひとびとからの罵声にも動じない心を身につける。 だけど、そのあとに語られるもう一つの対処法は遥かに哀しくて残酷だ。 それゆえ、今なお強く印象に残っている。 - 2025年3月7日
 不道徳教育講座 (角川文庫)三島由紀夫買ったかつて読んだ三島由紀夫といえば『青の時代』とか『金閣寺』とかのように小説作品を思い浮かべるひとも多いかも知れない。ただ、自分は論説・エッセイの類も好き。 本書でいうと「批評と悪口について」が印象に残っていて、わたしが作家の顔を知りたくない理由ってこういうところなんだよなぁ、と思った覚えがある。 あと、不道徳は一つだけ持っていると危ないから沢山持ってその間のバランスをとるようにすべき、という指摘は、まさしくと思った。 けっこうキレッキレなので、他者の思考や主張を愉しみたいひとにはおすすめな感じ。
不道徳教育講座 (角川文庫)三島由紀夫買ったかつて読んだ三島由紀夫といえば『青の時代』とか『金閣寺』とかのように小説作品を思い浮かべるひとも多いかも知れない。ただ、自分は論説・エッセイの類も好き。 本書でいうと「批評と悪口について」が印象に残っていて、わたしが作家の顔を知りたくない理由ってこういうところなんだよなぁ、と思った覚えがある。 あと、不道徳は一つだけ持っていると危ないから沢山持ってその間のバランスをとるようにすべき、という指摘は、まさしくと思った。 けっこうキレッキレなので、他者の思考や主張を愉しみたいひとにはおすすめな感じ。 - 2025年3月6日
 未来経過観測員田中空買ったかつて読んだこの作者さんのコミック、『タテの国』が好きで、小説も読んだという経緯。 作中で描かれる時間と空間のスケールの広大さ、遠大さが作者さんの持ち味のひとつなんじゃないかと個人的には思っていて、小さな悩みが吹き飛ぶような副次効果が嬉しい。 表題作は超長期睡眠技術を活用して100年ごとの定点未来観測を50000年先まで行うという主人公の話。 10年先の未来ですら朧げな身からすると、なんともまあ、ワクワクさせられるお話じゃあないですか。
未来経過観測員田中空買ったかつて読んだこの作者さんのコミック、『タテの国』が好きで、小説も読んだという経緯。 作中で描かれる時間と空間のスケールの広大さ、遠大さが作者さんの持ち味のひとつなんじゃないかと個人的には思っていて、小さな悩みが吹き飛ぶような副次効果が嬉しい。 表題作は超長期睡眠技術を活用して100年ごとの定点未来観測を50000年先まで行うという主人公の話。 10年先の未来ですら朧げな身からすると、なんともまあ、ワクワクさせられるお話じゃあないですか。 - 2025年3月6日
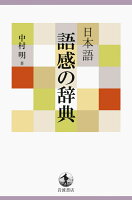 日本語 語感の辞典中村明買った読んでる辞典って好き? わたしはけっこう好き。眺めていたら言葉に埋もれられるから。 じゃあどんな辞典がいいかと聞かれたら挙げたいのが、語感の辞典。あと広辞苑も。 同じセリフでも言い方によって印象がまったく異なるというのはよく言われるけれど、同じ言葉でも、そのひとがその言葉にどのようなイメージをいだいているかによって伝わり方が異なる、というのもあると感じている。 この辞典は、単に知らない言葉に出逢えるというだけじゃなくて、知っているはずの言葉の感触を改めて確かめられる、そんな一冊。 なかなか浸れます。
日本語 語感の辞典中村明買った読んでる辞典って好き? わたしはけっこう好き。眺めていたら言葉に埋もれられるから。 じゃあどんな辞典がいいかと聞かれたら挙げたいのが、語感の辞典。あと広辞苑も。 同じセリフでも言い方によって印象がまったく異なるというのはよく言われるけれど、同じ言葉でも、そのひとがその言葉にどのようなイメージをいだいているかによって伝わり方が異なる、というのもあると感じている。 この辞典は、単に知らない言葉に出逢えるというだけじゃなくて、知っているはずの言葉の感触を改めて確かめられる、そんな一冊。 なかなか浸れます。 - 2025年3月6日
 オー・ヘンリー傑作選大津栄一郎買ったかつて読んだベタなチョイスかも知れないけれど、オー・ヘンリーならわたしは「賢者の贈りもの」が好き。 お互いに不要な物を贈り合った、いや、相手へ贈りものをすることによって相手からの贈り物を不要なものにしてしまった行為は、その表層だけを見るならむしろ愚かとも言える。 なのに、それこそが賢者の贈りものなのだ。 ジムとデラ、このふたりの行為を「賢者」によるものと呼ぶ、その優しさが読んでいてうれしかったんだと思う。
オー・ヘンリー傑作選大津栄一郎買ったかつて読んだベタなチョイスかも知れないけれど、オー・ヘンリーならわたしは「賢者の贈りもの」が好き。 お互いに不要な物を贈り合った、いや、相手へ贈りものをすることによって相手からの贈り物を不要なものにしてしまった行為は、その表層だけを見るならむしろ愚かとも言える。 なのに、それこそが賢者の贈りものなのだ。 ジムとデラ、このふたりの行為を「賢者」によるものと呼ぶ、その優しさが読んでいてうれしかったんだと思う。 - 2025年3月5日
 8月のソーダ水コマツシンヤ買ったかつて読んだ夏の爽やかさを凝縮したかのような一冊。 夏が好きなひとへの贈り物としてもいい感じ。 (爽やかは秋の季語だけどそれはそれとして) カンカン照りと海沿いの白亜の家々、そしてソーダ水。 いいよね……。
8月のソーダ水コマツシンヤ買ったかつて読んだ夏の爽やかさを凝縮したかのような一冊。 夏が好きなひとへの贈り物としてもいい感じ。 (爽やかは秋の季語だけどそれはそれとして) カンカン照りと海沿いの白亜の家々、そしてソーダ水。 いいよね……。 - 2025年3月5日
 だれかさんの悪夢星新一買ったかつて読んだこの中の「一日の仕事」という掌編がとても好き。 ひとりでパスタを食べるときにはいつも読む。 近未来の話のようでありながら、食べることと仕事することが直接的に結び付けられていて、働くことに絡む虚飾が剥ぎ取られているような感覚を与えてくれる。
だれかさんの悪夢星新一買ったかつて読んだこの中の「一日の仕事」という掌編がとても好き。 ひとりでパスタを食べるときにはいつも読む。 近未来の話のようでありながら、食べることと仕事することが直接的に結び付けられていて、働くことに絡む虚飾が剥ぎ取られているような感覚を与えてくれる。
読み込み中...
