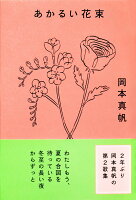ゆう
@yu_32
とにかく本が好き。
読んだ本の記録を残しておきたくて始めました。
楽しそうと思った本は何でも読みますが、小説やエッセイが多めです。
- 2026年2月15日
- 2026年2月14日
 水上バス浅草行き岡本真帆読み終わった再読岡本真帆さんの第一歌集。 明るい、楽しい、幸せ、な歌がたくさん。 でもそれだけじゃなくて、どこか心がざわざわと揺さぶられる。 光があれば影も生まれるかのように。
水上バス浅草行き岡本真帆読み終わった再読岡本真帆さんの第一歌集。 明るい、楽しい、幸せ、な歌がたくさん。 でもそれだけじゃなくて、どこか心がざわざわと揺さぶられる。 光があれば影も生まれるかのように。 - 2026年2月11日
 落雷と祝福岡本真帆読み終わった再読大好きな歌人、岡本真帆さんの短歌とエッセイ。 「好き」をテーマにしたエッセイは幸せに満ちている。 心の震え、笑顔、静かな高揚感。 「好き」と一口に言っても、そこには綺麗な感情だけではないかもしれない。 それでも、「好き」は特別な感情だ。 「おわりに」の文章もとても素敵なので、ぜひ本編と併せてじっくり味わってほしい。
落雷と祝福岡本真帆読み終わった再読大好きな歌人、岡本真帆さんの短歌とエッセイ。 「好き」をテーマにしたエッセイは幸せに満ちている。 心の震え、笑顔、静かな高揚感。 「好き」と一口に言っても、そこには綺麗な感情だけではないかもしれない。 それでも、「好き」は特別な感情だ。 「おわりに」の文章もとても素敵なので、ぜひ本編と併せてじっくり味わってほしい。 - 2026年2月8日
- 2026年2月7日
- 2026年2月4日
 おくれ毛で風を切れ古賀及子読み終わった再読古賀さんファミリーの一員になりたい、と一瞬考えるけど、この3人だからこその絶妙で繊細なバランスがあるのであって、それを見守らせてもらうといあ立場だからこそいいんだろうなと考え直す。
おくれ毛で風を切れ古賀及子読み終わった再読古賀さんファミリーの一員になりたい、と一瞬考えるけど、この3人だからこその絶妙で繊細なバランスがあるのであって、それを見守らせてもらうといあ立場だからこそいいんだろうなと考え直す。 - 2026年2月3日
- 2026年2月2日
 5秒日記古賀及子読み終わった古賀さんの最新作、待ちわびてました! もう、古賀さんの日記大好き。 息子さん娘さんも大好き。愛おしい。 ふふふと笑ってしまうところと、なるほど……と感じ入ってしまうところの塩梅が絶妙。 最新作出たばかりなのに、新刊まだですか?と思ってしまう己の強欲さに引く。 日記本っていいなぁ。
5秒日記古賀及子読み終わった古賀さんの最新作、待ちわびてました! もう、古賀さんの日記大好き。 息子さん娘さんも大好き。愛おしい。 ふふふと笑ってしまうところと、なるほど……と感じ入ってしまうところの塩梅が絶妙。 最新作出たばかりなのに、新刊まだですか?と思ってしまう己の強欲さに引く。 日記本っていいなぁ。 - 2026年1月24日
- 2026年1月18日
 伝える準備 携書版藤井貴彦読み終わった言葉の力を信じている藤井さんの、指南書。 言葉を丁寧に選び取っていく、でもアナウンサーとして瞬発力を求められる部分もある、その両輪を動かし続ける藤井さんの生身の言葉。 具体的に、相手に伝わるための言葉を選び取るために何をしたらいいのか、実際に藤井さんがやってきたことを紹介してくれているので、実践しやすい。 机上の空論じゃない。 言葉をただ相手に渡すだけじゃなくて、「伝わる」ためにできること。 指南書なのに読んでいて涙が出てしまった。 私たちが、「伝わる」言葉を選び始めたら、きっと世界はちょっと優しくなる。
伝える準備 携書版藤井貴彦読み終わった言葉の力を信じている藤井さんの、指南書。 言葉を丁寧に選び取っていく、でもアナウンサーとして瞬発力を求められる部分もある、その両輪を動かし続ける藤井さんの生身の言葉。 具体的に、相手に伝わるための言葉を選び取るために何をしたらいいのか、実際に藤井さんがやってきたことを紹介してくれているので、実践しやすい。 机上の空論じゃない。 言葉をただ相手に渡すだけじゃなくて、「伝わる」ためにできること。 指南書なのに読んでいて涙が出てしまった。 私たちが、「伝わる」言葉を選び始めたら、きっと世界はちょっと優しくなる。 - 2026年1月17日
 まだまだ大人になれませんひらりさ読み終わったえ?ひらりささんって私か? そう思った。自己効力感が低くて、選ばなかった選択肢にいつまでも未練がましくしがみついて。 自分を律することもままならない。 お酒とか危ない遊びとかの部分は共通していないけど。 迷いは消えないし、いつまでもふらふら流されている。 自分に責任を持てる気がしない。 それでも生きていく。生きていくしかない。 明確にエールとか支えとかになった!と断言する感じではないけど、「同世代のひらりささんもこんな感じなのか」と知ったことでちょっと楽になった節はある。 丁度、自分の中のもう一人の自分が「いい加減自分の人生ちゃんと考えた方がいいよ」と言ってきたタイミングで手に取った本。心が求めていたのかも。 どうにかサバイブしていくしかないなぁと。 にしても、こんなに心の内とか弱さとか開示できるの、逆に強くない?とひらりささんのまだまだこれからも開花するだろう大きな可能性を感じた。
まだまだ大人になれませんひらりさ読み終わったえ?ひらりささんって私か? そう思った。自己効力感が低くて、選ばなかった選択肢にいつまでも未練がましくしがみついて。 自分を律することもままならない。 お酒とか危ない遊びとかの部分は共通していないけど。 迷いは消えないし、いつまでもふらふら流されている。 自分に責任を持てる気がしない。 それでも生きていく。生きていくしかない。 明確にエールとか支えとかになった!と断言する感じではないけど、「同世代のひらりささんもこんな感じなのか」と知ったことでちょっと楽になった節はある。 丁度、自分の中のもう一人の自分が「いい加減自分の人生ちゃんと考えた方がいいよ」と言ってきたタイミングで手に取った本。心が求めていたのかも。 どうにかサバイブしていくしかないなぁと。 にしても、こんなに心の内とか弱さとか開示できるの、逆に強くない?とひらりささんのまだまだこれからも開花するだろう大きな可能性を感じた。 - 2026年1月17日
 文通 答えのない答え合わせスズキナオ,古賀及子読み終わった本当に答えがないことについて話し合う往復書簡。 手紙のやり取りの中で答えらしいものってあまり出てこないんだけど、簡単に答えが出てこないものを考え続けることって大事だなと教えてくれる。
文通 答えのない答え合わせスズキナオ,古賀及子読み終わった本当に答えがないことについて話し合う往復書簡。 手紙のやり取りの中で答えらしいものってあまり出てこないんだけど、簡単に答えが出てこないものを考え続けることって大事だなと教えてくれる。 - 2026年1月8日
- 2026年1月7日
 推してる、より、愛してる。最果タヒ読み終わった「好き」は光。 「好き」は心の音。 タヒさんが愛する宝塚の方への想いを綴ったエッセイ。 愛は静かに、そして真っ直ぐにきらめき続ける。 推しがいる身として、共感するところが多かった。 推しが推しになった瞬間の、心が撃ち抜かれるような衝撃はもちろん、推しの活動に触れるたびに高鳴る胸、目に焼き付けた光景を反芻しながら推しに馳せる思い。 それらが私の人生を豊かにしてくれる。 その分、推しの未来も明るく照らされますように。もし許されるならばその光の一部になれますように。 そう思うのです。
推してる、より、愛してる。最果タヒ読み終わった「好き」は光。 「好き」は心の音。 タヒさんが愛する宝塚の方への想いを綴ったエッセイ。 愛は静かに、そして真っ直ぐにきらめき続ける。 推しがいる身として、共感するところが多かった。 推しが推しになった瞬間の、心が撃ち抜かれるような衝撃はもちろん、推しの活動に触れるたびに高鳴る胸、目に焼き付けた光景を反芻しながら推しに馳せる思い。 それらが私の人生を豊かにしてくれる。 その分、推しの未来も明るく照らされますように。もし許されるならばその光の一部になれますように。 そう思うのです。 - 2026年1月3日
- 2026年1月3日
- 2025年12月30日
 虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった話題になってたので買ってみた本。 何だか、引っかかる。 それが読書の醍醐味の一つでもあるんだけど、どうにも咀嚼しきれない引っかかりがある。 それは自分も虚弱な部類に入るからだろうか。 ただ虚弱の方向が微妙に違うからだろうか。 その辺りはよく分からない。 時を経て読み直したらまた違う感想を持つかも。 何も感じないより、少しでも引っかかりがある本の方がいいのかもしれない。 数年後にまた読み直したい。
虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった話題になってたので買ってみた本。 何だか、引っかかる。 それが読書の醍醐味の一つでもあるんだけど、どうにも咀嚼しきれない引っかかりがある。 それは自分も虚弱な部類に入るからだろうか。 ただ虚弱の方向が微妙に違うからだろうか。 その辺りはよく分からない。 時を経て読み直したらまた違う感想を持つかも。 何も感じないより、少しでも引っかかりがある本の方がいいのかもしれない。 数年後にまた読み直したい。 - 2025年12月30日
 犬ではないと言われた犬向坂くじら読み終わったそうだよなぁと納得したり、むむむ?と考えさせられたり。 言葉って深いと言ってしまうとそれで終わってしまうけど、「深い」んだよなぁ。 なかなか自分の中のリズムと噛み合わなかったり、自分の中の文体と違ったりして、読み進めるのに体力が必要だったけど、それがポリリズムを生み出していて、「あー、読書の旨味……」と思いながら読んだ。
犬ではないと言われた犬向坂くじら読み終わったそうだよなぁと納得したり、むむむ?と考えさせられたり。 言葉って深いと言ってしまうとそれで終わってしまうけど、「深い」んだよなぁ。 なかなか自分の中のリズムと噛み合わなかったり、自分の中の文体と違ったりして、読み進めるのに体力が必要だったけど、それがポリリズムを生み出していて、「あー、読書の旨味……」と思いながら読んだ。 - 2025年12月29日
- 2025年12月28日
 ひきこもらないpha読み終わった再読超インドア、否、引きこもり予備軍、『ひきこもらない』を読む。 街に、住まいの機能をアウトソーシングしたら……みたいな話なんだけど、この本が出てからコロナ禍もあり、今もインフレしてるし、だいぶ事情が違ってきたなぁと思う。 でも、自分の気持ちをリフレッシュさせるために、どこかにふらっと出掛けたり、旅してみたり、そういうのはいいよね。 体力気力がないところとか、phaさんに似ているところもあるので、ふらっと出掛けられるところには憧れるけど、お家大好き人間なので、その域に達するのはいつになるやら。
ひきこもらないpha読み終わった再読超インドア、否、引きこもり予備軍、『ひきこもらない』を読む。 街に、住まいの機能をアウトソーシングしたら……みたいな話なんだけど、この本が出てからコロナ禍もあり、今もインフレしてるし、だいぶ事情が違ってきたなぁと思う。 でも、自分の気持ちをリフレッシュさせるために、どこかにふらっと出掛けたり、旅してみたり、そういうのはいいよね。 体力気力がないところとか、phaさんに似ているところもあるので、ふらっと出掛けられるところには憧れるけど、お家大好き人間なので、その域に達するのはいつになるやら。
読み込み中...