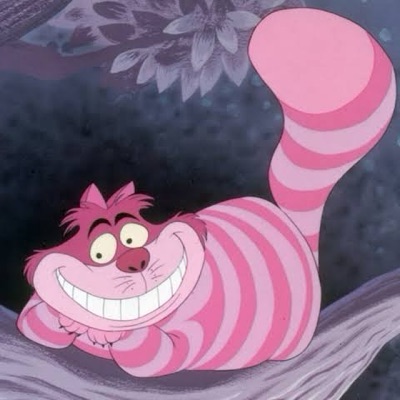批評理論入門 『フランケンシュタイン』解剖講義 (中公新書)

17件の記録
 tony_musik@tony_musik2025年11月1日読み終わった小説『フランケンシュタイン』をどのように読むことができるか、小説技法と批評理論に分けて徹底的に解説した本。この類の本は、研究対象となる作品が複数になることが多いと思うが、本作は『フランケンシュタイン』だけを読んでおけばいいのでとっつきやすかった。大変面白く勉強になる内容だったので時間をかけて読んだ。
tony_musik@tony_musik2025年11月1日読み終わった小説『フランケンシュタイン』をどのように読むことができるか、小説技法と批評理論に分けて徹底的に解説した本。この類の本は、研究対象となる作品が複数になることが多いと思うが、本作は『フランケンシュタイン』だけを読んでおけばいいのでとっつきやすかった。大変面白く勉強になる内容だったので時間をかけて読んだ。
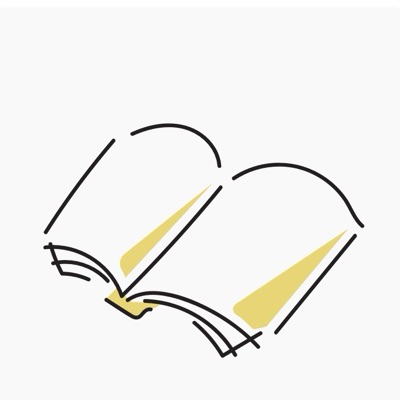
- barna-etsu@barba-etsu2025年9月20日読み終わった文学の読み方を体系的に教えてくれている本。ただ単に読むことももちろん一つの読み方であるけれども、いろんな批評のメソドロジーに基づいて読むことで深く読むことができるということを教えてくれる。ただ、批評できるということは、周辺知識がないと厳しいのが現実で、教養をつけなければ。。。と思わされた
- のーとみ@notomi2025年4月16日かつて読んだ基本「フランケンシュタイン」モノは読むようにしてるから、読まなきゃと思いつつ、つい創作・小説を優先して後回しにしちゃってたけど、これ凄い仕事だった。もう小学校高学年から中学の国語は、この本の第1部「小説技法篇」を、高校では第2部「批評理論篇」をベースに教えるといいんじゃないの?と思えるほどに、「小説」という表現の基本的な読み方と技術、それをどう分析するか、どう楽しむかの理論を考えるための材料が網羅されてる。そこにメアリ・シェリーが「フランケンシュタイン」をどのような小説技法で書き、現代の視点からそれを読み解くどういう方法があるのかが、ものすごく具体的に分かる仕掛けにもなってて、この二重構造自体が「小説論」への入門になっているのだった。 だから、まあ、私も長く小説読んで、文学批評もそこそこ目を通しているから、書かれていること自体に未知のものは無かったのだけど、ここまで明晰に具体的に、技術の使われ方、様々な批評視点のな活用法が書かれていると、自分がぼんやりしか理解していなかった部分がクッキリしてきて興奮してしまった。文章を読む面白さに溢れていた。さらにフランケンシュタインについての多様な読まれ方の実例がどんどん並んでいるのだから、そりゃ面白いに決まってるのだ。筒井康隆「文学部唯野教授」から怒りと男権的な視点を抜いて、評論として現代にアップデートした作品的な読み方も出来るかも。 これ2005年に出てたんだよね。19年も読まずにいたのが恥ずかしい。そのくらい基本図書的な素晴らしい仕事なのだった。もちろん「フランケンシュタイン」研究としても重要。なぜ、あの小説が200年以上読み継がれ、同様のテーマが反復され、様々なエンターテインメントの素材に使われ、今もなお研究されているかの理由もはっきりと分かる。副読本として藤田和日郎「怪物よ、三日月に踊れ」全6巻もね。