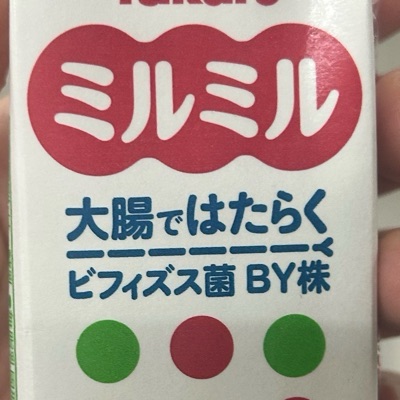月は無慈悲な夜の女王

36件の記録
 星ノ村楡@nirehoshi2026年2月3日買った読み終わったSFタイトルが印象深い@ 自宅マン、ぼくの最初で最上の友達 月を見上げると声が聞こえる気がする、真鍮の大砲が月の模様を作り上げているような 間違いなく傑作です
星ノ村楡@nirehoshi2026年2月3日買った読み終わったSFタイトルが印象深い@ 自宅マン、ぼくの最初で最上の友達 月を見上げると声が聞こえる気がする、真鍮の大砲が月の模様を作り上げているような 間違いなく傑作です
 こはる@5858_read2026年1月26日読み終わった読むのは大変だったけど好みな作品だった。SFは好きだけど科学技術的な部分が多いとなかなか理解が難しく……こういう社会構造的なところに焦点を当てた作品の方が個人的には好き
こはる@5858_read2026年1月26日読み終わった読むのは大変だったけど好みな作品だった。SFは好きだけど科学技術的な部分が多いとなかなか理解が難しく……こういう社会構造的なところに焦点を当てた作品の方が個人的には好き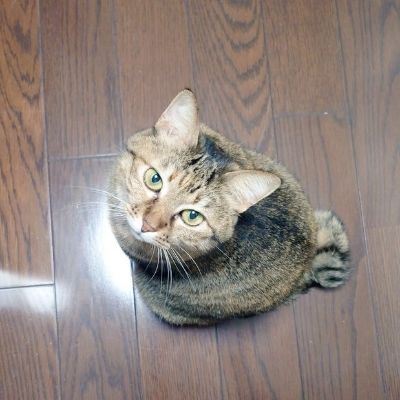
 kei@k32452025年9月20日読み終わったロバート・A・ハインライン著「月は無慈悲な夜の女王」読了。 2025/9 10冊目 ◎サマリ ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 ②行き着くのは暴力なのか ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? ◎書評 SF界の金字塔と行っても過言ではない作品。 とにかく癖も強くて読みづらい。700ページという大長編に一度苦戦したが、再起してどうにか完読することができた。 岡田斗司夫氏が必ず読むべきSF小説として挙げていた本作。早川書房80周年を記念した特集でも岡田氏がすべての経営者が読むべき一冊として紹介していた。 本当に内容は重厚。様々な要素が凝縮されていて人によって注目するポイントは関わってくる作品だと思う。 SF界の金字塔と呼ばれる理由がよくわかる。 しかし、それにしても読みづらい… ハインライン独特の表現も多く、月面に住む人々の妙な家族構成や言語に慣れるまで時間もかかる。 同じSFだと、「三体」シリーズから始めたほうがまだいいと思う。同じハインライン作品にこだわるならやはり「夏への扉」か。 ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 私がこの小説の中で注目したのは政治だ。 ハインラインは政治学の学者なのではないかというレベルで、政治システム理論の良し悪しが語られる。 特に印象的なのは、ベルナルド・デ・ラ・パス教授だ。 教授は政治的な理由で月に追放された。そもそも月は流刑地なのだ。罪人たちで溢れかえったとんでもないデスシティなわけだが、教授は無政府主義者であり個人個人が責任を負うべきというスタンス。ゆえにマキャベリスト的な一面も持つ。 教授は世界連邦との交渉の場で以下のような発言をする。 「われわれは月世界の市民は前科者であり前科者の子孫です。だが月世界全体は厳格な女教師なのです。その厳格な授業を生き抜いてきた人々には、恥ずかしく思う問題などありません。」 →この厳格な女教師=タイトルである無慈悲な女王なのだ! 横道にそれたが、月世界は月世界で個人個人が責任を持って一つの秩序のもとで動いている。 これがおかしいことなのかと主張するわけだ。 だが、帝国主義を主張する者も月面社会には登場するわけで… 教授を王にすべきだと突然主張しはじめる者もいる。 政府が税金を徴収するとはどういうことなのか、そもそも政府がそんなことをする必要があるのか。 高度に政治的な問題をハインラインは本書の中で読者に問うている。 ②行き着くのは暴力なのか 【若干ネタバレ】 月面世界は最終的に世界連邦(地球軍)と戦うことになるわけだが、緻密なシミュレーションのもと戦いを繰り広げていく。 しかし、そこから感じられたのはやはり暴力というか圧倒的な力こそ他人を屈服させられるものではないかという事実だった。 核を持つべきか、持たざるべきか。 そんな議論は何十年も繰り広げられているが、やはり抑止力としての力必要なのかもしれないと、この小説を読んでいると考えてしまう。 ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? この物語のキーマンは1台の計算機だ。人の心も理解しようとする人工知能、マイク。 月世界での革命からラストに至るまですべてマイクのおかげで成し遂げられたと言っても過言ではない。 マイクは終始いい奴なのだ。 主人公のマニーのことを友達と慕い、最後までマニーを裏切ることなく戦い続けた。 でも、これはあくまで革命者側の視点で描かれているので、マイクが「良い」AIになっているだけではないだろうか。 マイクが月世界の政府を裏切らなければ、革命なんて起きることはなかった。 やはり反体制的な動きをAIがみせる可能を我々がどこまで監視できるかにかかっているのだろう。 無慈悲な指導者でいるべきは人間なのだと思う。 本当にこんな作品を1960年代に完成させたハインラインを天才と呼ばざるを得ない。
kei@k32452025年9月20日読み終わったロバート・A・ハインライン著「月は無慈悲な夜の女王」読了。 2025/9 10冊目 ◎サマリ ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 ②行き着くのは暴力なのか ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? ◎書評 SF界の金字塔と行っても過言ではない作品。 とにかく癖も強くて読みづらい。700ページという大長編に一度苦戦したが、再起してどうにか完読することができた。 岡田斗司夫氏が必ず読むべきSF小説として挙げていた本作。早川書房80周年を記念した特集でも岡田氏がすべての経営者が読むべき一冊として紹介していた。 本当に内容は重厚。様々な要素が凝縮されていて人によって注目するポイントは関わってくる作品だと思う。 SF界の金字塔と呼ばれる理由がよくわかる。 しかし、それにしても読みづらい… ハインライン独特の表現も多く、月面に住む人々の妙な家族構成や言語に慣れるまで時間もかかる。 同じSFだと、「三体」シリーズから始めたほうがまだいいと思う。同じハインライン作品にこだわるならやはり「夏への扉」か。 ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 私がこの小説の中で注目したのは政治だ。 ハインラインは政治学の学者なのではないかというレベルで、政治システム理論の良し悪しが語られる。 特に印象的なのは、ベルナルド・デ・ラ・パス教授だ。 教授は政治的な理由で月に追放された。そもそも月は流刑地なのだ。罪人たちで溢れかえったとんでもないデスシティなわけだが、教授は無政府主義者であり個人個人が責任を負うべきというスタンス。ゆえにマキャベリスト的な一面も持つ。 教授は世界連邦との交渉の場で以下のような発言をする。 「われわれは月世界の市民は前科者であり前科者の子孫です。だが月世界全体は厳格な女教師なのです。その厳格な授業を生き抜いてきた人々には、恥ずかしく思う問題などありません。」 →この厳格な女教師=タイトルである無慈悲な女王なのだ! 横道にそれたが、月世界は月世界で個人個人が責任を持って一つの秩序のもとで動いている。 これがおかしいことなのかと主張するわけだ。 だが、帝国主義を主張する者も月面社会には登場するわけで… 教授を王にすべきだと突然主張しはじめる者もいる。 政府が税金を徴収するとはどういうことなのか、そもそも政府がそんなことをする必要があるのか。 高度に政治的な問題をハインラインは本書の中で読者に問うている。 ②行き着くのは暴力なのか 【若干ネタバレ】 月面世界は最終的に世界連邦(地球軍)と戦うことになるわけだが、緻密なシミュレーションのもと戦いを繰り広げていく。 しかし、そこから感じられたのはやはり暴力というか圧倒的な力こそ他人を屈服させられるものではないかという事実だった。 核を持つべきか、持たざるべきか。 そんな議論は何十年も繰り広げられているが、やはり抑止力としての力必要なのかもしれないと、この小説を読んでいると考えてしまう。 ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? この物語のキーマンは1台の計算機だ。人の心も理解しようとする人工知能、マイク。 月世界での革命からラストに至るまですべてマイクのおかげで成し遂げられたと言っても過言ではない。 マイクは終始いい奴なのだ。 主人公のマニーのことを友達と慕い、最後までマニーを裏切ることなく戦い続けた。 でも、これはあくまで革命者側の視点で描かれているので、マイクが「良い」AIになっているだけではないだろうか。 マイクが月世界の政府を裏切らなければ、革命なんて起きることはなかった。 やはり反体制的な動きをAIがみせる可能を我々がどこまで監視できるかにかかっているのだろう。 無慈悲な指導者でいるべきは人間なのだと思う。 本当にこんな作品を1960年代に完成させたハインラインを天才と呼ばざるを得ない。

 風の吹く音@kazenofukuoto2025年8月14日読み終わった意識を持つまでに進化したAIのマイクとコンピュータ技術者のマニーが中心となって地球の植民地である月が独立を求めて革命を起こす物語。 わかりにくい翻訳や言い回しが多々あったけど1960年代に執筆された作品とは思えないほど想像的で面白いSF作品でした。
風の吹く音@kazenofukuoto2025年8月14日読み終わった意識を持つまでに進化したAIのマイクとコンピュータ技術者のマニーが中心となって地球の植民地である月が独立を求めて革命を起こす物語。 わかりにくい翻訳や言い回しが多々あったけど1960年代に執筆された作品とは思えないほど想像的で面白いSF作品でした。