

kei
@k3245
とあるコンサルタントのつぶやき。
- 2025年10月21日
 世阿弥風姿花伝土屋恵一郎読み終わった土屋惠一郎著「100分de名著books 風姿花伝」読了。 2025/10 2冊目 ◎サマリ ①100分de名著booksのすばらしさ ②3つの初心 ③男どき女どき(おどきめどき)と秘すれば花 ◎書評 能の大家、世阿弥の著作である「風姿花伝」を読もうと思ったが、前置きなしに読める自信がなく初めてこの100分de名著シリーズに手を出した。 ①100分de名著booksのすばらしさ これが正解だった。古典への入り口としてとても分かりやすく解説されている。 世阿弥が生きた時代や生涯もきちんとまとめられているので、頭の中での整理も進みやすい。 しかし、これで風姿花伝を読んだつもりになってはいけないだろう。 あくまで導入を助けるための書籍であって、これを読んで風姿花伝を読んだというのは違うと思う。 風姿花伝への入り口としては最適なので、ここから自分で深堀をしていく必要があると感じた。 ②3つの初心 初心忘るべからず。 世阿弥の遺した言葉の中でも一番有名と言っても過言ではないだろう。 これは能を始めた頃の気持ちを忘れるなという意味だと思っていたが実は違うことがわかった。 世阿弥は3つの初心を提示する。 24,5歳 一人前になるタイミングで自分は達人であるかのような錯覚を覚える。 ここで初心を忘れず稽古に臨め。 34,5歳 能のピーク このタイミングで天下を取らなければならない。 自分のこれまでの人生を振り返り、今後進むべき道を考えることが必要。 50歳超え 老木としていかに花を咲かせるか。 初心にかえって見定めるべき。 私もそろそろ能のピークの時期に差し掛かる。 天下を取るなんてできるのだろうか…と不安になるものの、現代社会だとピークはもう少し後ろなのかもしれない。 であれば、今が一人前になり花盛りなのかもしれない。 その時期に初心を忘れずに臨む。 改めて自己分析なんかも行うのにぴったりのタイミングと言えるだろう。 3つの初心の考えは目からうろこだった。 ③男どき女どき(おどきめどき)と秘すれば花 人生には勢いがあり何をやってもうまくいく男どきとその逆の女どきがある。 いい時もあれば悪い時もある。それが人生だと世阿弥も言う。 しかし、女どきにも努力を怠ってはいけない。しっかり準備をして男どきを待つ。 調子悪いなというタイミングでは、変にもがいたりせず考え方を少し変えてみて、新たな波が来るのに備えてもいいのかもしれない。 混沌とする現代社会に必要な考え方だ。 そして、秘すれば花。 これも有名な言葉だが、世阿弥はただ隠せばいいと言っているわけではないという。 時流に乗ってタイミングよく披露することこそ、秘すれば花の真の意味だと。 タイミングを自分で作っていき、場という生き物を制す。 とても難しいことではあるが時代の潮流を見定め、うまく波に乗ることは今後からに求められていくだろう。 こういったふうに世阿弥の考え方は現代のビジネス、特にマーケティング論に通ずると著者はいう。 これも世阿弥の生きた時代は能のパトロンが変化し、年功序列も崩れていった時代であったことが影響する。 世阿弥の考え方はもっと深堀したくなった。 そして、巻末には能の見方についても丁寧に解説されている。 能楽場にも足を運んでみたい。
世阿弥風姿花伝土屋恵一郎読み終わった土屋惠一郎著「100分de名著books 風姿花伝」読了。 2025/10 2冊目 ◎サマリ ①100分de名著booksのすばらしさ ②3つの初心 ③男どき女どき(おどきめどき)と秘すれば花 ◎書評 能の大家、世阿弥の著作である「風姿花伝」を読もうと思ったが、前置きなしに読める自信がなく初めてこの100分de名著シリーズに手を出した。 ①100分de名著booksのすばらしさ これが正解だった。古典への入り口としてとても分かりやすく解説されている。 世阿弥が生きた時代や生涯もきちんとまとめられているので、頭の中での整理も進みやすい。 しかし、これで風姿花伝を読んだつもりになってはいけないだろう。 あくまで導入を助けるための書籍であって、これを読んで風姿花伝を読んだというのは違うと思う。 風姿花伝への入り口としては最適なので、ここから自分で深堀をしていく必要があると感じた。 ②3つの初心 初心忘るべからず。 世阿弥の遺した言葉の中でも一番有名と言っても過言ではないだろう。 これは能を始めた頃の気持ちを忘れるなという意味だと思っていたが実は違うことがわかった。 世阿弥は3つの初心を提示する。 24,5歳 一人前になるタイミングで自分は達人であるかのような錯覚を覚える。 ここで初心を忘れず稽古に臨め。 34,5歳 能のピーク このタイミングで天下を取らなければならない。 自分のこれまでの人生を振り返り、今後進むべき道を考えることが必要。 50歳超え 老木としていかに花を咲かせるか。 初心にかえって見定めるべき。 私もそろそろ能のピークの時期に差し掛かる。 天下を取るなんてできるのだろうか…と不安になるものの、現代社会だとピークはもう少し後ろなのかもしれない。 であれば、今が一人前になり花盛りなのかもしれない。 その時期に初心を忘れずに臨む。 改めて自己分析なんかも行うのにぴったりのタイミングと言えるだろう。 3つの初心の考えは目からうろこだった。 ③男どき女どき(おどきめどき)と秘すれば花 人生には勢いがあり何をやってもうまくいく男どきとその逆の女どきがある。 いい時もあれば悪い時もある。それが人生だと世阿弥も言う。 しかし、女どきにも努力を怠ってはいけない。しっかり準備をして男どきを待つ。 調子悪いなというタイミングでは、変にもがいたりせず考え方を少し変えてみて、新たな波が来るのに備えてもいいのかもしれない。 混沌とする現代社会に必要な考え方だ。 そして、秘すれば花。 これも有名な言葉だが、世阿弥はただ隠せばいいと言っているわけではないという。 時流に乗ってタイミングよく披露することこそ、秘すれば花の真の意味だと。 タイミングを自分で作っていき、場という生き物を制す。 とても難しいことではあるが時代の潮流を見定め、うまく波に乗ることは今後からに求められていくだろう。 こういったふうに世阿弥の考え方は現代のビジネス、特にマーケティング論に通ずると著者はいう。 これも世阿弥の生きた時代は能のパトロンが変化し、年功序列も崩れていった時代であったことが影響する。 世阿弥の考え方はもっと深堀したくなった。 そして、巻末には能の見方についても丁寧に解説されている。 能楽場にも足を運んでみたい。 - 2025年10月14日
 自省録(マルクス・アウレーリウス)マルクス・アウレーリウス,神谷美恵子読み終わったマルクス・アウレリウス・アントニヌス著「自省録」読了。 2025/10 1冊目 ◎サマリ ①今を善く生きろ。 ②万物の変化を受け入れろ ③すべては諸行無常 ◎書評 哲人皇帝、マルクス・アウレリウスの日記のような散文がまとめられた作品。 そもそも皇帝になどなりたくはなく、それをも自分の運命だと受け入れ、皇帝としてのとしての職務をまっとうしたマルクス。 度重なる異国人との戦争の際、野営地でも自分を戒めるため文章を書き続けた。 ストア派哲学のお手本のように、哲学にストイックな面が多分に見られる。 しかし、ただただ小難しいことを言っているだけではない。 マルクスが自分自身を奮い立たせるため書いた文章に熱い想いを抱かずにはいられなくなる。 ストレスの多い現代社会を生き抜くためのヒントがこの名著には眠っていると感じた。 ①今を善く生きろ。 マルクスはとにかく人生は短い、今を善く生きろと何度も書いている。 他人のことをあれこれ言ったり、無駄なことに時間を使っている暇はない。未来も過去も存在しない。存在するのは今だけ。 神から与えられた自然の法に従い、困難なことも耐え忍び今を懸命に生きるのだ。 そういったメッセージを常にマルクスは自分自身に送っている。 これは一種のアファメーションのようなものではないかとも思う。 つらい皇帝という職を平和主義的にまっとうするためマルクスは約60年の生涯を使い切った。 哲学で自分自身を奮い立たせずにはいられないこともあったのだろうと想像する。 「現在の時を自分への贈物として与えるように心がけるがよい。」 やりたいことをやりなさい。 そんな自己啓発もよく見かけるが、ローマ帝国の時代から賢人の主張は変わらないのだ。 でも、我々は変化を恐れて行動に移せない。それではだめだ!自分はできる!と常にマルクスは自省していたのだろう。 ②万物の変化を受け入れろ 現代人にとって苦手なことのひとつだと思う。 分かっていてもなかなかできないこと第1位かもしれない。 こんな困難なことにもマルクスはしっかり触れている。 「変化を恐れる者があるのか。しかし変化なくしてなにぞ生じえようぞ。宇宙の自然にとってこれよりも愛すべく親しみ深いものがあろうか。君自身だって、木がある変化を経たなかったならば、熱い湯にひとつはいれるだろうか。もし食物が変化を経なかったならば、自分を養うことができるだろうか。」 万物は変わり続ける。 そして歴史は繰り返す。それを受け入れることができるかどうかなのだろう。 これもアファメーション的に自分の身に浸透させていくしかないのだと思う。 ③すべては諸行無常 「人生の時は一瞬にすぎず、人の実質は流れ行き、その感覚は鈍く、その肉体全体の組合せは腐敗しやすく、その魂は渦を巻いており、その運命ははかりがたく、その名声は不確実である。」 変化の話に似ているが、永遠などというものはないと何度もマルクスは語る。 だからこそ名声や財産に執着してはいけないと。 マルクスの哲学は禅の思想にも通ずるものがあるように思う。 とにかく日々を善く生きようと努力すること。 そのために自分自身の行動を変えていく大切さを現代人に教えてくれているのだ。
自省録(マルクス・アウレーリウス)マルクス・アウレーリウス,神谷美恵子読み終わったマルクス・アウレリウス・アントニヌス著「自省録」読了。 2025/10 1冊目 ◎サマリ ①今を善く生きろ。 ②万物の変化を受け入れろ ③すべては諸行無常 ◎書評 哲人皇帝、マルクス・アウレリウスの日記のような散文がまとめられた作品。 そもそも皇帝になどなりたくはなく、それをも自分の運命だと受け入れ、皇帝としてのとしての職務をまっとうしたマルクス。 度重なる異国人との戦争の際、野営地でも自分を戒めるため文章を書き続けた。 ストア派哲学のお手本のように、哲学にストイックな面が多分に見られる。 しかし、ただただ小難しいことを言っているだけではない。 マルクスが自分自身を奮い立たせるため書いた文章に熱い想いを抱かずにはいられなくなる。 ストレスの多い現代社会を生き抜くためのヒントがこの名著には眠っていると感じた。 ①今を善く生きろ。 マルクスはとにかく人生は短い、今を善く生きろと何度も書いている。 他人のことをあれこれ言ったり、無駄なことに時間を使っている暇はない。未来も過去も存在しない。存在するのは今だけ。 神から与えられた自然の法に従い、困難なことも耐え忍び今を懸命に生きるのだ。 そういったメッセージを常にマルクスは自分自身に送っている。 これは一種のアファメーションのようなものではないかとも思う。 つらい皇帝という職を平和主義的にまっとうするためマルクスは約60年の生涯を使い切った。 哲学で自分自身を奮い立たせずにはいられないこともあったのだろうと想像する。 「現在の時を自分への贈物として与えるように心がけるがよい。」 やりたいことをやりなさい。 そんな自己啓発もよく見かけるが、ローマ帝国の時代から賢人の主張は変わらないのだ。 でも、我々は変化を恐れて行動に移せない。それではだめだ!自分はできる!と常にマルクスは自省していたのだろう。 ②万物の変化を受け入れろ 現代人にとって苦手なことのひとつだと思う。 分かっていてもなかなかできないこと第1位かもしれない。 こんな困難なことにもマルクスはしっかり触れている。 「変化を恐れる者があるのか。しかし変化なくしてなにぞ生じえようぞ。宇宙の自然にとってこれよりも愛すべく親しみ深いものがあろうか。君自身だって、木がある変化を経たなかったならば、熱い湯にひとつはいれるだろうか。もし食物が変化を経なかったならば、自分を養うことができるだろうか。」 万物は変わり続ける。 そして歴史は繰り返す。それを受け入れることができるかどうかなのだろう。 これもアファメーション的に自分の身に浸透させていくしかないのだと思う。 ③すべては諸行無常 「人生の時は一瞬にすぎず、人の実質は流れ行き、その感覚は鈍く、その肉体全体の組合せは腐敗しやすく、その魂は渦を巻いており、その運命ははかりがたく、その名声は不確実である。」 変化の話に似ているが、永遠などというものはないと何度もマルクスは語る。 だからこそ名声や財産に執着してはいけないと。 マルクスの哲学は禅の思想にも通ずるものがあるように思う。 とにかく日々を善く生きようと努力すること。 そのために自分自身の行動を変えていく大切さを現代人に教えてくれているのだ。 - 2025年10月14日
- 2025年10月14日
 Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章ルトガー・ブレグマン,野中香方子読みたい
Humankind 希望の歴史 上 人類が善き未来をつくるための18章ルトガー・ブレグマン,野中香方子読みたい - 2025年10月14日
 菜根譚今井宇三郎,洪自誠読みたい
菜根譚今井宇三郎,洪自誠読みたい - 2025年10月14日
 料理の四面体玉村豊男読みたい
料理の四面体玉村豊男読みたい - 2025年10月7日
![[完全版]生きがいの創造](https://m.media-amazon.com/images/I/51R0wWTN5RL._SL500_.jpg) [完全版]生きがいの創造飯田史彦読みたい
[完全版]生きがいの創造飯田史彦読みたい - 2025年10月3日
 陰翳礼讃谷崎潤一郎読みたい
陰翳礼讃谷崎潤一郎読みたい - 2025年9月20日
 月は無慈悲な夜の女王ロバート・A・ハインライン,矢野徹読み終わったロバート・A・ハインライン著「月は無慈悲な夜の女王」読了。 2025/9 10冊目 ◎サマリ ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 ②行き着くのは暴力なのか ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? ◎書評 SF界の金字塔と行っても過言ではない作品。 とにかく癖も強くて読みづらい。700ページという大長編に一度苦戦したが、再起してどうにか完読することができた。 岡田斗司夫氏が必ず読むべきSF小説として挙げていた本作。早川書房80周年を記念した特集でも岡田氏がすべての経営者が読むべき一冊として紹介していた。 本当に内容は重厚。様々な要素が凝縮されていて人によって注目するポイントは関わってくる作品だと思う。 SF界の金字塔と呼ばれる理由がよくわかる。 しかし、それにしても読みづらい… ハインライン独特の表現も多く、月面に住む人々の妙な家族構成や言語に慣れるまで時間もかかる。 同じSFだと、「三体」シリーズから始めたほうがまだいいと思う。同じハインライン作品にこだわるならやはり「夏への扉」か。 ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 私がこの小説の中で注目したのは政治だ。 ハインラインは政治学の学者なのではないかというレベルで、政治システム理論の良し悪しが語られる。 特に印象的なのは、ベルナルド・デ・ラ・パス教授だ。 教授は政治的な理由で月に追放された。そもそも月は流刑地なのだ。罪人たちで溢れかえったとんでもないデスシティなわけだが、教授は無政府主義者であり個人個人が責任を負うべきというスタンス。ゆえにマキャベリスト的な一面も持つ。 教授は世界連邦との交渉の場で以下のような発言をする。 「われわれは月世界の市民は前科者であり前科者の子孫です。だが月世界全体は厳格な女教師なのです。その厳格な授業を生き抜いてきた人々には、恥ずかしく思う問題などありません。」 →この厳格な女教師=タイトルである無慈悲な女王なのだ! 横道にそれたが、月世界は月世界で個人個人が責任を持って一つの秩序のもとで動いている。 これがおかしいことなのかと主張するわけだ。 だが、帝国主義を主張する者も月面社会には登場するわけで… 教授を王にすべきだと突然主張しはじめる者もいる。 政府が税金を徴収するとはどういうことなのか、そもそも政府がそんなことをする必要があるのか。 高度に政治的な問題をハインラインは本書の中で読者に問うている。 ②行き着くのは暴力なのか 【若干ネタバレ】 月面世界は最終的に世界連邦(地球軍)と戦うことになるわけだが、緻密なシミュレーションのもと戦いを繰り広げていく。 しかし、そこから感じられたのはやはり暴力というか圧倒的な力こそ他人を屈服させられるものではないかという事実だった。 核を持つべきか、持たざるべきか。 そんな議論は何十年も繰り広げられているが、やはり抑止力としての力必要なのかもしれないと、この小説を読んでいると考えてしまう。 ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? この物語のキーマンは1台の計算機だ。人の心も理解しようとする人工知能、マイク。 月世界での革命からラストに至るまですべてマイクのおかげで成し遂げられたと言っても過言ではない。 マイクは終始いい奴なのだ。 主人公のマニーのことを友達と慕い、最後までマニーを裏切ることなく戦い続けた。 でも、これはあくまで革命者側の視点で描かれているので、マイクが「良い」AIになっているだけではないだろうか。 マイクが月世界の政府を裏切らなければ、革命なんて起きることはなかった。 やはり反体制的な動きをAIがみせる可能を我々がどこまで監視できるかにかかっているのだろう。 無慈悲な指導者でいるべきは人間なのだと思う。 本当にこんな作品を1960年代に完成させたハインラインを天才と呼ばざるを得ない。
月は無慈悲な夜の女王ロバート・A・ハインライン,矢野徹読み終わったロバート・A・ハインライン著「月は無慈悲な夜の女王」読了。 2025/9 10冊目 ◎サマリ ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 ②行き着くのは暴力なのか ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? ◎書評 SF界の金字塔と行っても過言ではない作品。 とにかく癖も強くて読みづらい。700ページという大長編に一度苦戦したが、再起してどうにか完読することができた。 岡田斗司夫氏が必ず読むべきSF小説として挙げていた本作。早川書房80周年を記念した特集でも岡田氏がすべての経営者が読むべき一冊として紹介していた。 本当に内容は重厚。様々な要素が凝縮されていて人によって注目するポイントは関わってくる作品だと思う。 SF界の金字塔と呼ばれる理由がよくわかる。 しかし、それにしても読みづらい… ハインライン独特の表現も多く、月面に住む人々の妙な家族構成や言語に慣れるまで時間もかかる。 同じSFだと、「三体」シリーズから始めたほうがまだいいと思う。同じハインライン作品にこだわるならやはり「夏への扉」か。 ①SF界の金字塔であり高度に政治的な小説 私がこの小説の中で注目したのは政治だ。 ハインラインは政治学の学者なのではないかというレベルで、政治システム理論の良し悪しが語られる。 特に印象的なのは、ベルナルド・デ・ラ・パス教授だ。 教授は政治的な理由で月に追放された。そもそも月は流刑地なのだ。罪人たちで溢れかえったとんでもないデスシティなわけだが、教授は無政府主義者であり個人個人が責任を負うべきというスタンス。ゆえにマキャベリスト的な一面も持つ。 教授は世界連邦との交渉の場で以下のような発言をする。 「われわれは月世界の市民は前科者であり前科者の子孫です。だが月世界全体は厳格な女教師なのです。その厳格な授業を生き抜いてきた人々には、恥ずかしく思う問題などありません。」 →この厳格な女教師=タイトルである無慈悲な女王なのだ! 横道にそれたが、月世界は月世界で個人個人が責任を持って一つの秩序のもとで動いている。 これがおかしいことなのかと主張するわけだ。 だが、帝国主義を主張する者も月面社会には登場するわけで… 教授を王にすべきだと突然主張しはじめる者もいる。 政府が税金を徴収するとはどういうことなのか、そもそも政府がそんなことをする必要があるのか。 高度に政治的な問題をハインラインは本書の中で読者に問うている。 ②行き着くのは暴力なのか 【若干ネタバレ】 月面世界は最終的に世界連邦(地球軍)と戦うことになるわけだが、緻密なシミュレーションのもと戦いを繰り広げていく。 しかし、そこから感じられたのはやはり暴力というか圧倒的な力こそ他人を屈服させられるものではないかという事実だった。 核を持つべきか、持たざるべきか。 そんな議論は何十年も繰り広げられているが、やはり抑止力としての力必要なのかもしれないと、この小説を読んでいると考えてしまう。 ③AIはみんなマイクのような「良い」AIなのか? この物語のキーマンは1台の計算機だ。人の心も理解しようとする人工知能、マイク。 月世界での革命からラストに至るまですべてマイクのおかげで成し遂げられたと言っても過言ではない。 マイクは終始いい奴なのだ。 主人公のマニーのことを友達と慕い、最後までマニーを裏切ることなく戦い続けた。 でも、これはあくまで革命者側の視点で描かれているので、マイクが「良い」AIになっているだけではないだろうか。 マイクが月世界の政府を裏切らなければ、革命なんて起きることはなかった。 やはり反体制的な動きをAIがみせる可能を我々がどこまで監視できるかにかかっているのだろう。 無慈悲な指導者でいるべきは人間なのだと思う。 本当にこんな作品を1960年代に完成させたハインラインを天才と呼ばざるを得ない。 - 2025年9月13日
 怒り 上下巻セット吉田修一読み終わった吉田修一著「怒り 上下巻」読了。 2025/9 8冊目,9冊目 ◎書評 大ヒット中の映画「国宝」の作者、吉田修一の小説。 総論的として、とても面白かった。 最後の風呂敷の閉じ方もうますぎる。 吉田修一の小説はやはり濃厚。 八王子での殺人事件をベースに、千葉の房総半島に住む親子、東京に住む30代のゲイ、沖縄に住む夜逃げを何度も繰り返す親子の物語が順に描かれる。 八王子での殺人事件の犯人、山神は逃亡しておりどこかに潜伏している。 それを警察が追っていく中でいくつかの犯人の特徴を得る。 犯人の特徴は房総半島に住む親子の元に現れた青年、ゲイの家に転がり込んだ男、沖縄の無人島で偶然出会った男と一致する。 果たして誰が犯人なのか…最後までハラハラする展開だった。 そして、八王子の事件現場に残された「怒」の血文字。 犯人は何に怒っていたのだろうか。 個人的には、自分が生きていることへの「怒り」のように感じた。 【ここからネタバレあり】 犯人の気に入った人間の懐に入っていくことが得意という特性、死にたくはないけど死んでもいいという考え方。 相手と仲良くなってもどこか空虚感を感じてしまう自分に対する「怒り」。 その怒りを思わず相手にぶつけてしまうことの「怒り」へと通じていたのではないかと思う。 しかし、この小説で怒っていたのは犯人だけではない。 多くの登場人物が様々な事象に「怒り」を感じていた。 これらの「怒り」とどう向き合っていくか。それが試される世の中であることを吉田修一は示したかったようにも感じた。
怒り 上下巻セット吉田修一読み終わった吉田修一著「怒り 上下巻」読了。 2025/9 8冊目,9冊目 ◎書評 大ヒット中の映画「国宝」の作者、吉田修一の小説。 総論的として、とても面白かった。 最後の風呂敷の閉じ方もうますぎる。 吉田修一の小説はやはり濃厚。 八王子での殺人事件をベースに、千葉の房総半島に住む親子、東京に住む30代のゲイ、沖縄に住む夜逃げを何度も繰り返す親子の物語が順に描かれる。 八王子での殺人事件の犯人、山神は逃亡しておりどこかに潜伏している。 それを警察が追っていく中でいくつかの犯人の特徴を得る。 犯人の特徴は房総半島に住む親子の元に現れた青年、ゲイの家に転がり込んだ男、沖縄の無人島で偶然出会った男と一致する。 果たして誰が犯人なのか…最後までハラハラする展開だった。 そして、八王子の事件現場に残された「怒」の血文字。 犯人は何に怒っていたのだろうか。 個人的には、自分が生きていることへの「怒り」のように感じた。 【ここからネタバレあり】 犯人の気に入った人間の懐に入っていくことが得意という特性、死にたくはないけど死んでもいいという考え方。 相手と仲良くなってもどこか空虚感を感じてしまう自分に対する「怒り」。 その怒りを思わず相手にぶつけてしまうことの「怒り」へと通じていたのではないかと思う。 しかし、この小説で怒っていたのは犯人だけではない。 多くの登場人物が様々な事象に「怒り」を感じていた。 これらの「怒り」とどう向き合っていくか。それが試される世の中であることを吉田修一は示したかったようにも感じた。 - 2025年9月12日
 新しい文章力の教室唐木元読み終わった唐木元著「新しい文章力の教室」読了。 2025/9 7冊目 ◎書評 文章を書くって学校ではあまり習わない。 読書感想文なども書かされるが何がいい文章で何が悪い文章なのか分からない。 この本は学生のうちに読んでおくべき本だと思う。 正直、文章をある程度書けていてそこからのレベルアップを図りたい人には物足りないかもしれない。 でも基礎から復習ができるし、あーこれ自分もクセでやっちゃってるなという感じで、自分の悪いクセを再認識するきっかけにもなる。 定期的に読み返すことで自分の文章を磨くことができる良書であることには変わりない。
新しい文章力の教室唐木元読み終わった唐木元著「新しい文章力の教室」読了。 2025/9 7冊目 ◎書評 文章を書くって学校ではあまり習わない。 読書感想文なども書かされるが何がいい文章で何が悪い文章なのか分からない。 この本は学生のうちに読んでおくべき本だと思う。 正直、文章をある程度書けていてそこからのレベルアップを図りたい人には物足りないかもしれない。 でも基礎から復習ができるし、あーこれ自分もクセでやっちゃってるなという感じで、自分の悪いクセを再認識するきっかけにもなる。 定期的に読み返すことで自分の文章を磨くことができる良書であることには変わりない。 - 2025年9月11日
 読み終わった千葉雅也著「勉強の哲学 来たるべきバカのために」読了。 2025/9 6冊目 ◎サマリ ①勉強するとは既存のノリから外れること ②ボケとツッコミ ③決断ではなく仮固定 ◎書評 千葉先生の名著。 中身は難しいが分かりやすい例えにいい具合で脱線してくれて飽きずに最後まで読むことができた。 動物化するポストモダンの著者、東先生を尊敬している千葉先生ならでは東先生譲りと思われる鋭い視点と哲学初心者にも手を差し伸べてくれる優しさが共存したとても素敵な一冊。 ①勉強するとは既存のノリから外れること この本は勉強の哲学といいつつ、勉強はいいぞ〜とかもっと勉強しろとかの説教は一切ない。 千葉先生は勉強をする=既存のノリから外れることであり自己破壊的な行為であるとした。 あと既存のノリから外れはじめると周囲からキモく見られる。 この感覚の言語化とてもすごいと感じた。 物知りというか教養がある人って何か違う世界線を生きている気がしていた。 それは自分とはノリがまったく違うからだと改めて気づかされた。 この本では勉強を進めるとしたらこういうのがいいよというひとつの解も示されている。 まずは自分の欲望年表を作って自分自身を知り、自分に必要な勉強を見出すというのもとても面白かった。 実際に自分もやってみたが自分自身をうまく言語化できた気がして、この本の価値って何十万円にも値するのではないかと感じた。 ②ボケとツッコミ 勉強をする=ノリから外れるために必要なことはボケとツッコミだと千葉先生は主張する。 ボケ=ユーモア、ツッコミ=アイロニーだ。 ボケは横展開、ツッコミは縦展開。 ボケはこういうのもいいけどこういう考え方もあるよねと当初の論を否定せずどんどん違った切り口を考えていくこと。 ツッコミはひとつの主張を疑い、これは実際こうなのでは、こうなっているのはなんで、とどんどん縦穴を掘っていく。 ボケにもツッコミにも弱点はあるので適度さが大切ではあるものの、この2人をベースに物事を見ていくというのはとても学びになった。 ③決断ではなく仮固定 ツッコミを重ねていく人のクセとして、あるところまで行ったら、これで間違いないという「決断」を下してしまい他を受け入れなくなってしまう。 千葉先生はこの状態になってはいけないと主張する。 目指すべきは「仮固定」。今の自分の持つ主張して、これ!というのを語れるようになること。 ボケのほうも横展開していくと際限がないのだが、どこかのタイミングで「仮固定」。 「仮固定」に使えるのは自らの享楽的こだわりであるという考え方も面白かった。 この享楽的こだわりも欲望年表を書いてみることで見えてくるはずだ。 本当にいろんな視点を手に入れることができる名著。 千葉先生の他の作品も読んでみたいと思う。
読み終わった千葉雅也著「勉強の哲学 来たるべきバカのために」読了。 2025/9 6冊目 ◎サマリ ①勉強するとは既存のノリから外れること ②ボケとツッコミ ③決断ではなく仮固定 ◎書評 千葉先生の名著。 中身は難しいが分かりやすい例えにいい具合で脱線してくれて飽きずに最後まで読むことができた。 動物化するポストモダンの著者、東先生を尊敬している千葉先生ならでは東先生譲りと思われる鋭い視点と哲学初心者にも手を差し伸べてくれる優しさが共存したとても素敵な一冊。 ①勉強するとは既存のノリから外れること この本は勉強の哲学といいつつ、勉強はいいぞ〜とかもっと勉強しろとかの説教は一切ない。 千葉先生は勉強をする=既存のノリから外れることであり自己破壊的な行為であるとした。 あと既存のノリから外れはじめると周囲からキモく見られる。 この感覚の言語化とてもすごいと感じた。 物知りというか教養がある人って何か違う世界線を生きている気がしていた。 それは自分とはノリがまったく違うからだと改めて気づかされた。 この本では勉強を進めるとしたらこういうのがいいよというひとつの解も示されている。 まずは自分の欲望年表を作って自分自身を知り、自分に必要な勉強を見出すというのもとても面白かった。 実際に自分もやってみたが自分自身をうまく言語化できた気がして、この本の価値って何十万円にも値するのではないかと感じた。 ②ボケとツッコミ 勉強をする=ノリから外れるために必要なことはボケとツッコミだと千葉先生は主張する。 ボケ=ユーモア、ツッコミ=アイロニーだ。 ボケは横展開、ツッコミは縦展開。 ボケはこういうのもいいけどこういう考え方もあるよねと当初の論を否定せずどんどん違った切り口を考えていくこと。 ツッコミはひとつの主張を疑い、これは実際こうなのでは、こうなっているのはなんで、とどんどん縦穴を掘っていく。 ボケにもツッコミにも弱点はあるので適度さが大切ではあるものの、この2人をベースに物事を見ていくというのはとても学びになった。 ③決断ではなく仮固定 ツッコミを重ねていく人のクセとして、あるところまで行ったら、これで間違いないという「決断」を下してしまい他を受け入れなくなってしまう。 千葉先生はこの状態になってはいけないと主張する。 目指すべきは「仮固定」。今の自分の持つ主張して、これ!というのを語れるようになること。 ボケのほうも横展開していくと際限がないのだが、どこかのタイミングで「仮固定」。 「仮固定」に使えるのは自らの享楽的こだわりであるという考え方も面白かった。 この享楽的こだわりも欲望年表を書いてみることで見えてくるはずだ。 本当にいろんな視点を手に入れることができる名著。 千葉先生の他の作品も読んでみたいと思う。 - 2025年9月9日
 読み終わった東浩紀著「動物化するポストモダン」読了。 2025/9 5冊目 ◎サマリ ①大きな物語消費→データベース消費へ ②主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 ③現代はデータベース消費が加速化している? ◎書評 三宅香帆さんおすすめの一冊。 ゼロ世代批評の代表的名著と言われている本作は、オタク文化からデータベース消費を考えるという斬新な切り口が人々の興味をそそる。 中身は哲学的な要素もガッツリ入っているので、決して簡単な本ではないものの、データベース消費という概念だけでも摂取できるとモノの見方が大きく変わると思う。 ① 大きな物語消費→データベース消費へ 何を言ってるんだという感じだと思うが、東先生はアニメの見方を具体例にしてこのふたつの消費行動をわかりやすく説明してくれている。 ◎大きな物語消費 ガンダムに代表されるような作品 背後に象徴的な世界である大きな物語が存在して、消費者が見ているのはあくまで大きな物語と同じ世界観を反映した小さな物語という名の作品群 ◎データベース消費 エヴァンゲリオンやエロゲのような作品 背後に大きな物語はなく、データベースのみがある。 消費者はデータベースから様々な組み合わせで抽出された作品を見ているにすぎない。 また、場合によっては自らデータベースにアクセスすることができる。 1990年以降はこのデータベース消費に人々の消費行動が移行しているというのが最大のポイント。 ② 主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 では、この本のタイトルの「動物化」とはなんなのか。 これは欲望を持たず欲求のみとなった状態のことを指している。 オタクたちはオタクたちにウケるであろう組み合わせをデータベースから永遠と提供される。 そこに他者の介在はなく、与えられたものをひたすら貪る人間性の無意味化が起こっている。 この動物化理論は「暇と退屈の倫理学」の著者である國分先生はバカにしていたが、東先生は逆に注目に値するとしているのが興味深かった。 ③現代はデータベース消費が加速化している? この本は25年以上前に出版された本だが、さらにデータベース消費は加速化しているのではないかと思う。 ソニーがプロデュースしている「夜系アーティスト」も典型ではないだろうか。 売れるであろう要素、「アーティストの匿名性」、「アングラ感」、「物語性の強い歌詞」などをデータベースから引っ張り出して提供。 YOASOBIに関しては、匿名的だったものを少しずつ小出しにしていく=データベースをわざと消費者に見せている? これをマーケティングと呼ぶのだと思うが、現代の消費者はあまりにマーケティングという名の悪魔に人間性を売りすぎているように思う。 このデータベース消費という切り口で様々な物事を見ていくのもとても面白いと感じている。
読み終わった東浩紀著「動物化するポストモダン」読了。 2025/9 5冊目 ◎サマリ ①大きな物語消費→データベース消費へ ②主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 ③現代はデータベース消費が加速化している? ◎書評 三宅香帆さんおすすめの一冊。 ゼロ世代批評の代表的名著と言われている本作は、オタク文化からデータベース消費を考えるという斬新な切り口が人々の興味をそそる。 中身は哲学的な要素もガッツリ入っているので、決して簡単な本ではないものの、データベース消費という概念だけでも摂取できるとモノの見方が大きく変わると思う。 ① 大きな物語消費→データベース消費へ 何を言ってるんだという感じだと思うが、東先生はアニメの見方を具体例にしてこのふたつの消費行動をわかりやすく説明してくれている。 ◎大きな物語消費 ガンダムに代表されるような作品 背後に象徴的な世界である大きな物語が存在して、消費者が見ているのはあくまで大きな物語と同じ世界観を反映した小さな物語という名の作品群 ◎データベース消費 エヴァンゲリオンやエロゲのような作品 背後に大きな物語はなく、データベースのみがある。 消費者はデータベースから様々な組み合わせで抽出された作品を見ているにすぎない。 また、場合によっては自らデータベースにアクセスすることができる。 1990年以降はこのデータベース消費に人々の消費行動が移行しているというのが最大のポイント。 ② 主体的な構造が消え、他者なしに満たされる動物的行動 では、この本のタイトルの「動物化」とはなんなのか。 これは欲望を持たず欲求のみとなった状態のことを指している。 オタクたちはオタクたちにウケるであろう組み合わせをデータベースから永遠と提供される。 そこに他者の介在はなく、与えられたものをひたすら貪る人間性の無意味化が起こっている。 この動物化理論は「暇と退屈の倫理学」の著者である國分先生はバカにしていたが、東先生は逆に注目に値するとしているのが興味深かった。 ③現代はデータベース消費が加速化している? この本は25年以上前に出版された本だが、さらにデータベース消費は加速化しているのではないかと思う。 ソニーがプロデュースしている「夜系アーティスト」も典型ではないだろうか。 売れるであろう要素、「アーティストの匿名性」、「アングラ感」、「物語性の強い歌詞」などをデータベースから引っ張り出して提供。 YOASOBIに関しては、匿名的だったものを少しずつ小出しにしていく=データベースをわざと消費者に見せている? これをマーケティングと呼ぶのだと思うが、現代の消費者はあまりにマーケティングという名の悪魔に人間性を売りすぎているように思う。 このデータベース消費という切り口で様々な物事を見ていくのもとても面白いと感じている。 - 2025年9月8日
- 2025年9月7日
 結婚式のメンバーカーソン・マッカラーズ,村上春樹読みたい
結婚式のメンバーカーソン・マッカラーズ,村上春樹読みたい - 2025年9月6日
 TVピープル (文春文庫)村上春樹読み終わった村上春樹著「TVピープル」読了。 2025/9 4冊目 ◎サマリ ①30歳だから分かる処女性の喪失 我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史 ②眠らないことが自らを覚醒させる? 眠り ◎書評 10代、20代頃、なんとなく面白いと感じていた村上春樹作品が、30歳の今、自分ごとになって自らを襲ってくる。 TVピープルも素晴らしい短編集だった。 特に自分が好きだった「我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史」と「眠り」について触れたい。 ①30歳だから分かる処女性の喪失 我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史 60年代に学生時代を過ごした2人の男がイタリアのレストランで過去を懐かしむ。 処女性を尊び、婚姻前に身体を許さない彼女を持った男が最後に彼女と果たした不思議な誓約。 「すべてが終わったあとで、王様も家来たちもみんな腹を抱えておお笑いしました」 彼女と誓約を果たした後、男の脳裏に童話の変な終わり方がこびりつく。 それを聞いていた男は「おお笑いなんかできなかった」 不思議な物語ではあるものの、誰にでも起こる可能性のある、正確には60年代に起こる可能性があった物語に惹き込まれる。 実際、これは実話なのではないかとも思う。 なんとなく輝かしい過去を思い出させるノスタルジックな感覚とどす黒い一生心の奥底に閉まっておきたい感覚が共存する作品だった。 30歳の今読んだからこそこの感覚が持てたのだと思う。 ②眠らないことが自らを覚醒させる 眠り 17日間眠れなくなった主婦が主人公の物語。 当たり前の日常の繰り返しとなっていたことに違和感を感じ、そして急に眠れなくなる。 眠れなくなることで自らの可能性が拡大していることを感じると同時に、死への感覚、これまで気づかなかった(気づく必要のなかった)様々な感覚を掴んでしまう。 眠れない=不幸せではないものの、人間として何かが崩れていく様子が軽快な文章で記される。 眠ることは当然に必要なことであるという常識を飛び越えて、村上春樹が描き出す狂気がたまらなく面白かった。 眠らないことで何か得られるのかもしれないが、そんな状況で得た何かは決して気分のいいものではないだろう。
TVピープル (文春文庫)村上春樹読み終わった村上春樹著「TVピープル」読了。 2025/9 4冊目 ◎サマリ ①30歳だから分かる処女性の喪失 我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史 ②眠らないことが自らを覚醒させる? 眠り ◎書評 10代、20代頃、なんとなく面白いと感じていた村上春樹作品が、30歳の今、自分ごとになって自らを襲ってくる。 TVピープルも素晴らしい短編集だった。 特に自分が好きだった「我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史」と「眠り」について触れたい。 ①30歳だから分かる処女性の喪失 我らの時代のフォークロア―高度資本主義前史 60年代に学生時代を過ごした2人の男がイタリアのレストランで過去を懐かしむ。 処女性を尊び、婚姻前に身体を許さない彼女を持った男が最後に彼女と果たした不思議な誓約。 「すべてが終わったあとで、王様も家来たちもみんな腹を抱えておお笑いしました」 彼女と誓約を果たした後、男の脳裏に童話の変な終わり方がこびりつく。 それを聞いていた男は「おお笑いなんかできなかった」 不思議な物語ではあるものの、誰にでも起こる可能性のある、正確には60年代に起こる可能性があった物語に惹き込まれる。 実際、これは実話なのではないかとも思う。 なんとなく輝かしい過去を思い出させるノスタルジックな感覚とどす黒い一生心の奥底に閉まっておきたい感覚が共存する作品だった。 30歳の今読んだからこそこの感覚が持てたのだと思う。 ②眠らないことが自らを覚醒させる 眠り 17日間眠れなくなった主婦が主人公の物語。 当たり前の日常の繰り返しとなっていたことに違和感を感じ、そして急に眠れなくなる。 眠れなくなることで自らの可能性が拡大していることを感じると同時に、死への感覚、これまで気づかなかった(気づく必要のなかった)様々な感覚を掴んでしまう。 眠れない=不幸せではないものの、人間として何かが崩れていく様子が軽快な文章で記される。 眠ることは当然に必要なことであるという常識を飛び越えて、村上春樹が描き出す狂気がたまらなく面白かった。 眠らないことで何か得られるのかもしれないが、そんな状況で得た何かは決して気分のいいものではないだろう。 - 2025年9月5日
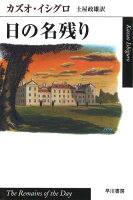 日の名残りカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わったカズオ・イシグロ著「日の名残り」読了。 2025/9 3冊目 ◎サマリ ①古き良きイギリスの衰退 ②執事の品格とは ③変わることが正しいのか ◎書評 大英帝国の国力、文化の衰退を克明に描いた名作。 小説ではあるものの、学びの多い作品だった。 ① 古き良きイギリスの衰退 主人公は名門貴族、ダーリントン卿に仕えた執事、スティーブンソン。 ダーリントン卿は3年前に亡くなり、新たに屋敷の主人となったアメリカ人に仕えている。 そんな新たな主人からスティーブンソンは休暇をもらい、フォードに乗ってイギリスの田園地帯を走り旅に出る。 物語は大部分が過去の回想だ。 第一次世界大戦後から第二次世界大戦前夜にダーリントン・ホールで何が行われていたかがスティーブンソンの回想のもと描かれる。 しかし、古き良きイギリスの衰退はアメリカ人主人との日常のやり取りで色濃く描かれている。 スティーブンソンは新たな主人が飛ばすジョークについていけない。 過去のイギリスではこんなことはなかったのに…と苦虫を噛み潰すような思いをするわけだ。 イギリスの一級貴族の邸宅がアメリカ人に購入されていることで経済的なイギリスの敗北を描き、文化としても潮流はアメリカンカルチャーが中心となり、イギリス文化は古くは臭いものになっている。 執事としてのプライドもズタボロにされていくスティーブンソンは、過去の時代に取り残されている老兵ともいうべきだろう。 カズオ・イシグロはこのイギリス経済、文化の衰退を執事視点で暗に、時には鮮明に描き切っている。 ②執事の品格とは スティーブンソンが過去の回想をする際のひとつのポイントになっているのが執事の品格だ。 スティーブンソンは多くの執事仲間と執事とはどうあるべきかを論議し、その時代の立派な執事へと成長した。 その一方で、父の最期にも立ち会えない、女中頭の恋心にも気づけないような空虚化した存在になってしまったことへの後悔の念も描かれる。 極めつけは主人であるダーリントン卿が第二次世界大戦前に行なっていたことは、決して正しいことではないと薄々気づいていたものの、主人を信じるということを言い訳にダーリントン卿への進言を行うことは避け続けた。 結果、戦後ダーリントン卿は世間からの大バッシングを受け、失意のまま亡くなる。 正しい執事の在り方、執事の品格とは何か。 このテーマを追いかけることこそこの小説を楽しむひとつの鍵になると考えられる。 ③変わることが正しいのか ダーリントン卿が冒した罪とは、親ナチス派になってしまったことだった。 ダーリントン卿自身、古き良きイギリスが大切にしているものなど今の時代には合わないものだと自覚している。 しかし彼が求めてしまったものはヒトラーやムッソリーニといった過激な指導者だった。 確かに大きく世の中は変わるがこれが本当に正しいのか。そういった視点が抜けていたのだろう。 ここから変わることが正しいのか、改めて考えさせられた。 ビジネスの場でも変革、変革とばかり言うが、それは過去を全否定すべきものではない。 そういった大局観のようなものもカズオ・イシグロは読者に伝えたかったのではないだろうかと感じた。
日の名残りカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わったカズオ・イシグロ著「日の名残り」読了。 2025/9 3冊目 ◎サマリ ①古き良きイギリスの衰退 ②執事の品格とは ③変わることが正しいのか ◎書評 大英帝国の国力、文化の衰退を克明に描いた名作。 小説ではあるものの、学びの多い作品だった。 ① 古き良きイギリスの衰退 主人公は名門貴族、ダーリントン卿に仕えた執事、スティーブンソン。 ダーリントン卿は3年前に亡くなり、新たに屋敷の主人となったアメリカ人に仕えている。 そんな新たな主人からスティーブンソンは休暇をもらい、フォードに乗ってイギリスの田園地帯を走り旅に出る。 物語は大部分が過去の回想だ。 第一次世界大戦後から第二次世界大戦前夜にダーリントン・ホールで何が行われていたかがスティーブンソンの回想のもと描かれる。 しかし、古き良きイギリスの衰退はアメリカ人主人との日常のやり取りで色濃く描かれている。 スティーブンソンは新たな主人が飛ばすジョークについていけない。 過去のイギリスではこんなことはなかったのに…と苦虫を噛み潰すような思いをするわけだ。 イギリスの一級貴族の邸宅がアメリカ人に購入されていることで経済的なイギリスの敗北を描き、文化としても潮流はアメリカンカルチャーが中心となり、イギリス文化は古くは臭いものになっている。 執事としてのプライドもズタボロにされていくスティーブンソンは、過去の時代に取り残されている老兵ともいうべきだろう。 カズオ・イシグロはこのイギリス経済、文化の衰退を執事視点で暗に、時には鮮明に描き切っている。 ②執事の品格とは スティーブンソンが過去の回想をする際のひとつのポイントになっているのが執事の品格だ。 スティーブンソンは多くの執事仲間と執事とはどうあるべきかを論議し、その時代の立派な執事へと成長した。 その一方で、父の最期にも立ち会えない、女中頭の恋心にも気づけないような空虚化した存在になってしまったことへの後悔の念も描かれる。 極めつけは主人であるダーリントン卿が第二次世界大戦前に行なっていたことは、決して正しいことではないと薄々気づいていたものの、主人を信じるということを言い訳にダーリントン卿への進言を行うことは避け続けた。 結果、戦後ダーリントン卿は世間からの大バッシングを受け、失意のまま亡くなる。 正しい執事の在り方、執事の品格とは何か。 このテーマを追いかけることこそこの小説を楽しむひとつの鍵になると考えられる。 ③変わることが正しいのか ダーリントン卿が冒した罪とは、親ナチス派になってしまったことだった。 ダーリントン卿自身、古き良きイギリスが大切にしているものなど今の時代には合わないものだと自覚している。 しかし彼が求めてしまったものはヒトラーやムッソリーニといった過激な指導者だった。 確かに大きく世の中は変わるがこれが本当に正しいのか。そういった視点が抜けていたのだろう。 ここから変わることが正しいのか、改めて考えさせられた。 ビジネスの場でも変革、変革とばかり言うが、それは過去を全否定すべきものではない。 そういった大局観のようなものもカズオ・イシグロは読者に伝えたかったのではないだろうかと感じた。 - 2025年9月2日
 暇と退屈の倫理学國分功一郎読み終わった國分功一郎著「暇と退屈の倫理学」読了。 2025/9 2冊目 ◎サマリ ①退屈のはじまりは定住生活?ウサギ狩りをしている者にウサギを渡したらどうか? ②我々は消費はできるが浪費はできない ③ハイデガーの論ずる「パーティーでの退屈さ」をベースに生きる ◎書評 一言で言えばもっと早く読むべきだったと感じた一冊。 遅くとも20代のうちに読み、退屈に対しての人間の考え方を学ぶべきだったと感じた。 退屈を知ることで楽しく生きることの難しさとその重要性を知ることができる名著。 ① 退屈のはじまりは定住生活?ウサギ狩りをしている者にウサギを渡したらどうか? この本には國分先生の多くの示唆が込められているが、中でも退屈の始まりを定住生活とする序盤の主張は印象的だった。 移住生活をいたときは必要なものを必要なだけ採取し、しばらく時間が経ったら移動をする。 一方、定住生活は農業生産をベースに加速度的な文明の発展を果たすのに適したスタイルであった。しかし、人々は「退屈」という原罪を背負うこととなる。 そして、パスカルが語るウサギ狩りの例え。 ウサギ狩りをしている者にウサギを差し出しても誰も喜ばない。ウサギを狩る行為をしているにも関わらずだ。 つまり、目的物なんてどうでもよくウサギ狩りのようなものは単なる暇つぶし→興奮を得るための行為として行っているのだとパスカルは主張する。 序盤のこの論理展開が美しすぎて國分先生の筆力に魅了された。 ② 我々は消費はできるが浪費はできない これも新たな気づきだった。 我々がやっていることは浪費ではなく消費だという。 浪費はひたすらモノを買っていくだけなので際限があるが、消費はモノの背景にある観念も一緒に買うので際限がなくなる。 資本主義経済ではこの観念の消費を供給側が意図的に実施している。 暇だから何かを買いたいわけでもないのにウィンドウショッピングに出かけてしまい、しまいには何かを消費する。 これは仕掛けられた罠なのだ。 ③ ハイデガーの論ずる「パーティーでの退屈さ」をベースに生きる 最終的に國分先生は「何かに際して退屈すること」、ハイデガーの言うパーティーでの退屈さと向き合うことこそ一番健康的な退屈への対処法だと語る。 ハイデガーの言うパーティーとは、パーティーそのものが気晴らしのものとなっており、そのパーティーに参加したとして楽しい思いをしても、なんとなく退屈を感じてしまうというものだ。 この状態は何らかの奴隷の状態ではなく、一番自律できていて余裕のある状態であるという。 この状態をうまく保ち、「楽しさ」を見出していくこと。 暇や退屈を感じつつも、その中で楽しむための訓練を行い贅沢を取り戻す努力をすること。 これこそが良く生きるということではないかと國分先生は語りたかったのだと思う。 色んな解釈でOK、どういったプロセスで何を考えたのかに注目してほしいと國分先生も結論で語っている。 自分もこんな大学の先生に哲学を習ってみたかった。
暇と退屈の倫理学國分功一郎読み終わった國分功一郎著「暇と退屈の倫理学」読了。 2025/9 2冊目 ◎サマリ ①退屈のはじまりは定住生活?ウサギ狩りをしている者にウサギを渡したらどうか? ②我々は消費はできるが浪費はできない ③ハイデガーの論ずる「パーティーでの退屈さ」をベースに生きる ◎書評 一言で言えばもっと早く読むべきだったと感じた一冊。 遅くとも20代のうちに読み、退屈に対しての人間の考え方を学ぶべきだったと感じた。 退屈を知ることで楽しく生きることの難しさとその重要性を知ることができる名著。 ① 退屈のはじまりは定住生活?ウサギ狩りをしている者にウサギを渡したらどうか? この本には國分先生の多くの示唆が込められているが、中でも退屈の始まりを定住生活とする序盤の主張は印象的だった。 移住生活をいたときは必要なものを必要なだけ採取し、しばらく時間が経ったら移動をする。 一方、定住生活は農業生産をベースに加速度的な文明の発展を果たすのに適したスタイルであった。しかし、人々は「退屈」という原罪を背負うこととなる。 そして、パスカルが語るウサギ狩りの例え。 ウサギ狩りをしている者にウサギを差し出しても誰も喜ばない。ウサギを狩る行為をしているにも関わらずだ。 つまり、目的物なんてどうでもよくウサギ狩りのようなものは単なる暇つぶし→興奮を得るための行為として行っているのだとパスカルは主張する。 序盤のこの論理展開が美しすぎて國分先生の筆力に魅了された。 ② 我々は消費はできるが浪費はできない これも新たな気づきだった。 我々がやっていることは浪費ではなく消費だという。 浪費はひたすらモノを買っていくだけなので際限があるが、消費はモノの背景にある観念も一緒に買うので際限がなくなる。 資本主義経済ではこの観念の消費を供給側が意図的に実施している。 暇だから何かを買いたいわけでもないのにウィンドウショッピングに出かけてしまい、しまいには何かを消費する。 これは仕掛けられた罠なのだ。 ③ ハイデガーの論ずる「パーティーでの退屈さ」をベースに生きる 最終的に國分先生は「何かに際して退屈すること」、ハイデガーの言うパーティーでの退屈さと向き合うことこそ一番健康的な退屈への対処法だと語る。 ハイデガーの言うパーティーとは、パーティーそのものが気晴らしのものとなっており、そのパーティーに参加したとして楽しい思いをしても、なんとなく退屈を感じてしまうというものだ。 この状態は何らかの奴隷の状態ではなく、一番自律できていて余裕のある状態であるという。 この状態をうまく保ち、「楽しさ」を見出していくこと。 暇や退屈を感じつつも、その中で楽しむための訓練を行い贅沢を取り戻す努力をすること。 これこそが良く生きるということではないかと國分先生は語りたかったのだと思う。 色んな解釈でOK、どういったプロセスで何を考えたのかに注目してほしいと國分先生も結論で語っている。 自分もこんな大学の先生に哲学を習ってみたかった。 - 2025年9月1日
 帝国ホテル建築物語植松三十里読み終わった植松三十里著「帝国ホテル建築物語」読了。 2025/9 1冊目 ◎サマリ ・フランク・ロイド・ライトに魅了された男たち ・ライト館という巨人の存在 ・つながれるバトン ◎書評 国内資本のホテルの中でも帝国ホテルは特別だ。 圧倒的な荘厳さと日本の象徴としての誇りを持つホテル。 中でも2代目、帝国ホテル(ライト館)は帝国ホテルの優美さを象徴するような建築だ。 そのライト館に関わる人々の苦悩を描き切ったこの作品は日本人として読んでおくべき素晴らしい作品だった。 ①フランク・ロイド・ライトに魅了された男たち この物語は帝国ホテル支配人の林愛作とライトの右腕となってライト館建築に関わる遠藤新を中心に進む。 ライトは施主の嫁を略奪したり、気の狂った弟子がライトの作業場を放火したりと事件が続いたことで、世間からは冷飯を食わされていた。 しかし、ライトの日本文化へのリスペクトの心や圧倒的な芸術センスに愛作も新も魅了されていく。 どんな難題でもライトのためであれば骨を折り、ライト館の竣工に向けて邁進する姿から彼らの圧倒的な情熱を感じずにはいられない。 愛作に至っては、ライトが求めるレンガを作るため、愛知県の常滑まで何度も出向き気難しい職人と対話を重ねる。 支配人という立場でこのような動き方を続けていた愛作のライト、そして帝国ホテルライト館に対する思いは並々ならぬものがあったのだと感じる。 ②ライト館という巨人の存在 美しさに魅せられた男たちがライト感という名の呪われた巨人に呑まれていく姿を映し出したのもこの作品のすごいところだと思う。 愛作、新、そしてライトに至るまでライト館に関わったが故に犠牲するものがあまりにも多すぎた。 最後はどうにか竣工するのだが、開業日に関東大震災が襲ってくる。 ライト館という恐ろしくも美しい巨人に寄り添わなければこんなことにはならなかったかもしれないということが立て続けに起こる。 美しさと恐ろしさは表裏一体であると改めて感じさせられる。 ③つながれるバトン 現在、ライト館の玄関部分は愛知県の明治村に保存されている。 恐ろしくも美しすぎるライト館はまだ生きているのだ。 これも時の総理、佐藤栄作がバトンを受け継ぎ、最後は明治村に移築するに至った。 佐藤は政治的配慮のもと保存を指示したわけだが、それでもライト館に魅了された人々が裏で手を引いていたからこそ時の総理が動くまでとなる。 フランク・ロイド・ライトという建築家のすごさと帝国ホテルに込められた男たちの熱い想いを感じられる素晴らしい一冊だった。 近々明治村にも足を運んでみたい。
帝国ホテル建築物語植松三十里読み終わった植松三十里著「帝国ホテル建築物語」読了。 2025/9 1冊目 ◎サマリ ・フランク・ロイド・ライトに魅了された男たち ・ライト館という巨人の存在 ・つながれるバトン ◎書評 国内資本のホテルの中でも帝国ホテルは特別だ。 圧倒的な荘厳さと日本の象徴としての誇りを持つホテル。 中でも2代目、帝国ホテル(ライト館)は帝国ホテルの優美さを象徴するような建築だ。 そのライト館に関わる人々の苦悩を描き切ったこの作品は日本人として読んでおくべき素晴らしい作品だった。 ①フランク・ロイド・ライトに魅了された男たち この物語は帝国ホテル支配人の林愛作とライトの右腕となってライト館建築に関わる遠藤新を中心に進む。 ライトは施主の嫁を略奪したり、気の狂った弟子がライトの作業場を放火したりと事件が続いたことで、世間からは冷飯を食わされていた。 しかし、ライトの日本文化へのリスペクトの心や圧倒的な芸術センスに愛作も新も魅了されていく。 どんな難題でもライトのためであれば骨を折り、ライト館の竣工に向けて邁進する姿から彼らの圧倒的な情熱を感じずにはいられない。 愛作に至っては、ライトが求めるレンガを作るため、愛知県の常滑まで何度も出向き気難しい職人と対話を重ねる。 支配人という立場でこのような動き方を続けていた愛作のライト、そして帝国ホテルライト館に対する思いは並々ならぬものがあったのだと感じる。 ②ライト館という巨人の存在 美しさに魅せられた男たちがライト感という名の呪われた巨人に呑まれていく姿を映し出したのもこの作品のすごいところだと思う。 愛作、新、そしてライトに至るまでライト館に関わったが故に犠牲するものがあまりにも多すぎた。 最後はどうにか竣工するのだが、開業日に関東大震災が襲ってくる。 ライト館という恐ろしくも美しい巨人に寄り添わなければこんなことにはならなかったかもしれないということが立て続けに起こる。 美しさと恐ろしさは表裏一体であると改めて感じさせられる。 ③つながれるバトン 現在、ライト館の玄関部分は愛知県の明治村に保存されている。 恐ろしくも美しすぎるライト館はまだ生きているのだ。 これも時の総理、佐藤栄作がバトンを受け継ぎ、最後は明治村に移築するに至った。 佐藤は政治的配慮のもと保存を指示したわけだが、それでもライト館に魅了された人々が裏で手を引いていたからこそ時の総理が動くまでとなる。 フランク・ロイド・ライトという建築家のすごさと帝国ホテルに込められた男たちの熱い想いを感じられる素晴らしい一冊だった。 近々明治村にも足を運んでみたい。 - 2025年8月22日
読み込み中...


