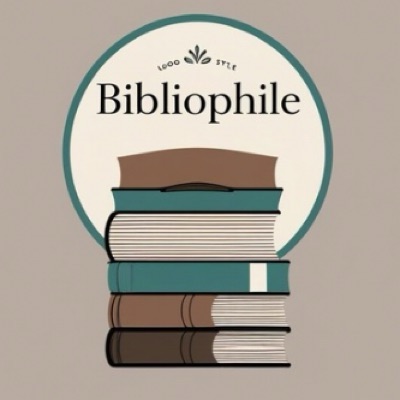極北の海獣

48件の記録
 たこちゃむ@meissa_vela2026年1月9日読み終わった2026年1冊目 訳文を読むのがすごく苦手でいつもより時間かかったし…難しいな、と思っちゃった。 ステラーカイギュウに限らず、絶滅した生き物って、どうしてあんなに人を惹きつけるんだろう。 人の手によって絶滅してしまった生き物の最期もまるで美談のようで(美談として描かれてないけど、そう受け取ってしまった)、なんだかな…と気持ちが晴れないでいる。 もっと時間をあけてからもう一回読み返したら、また違う感想もてるかな。
たこちゃむ@meissa_vela2026年1月9日読み終わった2026年1冊目 訳文を読むのがすごく苦手でいつもより時間かかったし…難しいな、と思っちゃった。 ステラーカイギュウに限らず、絶滅した生き物って、どうしてあんなに人を惹きつけるんだろう。 人の手によって絶滅してしまった生き物の最期もまるで美談のようで(美談として描かれてないけど、そう受け取ってしまった)、なんだかな…と気持ちが晴れないでいる。 もっと時間をあけてからもう一回読み返したら、また違う感想もてるかな。
 りら@AnneLilas2025年9月20日読み終わった@ カフェ文学と歴史と博物学が交錯する、失われたものの幻を垣間見ることのできる不思議な読み心地。かつてキアラン・カーソンの小説を読んだ時を思い出す。 版元のプレスリリースでこの作品の刊行を知って、これはもしかしてとびびびと来たんだけど、まさしく自分にとって最も好ましいタイプの本だった。 読み終わりたくなくてちびちび読んでいたけれど、第三部からはほぼ一気読み。 終盤は鳥とその卵の話題が多かった。 ステラーカイギュウをめぐる人々には学者だけではなく、その家族や名も知れぬ漁師や画家やコレクションの管理者や標本修復師がいて、もちろん女性たちもいた。 絶滅種含め、みな今はこの地球上にはいないけれど、彼らの存在を束の間感じることができるのはやはりこれが文学だからなのだろう。 いつかヘルシンキを再訪して、ステラーカイギュウの骨格標本と対峙してみたい。
りら@AnneLilas2025年9月20日読み終わった@ カフェ文学と歴史と博物学が交錯する、失われたものの幻を垣間見ることのできる不思議な読み心地。かつてキアラン・カーソンの小説を読んだ時を思い出す。 版元のプレスリリースでこの作品の刊行を知って、これはもしかしてとびびびと来たんだけど、まさしく自分にとって最も好ましいタイプの本だった。 読み終わりたくなくてちびちび読んでいたけれど、第三部からはほぼ一気読み。 終盤は鳥とその卵の話題が多かった。 ステラーカイギュウをめぐる人々には学者だけではなく、その家族や名も知れぬ漁師や画家やコレクションの管理者や標本修復師がいて、もちろん女性たちもいた。 絶滅種含め、みな今はこの地球上にはいないけれど、彼らの存在を束の間感じることができるのはやはりこれが文学だからなのだろう。 いつかヘルシンキを再訪して、ステラーカイギュウの骨格標本と対峙してみたい。
 かもめ通信@kamome2025年9月15日読み終わった18世紀の史実に基づいた海洋冒険譚からはじまって現代まで。絶滅した生き物とその生き物を巡るあれこれを語りあげるフィクションは、読み手の心の中に幻の海獣を蘇らせると同時に、人間の愚行の結果をこれでもかと突きつけて、過ちを繰り返す愚かさを告発する。
かもめ通信@kamome2025年9月15日読み終わった18世紀の史実に基づいた海洋冒険譚からはじまって現代まで。絶滅した生き物とその生き物を巡るあれこれを語りあげるフィクションは、読み手の心の中に幻の海獣を蘇らせると同時に、人間の愚行の結果をこれでもかと突きつけて、過ちを繰り返す愚かさを告発する。

 fuyunowaqs@paajiiym2025年8月15日読んだ🌟WITMonth人為絶滅をテーマに、18世紀カムチャツカ半島、19世紀アラスカ、現代のヘルシンキという異なる時と地域を繋ぐ傑作だった。 さまざまな自然災害の記録と適応の歴史を持つ国に長く暮らしていると信じがたいことだが、キリスト教徒が多数を占める欧米の「自然は人間によってコントロール可能なもの」という考え方はフィクションではなく、良い意味でも悪い意味でも日常生活の隅々まで根を張っていると感じる。「我々だけが神に赦されている」という特権意識より不遜な「あらゆるものは自分たちが使うために用意された」という無意識、これらの価値観とそれによって生じる問題が淡々と描かれるので、その度ごとに胸が悪くなる。とくに水産資源に関しては、日本もいまだに政治と経済を優先して一喜一憂しながら、保護と管理という観点を蔑ろにしつづけている。他人事ではない。人の欲は際限なく、いつだって信じたいものを選んで信じてしまう。特定の宗教や状況に限らず、事実を遠ざけて想像の芽を摘む信仰は害悪だ。 本作には華々しい成功も破滅も描かれない。祝福も断罪もない。物語の印象を一言で表すなら「地味」だが、重いテーマを扱いながらも、作者の善意と希望とが感じられる構成になっている。 第三部前半は大学教授の助手として蜘蛛をスケッチする女性画家、後半は兄弟で鳥類保護に取り組む男性を軸に物語が進んでいく。対象をつぶさに観察して紙に描き写す画家は、己の目で見たものをそのまま描く。コレクションされた鳥卵の修繕に携わる標本管理士は、人の手によって壊されたものや歪められたものを元の姿に近づける。直接交わることのない二人の活動に、破壊と略奪の連鎖に抗う光を見出すことができた。100年後に第四部が書かれるとしたら、一体どんな内容になるだろうか。
fuyunowaqs@paajiiym2025年8月15日読んだ🌟WITMonth人為絶滅をテーマに、18世紀カムチャツカ半島、19世紀アラスカ、現代のヘルシンキという異なる時と地域を繋ぐ傑作だった。 さまざまな自然災害の記録と適応の歴史を持つ国に長く暮らしていると信じがたいことだが、キリスト教徒が多数を占める欧米の「自然は人間によってコントロール可能なもの」という考え方はフィクションではなく、良い意味でも悪い意味でも日常生活の隅々まで根を張っていると感じる。「我々だけが神に赦されている」という特権意識より不遜な「あらゆるものは自分たちが使うために用意された」という無意識、これらの価値観とそれによって生じる問題が淡々と描かれるので、その度ごとに胸が悪くなる。とくに水産資源に関しては、日本もいまだに政治と経済を優先して一喜一憂しながら、保護と管理という観点を蔑ろにしつづけている。他人事ではない。人の欲は際限なく、いつだって信じたいものを選んで信じてしまう。特定の宗教や状況に限らず、事実を遠ざけて想像の芽を摘む信仰は害悪だ。 本作には華々しい成功も破滅も描かれない。祝福も断罪もない。物語の印象を一言で表すなら「地味」だが、重いテーマを扱いながらも、作者の善意と希望とが感じられる構成になっている。 第三部前半は大学教授の助手として蜘蛛をスケッチする女性画家、後半は兄弟で鳥類保護に取り組む男性を軸に物語が進んでいく。対象をつぶさに観察して紙に描き写す画家は、己の目で見たものをそのまま描く。コレクションされた鳥卵の修繕に携わる標本管理士は、人の手によって壊されたものや歪められたものを元の姿に近づける。直接交わることのない二人の活動に、破壊と略奪の連鎖に抗う光を見出すことができた。100年後に第四部が書かれるとしたら、一体どんな内容になるだろうか。



 fuyunowaqs@paajiiym2025年8月14日読み始めたWITMonth#WITMonth 2025 として。作者のイーダ・トゥルペイネンはフィンランドの文学研究者で、本作が初の長編小説。 第一部は、科学軽視の海洋冒険小説 with ステラーカイギュウという内容。冒険や航海ではなく漂流かも。淡々と状況が悪化してゆくさまを読むのがなぜか楽しくページをめくる手が止まらない。 装画はミロコマチコさん、装幀は大倉真一郎さん。カバー下はもちろん、帯の下、帯の裏まで楽しめる。ミロコマチコさんの猫や人ではない大きな生きものの絵が見られてうれしい。
fuyunowaqs@paajiiym2025年8月14日読み始めたWITMonth#WITMonth 2025 として。作者のイーダ・トゥルペイネンはフィンランドの文学研究者で、本作が初の長編小説。 第一部は、科学軽視の海洋冒険小説 with ステラーカイギュウという内容。冒険や航海ではなく漂流かも。淡々と状況が悪化してゆくさまを読むのがなぜか楽しくページをめくる手が止まらない。 装画はミロコマチコさん、装幀は大倉真一郎さん。カバー下はもちろん、帯の下、帯の裏まで楽しめる。ミロコマチコさんの猫や人ではない大きな生きものの絵が見られてうれしい。

 つたゐ@tutai_k2025年6月20日読み終わった18世紀ロシア、19世紀アラスカ、現代フィンランド。人類に絶滅させられたステラーカイギュウをめぐり、そのステラーカイギュウがまだ生きていた時代から、絶滅後「ロマン」として求められていた時代、人類が「絶滅」という言葉や現象と、自分たちが生き物を絶滅させているという自覚を持った時代、「私たち」へと辿り着く物語。 シュテラーとかベーリングとかたくさんの実在の人物の名前が出てくるから、伝記なのかな?と思うけれどそうではなくてフィクションで、歴史の中に「あったかもしれない(あっただろう)」人々の高揚や葛藤が描かれているのがとてもおもしろかった。 これは別の本で読んだのだけど、かつてキリスト教圏のひとびとは、動物や環境というのは神が人間のために整えたから「使ってもいい」と思っていたらしい。だから絶滅という現象が起こるとは夢にも思っていなくて…。その頃の時代というのは、ツバメは冬になると海の中で過ごしているとか、現代からみたら荒唐無稽な「科学」の時代ではあったんだが…「絶滅」を知った時だって「とにかく標本を作ること」が「最先端の科学」だったりとかする「過去」から、「私たちの手で今まさに絶滅させてしまった生き物たち」をはっきりとした自責と自覚で見送る現代、その絶滅を食い止めようと努力する人もいる現代にたどり着く。それでもいまなお、食い止めようとするひとの努力よりも、待てずに去る生き物のほうが圧倒的に多く、無自覚に(或いは自覚的に!それがどうなってもいいという慢心で)絶滅への拍車をかける経済/社会/国際(戦争!)活動が行われている。 物語の結末、謝辞にたどり着いたとき「絶滅文学」という悲しいカテゴリの本質を目の当たりにする。 最高におもしろいけれど、おもしろいだけですまされない、骨の上に寝起きする私たちの文明に幾度でも問い直せというメッセージを握りしめて本を閉じた。
つたゐ@tutai_k2025年6月20日読み終わった18世紀ロシア、19世紀アラスカ、現代フィンランド。人類に絶滅させられたステラーカイギュウをめぐり、そのステラーカイギュウがまだ生きていた時代から、絶滅後「ロマン」として求められていた時代、人類が「絶滅」という言葉や現象と、自分たちが生き物を絶滅させているという自覚を持った時代、「私たち」へと辿り着く物語。 シュテラーとかベーリングとかたくさんの実在の人物の名前が出てくるから、伝記なのかな?と思うけれどそうではなくてフィクションで、歴史の中に「あったかもしれない(あっただろう)」人々の高揚や葛藤が描かれているのがとてもおもしろかった。 これは別の本で読んだのだけど、かつてキリスト教圏のひとびとは、動物や環境というのは神が人間のために整えたから「使ってもいい」と思っていたらしい。だから絶滅という現象が起こるとは夢にも思っていなくて…。その頃の時代というのは、ツバメは冬になると海の中で過ごしているとか、現代からみたら荒唐無稽な「科学」の時代ではあったんだが…「絶滅」を知った時だって「とにかく標本を作ること」が「最先端の科学」だったりとかする「過去」から、「私たちの手で今まさに絶滅させてしまった生き物たち」をはっきりとした自責と自覚で見送る現代、その絶滅を食い止めようと努力する人もいる現代にたどり着く。それでもいまなお、食い止めようとするひとの努力よりも、待てずに去る生き物のほうが圧倒的に多く、無自覚に(或いは自覚的に!それがどうなってもいいという慢心で)絶滅への拍車をかける経済/社会/国際(戦争!)活動が行われている。 物語の結末、謝辞にたどり着いたとき「絶滅文学」という悲しいカテゴリの本質を目の当たりにする。 最高におもしろいけれど、おもしろいだけですまされない、骨の上に寝起きする私たちの文明に幾度でも問い直せというメッセージを握りしめて本を閉じた。
 つたゐ@tutai_k2025年6月16日読み始めたちょっと開いた読み始めたー!おもしろい! 今日は昼から浜を歩いてたんだけど、二ヶ月くらい前から観察していた打ち上げられたイルカの死骸がついに骨だけになった
つたゐ@tutai_k2025年6月16日読み始めたちょっと開いた読み始めたー!おもしろい! 今日は昼から浜を歩いてたんだけど、二ヶ月くらい前から観察していた打ち上げられたイルカの死骸がついに骨だけになった





 りら@AnneLilas2025年6月8日ちょっと開いた図書館本序文と訳者あとがきのみ走り読み。 ノンフィクションかと思っていたら、小説だった。故に表はあるけれど、写真などは一切なし。 でもすごく面白そう。 今までステラーカイギュウのことなんて全然知らなかったからこそ、ドードー以上にこの謎めいた絶滅種への興味が惹かれる。 先日買ったばかりの『ウナギが故郷に帰るとき』にもステラーカイギュウへの言及があった。
りら@AnneLilas2025年6月8日ちょっと開いた図書館本序文と訳者あとがきのみ走り読み。 ノンフィクションかと思っていたら、小説だった。故に表はあるけれど、写真などは一切なし。 でもすごく面白そう。 今までステラーカイギュウのことなんて全然知らなかったからこそ、ドードー以上にこの謎めいた絶滅種への興味が惹かれる。 先日買ったばかりの『ウナギが故郷に帰るとき』にもステラーカイギュウへの言及があった。