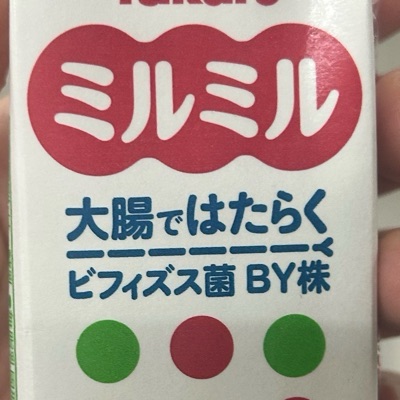ラディカル・マスキュリズム

28件の記録
- MS@MS11192026年1月20日読み終わった理解したけど納得いかなかったところ、そもそも理解も難しいところもあったが、男性学をさまざまな視点から学べる一冊。 半分フェミニズムを取り入れてもう半分は自分の考えでやっていく、の半フェミニズムはぜひ男性として生きている人に身につけてほしいと感じた。
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月27日読み終わった@ カフェ第6章読む。 〈本章ではミサンドリーをミソジニーの副産物に限定させず、それ自体で「ある」ものだと仮定する。そうすることで、女性との関係論に依拠せずとも、男性が抱える自己嫌悪としてのミサンドリーが露わになる。〉(196頁) 〈男性を「つまらない存在」にする根幹〉(237頁)としてミサンドリーを考えていくアプローチに、前章同様ハッとさせらる。 次のくだりなんかは、小沼理『共感と距離感の練習』ともリンクしそうな議論でドキドキした。 〈しかし、ほかの解釈もできる。ゲイ男性はそうではない男性にとって、「男性と向き合い、男性を愛する」という、ミサンドリーを克服した存在として把握されているのではないか。〉(203頁) 「男性と性」、「異性愛(ヘテロセクシュアル)」を考えるうえで「Aro/Ace(アロ/エース)」を参照するパートも面白かった。 「弱者男性論」の中身を検証する節についた次の脚注も大事だな、と。 〈「弱者男性論」が話題になることで、得をするのは「強者男性」である。自分とは縁のない「弱者男性」と女性やフェミニストが対立しているかのような枠組みが設けられることで、男性がトータルで優位に立っている事実は覆い隠され、「強者男性」が追及されずに済むからだ。だからこそ「強者男性」にとって、男性の権力や加害性が批判されたとき、「弱者男性論」は使い捨ての駒として差し出すにはちょうどいい。〉(213頁) 「インセル」の脚注でふれられる、その語の〈元の趣旨〉(221頁)にもへぇ〜となった。完全に見えなくなってしまっているけど、別の可能性、方向性がありえた言葉だったのだな...。 最終的にミサンドリーに対抗する処方箋として①〜④が提出されるが、「②家父長制を内側から蝕む男性の声として、ミサンドリーを再定位する」が特に面白かった。そして結局、それだけでは限界があり、どれも満遍なく実践していくことが大事、というのは至極まっとうな結論だと思った。 「おわりに」で執筆背景と共に語られる、なぜ「批判的男性研究(CSM)」ではなくあえて「マスキュリズム」を冠したか、という狙いの部分も、読み終えるにあたってはかなり切実に響くものがある。 全体的に尻上がりな構成だった。 書き忘れていたこと:第3章の脚注26で堀川修平『「日本に性教育はなかった」と言う前に』を参照いただいており、嬉しかった。ありがとうございます。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月27日読み終わった@ カフェ第6章読む。 〈本章ではミサンドリーをミソジニーの副産物に限定させず、それ自体で「ある」ものだと仮定する。そうすることで、女性との関係論に依拠せずとも、男性が抱える自己嫌悪としてのミサンドリーが露わになる。〉(196頁) 〈男性を「つまらない存在」にする根幹〉(237頁)としてミサンドリーを考えていくアプローチに、前章同様ハッとさせらる。 次のくだりなんかは、小沼理『共感と距離感の練習』ともリンクしそうな議論でドキドキした。 〈しかし、ほかの解釈もできる。ゲイ男性はそうではない男性にとって、「男性と向き合い、男性を愛する」という、ミサンドリーを克服した存在として把握されているのではないか。〉(203頁) 「男性と性」、「異性愛(ヘテロセクシュアル)」を考えるうえで「Aro/Ace(アロ/エース)」を参照するパートも面白かった。 「弱者男性論」の中身を検証する節についた次の脚注も大事だな、と。 〈「弱者男性論」が話題になることで、得をするのは「強者男性」である。自分とは縁のない「弱者男性」と女性やフェミニストが対立しているかのような枠組みが設けられることで、男性がトータルで優位に立っている事実は覆い隠され、「強者男性」が追及されずに済むからだ。だからこそ「強者男性」にとって、男性の権力や加害性が批判されたとき、「弱者男性論」は使い捨ての駒として差し出すにはちょうどいい。〉(213頁) 「インセル」の脚注でふれられる、その語の〈元の趣旨〉(221頁)にもへぇ〜となった。完全に見えなくなってしまっているけど、別の可能性、方向性がありえた言葉だったのだな...。 最終的にミサンドリーに対抗する処方箋として①〜④が提出されるが、「②家父長制を内側から蝕む男性の声として、ミサンドリーを再定位する」が特に面白かった。そして結局、それだけでは限界があり、どれも満遍なく実践していくことが大事、というのは至極まっとうな結論だと思った。 「おわりに」で執筆背景と共に語られる、なぜ「批判的男性研究(CSM)」ではなくあえて「マスキュリズム」を冠したか、という狙いの部分も、読み終えるにあたってはかなり切実に響くものがある。 全体的に尻上がりな構成だった。 書き忘れていたこと:第3章の脚注26で堀川修平『「日本に性教育はなかった」と言う前に』を参照いただいており、嬉しかった。ありがとうございます。

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月26日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第4章読み終わる。 〈これまで日本の男性学では、メンズリブ系の男性運動が正当性をもって語られる一方で、他の運動がどのような展開を迎えているか十分に描かれてこなかった。そのため第4章では、無視するか否定的な評価を下したくなる運動についても、「男性運動」の範疇で捉えてその内実を追うことを目的とした。〉(163頁) 確かに目から鱗のアプローチだった。「男性運動」を幅広く捉えることで新たに見えてくるものがあるな、と。〈男性が「男性であること」を引き受けながら(性)差別に抗うとしたら、「親フェミニズム」というより「反セクシズム(反・家父長制)」や「半フェミニズム」の姿勢で関わるのが望ましい〉(165頁)という提案も、そうだよなと思う。 第5章も読む。 主題はヘゲモニーだけど、「共犯的な男性性」のくだりは痛いところを突かれたと感じるし、そう感じる男性は多いのでは。 〈男性を優位とするジェンダー秩序が少し揺れたとみるや、セラピー(癒し)を必要とし、現存する性差別には無関心でいられる。そのような男性の有り様は、直接的なヘゲモニックな男性性ではないにしても、それを支える共犯的な男性性なのである。〉(180頁) 〈ヘゲモニックな男性性はその内実が変化するものである。他方で変わらないものがあるとしたら、男性のヘゲモニーのほうである。/だから問題は、男性をヘゲモニーにいさせつづけるジェンダー・システムが不問にされてしまうことなのだ。〉(182頁) ちなみに、ここからさらに「トランス男性」の視点が加わり、「複合特権」という概念や「ヘゲモニーなき男性」という構想が提出される。著者ならではの考察が展開されていて、ここだけでも読めてよかったなと思った。 〈さて、問題はここからである。トランス男性が「女性」から「男性」へ社会的カテゴリーを変えていくとき、いったいトランス男性は何を「変えて」いるのか。〉(183頁) 〈ジェンダー秩序を問題にするとき、男性はヘゲモニーを有するカテゴリーだと通常想定されている。しかし、そこには大きな見落としがある。いったい男性は「いつから」ヘゲモニーを有するのか、という問いが不問になっているのだ。〉(186頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月26日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第4章読み終わる。 〈これまで日本の男性学では、メンズリブ系の男性運動が正当性をもって語られる一方で、他の運動がどのような展開を迎えているか十分に描かれてこなかった。そのため第4章では、無視するか否定的な評価を下したくなる運動についても、「男性運動」の範疇で捉えてその内実を追うことを目的とした。〉(163頁) 確かに目から鱗のアプローチだった。「男性運動」を幅広く捉えることで新たに見えてくるものがあるな、と。〈男性が「男性であること」を引き受けながら(性)差別に抗うとしたら、「親フェミニズム」というより「反セクシズム(反・家父長制)」や「半フェミニズム」の姿勢で関わるのが望ましい〉(165頁)という提案も、そうだよなと思う。 第5章も読む。 主題はヘゲモニーだけど、「共犯的な男性性」のくだりは痛いところを突かれたと感じるし、そう感じる男性は多いのでは。 〈男性を優位とするジェンダー秩序が少し揺れたとみるや、セラピー(癒し)を必要とし、現存する性差別には無関心でいられる。そのような男性の有り様は、直接的なヘゲモニックな男性性ではないにしても、それを支える共犯的な男性性なのである。〉(180頁) 〈ヘゲモニックな男性性はその内実が変化するものである。他方で変わらないものがあるとしたら、男性のヘゲモニーのほうである。/だから問題は、男性をヘゲモニーにいさせつづけるジェンダー・システムが不問にされてしまうことなのだ。〉(182頁) ちなみに、ここからさらに「トランス男性」の視点が加わり、「複合特権」という概念や「ヘゲモニーなき男性」という構想が提出される。著者ならではの考察が展開されていて、ここだけでも読めてよかったなと思った。 〈さて、問題はここからである。トランス男性が「女性」から「男性」へ社会的カテゴリーを変えていくとき、いったいトランス男性は何を「変えて」いるのか。〉(183頁) 〈ジェンダー秩序を問題にするとき、男性はヘゲモニーを有するカテゴリーだと通常想定されている。しかし、そこには大きな見落としがある。いったい男性は「いつから」ヘゲモニーを有するのか、という問いが不問になっているのだ。〉(186頁)

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月24日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第3章読む。 「メンズリズ」は衰退したのか。衰退したとしたらその原因とは何か。著者が個人的にメンズリブに感じる課題とは。 そして、その後学問領域として発展していく「男性学」とは何か。アメリカの社会学者マイケル・メスナーが提起した、男性運動の布置を捉える枠組みとしての三つの視点とは(男性の制度的特権/男らしさのコスト/男性内の差異と不平等、著者はどの視点に可能性を感じているか)。 読み応えも痛いところを突かれている感覚も増してきた。面白くなってきた。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月24日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第3章読む。 「メンズリズ」は衰退したのか。衰退したとしたらその原因とは何か。著者が個人的にメンズリブに感じる課題とは。 そして、その後学問領域として発展していく「男性学」とは何か。アメリカの社会学者マイケル・メスナーが提起した、男性運動の布置を捉える枠組みとしての三つの視点とは(男性の制度的特権/男らしさのコスト/男性内の差異と不平等、著者はどの視点に可能性を感じているか)。 読み応えも痛いところを突かれている感覚も増してきた。面白くなってきた。

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月23日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第2章読む。 トランプ就任初日に出された大統領令のうちの一つ(「ジェンダーイデオロギーの過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的真実を取り戻す」)を取り上げ、性別とは一貫しており、しかも不変であるとする二つの発想が退けられる。「男性の身体」という型が実際どのように運用されているのか。押さえておいたほうがよい内容。 次章からは「男性運動」の話になるので楽しみ。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月23日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第2章読む。 トランプ就任初日に出された大統領令のうちの一つ(「ジェンダーイデオロギーの過激主義から女性を守り、連邦政府に生物学的真実を取り戻す」)を取り上げ、性別とは一貫しており、しかも不変であるとする二つの発想が退けられる。「男性の身体」という型が実際どのように運用されているのか。押さえておいたほうがよい内容。 次章からは「男性運動」の話になるので楽しみ。

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月22日読み始めた就寝前読書お風呂読書@ 自宅第1章を読む。助走的な内容。 〈男とは何か。その話にふみこもうとしても、他の話題によくすり替わってしまう。「男」の話を期待していたのに、いつの間にか「男らしさ」の話ばかりになっているのだ。いったい「男」はどこへいってしまったのか。〉(13頁) 良い始まり方。そしてやはり概念の整理がお上手。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月22日読み始めた就寝前読書お風呂読書@ 自宅第1章を読む。助走的な内容。 〈男とは何か。その話にふみこもうとしても、他の話題によくすり替わってしまう。「男」の話を期待していたのに、いつの間にか「男らしさ」の話ばかりになっているのだ。いったい「男」はどこへいってしまったのか。〉(13頁) 良い始まり方。そしてやはり概念の整理がお上手。