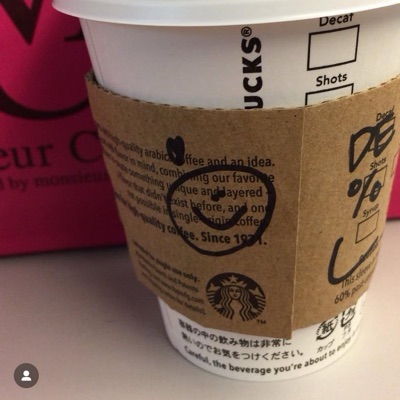ルール?本

21件の記録
 うみ@kaich12202026年1月29日読み終わった納得したり大事にしたい価値観をおぼえておきたい ルールは社会を豊かにするもの ルールは見直して更新していくもの ルールがないこともルール ルールメーカーとテイカーは協力すべし トランプのアレをちゃんと読んでみようと思うなど。
うみ@kaich12202026年1月29日読み終わった納得したり大事にしたい価値観をおぼえておきたい ルールは社会を豊かにするもの ルールは見直して更新していくもの ルールがないこともルール ルールメーカーとテイカーは協力すべし トランプのアレをちゃんと読んでみようと思うなど。 ふるえ@furu_furu2025年7月23日読み終わったルールを守る(使う)ことに対する主体性という話が最後の対談の部分で触れられていて面白かった。明文化することで失われる余白と、増えていくコスト。ルールをつくることはそれを守ってもらうための認識を生み出すこと、それを監視する人(対応する人かシステム)を設定しないといけなかったり、必要なコストがある。管理するということは、ルールが十全に機能している間は効率がいいのかもしれないが、そこを目指すためにはかなりのコストをかける必要があるのかもしれない。
ふるえ@furu_furu2025年7月23日読み終わったルールを守る(使う)ことに対する主体性という話が最後の対談の部分で触れられていて面白かった。明文化することで失われる余白と、増えていくコスト。ルールをつくることはそれを守ってもらうための認識を生み出すこと、それを監視する人(対応する人かシステム)を設定しないといけなかったり、必要なコストがある。管理するということは、ルールが十全に機能している間は効率がいいのかもしれないが、そこを目指すためにはかなりのコストをかける必要があるのかもしれない。
 ふるえ@furu_furu2025年7月21日読んでる育ってきた中で思考に染み付いているルールが衝突というか、照らし合わされるという意味では家庭の中でのルールが1番創造的でありたいなと思う。 「ルール?展」が開催されていた時の葛藤や対応、そこで信じたかったことなどが丁寧に書かれていてとてもよかった。
ふるえ@furu_furu2025年7月21日読んでる育ってきた中で思考に染み付いているルールが衝突というか、照らし合わされるという意味では家庭の中でのルールが1番創造的でありたいなと思う。 「ルール?展」が開催されていた時の葛藤や対応、そこで信じたかったことなどが丁寧に書かれていてとてもよかった。




 ふるえ@furu_furu2025年7月20日読んでる法律とかルールにはわざと解釈を緩めているというか、余白を生み出しているような書き方で定められているものがある。時代や社会情勢によってアップデートされていく社会の形や、価値観に対応するためのものなのだろうけれど、それを運用する側にとっては扱い方が難しい。ルールを運用する人たちと、ルールが適用される(使う)人たちとの関係性が一方的なものではなく、対話の中で適応していくことができれば理想なのかもしれないが、それも他の人たちとの公平性という理由でなかなか前に進まなかったりする。どうすればルールは変化し、適応していけるのか。
ふるえ@furu_furu2025年7月20日読んでる法律とかルールにはわざと解釈を緩めているというか、余白を生み出しているような書き方で定められているものがある。時代や社会情勢によってアップデートされていく社会の形や、価値観に対応するためのものなのだろうけれど、それを運用する側にとっては扱い方が難しい。ルールを運用する人たちと、ルールが適用される(使う)人たちとの関係性が一方的なものではなく、対話の中で適応していくことができれば理想なのかもしれないが、それも他の人たちとの公平性という理由でなかなか前に進まなかったりする。どうすればルールは変化し、適応していけるのか。




 ふるえ@furu_furu2025年7月13日読んでる電車で読み進める。ルールが創造性を生み出す、とはどこか矛盾しているような感覚になるけれど、制約があることで線引きされ、内と外を認識することから新しいものが生み出されていくのかも知れない。 「ルールをつくることは、物事の枠や外縁を生み出したり、線を引く行為でもあります。一方で、ルールがその枠や線を可視化することで、逆に枠や線をはみ出すことができます。ルールがあったり、明確化されていることにより、どこから先に行けば新しいのかがわかるようになり、新しさが可視化される面があるのです。そして、線や枠をつくると、そこから一歩はみ出たくなる人が出てくるものです。(中略)これは人間に備わった好奇心やフロンティア精神によるものなのかはわかりませんが、ルールにはこのような制約や設定された線や枠を一歩越えようという人間の創造性や新たな問いを生み出す面があると言えます。」菅俊一/田中みゆき/水野祐『ルール?本』(フィルムアート社)p.80
ふるえ@furu_furu2025年7月13日読んでる電車で読み進める。ルールが創造性を生み出す、とはどこか矛盾しているような感覚になるけれど、制約があることで線引きされ、内と外を認識することから新しいものが生み出されていくのかも知れない。 「ルールをつくることは、物事の枠や外縁を生み出したり、線を引く行為でもあります。一方で、ルールがその枠や線を可視化することで、逆に枠や線をはみ出すことができます。ルールがあったり、明確化されていることにより、どこから先に行けば新しいのかがわかるようになり、新しさが可視化される面があるのです。そして、線や枠をつくると、そこから一歩はみ出たくなる人が出てくるものです。(中略)これは人間に備わった好奇心やフロンティア精神によるものなのかはわかりませんが、ルールにはこのような制約や設定された線や枠を一歩越えようという人間の創造性や新たな問いを生み出す面があると言えます。」菅俊一/田中みゆき/水野祐『ルール?本』(フィルムアート社)p.80


 ふるえ@furu_furu2025年7月12日読んでる借りてきた当たり前に思っていた標識も、法律とかのルールに基づいているし、看板もタダというわけではないから広告とかで費用を捻出とかあるんだろうなと読みながら、今まで知らなかったルールを見せるための背景が見えてきてたのしい。
ふるえ@furu_furu2025年7月12日読んでる借りてきた当たり前に思っていた標識も、法律とかのルールに基づいているし、看板もタダというわけではないから広告とかで費用を捻出とかあるんだろうなと読みながら、今まで知らなかったルールを見せるための背景が見えてきてたのしい。



- かよ@kayo_nazo2025年3月24日読み終わったかつてとあるコミュニティ内の暗黙のルール(マナー)が肌に合わなくて色々あったので、ルールを見直す・更新するという視点の内容が読んでてとても面白かったです