無教養
@mukyoyo
- 2026年1月17日
- 2026年1月12日
 BOXBOXBOXBOX坂本湾読み終わった不気味な環境の中で単純作業を続け、みんながみんなおかしくなりそうな中で酒や盗み、物へあたることで気晴らしをしている。 そんな将来どうなるか分からない労働の中で、悲痛なだけでなく希望も感じることができる作品でした。 ループのようであるけれど、不安のなかで希望を見いだしたり、かと思ったらまた新たな問題を見つけたり、それをまた解決したり、労働とはその繰り返しで進んでいくのかもと思いました。
BOXBOXBOXBOX坂本湾読み終わった不気味な環境の中で単純作業を続け、みんながみんなおかしくなりそうな中で酒や盗み、物へあたることで気晴らしをしている。 そんな将来どうなるか分からない労働の中で、悲痛なだけでなく希望も感じることができる作品でした。 ループのようであるけれど、不安のなかで希望を見いだしたり、かと思ったらまた新たな問題を見つけたり、それをまた解決したり、労働とはその繰り返しで進んでいくのかもと思いました。 - 2026年1月12日
- 2026年1月4日
 言語化するための小説思考小川哲読み終わった帰省の電車の中で一気読みしました。 小説を書いたり、読んだりするための本ですが、以下のように他の仕事でも通じるところがあるなあと思いました。 ・抽象化と個別化、何が普遍的で何がそうではないか ・読みやすさとは、視点人物と読者との情報の量の差 ・冒頭の重要性 ・語り手が聞き手に正しく情報を伝える ・一人の人間のアイディアが面白いはずがない ・作者が何を表現したか、ではなく読者が何を受け取ったか、で価値が決まる 細かくは書きませんが、異なる業界のお客様にどう提案するか、提案内容の情報整理、良いプロダクトを作るためのアイディア、どんな価値を提案するか、などを考える時に指針にできそうです。 一方、以下の内容は自分の職業では使いどきがないと思いました(自分がまだこれを実施すべき状況になったことがないだけかもしれませんが笑) ・書いてしまったことをいかに伏線にするか また、短編小説も収録されており、言語化するための小説思考を題材とした内容となっており面白いです。
言語化するための小説思考小川哲読み終わった帰省の電車の中で一気読みしました。 小説を書いたり、読んだりするための本ですが、以下のように他の仕事でも通じるところがあるなあと思いました。 ・抽象化と個別化、何が普遍的で何がそうではないか ・読みやすさとは、視点人物と読者との情報の量の差 ・冒頭の重要性 ・語り手が聞き手に正しく情報を伝える ・一人の人間のアイディアが面白いはずがない ・作者が何を表現したか、ではなく読者が何を受け取ったか、で価値が決まる 細かくは書きませんが、異なる業界のお客様にどう提案するか、提案内容の情報整理、良いプロダクトを作るためのアイディア、どんな価値を提案するか、などを考える時に指針にできそうです。 一方、以下の内容は自分の職業では使いどきがないと思いました(自分がまだこれを実施すべき状況になったことがないだけかもしれませんが笑) ・書いてしまったことをいかに伏線にするか また、短編小説も収録されており、言語化するための小説思考を題材とした内容となっており面白いです。 - 2026年1月4日
 過疎ビジネス横山勲読み終わった「町長たちが自分たちだけ給料を上げている」というタレコミをもらった新聞記者が、問題を追求すべく議事録を調査していると、別の問題が見つかって、、、 と言う流れなのですが、違和感を見逃さず、疑問を解消すべく行動していく様はまさに記者魂を感じました。
過疎ビジネス横山勲読み終わった「町長たちが自分たちだけ給料を上げている」というタレコミをもらった新聞記者が、問題を追求すべく議事録を調査していると、別の問題が見つかって、、、 と言う流れなのですが、違和感を見逃さず、疑問を解消すべく行動していく様はまさに記者魂を感じました。 - 2026年1月4日
- 2026年1月4日
 読み終わった最近、読書をあまりしない知人におすすめの本を聞かれることが増えており、聞いてくれる方々の興味にあった本を紹介できるように、読んでない本も概要を把握するために読みました。 そんな目的で読んでいましたが、紹介が面白く、自分が読みたい本もいっぱい増えました笑。 特に児童書や絵本は普段目にする機会がななく、特に「杉本くんを殺すには」は読んで見たくなりました。 普段本を読まない人がこの本を読む際は、各章末のコラム「読めない人のQ&A」から読むことをオススメします。読書の悩みに対するアドバイスを聞けるという実用的な面だけでなく、横道さんの文章が面白くて引き込まれるので本題の本紹介もすっと入ってくると思います!
読み終わった最近、読書をあまりしない知人におすすめの本を聞かれることが増えており、聞いてくれる方々の興味にあった本を紹介できるように、読んでない本も概要を把握するために読みました。 そんな目的で読んでいましたが、紹介が面白く、自分が読みたい本もいっぱい増えました笑。 特に児童書や絵本は普段目にする機会がななく、特に「杉本くんを殺すには」は読んで見たくなりました。 普段本を読まない人がこの本を読む際は、各章末のコラム「読めない人のQ&A」から読むことをオススメします。読書の悩みに対するアドバイスを聞けるという実用的な面だけでなく、横道さんの文章が面白くて引き込まれるので本題の本紹介もすっと入ってくると思います! - 2025年12月31日
 哲学史入門1(1)伊藤博明,千葉雅也,山内志朗,斎藤哲也,納富信留読み終わった3年前に熊野さんの西洋哲学史を読んで以来の哲学史に関する読書となりました。 西洋哲学史は良書と評判だったのですが、当方は門外漢なので難解でした。 個別に読みたい哲学者がおり、下地をつけるために再度入門書を読むことにしました。 ライターの斎藤さんと各年代の専門家とのインタビュー形式で書かれており、非常にわかりやすかったです。 一般的な通史(扱う範囲が広大なので概略的)に加えて、無知の知やオッカムの唯名論など、各専門家の方の関心や難所にフォーカスされており、わかりやすいとともに面白く読めました。 続刊も読むのが楽しみです。 他の入門書も読みつつ、西洋哲学史も再読すれば前よりは理解できる気がします。
哲学史入門1(1)伊藤博明,千葉雅也,山内志朗,斎藤哲也,納富信留読み終わった3年前に熊野さんの西洋哲学史を読んで以来の哲学史に関する読書となりました。 西洋哲学史は良書と評判だったのですが、当方は門外漢なので難解でした。 個別に読みたい哲学者がおり、下地をつけるために再度入門書を読むことにしました。 ライターの斎藤さんと各年代の専門家とのインタビュー形式で書かれており、非常にわかりやすかったです。 一般的な通史(扱う範囲が広大なので概略的)に加えて、無知の知やオッカムの唯名論など、各専門家の方の関心や難所にフォーカスされており、わかりやすいとともに面白く読めました。 続刊も読むのが楽しみです。 他の入門書も読みつつ、西洋哲学史も再読すれば前よりは理解できる気がします。 - 2025年11月24日
 なぜ人は自分を責めてしまうのか信田さよ子母と娘、共依存、育児、そして自責感の問題について書かれた本です。 共依存は「他者の世話をすることで本当の自分を見ないようにすること」という生やさしいものではなく、相手を支配すること、ということを理解することができました。 相手に何かをする時、共依存かもしれないという自覚を持ち、一旦立ち止まって考えるようにしたいと思いました。 また、4章の教育に関して、虐待とは程遠い家庭でも、子供に愚痴を聞かせることなどはよく起こっていることだよなと思いながら読みました。あまり関係ないかもですが、夫婦仲が悪く、喧嘩や愚痴の絶えなかった環境で育った人たちは自身の恋愛についても不安を感じている人が自分の周りでは多いです。 子供の前では幸せな姿を見せること、根本的受動性の承認、いけないことはちゃんと注意すること、など多くのことを学ぶことができました。自分も子育てをすることになったら、もう一度この本を読みたいです。 キーワードはページ下に付箋のように書かれていて読み返すときに便利だと思いました。 また、言葉や対処法の説明する際に具体的な話を元に書かれており、分かりやすかったと共に、まさに筆者の辞書はクライアントの語る言葉なのだなと思いました。
なぜ人は自分を責めてしまうのか信田さよ子母と娘、共依存、育児、そして自責感の問題について書かれた本です。 共依存は「他者の世話をすることで本当の自分を見ないようにすること」という生やさしいものではなく、相手を支配すること、ということを理解することができました。 相手に何かをする時、共依存かもしれないという自覚を持ち、一旦立ち止まって考えるようにしたいと思いました。 また、4章の教育に関して、虐待とは程遠い家庭でも、子供に愚痴を聞かせることなどはよく起こっていることだよなと思いながら読みました。あまり関係ないかもですが、夫婦仲が悪く、喧嘩や愚痴の絶えなかった環境で育った人たちは自身の恋愛についても不安を感じている人が自分の周りでは多いです。 子供の前では幸せな姿を見せること、根本的受動性の承認、いけないことはちゃんと注意すること、など多くのことを学ぶことができました。自分も子育てをすることになったら、もう一度この本を読みたいです。 キーワードはページ下に付箋のように書かれていて読み返すときに便利だと思いました。 また、言葉や対処法の説明する際に具体的な話を元に書かれており、分かりやすかったと共に、まさに筆者の辞書はクライアントの語る言葉なのだなと思いました。 - 2025年11月22日
 すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子何も知らずに読んだので、解説を読んだ時にハッとして即座にもう一度読み直しました。 私小説のような、詩のような、不思議なお話でした。 読みながら、自分がこれまでに見て来た白いものと、生と死、特にともに将来を夢見た、まだ若かった友人のそれが思い浮かびました。
すべての、白いものたちのハン・ガン,斎藤真理子何も知らずに読んだので、解説を読んだ時にハッとして即座にもう一度読み直しました。 私小説のような、詩のような、不思議なお話でした。 読みながら、自分がこれまでに見て来た白いものと、生と死、特にともに将来を夢見た、まだ若かった友人のそれが思い浮かびました。 - 2025年10月22日
 選ばない仕事選び浅生鴨気になる
選ばない仕事選び浅生鴨気になる - 2025年10月22日
 論理的思考とは何か渡邉雅子思考法について、論理学、レトリック、科学、哲学の4つの専門技術と、経済、政治、法技術、社会の4つの文化的領域あり、論理的思考は一つではなく、それぞれの領域ごとに異なる思考法が作られてきた。 アメリカでは経済、日本では社会、と言ったようにそれぞれの国では主流となる領域が異なり、主流の文化に合う思考法が一般的に使われている。 文化・思考法ごとに何が論理的かが異なるため、別の思考法で考える他者を非論理と感じてしまうということである。 文化相対主義に陥らず、どの論理が優れているかではなく、目的に応じて論理を使い分ける、という考えは勉強になりました。 特に日本の社会領域の思考はイデオロギーによらずに「間主観」と対話の繰り返しで、状況に合わせて柔軟に社会秩序を形成していく、と言った点で、先行きが不透明な時代に適した思考だと思いました。 SNSでは排他的な主張や、異なる意見のもの同士の対立が起こりやすくなっており、実社会でも分断が顕在化し始めた今だからこそ、読んでおきたい本だと思いました。
論理的思考とは何か渡邉雅子思考法について、論理学、レトリック、科学、哲学の4つの専門技術と、経済、政治、法技術、社会の4つの文化的領域あり、論理的思考は一つではなく、それぞれの領域ごとに異なる思考法が作られてきた。 アメリカでは経済、日本では社会、と言ったようにそれぞれの国では主流となる領域が異なり、主流の文化に合う思考法が一般的に使われている。 文化・思考法ごとに何が論理的かが異なるため、別の思考法で考える他者を非論理と感じてしまうということである。 文化相対主義に陥らず、どの論理が優れているかではなく、目的に応じて論理を使い分ける、という考えは勉強になりました。 特に日本の社会領域の思考はイデオロギーによらずに「間主観」と対話の繰り返しで、状況に合わせて柔軟に社会秩序を形成していく、と言った点で、先行きが不透明な時代に適した思考だと思いました。 SNSでは排他的な主張や、異なる意見のもの同士の対立が起こりやすくなっており、実社会でも分断が顕在化し始めた今だからこそ、読んでおきたい本だと思いました。 - 2025年10月20日
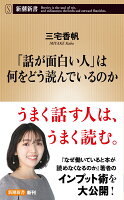 エピソードトークに限界を迎えていた私にとって、今読むべき本でした。 友人と本やドラマ、アニメの感想を話す時、会話が弾む時とそうでない時があってなぜだろうと思っていたのですが、この本を読んで理由がよくわかりました。 思い返してみると、相手が盛り上がってくれる時は、あの5つのパターンに自然と話せていたときだ!、となりました。 意識して話すことや、レパートリーを増やすためには練習あるのみだと思うので、頑張っていきたいです。 最近の悩みとしては、読みたいと思った本をすでに三宅さんが読んでおられることが多いので、まだ発掘されていない面白い本を見つけるスキルも鍛えていきたいなあと、、、(評論家の方相手におこがましいですが、、、)
エピソードトークに限界を迎えていた私にとって、今読むべき本でした。 友人と本やドラマ、アニメの感想を話す時、会話が弾む時とそうでない時があってなぜだろうと思っていたのですが、この本を読んで理由がよくわかりました。 思い返してみると、相手が盛り上がってくれる時は、あの5つのパターンに自然と話せていたときだ!、となりました。 意識して話すことや、レパートリーを増やすためには練習あるのみだと思うので、頑張っていきたいです。 最近の悩みとしては、読みたいと思った本をすでに三宅さんが読んでおられることが多いので、まだ発掘されていない面白い本を見つけるスキルも鍛えていきたいなあと、、、(評論家の方相手におこがましいですが、、、) - 2025年10月20日
 幽霊の脳科学古谷博和幽霊の現象を脳科学で解き明かす本でした。 夏に幽霊が出やすいことや、運転中の幽霊の出現しやすい場所について、病的な症状を元に説明試みており大変おもしろかったです。 また、断言系ではなく、可能性が高い、という書き方も科学に誠実な感じがしてよかったです。 幽霊に出くわさないように、睡眠の質は向上しようと思いました。
幽霊の脳科学古谷博和幽霊の現象を脳科学で解き明かす本でした。 夏に幽霊が出やすいことや、運転中の幽霊の出現しやすい場所について、病的な症状を元に説明試みており大変おもしろかったです。 また、断言系ではなく、可能性が高い、という書き方も科学に誠実な感じがしてよかったです。 幽霊に出くわさないように、睡眠の質は向上しようと思いました。
読み込み中...



