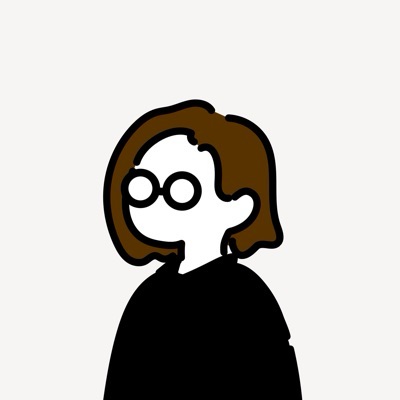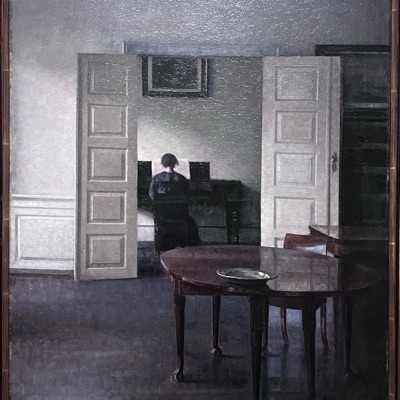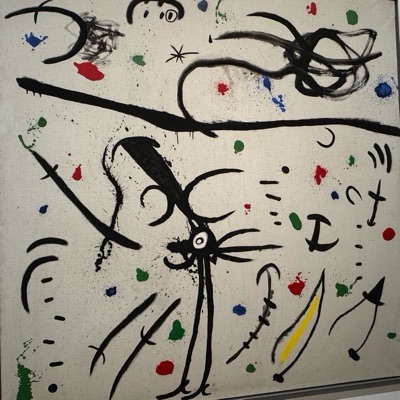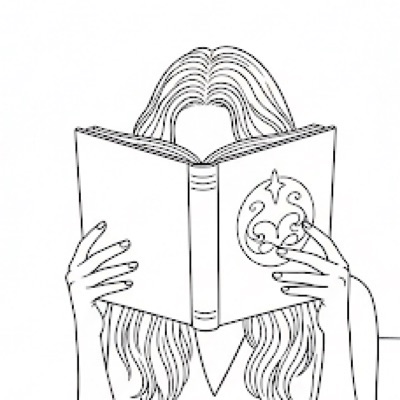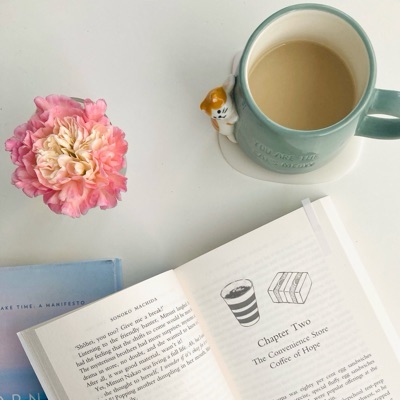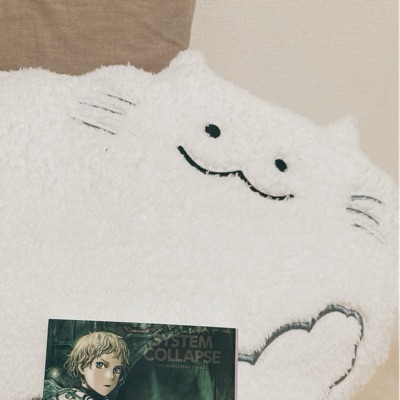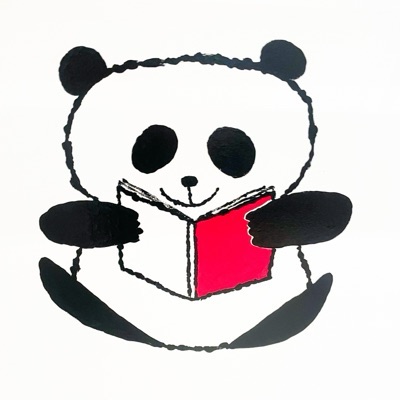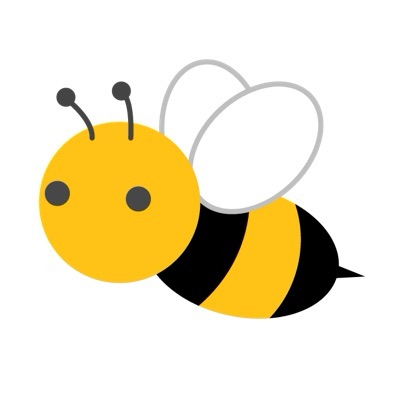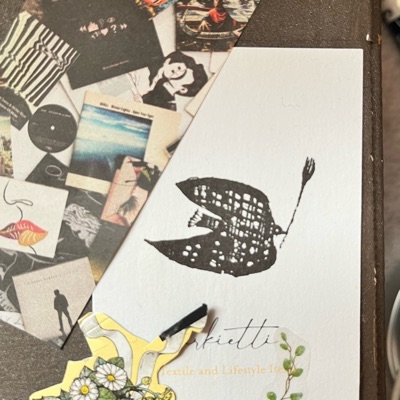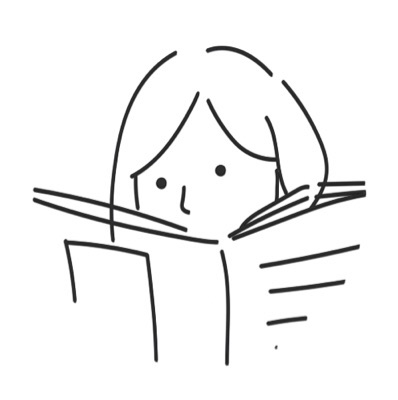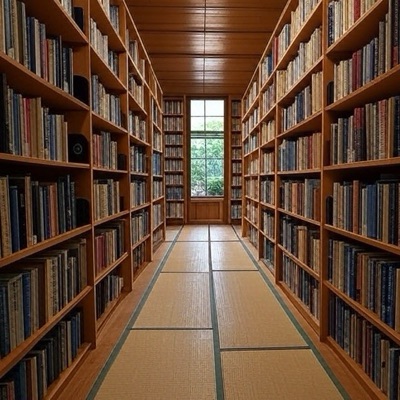なぜ人は自分を責めてしまうのか

430件の記録
 もふもふと読書@sunny3782026年2月17日読み終わった図書館で借りた一度借りて、パラパラと斜め読みして返却してしまったものを再度借りてじっくりと読んだ。 公開講座が元になっているようで、わかりやすい語り口。著者の潔い話し方が好き。 ・私たちは人に迷惑をかけずに生きることはできない。 ・親になったら、少なくとも子供の前では幸せでいる義務がある。 ・とりかえしがつかないことはない。 ・子ども以外の存在から支えられること。そして孤立しないこと。 など、心に留めておきたい言葉が多かった。自責のメカニズムもなるほどと思った。自責から抜け始めているからそう思えるのかなぁ。 それにしても、こういう言動はよくないとして挙げられている事例が、両親からいつもやられていた言動に当てはまりすぎて笑ってしまった。
もふもふと読書@sunny3782026年2月17日読み終わった図書館で借りた一度借りて、パラパラと斜め読みして返却してしまったものを再度借りてじっくりと読んだ。 公開講座が元になっているようで、わかりやすい語り口。著者の潔い話し方が好き。 ・私たちは人に迷惑をかけずに生きることはできない。 ・親になったら、少なくとも子供の前では幸せでいる義務がある。 ・とりかえしがつかないことはない。 ・子ども以外の存在から支えられること。そして孤立しないこと。 など、心に留めておきたい言葉が多かった。自責のメカニズムもなるほどと思った。自責から抜け始めているからそう思えるのかなぁ。 それにしても、こういう言動はよくないとして挙げられている事例が、両親からいつもやられていた言動に当てはまりすぎて笑ってしまった。
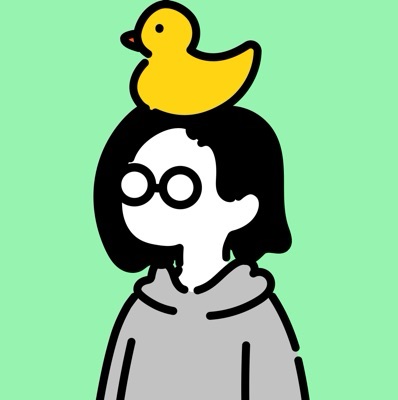 はやしえりか@uma_no_332026年2月12日読み終わったタイトルにビビッときて読む。きっと同じ感情で手に取った人も多いのではないか。 自責感と親子関係がこういうふうに繋がっているのか…と、驚きがたくさんあった。 自分の場合はどうなんだろう?と、ふわふわと記憶を遡ってみて、ああ、こういうことなのかな〜と思うことがあったり。 知ったからといってすぐ好転するものでもないけど、少しずつ変わっていけたらいいなと思う。
はやしえりか@uma_no_332026年2月12日読み終わったタイトルにビビッときて読む。きっと同じ感情で手に取った人も多いのではないか。 自責感と親子関係がこういうふうに繋がっているのか…と、驚きがたくさんあった。 自分の場合はどうなんだろう?と、ふわふわと記憶を遡ってみて、ああ、こういうことなのかな〜と思うことがあったり。 知ったからといってすぐ好転するものでもないけど、少しずつ変わっていけたらいいなと思う。
- saori@sweetbox1042026年2月11日読み終わった“子どもは親にとって一種の解放区” 共依存は支配 “抑圧を受けたら、それをもっと弱いものに移譲していく。これが、日本という国のあり方です。” “親になったら、少なくとも子どもの前では幸せでいる義務がある” “とりかえしがつかないようなことはない” “なんとか自分のやったことを謝って、フォローして、償っていく” 罪悪感は外部に規範がある 自責感は自分で自分の存在を否定する 文脈のない世界を生きるための合理性 「すべて自分が悪い」「自分の責任」 愛着=根源的受動性の承認 子どもには何の責任もない “家族の中に正義を持ち込んではいけない”


 ちはる@chiharium2026年2月2日読み終わった借りてきたp.187-188 ーー虐待的環境を生きるということは、自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得することなんですね。 すごいことです。自分を徹底して否定することで、世の中が説明できる。世の中はそれなりに合理的なんだ、なぜなら自分が悪いから。こういうことです。 (略) 母の不幸や父の不幸、殴られること、ぜんぶ自分が悪いんだと。自分が悪いというのは、イコール自分の責任ということです。これを、自責感と言います。
ちはる@chiharium2026年2月2日読み終わった借りてきたp.187-188 ーー虐待的環境を生きるということは、自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得することなんですね。 すごいことです。自分を徹底して否定することで、世の中が説明できる。世の中はそれなりに合理的なんだ、なぜなら自分が悪いから。こういうことです。 (略) 母の不幸や父の不幸、殴られること、ぜんぶ自分が悪いんだと。自分が悪いというのは、イコール自分の責任ということです。これを、自責感と言います。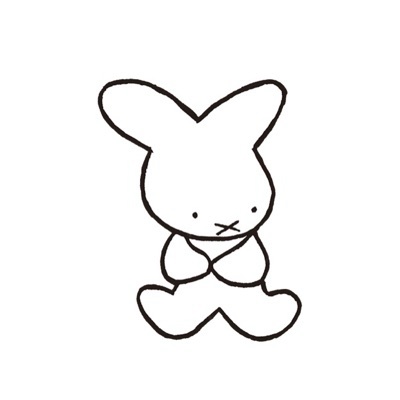


 こんじょー@konjo_note2026年1月20日読み終わった子育てをしていくうえで、常に心に留めておきたい名言に溢れていた。 子供は責任ゼロで生まれてくる、差別は家族によって作られる、親が子どもの前で幸せでいることは義務、などなど。 子育てに悩んだ時は何度も読み直したい。
こんじょー@konjo_note2026年1月20日読み終わった子育てをしていくうえで、常に心に留めておきたい名言に溢れていた。 子供は責任ゼロで生まれてくる、差別は家族によって作られる、親が子どもの前で幸せでいることは義務、などなど。 子育てに悩んだ時は何度も読み直したい。
- roku@mgm_62026年1月3日読み終わった「傷の声」と同時に買って読んだ。 当事者と時間を長く共にしてきたカウンセリング専門家の視点。信田さんの潔く愛のある筆致の文章はいつも読みやすい。 機能していない家庭で、子供は全てを自責にすることで合理性を得る、という話が興味深かった。 一貫性のない親の行動、理不尽な言動を、全て自分が悪いんだにすればその子の中では一定の合理性を得るのだと。 子どもの、生まれてきたことへの健全な受身感。 世の中を生き抜くためのルールを教えるのが躾。 それは生んでやったから、あなたに対してこんなに尽くしているんだから、で行われるべきものではない。

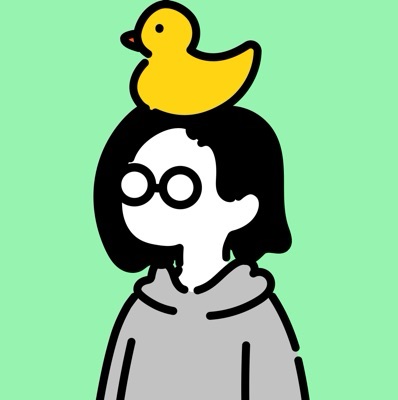
 ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年12月8日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、12月8日(月)open。11‐18時。ご来店お待ちしてます。 信田さよ子『なぜ人は自分を責めてしまうのか』ちくま新書 当事者の言葉を辞書として、私たちを苦しめるものの正体に迫る。 公開講座をもとにした、もっともやさしい信田さよ子の本。 自責感とうまくつきあう。
ブックスエコーロケーション@books-echolocation2025年12月8日新刊入荷@ ブックスエコーロケーションブックスエコーロケーション、12月8日(月)open。11‐18時。ご来店お待ちしてます。 信田さよ子『なぜ人は自分を責めてしまうのか』ちくま新書 当事者の言葉を辞書として、私たちを苦しめるものの正体に迫る。 公開講座をもとにした、もっともやさしい信田さよ子の本。 自責感とうまくつきあう。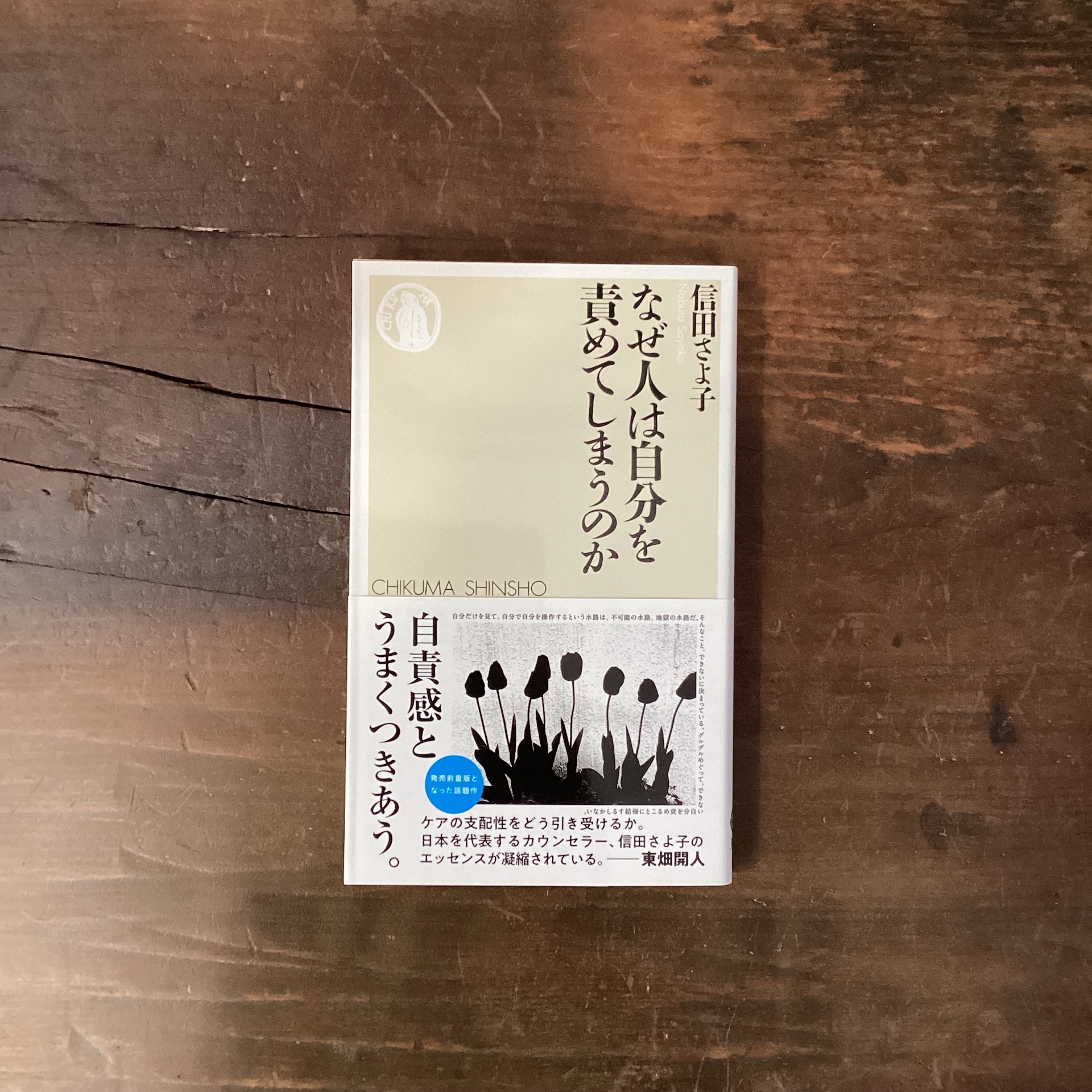
- 無教養@mukyoyo2025年11月24日母と娘、共依存、育児、そして自責感の問題について書かれた本です。 共依存は「他者の世話をすることで本当の自分を見ないようにすること」という生やさしいものではなく、相手を支配すること、ということを理解することができました。 相手に何かをする時、共依存かもしれないという自覚を持ち、一旦立ち止まって考えるようにしたいと思いました。 また、4章の教育に関して、虐待とは程遠い家庭でも、子供に愚痴を聞かせることなどはよく起こっていることだよなと思いながら読みました。あまり関係ないかもですが、夫婦仲が悪く、喧嘩や愚痴の絶えなかった環境で育った人たちは自身の恋愛についても不安を感じている人が自分の周りでは多いです。 子供の前では幸せな姿を見せること、根本的受動性の承認、いけないことはちゃんと注意すること、など多くのことを学ぶことができました。自分も子育てをすることになったら、もう一度この本を読みたいです。 キーワードはページ下に付箋のように書かれていて読み返すときに便利だと思いました。 また、言葉や対処法の説明する際に具体的な話を元に書かれており、分かりやすかったと共に、まさに筆者の辞書はクライアントの語る言葉なのだなと思いました。



 夏@apricity2025年10月31日読み終わった一文読み進める度に泣きすぎて全く読み終わらず、閉じては開いて泣いて、書いて、だったから本当に時間がかかった。月並みな感想だけど、わたしのための本だった。わたしがずっと苦しんでいる症状は、家庭環境や家族の問題に起因してる、って言っていいんだって知れて、ものすごく泣いた。すべて内面化して自責して、そうして正当化することでしか自分の存在を保つことで生きてきてしまった代償を抱えて溢れてしまって久しいから、適切な他責というやり方があるって知らなかった。意味わからないくらいに泣いた。へにゃってしてるページがたくさん。
夏@apricity2025年10月31日読み終わった一文読み進める度に泣きすぎて全く読み終わらず、閉じては開いて泣いて、書いて、だったから本当に時間がかかった。月並みな感想だけど、わたしのための本だった。わたしがずっと苦しんでいる症状は、家庭環境や家族の問題に起因してる、って言っていいんだって知れて、ものすごく泣いた。すべて内面化して自責して、そうして正当化することでしか自分の存在を保つことで生きてきてしまった代償を抱えて溢れてしまって久しいから、適切な他責というやり方があるって知らなかった。意味わからないくらいに泣いた。へにゃってしてるページがたくさん。 竹口洋平@takezin2025年10月10日買った読み終わった友人のために買って読んだ。しかし自分でも意外なことに自分自身のためになる本だった。僕の周りにいる人は皆善良なのだが、それでも知らず知らずに誰かを傷つけているのだ。
竹口洋平@takezin2025年10月10日買った読み終わった友人のために買って読んだ。しかし自分でも意外なことに自分自身のためになる本だった。僕の周りにいる人は皆善良なのだが、それでも知らず知らずに誰かを傷つけているのだ。
 いま@mayonakayom222025年10月5日読み終わった新書の秋、といえるくらいどっさり新書を買い込み併読中。 今まさに子育て真っ只中の身としては、4章が今はとても興味深かった。 それから5章の『つまり「私は一人だ」と思えるのって、ものすごい高級な感覚なんですよ』 から孤独について考えている。
いま@mayonakayom222025年10月5日読み終わった新書の秋、といえるくらいどっさり新書を買い込み併読中。 今まさに子育て真っ只中の身としては、4章が今はとても興味深かった。 それから5章の『つまり「私は一人だ」と思えるのって、ものすごい高級な感覚なんですよ』 から孤独について考えている。


 icue@icue2025年9月23日読み終わったタイトルに興味を惹かれて読んだ。 帯と表紙に「わかりやすい」「やさしい」とあるのだが、個人的には存外に読みづらかった。書かれている内容そのものは平易なもので部分的にはよくわかる。が、タイトルの「なぜ人は自分を責めてしまうのか」という問題意識だけで入ると、いきなり「母娘問題」の概要から始まるのだが、そのふたつがどう繋がっているかが自明ではない読者にとってはちょっとわかりづらかった。この本全体を貫く通奏低音は家族の問題で、とりわけ「母娘問題」であるということを前提とした本だということがタイトルで示されていればよかったのにと思う。信田氏の著書を読んだことがあれば自明なのだろうが、自分は初めて読んだので。どうも、自分にとっては最初の一冊として不適切だったようだ。内容自体は興味深く読んだので、別の本をあたってみようか(たしか積読本の中にあったはず)。
icue@icue2025年9月23日読み終わったタイトルに興味を惹かれて読んだ。 帯と表紙に「わかりやすい」「やさしい」とあるのだが、個人的には存外に読みづらかった。書かれている内容そのものは平易なもので部分的にはよくわかる。が、タイトルの「なぜ人は自分を責めてしまうのか」という問題意識だけで入ると、いきなり「母娘問題」の概要から始まるのだが、そのふたつがどう繋がっているかが自明ではない読者にとってはちょっとわかりづらかった。この本全体を貫く通奏低音は家族の問題で、とりわけ「母娘問題」であるということを前提とした本だということがタイトルで示されていればよかったのにと思う。信田氏の著書を読んだことがあれば自明なのだろうが、自分は初めて読んだので。どうも、自分にとっては最初の一冊として不適切だったようだ。内容自体は興味深く読んだので、別の本をあたってみようか(たしか積読本の中にあったはず)。 r@teihakutou2025年9月17日読み終わったアダルトチルドレンとか共依存とか、これまでに読んだ信田さんの本と重なる内容も多かった。 タイトルになっている問いそのものを扱うのは最終章のみ。その章で、芹沢俊介という人の「根源的受動性」のことを知れたのは収穫だった。 ── p.190-191 この根源的受動性というのは、子どもとともに語られないといけない。芹沢さんによれば、子育てにおいて子どもは、「解決の見通しがない世の中に生まれさせられたんですよ、あなたは」ということを誰かに承認されなきゃいけないんです。 […] こういう世の中だけど、私はあなたを産みました。あなたに責任はありません。産んでしまったことを、私はちゃんと認めてますよ。これを、「根源的受動性の承認」と芹沢さんは言っている。 […] そういうふうに認めてもらうことで、芹沢理論によると「イノセンスの解体」が起きる。「自分には何の責任もない」それが承認されることで、はじめて「自分の人生は自分が主体なんだ」「痛い、お腹がすいたっていう感覚は、私のものなんだ」と、そういう自分を受け止められるようになる。 こう、芹沢さんは言っています。 愛着障害という言葉が流行ってます。この言葉は好きに使っていただければいいけど、愛着とは、本来はこの根源的受動性の承認を意味してるんじゃないかと思います。 ── 講座をまとめた本で、話し言葉なので読みやすかった。こことか、痛快で笑ってしまった。↓ 「すごくひどいこと言ったあとに、「でもね、こんなこと言ってくれるのは親だけだからね。他人はね、思ってても言わないんだよ」って言う。すごく手が込んでますよね。私も芸術的だなと思って聞いたりしてます。こんなに手のこんだ言葉は、アートでしかありません。」(p.152-153)
r@teihakutou2025年9月17日読み終わったアダルトチルドレンとか共依存とか、これまでに読んだ信田さんの本と重なる内容も多かった。 タイトルになっている問いそのものを扱うのは最終章のみ。その章で、芹沢俊介という人の「根源的受動性」のことを知れたのは収穫だった。 ── p.190-191 この根源的受動性というのは、子どもとともに語られないといけない。芹沢さんによれば、子育てにおいて子どもは、「解決の見通しがない世の中に生まれさせられたんですよ、あなたは」ということを誰かに承認されなきゃいけないんです。 […] こういう世の中だけど、私はあなたを産みました。あなたに責任はありません。産んでしまったことを、私はちゃんと認めてますよ。これを、「根源的受動性の承認」と芹沢さんは言っている。 […] そういうふうに認めてもらうことで、芹沢理論によると「イノセンスの解体」が起きる。「自分には何の責任もない」それが承認されることで、はじめて「自分の人生は自分が主体なんだ」「痛い、お腹がすいたっていう感覚は、私のものなんだ」と、そういう自分を受け止められるようになる。 こう、芹沢さんは言っています。 愛着障害という言葉が流行ってます。この言葉は好きに使っていただければいいけど、愛着とは、本来はこの根源的受動性の承認を意味してるんじゃないかと思います。 ── 講座をまとめた本で、話し言葉なので読みやすかった。こことか、痛快で笑ってしまった。↓ 「すごくひどいこと言ったあとに、「でもね、こんなこと言ってくれるのは親だけだからね。他人はね、思ってても言わないんだよ」って言う。すごく手が込んでますよね。私も芸術的だなと思って聞いたりしてます。こんなに手のこんだ言葉は、アートでしかありません。」(p.152-153)



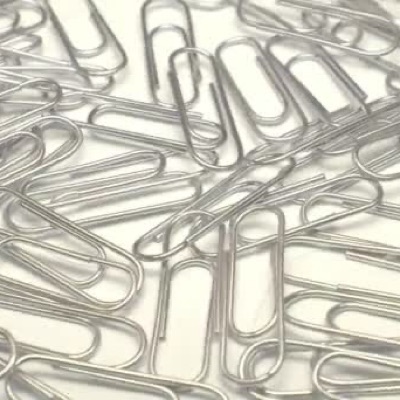



 いっちー@icchii3172025年9月6日読み終わった読了第5章 一定の規範を自分に取り込むのできるが躾。規範は一貫してないといけない。ただ、例外を認める必要もある。 規範を内面化することが、軽い罪悪感になる(勉強の計画を立てたのに、できなかったとか) 虐待家庭は規範が一貫していない。そして文脈化できない(一貫性がない)。そして感情をなかなか抱くことができない →「すべて自分が悪い」という言葉に合理性が宿る ・家族の中に正義を持ち込んではいけない ・信田さんは、机上の言葉ではなく、当事者の言葉につねに向き合ってきた方なんだなと思った。 ・「自己肯定感」という言葉のように、言葉に内包されている問いによって、出口を自ら閉ざしていることがある。これはまだまだ浸透されていない、みんな自己肯定感という言葉の中で苦しんでいる。某Podcastのオールナイト配信のリスナーの質問にも「自己肯定感」という言葉は何度出てきたか知れない。 病んでた高校生の頃、「なぜ自分がこの世からいなくなればいいのか」というのを当時持ってたケータイのメモに書き込んでは少し心が落ち着いていたのを思い出す。いない方が良いという究極の論理が前提にあって、その中でしか問いを立てられなかった。わからん、そこまでの共依存でもなかったかもしれないし厨二病なのかもしれんけど。今はいろんな人に恵まれて精神的にも身体的?生活も休みたい時に休める環境になってだいぶ回復して、ほんとに最近死にたいって思うこともない。ここに至るまで10年くらいかかってるけど、無事に回復できて本当に良かった。生きててこの先の不安とかも全然あるけど、生きてて良かった、楽しいとは思えている。「自己肯定感が低い」とまさに思ってたけど最近はどうでも良くなってた(笑)高いとも思わんけど低いとも思わん、てかどうでもいい、みたいな(笑)その問いの構造からようやく抜け出せたのかもしれない。 ・当事者研究しかり、すでにある水路と別の水路を見つけるために、似た経験をした他者の存在がいかに重要なのか……
いっちー@icchii3172025年9月6日読み終わった読了第5章 一定の規範を自分に取り込むのできるが躾。規範は一貫してないといけない。ただ、例外を認める必要もある。 規範を内面化することが、軽い罪悪感になる(勉強の計画を立てたのに、できなかったとか) 虐待家庭は規範が一貫していない。そして文脈化できない(一貫性がない)。そして感情をなかなか抱くことができない →「すべて自分が悪い」という言葉に合理性が宿る ・家族の中に正義を持ち込んではいけない ・信田さんは、机上の言葉ではなく、当事者の言葉につねに向き合ってきた方なんだなと思った。 ・「自己肯定感」という言葉のように、言葉に内包されている問いによって、出口を自ら閉ざしていることがある。これはまだまだ浸透されていない、みんな自己肯定感という言葉の中で苦しんでいる。某Podcastのオールナイト配信のリスナーの質問にも「自己肯定感」という言葉は何度出てきたか知れない。 病んでた高校生の頃、「なぜ自分がこの世からいなくなればいいのか」というのを当時持ってたケータイのメモに書き込んでは少し心が落ち着いていたのを思い出す。いない方が良いという究極の論理が前提にあって、その中でしか問いを立てられなかった。わからん、そこまでの共依存でもなかったかもしれないし厨二病なのかもしれんけど。今はいろんな人に恵まれて精神的にも身体的?生活も休みたい時に休める環境になってだいぶ回復して、ほんとに最近死にたいって思うこともない。ここに至るまで10年くらいかかってるけど、無事に回復できて本当に良かった。生きててこの先の不安とかも全然あるけど、生きてて良かった、楽しいとは思えている。「自己肯定感が低い」とまさに思ってたけど最近はどうでも良くなってた(笑)高いとも思わんけど低いとも思わん、てかどうでもいい、みたいな(笑)その問いの構造からようやく抜け出せたのかもしれない。 ・当事者研究しかり、すでにある水路と別の水路を見つけるために、似た経験をした他者の存在がいかに重要なのか……
 いっちー@icchii3172025年9月5日読んでるもう少し誤植『後悔しない子育て』と似た内容と思うけど、すごい面白い。 ・「私は反抗期という言葉をあんまり使わない。だってこれは、親が「反抗」してると勝手に決めつけているからです。子供は自己主張してるだけかもしれないでしょう。」p145 →ほんとその通りだと思った。 ・「そんなことするとまわりの迷惑でしょ」も、まわりの人のせいにしてるってことなのか!「静かにしなさい」の単なる理由説明だと思ってたけど、言われてみれば迷惑かどうかは本来は人それぞれなのかな?例えば電車で騒ぐとかは、マナーが決まってるから迷惑行為として認定されるけれど、それ以外で勝手に親が「迷惑になる」って判定してることはあるかもな。 「私たちは人に迷惑をかけずに生きることはできないと思ってるから」そういうことか。確かに。 ・子どもが親に「どうして僕を怒らせるの?」なんて言わない、ということを考えれば、この言葉がいかに巧妙なのかよくわかる。「共依存は親から子へ起こる」p156 ・p157に誤植発見(第四版) なんか、まともな人、まともな学問があってよかった〜と思える。でも、こういう本でどんどん目から鱗が落ちるってことは、私自身も無自覚のうちに世間や常識にとらわれてたってことなんだな…。だから学ばねばならないってことか。でも学んでない領域が山ほどある…。 あと、『母親になって後悔してる』の方について男友達に話したら、個人の自由をこれだけ考えられるのも、日本がまだ人口が多くて平和だからだよねって話になってそれもそうだなと。フェミニズムが浸透して女性が自由を手に入れられることはとても大事だと思う一方で、極論だけど子供を産まない選択をする女性が9割とかになったら国が黙ってないだろうなとか。まあ、それでもやっぱり女性の抑圧などが前提になっている社会は私はおかしいと思うけど。その友達の言ってることも分かったという感じ。見てる視点が違って面白かった。 ・子どもと親は対等ではない、それは事実としてある。(人権という意味では平等)そのため命令も時には必要。 ・子どもの前では幸せでいる義務がある →これに関してはうちの親は楽しそうに生きてたから、ほんとに良かった。 信田さん曰く「演技をしてでもいいから幸せそうにしろ」つまり見抜かれてたとしても、「フリをしてくれることで子どもは救われる」。 ・子どもが許せない気持ちについて。絶対、あるよねぇ、、これについては「やってる自分が偉いと思っていただきたい」p174。
いっちー@icchii3172025年9月5日読んでるもう少し誤植『後悔しない子育て』と似た内容と思うけど、すごい面白い。 ・「私は反抗期という言葉をあんまり使わない。だってこれは、親が「反抗」してると勝手に決めつけているからです。子供は自己主張してるだけかもしれないでしょう。」p145 →ほんとその通りだと思った。 ・「そんなことするとまわりの迷惑でしょ」も、まわりの人のせいにしてるってことなのか!「静かにしなさい」の単なる理由説明だと思ってたけど、言われてみれば迷惑かどうかは本来は人それぞれなのかな?例えば電車で騒ぐとかは、マナーが決まってるから迷惑行為として認定されるけれど、それ以外で勝手に親が「迷惑になる」って判定してることはあるかもな。 「私たちは人に迷惑をかけずに生きることはできないと思ってるから」そういうことか。確かに。 ・子どもが親に「どうして僕を怒らせるの?」なんて言わない、ということを考えれば、この言葉がいかに巧妙なのかよくわかる。「共依存は親から子へ起こる」p156 ・p157に誤植発見(第四版) なんか、まともな人、まともな学問があってよかった〜と思える。でも、こういう本でどんどん目から鱗が落ちるってことは、私自身も無自覚のうちに世間や常識にとらわれてたってことなんだな…。だから学ばねばならないってことか。でも学んでない領域が山ほどある…。 あと、『母親になって後悔してる』の方について男友達に話したら、個人の自由をこれだけ考えられるのも、日本がまだ人口が多くて平和だからだよねって話になってそれもそうだなと。フェミニズムが浸透して女性が自由を手に入れられることはとても大事だと思う一方で、極論だけど子供を産まない選択をする女性が9割とかになったら国が黙ってないだろうなとか。まあ、それでもやっぱり女性の抑圧などが前提になっている社会は私はおかしいと思うけど。その友達の言ってることも分かったという感じ。見てる視点が違って面白かった。 ・子どもと親は対等ではない、それは事実としてある。(人権という意味では平等)そのため命令も時には必要。 ・子どもの前では幸せでいる義務がある →これに関してはうちの親は楽しそうに生きてたから、ほんとに良かった。 信田さん曰く「演技をしてでもいいから幸せそうにしろ」つまり見抜かれてたとしても、「フリをしてくれることで子どもは救われる」。 ・子どもが許せない気持ちについて。絶対、あるよねぇ、、これについては「やってる自分が偉いと思っていただきたい」p174。



 いっちー@icchii3172025年9月5日読んでるフーコー曰く「権力は状況の定義権」、つまり「いまの状況を定義できるのは、僕だけ」の状態。(p97)「家の中は裸ね」と言ったらそうなってしまうような。そうして、世界そのものを作り出されてしまうと、逃げるということが、宇宙船から、宇宙に飛び出すようなものでとても怖いことになる。DVの本質。 愛情と見分けのつかないような形の支配はどこから来るのか? →あらゆる支配の背後にはトラウマ的なものがある。 PTSDの診断基準の「再体験」「解離・麻痺」「過覚醒」のうち「解離・麻痺」が共依存と深いつながりがある。はたから見るとすごい辛い状況下にあるのに、本人は変える気がないような。 日本の女性にとって共依存はありふれていて、共依存的でないことをすると風当たりが強くなるぐらい。 (3章)罪悪感の正体はどこにあるのか? →世間や常識なのではないか。 参考書籍『母性愛という制度』→母性や実子主義が明治以降に構築された。 (この辺の例がえぐい…。) 母性の条件 ・女性は、みんな母親になるものだ ・母親は実の子どもを愛するものである ・子どもは、みんな実のお母さんの愛を必要とくる 母性愛は、「愛」と「自己犠牲」のふたつを柱にきている。(これらを要りませんと言うと人でなしになる笑) エディプスコンプレックスに対して、日本は阿闍世コンプレックスらしい。「お母さんが女だって?そりゃないだろう」らしい笑前者と対照的に後者には父が不在、母子のみの関係。その固定化されたイメージが今も脈々と受け継がれている(DV加害者の男性が妻にお母さんを求めていることもあったり、男性の精神科医が女性に「だって、あなたお母さんでしょ」と言ったり) 子どもを産んだとたんに母性愛を発揮しなければいけない母の恨みが娘に向かう(!) 「こんな理不尽さを生きている私は、あなただけがのうのうと自由に生きることを許さない」(p124)=ミソジニーそのもの。女性自身も内面化している 読んでると、なんというか、構造で無理を押し付けると、必ず歪みが起きるんだなと思った。無償の愛という尊いものの裏側にミソジニーがあるなんて。。。 なぜ自分を責めるのか? →背負わなくてもいい責任(親への責任)をずっと背負ってきた人が抱くもの(p126) 罪悪感は第三者の介入によって救済される! 本来は最良の第三者は父であるべきだけど、日本においては「父の不在」という名の父権主義である(by『母性愛という制度』) →ケアをしてこなかった父親にも責任がある ・反出生主義が流行ってるのを「どれだけ多くの家族が虐待的だったのかと思います」と書いてある。こういうことなのかな? ・『反共感論』という本の話にも繋がる。弱い人がいた時に思わず助けたくなるような共感を「情動的共感」と呼ぶけどそのことがこっちの本にも書かれている。それは「人間の文化であり、権力であり、尊厳である」。(p137)だから、赤ちゃんが泣いてる時になんとかしなきゃと思うのは母性愛というよりも「母親の尊厳」(p138) これは名言だ。母性愛というものは存在しない、と言い切っちゃってもいいんだ。母性愛がなくても、赤ん坊を育てるのは、母である以前に人間の尊厳なんだ。そして、だんだんと手が離れるようになっていくものなのだ。 そう言ってみるとたしかに、共依存の一つが過干渉だったけど、それって人間の文化とか本能的なものではない。やっぱりそのケアはやり過ぎに値するし、そこにはエゴとか、歪みが含まれてれるよなぁ。 『母親になって後悔してる』を読んで結構スッキリした(母親にならねばならないという圧力の説明がついた)けど、この本もだいぶスッキリ。母性愛がなくても、子どもを育てることができるし、「愛という言葉を使わなくても、人は十分に人を大切にすることができる」。
いっちー@icchii3172025年9月5日読んでるフーコー曰く「権力は状況の定義権」、つまり「いまの状況を定義できるのは、僕だけ」の状態。(p97)「家の中は裸ね」と言ったらそうなってしまうような。そうして、世界そのものを作り出されてしまうと、逃げるということが、宇宙船から、宇宙に飛び出すようなものでとても怖いことになる。DVの本質。 愛情と見分けのつかないような形の支配はどこから来るのか? →あらゆる支配の背後にはトラウマ的なものがある。 PTSDの診断基準の「再体験」「解離・麻痺」「過覚醒」のうち「解離・麻痺」が共依存と深いつながりがある。はたから見るとすごい辛い状況下にあるのに、本人は変える気がないような。 日本の女性にとって共依存はありふれていて、共依存的でないことをすると風当たりが強くなるぐらい。 (3章)罪悪感の正体はどこにあるのか? →世間や常識なのではないか。 参考書籍『母性愛という制度』→母性や実子主義が明治以降に構築された。 (この辺の例がえぐい…。) 母性の条件 ・女性は、みんな母親になるものだ ・母親は実の子どもを愛するものである ・子どもは、みんな実のお母さんの愛を必要とくる 母性愛は、「愛」と「自己犠牲」のふたつを柱にきている。(これらを要りませんと言うと人でなしになる笑) エディプスコンプレックスに対して、日本は阿闍世コンプレックスらしい。「お母さんが女だって?そりゃないだろう」らしい笑前者と対照的に後者には父が不在、母子のみの関係。その固定化されたイメージが今も脈々と受け継がれている(DV加害者の男性が妻にお母さんを求めていることもあったり、男性の精神科医が女性に「だって、あなたお母さんでしょ」と言ったり) 子どもを産んだとたんに母性愛を発揮しなければいけない母の恨みが娘に向かう(!) 「こんな理不尽さを生きている私は、あなただけがのうのうと自由に生きることを許さない」(p124)=ミソジニーそのもの。女性自身も内面化している 読んでると、なんというか、構造で無理を押し付けると、必ず歪みが起きるんだなと思った。無償の愛という尊いものの裏側にミソジニーがあるなんて。。。 なぜ自分を責めるのか? →背負わなくてもいい責任(親への責任)をずっと背負ってきた人が抱くもの(p126) 罪悪感は第三者の介入によって救済される! 本来は最良の第三者は父であるべきだけど、日本においては「父の不在」という名の父権主義である(by『母性愛という制度』) →ケアをしてこなかった父親にも責任がある ・反出生主義が流行ってるのを「どれだけ多くの家族が虐待的だったのかと思います」と書いてある。こういうことなのかな? ・『反共感論』という本の話にも繋がる。弱い人がいた時に思わず助けたくなるような共感を「情動的共感」と呼ぶけどそのことがこっちの本にも書かれている。それは「人間の文化であり、権力であり、尊厳である」。(p137)だから、赤ちゃんが泣いてる時になんとかしなきゃと思うのは母性愛というよりも「母親の尊厳」(p138) これは名言だ。母性愛というものは存在しない、と言い切っちゃってもいいんだ。母性愛がなくても、赤ん坊を育てるのは、母である以前に人間の尊厳なんだ。そして、だんだんと手が離れるようになっていくものなのだ。 そう言ってみるとたしかに、共依存の一つが過干渉だったけど、それって人間の文化とか本能的なものではない。やっぱりそのケアはやり過ぎに値するし、そこにはエゴとか、歪みが含まれてれるよなぁ。 『母親になって後悔してる』を読んで結構スッキリした(母親にならねばならないという圧力の説明がついた)けど、この本もだいぶスッキリ。母性愛がなくても、子どもを育てることができるし、「愛という言葉を使わなくても、人は十分に人を大切にすることができる」。

 いっちー@icchii3172025年9月5日読んでる共依存の三つの支配のかたち(p85) ①ケアや愛情によって、相手を弱体化することによる支配 ②相手にとってかけがえのない、交換不能な存在になることによる支配 ③女性にとって最も適応的な支配 ①→過保護、過干渉的なやつ ②→「私が離れたらダメだ」と思わせるやつ。映画『マザー』の母親もそんなだったな… ③→これは従来の価値観ではむしろ理想的で、共依存だと分からないやつ。
いっちー@icchii3172025年9月5日読んでる共依存の三つの支配のかたち(p85) ①ケアや愛情によって、相手を弱体化することによる支配 ②相手にとってかけがえのない、交換不能な存在になることによる支配 ③女性にとって最も適応的な支配 ①→過保護、過干渉的なやつ ②→「私が離れたらダメだ」と思わせるやつ。映画『マザー』の母親もそんなだったな… ③→これは従来の価値観ではむしろ理想的で、共依存だと分からないやつ。


 いっちー@icchii3172025年9月2日読んでる・母の愛を語る母たちは、なぜあんなにいかがわしいのか。 →弱者になることの権力性があるんじゃないか? (p81)被害者権力の特徴 ①被害者は(しばしば)自分より弱者を支配することで生きていく ②被害者は(しばしば)強迫的にケアを与えたくなることがある ③被害者は「正義」をよりどころにすることで生きることがある ケアって、普通は「正しい」し「美しい」ことだけど、ケアを与えるという形での権力性、支配性は、これまでほとんど注目されてこなかった。 →贈与論にもつながる。実際に起きていることを贈与の毒として、認知するにはまた時間が必要だったということ。 本では、なぜケアや援助が支配性を持ってしまうのかをパターナリズムを用いて説明している。 ・パターナリズムは「相手の意志と自分の意志が一緒であると思うこと」と、「自分の行為は善意と良識に従っていると思うこと」という要素で成り立っている。 つまり「自分のやってることは、良識ある善意に従っていて、正しいことだ。だから相手もそれを良いことと思うに違いない」(p84) 言われてみれば贈与論の理論?も言っちゃえば事例を集めて普遍化したものに過ぎないから、「なぜ与えることが毒になるのか」という説明にはなってないかも。
いっちー@icchii3172025年9月2日読んでる・母の愛を語る母たちは、なぜあんなにいかがわしいのか。 →弱者になることの権力性があるんじゃないか? (p81)被害者権力の特徴 ①被害者は(しばしば)自分より弱者を支配することで生きていく ②被害者は(しばしば)強迫的にケアを与えたくなることがある ③被害者は「正義」をよりどころにすることで生きることがある ケアって、普通は「正しい」し「美しい」ことだけど、ケアを与えるという形での権力性、支配性は、これまでほとんど注目されてこなかった。 →贈与論にもつながる。実際に起きていることを贈与の毒として、認知するにはまた時間が必要だったということ。 本では、なぜケアや援助が支配性を持ってしまうのかをパターナリズムを用いて説明している。 ・パターナリズムは「相手の意志と自分の意志が一緒であると思うこと」と、「自分の行為は善意と良識に従っていると思うこと」という要素で成り立っている。 つまり「自分のやってることは、良識ある善意に従っていて、正しいことだ。だから相手もそれを良いことと思うに違いない」(p84) 言われてみれば贈与論の理論?も言っちゃえば事例を集めて普遍化したものに過ぎないから、「なぜ与えることが毒になるのか」という説明にはなってないかも。

 いっちー@icchii3172025年9月2日読んでる・共依存という言葉はベトナム戦争をきっかけに生まれた ・70〜80年代?にシステム家族論(「家族のなかに原因/結果はない」)というものが登場し、その中で共依存という言葉が発展した。 →加害/被害という非対称的な、ときには対立する関係は想定されていない。これが、アルコール依存症の妻たちがDVを受けている現実を見逃してきた →妻は子どもを支配することでかろうじて生き延びた →共依存を権力と支配の文脈でとらえる(共依存は「支配」) ・依存症はそもそも酒がやめられるかどうかもあやふやだったから、専門家の権威がなかったのおもろい(p65) それでいくと、やっぱり腕のいい外科医とかに権威が集まってくるのかな ・第2波フェミニズムのムーブメントの話とか、ちゃんと読んだの初めてかも。
いっちー@icchii3172025年9月2日読んでる・共依存という言葉はベトナム戦争をきっかけに生まれた ・70〜80年代?にシステム家族論(「家族のなかに原因/結果はない」)というものが登場し、その中で共依存という言葉が発展した。 →加害/被害という非対称的な、ときには対立する関係は想定されていない。これが、アルコール依存症の妻たちがDVを受けている現実を見逃してきた →妻は子どもを支配することでかろうじて生き延びた →共依存を権力と支配の文脈でとらえる(共依存は「支配」) ・依存症はそもそも酒がやめられるかどうかもあやふやだったから、専門家の権威がなかったのおもろい(p65) それでいくと、やっぱり腕のいい外科医とかに権威が集まってくるのかな ・第2波フェミニズムのムーブメントの話とか、ちゃんと読んだの初めてかも。

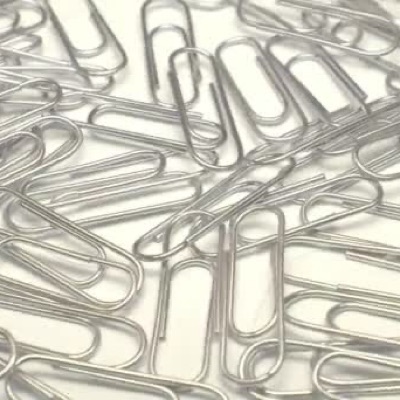


 いっちー@icchii3172025年9月1日読んでるオンラインセミナーをもとにしているから、口語体。読みやすいは読みやすいけど、信田さんの立場の主張も多い。主題「なぜ人は自分を責めてしまうのか」というところに辿り着くのはまだ先そう。
いっちー@icchii3172025年9月1日読んでるオンラインセミナーをもとにしているから、口語体。読みやすいは読みやすいけど、信田さんの立場の主張も多い。主題「なぜ人は自分を責めてしまうのか」というところに辿り着くのはまだ先そう。
 いっちー@icchii3172025年9月1日読んでるパワーワード出てきて面白くなってきた笑 「カウンセリングでも日常生活でも、避けたいのは、自己完結するということです。「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんてはっきり言うと、これはNGワードなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。だから私は「自己肯定感」という言葉は絶対使わないし、それから、「自分を許す」とか、そういう言葉も嫌です。」p51 →他者との関係のなかで、結果的に、自分が肯定できるようになることがあるが、自分だけで自分を肯定することはできないということ。だからこそ、当事者グループが必要だし、自分で自分を肯定できていると言う人は、周りとの関係が良好で、そのことに気づいていないだけかもしれない。 ・グループであることの大切さ。最近読みかけて返しちゃった、「刑務所に回復共同体をつくる」とも繋がってくる話しだ。 ・親のことを毒だとかひどいと思っていることを肯定した上で、なぜそんなことをしたのかや、なぜ父親と一緒に居続けるのかということを探究すること。それによって距離をとる。毒とかって言葉も、距離を取るための一つだけど、そこから、さらに俯瞰できるように高い位置に行く。 →「それによって、怖くもなんともなくなる」p60 ・パワーワードは続くよ「ケアと暴力は、紙一重」p58 こんなん自覚してたら母親になんて誰もなれないとか思うけど、どうすればいいんだろうね、私は怖いですよ、母親になんてなりたくないですよ、だけど。
いっちー@icchii3172025年9月1日読んでるパワーワード出てきて面白くなってきた笑 「カウンセリングでも日常生活でも、避けたいのは、自己完結するということです。「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんてはっきり言うと、これはNGワードなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。だから私は「自己肯定感」という言葉は絶対使わないし、それから、「自分を許す」とか、そういう言葉も嫌です。」p51 →他者との関係のなかで、結果的に、自分が肯定できるようになることがあるが、自分だけで自分を肯定することはできないということ。だからこそ、当事者グループが必要だし、自分で自分を肯定できていると言う人は、周りとの関係が良好で、そのことに気づいていないだけかもしれない。 ・グループであることの大切さ。最近読みかけて返しちゃった、「刑務所に回復共同体をつくる」とも繋がってくる話しだ。 ・親のことを毒だとかひどいと思っていることを肯定した上で、なぜそんなことをしたのかや、なぜ父親と一緒に居続けるのかということを探究すること。それによって距離をとる。毒とかって言葉も、距離を取るための一つだけど、そこから、さらに俯瞰できるように高い位置に行く。 →「それによって、怖くもなんともなくなる」p60 ・パワーワードは続くよ「ケアと暴力は、紙一重」p58 こんなん自覚してたら母親になんて誰もなれないとか思うけど、どうすればいいんだろうね、私は怖いですよ、母親になんてなりたくないですよ、だけど。
 いっちー@icchii3172025年8月31日借りてきたようやく借りたよりすな昨晩某Podcastのオールナイト配信にておすすめされていた本。ちょうど、図書館の予約がきたところだった。 信田さよ子さんとよりすなとの相性が良かった。
いっちー@icchii3172025年8月31日借りてきたようやく借りたよりすな昨晩某Podcastのオールナイト配信にておすすめされていた本。ちょうど、図書館の予約がきたところだった。 信田さよ子さんとよりすなとの相性が良かった。

- win@winksniper2025年8月6日読んでる“自己認知、つまり自分を自分で名づけるのがACなんです。” 私はACなのか?とモヤモヤしていたところにこの言葉。 知ることは自分を救う、と本当に思う。

 読書猫@bookcat2025年8月4日読み終わった(本文抜粋) “「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんて、はっきり言うと、これはNGワードなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。だから私は「自己肯定感」という言葉は絶対使わないし、それから、「自分を許す」とか、そういう言葉も嫌です。 他者との関係のなかで、結果的に自分が肯定できるようになることはあります。でも自分だけで自分を肯定することはできません。“ ”ケアと暴力は、紙一重です。介護施設の暴力って、非常に危ないところにありますよね。だから、他者を一生懸命ケアする場所は、絶えず暴力に移行する危険をはらんでいるということを、私たちはもっと意識しなきゃいけないと思います。“ ”共依存を表す一番わかりやすいフレーズが「あなたのために」です。“ “どうして他者のケアをすることが、気持ちいいのか。それは、相手を弱体化できますし、自分は強者の立場になるからです。かけがえのない存在になることで、自分はあたかも相手にとって神に等しい地位に上りつめることができる。 (中略) だから「いいことやってる」と思ったら危ないんです。ケアにまつわる支配性を、よく知らないといけない。” “やっぱり親子の問題は、親子だけ、まして母と子の二者だけでは、私はもう絶望的だと思う。そこには第三者の介入がなくてはいけない。“ ”母性愛は制度=作られてきたものである。これを知るだけでも、自分は母性愛がないから人間失格だなんて自分を責めることはないということになります。“ ”子どもは生まれさせられる。この事実を外してはいけないと思う。“ ”自己肯定感も、自分を好きになることも、そして「心」も、結果として生まれるものではないか。 そのために必要なのは、他者である。自分を助けようとする他者だけではない。自分に似た経験をした他者、類似した他者の存在こそ必要なのではないか。“
読書猫@bookcat2025年8月4日読み終わった(本文抜粋) “「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんて、はっきり言うと、これはNGワードなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。だから私は「自己肯定感」という言葉は絶対使わないし、それから、「自分を許す」とか、そういう言葉も嫌です。 他者との関係のなかで、結果的に自分が肯定できるようになることはあります。でも自分だけで自分を肯定することはできません。“ ”ケアと暴力は、紙一重です。介護施設の暴力って、非常に危ないところにありますよね。だから、他者を一生懸命ケアする場所は、絶えず暴力に移行する危険をはらんでいるということを、私たちはもっと意識しなきゃいけないと思います。“ ”共依存を表す一番わかりやすいフレーズが「あなたのために」です。“ “どうして他者のケアをすることが、気持ちいいのか。それは、相手を弱体化できますし、自分は強者の立場になるからです。かけがえのない存在になることで、自分はあたかも相手にとって神に等しい地位に上りつめることができる。 (中略) だから「いいことやってる」と思ったら危ないんです。ケアにまつわる支配性を、よく知らないといけない。” “やっぱり親子の問題は、親子だけ、まして母と子の二者だけでは、私はもう絶望的だと思う。そこには第三者の介入がなくてはいけない。“ ”母性愛は制度=作られてきたものである。これを知るだけでも、自分は母性愛がないから人間失格だなんて自分を責めることはないということになります。“ ”子どもは生まれさせられる。この事実を外してはいけないと思う。“ ”自己肯定感も、自分を好きになることも、そして「心」も、結果として生まれるものではないか。 そのために必要なのは、他者である。自分を助けようとする他者だけではない。自分に似た経験をした他者、類似した他者の存在こそ必要なのではないか。“


 久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年7月16日読み終わったケアにまつわる支配性を、よく知らないといけない。 他者のケアをしたら「今日はどうだったんだろう……自己治療にはなってるけど、支配的になってないか。なってたらごめんなさい」ぐらいの自覚がないと、共依存は危ない。(p.104) 自分が受けた傷についても、これから我が子につけてしまう傷についてもひとつなぎに説明されていた。じゃあどうすればいいの、はこの一文に集約されているのでは。この本のタイトルになっている自責感が、理不尽な閉鎖空間における究極の合理性と表現されているのもグッときた。反出生主義が出現したのもすべて、これまでと今の時代の背景そして親子関係に問題がある。と、ここまで。社会がどう変わるべきかについては触れられず、個人レベルでどうするかミクロの視点を持てる本だった。
久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年7月16日読み終わったケアにまつわる支配性を、よく知らないといけない。 他者のケアをしたら「今日はどうだったんだろう……自己治療にはなってるけど、支配的になってないか。なってたらごめんなさい」ぐらいの自覚がないと、共依存は危ない。(p.104) 自分が受けた傷についても、これから我が子につけてしまう傷についてもひとつなぎに説明されていた。じゃあどうすればいいの、はこの一文に集約されているのでは。この本のタイトルになっている自責感が、理不尽な閉鎖空間における究極の合理性と表現されているのもグッときた。反出生主義が出現したのもすべて、これまでと今の時代の背景そして親子関係に問題がある。と、ここまで。社会がどう変わるべきかについては触れられず、個人レベルでどうするかミクロの視点を持てる本だった。



 久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年7月15日読み始めたカウンセリングでも日常生活でも、避けたいのは、自己完結するということです。 「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんて、はっきり言うと、これはNGワートなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。だから私は「自己肯定感」という言葉は絶対使わないし、それから、「自分を許す」とか、そういう言葉も嫌です。(p.51) 「自己肯定感」ということばが持つ気持ち悪さを言語化してくださっている。自分で自分を肯定できないとダメ、そういう空気感がこのことばにあるからか。信田さよ子さんの文章、かたくなく、当事者をよく知っていて読みやすい。専門家というと難しいことばを使う人を想定してしまうけど、この本は平易なことば遣いでスッと入ってくる。もっと早く手をつければよかった。
久保みのり|書店よむにわ@kubomisan2025年7月15日読み始めたカウンセリングでも日常生活でも、避けたいのは、自己完結するということです。 「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんて、はっきり言うと、これはNGワートなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。だから私は「自己肯定感」という言葉は絶対使わないし、それから、「自分を許す」とか、そういう言葉も嫌です。(p.51) 「自己肯定感」ということばが持つ気持ち悪さを言語化してくださっている。自分で自分を肯定できないとダメ、そういう空気感がこのことばにあるからか。信田さよ子さんの文章、かたくなく、当事者をよく知っていて読みやすい。専門家というと難しいことばを使う人を想定してしまうけど、この本は平易なことば遣いでスッと入ってくる。もっと早く手をつければよかった。





 読書日和@miou-books2025年7月4日読み終わった罪悪感と自責感の違い、これを分かっておくだけでも大事。 虐待も受けてないし、大切に育ててもらったのになんだろう、このザラザラ感と分かりみの深さ。 何度も途中で読むのやめたくなる、そんな一冊でした…深い。
読書日和@miou-books2025年7月4日読み終わった罪悪感と自責感の違い、これを分かっておくだけでも大事。 虐待も受けてないし、大切に育ててもらったのになんだろう、このザラザラ感と分かりみの深さ。 何度も途中で読むのやめたくなる、そんな一冊でした…深い。

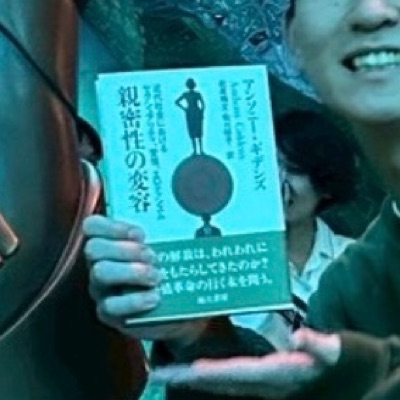 中村@boldmove332025年6月7日読み終わった"私も含めて、この世に生きているかぎり、誰に対しても加害をせずには生きていけません。いつも誰かを傷つけているんです。それを自覚してるかどうか。「加害者にも被害者にもなりたくありません」なんて、ムリだし、ありえない。昨今流行りのスローガンほどムカつくものはないですね。"(p. 95)
中村@boldmove332025年6月7日読み終わった"私も含めて、この世に生きているかぎり、誰に対しても加害をせずには生きていけません。いつも誰かを傷つけているんです。それを自覚してるかどうか。「加害者にも被害者にもなりたくありません」なんて、ムリだし、ありえない。昨今流行りのスローガンほどムカつくものはないですね。"(p. 95)
 クイスケ@kuiske07172025年6月1日読み終わった借りてきた母娘の問題についてカウンセラーが書いた本。 「自己肯定感」という言葉を嫌う作者は、他者に認められてこそだと言う。 女性によるミソジニーの内在化など的確な指摘が多くて読んで良かった。
クイスケ@kuiske07172025年6月1日読み終わった借りてきた母娘の問題についてカウンセラーが書いた本。 「自己肯定感」という言葉を嫌う作者は、他者に認められてこそだと言う。 女性によるミソジニーの内在化など的確な指摘が多くて読んで良かった。

 ぼっけ@bokeh2025年5月24日読み終わった話題になっていたので読んでみました。 パターナリズムな干渉という構図や、自己肯定感という言葉への矮小化に否定的な部分など、共感する事が多々ありました。 外部からは分かりにくい特殊な親子関係の存在、知人にも同様な問題から?家から離れている人がいることを思い出しました。
ぼっけ@bokeh2025年5月24日読み終わった話題になっていたので読んでみました。 パターナリズムな干渉という構図や、自己肯定感という言葉への矮小化に否定的な部分など、共感する事が多々ありました。 外部からは分かりにくい特殊な親子関係の存在、知人にも同様な問題から?家から離れている人がいることを思い出しました。 はる@tsukiyo_04292025年5月20日読み終わった「すべて自分が悪い」という思考は、虐待的環境で生きるために自分の存在を否定し、合理性を獲得することだ、という言葉に衝撃を受けた。 それと同時に納得した。 何か理不尽なことが起きたとき、自分を徹底して否定してしまえば、説明できるようになる。 世の中は合理的なんだ、間違っていない、なぜなら自分が悪いから、と。 こう思わなければ生きていけない状況になってしまうのは、家庭環境によるものが大きいということも分かった。 本書は、 第1章 母はまだ重い 第2章 共依存を読みとく 第3章 母への罪悪感と自責感 第4章 逆算の育児 第5章 なぜ人は自分を責めてしまうのか の全5章で構成されている。 カウンセリングセミナーの講座の内容を文字にしたもので、話し言葉寄りの文章で書かれている。 もくじを見て気になる箇所がある方は、ぜひ読んでみてほしい。
はる@tsukiyo_04292025年5月20日読み終わった「すべて自分が悪い」という思考は、虐待的環境で生きるために自分の存在を否定し、合理性を獲得することだ、という言葉に衝撃を受けた。 それと同時に納得した。 何か理不尽なことが起きたとき、自分を徹底して否定してしまえば、説明できるようになる。 世の中は合理的なんだ、間違っていない、なぜなら自分が悪いから、と。 こう思わなければ生きていけない状況になってしまうのは、家庭環境によるものが大きいということも分かった。 本書は、 第1章 母はまだ重い 第2章 共依存を読みとく 第3章 母への罪悪感と自責感 第4章 逆算の育児 第5章 なぜ人は自分を責めてしまうのか の全5章で構成されている。 カウンセリングセミナーの講座の内容を文字にしたもので、話し言葉寄りの文章で書かれている。 もくじを見て気になる箇所がある方は、ぜひ読んでみてほしい。 socotsu@shelf_soya2025年5月7日読み終わった抱えている自責について、これ一冊だけ読んですっきりするような本ではないが、母の日が近づいているこのタイミングでこの本を読めてよかったとは思う。 まず女親に押し付けられている「母性愛」は明治以降に構築された制度であること、その制度、役割が押し付けられている段階で母もまた被害者ではあるけれど、被害者の立場で、より弱いものへ、物理的に手をあげるなどの暴力を振るう暴力ではなく、ケア、世話、愛情という「無敵の価値を利用して行われる支配」という子どもへの暴力をはたらく存在と化す可能性があること、ケアの支配性が発揮されるしくみを知ることができたのが、個人的には一番よかった。 一方で「ぜんぶ自分のせいだ」という自責は容易に反転する、というくだりもSNSを例に取り上げていたが、自分も陥りがちなシチュエーションであるため注意したい。
socotsu@shelf_soya2025年5月7日読み終わった抱えている自責について、これ一冊だけ読んですっきりするような本ではないが、母の日が近づいているこのタイミングでこの本を読めてよかったとは思う。 まず女親に押し付けられている「母性愛」は明治以降に構築された制度であること、その制度、役割が押し付けられている段階で母もまた被害者ではあるけれど、被害者の立場で、より弱いものへ、物理的に手をあげるなどの暴力を振るう暴力ではなく、ケア、世話、愛情という「無敵の価値を利用して行われる支配」という子どもへの暴力をはたらく存在と化す可能性があること、ケアの支配性が発揮されるしくみを知ることができたのが、個人的には一番よかった。 一方で「ぜんぶ自分のせいだ」という自責は容易に反転する、というくだりもSNSを例に取り上げていたが、自分も陥りがちなシチュエーションであるため注意したい。





 akamatie@matie2025年5月6日読み終わった自分を責める癖の根っこには、存在の軽さや生まれてこなければよかったと思ってきた感覚があるんだなと気づいた。 脅迫的なケアという言葉が印象的で、してやってるんだから反抗するなという圧力は支配だったんだなと思ったり。 反転する自責感の話では、正しさを盾にした攻撃性はこれかと納得。自分が傷ついていると、無意識に他人を攻撃してしまう可能性がある。だからこそ、自分の問題はちゃんと自分で引き受けて、解決できるようになりたい。
akamatie@matie2025年5月6日読み終わった自分を責める癖の根っこには、存在の軽さや生まれてこなければよかったと思ってきた感覚があるんだなと気づいた。 脅迫的なケアという言葉が印象的で、してやってるんだから反抗するなという圧力は支配だったんだなと思ったり。 反転する自責感の話では、正しさを盾にした攻撃性はこれかと納得。自分が傷ついていると、無意識に他人を攻撃してしまう可能性がある。だからこそ、自分の問題はちゃんと自分で引き受けて、解決できるようになりたい。

 るい@Lui110372025年5月2日気になる読み終わった母と娘の関係について書いてあり、母との記憶がよみがえった。 母の愛はいかがわしい。 母は子どもを一番よく分かっているとか、お母さんなら私のことを理解してくれるとか、そんなのは幻想だ。 けっこう、衝撃的な文章が並ぶ。 母は母になった時、強制的に「供給者」となる。 その苦しみを娘にケアしてもらおうとする。 娘は自分のせいで母が苦しいと思い、自責感を抱えて生きる。 今日、母でもあり、娘でもあるわたしは、読み進めるたびに、心が揺さぶられてばかりだった。
るい@Lui110372025年5月2日気になる読み終わった母と娘の関係について書いてあり、母との記憶がよみがえった。 母の愛はいかがわしい。 母は子どもを一番よく分かっているとか、お母さんなら私のことを理解してくれるとか、そんなのは幻想だ。 けっこう、衝撃的な文章が並ぶ。 母は母になった時、強制的に「供給者」となる。 その苦しみを娘にケアしてもらおうとする。 娘は自分のせいで母が苦しいと思い、自責感を抱えて生きる。 今日、母でもあり、娘でもあるわたしは、読み進めるたびに、心が揺さぶられてばかりだった。

 らじゃまる@return10302025年5月1日買った読んでるずっと気になっててようやく買って読み始めた。 高校生の頃「毒になる親」を本屋で見つけて買って読んだ程度にはACの自覚ありで、最近chatGPTに自責感情つよすぎると指摘されたので😂なにか自分の救いになるといいなと思う。 ひとまず第一章まで読んだ。 生育歴は自分のことを喋っているようで母のことを喋ってるっていうのにびっくりした。たしかに! 作ってみよう…
らじゃまる@return10302025年5月1日買った読んでるずっと気になっててようやく買って読み始めた。 高校生の頃「毒になる親」を本屋で見つけて買って読んだ程度にはACの自覚ありで、最近chatGPTに自責感情つよすぎると指摘されたので😂なにか自分の救いになるといいなと思う。 ひとまず第一章まで読んだ。 生育歴は自分のことを喋っているようで母のことを喋ってるっていうのにびっくりした。たしかに! 作ってみよう…
- 万年あぶれ人@u_su_al2025年4月30日読み終わった自己肯定感を上げる、まずは自分を愛するといった言葉があふれるなか、他者ありきでしか自分を認め愛することなどできない。自責感も然り。という信田先生の言葉がガツンと響いた。
 いっちー@icchii3172025年4月24日気になる東畑開人さんが書評書いててちょっと気になる https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/reviews/20250324-OYT8T50086/
いっちー@icchii3172025年4月24日気になる東畑開人さんが書評書いててちょっと気になる https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/reviews/20250324-OYT8T50086/ 晶子@minimumsho2025年4月20日読み終わった「この世でもっとも悲惨でもっとも残酷な話が、仲間の希望になる」 読んだ。いや、なんかすごい内容だった。打ちのめされることと希望の両側から殴られるような一冊で、特に支配について言及されてる部分に唸ってしまった。
晶子@minimumsho2025年4月20日読み終わった「この世でもっとも悲惨でもっとも残酷な話が、仲間の希望になる」 読んだ。いや、なんかすごい内容だった。打ちのめされることと希望の両側から殴られるような一冊で、特に支配について言及されてる部分に唸ってしまった。



 晶子@minimumsho2025年4月19日読んでるカウンセリングでも日常でも、避けたいのは、自己完結するということなんです。「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんて、はっきりいうと、これはNGワードなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。
晶子@minimumsho2025年4月19日読んでるカウンセリングでも日常でも、避けたいのは、自己完結するということなんです。「自分で自分を癒す」とか「自分で自分を肯定する」なんて、はっきりいうと、これはNGワードなんですけど「くそくらえ」だと思ってるんですよ。




 ひなこ@hnk9272025年4月12日読み終わった@ ON READING自責感情それ自体を深掘りするものかと勝手に想定していたが、母娘の関係から紐解いていく感じだった。実は最も関心を寄せているため、非常に面白かった。でも読みながらしんどいなっていう自分もいて、まだ名残があることに気付く。先生と話したくなった。
ひなこ@hnk9272025年4月12日読み終わった@ ON READING自責感情それ自体を深掘りするものかと勝手に想定していたが、母娘の関係から紐解いていく感じだった。実は最も関心を寄せているため、非常に面白かった。でも読みながらしんどいなっていう自分もいて、まだ名残があることに気付く。先生と話したくなった。





 みずかり@mm_calling2025年3月28日読み終わった母のことを毒親とまでは思ってないけど「重い」「放っておけない」「離れて暮らす母が倒れたら自分の生活は変わってしまう」と、自分の人生から母をいっときも切り離せないという気持ちはある。 母娘問題をベースに自責感を紐解く構成だったけど、私個人としては、「自己責任論」が強まる現代社会の中で「自己肯定感」向上に孤独に取り組む個人たち…という酷な図式が完成した(自己肯定感という言葉を筆者は「激しく忌み嫌っている」)。 「根源的受動性」という言葉にも出合えたのは収穫。この世に生まれたことは自分自身になんの責任もない。子どもは責任ゼロで生まれてくる。そして、主体的に生きるためにはこれを親に承認されることが必要。(ここの帰結がよく分からなかったから、提唱者の芹沢俊介の本も読みたい) それにしても、母親が「常識」として背負わされてる母性神話とか自己犠牲もしんどすぎる。このへんをそのままにして健全な育児を目指しても、母親だけがまた負担増になるのだろうな、、。そして負担が増えると子供に矛先が、という今のサイクルが維持されてしまう。
みずかり@mm_calling2025年3月28日読み終わった母のことを毒親とまでは思ってないけど「重い」「放っておけない」「離れて暮らす母が倒れたら自分の生活は変わってしまう」と、自分の人生から母をいっときも切り離せないという気持ちはある。 母娘問題をベースに自責感を紐解く構成だったけど、私個人としては、「自己責任論」が強まる現代社会の中で「自己肯定感」向上に孤独に取り組む個人たち…という酷な図式が完成した(自己肯定感という言葉を筆者は「激しく忌み嫌っている」)。 「根源的受動性」という言葉にも出合えたのは収穫。この世に生まれたことは自分自身になんの責任もない。子どもは責任ゼロで生まれてくる。そして、主体的に生きるためにはこれを親に承認されることが必要。(ここの帰結がよく分からなかったから、提唱者の芹沢俊介の本も読みたい) それにしても、母親が「常識」として背負わされてる母性神話とか自己犠牲もしんどすぎる。このへんをそのままにして健全な育児を目指しても、母親だけがまた負担増になるのだろうな、、。そして負担が増えると子供に矛先が、という今のサイクルが維持されてしまう。


 数奇@suuqi2025年3月28日読み終わった母娘問題、共依存、虐待などの背景から、自責感の正体を読み解く一冊。講演の内容をまとめたものなので話し言葉でわかりやすく、信田先生の毒舌ぶりも随所に見られ、「自己肯定感なんてクソ食らえだ」というような発言も面白い。 親の問題や育児の話が多いので自分とは直接的な関係が薄い内容でもあったが、「すべて自分が悪い」と思うことは世の中の理不尽を合理的に説明する唯一の方法だとか、ハッとさせられる部分も多くて、読んでよかった。
数奇@suuqi2025年3月28日読み終わった母娘問題、共依存、虐待などの背景から、自責感の正体を読み解く一冊。講演の内容をまとめたものなので話し言葉でわかりやすく、信田先生の毒舌ぶりも随所に見られ、「自己肯定感なんてクソ食らえだ」というような発言も面白い。 親の問題や育児の話が多いので自分とは直接的な関係が薄い内容でもあったが、「すべて自分が悪い」と思うことは世の中の理不尽を合理的に説明する唯一の方法だとか、ハッとさせられる部分も多くて、読んでよかった。
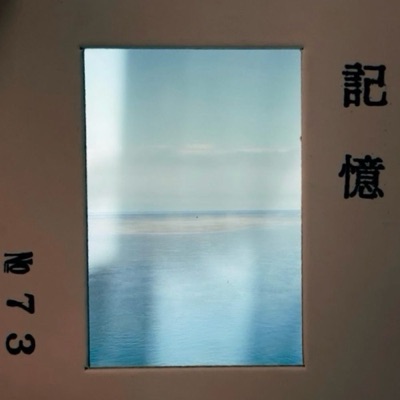





 朝@asa_3332025年3月27日読み終わった今読み終わっていちばん強く感じているのは、自分は自責感が強いんだと自覚した驚きだな。強すぎて当たり前すぎて見えてなかったものが、ぺろっと皮がむけて見えたって感じ。あと子どもについての本、まだ読んでいなかったので読もうと思っている。たくさん付箋を貼りたくさん線を引いた。ジャーニーって捉え方、なんかいいなあと思った。こどもは産まれるにあたって何も選んでいない、わたしが勝手に産んだというのって、人に言ってもなかなか伝わんないなって感じだったが名前がついているんだって驚いた。自責感というもの、共依存は支配。
朝@asa_3332025年3月27日読み終わった今読み終わっていちばん強く感じているのは、自分は自責感が強いんだと自覚した驚きだな。強すぎて当たり前すぎて見えてなかったものが、ぺろっと皮がむけて見えたって感じ。あと子どもについての本、まだ読んでいなかったので読もうと思っている。たくさん付箋を貼りたくさん線を引いた。ジャーニーって捉え方、なんかいいなあと思った。こどもは産まれるにあたって何も選んでいない、わたしが勝手に産んだというのって、人に言ってもなかなか伝わんないなって感じだったが名前がついているんだって驚いた。自責感というもの、共依存は支配。





 しらすアイス@shirasu_aisu2025年3月27日読み終わった思ってたノリとは違った(オンライン講義の文字起こし、フランクな口語、話題があちこちに飛ぶ)けど、広く浅くの入門編としては良かった。すぐに読み終わった。
しらすアイス@shirasu_aisu2025年3月27日読み終わった思ってたノリとは違った(オンライン講義の文字起こし、フランクな口語、話題があちこちに飛ぶ)けど、広く浅くの入門編としては良かった。すぐに読み終わった。

 opsun@gomi_atsume2025年3月27日読み終わったほんとに、ほんとに読む手が止まらなくなるほど面白い本。共依存とは支配であること、ケアする側のもつ権力についても真正面から書かれている。 ふと俯瞰してみると、実家にいるときだけ異常なほど呼吸が浅くなっていたり、体の一部が痙攣したりする。疲れてんな〜と思っていたけど、外に出るとケロッと良くなるので、多分この本の中にあるようにチューっと吸われてたのかも。
opsun@gomi_atsume2025年3月27日読み終わったほんとに、ほんとに読む手が止まらなくなるほど面白い本。共依存とは支配であること、ケアする側のもつ権力についても真正面から書かれている。 ふと俯瞰してみると、実家にいるときだけ異常なほど呼吸が浅くなっていたり、体の一部が痙攣したりする。疲れてんな〜と思っていたけど、外に出るとケロッと良くなるので、多分この本の中にあるようにチューっと吸われてたのかも。 opsun@gomi_atsume2025年3月27日読んでる中井久夫を読んでいる時も思うけれど、平易な文章でありながら、たくさんの皮に覆われたたまねぎの中央にあるたったひとつの細胞を一撃で射抜いてしまうような言葉の正確さと迷いのなさがすごい。 第5章はひとつめのパラグラフからそれが炸裂してる。 「虐待的環境を生きるということは、自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得することなんです。 すごいことです。自分を徹底して否定することで、世の中が説明できる。世の中はそれなりに合理的なんだ、なぜなら自分が悪いから。こういうことです。」
opsun@gomi_atsume2025年3月27日読んでる中井久夫を読んでいる時も思うけれど、平易な文章でありながら、たくさんの皮に覆われたたまねぎの中央にあるたったひとつの細胞を一撃で射抜いてしまうような言葉の正確さと迷いのなさがすごい。 第5章はひとつめのパラグラフからそれが炸裂してる。 「虐待的環境を生きるということは、自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得することなんです。 すごいことです。自分を徹底して否定することで、世の中が説明できる。世の中はそれなりに合理的なんだ、なぜなら自分が悪いから。こういうことです。」

 opsun@gomi_atsume2025年3月27日読んでる日本は「父の不在」という名の父権主義、という一節がぬるりと抵抗なく自分の中に入ってきて、家族の風景にパチッと説明を加える感じ。とても興味深い。 「家族の難しいことからは責任逃れをして、そのくせ自分は被害者ぶった顔をして、なおかつ既得権益は手離さない。」
opsun@gomi_atsume2025年3月27日読んでる日本は「父の不在」という名の父権主義、という一節がぬるりと抵抗なく自分の中に入ってきて、家族の風景にパチッと説明を加える感じ。とても興味深い。 「家族の難しいことからは責任逃れをして、そのくせ自分は被害者ぶった顔をして、なおかつ既得権益は手離さない。」
 opsun@gomi_atsume2025年3月25日システム家族論の話を読みながら、中井久夫の『家族の深淵』に出る様々な治療記を思い出すなど。 メモ 「実は、今回の主眼はそこにあります。被害を受けた人は、被害を受けっぱなしではいられないということです。」
opsun@gomi_atsume2025年3月25日システム家族論の話を読みながら、中井久夫の『家族の深淵』に出る様々な治療記を思い出すなど。 メモ 「実は、今回の主眼はそこにあります。被害を受けた人は、被害を受けっぱなしではいられないということです。」 opsun@gomi_atsume2025年3月25日読んでる100分de名著のなんの回だったか忘れたけど、司会の阿部みちこさんが息子へ強く干渉したくなってしまう自分がいる話をしたときに、TLが否定的な意見で溢れ返ったのを思い出す。 あの時の社会の拒絶するような反応に対するもやもやをうまく消化出来てなかったんだけど、「自分と区別のない存在(一体である存在)として娘や息子を思うことは、しばしば、ひっくり返ると虐待になるということです。(中略)ケアと暴力は、紙一重です。」を読んでふっと落ちてきた。
opsun@gomi_atsume2025年3月25日読んでる100分de名著のなんの回だったか忘れたけど、司会の阿部みちこさんが息子へ強く干渉したくなってしまう自分がいる話をしたときに、TLが否定的な意見で溢れ返ったのを思い出す。 あの時の社会の拒絶するような反応に対するもやもやをうまく消化出来てなかったんだけど、「自分と区別のない存在(一体である存在)として娘や息子を思うことは、しばしば、ひっくり返ると虐待になるということです。(中略)ケアと暴力は、紙一重です。」を読んでふっと落ちてきた。
 すべての本読み読み委員会@nadare2025年3月24日読み終わった明瞭かつ端的なので、必要としている人に「まずここから」と渡してあげられる一冊だと感じる。ただその分書き口は直球な点に留意したい…/ 🪵🌿グループカウンセリング。"乾いた地面が雨を吸い取るように(言葉が)消えていくのが理想""夜の森でキャンプファイヤーをするように"進行するのが良いという部分にハッとする。 あなたが炎のそばで語りたい時、同伴に私を選んでくれたら、それが生まれてきた意味という気もする。
すべての本読み読み委員会@nadare2025年3月24日読み終わった明瞭かつ端的なので、必要としている人に「まずここから」と渡してあげられる一冊だと感じる。ただその分書き口は直球な点に留意したい…/ 🪵🌿グループカウンセリング。"乾いた地面が雨を吸い取るように(言葉が)消えていくのが理想""夜の森でキャンプファイヤーをするように"進行するのが良いという部分にハッとする。 あなたが炎のそばで語りたい時、同伴に私を選んでくれたら、それが生まれてきた意味という気もする。


 本所あさひ@asahi_honjo2025年3月23日読み終わった・きっっっつい。読みながら何度も泣いた。親の立場の人間にはかなりシビアだと思われる内容の数々。でもすごく真っ当な主張だと思った。自分が親にされてきたなと感じて胸がヒリつく事例と、自分が我が子にひょっとしたらそうしてしまうかもしれないと想像して肝が冷える事例が多くあり、決して長くない新書のなかで感情が幾度も乱高下させられた。 ・自責感と罪悪感は似て非なるもの。後者は社会的規範ないし信仰を侵犯した際に覚えるのに対し、後者にはそうした枠組みがない。自分で自分を責める感情。その感情は、文脈のない理不尽な社会の中で最も合理的に自分の存在に納得を持たせることができる。「虐待的環境を生きるということは、自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得することなんですね。すごいことです。自分を徹底して否定することで、世の中が説明できる。世の中はそれなりに合理的なんだ、なぜなら自分が悪いから。」 ・根源的受動性。「言い換えると、「ぜんぶ受身」ということですね。子どもは、何ひとつ選んでない。性別も、名前も、顔も、身長も。生命すら選んでいない。 この根源的受動性というのは、子どもとともに語られないといけない。」「子育てにおいて子どもは、「解決の見通しがない世の中に生まれさせられたんですよ、あなたは」ということを誰かに承認されなきゃいけないんです。 承認するのはだれか。第一は親だと思います。 こういう世の中だけど、私はあなたを産みました。あなたに責任はありません。産んでしまったことを、私はちゃんと認めてますよ。」 ・あなたが生まれてきたことにあなた自身の責任は何ひとつないということを親が承認する。その承認を得ることで初めて、自分の人生は自分のものなのだ、自分の痛みは自分だけのものなのだと思うことができる。それこそが真の愛着形成である。 ・自分の経験が誰かの希望になり得るということ。小説を読むこと、書くこととカウンセリングの親和性。
本所あさひ@asahi_honjo2025年3月23日読み終わった・きっっっつい。読みながら何度も泣いた。親の立場の人間にはかなりシビアだと思われる内容の数々。でもすごく真っ当な主張だと思った。自分が親にされてきたなと感じて胸がヒリつく事例と、自分が我が子にひょっとしたらそうしてしまうかもしれないと想像して肝が冷える事例が多くあり、決して長くない新書のなかで感情が幾度も乱高下させられた。 ・自責感と罪悪感は似て非なるもの。後者は社会的規範ないし信仰を侵犯した際に覚えるのに対し、後者にはそうした枠組みがない。自分で自分を責める感情。その感情は、文脈のない理不尽な社会の中で最も合理的に自分の存在に納得を持たせることができる。「虐待的環境を生きるということは、自分の存在を否定することで、世界の合理性を獲得することなんですね。すごいことです。自分を徹底して否定することで、世の中が説明できる。世の中はそれなりに合理的なんだ、なぜなら自分が悪いから。」 ・根源的受動性。「言い換えると、「ぜんぶ受身」ということですね。子どもは、何ひとつ選んでない。性別も、名前も、顔も、身長も。生命すら選んでいない。 この根源的受動性というのは、子どもとともに語られないといけない。」「子育てにおいて子どもは、「解決の見通しがない世の中に生まれさせられたんですよ、あなたは」ということを誰かに承認されなきゃいけないんです。 承認するのはだれか。第一は親だと思います。 こういう世の中だけど、私はあなたを産みました。あなたに責任はありません。産んでしまったことを、私はちゃんと認めてますよ。」 ・あなたが生まれてきたことにあなた自身の責任は何ひとつないということを親が承認する。その承認を得ることで初めて、自分の人生は自分のものなのだ、自分の痛みは自分だけのものなのだと思うことができる。それこそが真の愛着形成である。 ・自分の経験が誰かの希望になり得るということ。小説を読むこと、書くこととカウンセリングの親和性。
 にわか読書家@niwakadokushoka2025年3月22日読み終わった@ 自宅ポッドキャストでも誰しもが加害者になってしまうからケアについて考えていたいという話をしたのだが、運よく素晴らしい現場に出会えたことがきっかけだった。 圧倒的に現場を見続けてこられた方の、まさにこういう本が読みたい、とめちゃくちゃ実感した。
にわか読書家@niwakadokushoka2025年3月22日読み終わった@ 自宅ポッドキャストでも誰しもが加害者になってしまうからケアについて考えていたいという話をしたのだが、運よく素晴らしい現場に出会えたことがきっかけだった。 圧倒的に現場を見続けてこられた方の、まさにこういう本が読みたい、とめちゃくちゃ実感した。



 ゆう@suisuiu2025年3月21日読み終わった面白かった〜 講座をもとにしているから口語的な表現で、信田先生節が気持ち良い。あっそう言っちゃっていいんですね、という感じで元気出る。それが本になっていることが嬉しい。タイトルからはもう少し汎用的な内容をイメージしていたけど、母と娘の関係性についての比重が大きかった。 特に共依存の章を興味深く読んだ。相手を弱体化する支配、交換不能な存在になる支配。そして、その支配の形は、残念ながら今の日本の女性にとって最も適応的な生き方になってしまっているということ(素直で可愛くて面倒見が良くて優しい女性像は共依存につながる)
ゆう@suisuiu2025年3月21日読み終わった面白かった〜 講座をもとにしているから口語的な表現で、信田先生節が気持ち良い。あっそう言っちゃっていいんですね、という感じで元気出る。それが本になっていることが嬉しい。タイトルからはもう少し汎用的な内容をイメージしていたけど、母と娘の関係性についての比重が大きかった。 特に共依存の章を興味深く読んだ。相手を弱体化する支配、交換不能な存在になる支配。そして、その支配の形は、残念ながら今の日本の女性にとって最も適応的な生き方になってしまっているということ(素直で可愛くて面倒見が良くて優しい女性像は共依存につながる)









 JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月20日読み終わったお風呂読書@ 自宅最後の第5章は、まさに本書のタイトルと直接関係する「自責感」について。出だしの「躾」と「規範」の整理の仕方が面白い。 “そこで[地球で]生きていくには、一定の規範を自分に取り込むことが必要です。それを総称して「躾」と言います。/子どもが生まれたそのときから、その養育者は[...]これはやっていいこと、これはやっちゃいけないことというのを、植え付けていく。これが躾です。/この世に適応しなければ、私たちは生きていけないからです。[....]/そう子どもには言えないので、これは間違っていること、これは正しいことというふうにして、教え込んでいく。/そして規範というのは、私たちが世の中で生きていけるようになることによって、正当化される。”(180-181頁) つづく「文脈化」、「究極の合理性」、「根源的受動性」と「愛着」、「正義」の話などもとても大事。あまりに読みやすいかたちで大事なことが提示されているので、何度か読んで自分の中に落とし込んだほうが良い気さえする。 個人的に最もグサッときた箇所のひとつがこちら。 “あともうひとつ。どの教科書にも、虐待されてる子に対して「あなたは悪くない」と言いなさい、と書いてあります。/どうぞ、勝手に言ってください。/そんなことで、どうにもならないと私は思う。むしろ専門家は、この子は悪くないんだと、自分に言い聞かせるべきです。”(205頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月20日読み終わったお風呂読書@ 自宅最後の第5章は、まさに本書のタイトルと直接関係する「自責感」について。出だしの「躾」と「規範」の整理の仕方が面白い。 “そこで[地球で]生きていくには、一定の規範を自分に取り込むことが必要です。それを総称して「躾」と言います。/子どもが生まれたそのときから、その養育者は[...]これはやっていいこと、これはやっちゃいけないことというのを、植え付けていく。これが躾です。/この世に適応しなければ、私たちは生きていけないからです。[....]/そう子どもには言えないので、これは間違っていること、これは正しいことというふうにして、教え込んでいく。/そして規範というのは、私たちが世の中で生きていけるようになることによって、正当化される。”(180-181頁) つづく「文脈化」、「究極の合理性」、「根源的受動性」と「愛着」、「正義」の話などもとても大事。あまりに読みやすいかたちで大事なことが提示されているので、何度か読んで自分の中に落とし込んだほうが良い気さえする。 個人的に最もグサッときた箇所のひとつがこちら。 “あともうひとつ。どの教科書にも、虐待されてる子に対して「あなたは悪くない」と言いなさい、と書いてあります。/どうぞ、勝手に言ってください。/そんなことで、どうにもならないと私は思う。むしろ専門家は、この子は悪くないんだと、自分に言い聞かせるべきです。”(205頁)
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月20日まだ読んでる@ カフェ近所のカフェで2章分読み進める。思い当たる節や思い出される実家の場面が、たくさんある。 第3章。 “これは私の持論なんですが、最良の第三者は、本来は父であるべきなんです。/[...]家族の難しいことからは責任逃れをして、そのくせ自分は犠牲者ぶった顔をして、なおかつ既得権益は手離さない。こういうやり方が日本の父権主義です。”(133頁) “[...]かわいいかどうかは別にして、赤ちゃんが泣いてると何とかしなきゃと思うのは、母性愛というより、母親の尊厳なんですよ。愛という言葉を使わなくても、十分に私は人は人を大切にできると思う。”(137-138頁) 第4章。 “[...]子どもは親にとって一種の解放区でもあります。[...]/何を言っても何をしても、どんなに叫んでも、許される。このことが虐待につながっていく。/この解放区というのは、自分の延長であることと表裏の関係なんです。[...]この二面性を、やっぱり知っておかないといけない。”(148頁) “[弱者の権力性について]ところが、母の愛は違うんですよ。犠牲者のままでいられる。子どもからしたら、母の不幸というのはすべての不安の種なんですね。お母さんが不幸であることほど、子どもにとって苦しいものはない。だから、自分が自己犠牲を払って不幸でいるかぎり、子どもを味方に引き入れることができるんです。”(159頁) “子ども以外の存在から支えられること。これを考えなきゃいけない。”(172頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月20日まだ読んでる@ カフェ近所のカフェで2章分読み進める。思い当たる節や思い出される実家の場面が、たくさんある。 第3章。 “これは私の持論なんですが、最良の第三者は、本来は父であるべきなんです。/[...]家族の難しいことからは責任逃れをして、そのくせ自分は犠牲者ぶった顔をして、なおかつ既得権益は手離さない。こういうやり方が日本の父権主義です。”(133頁) “[...]かわいいかどうかは別にして、赤ちゃんが泣いてると何とかしなきゃと思うのは、母性愛というより、母親の尊厳なんですよ。愛という言葉を使わなくても、十分に私は人は人を大切にできると思う。”(137-138頁) 第4章。 “[...]子どもは親にとって一種の解放区でもあります。[...]/何を言っても何をしても、どんなに叫んでも、許される。このことが虐待につながっていく。/この解放区というのは、自分の延長であることと表裏の関係なんです。[...]この二面性を、やっぱり知っておかないといけない。”(148頁) “[弱者の権力性について]ところが、母の愛は違うんですよ。犠牲者のままでいられる。子どもからしたら、母の不幸というのはすべての不安の種なんですね。お母さんが不幸であることほど、子どもにとって苦しいものはない。だから、自分が自己犠牲を払って不幸でいるかぎり、子どもを味方に引き入れることができるんです。”(159頁) “子ども以外の存在から支えられること。これを考えなきゃいけない。”(172頁)
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月19日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅仕事でへろへろだけど2章まで。 信田さんのこういうスタンスは、本当に信頼できる。 “[...]「虐待」は、私は当事者の言葉だと思ってるんですよ。それから、「性暴力」も。両方とも、被害を受ける側に立った言葉だからです。/専門家は、必ずそういう言葉を奪っていきます。いつのまにか[...]医者の言葉になり、警察の言葉になり、司法の言葉になる。/だけど、当事者たちは自分の言葉としてちゃんと持ちつづけているんです。”(64-65頁) そして、こういう部分をちゃんと説得力のあるかたちで書けるのも、本当にすごいと思う。 “[...]私は共依存をあんまり依存だと思っていなくて、どちらかというと「支配」と言ったほうがいいと思っています。/[...]誰も抵抗できないケア、世話、愛情という「無敵の価値を利用して行われる支配」。”(76-77頁) “「被害者権力」というものがあるんじゃないか。そして、弱者になるということは、そのことによって権力性を帯びてしまうということがあるんじゃないか。/これは、なかなか嫌なことです。[...]だけどやっぱりこのことは、私も含めて、十分自覚しなきゃいけない。”(81頁) ケアがもちうる権力性や暴力性は、先日読んだ大嶋さんの新著『傷はそこにある』でも掘り下げられていた。併読するとよさそう。 “大事なことは、依存をさせる人がどういう人か、です。「依存は、依存させる人の問題」なんですよ。”(105頁) いやあ、本当に...。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年3月19日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅仕事でへろへろだけど2章まで。 信田さんのこういうスタンスは、本当に信頼できる。 “[...]「虐待」は、私は当事者の言葉だと思ってるんですよ。それから、「性暴力」も。両方とも、被害を受ける側に立った言葉だからです。/専門家は、必ずそういう言葉を奪っていきます。いつのまにか[...]医者の言葉になり、警察の言葉になり、司法の言葉になる。/だけど、当事者たちは自分の言葉としてちゃんと持ちつづけているんです。”(64-65頁) そして、こういう部分をちゃんと説得力のあるかたちで書けるのも、本当にすごいと思う。 “[...]私は共依存をあんまり依存だと思っていなくて、どちらかというと「支配」と言ったほうがいいと思っています。/[...]誰も抵抗できないケア、世話、愛情という「無敵の価値を利用して行われる支配」。”(76-77頁) “「被害者権力」というものがあるんじゃないか。そして、弱者になるということは、そのことによって権力性を帯びてしまうということがあるんじゃないか。/これは、なかなか嫌なことです。[...]だけどやっぱりこのことは、私も含めて、十分自覚しなきゃいけない。”(81頁) ケアがもちうる権力性や暴力性は、先日読んだ大嶋さんの新著『傷はそこにある』でも掘り下げられていた。併読するとよさそう。 “大事なことは、依存をさせる人がどういう人か、です。「依存は、依存させる人の問題」なんですよ。”(105頁) いやあ、本当に...。


 nogi@mitsu_read2025年3月19日買った信田さんの本は「タフラブ 絆を手放す生き方」を長いこと積読しているのだけど(なんとなく元気なときでないと読めない気がして)、新書ならばと手に取ってみた
nogi@mitsu_read2025年3月19日買った信田さんの本は「タフラブ 絆を手放す生き方」を長いこと積読しているのだけど(なんとなく元気なときでないと読めない気がして)、新書ならばと手に取ってみた
 すべての本読み読み委員会@nadare2025年3月19日読み始めたなんだかもっと、Readsの記録を増やして生活日記のような存在にしたいのだが許されるだろうか?📚 手持ちがなく、移動本(移動する際に読む本)としてKindleで購入。前から思っているのだが信田さんは結構はっきり話される方だ。
すべての本読み読み委員会@nadare2025年3月19日読み始めたなんだかもっと、Readsの記録を増やして生活日記のような存在にしたいのだが許されるだろうか?📚 手持ちがなく、移動本(移動する際に読む本)としてKindleで購入。前から思っているのだが信田さんは結構はっきり話される方だ。







 散策舎@sansakusha2025年3月18日ちょっと開いた暴力の連鎖をいかに断ち切り、支配の隘路からいかに脱するか。信田さんの集大成的な一冊の予感。 この本では母と娘の関係から自責へと内側へ話が進むが、『家族と国家は共謀する(角川新書)』では人をそうさせる構造が外側にあることも指摘される。ぜひ併せて読んでみて下さい。
散策舎@sansakusha2025年3月18日ちょっと開いた暴力の連鎖をいかに断ち切り、支配の隘路からいかに脱するか。信田さんの集大成的な一冊の予感。 この本では母と娘の関係から自責へと内側へ話が進むが、『家族と国家は共謀する(角川新書)』では人をそうさせる構造が外側にあることも指摘される。ぜひ併せて読んでみて下さい。


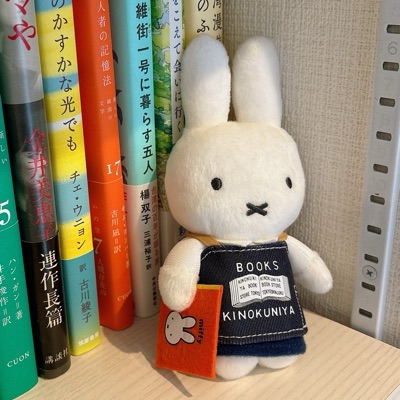 🍂@awasedashi2025年3月17日読み終わったたいしたトラブルはないけど、やっぱり母親のこと考えると暗澹たる気持ちになるもんだ。 依存させることは支配、みたいな話が印象に残った。依存されてる人に見える凄みってそれか。
🍂@awasedashi2025年3月17日読み終わったたいしたトラブルはないけど、やっぱり母親のこと考えると暗澹たる気持ちになるもんだ。 依存させることは支配、みたいな話が印象に残った。依存されてる人に見える凄みってそれか。 うたたねこ@ne9o2025年3月16日買った読み始めた読み終わった今まで私の中に染み付いていた「自責の念に駆られるのは"親の愛情"を受け取れない自分が悪いから」という呪いのような思いを、わかりやすい説明と寄り添う言葉によって根っこから剥がしてもらったような感覚があって、特に最終章を読みながら自然と涙が出てしまった。今必死に自分を取り戻そうとしてもがいている日々が、「ジャーニー」であり、また同じような苦しみを抱えた人たちの希望にもなり得る、という言葉もとても励みになる。
うたたねこ@ne9o2025年3月16日買った読み始めた読み終わった今まで私の中に染み付いていた「自責の念に駆られるのは"親の愛情"を受け取れない自分が悪いから」という呪いのような思いを、わかりやすい説明と寄り添う言葉によって根っこから剥がしてもらったような感覚があって、特に最終章を読みながら自然と涙が出てしまった。今必死に自分を取り戻そうとしてもがいている日々が、「ジャーニー」であり、また同じような苦しみを抱えた人たちの希望にもなり得る、という言葉もとても励みになる。

 数奇@suuqi2025年3月15日読んでる「自分を肯定する」とか「自分を許す」とかはくそくらえだ、という言葉が出てきてびっくりした。それは自己完結でしかなくて、自分ひとりで自分を肯定することはできない。他者との関係の中で結果的に自分を肯定ができるのだと書かれていて、ハッとさせられた。
数奇@suuqi2025年3月15日読んでる「自分を肯定する」とか「自分を許す」とかはくそくらえだ、という言葉が出てきてびっくりした。それは自己完結でしかなくて、自分ひとりで自分を肯定することはできない。他者との関係の中で結果的に自分を肯定ができるのだと書かれていて、ハッとさせられた。







 高尾清貴@kiyotakao2025年3月15日読み終わった母娘の関係性で生じる問題にフォーカスしていて、母でも娘でもない僕は、少し客観的に読めた。これは非常に面白いが、母や娘である人に、この本をどうやったらうまくおすすめできるのか、悩ましい。 『自責感は、自分を責めてしまう感覚を指しています。そこには、規範にそむいたからといった理由は存在しません。 自分を責めるとは、自分にすべて責任があるという感覚で、裏返せば「みんな自分のせい」という、非合理的万能感にも通じるものです。』
高尾清貴@kiyotakao2025年3月15日読み終わった母娘の関係性で生じる問題にフォーカスしていて、母でも娘でもない僕は、少し客観的に読めた。これは非常に面白いが、母や娘である人に、この本をどうやったらうまくおすすめできるのか、悩ましい。 『自責感は、自分を責めてしまう感覚を指しています。そこには、規範にそむいたからといった理由は存在しません。 自分を責めるとは、自分にすべて責任があるという感覚で、裏返せば「みんな自分のせい」という、非合理的万能感にも通じるものです。』





 スヌーズは神@mo_rechu2025年3月10日読んでる金銭の面倒を見てもらい、食の面倒を見てもらい、住処の面倒を見てもらい、親子間の面倒を見てもらった。そういう、非常に援助してもらった人から、無理矢理、跡を濁しまくって、逃げたことがある。 「ああ、あのときのどうしようもない鬱屈と苦しみはこういうことだったんだ」 あんなにも世話になった人に対してという自責と、自分を守るためにはあれしかなかったという本音の中でどうしようもなく呻いている中に、少しだけ光が差した感じがする。 何度も繰り返し読んでみようと思う。
スヌーズは神@mo_rechu2025年3月10日読んでる金銭の面倒を見てもらい、食の面倒を見てもらい、住処の面倒を見てもらい、親子間の面倒を見てもらった。そういう、非常に援助してもらった人から、無理矢理、跡を濁しまくって、逃げたことがある。 「ああ、あのときのどうしようもない鬱屈と苦しみはこういうことだったんだ」 あんなにも世話になった人に対してという自責と、自分を守るためにはあれしかなかったという本音の中でどうしようもなく呻いている中に、少しだけ光が差した感じがする。 何度も繰り返し読んでみようと思う。


 ゆう@suisuiu2025年3月6日気になる買ったちくまwebでも見られる「あとがき」もかっこいい 「〜不平等で理不尽な関係を生きてきたクライエントへの敬意と驚嘆が私の基本となっている。そこに「どうしてそんなことができたのか」という関心が加わることで、かろうじてその人たちの言葉を聞く資格があるように思える。 自己肯定感も、自分を好きになることも、そして「心」も、結果として生まれるものではないか。 そのために必要なのは、他者である。自分を助けようとする他者だけではない。自分に似た経験をした他者、類似した他者の存在こそ必要なのではないか。」
ゆう@suisuiu2025年3月6日気になる買ったちくまwebでも見られる「あとがき」もかっこいい 「〜不平等で理不尽な関係を生きてきたクライエントへの敬意と驚嘆が私の基本となっている。そこに「どうしてそんなことができたのか」という関心が加わることで、かろうじてその人たちの言葉を聞く資格があるように思える。 自己肯定感も、自分を好きになることも、そして「心」も、結果として生まれるものではないか。 そのために必要なのは、他者である。自分を助けようとする他者だけではない。自分に似た経験をした他者、類似した他者の存在こそ必要なのではないか。」








 サラエ@hacofug1900年1月1日読み終わった「子どもは、何ひとつ選んでない。性別も、名前も、顔も、身長も。生命すら選んでいない。」 「子どもは誰かといるときにしか一人になれないと言っています。子どもはずっと一人でいたら、一人と思えない。」
サラエ@hacofug1900年1月1日読み終わった「子どもは、何ひとつ選んでない。性別も、名前も、顔も、身長も。生命すら選んでいない。」 「子どもは誰かといるときにしか一人になれないと言っています。子どもはずっと一人でいたら、一人と思えない。」