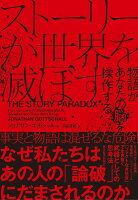なきりけい
@nakirikei
興味関心:現象学、ストーリー・ナラティブ
- 2025年10月27日
- 2025年9月28日
 飛越馳星周気になるその表紙を見るだけで 「前王者か、現王者か。青い帽子の2頭の追い比べにかわる直線」 という実況が聞こえてくるよう。 小説として脚色はされているものの、この2頭のモデルがオジュウチョウサンとアップトゥデートであることだけは間違いない。この本はKindleではなく実本でほしい。本棚の一角に飾りたい。
飛越馳星周気になるその表紙を見るだけで 「前王者か、現王者か。青い帽子の2頭の追い比べにかわる直線」 という実況が聞こえてくるよう。 小説として脚色はされているものの、この2頭のモデルがオジュウチョウサンとアップトゥデートであることだけは間違いない。この本はKindleではなく実本でほしい。本棚の一角に飾りたい。 - 2025年9月24日
 哲学は何ではないのか江川隆男気になる10月上旬に発刊される新書。 この世には「哲学っぽい」ものが多すぎる Amazonの説明文の冒頭がこれ。場末の読者である私ですら「これは哲学とは呼べないだろう⋯⋯」と感じるものがあるのだから、哲学者にとっては「ふざけるな!」と言いたくなる瞬間は多いだろうと思う。 世の中にはびこる哲学のフリをしたなにかを暴く一冊として期待。『哲学は何ではないのか』という否定的に語ることで肯定を導くという手法にも期待したい。
哲学は何ではないのか江川隆男気になる10月上旬に発刊される新書。 この世には「哲学っぽい」ものが多すぎる Amazonの説明文の冒頭がこれ。場末の読者である私ですら「これは哲学とは呼べないだろう⋯⋯」と感じるものがあるのだから、哲学者にとっては「ふざけるな!」と言いたくなる瞬間は多いだろうと思う。 世の中にはびこる哲学のフリをしたなにかを暴く一冊として期待。『哲学は何ではないのか』という否定的に語ることで肯定を導くという手法にも期待したい。 - 2025年9月24日
 愚か者の哲学竹田青嗣読み始めたオークションサイトで見つけた本。 20年以上前に哲学エッセイというかたちで出版された本らしい。さらさらと読める内容ではあるけれど、ちゃんと勘どころは押さえられているのは、さすが竹田氏といったところ。現代であれば哲学入門や人生に役立つ哲学みたく出版されるであろう内容。 邪推ではあるが、この本が世に出た00年代前半は、著者が読者を試すような硬派な本(無駄に難しい本ともいう)がまだまだ多かったのだろうなと思う。
愚か者の哲学竹田青嗣読み始めたオークションサイトで見つけた本。 20年以上前に哲学エッセイというかたちで出版された本らしい。さらさらと読める内容ではあるけれど、ちゃんと勘どころは押さえられているのは、さすが竹田氏といったところ。現代であれば哲学入門や人生に役立つ哲学みたく出版されるであろう内容。 邪推ではあるが、この本が世に出た00年代前半は、著者が読者を試すような硬派な本(無駄に難しい本ともいう)がまだまだ多かったのだろうなと思う。 - 2025年9月18日
 「いきり」の構造武田砂鉄気になる題名は九鬼周造の「「いき」の構造」をオマージュしたもの。確かに現代はいきな人よりいきり散らかしている人のほうが多い。 著者は以前100分de名著にてル・ボンの「群衆心理」について解説されていた。コメントは平易ながら切れ味が鋭かったのをよく覚えている。その後著作に触れることはなかったが、この一冊は読んでみたい。 一種の令和版・群衆心理であることに期待。
「いきり」の構造武田砂鉄気になる題名は九鬼周造の「「いき」の構造」をオマージュしたもの。確かに現代はいきな人よりいきり散らかしている人のほうが多い。 著者は以前100分de名著にてル・ボンの「群衆心理」について解説されていた。コメントは平易ながら切れ味が鋭かったのをよく覚えている。その後著作に触れることはなかったが、この一冊は読んでみたい。 一種の令和版・群衆心理であることに期待。 - 2025年9月17日
 「いき」の構造改版九鬼周造読んでる九鬼がハイデガーの教え子だったことを知って、興味が再燃した。 パラグラフごとに「これは一体なにを⋯⋯」と考えていかないといけない本ではあるが、ノートを作りながら再読したいと思う。 ある本、引用されていた 『「いき」は個々の概念契機に分析することはできるが、逆に、分析された個々の概念契機をもって「いき」の存在を構成することはできない。』 にはいろいろなことを教えられた。
「いき」の構造改版九鬼周造読んでる九鬼がハイデガーの教え子だったことを知って、興味が再燃した。 パラグラフごとに「これは一体なにを⋯⋯」と考えていかないといけない本ではあるが、ノートを作りながら再読したいと思う。 ある本、引用されていた 『「いき」は個々の概念契機に分析することはできるが、逆に、分析された個々の概念契機をもって「いき」の存在を構成することはできない。』 にはいろいろなことを教えられた。 - 2025年9月13日
- 2025年9月13日
- 2025年8月26日
- 2025年8月17日
 性格診断ブームを問う小塩真司買ったSNSの自己紹介でよく書かれている四文字のアレについて批判した一冊。 コロナ禍前には16personalitiesを使ったコンサルティングなどという、かなり怪しげなサービスも見かけたものだが、昨今はどうなのだろうか? わずか80ページ足らずの小冊子なので、出張するときに持っていって、新幹線のなかで読み切りたい。
性格診断ブームを問う小塩真司買ったSNSの自己紹介でよく書かれている四文字のアレについて批判した一冊。 コロナ禍前には16personalitiesを使ったコンサルティングなどという、かなり怪しげなサービスも見かけたものだが、昨今はどうなのだろうか? わずか80ページ足らずの小冊子なので、出張するときに持っていって、新幹線のなかで読み切りたい。 - 2025年8月17日
 趣味は読書。 (ちくま文庫)斎藤美奈子かつて読んだ『ふだん本を読まない人が読むからベストセラーになる』 今から25年前、2000年前後のベストセラーについて(大半はケチョンケチョンな)書評を並べた一冊。 一応、書評本だが、その内容のほとんどは「お前らちゃんと読んでないだろ!?」というベストセラーにしか興味のない「普段は本を読まない人たち」への怒りに満ちているという謎の本がこちら。 ベストセラーを生み出す流れは、そのままSNSでバズを起こす流れに置き換えられる。著者の書評(本に関する分析)をメタ的に読むことができれば、SNSで見かける「なぜこんなポストがこれほどバズっているのか……?」という疑問の答えにたどり着けるかもしれない。
趣味は読書。 (ちくま文庫)斎藤美奈子かつて読んだ『ふだん本を読まない人が読むからベストセラーになる』 今から25年前、2000年前後のベストセラーについて(大半はケチョンケチョンな)書評を並べた一冊。 一応、書評本だが、その内容のほとんどは「お前らちゃんと読んでないだろ!?」というベストセラーにしか興味のない「普段は本を読まない人たち」への怒りに満ちているという謎の本がこちら。 ベストセラーを生み出す流れは、そのままSNSでバズを起こす流れに置き換えられる。著者の書評(本に関する分析)をメタ的に読むことができれば、SNSで見かける「なぜこんなポストがこれほどバズっているのか……?」という疑問の答えにたどり着けるかもしれない。 - 2025年8月17日
 暴走するポピュリズム有馬晋作読みたい耳目を引けば勝ち、そんな価値観が支配する昨今、ポピュリズムという言葉をよく耳にするようになった。 そのようななか、ポピュリズムとは何かを知るために読みたいと思った一冊。 政治から日常までそのイデオロギーは浸透してしまっているので、ポピュリズムに飲み込まれないためにも知識はつけておきたいもの。
暴走するポピュリズム有馬晋作読みたい耳目を引けば勝ち、そんな価値観が支配する昨今、ポピュリズムという言葉をよく耳にするようになった。 そのようななか、ポピュリズムとは何かを知るために読みたいと思った一冊。 政治から日常までそのイデオロギーは浸透してしまっているので、ポピュリズムに飲み込まれないためにも知識はつけておきたいもの。 - 2025年8月16日
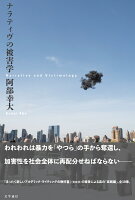 ナラティヴの被害学阿部幸大読みたい「まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書」が東大京大でいちばん読まれている本の選出された著者の一冊。 二元論で考える恐ろしさと、それを巧み操るポピュリズムの恐ろしさを教えてくれる一冊として期待。 検索のときにはナラティブといれると出てこないことがあるので要注意⋯。
ナラティヴの被害学阿部幸大読みたい「まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書」が東大京大でいちばん読まれている本の選出された著者の一冊。 二元論で考える恐ろしさと、それを巧み操るポピュリズムの恐ろしさを教えてくれる一冊として期待。 検索のときにはナラティブといれると出てこないことがあるので要注意⋯。 - 2025年8月16日
- 2025年8月15日
- 2025年8月15日
- 2025年8月12日
- 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 現象学入門竹田青嗣かつて読んだ竹田現象学の入門書のひとつ。こちらのほうが難しい。写真は旧版のもので、現在は同出版社から新版がでているので、そちらをどうぞ。 一度読んだだけで理解するのは無理なので、何度か読み直している本。とはいえ、まだまだ理解できる気がしない。
現象学入門竹田青嗣かつて読んだ竹田現象学の入門書のひとつ。こちらのほうが難しい。写真は旧版のもので、現在は同出版社から新版がでているので、そちらをどうぞ。 一度読んだだけで理解するのは無理なので、何度か読み直している本。とはいえ、まだまだ理解できる気がしない。 - 1900年1月1日
読み込み中...