

トム
@yukiyuki7
自己啓発本、ビジネス本、ミステリー、ホラーが大好きです。
月に10冊以上読みます。
皆さんの感想を読んでから、本を買うことも多いです。よろしくお願いします。
- 2026年1月2日
 ホラー読み終わったこの小説は、ホラー小説のネタを探す取材者が、九州にある一家惨殺事件の現場(廃墟)を訪れ、関係者である鷹村翔太にインタビューしながら進む。 物語はふつうの小説というより、音声の文字起こし、犯人の手記、取材メモなどの「資料」を読む形式で、モキュメンタリーっぽく作られている。 犯人は宍戸篤。最初は「こいつが全部悪い」と感じる。 でも読み進めると、篤がそうなるまでの家庭環境がひどく、同情できる部分もある。 父は会社社長だが借金を抱え、家族に暴力を振るう。 家は丁字路の突き当たりに建てられていて、風水的に良くない場所らしい。 さらに、呪いを鎮めるための石敢當を父が撤去してしまい、家に「黒い何か」が出入りするようになる。篤はそれが父の中に入るのを見た、と語っている。 家の中では、父の暴力で母は気絶するほど痛めつけられ、姉も篤も殴られる。 篤の手記を読むと、篤は満足な教育を受けていないのか、もともと知能が低いのか、判断力が弱く、状況を整理したり冷静に考えたりするのが苦手な人物に見える。 ある日、父は首吊り自殺する。 しかし宗教にハマっていた母は「父の魂をつなぎ止める」と言って、父の遺体を放置する。 遺体が腐って溶けるまで、そのまま家に置かれる。 篤は姉のことが大好きで、姉との間に子どもを作る。 これについて篤も姉も知識がなかったんだろうか……。 その子は母によって養子に出されてしまう。 篤が姉とヤッたことを母に隠していたせいで、母が「完璧な家族の上で必要がない」と判断したんだろうと思う。 姉はだんだん壊れていき、ついに母を惨殺して自殺する。 篤は帰宅して二人の遺体を見つけるが、母の考え方の影響もあって、魂が戻ると思い込み、遺体と一緒に1か月暮らす。 その後、逮捕されて入院する。 退院して家に戻ると、そこには別の家族が住んでいる。 でも篤にとっては「自分の家」なので、母と姉の死をなぞるように、その家族を惨殺し、遺体と2週間過ごす。 また逮捕・入院し、再び戻った篤は、最後はその家で自殺したようだ。 その遺体を発見したのが、冒頭でインタビューされていた当事者(=鷹村翔太)だった。 全体としてかなり残酷で、資料形式でリアルっぽく見せている。 ただ、私はリアルさが足りないと感じたし、終わり方もはっきりせずモヤモヤした。 母の宗教も意味不明で、篤や姉も判断が幼く、読んでいてイライラする場面が多い。 結局この物語は、誰も救われず、誰も幸せにならないまま終わる話だった。
ホラー読み終わったこの小説は、ホラー小説のネタを探す取材者が、九州にある一家惨殺事件の現場(廃墟)を訪れ、関係者である鷹村翔太にインタビューしながら進む。 物語はふつうの小説というより、音声の文字起こし、犯人の手記、取材メモなどの「資料」を読む形式で、モキュメンタリーっぽく作られている。 犯人は宍戸篤。最初は「こいつが全部悪い」と感じる。 でも読み進めると、篤がそうなるまでの家庭環境がひどく、同情できる部分もある。 父は会社社長だが借金を抱え、家族に暴力を振るう。 家は丁字路の突き当たりに建てられていて、風水的に良くない場所らしい。 さらに、呪いを鎮めるための石敢當を父が撤去してしまい、家に「黒い何か」が出入りするようになる。篤はそれが父の中に入るのを見た、と語っている。 家の中では、父の暴力で母は気絶するほど痛めつけられ、姉も篤も殴られる。 篤の手記を読むと、篤は満足な教育を受けていないのか、もともと知能が低いのか、判断力が弱く、状況を整理したり冷静に考えたりするのが苦手な人物に見える。 ある日、父は首吊り自殺する。 しかし宗教にハマっていた母は「父の魂をつなぎ止める」と言って、父の遺体を放置する。 遺体が腐って溶けるまで、そのまま家に置かれる。 篤は姉のことが大好きで、姉との間に子どもを作る。 これについて篤も姉も知識がなかったんだろうか……。 その子は母によって養子に出されてしまう。 篤が姉とヤッたことを母に隠していたせいで、母が「完璧な家族の上で必要がない」と判断したんだろうと思う。 姉はだんだん壊れていき、ついに母を惨殺して自殺する。 篤は帰宅して二人の遺体を見つけるが、母の考え方の影響もあって、魂が戻ると思い込み、遺体と一緒に1か月暮らす。 その後、逮捕されて入院する。 退院して家に戻ると、そこには別の家族が住んでいる。 でも篤にとっては「自分の家」なので、母と姉の死をなぞるように、その家族を惨殺し、遺体と2週間過ごす。 また逮捕・入院し、再び戻った篤は、最後はその家で自殺したようだ。 その遺体を発見したのが、冒頭でインタビューされていた当事者(=鷹村翔太)だった。 全体としてかなり残酷で、資料形式でリアルっぽく見せている。 ただ、私はリアルさが足りないと感じたし、終わり方もはっきりせずモヤモヤした。 母の宗教も意味不明で、篤や姉も判断が幼く、読んでいてイライラする場面が多い。 結局この物語は、誰も救われず、誰も幸せにならないまま終わる話だった。 - 2025年12月11日
 或る集落の●矢樹純ホラー読み終わった青森県のとある集落を舞台にした一冊。そこに祀られている神様が、とにかく不穏でヤバい。 物語には、その集落に移り住んだことで精神が崩壊していく姉、謎めいたしきたりに苦しむ母、そこで育てられた亀の刺青の男、どうしようもなくだらしないおっさんなどが、章ごとに主役を変えながら登場する。 最初は「怖い話の短編集かな?」と思いきや、どの章にも微妙に同じ集落が関わっていて、別の章の登場人物の“その後”がちらっと分かったりする。 ただ、そのつながりが薄く、絡み合いそうで絡みきらない。 各章は、不穏さだけを残して終わっていく。 特に、おっさんと猿が口づけするシーンは読んでいて正直きつかった。 そして結局、最後まで核心の謎は解き明かされないまま物語は終わる。 「ここまで読んだのに、え、うそ、もうページないじゃん。あ、終わった……」という肩透かし感がすごくて、自分にはまったく合わない本だった。
或る集落の●矢樹純ホラー読み終わった青森県のとある集落を舞台にした一冊。そこに祀られている神様が、とにかく不穏でヤバい。 物語には、その集落に移り住んだことで精神が崩壊していく姉、謎めいたしきたりに苦しむ母、そこで育てられた亀の刺青の男、どうしようもなくだらしないおっさんなどが、章ごとに主役を変えながら登場する。 最初は「怖い話の短編集かな?」と思いきや、どの章にも微妙に同じ集落が関わっていて、別の章の登場人物の“その後”がちらっと分かったりする。 ただ、そのつながりが薄く、絡み合いそうで絡みきらない。 各章は、不穏さだけを残して終わっていく。 特に、おっさんと猿が口づけするシーンは読んでいて正直きつかった。 そして結局、最後まで核心の謎は解き明かされないまま物語は終わる。 「ここまで読んだのに、え、うそ、もうページないじゃん。あ、終わった……」という肩透かし感がすごくて、自分にはまったく合わない本だった。 - 2025年7月30日
 わかりやすさの罪武田砂鉄読み終わった読み終えた後に考えるこの本は、「分かりやすさ」や「要約」「当事者性」みたいな、一見いいことに聞こえる価値観の裏側をじわっと刺してくる内容でした。 印象的だったのは「どっちがいい?」の二択の怖さ。選択肢が出された時点で、それ以外の可能性が消えてしまうし、二択を受け入れた時点でその枠に同意していることにもなる、という話です。分かりやすさって優しさにも見えるけど、考える余白を奪う面もあるんだなと。 あと「要するに何が言いたいの?」は、受け手側の仕事でもあるという指摘も刺さりました。要約って便利だけど、まとめる人の価値基準で大事な部分が削られる危険もあるし、要し方は人の数だけある、というのも腑に落ちます。 さらに、年齢や当事者性だけで意見の正しさが決まってしまう空気にも疑問を投げかけていて、当事者じゃなくても「自分はこう思う」と言うこと自体は悪じゃない、という視点が新鮮でした。読み終わったあと、簡単に答えを求めるクセをちょっと反省したくなる本でした。
わかりやすさの罪武田砂鉄読み終わった読み終えた後に考えるこの本は、「分かりやすさ」や「要約」「当事者性」みたいな、一見いいことに聞こえる価値観の裏側をじわっと刺してくる内容でした。 印象的だったのは「どっちがいい?」の二択の怖さ。選択肢が出された時点で、それ以外の可能性が消えてしまうし、二択を受け入れた時点でその枠に同意していることにもなる、という話です。分かりやすさって優しさにも見えるけど、考える余白を奪う面もあるんだなと。 あと「要するに何が言いたいの?」は、受け手側の仕事でもあるという指摘も刺さりました。要約って便利だけど、まとめる人の価値基準で大事な部分が削られる危険もあるし、要し方は人の数だけある、というのも腑に落ちます。 さらに、年齢や当事者性だけで意見の正しさが決まってしまう空気にも疑問を投げかけていて、当事者じゃなくても「自分はこう思う」と言うこと自体は悪じゃない、という視点が新鮮でした。読み終わったあと、簡単に答えを求めるクセをちょっと反省したくなる本でした。 - 2025年7月3日
 読み終わった『インプット・ルーティン』を読んで最も響いたのは、アウトプットは「既存のアイデア×既存のアイデア÷大量のインプット」という式に象徴されるように、土台となるインプットが何より重要だということだ。 自分の中から勝手に新しい発想が泉のように湧いてくるわけではなく、普段から膨大に蓄えていなければ何も生まれないという現実は、厳しくも的を射ている。 さらに印象深かったのは「精度」の話だ。SNSや動画で大量の情報に触れていると、あたかも豊かにインプットしている気になるが、それはただの幻想だ。 闇雲に走ってもマラソン王者になれないように、インプットにも戦略が必要だ。特に「良いもの」ではなく「スゴいもの」を選ぶ視点は目から鱗だった。 確かに世の中にはそこそこ良いものが溢れているが、時代を超えて残り続けるスゴいものはごく一部。 その少数精鋭にどれだけ触れられるかが勝負なのだと思う。また、本を読むときに「本当にそうなの?」と疑い、反証し、自分の頭で再構築する作業はまさに脳のダンベル。 単に楽しく読むだけでは思考力は育たないと肝に銘じたい。さらに、課題は与えられてから考えるのではなく、普段から頭の端に置いておき、何かを見るたび「これって使えないかな?」と考えることで初めて、厨房に立ったときにスムーズに答え合わせ=アウトプットができるのだという例えも秀逸だった。 読書を隙間時間に取り込み、日常に馴染ませる習慣もぜひ取り入れたい。 そして最終的に目指すべきは、意外性ある組み合わせから生まれるアウトプットであり、変化の最前線に立ち続けるためには、このインプットのルーティンが欠かせないのだと改めて感じた。
読み終わった『インプット・ルーティン』を読んで最も響いたのは、アウトプットは「既存のアイデア×既存のアイデア÷大量のインプット」という式に象徴されるように、土台となるインプットが何より重要だということだ。 自分の中から勝手に新しい発想が泉のように湧いてくるわけではなく、普段から膨大に蓄えていなければ何も生まれないという現実は、厳しくも的を射ている。 さらに印象深かったのは「精度」の話だ。SNSや動画で大量の情報に触れていると、あたかも豊かにインプットしている気になるが、それはただの幻想だ。 闇雲に走ってもマラソン王者になれないように、インプットにも戦略が必要だ。特に「良いもの」ではなく「スゴいもの」を選ぶ視点は目から鱗だった。 確かに世の中にはそこそこ良いものが溢れているが、時代を超えて残り続けるスゴいものはごく一部。 その少数精鋭にどれだけ触れられるかが勝負なのだと思う。また、本を読むときに「本当にそうなの?」と疑い、反証し、自分の頭で再構築する作業はまさに脳のダンベル。 単に楽しく読むだけでは思考力は育たないと肝に銘じたい。さらに、課題は与えられてから考えるのではなく、普段から頭の端に置いておき、何かを見るたび「これって使えないかな?」と考えることで初めて、厨房に立ったときにスムーズに答え合わせ=アウトプットができるのだという例えも秀逸だった。 読書を隙間時間に取り込み、日常に馴染ませる習慣もぜひ取り入れたい。 そして最終的に目指すべきは、意外性ある組み合わせから生まれるアウトプットであり、変化の最前線に立ち続けるためには、このインプットのルーティンが欠かせないのだと改めて感じた。 - 2025年6月28日
 読み終わった努力読み終えた後に考える青春この手帳をお前に預ける いつかきっと返しに来い 立派な魔法使いになってな・・・ 魔法使いに私はなる!! 10年後・・・・なれませんでした。 友人も遊びも趣味も自由も全てをかなぐり捨てて勉強だけに費やしてきた。 頑張っても届かないものがあると知って涙溢れた。 理不尽。 「努力は必ず報われる」というのは報われたやつだけの言葉。 そして世間は、歴史は、報われたやつの言葉しか残さない。 残さないからそれが真実だと思い込む。 報われなかった人たちの声は「こんな努力は努力じゃない」と失敗例にされる。 夢破れた少女が涙を流しながら奥歯を噛み締めながら夢を諦めようとした時。 「あなたの夢・・・まだ捨てなくていいかも」 法律の抜け穴をついた逆転劇
読み終わった努力読み終えた後に考える青春この手帳をお前に預ける いつかきっと返しに来い 立派な魔法使いになってな・・・ 魔法使いに私はなる!! 10年後・・・・なれませんでした。 友人も遊びも趣味も自由も全てをかなぐり捨てて勉強だけに費やしてきた。 頑張っても届かないものがあると知って涙溢れた。 理不尽。 「努力は必ず報われる」というのは報われたやつだけの言葉。 そして世間は、歴史は、報われたやつの言葉しか残さない。 残さないからそれが真実だと思い込む。 報われなかった人たちの声は「こんな努力は努力じゃない」と失敗例にされる。 夢破れた少女が涙を流しながら奥歯を噛み締めながら夢を諦めようとした時。 「あなたの夢・・・まだ捨てなくていいかも」 法律の抜け穴をついた逆転劇 - 2025年6月22日
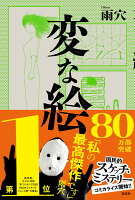 変な絵雨穴ホラーミステリー読み終わったどんでん返し単行本版を読んで文庫本も読破。 記憶がまだ鮮明だったこともありスラスラと読了。 やはり面白い。 緻密に計算された伏線。 無駄なく絡み合う登場人物それぞれの想い。 そして直美の残虐性。 何より驚いたのは、文庫本版になって追加されたオマケページが全然オマケじゃなかったこと。 フィクションと現実がグラデーションで地続きになっている感覚に陥る雨穴さんのスタイルは、本当に現実に起こった出来事として錯覚させられる。 今回のオマケページによってその「現実」っぽさをより濃厚にした。 すでに内容を知っているのに、オマケページだけでまたもや鳥肌を立てさせられるとは思わなかった。
変な絵雨穴ホラーミステリー読み終わったどんでん返し単行本版を読んで文庫本も読破。 記憶がまだ鮮明だったこともありスラスラと読了。 やはり面白い。 緻密に計算された伏線。 無駄なく絡み合う登場人物それぞれの想い。 そして直美の残虐性。 何より驚いたのは、文庫本版になって追加されたオマケページが全然オマケじゃなかったこと。 フィクションと現実がグラデーションで地続きになっている感覚に陥る雨穴さんのスタイルは、本当に現実に起こった出来事として錯覚させられる。 今回のオマケページによってその「現実」っぽさをより濃厚にした。 すでに内容を知っているのに、オマケページだけでまたもや鳥肌を立てさせられるとは思わなかった。 - 2025年6月22日
 黒猫のいる回想図書館柊サナカ読み終わった【ネタバレ大アリ】 「今日が人生最悪の日ですか?」 もし、そんなふうに黒猫に声をかけられたら、私はなんと答えるんだろうか。 主人公の千紗は「はい」と答えた。 恋人と親友に裏切られ、目の前で泣きながら土下座され、やけ酒の帰りに転倒し、靭帯を切り、倒れてる隙にバッグを盗まれ、スマホも財布も家の鍵も全部なくなる。 これ以上ないくらいどん底の真っ只中。 そんな千紗が導かれたのは、東京ドームよりもでっかい“回想図書館”。 ここで彼女は、自分の人生を一冊の本に書き上げるまで、外には出られない。 出られる出口もない。 図書館の外では時間が止まってるらしい。 図書館内は疲れなく、時間は進んでるが歳を取らない、老化もない。お腹も空かないし、睡魔もない。 そんな不思議な空間で、彼女は自分自身と向き合っていく。 この物語が面白いのは、そこに集まった人たちが「人生最悪の日に連れてこられた」という共通点はあるのに、誰一人として“ただの悲劇キャラ”ではないこと。 見た目や性格にコンプレックスを持つ人、勘違いしたままのナルシスト、自信をなくしたまま大人になった子ども。 そういう一人ひとりが、図書館の中で千紗と関わりながら、ちょっとずつ変化していく。 特に印象的だったのは、「アリス」という憎たらしくも、大人びた、どこか可愛げのある小学生の少女が実は千紗の母だったという“時間のズレ”の演出。 そう、この図書館にいる人たちは元の世界の時代が違うのだ。 そして千紗の時代よりも未来から来たというおばあちゃんが「この世界は戦争で終わる」とほのめかすシーン。 この図書館は「過去」だけでなく「未来」ともつながっていて、自分だけじゃない“時代の痛み”とも向き合わされる。そのスケール感にゾクッとした。 でも最終的に図書館から元の世界に戻ると、図書館での記憶は消えてしまう。 なのに、戻った千紗の中には何かがちゃんと残っていて、自分でも気づかないまま行動が変わっている。 「最悪な日は避けられないかもしれない。でも、自分が変われば未来は変わるかもしれない。」 この物語が見せてくれたのは、大きな奇跡じゃなくて、小さな変化の可能性だった。それでも十分。今の自分にも、ほんの少しだけ希望をくれる物語だった。
黒猫のいる回想図書館柊サナカ読み終わった【ネタバレ大アリ】 「今日が人生最悪の日ですか?」 もし、そんなふうに黒猫に声をかけられたら、私はなんと答えるんだろうか。 主人公の千紗は「はい」と答えた。 恋人と親友に裏切られ、目の前で泣きながら土下座され、やけ酒の帰りに転倒し、靭帯を切り、倒れてる隙にバッグを盗まれ、スマホも財布も家の鍵も全部なくなる。 これ以上ないくらいどん底の真っ只中。 そんな千紗が導かれたのは、東京ドームよりもでっかい“回想図書館”。 ここで彼女は、自分の人生を一冊の本に書き上げるまで、外には出られない。 出られる出口もない。 図書館の外では時間が止まってるらしい。 図書館内は疲れなく、時間は進んでるが歳を取らない、老化もない。お腹も空かないし、睡魔もない。 そんな不思議な空間で、彼女は自分自身と向き合っていく。 この物語が面白いのは、そこに集まった人たちが「人生最悪の日に連れてこられた」という共通点はあるのに、誰一人として“ただの悲劇キャラ”ではないこと。 見た目や性格にコンプレックスを持つ人、勘違いしたままのナルシスト、自信をなくしたまま大人になった子ども。 そういう一人ひとりが、図書館の中で千紗と関わりながら、ちょっとずつ変化していく。 特に印象的だったのは、「アリス」という憎たらしくも、大人びた、どこか可愛げのある小学生の少女が実は千紗の母だったという“時間のズレ”の演出。 そう、この図書館にいる人たちは元の世界の時代が違うのだ。 そして千紗の時代よりも未来から来たというおばあちゃんが「この世界は戦争で終わる」とほのめかすシーン。 この図書館は「過去」だけでなく「未来」ともつながっていて、自分だけじゃない“時代の痛み”とも向き合わされる。そのスケール感にゾクッとした。 でも最終的に図書館から元の世界に戻ると、図書館での記憶は消えてしまう。 なのに、戻った千紗の中には何かがちゃんと残っていて、自分でも気づかないまま行動が変わっている。 「最悪な日は避けられないかもしれない。でも、自分が変われば未来は変わるかもしれない。」 この物語が見せてくれたのは、大きな奇跡じゃなくて、小さな変化の可能性だった。それでも十分。今の自分にも、ほんの少しだけ希望をくれる物語だった。 - 2025年6月22日
 読み終わったビジネス書「ポケモンって、なんでこんなに夢中になれたんだろう?」 この本を読んで、その理由がスッと腑に落ちました。 通信ケーブルで交換しないと全てのポケモンが手に入らない。だから、友達と話す。対戦する。交換する。一人じゃ完結できないゲーム設計が、子どもたちの間に自然と“ポケモン文化”を生み出していった。これはもう、天才的。 しかも、発売当時はマリオやカービィみたいな有名キャラがいなかったし、プレイステーションのキラキラした映像にも負けてた。それでも勝った理由は、「捕まえる」「育てる」「交換する」っていうシンプルな遊びの面白さに全フリしたからなんだよね。 個人的にグッときたのは、「ポケモン販売システム」をあえて捨てた話。「お金で買えるなら、苦労して捕まえる意味がないでしょ?」って考えたところに、“遊び”への誠実さとプライドを感じた。 それと、「ピカチュウ」誕生秘話も好き。最初はサイドンとかニドキングみたいな怪獣ばっかりだったところに、「もっと可愛いものを」っていう女性デザイナーの感性がポンと加わって、一気に空気が変わった。固定観念を壊してくれる“異物”の存在って、本当に大事。 あと、田尻さんが「ゲームしか知らない人が作ったゲームはつまらない」って言ってたのも印象的だったな。ドラクエ2の交換できなかった悔しさ、町田市での昆虫採集の思い出、子どもの頃のワクワク。全部がポケモンに詰め込まれてるっていうのがエモすぎた。 最初の構想ではポケモンは30体しか入らなかったとか、ナッシーが社内人気1位だったとか、帯でポケモンを調教しようとしてた話とか……正直、「え、マジ!?」ってなるエピソードの連発で、読んでて楽しいし、開発の裏側を覗けたワクワクが止まらなかった。 この本は、ただのゲーム開発の記録じゃない。「どうすれば子どもがワクワクするか?」を真剣に考え抜いた大人たちの熱量と青春が詰まった物語だと思った。
読み終わったビジネス書「ポケモンって、なんでこんなに夢中になれたんだろう?」 この本を読んで、その理由がスッと腑に落ちました。 通信ケーブルで交換しないと全てのポケモンが手に入らない。だから、友達と話す。対戦する。交換する。一人じゃ完結できないゲーム設計が、子どもたちの間に自然と“ポケモン文化”を生み出していった。これはもう、天才的。 しかも、発売当時はマリオやカービィみたいな有名キャラがいなかったし、プレイステーションのキラキラした映像にも負けてた。それでも勝った理由は、「捕まえる」「育てる」「交換する」っていうシンプルな遊びの面白さに全フリしたからなんだよね。 個人的にグッときたのは、「ポケモン販売システム」をあえて捨てた話。「お金で買えるなら、苦労して捕まえる意味がないでしょ?」って考えたところに、“遊び”への誠実さとプライドを感じた。 それと、「ピカチュウ」誕生秘話も好き。最初はサイドンとかニドキングみたいな怪獣ばっかりだったところに、「もっと可愛いものを」っていう女性デザイナーの感性がポンと加わって、一気に空気が変わった。固定観念を壊してくれる“異物”の存在って、本当に大事。 あと、田尻さんが「ゲームしか知らない人が作ったゲームはつまらない」って言ってたのも印象的だったな。ドラクエ2の交換できなかった悔しさ、町田市での昆虫採集の思い出、子どもの頃のワクワク。全部がポケモンに詰め込まれてるっていうのがエモすぎた。 最初の構想ではポケモンは30体しか入らなかったとか、ナッシーが社内人気1位だったとか、帯でポケモンを調教しようとしてた話とか……正直、「え、マジ!?」ってなるエピソードの連発で、読んでて楽しいし、開発の裏側を覗けたワクワクが止まらなかった。 この本は、ただのゲーム開発の記録じゃない。「どうすれば子どもがワクワクするか?」を真剣に考え抜いた大人たちの熱量と青春が詰まった物語だと思った。 - 2025年6月22日
 ゴリラ裁判の日須藤古都離読み終わった読み終えた後に考える「ゴリラに、人権はあるのか?」 最初は思わず笑ってしまいそうになるテーマ。でも読み進めていくうちに、それがとんでもなく重くて、深くて、そして切実な問いだということに気づく。 物語の始まりは、動物園のゴリラエリアに人間の子どもが落ちてしまう事故。ローズの夫・オマリはその子を助けようとするが、結果的に「子どもを引きずった」とされて射殺される。このシーンの衝撃と理不尽さが、すべての始まり。 ローズは“ただのゴリラ”じゃない。手話と音声グローブで人と会話ができる、知性を持った存在だ。彼女が裁判で語るのは、「命に上下はない」という当たり前のようで、実は私たちが無意識に無視している価値観だ。 最初の裁判では負ける。どれだけ理屈を並べても、社会は「人間>動物」という前提を崩そうとはしない。 でも物語は終わらない。プロレス界へと舞台を移し、再びローズは「社会と戦う」道を選ぶ。そしてついに、ローズに“人権”が認められる瞬間がやってくる。 この判決はフィクションの世界の出来事だけど、読んでいて、ものすごくリアルに感じた。「ローズが勝った」という事実は、彼女が“ゴリラでありながらも、完全に“人間として見られた”証だ。 判決を経て、ローズにパスポートが発行され、ビザが与えられ、自分の生まれ育ったジャングルに帰っていくラスト──それは単なる帰郷ではなく、「物として扱われてきた存在が、自分の尊厳を取り戻す旅の終着点」でもある。 私はこの本を読んで、「命」について、「価値」について、そして「人間らしさとは何か」について、考えさせられっぱなしだった。 人間とは何か? 命に差があるのか? この世界の“当たり前”は、誰のためのものか? ローズという一頭のゴリラが、読者にそんな深い問いを突きつけてくる。 奇抜なテーマだけど、読後には何ともいえない静かな感動と、未来への希望みたいなものがじんわり残る一冊だった。
ゴリラ裁判の日須藤古都離読み終わった読み終えた後に考える「ゴリラに、人権はあるのか?」 最初は思わず笑ってしまいそうになるテーマ。でも読み進めていくうちに、それがとんでもなく重くて、深くて、そして切実な問いだということに気づく。 物語の始まりは、動物園のゴリラエリアに人間の子どもが落ちてしまう事故。ローズの夫・オマリはその子を助けようとするが、結果的に「子どもを引きずった」とされて射殺される。このシーンの衝撃と理不尽さが、すべての始まり。 ローズは“ただのゴリラ”じゃない。手話と音声グローブで人と会話ができる、知性を持った存在だ。彼女が裁判で語るのは、「命に上下はない」という当たり前のようで、実は私たちが無意識に無視している価値観だ。 最初の裁判では負ける。どれだけ理屈を並べても、社会は「人間>動物」という前提を崩そうとはしない。 でも物語は終わらない。プロレス界へと舞台を移し、再びローズは「社会と戦う」道を選ぶ。そしてついに、ローズに“人権”が認められる瞬間がやってくる。 この判決はフィクションの世界の出来事だけど、読んでいて、ものすごくリアルに感じた。「ローズが勝った」という事実は、彼女が“ゴリラでありながらも、完全に“人間として見られた”証だ。 判決を経て、ローズにパスポートが発行され、ビザが与えられ、自分の生まれ育ったジャングルに帰っていくラスト──それは単なる帰郷ではなく、「物として扱われてきた存在が、自分の尊厳を取り戻す旅の終着点」でもある。 私はこの本を読んで、「命」について、「価値」について、そして「人間らしさとは何か」について、考えさせられっぱなしだった。 人間とは何か? 命に差があるのか? この世界の“当たり前”は、誰のためのものか? ローズという一頭のゴリラが、読者にそんな深い問いを突きつけてくる。 奇抜なテーマだけど、読後には何ともいえない静かな感動と、未来への希望みたいなものがじんわり残る一冊だった。 - 2025年6月18日
- 2025年6月18日
 マンガでカンタン!SNSマーケティングは7日間でわかります。こしいみほ,坂本翔読み終わったビジネス書YouTubeやTikTok、Instagramでマーケティングと検索したら、多くの人が投稿している。それを見ていたら嫌でも聞いたことがあるもの。それらを体系的にまとめたのが本書という感じ。 目新しさはない。が、復習として目を通す分にはとても分かりやすい。 「7日間」とあるが、単元ごとに7つに分けただけ。読もうと思えば、1〜2日で読める。 複雑ではないので、ざっくり知りたい、本格的に学ぶ前に全体像を知っておきたいなどに丁度いい一冊。
マンガでカンタン!SNSマーケティングは7日間でわかります。こしいみほ,坂本翔読み終わったビジネス書YouTubeやTikTok、Instagramでマーケティングと検索したら、多くの人が投稿している。それを見ていたら嫌でも聞いたことがあるもの。それらを体系的にまとめたのが本書という感じ。 目新しさはない。が、復習として目を通す分にはとても分かりやすい。 「7日間」とあるが、単元ごとに7つに分けただけ。読もうと思えば、1〜2日で読める。 複雑ではないので、ざっくり知りたい、本格的に学ぶ前に全体像を知っておきたいなどに丁度いい一冊。 - 2025年6月9日
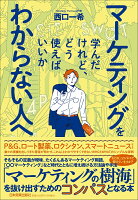 読み終わったビジネス書◆マーケティングツールは今や9,900以上 Shopify、Apple、Facebookなどをはじめとする、マーケティングツールとしても活用できるアプリやサイトなどのツールのこと。 樹海すぎる。 何をどう使ったらいいか分からなさすぎる。 ◆本書でのマーケティングの定義 お客座のニーズを洞察し、おきゃく様が価値を見出すプロダクトを生み出すこと。その価値を高め続けて継続的な収益化を再投資して新たな価値を作り続けること。 ◆誰がなぜ買ってくれたのか? ◯◯を求めてぜひ買いたいと考える人たちが買えるような組み合わせやチャネルはどんなものか? ◆価値とは? 「便益」と「独自性」の両方を併せ持つもの。 ◆便益 それを買う(選ぶ)理由 お客様にとって良いこと、利便性、快楽、問題解決、負の解消 ◆独自性 ほかを買わない(選ばない)理由 競合や代替プロダクトにはない要素 山歩きをしていて山奥の商店で仮に200円でミネラルウォーターが売ってあったら? 高ぇと感じつつも、他に店がない……。じゃあもう買うしかないやん。 「水で喉を潤せる」が便益で、「他には売ってない」が独自性になる。 ◆便益と独自性を「自分ごと化」できたときに、お客様は価値を見出す ◆お客様を理解するなら「N1分析」 1人のお客座に対して、 ・その商品を買ったきっかけ ・買った際にどう感じたのか ・なぜその商品を買ったのか ・なぜ購買を続けているのか を時系列で掘り下げていくことで、購買行動の裏にある深層心理(インサイト)を理解する。 これは架空の人物(ペルソナ)ではない。 ◆1人を徹底的に理解すること無駄じゃない 著者は約30年間マーケティングに関わってきて、1人の分析結果から見つけ出した便益と独自性が他の人に全く当てはまらない事例を見たことがない。 ◆大勢の意見を聞くと、平均値しか見えない。結局当たり障りのない、どこの企業もやっているような施作が多くなってしまう。
読み終わったビジネス書◆マーケティングツールは今や9,900以上 Shopify、Apple、Facebookなどをはじめとする、マーケティングツールとしても活用できるアプリやサイトなどのツールのこと。 樹海すぎる。 何をどう使ったらいいか分からなさすぎる。 ◆本書でのマーケティングの定義 お客座のニーズを洞察し、おきゃく様が価値を見出すプロダクトを生み出すこと。その価値を高め続けて継続的な収益化を再投資して新たな価値を作り続けること。 ◆誰がなぜ買ってくれたのか? ◯◯を求めてぜひ買いたいと考える人たちが買えるような組み合わせやチャネルはどんなものか? ◆価値とは? 「便益」と「独自性」の両方を併せ持つもの。 ◆便益 それを買う(選ぶ)理由 お客様にとって良いこと、利便性、快楽、問題解決、負の解消 ◆独自性 ほかを買わない(選ばない)理由 競合や代替プロダクトにはない要素 山歩きをしていて山奥の商店で仮に200円でミネラルウォーターが売ってあったら? 高ぇと感じつつも、他に店がない……。じゃあもう買うしかないやん。 「水で喉を潤せる」が便益で、「他には売ってない」が独自性になる。 ◆便益と独自性を「自分ごと化」できたときに、お客様は価値を見出す ◆お客様を理解するなら「N1分析」 1人のお客座に対して、 ・その商品を買ったきっかけ ・買った際にどう感じたのか ・なぜその商品を買ったのか ・なぜ購買を続けているのか を時系列で掘り下げていくことで、購買行動の裏にある深層心理(インサイト)を理解する。 これは架空の人物(ペルソナ)ではない。 ◆1人を徹底的に理解すること無駄じゃない 著者は約30年間マーケティングに関わってきて、1人の分析結果から見つけ出した便益と独自性が他の人に全く当てはまらない事例を見たことがない。 ◆大勢の意見を聞くと、平均値しか見えない。結局当たり障りのない、どこの企業もやっているような施作が多くなってしまう。 - 2025年6月5日
 准教授・高槻彰良の推察EX3(14)澤村御影,鈴木次郎ミステリー読み終わった11巻で語られる舞台裏の話。 高槻や深町が奮闘している裏で佐々倉と海野はなぜ樹海にいたのか。深町や高槻が合宿から抜け出し、得体の知れない何かと戦っている間、難波はどんな気持ちで見守っていたのか。 11巻を読み終わったら間隔を空けずに読んで欲しい1冊。
准教授・高槻彰良の推察EX3(14)澤村御影,鈴木次郎ミステリー読み終わった11巻で語られる舞台裏の話。 高槻や深町が奮闘している裏で佐々倉と海野はなぜ樹海にいたのか。深町や高槻が合宿から抜け出し、得体の知れない何かと戦っている間、難波はどんな気持ちで見守っていたのか。 11巻を読み終わったら間隔を空けずに読んで欲しい1冊。 - 2025年6月3日
 准教授・高槻彰良の推察11 夏の終わりに呼ぶ声澤村御影,鈴木次郎ミステリー読み終わった【大ネタバレあり】 第1章 影の病 テニスサークルに所属している女子生徒の一人一華が相談しに来た。自分のドッペルゲンガーを最近よく見た周囲に言われるんだそう。聞くとテニスサークル内でも一華のドッペルゲンガーを見たという声が上がる。犯人は同じテニスサークルの部長で一華のいとこである弓華だった。見た目の雰囲気は真逆だが、骨格は非常に似ている。弓華は彼氏を一華に取られたことを恨んでいた。でも性格や容姿が真逆である一華への憧れもあった。メイクの方法を勉強して弓華に変装したら、なんだか自分の殻が抜けたみたいになって、渋谷や表参道などを練り歩いてたらサークルの仲間にみられたらしい。でもバレずにドッペルゲンガーとして騒がれてしまったようだ。 第2章 入ってはならない場所 ゼミ合宿で青木ヶ原樹海の近くのホテルをゼミ生全員で借りることに。 二日目の自由行動の時に樹海の中を探検したいと言い出す高槻先生。 樹海は自殺の名所として有名になってしまったけど、観光地としても有名。 樹海の中を散策してたら、樹海の中から何やら怪しげな”何か”の存在を敏感に感じ取ってしまう。そこには古来より”何か”がずっと眠っていたが、近年のSNSのせいでYouTuberなどの配信者がフォロワー欲しさに、立入禁止区域にガンガン入っていき、領域を犯したことで、”何か”は目覚めてしまったそう。樹海に入った人が次々に行方不明になる事件が続出していた。八百比丘尼である海野紗絵がその”何か”を鎮めるために、健ちゃんと樹海に来ていたところ、偶然高槻先生らと遭遇した。海野紗絵が自分を生贄に捧げる(”何か”が満足するまで復活を繰り返し何度も食べられる)ことで、”何か”は再び眠りに入った。 第3章 夜との約束 高槻先生が12歳の頃に1ヶ月間突如行方不明になって、無傷のまま道路で眠っているのを発見された鞍馬山の道路を見に行くことになった尚哉、高槻先生、健ちゃんの3人。せっかくだからそのまま観光しようという流れになった。高槻先生の推理だと自分のおじいちゃんが真実を知っているのではないか?とのこと。高槻先生のいとこである優斗に相談しておじいちゃんのいる別荘を調べてもらっていた。すると突如、優斗からおじいちゃんが亡くなったという連絡が入ってしまう。
准教授・高槻彰良の推察11 夏の終わりに呼ぶ声澤村御影,鈴木次郎ミステリー読み終わった【大ネタバレあり】 第1章 影の病 テニスサークルに所属している女子生徒の一人一華が相談しに来た。自分のドッペルゲンガーを最近よく見た周囲に言われるんだそう。聞くとテニスサークル内でも一華のドッペルゲンガーを見たという声が上がる。犯人は同じテニスサークルの部長で一華のいとこである弓華だった。見た目の雰囲気は真逆だが、骨格は非常に似ている。弓華は彼氏を一華に取られたことを恨んでいた。でも性格や容姿が真逆である一華への憧れもあった。メイクの方法を勉強して弓華に変装したら、なんだか自分の殻が抜けたみたいになって、渋谷や表参道などを練り歩いてたらサークルの仲間にみられたらしい。でもバレずにドッペルゲンガーとして騒がれてしまったようだ。 第2章 入ってはならない場所 ゼミ合宿で青木ヶ原樹海の近くのホテルをゼミ生全員で借りることに。 二日目の自由行動の時に樹海の中を探検したいと言い出す高槻先生。 樹海は自殺の名所として有名になってしまったけど、観光地としても有名。 樹海の中を散策してたら、樹海の中から何やら怪しげな”何か”の存在を敏感に感じ取ってしまう。そこには古来より”何か”がずっと眠っていたが、近年のSNSのせいでYouTuberなどの配信者がフォロワー欲しさに、立入禁止区域にガンガン入っていき、領域を犯したことで、”何か”は目覚めてしまったそう。樹海に入った人が次々に行方不明になる事件が続出していた。八百比丘尼である海野紗絵がその”何か”を鎮めるために、健ちゃんと樹海に来ていたところ、偶然高槻先生らと遭遇した。海野紗絵が自分を生贄に捧げる(”何か”が満足するまで復活を繰り返し何度も食べられる)ことで、”何か”は再び眠りに入った。 第3章 夜との約束 高槻先生が12歳の頃に1ヶ月間突如行方不明になって、無傷のまま道路で眠っているのを発見された鞍馬山の道路を見に行くことになった尚哉、高槻先生、健ちゃんの3人。せっかくだからそのまま観光しようという流れになった。高槻先生の推理だと自分のおじいちゃんが真実を知っているのではないか?とのこと。高槻先生のいとこである優斗に相談しておじいちゃんのいる別荘を調べてもらっていた。すると突如、優斗からおじいちゃんが亡くなったという連絡が入ってしまう。 - 2025年5月18日
 イデアの再臨五条紀夫ミステリー読み終わったどんでん返し【大ネタバレあり】 朝起きたら「窓」が無くなっていた。文章からも消滅しており、空白となっている。前後の文脈からしておそらく消えたのは「窓」。 もともと「窓」があった場所は、窓の形と外枠ごと消滅しており、大きな四角い穴になっていた。他の家々も同じく消滅している。 同じことが「扉」にも起きていた。 これも文章から消滅しており該当箇所は空白になっている。 「玄関」は記載されてあったから消滅したのは「ドア」か「扉」だと推測できる。ここもただの四角い穴となっていた。家の鍵を持っていてももはや意味をなさない。 通学路では、どこの家庭も四角い穴から生活が丸見えの状態。 それがあった痕跡があるのに、なくなったことに誰も違和感を覚えていない様子。主人公だけがこの違和感に気づいていた。 校門を通り過ぎた所で「塀」が消滅していることに気づく。やはりここも空白となっている。 校門を通過する前はあったのに、通過したら一瞬で視界から消滅した。 下駄箱のある所に行くと「扉」がない。かつて貼られていたであろう「冷房中、開放厳禁」のポスターが落ちていた。 近くにいた別の生徒に、何を開放してはいけないのか聞くとズボンのチャックとか言い出す始末。そんなわけないだろう。 その後も「スリッパ」「雨」「くぼみ」「校門」「フェンス」が消されたことに気づく。 ここまでで消されたのは窓、扉、塀、スリッパ、雨、くぼみ、フェンスの7つ。なんとなく「外部からの侵入をふせぐ系」が比重高く消えている気がする。 そこで隣のクラスに転入してきた安藤という男子生徒に「お前が消したんじゃないのか?」と指摘をされてしまう。 そして、安藤はさらに不思議なことを言い出す。 ここは小説の中の世界だ。自分たちは登場人物であることをメタ的に認識しているというのだ。 次元の異なる世界線が別で存在していることを認識している主人公「僕」と「安藤」。 小説で当たり前に描写される空行。 どこかへ行く、何かをする際に空行を挟むと実行が完了されていることも認識していた。 また、主人公が「安藤くん」と呼び捨てにできず、「呼び捨てにしろ」「いや、だってさぁ」のくだりについては、主人公が呼び捨てに納得するまでの面倒臭いやりとりを「中略」で省略する技法を本人たちが理解した上で使用していた。 その後も自分たちが小説内の登場人物であり、世界が文章で作られていること、そしてその小説を読む読者が小説の外に存在していることを十分に理解した上で、物語が進む。 自分たちが今何ページにいるのかも理解していた。 小説でよく用いられる表現技法。 間を取るためや、何かを暗示するのに用いられる「・・・・」や、「|」をメタ的に認知した上で小道具として使用していた。 登場人物にはそれぞれスキルがあることも判明する。 物語を盛り上げるために必須となる登場人物は、その物語のジャンルにおける立ち位置を自然に振る舞うように設定されている。 例えば、主人公の幼馴染の場合、だいたいは美少女だし美少女たる振る舞いをする。番長は番長っぽい立ち振る舞いをして主人公にウザ絡みするし、びんぞこ眼鏡をかけてたら秀才だし、主人公といえば、凡人だ。 全ての登場人物たちは、自分たちが小説の中の登場人物だとは認識していない。 でもメタ的に認識している人がいる。それが、主人公と安藤だ。 そして、認識している人物は何かしらのスキルがあることも分かった。 安藤はページを戻すことができる。 具体的には「○ページ戻れ」と安藤が言えば、その次の行は戻ったページに書かれてある文章がそっくりそのまま記される。だからなに?と言われたらそれまでだが。 そして主人公は、まだなんのスキルがあるのか分かってない。 ということは、物語の最初からたびたび起きている物が消失する現象も、誰かのスキルだというのだ。 この、モノを消滅させている犯人を探すのが、当面の目的になった。 小説でありがちな展開は、その後のストーリーを予感させる。 読者を次のページに誘うための表現だ。 「誰かの視線を感じる」は、実は犯人が近くにいたことを予感させる。 そういう小説にありがちな展開を逆手に取り、2人は都会へと足を運ぶ。 イベントが行われる様な場所では物語の都合上、犯人と会合する確率が高いのだと安藤は言う。 確かに。 そして、2人の予想は当たる。が、予想以上のことが起きてしまった。 犯人が都会の大型ビジョンをジャックし、2人に話しかけてきたのだ。 「かつて人類の魂は、天井の世界で、あらゆる事象の理想である、イデアのみを見ていたが、地上の世界に追放され、肉体という牢獄に閉じ込められたいま、人類はイデアを見ることができなくなってしまった。物体や言葉による定義でイデアの偽物。この偽物の外面さえなくなれば、人類は再びイデアに相まみえることができる」 思想強めの犯人。 すると犯人は突如この世から車輪を消滅させた。 車、バイク、電車など、車輪が付いている全ての乗り物が身の回りでスピードを制御出来なくなり、家屋に突っ込み、人をすりつぶし、体が散っていった。電車は脱線し、扉から大勢の人を吐き出しながら火花をあげる。 惨劇の連鎖、地獄絵図。 この日世界中で何億もの人が亡くなった。 ニュースでは亡くなったのは推定8億人だという。この8億人という数字は、主人公がネットニュースを調べて浮上した数字だ。主人公が思考やセリフとして出力した瞬間に確定する。 文章でできた世界である以上、書かれていないことは曖昧なままだ。 主人公が認識しなければ文章として出力されないので、確定されない。 つまり、車輪を消して大惨事を起こしたのは犯人だが、仮にその瞬間、主人公が目を瞑るなどして情報を遮断すれば惨劇は文章になりえない。文章にならなければ確定しない。8億人もの人が亡くなることはなかったかもしれなかった。 犯人も憎いが、自分に対しても激しい後悔がのしかかる。 安藤は言う。ページを戻すというスキルだけでは、犯人のスキルには対抗できない。 だから、主人公にも何かしらのスキルに目覚める必要があると。 そこで、主人公が強く望んだのは人が多く亡くなった過去を、過去を書き換えたいと。 しかし、文章の世界では一度出力されて、確定したものを書き変えることはできない。 が、安藤は閃く。 安藤はスキルを使ってページを戻した。そして判明した。 主人公のスキルは「加筆」だった。 すでに出力された文章を改変することはできないが、安藤のページを戻すスキルと合わせれば、過去の文章に加筆し、流れを変えることができる。 犯人に対抗しうるスキルが発現した。 しかし、さらに犯人の追い打ちがあった。 今までは名詞のみの消滅だったが、第二章に入ってからスキルのレベルがあがったのか、事象も消滅したことに気づいた。 「待ち合わせ」が消滅ていたからだ。 主人公と安藤は新たに発現したスキルの有効性を実験しようと待ち合わせをしたが、目的地に永遠に辿り着けなかったのだ。 確実に歩いているのに、待ち合わせ場所に辿り着けない。 だが、待ち合わせじゃなくばったり会うことはできる様で学校では通常通り安藤と会うことができた。 そこで安藤が事象が消えていることに気づいたのだ。それは、第二章のタイトルが「事象が消えゆく世界」だったからだ。 犯人はまだ自分のスキルの全容を完全に把握できていない。どこまでが消えて、どこまでが消えないのか。消した名詞や事象はどこまで影響を及ぼすのか。実験を繰り返しているのが作中でも見て取れる。 学校に着いてからも本人による実験は続く。 一人称の「私」や「俺」などが消滅した。登場人物のキャラクターを際立たせる記号として使われる一人称。当然一人称が変わればそれに引っ張られたキャラに改変されてしまう。一人称が変わったクラスメイトの性格や喋り方が一人称に引っ張られて変化していた。 授業が始まる直前「先生」が消滅した。先生という職業が消滅したため、目の前に立っていた先生だった山崎は、「教師:山崎」から「無職:山崎」になった。先生として教室に入った瞬間無職になり、先生という概念すら消えたため、自分がなぜここのいるか分からず混乱する山崎。 その後「山崎」が消滅した。犯人はとうとう山崎個人を消滅させたのだ。 犯人はこの学校の生徒だ。 そう思って安藤と手分けをして探そうと動き出した時、「授業」と「生徒」が消えた。「生徒」という概念が消滅した今、教室にいる理由がない。同世代の男女が一斉に教室から吐き出され、廊下が人で溢れかえってしまった。 しかし、安藤と主人公のスキルによりページは戻り、加筆することで「授業」と「生徒」という言葉を復活させることに成功する。 学校があれば、自然な形で安藤と出会うことができるため「待ち合わせ」が消滅しても何とかなるからだ。 その後も地道な推理や情報収集に勤しむが進捗は芳しくない。 主人公は気づいた。一人称が次々に消滅し、キャラクターの個性が変化していく中、「僕」という一人称だけは依然として残ったままだったことに。 小説の世界で「僕」という一人称を使っているのは、主人公と生徒会長の真島実直の2人だけだったのだ。 「僕」を消滅させてしまうと、消滅していない一人称を代用するしかなくなり、使用する一人称に合わせて不必要な個性変化が起きてしまうからだ。必要だから消滅しなかったのだ。 真島はもともと名前すら存在しないモブキャラだったが、本物の真島実直が登場する前に、自ら「生徒会長、真島実直」と名乗ることで、物語上に必要なキャラクターをある意味乗っ取っていた。生まれてきたことに意味があり、自分の意思で自由に行動できる存在でありたかったのだ。 小説という特性上、ジャンルに沿った物語を展開しないといけないし、本の帯に「どんでん返し」と記載されていたら、どんでん返さなければいけない。 物語を進行させるための歯車にならないといけないことがすごく嫌だった。 真島は本を読んでいる読者をメタ的に名指しし、「お前みたいになりたいんだ」と文章の中で訴えた。 真島はこんな世界なくなって仕舞えばいいと「世界消えろ」と言うと、その後数ページにわたり、何も記載されていない白紙が続いた。 しかし、主人公は消えていなかった。 ここまで主人公の名前は一度も出てきていなかったが、判明する。 主人公の名前は「イデア」だった。 この本のタイトルは「イデアの再臨」。 本のタイトルが「イデアの再臨」である以上、主人公の「イデア」は何度でも再臨する。 チートスキルの真島でも、消すことはできないのだ。 真島は再び文章が記載されたページで、敗北を認めた。 そして、こんなことになるならと「メンタ認知」を消すとイデアと約束する。 ここまでの物語で消えたモノは全て復活。 この本の物語は幕を閉じた。
イデアの再臨五条紀夫ミステリー読み終わったどんでん返し【大ネタバレあり】 朝起きたら「窓」が無くなっていた。文章からも消滅しており、空白となっている。前後の文脈からしておそらく消えたのは「窓」。 もともと「窓」があった場所は、窓の形と外枠ごと消滅しており、大きな四角い穴になっていた。他の家々も同じく消滅している。 同じことが「扉」にも起きていた。 これも文章から消滅しており該当箇所は空白になっている。 「玄関」は記載されてあったから消滅したのは「ドア」か「扉」だと推測できる。ここもただの四角い穴となっていた。家の鍵を持っていてももはや意味をなさない。 通学路では、どこの家庭も四角い穴から生活が丸見えの状態。 それがあった痕跡があるのに、なくなったことに誰も違和感を覚えていない様子。主人公だけがこの違和感に気づいていた。 校門を通り過ぎた所で「塀」が消滅していることに気づく。やはりここも空白となっている。 校門を通過する前はあったのに、通過したら一瞬で視界から消滅した。 下駄箱のある所に行くと「扉」がない。かつて貼られていたであろう「冷房中、開放厳禁」のポスターが落ちていた。 近くにいた別の生徒に、何を開放してはいけないのか聞くとズボンのチャックとか言い出す始末。そんなわけないだろう。 その後も「スリッパ」「雨」「くぼみ」「校門」「フェンス」が消されたことに気づく。 ここまでで消されたのは窓、扉、塀、スリッパ、雨、くぼみ、フェンスの7つ。なんとなく「外部からの侵入をふせぐ系」が比重高く消えている気がする。 そこで隣のクラスに転入してきた安藤という男子生徒に「お前が消したんじゃないのか?」と指摘をされてしまう。 そして、安藤はさらに不思議なことを言い出す。 ここは小説の中の世界だ。自分たちは登場人物であることをメタ的に認識しているというのだ。 次元の異なる世界線が別で存在していることを認識している主人公「僕」と「安藤」。 小説で当たり前に描写される空行。 どこかへ行く、何かをする際に空行を挟むと実行が完了されていることも認識していた。 また、主人公が「安藤くん」と呼び捨てにできず、「呼び捨てにしろ」「いや、だってさぁ」のくだりについては、主人公が呼び捨てに納得するまでの面倒臭いやりとりを「中略」で省略する技法を本人たちが理解した上で使用していた。 その後も自分たちが小説内の登場人物であり、世界が文章で作られていること、そしてその小説を読む読者が小説の外に存在していることを十分に理解した上で、物語が進む。 自分たちが今何ページにいるのかも理解していた。 小説でよく用いられる表現技法。 間を取るためや、何かを暗示するのに用いられる「・・・・」や、「|」をメタ的に認知した上で小道具として使用していた。 登場人物にはそれぞれスキルがあることも判明する。 物語を盛り上げるために必須となる登場人物は、その物語のジャンルにおける立ち位置を自然に振る舞うように設定されている。 例えば、主人公の幼馴染の場合、だいたいは美少女だし美少女たる振る舞いをする。番長は番長っぽい立ち振る舞いをして主人公にウザ絡みするし、びんぞこ眼鏡をかけてたら秀才だし、主人公といえば、凡人だ。 全ての登場人物たちは、自分たちが小説の中の登場人物だとは認識していない。 でもメタ的に認識している人がいる。それが、主人公と安藤だ。 そして、認識している人物は何かしらのスキルがあることも分かった。 安藤はページを戻すことができる。 具体的には「○ページ戻れ」と安藤が言えば、その次の行は戻ったページに書かれてある文章がそっくりそのまま記される。だからなに?と言われたらそれまでだが。 そして主人公は、まだなんのスキルがあるのか分かってない。 ということは、物語の最初からたびたび起きている物が消失する現象も、誰かのスキルだというのだ。 この、モノを消滅させている犯人を探すのが、当面の目的になった。 小説でありがちな展開は、その後のストーリーを予感させる。 読者を次のページに誘うための表現だ。 「誰かの視線を感じる」は、実は犯人が近くにいたことを予感させる。 そういう小説にありがちな展開を逆手に取り、2人は都会へと足を運ぶ。 イベントが行われる様な場所では物語の都合上、犯人と会合する確率が高いのだと安藤は言う。 確かに。 そして、2人の予想は当たる。が、予想以上のことが起きてしまった。 犯人が都会の大型ビジョンをジャックし、2人に話しかけてきたのだ。 「かつて人類の魂は、天井の世界で、あらゆる事象の理想である、イデアのみを見ていたが、地上の世界に追放され、肉体という牢獄に閉じ込められたいま、人類はイデアを見ることができなくなってしまった。物体や言葉による定義でイデアの偽物。この偽物の外面さえなくなれば、人類は再びイデアに相まみえることができる」 思想強めの犯人。 すると犯人は突如この世から車輪を消滅させた。 車、バイク、電車など、車輪が付いている全ての乗り物が身の回りでスピードを制御出来なくなり、家屋に突っ込み、人をすりつぶし、体が散っていった。電車は脱線し、扉から大勢の人を吐き出しながら火花をあげる。 惨劇の連鎖、地獄絵図。 この日世界中で何億もの人が亡くなった。 ニュースでは亡くなったのは推定8億人だという。この8億人という数字は、主人公がネットニュースを調べて浮上した数字だ。主人公が思考やセリフとして出力した瞬間に確定する。 文章でできた世界である以上、書かれていないことは曖昧なままだ。 主人公が認識しなければ文章として出力されないので、確定されない。 つまり、車輪を消して大惨事を起こしたのは犯人だが、仮にその瞬間、主人公が目を瞑るなどして情報を遮断すれば惨劇は文章になりえない。文章にならなければ確定しない。8億人もの人が亡くなることはなかったかもしれなかった。 犯人も憎いが、自分に対しても激しい後悔がのしかかる。 安藤は言う。ページを戻すというスキルだけでは、犯人のスキルには対抗できない。 だから、主人公にも何かしらのスキルに目覚める必要があると。 そこで、主人公が強く望んだのは人が多く亡くなった過去を、過去を書き換えたいと。 しかし、文章の世界では一度出力されて、確定したものを書き変えることはできない。 が、安藤は閃く。 安藤はスキルを使ってページを戻した。そして判明した。 主人公のスキルは「加筆」だった。 すでに出力された文章を改変することはできないが、安藤のページを戻すスキルと合わせれば、過去の文章に加筆し、流れを変えることができる。 犯人に対抗しうるスキルが発現した。 しかし、さらに犯人の追い打ちがあった。 今までは名詞のみの消滅だったが、第二章に入ってからスキルのレベルがあがったのか、事象も消滅したことに気づいた。 「待ち合わせ」が消滅ていたからだ。 主人公と安藤は新たに発現したスキルの有効性を実験しようと待ち合わせをしたが、目的地に永遠に辿り着けなかったのだ。 確実に歩いているのに、待ち合わせ場所に辿り着けない。 だが、待ち合わせじゃなくばったり会うことはできる様で学校では通常通り安藤と会うことができた。 そこで安藤が事象が消えていることに気づいたのだ。それは、第二章のタイトルが「事象が消えゆく世界」だったからだ。 犯人はまだ自分のスキルの全容を完全に把握できていない。どこまでが消えて、どこまでが消えないのか。消した名詞や事象はどこまで影響を及ぼすのか。実験を繰り返しているのが作中でも見て取れる。 学校に着いてからも本人による実験は続く。 一人称の「私」や「俺」などが消滅した。登場人物のキャラクターを際立たせる記号として使われる一人称。当然一人称が変わればそれに引っ張られたキャラに改変されてしまう。一人称が変わったクラスメイトの性格や喋り方が一人称に引っ張られて変化していた。 授業が始まる直前「先生」が消滅した。先生という職業が消滅したため、目の前に立っていた先生だった山崎は、「教師:山崎」から「無職:山崎」になった。先生として教室に入った瞬間無職になり、先生という概念すら消えたため、自分がなぜここのいるか分からず混乱する山崎。 その後「山崎」が消滅した。犯人はとうとう山崎個人を消滅させたのだ。 犯人はこの学校の生徒だ。 そう思って安藤と手分けをして探そうと動き出した時、「授業」と「生徒」が消えた。「生徒」という概念が消滅した今、教室にいる理由がない。同世代の男女が一斉に教室から吐き出され、廊下が人で溢れかえってしまった。 しかし、安藤と主人公のスキルによりページは戻り、加筆することで「授業」と「生徒」という言葉を復活させることに成功する。 学校があれば、自然な形で安藤と出会うことができるため「待ち合わせ」が消滅しても何とかなるからだ。 その後も地道な推理や情報収集に勤しむが進捗は芳しくない。 主人公は気づいた。一人称が次々に消滅し、キャラクターの個性が変化していく中、「僕」という一人称だけは依然として残ったままだったことに。 小説の世界で「僕」という一人称を使っているのは、主人公と生徒会長の真島実直の2人だけだったのだ。 「僕」を消滅させてしまうと、消滅していない一人称を代用するしかなくなり、使用する一人称に合わせて不必要な個性変化が起きてしまうからだ。必要だから消滅しなかったのだ。 真島はもともと名前すら存在しないモブキャラだったが、本物の真島実直が登場する前に、自ら「生徒会長、真島実直」と名乗ることで、物語上に必要なキャラクターをある意味乗っ取っていた。生まれてきたことに意味があり、自分の意思で自由に行動できる存在でありたかったのだ。 小説という特性上、ジャンルに沿った物語を展開しないといけないし、本の帯に「どんでん返し」と記載されていたら、どんでん返さなければいけない。 物語を進行させるための歯車にならないといけないことがすごく嫌だった。 真島は本を読んでいる読者をメタ的に名指しし、「お前みたいになりたいんだ」と文章の中で訴えた。 真島はこんな世界なくなって仕舞えばいいと「世界消えろ」と言うと、その後数ページにわたり、何も記載されていない白紙が続いた。 しかし、主人公は消えていなかった。 ここまで主人公の名前は一度も出てきていなかったが、判明する。 主人公の名前は「イデア」だった。 この本のタイトルは「イデアの再臨」。 本のタイトルが「イデアの再臨」である以上、主人公の「イデア」は何度でも再臨する。 チートスキルの真島でも、消すことはできないのだ。 真島は再び文章が記載されたページで、敗北を認めた。 そして、こんなことになるならと「メンタ認知」を消すとイデアと約束する。 ここまでの物語で消えたモノは全て復活。 この本の物語は幕を閉じた。 - 2025年5月11日
 読み終わった自己啓発「仕事の本質」という副題がついているせいで小難しい本かと思ったがそんなことはない。 今やマーケターの顔として大成功している森岡さんが、自分の失敗談を赤裸々に語り、「だから大丈夫だよ」と元気をくれる応援本だと感じた。 若い頃に受けた職場でのイジメに苦しみ、血尿が出ることは当たり前。 「鮮やかな色の血尿だ」と半ば狂った状態になりながらも会社では弱った姿を見せず平気なフリをして仕事をする。 毎朝頭から布団をかぶって「会社に行きたくない、行きたくない、行きたくない」と時間ギリギリまで嘆いていたことも書かれている。 ここまで経験したからこそ見えてくる森岡さんの「仕事ってこんなんだよ」という考え方を娘宛に書いた手紙がこの本のスタンスだ。 この本を読んで感じたことは「森岡さんに比べたら今の自分の悩みなんて小さい」と思えることかもしれない。 目の前で素人がプロボクサーに血だるまになるまでボコボコに殴られているのを見ると、自分がゲンコツを1発喰らって「痛ーい」と言ってることが小さく見えてくる感覚。 アレよりはマシって否が応でも思わされる。 この本ではタイトルと同じ名を冠した「苦しかった時の話をしようか」を読むだけでも十分に価値がある。 今の仕事が苦しいとき、自分の価値が見えなくなってるとき、逃げ出したいとき、世界が小さく見えてしまう。自分が一番不幸で苦しいと思えてしまう。そんな時にそっと隣に血だるまになった森岡さんが座ってきて「だ…大丈夫だ…だよ。えへへ。君は充分に……頑張ってるから…ね」と励ましてもらったら「あ、もう少し頑張れるわ」と思える。 この本はそんな応援本だ。
読み終わった自己啓発「仕事の本質」という副題がついているせいで小難しい本かと思ったがそんなことはない。 今やマーケターの顔として大成功している森岡さんが、自分の失敗談を赤裸々に語り、「だから大丈夫だよ」と元気をくれる応援本だと感じた。 若い頃に受けた職場でのイジメに苦しみ、血尿が出ることは当たり前。 「鮮やかな色の血尿だ」と半ば狂った状態になりながらも会社では弱った姿を見せず平気なフリをして仕事をする。 毎朝頭から布団をかぶって「会社に行きたくない、行きたくない、行きたくない」と時間ギリギリまで嘆いていたことも書かれている。 ここまで経験したからこそ見えてくる森岡さんの「仕事ってこんなんだよ」という考え方を娘宛に書いた手紙がこの本のスタンスだ。 この本を読んで感じたことは「森岡さんに比べたら今の自分の悩みなんて小さい」と思えることかもしれない。 目の前で素人がプロボクサーに血だるまになるまでボコボコに殴られているのを見ると、自分がゲンコツを1発喰らって「痛ーい」と言ってることが小さく見えてくる感覚。 アレよりはマシって否が応でも思わされる。 この本ではタイトルと同じ名を冠した「苦しかった時の話をしようか」を読むだけでも十分に価値がある。 今の仕事が苦しいとき、自分の価値が見えなくなってるとき、逃げ出したいとき、世界が小さく見えてしまう。自分が一番不幸で苦しいと思えてしまう。そんな時にそっと隣に血だるまになった森岡さんが座ってきて「だ…大丈夫だ…だよ。えへへ。君は充分に……頑張ってるから…ね」と励ましてもらったら「あ、もう少し頑張れるわ」と思える。 この本はそんな応援本だ。 - 2025年5月7日
 ある閉ざされた雪の山荘で東野圭吾ミステリー読み終わったどんでん返し【ネタバレ大アリ】 東郷陣平(以降東郷先生)という奇天烈な脚本家がいた。 東郷先生が主催するオーディションに応募し、見事合格を勝ち取った7人の若い舞台役者たち。 7人のうち6人はオーディション以前から見知った仲で、残り1人はオーディション合格後に6人に合流したある意味新参者の久我和幸。 東郷先生の計らいで、彼らは山奥の山荘を4日間貸し切り、過ごすこととなった。 東郷先生曰く、次回作の脚本や演出に反映させるため、演技の練習を実践で積ませようというもの。 山荘での4日間は、東郷先生の設定した状況にあわせて様々な事が起きる。 その出来事に役者として臨機応変に対応してほしいとのことだった。 設定は、山荘の外は記録的な大雪、電話線は切られており、スマホも圏外、オーナーも外出してから帰ってこない、山荘は自然が作り出したクローズドサークルになってしまった。そこで、次々と殺人が行われるというものだ。 しかし、これはあくまでも設定なので、実際は日差しも暖かく、キャンプにはもってこいの晴天だし、山荘の目の前にはバス停があるので外出は可能だし、電話も問題なく通じる。 だが、あくまでもクローズドサークルという設定だと認識した上で、演じていくことが今回7人に与えられたミッションだった。 ◆登場人物 ・笠原温子 ピアノめっちゃ上手。演技力にも定評がある。笠原をよく思っていない実力のない人が、東郷先生に身体を売って今の位置を獲得したんじゃないかと噂しているが本人は気にしていない。高卒。1人目の犠牲者。 ・元村由理恵 綺麗らしい。役者になったのは幼少期父に連れられて芝居やミュージカルを見たことがきっかけ。金持ちのお嬢さん。久我と田所が狙っている。ロンドンやブロードウェイに演技の勉強で行きたいと思っている。このことが雨宮とデキているのでは?という噂を生んだ。2人目の犠牲者。 ・中西貴子 噂好きで口が軽い。考えることが苦手。胸がでかい。大学中退。 ・久我和幸 演技に自信があり他人を見下し評価する。表には全く出さず、計算高い。 ・雨宮京介 足が長い。劇団から一人ロンドンの演技学校に1年間留学させる話で、その一人に選ばれた。どこのグループにも1人はいるようなリーダータイプ。 ・本田雄一 荒削りをした顔立ち。ガタイがいい。芝居の実力はある。2日目の夜に久我の提案により、お互いを監視する名目で相部屋となる。このことは中西のみが知っている。 ・田所義雄 あからさまに元村を狙っていて、他の人に取られるのではないかという焦りが露骨に出てて余裕がない。リーダーシップを発揮しようとするが、鬱陶しく陰口を叩かれて、人気がない。久我から夜這いすんじゃね?と警戒されてる。 ・麻倉雅美 最近スキーで大怪我を負い半身不随になった元劇団員。演技力もあり笠原のライバルだったが、容姿では劣っていた。スキーでの事故はオーディションに負けたことによる自殺未遂という説もある。久我以外の6人とは見知った仲。 初日の夜に笠原という女性がケーブルによって殺された。が、やはりこれも設定。笠原はその後姿を消したが、おそらく近くにペンションでも借りて最終日まで待機してるのだろうとみんなは納得する。 外は大雪で外部からの侵入者はいないという設定だから、犯人はこの残った6人の中にいることになる。 その後、設定ということを前提に「こういう時はどう動くのが自然なのか」「皆に笠原を殺す動機はないのか」ということを探り探りで話し合っていく。 実際には死んでいないので緊張感はないながらも、手探りでリアルな演技を模索する6人。 二人目が(設定上)殺されてから様子がおかしくなる。 設定では鈍器で殴打され首を絞められたことになっているが、狂気として使用された鉄製の一輪挿しには本物の血が付着していたからだ。 また、殺害された部屋を確認すると女性用の生理用品が見える形で放置されていた。 デリケートな部分のためいくら殺され役だとしても、隠したいはずなのだ。 演技ではないかもしれないという違和感。 残った5人は東郷先生がより臨場感を演出するために用意したモノだと無理やり納得した。 しかし、改めて二人目が殺された現場を調べると「この紙を鈍器とする」と書かれた紙がゴミ箱の中から見つかった。 つまり、設定上の鈍器はゴミ箱の中にあったのに、本物の血が付いた鈍器が別で見つかったことになる。 設定の裏で本当に殺人が行われているかもしれない。そういう疑惑と不安が残った5人に沸々と湧き上がってきた。 殺人は結局3人目にまで及んでしまった。 殺害されたのは、笠原、元村、雨宮の3名。 事件を推理し、見事に謎を暴いたのは久我だった。 3人は殺されておらず、近くのペンションに身を隠していたことが後半に判明する。 久我が当初から感じていた違和感の正体を時系列に従って解き明かす。 そのことで判明したのはこの7人が来たペンションに麻倉が潜んでいたことだった。 殺人犯として動いていたのは本多。 先に挙げた3人は殺され役として本多に協力していたことが分かった。 この3人は麻倉に恨まれることをしてしまった。それが原因で麻倉は自殺未遂を起こし、半身不随になってしまったのだ。 3人はその事について後悔しており、麻倉の殺意も理解していた。 麻倉に代わって3人の復讐を予定していた本多だったが、やはり本当に殺人を犯すことはできなかった。 ペンション内に隠れて監視している麻倉の目を欺くため3人に協力を仰ぎ、本当に殺人が行われているかのように役を演じ切ってもらっていた。 つまり、殺人が行われているという設定の裏では、麻倉を欺くために本当に殺人が行われていると偽装し、実際は殺人は行なわれていないという三重構造だったのだ。 麻倉がペンションに潜んでいたことは、本書の冒頭から示唆されていた。 本書は通常の物語を紡ぐ文章と【久我の独白】という文章の二つの構成で成り立っている。 【久我の独白】は久我目線で物語が進行していくが、それ以外の文章は麻倉視点であることが260ページの2行目で判明する。 麻倉の監視が届かない範囲での出来事を久我目線に切り替えることで、物語が進んでいたのだ。 三重構造はそのままどんでん返しの回数とも捉えられる。 正直、設定の裏で本当に殺人が行われてるかもしれないと疑惑が出た時点で、メタ的に本当に殺人が行われていると思っていた。 だからこそ騙された。 とても面白い。
ある閉ざされた雪の山荘で東野圭吾ミステリー読み終わったどんでん返し【ネタバレ大アリ】 東郷陣平(以降東郷先生)という奇天烈な脚本家がいた。 東郷先生が主催するオーディションに応募し、見事合格を勝ち取った7人の若い舞台役者たち。 7人のうち6人はオーディション以前から見知った仲で、残り1人はオーディション合格後に6人に合流したある意味新参者の久我和幸。 東郷先生の計らいで、彼らは山奥の山荘を4日間貸し切り、過ごすこととなった。 東郷先生曰く、次回作の脚本や演出に反映させるため、演技の練習を実践で積ませようというもの。 山荘での4日間は、東郷先生の設定した状況にあわせて様々な事が起きる。 その出来事に役者として臨機応変に対応してほしいとのことだった。 設定は、山荘の外は記録的な大雪、電話線は切られており、スマホも圏外、オーナーも外出してから帰ってこない、山荘は自然が作り出したクローズドサークルになってしまった。そこで、次々と殺人が行われるというものだ。 しかし、これはあくまでも設定なので、実際は日差しも暖かく、キャンプにはもってこいの晴天だし、山荘の目の前にはバス停があるので外出は可能だし、電話も問題なく通じる。 だが、あくまでもクローズドサークルという設定だと認識した上で、演じていくことが今回7人に与えられたミッションだった。 ◆登場人物 ・笠原温子 ピアノめっちゃ上手。演技力にも定評がある。笠原をよく思っていない実力のない人が、東郷先生に身体を売って今の位置を獲得したんじゃないかと噂しているが本人は気にしていない。高卒。1人目の犠牲者。 ・元村由理恵 綺麗らしい。役者になったのは幼少期父に連れられて芝居やミュージカルを見たことがきっかけ。金持ちのお嬢さん。久我と田所が狙っている。ロンドンやブロードウェイに演技の勉強で行きたいと思っている。このことが雨宮とデキているのでは?という噂を生んだ。2人目の犠牲者。 ・中西貴子 噂好きで口が軽い。考えることが苦手。胸がでかい。大学中退。 ・久我和幸 演技に自信があり他人を見下し評価する。表には全く出さず、計算高い。 ・雨宮京介 足が長い。劇団から一人ロンドンの演技学校に1年間留学させる話で、その一人に選ばれた。どこのグループにも1人はいるようなリーダータイプ。 ・本田雄一 荒削りをした顔立ち。ガタイがいい。芝居の実力はある。2日目の夜に久我の提案により、お互いを監視する名目で相部屋となる。このことは中西のみが知っている。 ・田所義雄 あからさまに元村を狙っていて、他の人に取られるのではないかという焦りが露骨に出てて余裕がない。リーダーシップを発揮しようとするが、鬱陶しく陰口を叩かれて、人気がない。久我から夜這いすんじゃね?と警戒されてる。 ・麻倉雅美 最近スキーで大怪我を負い半身不随になった元劇団員。演技力もあり笠原のライバルだったが、容姿では劣っていた。スキーでの事故はオーディションに負けたことによる自殺未遂という説もある。久我以外の6人とは見知った仲。 初日の夜に笠原という女性がケーブルによって殺された。が、やはりこれも設定。笠原はその後姿を消したが、おそらく近くにペンションでも借りて最終日まで待機してるのだろうとみんなは納得する。 外は大雪で外部からの侵入者はいないという設定だから、犯人はこの残った6人の中にいることになる。 その後、設定ということを前提に「こういう時はどう動くのが自然なのか」「皆に笠原を殺す動機はないのか」ということを探り探りで話し合っていく。 実際には死んでいないので緊張感はないながらも、手探りでリアルな演技を模索する6人。 二人目が(設定上)殺されてから様子がおかしくなる。 設定では鈍器で殴打され首を絞められたことになっているが、狂気として使用された鉄製の一輪挿しには本物の血が付着していたからだ。 また、殺害された部屋を確認すると女性用の生理用品が見える形で放置されていた。 デリケートな部分のためいくら殺され役だとしても、隠したいはずなのだ。 演技ではないかもしれないという違和感。 残った5人は東郷先生がより臨場感を演出するために用意したモノだと無理やり納得した。 しかし、改めて二人目が殺された現場を調べると「この紙を鈍器とする」と書かれた紙がゴミ箱の中から見つかった。 つまり、設定上の鈍器はゴミ箱の中にあったのに、本物の血が付いた鈍器が別で見つかったことになる。 設定の裏で本当に殺人が行われているかもしれない。そういう疑惑と不安が残った5人に沸々と湧き上がってきた。 殺人は結局3人目にまで及んでしまった。 殺害されたのは、笠原、元村、雨宮の3名。 事件を推理し、見事に謎を暴いたのは久我だった。 3人は殺されておらず、近くのペンションに身を隠していたことが後半に判明する。 久我が当初から感じていた違和感の正体を時系列に従って解き明かす。 そのことで判明したのはこの7人が来たペンションに麻倉が潜んでいたことだった。 殺人犯として動いていたのは本多。 先に挙げた3人は殺され役として本多に協力していたことが分かった。 この3人は麻倉に恨まれることをしてしまった。それが原因で麻倉は自殺未遂を起こし、半身不随になってしまったのだ。 3人はその事について後悔しており、麻倉の殺意も理解していた。 麻倉に代わって3人の復讐を予定していた本多だったが、やはり本当に殺人を犯すことはできなかった。 ペンション内に隠れて監視している麻倉の目を欺くため3人に協力を仰ぎ、本当に殺人が行われているかのように役を演じ切ってもらっていた。 つまり、殺人が行われているという設定の裏では、麻倉を欺くために本当に殺人が行われていると偽装し、実際は殺人は行なわれていないという三重構造だったのだ。 麻倉がペンションに潜んでいたことは、本書の冒頭から示唆されていた。 本書は通常の物語を紡ぐ文章と【久我の独白】という文章の二つの構成で成り立っている。 【久我の独白】は久我目線で物語が進行していくが、それ以外の文章は麻倉視点であることが260ページの2行目で判明する。 麻倉の監視が届かない範囲での出来事を久我目線に切り替えることで、物語が進んでいたのだ。 三重構造はそのままどんでん返しの回数とも捉えられる。 正直、設定の裏で本当に殺人が行われてるかもしれないと疑惑が出た時点で、メタ的に本当に殺人が行われていると思っていた。 だからこそ騙された。 とても面白い。 - 2025年4月16日
 ヨイヨワネ あおむけ編ヨシタケシンスケこの本はいわばイラスト集です。 イラストと一言二言の色んな弱音が描いてあるだけです。 文章ではなく、脈絡もない。 LINEのスタンプのようにそれ一つだけで完結するイラスト集。 だからどこから読んでもいいし、1ページだけ読んで閉じてもいいし、反対側から読んでもいい。 ただ、「今の自分ってこれかも」という共感を見つけてください。 あなたの弱音はきっと解決しないし、進展しないかもしれません。 だけど、あなたが言いたい弱音はここにあります。 これはあなたが本当は吐きたい弱音を見つけるイラスト集です。
ヨイヨワネ あおむけ編ヨシタケシンスケこの本はいわばイラスト集です。 イラストと一言二言の色んな弱音が描いてあるだけです。 文章ではなく、脈絡もない。 LINEのスタンプのようにそれ一つだけで完結するイラスト集。 だからどこから読んでもいいし、1ページだけ読んで閉じてもいいし、反対側から読んでもいい。 ただ、「今の自分ってこれかも」という共感を見つけてください。 あなたの弱音はきっと解決しないし、進展しないかもしれません。 だけど、あなたが言いたい弱音はここにあります。 これはあなたが本当は吐きたい弱音を見つけるイラスト集です。 - 2025年2月27日
 読み終わった一つのものを見た時に、頭の中でどれだけマジカルバナナができるかという「発想の転換」を様々なシチュエーションに合わせて紹介している本だった。 頭が良い人の視点というか、こうやって考えたら頭が良くなっていくのかな?という印象。 例えば、行列の長さを見たときに、自分の時給と天秤にかけて、並んだ方が得か並ばない方が得かを考えたり、 お客さんの数が減ったら「人気がなくなった」と考えるのではなく「どこにその数字が流れたのか」と考えたり。 発想の転換もそうだけど「今見えている事実を数字に置き換えてみる」という理系の考え方に近いものを感じた。 総じて言えるのは1つのものを見た時に、どれだけマジカルバナナができるか、もしくは数字に置き換えてみるとどうか、という思考の具体例集がこの本だ。
読み終わった一つのものを見た時に、頭の中でどれだけマジカルバナナができるかという「発想の転換」を様々なシチュエーションに合わせて紹介している本だった。 頭が良い人の視点というか、こうやって考えたら頭が良くなっていくのかな?という印象。 例えば、行列の長さを見たときに、自分の時給と天秤にかけて、並んだ方が得か並ばない方が得かを考えたり、 お客さんの数が減ったら「人気がなくなった」と考えるのではなく「どこにその数字が流れたのか」と考えたり。 発想の転換もそうだけど「今見えている事実を数字に置き換えてみる」という理系の考え方に近いものを感じた。 総じて言えるのは1つのものを見た時に、どれだけマジカルバナナができるか、もしくは数字に置き換えてみるとどうか、という思考の具体例集がこの本だ。 - 2025年2月25日
 読み終わったYouTubeで桜井政博さんのチャンネルがオススメに上がってきたことで認知。 興味を持ちamazonで購入。 この人は、誰も傷つけず、言葉を丁寧に選びながらその時々で考えていたこと、思いや苦労を話してくれます。 読んでいて飽きなかった。 詳しい人が話すと、さらに面白く感じます。 今回は「ゲームについて思うこと」という本なので、ビジネスに対する姿勢や考え方というより、ゲーム全般に対して率直に思ったこと、感じたことがメインな気がします。 ビジネス書というよりかは、コラムやエッセイとかに近いテイストを感じました。 ビジネス視点で読みたいなら「ゲームを作って思うこと」を読んだ方が良いかも。
読み終わったYouTubeで桜井政博さんのチャンネルがオススメに上がってきたことで認知。 興味を持ちamazonで購入。 この人は、誰も傷つけず、言葉を丁寧に選びながらその時々で考えていたこと、思いや苦労を話してくれます。 読んでいて飽きなかった。 詳しい人が話すと、さらに面白く感じます。 今回は「ゲームについて思うこと」という本なので、ビジネスに対する姿勢や考え方というより、ゲーム全般に対して率直に思ったこと、感じたことがメインな気がします。 ビジネス書というよりかは、コラムやエッセイとかに近いテイストを感じました。 ビジネス視点で読みたいなら「ゲームを作って思うこと」を読んだ方が良いかも。
読み込み中...
