目的への抵抗―シリーズ哲学講話―(新潮新書)

16件の記録
 noripiii@quadspin_norimusubi2025年4月18日読んでる@ COFFEE HALL くぐつ草あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは、世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。ガンジーの言葉、引用してる。
noripiii@quadspin_norimusubi2025年4月18日読んでる@ COFFEE HALL くぐつ草あなたがすることのほとんどは無意味であるが、それでもしなくてはならない。そうしたことをするのは、世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためである。ガンジーの言葉、引用してる。



 レイカ@yukari1252025年4月17日読み終わった◾️タイパ、コスパに疲れてない? 勉強の「目的」、仕事の「目的」、外出の「目的」、その商品を買う「目的」、あらゆる場面で、私たちは「目的」を考えるようになっている。 「目的」を明確にすると、それを達成するための手段も見つけやすいと言われる。 さまざまな手段がある中で、より効率的なものを選ぶことが良いとされる。 コスト(費用・お金)は掛けないほうがよい(コスパが良いほうがいい)。 時間も掛けないほうがよい(タイパも良いほうがいい)。 そんなふうに考えがちだ。 コスパやタイパを追い求めると、映画を早送りして見ることになったり、 要約を読むことで読書を済ませることになる。 それって、本当によいことなのだろうか? 國分功一郎・著「目的への抵抗」(新潮新書)は、「目的」というものについて、立ち止まって考えさせる一冊だ。 私たちの毎日の生活の中で、「目的」を明確にする必要なことって、どれくらいあるだろう? 何の目的もなく、行動することに価値があるのではないか。 そんなことを考えさせられる。 特定の目的や、効率的とされる手段に縛られず、「自由」であることの価値も示してくれる。 「コスパ」「タイパ」の考え方に疲れた人に、お勧めしたい1冊。 #読書記録 #読書
レイカ@yukari1252025年4月17日読み終わった◾️タイパ、コスパに疲れてない? 勉強の「目的」、仕事の「目的」、外出の「目的」、その商品を買う「目的」、あらゆる場面で、私たちは「目的」を考えるようになっている。 「目的」を明確にすると、それを達成するための手段も見つけやすいと言われる。 さまざまな手段がある中で、より効率的なものを選ぶことが良いとされる。 コスト(費用・お金)は掛けないほうがよい(コスパが良いほうがいい)。 時間も掛けないほうがよい(タイパも良いほうがいい)。 そんなふうに考えがちだ。 コスパやタイパを追い求めると、映画を早送りして見ることになったり、 要約を読むことで読書を済ませることになる。 それって、本当によいことなのだろうか? 國分功一郎・著「目的への抵抗」(新潮新書)は、「目的」というものについて、立ち止まって考えさせる一冊だ。 私たちの毎日の生活の中で、「目的」を明確にする必要なことって、どれくらいあるだろう? 何の目的もなく、行動することに価値があるのではないか。 そんなことを考えさせられる。 特定の目的や、効率的とされる手段に縛られず、「自由」であることの価値も示してくれる。 「コスパ」「タイパ」の考え方に疲れた人に、お勧めしたい1冊。 #読書記録 #読書



 ミキ@miki___632025年4月13日読み終わった國分さんの本を続けて。思えば、過去を振り返っても今現在も、目的にとらわれて、目の前のことをちゃんと感じたり楽しめていないなと思うことが多い。すべてがそうではないけれど、目的こそ優先すべきという感覚が自分の中にけっこう根深くあるのだと気づかされた。暇と退屈〜も読み直したい。
ミキ@miki___632025年4月13日読み終わった國分さんの本を続けて。思えば、過去を振り返っても今現在も、目的にとらわれて、目の前のことをちゃんと感じたり楽しめていないなと思うことが多い。すべてがそうではないけれど、目的こそ優先すべきという感覚が自分の中にけっこう根深くあるのだと気づかされた。暇と退屈〜も読み直したい。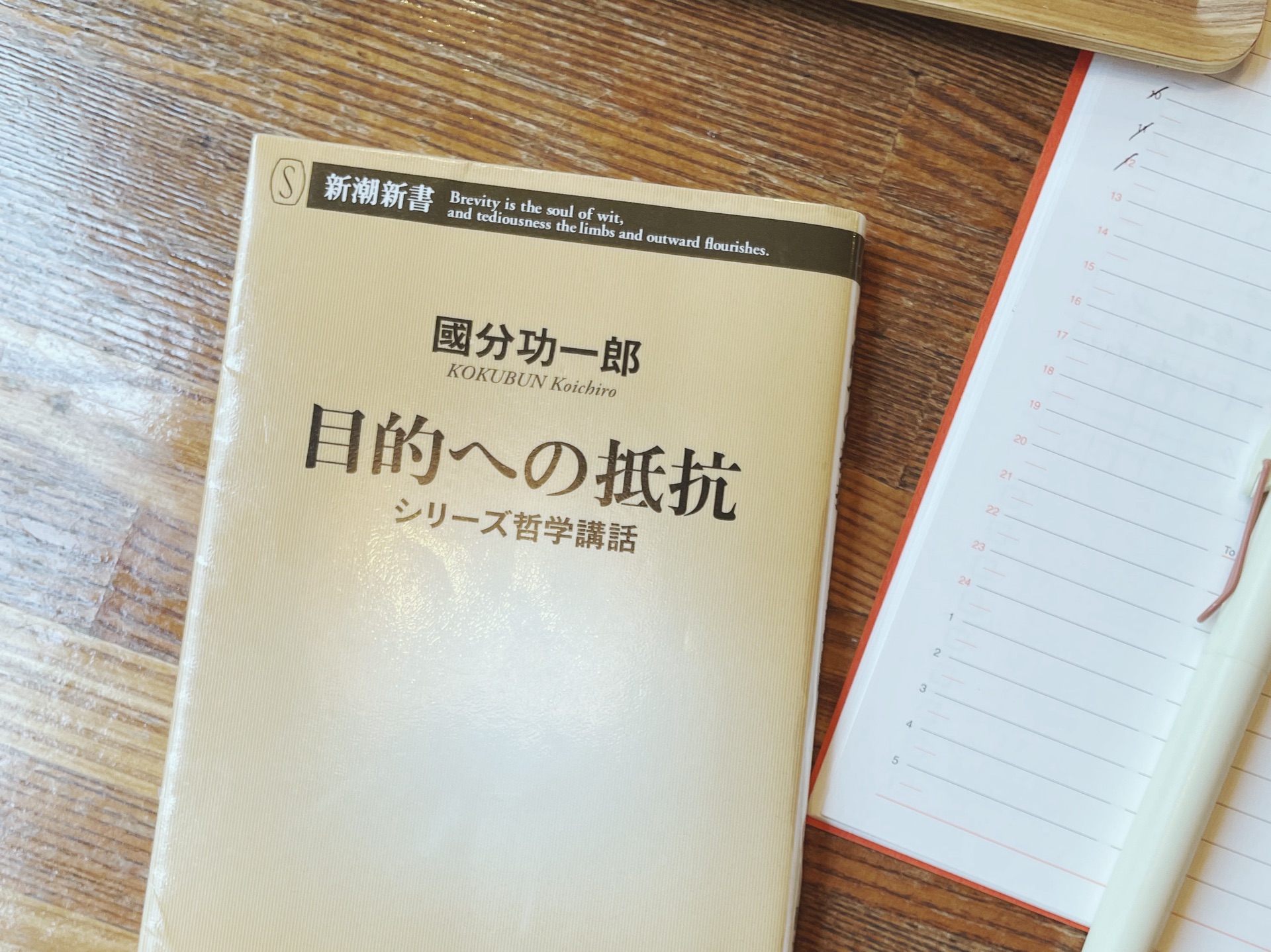


 noripiii@quadspin_norimusubi2025年4月13日読んでる哲学の役割-コロナ危機と民主主義、っていう章の名前がわかりやすい。アガンベンの哲学者としての仕事と、メルケルさんの政治家としての仕事っていう角度で見てるの面白い。そしてコロナ禍の移動の制限を行政と立法のバランスが崩れた場面として捉えたことがなかったから、ひたすら唸る。
noripiii@quadspin_norimusubi2025年4月13日読んでる哲学の役割-コロナ危機と民主主義、っていう章の名前がわかりやすい。アガンベンの哲学者としての仕事と、メルケルさんの政治家としての仕事っていう角度で見てるの面白い。そしてコロナ禍の移動の制限を行政と立法のバランスが崩れた場面として捉えたことがなかったから、ひたすら唸る。

 柿内正午@kakisiesta2025年4月11日読み終わった朝に本を読む習慣をつくろうとしていたのに、春になってからだいぶ崩れている。それで本が読めていない気分になっているので、今朝は新書でも読んで、さくっと読み終える充実感を得るか、と考える。日記に書いたか忘れたけれど、僕は、目的意識をもってしまうと過程がすべてうざくなる。それでただ結果だけをインスタントに欲してしまうことで、たとえば料理や食事が効率的に捌くべきタスクになりかねない危険を有しているということを最近よく考えている。読むべきだと思っている本も、だからさっさと読み終えたという実績だけ欲しくなる。楽しいから読むだけなのに、読んだ後に幻視している何かのための手段のように錯覚することがあり、そういう読書は楽しくない。あらゆる行為を、なるべく自己享楽的に、目的のための手段、省略することが望ましいコストとして感覚しないで行為することが肝腎。まあそんなことを考えていて、だから、國分功一郎の目的と手段のシリーズでも読もう。行きの電車で目的のほうをだいたい読む。新書は速くていいなあ。読了という目的をインスタントに達成できる。
柿内正午@kakisiesta2025年4月11日読み終わった朝に本を読む習慣をつくろうとしていたのに、春になってからだいぶ崩れている。それで本が読めていない気分になっているので、今朝は新書でも読んで、さくっと読み終える充実感を得るか、と考える。日記に書いたか忘れたけれど、僕は、目的意識をもってしまうと過程がすべてうざくなる。それでただ結果だけをインスタントに欲してしまうことで、たとえば料理や食事が効率的に捌くべきタスクになりかねない危険を有しているということを最近よく考えている。読むべきだと思っている本も、だからさっさと読み終えたという実績だけ欲しくなる。楽しいから読むだけなのに、読んだ後に幻視している何かのための手段のように錯覚することがあり、そういう読書は楽しくない。あらゆる行為を、なるべく自己享楽的に、目的のための手段、省略することが望ましいコストとして感覚しないで行為することが肝腎。まあそんなことを考えていて、だから、國分功一郎の目的と手段のシリーズでも読もう。行きの電車で目的のほうをだいたい読む。新書は速くていいなあ。読了という目的をインスタントに達成できる。



















