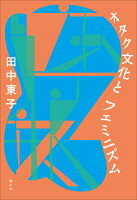八
@Hachi8
ゆるく読書が好き。積読多め。
- 2026年2月23日
- 2026年2月23日
 一枚の絵から 日本編高畑勲気になる
一枚の絵から 日本編高畑勲気になる - 2026年2月23日
 一枚の絵から 海外編高畑勲気になる
一枚の絵から 海外編高畑勲気になる - 2026年2月23日
 ユリイカ 2013年12月号 特集=高畑勲「かぐや姫の物語」の世界奈良美智,朝倉あき,細馬宏通,西村義明,高畑勲気になる
ユリイカ 2013年12月号 特集=高畑勲「かぐや姫の物語」の世界奈良美智,朝倉あき,細馬宏通,西村義明,高畑勲気になる - 2026年2月15日
- 2026年2月15日
 1945年のクリスマスベアテ・シロタ・ゴードン,平岡磨紀子気になる
1945年のクリスマスベアテ・シロタ・ゴードン,平岡磨紀子気になる - 2026年2月9日
 ザ・バックラッシャー(1)岡田索雲気になる
ザ・バックラッシャー(1)岡田索雲気になる - 2026年2月8日
- 2026年2月8日
- 2026年2月8日
 ある男平野啓一郎読み終わった映画版がとても良かったので原作を手にとった。 平野啓一郎作品は「マチネの終わりに」が個人的には乗れなかったので、手にとってこなかったが「ある男」はすごく良かった。 平野啓一郎作品はテーマ自体が自分の興味と重なるので気にはなっていたものの敬遠していたので、「ある男」きっかけに他の作品も読んでみたいなと思った。 「ある男」は人物像に立体感があって、人間のレイヤーというか多面性に共感した。 人の汚い部分の描き方が巧みで、実在する人間のようだったし、自分にもこういう汚い部分があるなと自覚したりした。 Kindle文庫電子版を購入したが、解説の代わりに平野啓一郎本人のインタビュー、石川慶監督との対談、読者からの質問返しが入っていて大変お得だった。
ある男平野啓一郎読み終わった映画版がとても良かったので原作を手にとった。 平野啓一郎作品は「マチネの終わりに」が個人的には乗れなかったので、手にとってこなかったが「ある男」はすごく良かった。 平野啓一郎作品はテーマ自体が自分の興味と重なるので気にはなっていたものの敬遠していたので、「ある男」きっかけに他の作品も読んでみたいなと思った。 「ある男」は人物像に立体感があって、人間のレイヤーというか多面性に共感した。 人の汚い部分の描き方が巧みで、実在する人間のようだったし、自分にもこういう汚い部分があるなと自覚したりした。 Kindle文庫電子版を購入したが、解説の代わりに平野啓一郎本人のインタビュー、石川慶監督との対談、読者からの質問返しが入っていて大変お得だった。 - 2026年2月8日
 戦争画リターンズ平山周吉気になる
戦争画リターンズ平山周吉気になる - 2026年2月7日
 抵抗のカルトグラフィ佐久本佳奈気になる
抵抗のカルトグラフィ佐久本佳奈気になる - 2026年2月2日
- 2026年2月1日
 未婚じゃなくて、非婚ですすんみ,ホンサムピギョル読み終わった韓国人フェミニストおふたりによるエッセイ。 最初から最後までぐんぐん読ませてくれてエンパワメントしてくれる本だった。 歳を重ねても結婚せずにバリバリ働く女性を韓国では「ゴールドミス」と言うらしい。 ゴールドミスになって「成功」するか、いい男と結婚して「成功」するか、ここでいう女性の「成功」は、大部分が高い地位やお金持ちを意味する。 だが、著者エイは非婚主義で結婚する意思はなく、だからといって成功者のゴールドミスになりたい気持ちもない。他人の基準に合わせず、自分らしく思うように生きたい。「結婚せずにひとりで思うように暮らす私」という文章に「成功した」という修飾語はなくて大丈夫だとエイは言う。 深く共感した。結婚していない女性で可視化されているのは所謂バリキャリ、もしくはその対極にいる貧困層の女性だ。 平凡と言われるような自分1人が暮らしていける稼ぎの女性はほぼ可視化されない。エイは優れた能力、才能、努力、夢なんかなくても、一人でこの世の中をくぐり抜けていくと強い決意を抱いてできる道があると若い女性に知らせたいと書いていた。 こういう話が読みたかったのだ。特別な女性の話じゃなくて、一人で生活しているけどそれなりに楽しく暮らしいる女性の話が。
未婚じゃなくて、非婚ですすんみ,ホンサムピギョル読み終わった韓国人フェミニストおふたりによるエッセイ。 最初から最後までぐんぐん読ませてくれてエンパワメントしてくれる本だった。 歳を重ねても結婚せずにバリバリ働く女性を韓国では「ゴールドミス」と言うらしい。 ゴールドミスになって「成功」するか、いい男と結婚して「成功」するか、ここでいう女性の「成功」は、大部分が高い地位やお金持ちを意味する。 だが、著者エイは非婚主義で結婚する意思はなく、だからといって成功者のゴールドミスになりたい気持ちもない。他人の基準に合わせず、自分らしく思うように生きたい。「結婚せずにひとりで思うように暮らす私」という文章に「成功した」という修飾語はなくて大丈夫だとエイは言う。 深く共感した。結婚していない女性で可視化されているのは所謂バリキャリ、もしくはその対極にいる貧困層の女性だ。 平凡と言われるような自分1人が暮らしていける稼ぎの女性はほぼ可視化されない。エイは優れた能力、才能、努力、夢なんかなくても、一人でこの世の中をくぐり抜けていくと強い決意を抱いてできる道があると若い女性に知らせたいと書いていた。 こういう話が読みたかったのだ。特別な女性の話じゃなくて、一人で生活しているけどそれなりに楽しく暮らしいる女性の話が。 - 2026年1月31日
 最後の決闘裁判エリック・ジェイガー,栗木さつき気になる
最後の決闘裁判エリック・ジェイガー,栗木さつき気になる - 2026年1月25日
 差別の民俗学赤松啓介気になる
差別の民俗学赤松啓介気になる - 2026年1月18日
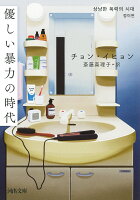 優しい暴力の時代チョン・イヒョン,斎藤真理子気になる
優しい暴力の時代チョン・イヒョン,斎藤真理子気になる - 2026年1月18日
- 2026年1月16日
- 2026年1月12日
 死体でもいいから、そばにいてほしいクォン・イルヨン,中川里沙気になる読みたい
死体でもいいから、そばにいてほしいクォン・イルヨン,中川里沙気になる読みたい
読み込み中...