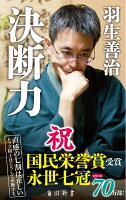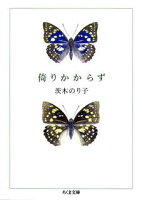サカグチ
@hisuissugi
あんまり本を読み切らずに色々乱読しています
主に「読み置き」です
「読み置き」についてはリストまで
たまに読み切ります
- 2025年4月24日
 読み置き人に勧められた! 面白い! (4月25日追記) 読みの仮説 「凡庸さ」という概念が発明された経緯について論述する。筆者は「凡庸さ」をこのように提起する。 「凡庸」とは、よく読まれている日本語の辞典なら「すぐれたところのないこと」という定義におさまっているように、いささかも特殊な概念ではない。ただ、その定義の非゠歴史性に深くいらだった著者は、相対的な定義におさまりがちな「凡庸」という語彙を、「すぐれたところ」の不在とはおよそ無縁の絶対的な現実として定義しなおし、その歴史的な新しさを視界に浮上させることに意味を見いだした。 →「凡庸さ」は相対的なものではない。そして、それは近代になって「発明」されたものである。 では、その「凡庸さ」とはいったいなんなのか? 想定ポイントは以下の四つ ・遊戯 ・成熟 ・捏造 ・旅行者 大作なのでゆっくり読んでいく。
読み置き人に勧められた! 面白い! (4月25日追記) 読みの仮説 「凡庸さ」という概念が発明された経緯について論述する。筆者は「凡庸さ」をこのように提起する。 「凡庸」とは、よく読まれている日本語の辞典なら「すぐれたところのないこと」という定義におさまっているように、いささかも特殊な概念ではない。ただ、その定義の非゠歴史性に深くいらだった著者は、相対的な定義におさまりがちな「凡庸」という語彙を、「すぐれたところ」の不在とはおよそ無縁の絶対的な現実として定義しなおし、その歴史的な新しさを視界に浮上させることに意味を見いだした。 →「凡庸さ」は相対的なものではない。そして、それは近代になって「発明」されたものである。 では、その「凡庸さ」とはいったいなんなのか? 想定ポイントは以下の四つ ・遊戯 ・成熟 ・捏造 ・旅行者 大作なのでゆっくり読んでいく。 - 2025年4月22日
- 2025年4月20日
- 2025年4月18日
- 2025年4月17日
- 2025年4月14日
- 2025年4月11日
- 2025年4月9日
 ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試みヨハン・ホイジンガ,里見元一郎読み終わった何度も読みたい「遊び」を高潔なものと定義したホイジンガの思索。遊びは常に遊びそれ自体に目的を持っており、そうでない遊びは、遊びたり得ない。 ホイジンガは「遊ぶ」余裕をなくした20世紀社会へ伶俐な視点を向ける。おれは21世紀に、遊ぶ。 以下核心。 我々はゆっくりとではあったがやっと一つの結論に近づいてきた。真の文化はある程度、遊びの内容をもたなくては成り立ちえない。なぜなら、文化はなんらかの自己抑制と克己を前提とし、さらにその文化に特有の性向を絶対最高のものと思い込んだりしない能力をもち、しかも自由意志で受け入れたある限界の中で閉ざされた自己を見つめる能力を前提としている。文化はある意味ではいつの時代でもやはり一定の規律への相互の合意に基づいて遊ばれることを欲している。真の文明はいかなる見方に立とうと常にフェアプレーを要求する。またそのフェアプレーとはつまり善良な誠実さを遊び言葉に言い換えたものにほかならない。遊びの協定破りは文化自体をも破壊する。文明のもつ遊びの内容が文化創造的、あるいは文化推進的であろうとするなら、それは純粋でなければならない。それは理性や人間性や信仰によって定められた規範から迷い出したり、それに違反したりしては成り立つはずがない。それは故意に育成された遊びの形式によって特定の目的を実現する企てを隠すための偽りの仮面の装いであってはならない。真の遊びはあらゆる宣伝を締め出す。それはそれ自身の中に目的をもっている。その精神と情緒はこころよい恍惚境のそれであり、ヒステリックな大騒ぎのそれではない。あらゆる生活分野を一手に支配しようとしている現代の宣伝はヒステリックな大衆的反応をまき起こそうとし、そのための手練手管を動員して運動している。その場合、遊びの形式を借りたにしても、それは遊びの精神の近代的表現とみなされるべきではなく、ただそれにあやかった偽物であると考えられるべきだ。
ホモ・ルーデンス 文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試みヨハン・ホイジンガ,里見元一郎読み終わった何度も読みたい「遊び」を高潔なものと定義したホイジンガの思索。遊びは常に遊びそれ自体に目的を持っており、そうでない遊びは、遊びたり得ない。 ホイジンガは「遊ぶ」余裕をなくした20世紀社会へ伶俐な視点を向ける。おれは21世紀に、遊ぶ。 以下核心。 我々はゆっくりとではあったがやっと一つの結論に近づいてきた。真の文化はある程度、遊びの内容をもたなくては成り立ちえない。なぜなら、文化はなんらかの自己抑制と克己を前提とし、さらにその文化に特有の性向を絶対最高のものと思い込んだりしない能力をもち、しかも自由意志で受け入れたある限界の中で閉ざされた自己を見つめる能力を前提としている。文化はある意味ではいつの時代でもやはり一定の規律への相互の合意に基づいて遊ばれることを欲している。真の文明はいかなる見方に立とうと常にフェアプレーを要求する。またそのフェアプレーとはつまり善良な誠実さを遊び言葉に言い換えたものにほかならない。遊びの協定破りは文化自体をも破壊する。文明のもつ遊びの内容が文化創造的、あるいは文化推進的であろうとするなら、それは純粋でなければならない。それは理性や人間性や信仰によって定められた規範から迷い出したり、それに違反したりしては成り立つはずがない。それは故意に育成された遊びの形式によって特定の目的を実現する企てを隠すための偽りの仮面の装いであってはならない。真の遊びはあらゆる宣伝を締め出す。それはそれ自身の中に目的をもっている。その精神と情緒はこころよい恍惚境のそれであり、ヒステリックな大騒ぎのそれではない。あらゆる生活分野を一手に支配しようとしている現代の宣伝はヒステリックな大衆的反応をまき起こそうとし、そのための手練手管を動員して運動している。その場合、遊びの形式を借りたにしても、それは遊びの精神の近代的表現とみなされるべきではなく、ただそれにあやかった偽物であると考えられるべきだ。 - 2025年4月7日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
 苦役列車(新潮文庫)西村賢太かつて読んだ何度も読みたいいい小説は文体とかストーリーとかを全く除いた部分で、「なんか記憶に残る」という評価ポイントを持つ。 おれにとってこの作品はそういう作品だった。 日雇い労働で得た金が、その日のうちに飲み食いして消えていく。
苦役列車(新潮文庫)西村賢太かつて読んだ何度も読みたいいい小説は文体とかストーリーとかを全く除いた部分で、「なんか記憶に残る」という評価ポイントを持つ。 おれにとってこの作品はそういう作品だった。 日雇い労働で得た金が、その日のうちに飲み食いして消えていく。 - 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
- 2025年4月6日
読み込み中...