

ザムザ
@zamzy733
よろしくお願いします。
野良で論文や詩、短歌、エッセイを書いています。
- 2025年7月7日
- 2025年7月4日
 内在的多様性批判久保明教気になる
内在的多様性批判久保明教気になる - 2025年7月4日
 ツインレイ夫婦の奇跡に逢いにゆくひらめき旅ナオとリョウ気になるツインレイの話題はYoutubeや書籍で、近年よくみかける。そういうのはツインレイとの出会うまでとか、出会い方とかが多い。この本ではツインレイの2人が「出逢ってから何をしたか」に言及しているのが興味深い。 タイトルにある通り、していることは旅である。 その旅の仕方は「ひらめきや直感に従うこと」。つまり、計画を立てずに、心の赴くままに、である。そこで出逢ったのは〈奇跡〉。その奇跡がどんなだったのか、って本。
ツインレイ夫婦の奇跡に逢いにゆくひらめき旅ナオとリョウ気になるツインレイの話題はYoutubeや書籍で、近年よくみかける。そういうのはツインレイとの出会うまでとか、出会い方とかが多い。この本ではツインレイの2人が「出逢ってから何をしたか」に言及しているのが興味深い。 タイトルにある通り、していることは旅である。 その旅の仕方は「ひらめきや直感に従うこと」。つまり、計画を立てずに、心の赴くままに、である。そこで出逢ったのは〈奇跡〉。その奇跡がどんなだったのか、って本。 - 2025年6月26日
- 2025年6月25日
 優雅な生活が最高の復讐であるカルヴィン・トムキンズ,青山南気になる
優雅な生活が最高の復讐であるカルヴィン・トムキンズ,青山南気になる - 2025年6月25日
- 2025年5月27日
- 2025年5月15日
 哲学への誘い(4)伊佐敷隆弘,倉田剛,吉田聡,朝倉友海,松永澄夫,渡辺由文,谷口薫読んでる@ 海老名市時間が経過すると、現在は過去になる。 これについて、現在は現象した途端に過去になるという性質を思う。 …でも、こうした概念的事情に対して、現在から経過を抜いたらどうかと考えてみたくなる。 経過抜きの今現在。 これはどうだろうか?
哲学への誘い(4)伊佐敷隆弘,倉田剛,吉田聡,朝倉友海,松永澄夫,渡辺由文,谷口薫読んでる@ 海老名市時間が経過すると、現在は過去になる。 これについて、現在は現象した途端に過去になるという性質を思う。 …でも、こうした概念的事情に対して、現在から経過を抜いたらどうかと考えてみたくなる。 経過抜きの今現在。 これはどうだろうか? - 2025年5月14日
- 2025年5月14日
 人間は自分が考えているような人間になるアール・ナイチンゲール気になる
人間は自分が考えているような人間になるアール・ナイチンゲール気になる - 2025年5月14日
- 2025年5月14日
- 2025年5月6日
 古代和歌の世界 (ちくま新書 191)鈴木日出男読み終わった@ 自宅日本神話でイザナギとイザナミの国産みの神話のおかげで、男女の贈答歌は「能動の男性」と「受動の女性」のイメージがついてたけれど、この本では女歌の特徴として反発のあるというのを指摘されていて、むしろB'zの稲葉浩志がつど綴っているような「弱い男」のイメージが走っていることが、贈答歌にあるのがわかった。
古代和歌の世界 (ちくま新書 191)鈴木日出男読み終わった@ 自宅日本神話でイザナギとイザナミの国産みの神話のおかげで、男女の贈答歌は「能動の男性」と「受動の女性」のイメージがついてたけれど、この本では女歌の特徴として反発のあるというのを指摘されていて、むしろB'zの稲葉浩志がつど綴っているような「弱い男」のイメージが走っていることが、贈答歌にあるのがわかった。 - 2025年5月4日
 日本文学史小西甚一読み終わった@ 自宅小西甚一の文学史はかねてより聞き及んでいたものだったが、ついに読めた。日本文学を雅と俗という極で見通す視線は、万葉集から古今和歌集への流れとも整合するし、理解しやすい道標として優秀。また、シナとの関係から和歌を眺めるのも楽しい。まさかシナからインストールした原初の事柄に、文藝の実力と政治的実力とを混合させる、ってのがあったとはね!確かに、奈良時代から先、平安朝なんかは詠歌の才はそのままその者の政治力となっていたと聞くし。
日本文学史小西甚一読み終わった@ 自宅小西甚一の文学史はかねてより聞き及んでいたものだったが、ついに読めた。日本文学を雅と俗という極で見通す視線は、万葉集から古今和歌集への流れとも整合するし、理解しやすい道標として優秀。また、シナとの関係から和歌を眺めるのも楽しい。まさかシナからインストールした原初の事柄に、文藝の実力と政治的実力とを混合させる、ってのがあったとはね!確かに、奈良時代から先、平安朝なんかは詠歌の才はそのままその者の政治力となっていたと聞くし。 - 2025年5月2日
 イルカと否定神学斎藤環読み終わった@ 自宅イルカと否定神学。こいつは人名に変換すると、ベイトソンとラカン。 読むとイルカ要素少なくて残念になるが、内容はグンバツ。 イルカはコンテクストの別名。ベイトソンの学習理論がイルカを例にしているのが由来。 学習はゼロに始まりⅣまである。 著者が推してるのはそのうちの学習IIと学習Ⅲ。 学習IIはコンテクストの学習で、学習Ⅲは他のコンテクストへの気づきから、自分のコンテクストを検討する、そんな学習。 精神医療でいったら、美容的な現状を生成しているコンテクストを変性させるきっかけみたいなものとして導入されているのが、こうしたイルカ。 否定神学のほうは、イルカが跳ねるためのエンジンとして、私たちがナチュラルに実装している言葉の働き。 関心したのは、著者がしきりにゴールや目標を設定「しない」ことが肝心だと説いていたこと。それは桎梏の別名らしい。
イルカと否定神学斎藤環読み終わった@ 自宅イルカと否定神学。こいつは人名に変換すると、ベイトソンとラカン。 読むとイルカ要素少なくて残念になるが、内容はグンバツ。 イルカはコンテクストの別名。ベイトソンの学習理論がイルカを例にしているのが由来。 学習はゼロに始まりⅣまである。 著者が推してるのはそのうちの学習IIと学習Ⅲ。 学習IIはコンテクストの学習で、学習Ⅲは他のコンテクストへの気づきから、自分のコンテクストを検討する、そんな学習。 精神医療でいったら、美容的な現状を生成しているコンテクストを変性させるきっかけみたいなものとして導入されているのが、こうしたイルカ。 否定神学のほうは、イルカが跳ねるためのエンジンとして、私たちがナチュラルに実装している言葉の働き。 関心したのは、著者がしきりにゴールや目標を設定「しない」ことが肝心だと説いていたこと。それは桎梏の別名らしい。 - 2025年5月2日
- 2025年5月1日
- 2025年4月30日
- 2025年4月29日
 言葉の誕生を科学する (河出文庫)小川洋子,岡ノ谷一夫気になる
言葉の誕生を科学する (河出文庫)小川洋子,岡ノ谷一夫気になる - 2025年4月25日
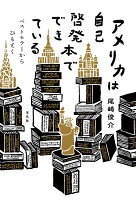 アメリカは自己啓発本でできている尾崎俊介読み終わったバチくそオモロい。アメリカが自己啓発本の源流やっつって、ピューリタンの教えと辻褄合わせるためにシュナイダーの理屈を引っ張ってきて、アメリカンな成功物語を起動させる。その後は第二次世界大戦による世代間闘争の勃発(シビル・ウォー!)。ここにできた大いなる溝を埋め合わせるように(いやいや、むしろ溝の拡大をうながしていたよ)自己啓発本が登場するわけですよ。いやはや、アメリカ史、じつに香ばしい。
アメリカは自己啓発本でできている尾崎俊介読み終わったバチくそオモロい。アメリカが自己啓発本の源流やっつって、ピューリタンの教えと辻褄合わせるためにシュナイダーの理屈を引っ張ってきて、アメリカンな成功物語を起動させる。その後は第二次世界大戦による世代間闘争の勃発(シビル・ウォー!)。ここにできた大いなる溝を埋め合わせるように(いやいや、むしろ溝の拡大をうながしていたよ)自己啓発本が登場するわけですよ。いやはや、アメリカ史、じつに香ばしい。
読み込み中...








