精神疾患をもつ人を,病院でない所で支援するときにまず読む本

31件の記録
 🪁@empowered_tako2025年3月22日読んでる@ 電車薬を預かって欲しいと頼まれても断る。代わりに支援者に電話をかけて欲しいとお願いされても断る。本人が望んでそう言ったとしても、自己責任感・自己関与感が得られるはずの場面でそれらを得られなくなる仕方では支援をしない。そういう線引きの仕方があるのかー! あと、書店で実物を見たら意外とでかい判型だったこと、冒頭に奥付が登場したことの2つでびっくりした
🪁@empowered_tako2025年3月22日読んでる@ 電車薬を預かって欲しいと頼まれても断る。代わりに支援者に電話をかけて欲しいとお願いされても断る。本人が望んでそう言ったとしても、自己責任感・自己関与感が得られるはずの場面でそれらを得られなくなる仕方では支援をしない。そういう線引きの仕方があるのかー! あと、書店で実物を見たら意外とでかい判型だったこと、冒頭に奥付が登場したことの2つでびっくりした



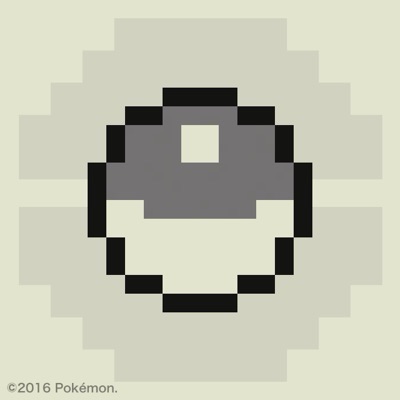

 ワタナベサトシ@mizio_s2025年3月17日読み終わった借りてきた感想図書館で借りて読了(4/14-25)。 職業として(プロが)患者の自宅を訪問して、限られた時間と回数で有効な支援につながる行動としてなにができるか・なにをすべきでないか、が具体例を挙げてまとめられている。同業者が参考にすべき手引書。 専門的な内容や特異な状況への対処マニュアル的な部分は一般の(職業として支援業に従事していない)人には関係がないところもあるが、例えば職場のさまざまな年代や役職の人間関係を円滑かつ効率的に進めるためのコミュニケーション術として、また家族関係や子育ての過程でとるべき言動や態度として、何かしらの参考になる部分は多いと感じた。 いっけん相手のためを思って為す行動が、実は相手の主体性を阻害し、奪い、依存を強めてしまう悪循環となってしまうといった負の連鎖は、しばしば日常で感じる歯痒さにも通じていると思う。 相手を尊重し、目指すべき方向を定め、互いに問題意識を共有する(あらかじめ前提を確認しておき、反れそうになったらそのつど原点に立ち返って再確認する)などの行為は、どんな場面でも使える覚えておきたい心構えであろう。
ワタナベサトシ@mizio_s2025年3月17日読み終わった借りてきた感想図書館で借りて読了(4/14-25)。 職業として(プロが)患者の自宅を訪問して、限られた時間と回数で有効な支援につながる行動としてなにができるか・なにをすべきでないか、が具体例を挙げてまとめられている。同業者が参考にすべき手引書。 専門的な内容や特異な状況への対処マニュアル的な部分は一般の(職業として支援業に従事していない)人には関係がないところもあるが、例えば職場のさまざまな年代や役職の人間関係を円滑かつ効率的に進めるためのコミュニケーション術として、また家族関係や子育ての過程でとるべき言動や態度として、何かしらの参考になる部分は多いと感じた。 いっけん相手のためを思って為す行動が、実は相手の主体性を阻害し、奪い、依存を強めてしまう悪循環となってしまうといった負の連鎖は、しばしば日常で感じる歯痒さにも通じていると思う。 相手を尊重し、目指すべき方向を定め、互いに問題意識を共有する(あらかじめ前提を確認しておき、反れそうになったらそのつど原点に立ち返って再確認する)などの行為は、どんな場面でも使える覚えておきたい心構えであろう。


 こんめ@conconcocon1900年1月1日かつて読んだ数年前にタイトルの状態になったので購入。 内容はどちらかというと看護職などが対象になっていたが、教育の現場でもなかなか参考になった。ヘルプとサポートの違いは都度振り返って自身に問いたい。 主体性を持ってもらうことの難しさは日々痛感している。声かけの工夫ひとつとは本当にその通り。 この本に書いてあった表現かは定かではないが、当人が「しっくりくること」が大事だな…と、これも日々思う。 定期的に読み返したい。
こんめ@conconcocon1900年1月1日かつて読んだ数年前にタイトルの状態になったので購入。 内容はどちらかというと看護職などが対象になっていたが、教育の現場でもなかなか参考になった。ヘルプとサポートの違いは都度振り返って自身に問いたい。 主体性を持ってもらうことの難しさは日々痛感している。声かけの工夫ひとつとは本当にその通り。 この本に書いてあった表現かは定かではないが、当人が「しっくりくること」が大事だな…と、これも日々思う。 定期的に読み返したい。



























