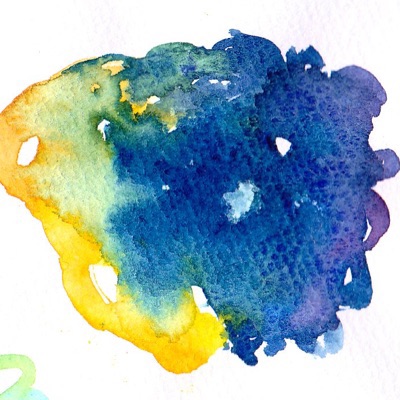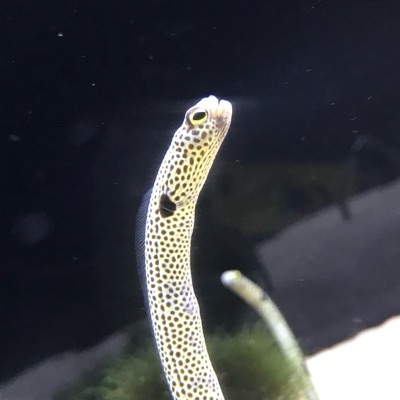嘔吐

52件の記録
 たま子@tama_co_co2026年2月5日読んでるロカンタンの日記を毎晩すこしずつ読み進めている。あれもこれも引用したいすきな文章だらけだけど、特にずっと忘れられない情景があって、こういうものと出会いたいからわたしも日記を書くのかもしれないなと思ったりする。 「独りきりの生活をしていると、物語るということさえ、どういうことなのか分からなくなる。本当らしさは友人とともに消えてしまう。出来事だって同様に、流れて行くがままだ。不意に人びとがあらわれ、話しかけ、去って行く。そしてこちらは脈絡のない話のなかにどっぷり沈みこむ。証言でもするとなったら最低の証人だろう。だがその埋め合わせに、すべての本当らしくないもの、カフェではとても信じられないようなものには、事欠かない。たとえば土曜日の午後四時ごろ、駅の工事現場におかれた板張りの歩道の端で、スカイブルーの服を着た小柄な女が一人、笑ってハンカチを振りながら、ちょこちょこと後ずさりをしていた。同時に、クリーム色のレインコートを着て、黄色い靴をはき、緑色の帽子をかぶった一人の黒人が、口笛を吹きながら道の角を曲がってきた。相変わらず後ずさりを続けていた女は、板掘に吊されていて夜になると人が明かりをつけにくる角灯の下で、その黒人とぶつかった。つまりそこには夕焼けの燃えるような空の下に、湿った木の臭いを強烈に放っているこの板堀、この角灯、黒人の腕に抱かれたこの金髪の小柄なお人好しの女が、同時にいたことになる。もし四、五人でそれを見ていたら、おそらくこの衝突、これらすべての優しい色の取り合わせ、まるで羽根布団のような青いきれいなコート、明るい色のレインコート、角灯の赤いガラスに気づいたことだろう。そしてわれわれは、この二人の顔にあらわれたぎょっとした子供のような表情を笑ったことだろう。 独りきりの男が笑いたくなることは稀である。その情景全体は私にとって、非常に強烈で、残忍とすら言えるような、ただし純粋な意味を与えられていた。ついで、それはばらばらになり、あとには角灯と板堀と空しか残らなかったが、それもまだかなり美しいものだった。一時間後になると、角灯は点されており、風が吹き、空は暗かった。もはや何も残ってはいなかった。」p17-18
たま子@tama_co_co2026年2月5日読んでるロカンタンの日記を毎晩すこしずつ読み進めている。あれもこれも引用したいすきな文章だらけだけど、特にずっと忘れられない情景があって、こういうものと出会いたいからわたしも日記を書くのかもしれないなと思ったりする。 「独りきりの生活をしていると、物語るということさえ、どういうことなのか分からなくなる。本当らしさは友人とともに消えてしまう。出来事だって同様に、流れて行くがままだ。不意に人びとがあらわれ、話しかけ、去って行く。そしてこちらは脈絡のない話のなかにどっぷり沈みこむ。証言でもするとなったら最低の証人だろう。だがその埋め合わせに、すべての本当らしくないもの、カフェではとても信じられないようなものには、事欠かない。たとえば土曜日の午後四時ごろ、駅の工事現場におかれた板張りの歩道の端で、スカイブルーの服を着た小柄な女が一人、笑ってハンカチを振りながら、ちょこちょこと後ずさりをしていた。同時に、クリーム色のレインコートを着て、黄色い靴をはき、緑色の帽子をかぶった一人の黒人が、口笛を吹きながら道の角を曲がってきた。相変わらず後ずさりを続けていた女は、板掘に吊されていて夜になると人が明かりをつけにくる角灯の下で、その黒人とぶつかった。つまりそこには夕焼けの燃えるような空の下に、湿った木の臭いを強烈に放っているこの板堀、この角灯、黒人の腕に抱かれたこの金髪の小柄なお人好しの女が、同時にいたことになる。もし四、五人でそれを見ていたら、おそらくこの衝突、これらすべての優しい色の取り合わせ、まるで羽根布団のような青いきれいなコート、明るい色のレインコート、角灯の赤いガラスに気づいたことだろう。そしてわれわれは、この二人の顔にあらわれたぎょっとした子供のような表情を笑ったことだろう。 独りきりの男が笑いたくなることは稀である。その情景全体は私にとって、非常に強烈で、残忍とすら言えるような、ただし純粋な意味を与えられていた。ついで、それはばらばらになり、あとには角灯と板堀と空しか残らなかったが、それもまだかなり美しいものだった。一時間後になると、角灯は点されており、風が吹き、空は暗かった。もはや何も残ってはいなかった。」p17-18









 Pha3@Pha32025年11月23日読み終わったモノの存在の観察で嘔吐の原因を知った彼に追い討ちをかけたのは、アニーからも必要でなくなったことだ。 さらに言えば、ロカンタンが(独学者のように事件を起こす訳でもなく)受け身であったことで、彼は切り札を失い彷徨う。 一つの光明として、レコードに吹き込まれた歌声にヒントをもらって本を書こうと意気込むのだが、 実際、他者との関わりを見失って苦悩を抱えて、自分を書き留める作品や作業で救われる人は案外多いのではないかと思った。
Pha3@Pha32025年11月23日読み終わったモノの存在の観察で嘔吐の原因を知った彼に追い討ちをかけたのは、アニーからも必要でなくなったことだ。 さらに言えば、ロカンタンが(独学者のように事件を起こす訳でもなく)受け身であったことで、彼は切り札を失い彷徨う。 一つの光明として、レコードに吹き込まれた歌声にヒントをもらって本を書こうと意気込むのだが、 実際、他者との関わりを見失って苦悩を抱えて、自分を書き留める作品や作業で救われる人は案外多いのではないかと思った。



 こここ@continue_reading2025年9月6日読み始めた中島義道『哲学の教科書』で取り上げられており、読んでみたくなった。 表紙、カバーデザインの雰囲気と手触り、紙質も好きだ。 本の内容は、気をつけないと暗くなりそうだが。。
こここ@continue_reading2025年9月6日読み始めた中島義道『哲学の教科書』で取り上げられており、読んでみたくなった。 表紙、カバーデザインの雰囲気と手触り、紙質も好きだ。 本の内容は、気をつけないと暗くなりそうだが。。









 monami@kiroku_library2025年7月16日読み終わった公転くらいの速度で読み進めている『失われた時を求めて 2』が割と深く絡んでる話だったので、読めてよかった 終わりかた好きだったなぁ そして、そういうことが言いたい話じゃないと頭で理解はしつつも、「暇」って人を不健全な思考にまで至らしめるよなぁと思った
monami@kiroku_library2025年7月16日読み終わった公転くらいの速度で読み進めている『失われた時を求めて 2』が割と深く絡んでる話だったので、読めてよかった 終わりかた好きだったなぁ そして、そういうことが言いたい話じゃないと頭で理解はしつつも、「暇」って人を不健全な思考にまで至らしめるよなぁと思った










 monami@kiroku_library2025年7月9日読み始めた完全に夏バテ、なのかしら。 とにかく起きた瞬間から頭が痛くて、結局なにも手につかなかった。 横になると寝てしまって、最終的に金縛りにあうまで眠った。沢山夢をみた。 起きても頭痛は悪化していた。 冷房もつけたし、水も飲んだ。アイスコーヒを飲んで、しょっぱいものだって食べた。冷えピタをつけたり、お風呂に入って血行を良くしたりもした。でも何も治らず、気づけば深夜2時。 ゴミ捨てに行き、ついでにコンビニに行って明日の朝ごはんを買った。 歩いていると軽い吐き気みたいな、気持ち悪さがある。 さっきまで本で読んでいて、しかし身の入らなかったセネカの『生の短さについて』をAudibleで聞いてみた。 「ただちに生きよ」 幼少から蒲柳(今日覚えた言葉)の質だったセネカの言葉なのだからと、どうにか聞き続けるも吐き気は増すばかり。 コンビニからの帰り道、そうだ、今こそ『嘔吐』を読めばいいじゃん、と天啓のようにひらめいた。 そう思い立つと、この軽い吐き気すらおあつらえ向きに思えてくる。 さて、今は3時10分。 相変わらず頭痛も吐き気もある。 読むぞ。
monami@kiroku_library2025年7月9日読み始めた完全に夏バテ、なのかしら。 とにかく起きた瞬間から頭が痛くて、結局なにも手につかなかった。 横になると寝てしまって、最終的に金縛りにあうまで眠った。沢山夢をみた。 起きても頭痛は悪化していた。 冷房もつけたし、水も飲んだ。アイスコーヒを飲んで、しょっぱいものだって食べた。冷えピタをつけたり、お風呂に入って血行を良くしたりもした。でも何も治らず、気づけば深夜2時。 ゴミ捨てに行き、ついでにコンビニに行って明日の朝ごはんを買った。 歩いていると軽い吐き気みたいな、気持ち悪さがある。 さっきまで本で読んでいて、しかし身の入らなかったセネカの『生の短さについて』をAudibleで聞いてみた。 「ただちに生きよ」 幼少から蒲柳(今日覚えた言葉)の質だったセネカの言葉なのだからと、どうにか聞き続けるも吐き気は増すばかり。 コンビニからの帰り道、そうだ、今こそ『嘔吐』を読めばいいじゃん、と天啓のようにひらめいた。 そう思い立つと、この軽い吐き気すらおあつらえ向きに思えてくる。 さて、今は3時10分。 相変わらず頭痛も吐き気もある。 読むぞ。









 aio@icecreamread2025年4月5日ちょっと開いた本当は大学生の時に読みたいと思っており、出会いを求めてもいたが、出会えなかった。なんかすごく高かった印象があったが、定価はそんなこともないのだね。 ひとまず最初数ページと後書きのみ読んだ。今回はいったん置いておいて、また時が来たら読もうかと思う(果たしてその時は来るのか)
aio@icecreamread2025年4月5日ちょっと開いた本当は大学生の時に読みたいと思っており、出会いを求めてもいたが、出会えなかった。なんかすごく高かった印象があったが、定価はそんなこともないのだね。 ひとまず最初数ページと後書きのみ読んだ。今回はいったん置いておいて、また時が来たら読もうかと思う(果たしてその時は来るのか)

 CandidE@araxia2025年3月25日読み終わった久しぶりにマインドセットを履き違えた読書となった。主人公の作中内思索と現代日本人の私との感性における隔たりやギャップが想定以上に大きく衝撃を受ける。 『嘔吐』は、謂わばコンセプト重視の作品で、美化すれば、小説という形式を借りた哲学的探求のスケッチブックという感じであった。なんというか、学生時代にあった、右も左もわからずに高度な専門書や哲学書の類を読み進める感覚が久しぶりに蘇った。率直に言えば一種の修行であり、部分部分で知的興奮や普通に面白さを得られたものの、個人的には読み始めと読み終わりの1/4ずつが特に苦行であった。嘔吐。 どうなんだろう、この読みにくさは、村上春樹の作品で全く合わない・シンクロしない・興味が持てない時に味わう感じに近しい。本作の踏襲だろうか。あるいは、マインドセットを間違えたという点では、『嘔吐』とは毛色が違うが、近年では鈴木健『なめらかな社会とその敵』とか、町田康『ホサナ』とかで体感したように記憶している。まあ前者に関しては、昨今はAIと一緒に逐一内容を精査しつつ理解を深めながら読み進めることができる時代なので、それはそれでモダーンな読書を楽しめそうだ。 差し詰め本作は、1938年当時におけるフランスの知的エリートの意識を記録した文化人類学的資料として読むことができる。あるいは、サルトルが自らの哲学的思考を物語形式で実験している過程として思想史的価値がある。また、文学史的には「意識の流れ」から「ヌーヴォー・ロマン」へと発展する過渡期の作品として、さらには、後のポストモダン文学が抱えることになる「コンセプトが作品の文学や芸術性を圧倒する」というような病を先取りした作風として哲学的・芸術的読書体験を楽しむことができる、、、って、どういうことやねん?・なんやねん? みたいな感じで繰り返しになるけれども、部分的には面白い、というか、めっちゃ面白い。それで別にぶっ飛びすぎていて支離滅裂で読めないということは一切ない。しかし、気軽な読書には正直あまり向いていない。サルトルを舐めてはいけない(戒め) まずは訳注だけをざっと眺め、主人公が1930年代のフランスの左翼知識人であることと、この小説が『存在と無』のスピンオフであることをよくよく肝に銘じ本文に入ることを推奨したい。さらに余力があれば、ハイデッガーの『存在と時間』における「本来性/非本来性」の議論にも目を通し、当時の読者にとっての革新性をキラ☆キラ想像しながら読み進めることで味わいが一層深まるかもしれない。嘔吐。
CandidE@araxia2025年3月25日読み終わった久しぶりにマインドセットを履き違えた読書となった。主人公の作中内思索と現代日本人の私との感性における隔たりやギャップが想定以上に大きく衝撃を受ける。 『嘔吐』は、謂わばコンセプト重視の作品で、美化すれば、小説という形式を借りた哲学的探求のスケッチブックという感じであった。なんというか、学生時代にあった、右も左もわからずに高度な専門書や哲学書の類を読み進める感覚が久しぶりに蘇った。率直に言えば一種の修行であり、部分部分で知的興奮や普通に面白さを得られたものの、個人的には読み始めと読み終わりの1/4ずつが特に苦行であった。嘔吐。 どうなんだろう、この読みにくさは、村上春樹の作品で全く合わない・シンクロしない・興味が持てない時に味わう感じに近しい。本作の踏襲だろうか。あるいは、マインドセットを間違えたという点では、『嘔吐』とは毛色が違うが、近年では鈴木健『なめらかな社会とその敵』とか、町田康『ホサナ』とかで体感したように記憶している。まあ前者に関しては、昨今はAIと一緒に逐一内容を精査しつつ理解を深めながら読み進めることができる時代なので、それはそれでモダーンな読書を楽しめそうだ。 差し詰め本作は、1938年当時におけるフランスの知的エリートの意識を記録した文化人類学的資料として読むことができる。あるいは、サルトルが自らの哲学的思考を物語形式で実験している過程として思想史的価値がある。また、文学史的には「意識の流れ」から「ヌーヴォー・ロマン」へと発展する過渡期の作品として、さらには、後のポストモダン文学が抱えることになる「コンセプトが作品の文学や芸術性を圧倒する」というような病を先取りした作風として哲学的・芸術的読書体験を楽しむことができる、、、って、どういうことやねん?・なんやねん? みたいな感じで繰り返しになるけれども、部分的には面白い、というか、めっちゃ面白い。それで別にぶっ飛びすぎていて支離滅裂で読めないということは一切ない。しかし、気軽な読書には正直あまり向いていない。サルトルを舐めてはいけない(戒め) まずは訳注だけをざっと眺め、主人公が1930年代のフランスの左翼知識人であることと、この小説が『存在と無』のスピンオフであることをよくよく肝に銘じ本文に入ることを推奨したい。さらに余力があれば、ハイデッガーの『存在と時間』における「本来性/非本来性」の議論にも目を通し、当時の読者にとっての革新性をキラ☆キラ想像しながら読み進めることで味わいが一層深まるかもしれない。嘔吐。