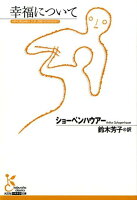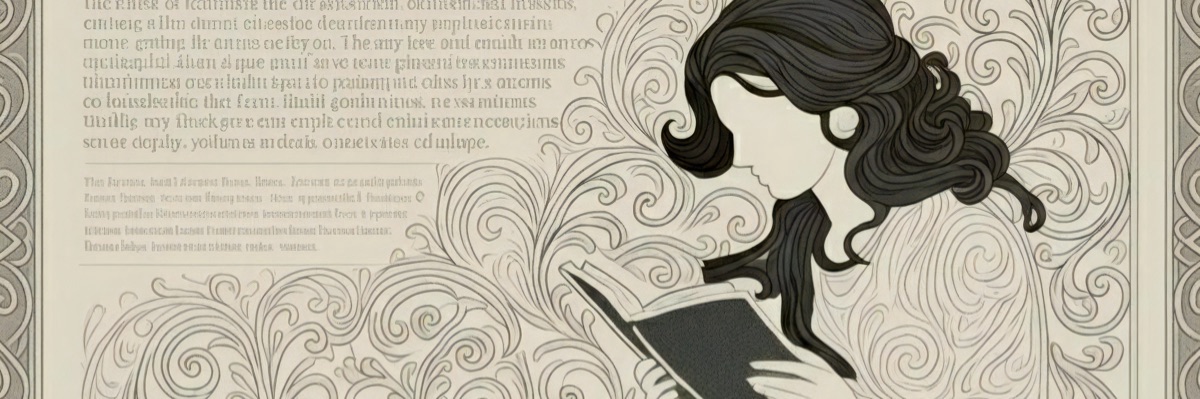

CandidE
@araxia
読書記録を主として。読めるときに読む。読めるうちに読む。
- 2025年10月5日
 読み終わった「徴がある? なら死ぬがいい! 秀でた徴がついている? なら滅びるがいい、それが自らに秀でた徴をつける者の報償なのだから!」(『ソル・フィロテアへの返信』) もう、めちゃくちゃアグレッシブ。言葉の荒波がドドドッと押し寄せる。その波を自在に乗りこなす彼女の魂にしびれた。完全にやられた。この本に出会えて本当に良かった。 ソル・フアナ。ご存知だろうか? 私は知らなかった。 17世紀メキシコの修道女にして、桁外れのセンスと鋭敏なインテリジェンス、そして燃え上がるスピリッツを内に秘めた詩人であり作家。生涯を修道院という檻の中で過ごしながら、彼女は文才を武器にも防具にも変え、詩や劇作、手紙という遠隔攻撃で世間を魅了した。メキシコでは紙幣にも描かれたスーパースターである。 本書には、彼女の詩と2通の手紙が収められている。 とくに手紙がすごい。「圧」が物凄い。完璧に組み上げられた文章の中に、知性と感情がギュギュギュッと圧縮され、激しい怒りではなく、論理と皮肉で世界をねじ伏せる強さと矜持に満ちている。 冒頭に引用した「秀でた徴があるなら滅びるがいい」という一節が放つ気炎に、思わず胸を打たれ、涙がこぼれる。痛みを推進力に、反抗を共鳴に変える力。みずみずしい感性が隅々にまで息づいている。それは文学を超えた、高貴な生命現象だ。300年の時を超え、いまもビリビリする鮮烈な電撃。生意気。 その魅力は、読めばきっとわかる。私のこのテンションがわかる。不意に笑って、元気が湧いて、勇気をもらって、そして少し泣いてしまう。訳者の素晴らしい解説とまえがきとあとがきとともに、ぜひ堪能してほしい。きっと誰もが、彼女を愛さずにはいられない。 フアナよ、甦れ。
読み終わった「徴がある? なら死ぬがいい! 秀でた徴がついている? なら滅びるがいい、それが自らに秀でた徴をつける者の報償なのだから!」(『ソル・フィロテアへの返信』) もう、めちゃくちゃアグレッシブ。言葉の荒波がドドドッと押し寄せる。その波を自在に乗りこなす彼女の魂にしびれた。完全にやられた。この本に出会えて本当に良かった。 ソル・フアナ。ご存知だろうか? 私は知らなかった。 17世紀メキシコの修道女にして、桁外れのセンスと鋭敏なインテリジェンス、そして燃え上がるスピリッツを内に秘めた詩人であり作家。生涯を修道院という檻の中で過ごしながら、彼女は文才を武器にも防具にも変え、詩や劇作、手紙という遠隔攻撃で世間を魅了した。メキシコでは紙幣にも描かれたスーパースターである。 本書には、彼女の詩と2通の手紙が収められている。 とくに手紙がすごい。「圧」が物凄い。完璧に組み上げられた文章の中に、知性と感情がギュギュギュッと圧縮され、激しい怒りではなく、論理と皮肉で世界をねじ伏せる強さと矜持に満ちている。 冒頭に引用した「秀でた徴があるなら滅びるがいい」という一節が放つ気炎に、思わず胸を打たれ、涙がこぼれる。痛みを推進力に、反抗を共鳴に変える力。みずみずしい感性が隅々にまで息づいている。それは文学を超えた、高貴な生命現象だ。300年の時を超え、いまもビリビリする鮮烈な電撃。生意気。 その魅力は、読めばきっとわかる。私のこのテンションがわかる。不意に笑って、元気が湧いて、勇気をもらって、そして少し泣いてしまう。訳者の素晴らしい解説とまえがきとあとがきとともに、ぜひ堪能してほしい。きっと誰もが、彼女を愛さずにはいられない。 フアナよ、甦れ。 - 2025年10月4日
- 2025年10月3日
 饗宴プラトン,中澤務読み終わった素晴らしいなあ。以下、長い感想。悪しからず。 ーーーーーー 本書を読み始めて、まず心を掴まれるのは場の雰囲気である。前夜の深酒がまだ抜けぬゆえに、今日は酩酊を避け、嗜む程度に留めよう。そうした合意のもとに始まる静かな会合は、粗野でありながら豪奢でもあり、ほどよい緊張と弛緩を湛えている。この寛ぎのある知的共同体の空気には、現代ではなかなか見られない、自然体で上品な魅力がある。端的に優雅である。 そして彼らが語る愛、そして「エロス」とは、単なる恋愛感情ではなく、より遍く我々が「生きたい」「もっと知りたい」と感じて湧き上がる、根源的なエネルギーそのものである。そのエロスの力は、純粋な高みや理想へ向かう上昇よりも、さらに複雑な運動として捉えられる。 本稿では、このギリシャ的な概念を指して、文脈に応じて「愛」と「エロス」という言葉を使い分けていきたい。 そのなかで、まず印象に残ったのは、アリストファネスの語る半身の神話だ。 「愛する人と一緒になって一つに溶け合い、二つではなく一つの存在になるということだ。なぜなら、これこそが俺たち人間の太古の姿であり、俺たち人間は一つの全体であったのだから。そして、この全体性への欲求と追求をあらわす言葉こそ〈エロス〉なのだ。すでに述べたとおり、俺たち人間は、かつては一つの存在だった。しかし現在は、罪を犯したために、神によって二つに引き裂かれている。」(第五章 アリストファネスの話) だから今でも、人は失われた自分の片割れを必死に探し求めている、と語るこの愛の起源には、愛の根源的な哀しみや切なさ、誰かを求める切実な気持ちが喚起され、素朴に、強く心を揺さぶられる。 さらにプラトンは、この肉体的な欠落の情を、深い次元へと導いていく。 「さまざまな美しいものから出発し、かの美を目指して、たゆまぬ上昇をしていくということなのだ。その姿は、さながら梯子を使って登る者のようだ。すなわち、一つの美しい体から二つの美しい体へ、二つの美しい体からすべての美しい体へと進んでいき、次いで美しい体から美しいふるまいへ、そしてふるまいからさまざまな美しい知へ、そしてついには、さまざまな知からかの知へと到達するのだ。それはまさにかの美そのものの知であり、彼はついに美それ自体を知るに至るのである」(第八章 ソクラテスの語り) このディオティマの「美の梯子」は、エロスの道の究極の奥義であり、プラトンのイデア論の表明でもある。ここで重要なことは、このエロスが、欲望の抑圧ではなく、知を生み出す推進力であるということ。そして上記の「もっと知りたい」「より善きものを生み出したい」という、たゆまぬ精神の上昇指向は、肉体の否定を意味しない。むしろエロスは、肉体と精神の両極を保持したまま、そのあいだの緊張を生きる力である。 そのようなディオティマのエロスの奥義を、まさに体現している人物(アイコン)としてソクラテスが描かれる。彼の内にあるエロスの情熱は決して暴走せず、知性によって完璧にコントロールされ、その理性は氷のように冷たいのではなく、マグマのような情熱を持続させるための知恵の結晶である。 そのソクラテスに、若く美しいアルキビアデスは熱烈に惹かれる。もちろん彼が求めたのは、ソクラテスの肉体というより、「熱を保ちながら燃え尽きない火」のような知性への憧れであろう。ここには、「手に入れたいけれど、手に入らないものにこそ惹かれる」という人間の矛盾した渇きの悦楽が垣間見える。 『饗宴』が面白いのは、このようにプラトンの理想的な愛の思想が語られたかと思うと、アルキビアデスが登場することで、物語が一気に嫉妬や憧れといった泥臭い感情の人間世界に引き戻される点にある。このように愛とは、理想へ向かう上昇と、現実の情念に戻る下降を、静止することなく往復する運動である。この昇華と混沌の永久運動の中途にこそ、エロスの真の価値があると私は考える。 エロスは、知性が人間的な弱さや懶惰を恐れず、また肉体的な欲望が知性を拒まない、そのようなバランス、微妙な熱の均衡に支えられている。ここでいう「懶惰」や、さらに言えば「腐敗」とは、単にだらしなく弛緩するとか、朽ちていくといったネガティブな意味だけではない。それは、肉体の甘美な腐敗の匂いを帯びた感覚で、古代ギリシアではそれこそがエロスの香りにふさわしい、人間が肉体をもち、いずれ死ぬ存在であることの厳かな認証である。 ゆえに理性は、この朽ちゆく肉体や精神の腐敗から目をそらすのではなく、それと共に生きることを選ぶ。なぜなら、ディオティマが語るエロスが目指す「美しいものの中で、生み、子をなすこと」(第八章 ソクラテスの語り)とは、まさに、滅びゆく肉体を通して、子孫や知恵といった不死なるものを後世に残していく運動に他ならないからである。 「エロスが子を生むことを求めるのはなぜか。それは、死をまぬがれぬ人間にとって、生むという営みは、永遠と不死にあずかる手段だからだ。そして、エロスはよいものだけでなく、不死をも欲しているはずだ。この点は、これまでの同意から明らかだ。なぜなら、エロスは、よいものを永遠に自分のものにすることを求めていたのだからな。この理由により、エロスは不死をも求めていると考えなければならぬわけだ」(第八章 ソクラテスの語り) かくして『饗宴』は、愛について深く語りながら、同時に「思考や哲学にとってちょうどいい塩梅」について考察している書でもある。理念へと向かおうとする上昇の動きと、生々しい肉体の混沌へと引き戻される動き。その終わりなきエロスの往復運動の中で、人間の知性は、冷たすぎず熱すぎず、「穏やかな熱」を保つことで発酵し、ゆるやかに成熟していく。 その穏やかな熱、すなわち朽ちゆく肉体と永遠を希求する精神との緊張が美しく釣り合う一点。その均衡点に宿る核の熱こそが、プラトンが我々に提示する「エロス」の姿のように思われる。
饗宴プラトン,中澤務読み終わった素晴らしいなあ。以下、長い感想。悪しからず。 ーーーーーー 本書を読み始めて、まず心を掴まれるのは場の雰囲気である。前夜の深酒がまだ抜けぬゆえに、今日は酩酊を避け、嗜む程度に留めよう。そうした合意のもとに始まる静かな会合は、粗野でありながら豪奢でもあり、ほどよい緊張と弛緩を湛えている。この寛ぎのある知的共同体の空気には、現代ではなかなか見られない、自然体で上品な魅力がある。端的に優雅である。 そして彼らが語る愛、そして「エロス」とは、単なる恋愛感情ではなく、より遍く我々が「生きたい」「もっと知りたい」と感じて湧き上がる、根源的なエネルギーそのものである。そのエロスの力は、純粋な高みや理想へ向かう上昇よりも、さらに複雑な運動として捉えられる。 本稿では、このギリシャ的な概念を指して、文脈に応じて「愛」と「エロス」という言葉を使い分けていきたい。 そのなかで、まず印象に残ったのは、アリストファネスの語る半身の神話だ。 「愛する人と一緒になって一つに溶け合い、二つではなく一つの存在になるということだ。なぜなら、これこそが俺たち人間の太古の姿であり、俺たち人間は一つの全体であったのだから。そして、この全体性への欲求と追求をあらわす言葉こそ〈エロス〉なのだ。すでに述べたとおり、俺たち人間は、かつては一つの存在だった。しかし現在は、罪を犯したために、神によって二つに引き裂かれている。」(第五章 アリストファネスの話) だから今でも、人は失われた自分の片割れを必死に探し求めている、と語るこの愛の起源には、愛の根源的な哀しみや切なさ、誰かを求める切実な気持ちが喚起され、素朴に、強く心を揺さぶられる。 さらにプラトンは、この肉体的な欠落の情を、深い次元へと導いていく。 「さまざまな美しいものから出発し、かの美を目指して、たゆまぬ上昇をしていくということなのだ。その姿は、さながら梯子を使って登る者のようだ。すなわち、一つの美しい体から二つの美しい体へ、二つの美しい体からすべての美しい体へと進んでいき、次いで美しい体から美しいふるまいへ、そしてふるまいからさまざまな美しい知へ、そしてついには、さまざまな知からかの知へと到達するのだ。それはまさにかの美そのものの知であり、彼はついに美それ自体を知るに至るのである」(第八章 ソクラテスの語り) このディオティマの「美の梯子」は、エロスの道の究極の奥義であり、プラトンのイデア論の表明でもある。ここで重要なことは、このエロスが、欲望の抑圧ではなく、知を生み出す推進力であるということ。そして上記の「もっと知りたい」「より善きものを生み出したい」という、たゆまぬ精神の上昇指向は、肉体の否定を意味しない。むしろエロスは、肉体と精神の両極を保持したまま、そのあいだの緊張を生きる力である。 そのようなディオティマのエロスの奥義を、まさに体現している人物(アイコン)としてソクラテスが描かれる。彼の内にあるエロスの情熱は決して暴走せず、知性によって完璧にコントロールされ、その理性は氷のように冷たいのではなく、マグマのような情熱を持続させるための知恵の結晶である。 そのソクラテスに、若く美しいアルキビアデスは熱烈に惹かれる。もちろん彼が求めたのは、ソクラテスの肉体というより、「熱を保ちながら燃え尽きない火」のような知性への憧れであろう。ここには、「手に入れたいけれど、手に入らないものにこそ惹かれる」という人間の矛盾した渇きの悦楽が垣間見える。 『饗宴』が面白いのは、このようにプラトンの理想的な愛の思想が語られたかと思うと、アルキビアデスが登場することで、物語が一気に嫉妬や憧れといった泥臭い感情の人間世界に引き戻される点にある。このように愛とは、理想へ向かう上昇と、現実の情念に戻る下降を、静止することなく往復する運動である。この昇華と混沌の永久運動の中途にこそ、エロスの真の価値があると私は考える。 エロスは、知性が人間的な弱さや懶惰を恐れず、また肉体的な欲望が知性を拒まない、そのようなバランス、微妙な熱の均衡に支えられている。ここでいう「懶惰」や、さらに言えば「腐敗」とは、単にだらしなく弛緩するとか、朽ちていくといったネガティブな意味だけではない。それは、肉体の甘美な腐敗の匂いを帯びた感覚で、古代ギリシアではそれこそがエロスの香りにふさわしい、人間が肉体をもち、いずれ死ぬ存在であることの厳かな認証である。 ゆえに理性は、この朽ちゆく肉体や精神の腐敗から目をそらすのではなく、それと共に生きることを選ぶ。なぜなら、ディオティマが語るエロスが目指す「美しいものの中で、生み、子をなすこと」(第八章 ソクラテスの語り)とは、まさに、滅びゆく肉体を通して、子孫や知恵といった不死なるものを後世に残していく運動に他ならないからである。 「エロスが子を生むことを求めるのはなぜか。それは、死をまぬがれぬ人間にとって、生むという営みは、永遠と不死にあずかる手段だからだ。そして、エロスはよいものだけでなく、不死をも欲しているはずだ。この点は、これまでの同意から明らかだ。なぜなら、エロスは、よいものを永遠に自分のものにすることを求めていたのだからな。この理由により、エロスは不死をも求めていると考えなければならぬわけだ」(第八章 ソクラテスの語り) かくして『饗宴』は、愛について深く語りながら、同時に「思考や哲学にとってちょうどいい塩梅」について考察している書でもある。理念へと向かおうとする上昇の動きと、生々しい肉体の混沌へと引き戻される動き。その終わりなきエロスの往復運動の中で、人間の知性は、冷たすぎず熱すぎず、「穏やかな熱」を保つことで発酵し、ゆるやかに成熟していく。 その穏やかな熱、すなわち朽ちゆく肉体と永遠を希求する精神との緊張が美しく釣り合う一点。その均衡点に宿る核の熱こそが、プラトンが我々に提示する「エロス」の姿のように思われる。 - 2025年10月2日
 シークレット・エージェントコンラッド,高橋和久読み終わった癖が強くておすすめしづらいが、おもしろかった。深みがあった。 ーーーーーー 以下ネタバレを含む。 ーーーーーー 『シークレット・エージェント』の前半は、正直つらい。コンラッド特有の緻密な描写は気怠く、興味を惹かれない人物たちが断片的に現れては消え、政治や思想のレイヤーだけが積み重なっていく。タイトルから期待するエンタメは一切なく、華も求心力もない。私の察しの悪さも手伝って、ドラマへの導線がまったく見えず、物語は湿った霧のなかで空転し続ける。ギブアップしなかった自分を褒めてあげたい。 しかし後半をとうに過ぎた11章を境に、すべてが反転する。爆発する。ヴァーロックとウィニー、そしてスティーヴィーと義母の小さな家族に焦点が収束し、前半の散漫が、読者のまともな期待と感覚を鈍らせるための緻密な下準備だったと気づいて、めっちゃびっくりした。感情投資に思わぬ利子がついた嬉しさと、遅い、もっとシュッとやれ、という苛立ちが同居する。この二律背反こそ、今回のコンラッドの巧みだと思う。 その終盤の凄味は、人が壊れる順序のリアルにある。夫は、妻が弟を失っても夫婦を続けられると思い込むほど家族に無理解で、その無自覚が機械じみたエージェント本来の冷酷さを露わにする。一方の妻は、弟と母への共依存から解き放たれた瞬間、反動で一気に流され、狂気へ傾く。そのとき周囲に頼れる人間はおらず、ろくでもないクズだけが寄ってくる。その必然のリアルは、社会の設計が生み出す環境悪の縮図だ。夫の無理解と妻の共依存が平穏の基盤であった。そのように、この世界の各人は自分の立場では合理的に、局所最適に振る舞うのに、俯瞰すると陳腐で怠惰で性悪で、誰ひとり全体の破滅を止められない。ウィニーの刃も、その後の転落も、悲劇であると同時に、そうなるよなー、と納得してしまう。哀しみが沁みる。この世に生きているのが嫌になるほどエグい。 結句、本書で描かれるのは、奇矯な悪人の悲劇ではない。愛する作法を知るに到らない普通の人々が、制度と惰性の歯車の中で少しずつ壊れていく過程だ。コンラッドは物語前半で読者を意図的に撹乱し、退屈で麻痺させたうえで、鈍刀の一撃を入れる。痛みは鋭くはないが、骨の髄まで響く。その疼痛の好き嫌いを超えて残るのは、凡庸が累積した果てに生まれる暴力の気配、そして地獄の温床である。 前半部への不満は消えない。マジでどうにかしてほしい。けれど、その停滞があったからこそ、後半の真っ暗な人間ドラマは容赦なく突き刺さった。苦行のあとに訪れる痛みと哀しみの法外な利息が、この小説の唯一無二の魅力だと思う。ずるい。だるい。でも、いやあ、意外に味わい深かった。
シークレット・エージェントコンラッド,高橋和久読み終わった癖が強くておすすめしづらいが、おもしろかった。深みがあった。 ーーーーーー 以下ネタバレを含む。 ーーーーーー 『シークレット・エージェント』の前半は、正直つらい。コンラッド特有の緻密な描写は気怠く、興味を惹かれない人物たちが断片的に現れては消え、政治や思想のレイヤーだけが積み重なっていく。タイトルから期待するエンタメは一切なく、華も求心力もない。私の察しの悪さも手伝って、ドラマへの導線がまったく見えず、物語は湿った霧のなかで空転し続ける。ギブアップしなかった自分を褒めてあげたい。 しかし後半をとうに過ぎた11章を境に、すべてが反転する。爆発する。ヴァーロックとウィニー、そしてスティーヴィーと義母の小さな家族に焦点が収束し、前半の散漫が、読者のまともな期待と感覚を鈍らせるための緻密な下準備だったと気づいて、めっちゃびっくりした。感情投資に思わぬ利子がついた嬉しさと、遅い、もっとシュッとやれ、という苛立ちが同居する。この二律背反こそ、今回のコンラッドの巧みだと思う。 その終盤の凄味は、人が壊れる順序のリアルにある。夫は、妻が弟を失っても夫婦を続けられると思い込むほど家族に無理解で、その無自覚が機械じみたエージェント本来の冷酷さを露わにする。一方の妻は、弟と母への共依存から解き放たれた瞬間、反動で一気に流され、狂気へ傾く。そのとき周囲に頼れる人間はおらず、ろくでもないクズだけが寄ってくる。その必然のリアルは、社会の設計が生み出す環境悪の縮図だ。夫の無理解と妻の共依存が平穏の基盤であった。そのように、この世界の各人は自分の立場では合理的に、局所最適に振る舞うのに、俯瞰すると陳腐で怠惰で性悪で、誰ひとり全体の破滅を止められない。ウィニーの刃も、その後の転落も、悲劇であると同時に、そうなるよなー、と納得してしまう。哀しみが沁みる。この世に生きているのが嫌になるほどエグい。 結句、本書で描かれるのは、奇矯な悪人の悲劇ではない。愛する作法を知るに到らない普通の人々が、制度と惰性の歯車の中で少しずつ壊れていく過程だ。コンラッドは物語前半で読者を意図的に撹乱し、退屈で麻痺させたうえで、鈍刀の一撃を入れる。痛みは鋭くはないが、骨の髄まで響く。その疼痛の好き嫌いを超えて残るのは、凡庸が累積した果てに生まれる暴力の気配、そして地獄の温床である。 前半部への不満は消えない。マジでどうにかしてほしい。けれど、その停滞があったからこそ、後半の真っ暗な人間ドラマは容赦なく突き刺さった。苦行のあとに訪れる痛みと哀しみの法外な利息が、この小説の唯一無二の魅力だと思う。ずるい。だるい。でも、いやあ、意外に味わい深かった。 - 2025年9月30日
 青春・台風コンラッド読み終わった『青春』と『台風』、どちらも好かった。まあ『青春』の方がややドラマというかロマンというか、淡い熱があって好かった。両者には対比的な構造があり、炎と水、情熱の残像と沈黙の実在。その間に大海原に対する人間の小ささが横たわる。
青春・台風コンラッド読み終わった『青春』と『台風』、どちらも好かった。まあ『青春』の方がややドラマというかロマンというか、淡い熱があって好かった。両者には対比的な構造があり、炎と水、情熱の残像と沈黙の実在。その間に大海原に対する人間の小ささが横たわる。 - 2025年9月29日
 闇の奥ジョウゼフ・コンラッド,黒原敏行読み終わっためっちゃいい、めっちゃ面白い。訳もわかりやすい。読後感がボワボワして素晴らしい。構造がスマートでとても素敵。 虚構の連鎖と意味の増幅装置の中心に「闇の奥」はあって、それは深淵であり、無限だと思った。The horror! ーーーーー 以下、ネタバレを含む。 ーーーーー 『闇の奥』は、理解の届かぬまま進んでいく、その物語構造自体に魅力がある小説だ。 クルツは実像ではなく伝聞によって膨張し、最後まで輪郭を結ばない。読者は説明を与えられず、ただ宙吊りにされる不穏のみが募る。この「不完全さ」こそが、逆説的に作品の完成度を高めているように強く思う。 例えばこの構造を象徴するのが、ジャングルの奥地に突如現れるロシア人。弓矢の雨をかいくぐって登場し、クルツの使者かと思えば、単なる信者であり、ただただ狂気に魅せられた若者にすぎない。その「脈絡のなさ」が小説全体をぐらつかせ、不気味な余白を生む。秩序への期待を攪乱する異物の登場によって、クルツはもはや「人物」ではなく、「信仰や噂を増幅する装置」として機能する。実体は遠ざかり、神話が肥大化していく。 そして終盤にて、クルツはついに掴みどころのないまま舞台から退場し、物語は見事に宙吊りまま幕を閉じる。説明を求める欲望そのものが物語を駆動し、その軌跡は入れ子のように無限へと開いていく。読者は奥へ奥へと進むが、あるのは新たな謎だけだ。 虚構の連鎖と意味の増幅装置の中心に、「闇の奥」は存在する。それは深淵であり、無限である。このホラーめいた構造こそ、本作を秀作たらしめる美しさだと私は思う。
闇の奥ジョウゼフ・コンラッド,黒原敏行読み終わっためっちゃいい、めっちゃ面白い。訳もわかりやすい。読後感がボワボワして素晴らしい。構造がスマートでとても素敵。 虚構の連鎖と意味の増幅装置の中心に「闇の奥」はあって、それは深淵であり、無限だと思った。The horror! ーーーーー 以下、ネタバレを含む。 ーーーーー 『闇の奥』は、理解の届かぬまま進んでいく、その物語構造自体に魅力がある小説だ。 クルツは実像ではなく伝聞によって膨張し、最後まで輪郭を結ばない。読者は説明を与えられず、ただ宙吊りにされる不穏のみが募る。この「不完全さ」こそが、逆説的に作品の完成度を高めているように強く思う。 例えばこの構造を象徴するのが、ジャングルの奥地に突如現れるロシア人。弓矢の雨をかいくぐって登場し、クルツの使者かと思えば、単なる信者であり、ただただ狂気に魅せられた若者にすぎない。その「脈絡のなさ」が小説全体をぐらつかせ、不気味な余白を生む。秩序への期待を攪乱する異物の登場によって、クルツはもはや「人物」ではなく、「信仰や噂を増幅する装置」として機能する。実体は遠ざかり、神話が肥大化していく。 そして終盤にて、クルツはついに掴みどころのないまま舞台から退場し、物語は見事に宙吊りまま幕を閉じる。説明を求める欲望そのものが物語を駆動し、その軌跡は入れ子のように無限へと開いていく。読者は奥へ奥へと進むが、あるのは新たな謎だけだ。 虚構の連鎖と意味の増幅装置の中心に、「闇の奥」は存在する。それは深淵であり、無限である。このホラーめいた構造こそ、本作を秀作たらしめる美しさだと私は思う。 - 2025年9月28日
 ヘンリー・ライクロフトの私記 (光文社古典新訳文庫)ギッシング,池央耿読み終わったなんというか、変に甘い作品で、不思議な魅力がある。言葉の響きに慰められながら、どこか胸に棘が残る。 ギッシングは、貧困と不幸な結婚に疲弊しながら40代半ばに本書を執筆したが、語り手ライクロフトは、すでに老境に達した穏やかな人物として自らの内実を披瀝する。この「少し先の自分」という仮面(ペルソナ)は、作家自身の屈辱や敗北の記憶を老成した回想へと翻訳する装置である。羞恥は整えられ、美しい形に記録される。それは虚飾であると同時に、フィクションにしか許されない自己救済でもある。だが老成や円熟として包み直されても、原文の切実な痛みは消えない。だからこそ私は老人の声の奥に、40代の作家の生々しい感覚を嗅ぎ取り、奇妙な違和を覚える。それがいい。 ライクロフトの住むデヴォンの田舎は、欲望が和らいだ隠遁の地として描かれる。だがそこには、大衆文化への嫌悪や教養なき人々への冷たい眼差しといったエリート主義も滲む。必死で教養にしがみついた都会の作家だからこそ、田園の理想には濁りが生じる。しかもその田園は農作業の汗を伴わない労働なきユートピアでもあり、社会的競争や文筆の重圧から逃れるための精神的避難所でもある。 この虚構の隠遁は「社会的挫折」であると同時に、「成功からの離脱」や「内面的充足」への誘いでもある。そこにあるのは社会変革を志す大きな理想ではなく、ただ個人が生き延びるための戦略、一種のサバイバルキットだ。ギッシングはライクロフトという仮面を介して「老成」を様式として提示する。その仮面の内側では、欺瞞とロマンが混じり合う。蜜は滴り、甘い匂いが漂う。 本書の魅力は、そうして立ち上がる「美しく整えられた真実」にある。老成の仮面をかぶればこそ、裸のままでは口にできない人生の汚点や煩悩が、熟した洞察へと姿を変え、読み手に差し出される。その自己編集の手腕は、我々に「自分の人生をいかに語り直すか」という問いを投げかける。それは優雅な演出なのか、それとも切実な救済の技法なのか。 『ヘンリー・ライクロフトの私記』は、人生の苦みを味わい尽くした作家が、架空の遺稿随筆という舞台で織り上げた祈りのような箴言書であり、変に甘い心の処方箋である。妙な余韻が残る。糸を引く。やみつきになる。
ヘンリー・ライクロフトの私記 (光文社古典新訳文庫)ギッシング,池央耿読み終わったなんというか、変に甘い作品で、不思議な魅力がある。言葉の響きに慰められながら、どこか胸に棘が残る。 ギッシングは、貧困と不幸な結婚に疲弊しながら40代半ばに本書を執筆したが、語り手ライクロフトは、すでに老境に達した穏やかな人物として自らの内実を披瀝する。この「少し先の自分」という仮面(ペルソナ)は、作家自身の屈辱や敗北の記憶を老成した回想へと翻訳する装置である。羞恥は整えられ、美しい形に記録される。それは虚飾であると同時に、フィクションにしか許されない自己救済でもある。だが老成や円熟として包み直されても、原文の切実な痛みは消えない。だからこそ私は老人の声の奥に、40代の作家の生々しい感覚を嗅ぎ取り、奇妙な違和を覚える。それがいい。 ライクロフトの住むデヴォンの田舎は、欲望が和らいだ隠遁の地として描かれる。だがそこには、大衆文化への嫌悪や教養なき人々への冷たい眼差しといったエリート主義も滲む。必死で教養にしがみついた都会の作家だからこそ、田園の理想には濁りが生じる。しかもその田園は農作業の汗を伴わない労働なきユートピアでもあり、社会的競争や文筆の重圧から逃れるための精神的避難所でもある。 この虚構の隠遁は「社会的挫折」であると同時に、「成功からの離脱」や「内面的充足」への誘いでもある。そこにあるのは社会変革を志す大きな理想ではなく、ただ個人が生き延びるための戦略、一種のサバイバルキットだ。ギッシングはライクロフトという仮面を介して「老成」を様式として提示する。その仮面の内側では、欺瞞とロマンが混じり合う。蜜は滴り、甘い匂いが漂う。 本書の魅力は、そうして立ち上がる「美しく整えられた真実」にある。老成の仮面をかぶればこそ、裸のままでは口にできない人生の汚点や煩悩が、熟した洞察へと姿を変え、読み手に差し出される。その自己編集の手腕は、我々に「自分の人生をいかに語り直すか」という問いを投げかける。それは優雅な演出なのか、それとも切実な救済の技法なのか。 『ヘンリー・ライクロフトの私記』は、人生の苦みを味わい尽くした作家が、架空の遺稿随筆という舞台で織り上げた祈りのような箴言書であり、変に甘い心の処方箋である。妙な余韻が残る。糸を引く。やみつきになる。 - 2025年9月26日
 19世紀イタリア怪奇幻想短篇集橋本勝雄読み終わった勝手な大雑把な印象を申せば、イタリア文学は低刺激・高残響の傾向がある。本書『19世紀イタリア怪奇幻想短篇集』の魅力も、怪奇や恐怖が突き抜ける力よりも、宗教や科学、家庭や風習という生活の制度を通して、日常の奥にじわりと滲む不安や風刺を映し出すところにあるように思う。そして、比較文学やイタリア文化・文学史の足場としての価値を強く感じた。 アッリーゴ・ボイト「黒のビショップ」がスマートで印象に残る。
19世紀イタリア怪奇幻想短篇集橋本勝雄読み終わった勝手な大雑把な印象を申せば、イタリア文学は低刺激・高残響の傾向がある。本書『19世紀イタリア怪奇幻想短篇集』の魅力も、怪奇や恐怖が突き抜ける力よりも、宗教や科学、家庭や風習という生活の制度を通して、日常の奥にじわりと滲む不安や風刺を映し出すところにあるように思う。そして、比較文学やイタリア文化・文学史の足場としての価値を強く感じた。 アッリーゴ・ボイト「黒のビショップ」がスマートで印象に残る。 - 2025年9月25日
 うたかたの日々ヴィアン,野崎歓読み終わった読んでいるうちに、遥か昔に新潮文庫で、さらには岡崎京子の漫画も読んだことを思い出した。どこか懐かしい感触がよみがえる。 凸凹な倫理、不協和音のポップ化。構造や装置、デザイン感度を優先する美学。消費社会のガジェットの輝きにまとわりつく空虚。言葉遊戯と都市の雑居が生む即興のテンポ。そうした軽さと重さの二重奏が、久々に甘酸っぱく胸にひろがった。 ポップ・アートやヌーヴェルヴァーグ的な感性、自棄っぱちな気持ち。1940年代当時としては、紛れもなく先進的な作品である。もっとも、その前衛は私の初読時においてすでに古典だった。 そして今では90年代も00年代もポストモダンもすっかり古典となり、私もまた大人になった。複雑である。絶望を軽やかに弾ませ、崩壊を祝祭に変える想像力とその技法。現在の私自身の性分には合わないけれど、時代はそれを切実に必要としているのかもしれない。そんなことを思う。
うたかたの日々ヴィアン,野崎歓読み終わった読んでいるうちに、遥か昔に新潮文庫で、さらには岡崎京子の漫画も読んだことを思い出した。どこか懐かしい感触がよみがえる。 凸凹な倫理、不協和音のポップ化。構造や装置、デザイン感度を優先する美学。消費社会のガジェットの輝きにまとわりつく空虚。言葉遊戯と都市の雑居が生む即興のテンポ。そうした軽さと重さの二重奏が、久々に甘酸っぱく胸にひろがった。 ポップ・アートやヌーヴェルヴァーグ的な感性、自棄っぱちな気持ち。1940年代当時としては、紛れもなく先進的な作品である。もっとも、その前衛は私の初読時においてすでに古典だった。 そして今では90年代も00年代もポストモダンもすっかり古典となり、私もまた大人になった。複雑である。絶望を軽やかに弾ませ、崩壊を祝祭に変える想像力とその技法。現在の私自身の性分には合わないけれど、時代はそれを切実に必要としているのかもしれない。そんなことを思う。 - 2025年9月24日
 老子蜂屋邦夫読み終わった論語を読み、次に老子を読む。 論語は関係の内側に秩序を、すなわちルールと姿勢を示し、老子は関係の外側の流れに身を委ねる知恵を説く。どちらも過剰を抑制することが目的となり、孔子は礼で調整し、老子は道・自然に戻す・還す。過剰は、自然を人工的に加速させた結果のねじれ。 個人的には、以下の章を、 歸根第十六 → 去用第四十 → 道化第四十二 → 象元第二十五 → 俗薄第十八 → 還淳第十九 → 異俗第二十 → 論德第三十八 → 歸根第十六 … とループして読むのが心地よい。すなわち、 観法(ものの見方)→ 運動則(変化の法則)→ 生成手順(生成のプロセス)→ 運用原理(実践の原理)→ 社会診断(現状分析)→ 制度の断捨離 → 心の断捨離 → 理論図解(全体像の把握)→ 再度観法へ … と螺旋を描き高みに登っていく無限の弁証法。疲弊した心と脳にやさしいのに、一方で容赦がない。これもまた過剰かな。 老子には浪漫がある。
老子蜂屋邦夫読み終わった論語を読み、次に老子を読む。 論語は関係の内側に秩序を、すなわちルールと姿勢を示し、老子は関係の外側の流れに身を委ねる知恵を説く。どちらも過剰を抑制することが目的となり、孔子は礼で調整し、老子は道・自然に戻す・還す。過剰は、自然を人工的に加速させた結果のねじれ。 個人的には、以下の章を、 歸根第十六 → 去用第四十 → 道化第四十二 → 象元第二十五 → 俗薄第十八 → 還淳第十九 → 異俗第二十 → 論德第三十八 → 歸根第十六 … とループして読むのが心地よい。すなわち、 観法(ものの見方)→ 運動則(変化の法則)→ 生成手順(生成のプロセス)→ 運用原理(実践の原理)→ 社会診断(現状分析)→ 制度の断捨離 → 心の断捨離 → 理論図解(全体像の把握)→ 再度観法へ … と螺旋を描き高みに登っていく無限の弁証法。疲弊した心と脳にやさしいのに、一方で容赦がない。これもまた過剰かな。 老子には浪漫がある。 - 2025年9月23日
 論語金谷治読み終わった論語を読み、次に老子を読む。 論語は関係の内側に秩序を、すなわちルールと姿勢を示し、老子は関係の外側の流れに身を委ねる知恵を説く。どちらも過剰を抑制することが目的となり、孔子は礼で調整し、老子は道・自然に戻す・還す。過剰は、自然を人工的に加速させた結果のねじれ。 泰伯第八・第8章(08-08) 子曰、興於詩、立於禮、成於樂。 (子曰く、詩に興り、礼に立ち、楽に成る。) いいなあ、ハーモニー。最初に詩で人の心を動かしてから礼で基礎を固め、最後に楽で社会全体と調和させる。仕上げが「楽しい」で終わるってのが孔子のセンス。好。 人は自分に甘く、他者に礼を求め、楽は二の次になりがち。 論語にはどことなく哀愁がある。
論語金谷治読み終わった論語を読み、次に老子を読む。 論語は関係の内側に秩序を、すなわちルールと姿勢を示し、老子は関係の外側の流れに身を委ねる知恵を説く。どちらも過剰を抑制することが目的となり、孔子は礼で調整し、老子は道・自然に戻す・還す。過剰は、自然を人工的に加速させた結果のねじれ。 泰伯第八・第8章(08-08) 子曰、興於詩、立於禮、成於樂。 (子曰く、詩に興り、礼に立ち、楽に成る。) いいなあ、ハーモニー。最初に詩で人の心を動かしてから礼で基礎を固め、最後に楽で社会全体と調和させる。仕上げが「楽しい」で終わるってのが孔子のセンス。好。 人は自分に甘く、他者に礼を求め、楽は二の次になりがち。 論語にはどことなく哀愁がある。 - 2025年9月22日
 論理哲学論考ルードヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン,丘沢静也読み終わった
論理哲学論考ルードヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン,丘沢静也読み終わった - 2025年9月22日
 菊と刀ルース・フルトン・ベネディクト,角田安正読み終わった
菊と刀ルース・フルトン・ベネディクト,角田安正読み終わった - 2025年9月20日
- 2025年9月20日
- 2025年9月19日
- 2025年9月19日
- 2025年9月18日
- 2025年9月17日
 新・思考のための道具 知性を拡張するためのテクノロジー―その歴史と未来ハワード・ラインゴールド,日暮雅通読み終わっためちゃくちゃすごい本。「ぼくらが欲しかったのは空飛ぶクルマだ。なのに手に入ったのは“140文字”だった。」というピーター・ティールの言葉がめっちゃ重くなる。
新・思考のための道具 知性を拡張するためのテクノロジー―その歴史と未来ハワード・ラインゴールド,日暮雅通読み終わっためちゃくちゃすごい本。「ぼくらが欲しかったのは空飛ぶクルマだ。なのに手に入ったのは“140文字”だった。」というピーター・ティールの言葉がめっちゃ重くなる。 - 2025年9月15日
読み込み中...