縁食論

15件の記録
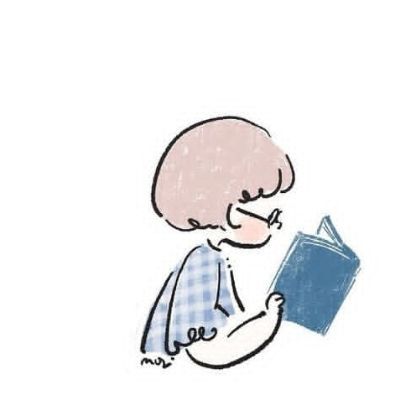 クジラ@need_a_nap2025年11月24日読み終わった✎_わたしメモ 「孤食」のもつ意味の変化 「縁食」あっさりとしためぐり合わせ、ゆるやかな並存の場、宿り木のような存在 「食べる場所が、ただ食べるための場所になってしまったことによって、食べるという行為が本来持っていた多様な可能性、食べることによって生まれる多様な出会いが失われてしまったのではないか」 「食べることは本来的には消費ではない」 「食の空間の寛容さこそが縁食の必須の条件」 子ども食堂のボランティア経験があり、この本を手にとってみた。心惹かれる文章がいくつかあったが、それを自分の中に落とし込みきれていない。ただ、これまでの人生で『食』に対して向き合う時間が多く、また死ぬまで切り離せないテーマでもある。もう少し色んな角度から『食』と向き合ってみたいと思った。
クジラ@need_a_nap2025年11月24日読み終わった✎_わたしメモ 「孤食」のもつ意味の変化 「縁食」あっさりとしためぐり合わせ、ゆるやかな並存の場、宿り木のような存在 「食べる場所が、ただ食べるための場所になってしまったことによって、食べるという行為が本来持っていた多様な可能性、食べることによって生まれる多様な出会いが失われてしまったのではないか」 「食べることは本来的には消費ではない」 「食の空間の寛容さこそが縁食の必須の条件」 子ども食堂のボランティア経験があり、この本を手にとってみた。心惹かれる文章がいくつかあったが、それを自分の中に落とし込みきれていない。ただ、これまでの人生で『食』に対して向き合う時間が多く、また死ぬまで切り離せないテーマでもある。もう少し色んな角度から『食』と向き合ってみたいと思った。 1neko.@ichineko112025年11月8日読み終わった「冷静と情熱のあいだ」、みたいなタイトル 著者の藤原辰史さんは、「分解の哲学」と「トラクターの世界史」も書かれていたんですね。この方の著作は、コンセプト買い&読みしてしまう。 以下、気になったキーワード&思い出し ・子ども食堂の「弱目的性 ・縁側の力(ばあちゃん不在時の茶飲みナンパ) ・縁側のタバコ(おやつ時間) ・サードプレイス(会社に集まって就業するいう働き方は、つづくのか/つづかないのではないか)
1neko.@ichineko112025年11月8日読み終わった「冷静と情熱のあいだ」、みたいなタイトル 著者の藤原辰史さんは、「分解の哲学」と「トラクターの世界史」も書かれていたんですね。この方の著作は、コンセプト買い&読みしてしまう。 以下、気になったキーワード&思い出し ・子ども食堂の「弱目的性 ・縁側の力(ばあちゃん不在時の茶飲みナンパ) ・縁側のタバコ(おやつ時間) ・サードプレイス(会社に集まって就業するいう働き方は、つづくのか/つづかないのではないか)




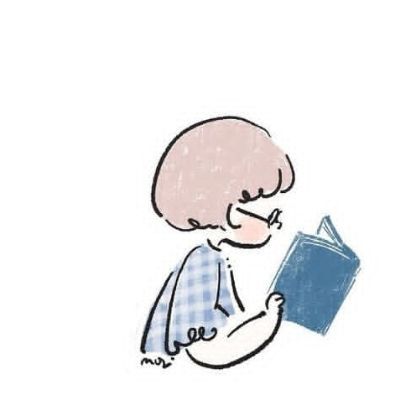
- myk.sk@reads-4404102025年3月25日読み終わった平野紗希子さんの著書内にて触れられていて、気になったので購入。旧式の家族観を押し付ける共食ではないかたちの「縁食」の実現を希う内容に、共感しつつも、さてどこから手を出すのかと考えると思考が止まってしまう。 たぶん、縁食を考えてみない?というテーブルを設けることが一番良い気がする。 場を設けること。
- 三月@sangatu2025年3月7日買った読み始めた食べ物は人間が生きるために必要なもの。だけど現状この社会では食べ物を手に入れるにはお金が要る。お金がなくなれば当然飢えて苦しむ社会は、「正しい」のかーーーーーという、生活を送る上で何度も浮かんだことのある疑問。その疑問を正面から受け止めてくれる本。











