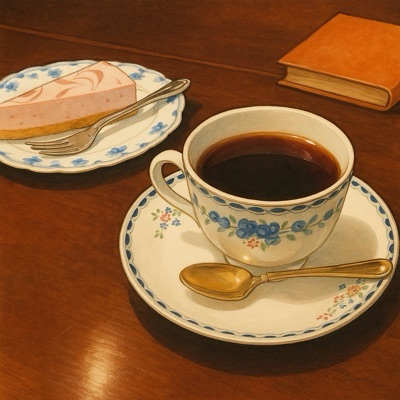もしもこの世に対話がなかったら。 オープンダイアローグ的対話実践を求めて

35件の記録
 だるま@daruma_01062026年1月12日読み終わった読んでよかったー 自分で悩みを反芻するばかりで考え過ぎてしまうから、こういう対話の場所があると知れてとてもよかった。「ゆくゆく!」参加してみたいな。
だるま@daruma_01062026年1月12日読み終わった読んでよかったー 自分で悩みを反芻するばかりで考え過ぎてしまうから、こういう対話の場所があると知れてとてもよかった。「ゆくゆく!」参加してみたいな。

 zzz@oownow2025年10月31日読み終わった自分が対話に参加しているような感覚になる本。 あくまでもオープンダイアローグから発展した?試みなので、ここからもう少し専門的な本を読んでみるのがよさそう。
zzz@oownow2025年10月31日読み終わった自分が対話に参加しているような感覚になる本。 あくまでもオープンダイアローグから発展した?試みなので、ここからもう少し専門的な本を読んでみるのがよさそう。

 さーちゃん@cong_mei2025年10月28日読み終わったオープンダイアローグとは、フィンランドの病院で生まれた精神療法なのだという。 患者さん(と患者さんの周囲の人)が相談をする。患者さんの治療チームが、患者さんや患者さんを取り巻く状況について話す。その様子を患者さんは外から見ている。というのを、日をあけて何度も繰り返すそうだ。 この本では、その手法に少しずつ改変を加えて、オープンダイアローグ的対話実践を試みた様子が描かれている。 この手法では、相談者が独特の幸福感に包まれるという。それは味わってみないとわからないものではあるけれど、自分の話を真剣に聞いてくれ、真摯に考えてくれている空間というのは、心地よいものであるだろうことは想像がつく。 それにはきっと、半年以上かけて作ってきたというルールが上手く作用しているんだろう。相談者を傷つけず、全員の心理的安全性が保たれるようみんなが最大限努力する場所。 私は、ルールの中でも特に、「不確実性に耐える」という項目が印象に残った。対話の中で何が起こるかわからない。もしかしたら予期しないことが起こるかもしれない。動揺したとしてもそのことを他の参加者に伝え、支え合いながら対処する。 これをみんなが心がけてくれているのは安心だろうなあ。
さーちゃん@cong_mei2025年10月28日読み終わったオープンダイアローグとは、フィンランドの病院で生まれた精神療法なのだという。 患者さん(と患者さんの周囲の人)が相談をする。患者さんの治療チームが、患者さんや患者さんを取り巻く状況について話す。その様子を患者さんは外から見ている。というのを、日をあけて何度も繰り返すそうだ。 この本では、その手法に少しずつ改変を加えて、オープンダイアローグ的対話実践を試みた様子が描かれている。 この手法では、相談者が独特の幸福感に包まれるという。それは味わってみないとわからないものではあるけれど、自分の話を真剣に聞いてくれ、真摯に考えてくれている空間というのは、心地よいものであるだろうことは想像がつく。 それにはきっと、半年以上かけて作ってきたというルールが上手く作用しているんだろう。相談者を傷つけず、全員の心理的安全性が保たれるようみんなが最大限努力する場所。 私は、ルールの中でも特に、「不確実性に耐える」という項目が印象に残った。対話の中で何が起こるかわからない。もしかしたら予期しないことが起こるかもしれない。動揺したとしてもそのことを他の参加者に伝え、支え合いながら対処する。 これをみんなが心がけてくれているのは安心だろうなあ。

 夏河@myhookbooks2025年7月15日読み終わったオープンダイアローグ(開かれた対話)という言葉はチラッと聞いたことがあるだけで、フィンランドで生まれた精神療法とは知らなかった。 話し手が悩みを話し、それについて聞き手が意見交換をする。それに話し手は耳を傾ける。話し手のこの体験が不思議でやってみないと分からない感じという感想をみんなが言っていて、とても興味深かった。一体どんな感じなのだろう。 そして、著者の横道さんが運営している「ゆくゆく!」の運営の仕方が誠実で、いろいろな試行錯誤のうえでより良くしようという姿勢も、なんだか身に染みた。運営側も「悩める当事者仲間」というのも、ルールがしっかりしていることも参加する側には、きっとありがたいことだろうなと思う。 いろんな場所でいろんな人が、より良く生きるために動いている。
夏河@myhookbooks2025年7月15日読み終わったオープンダイアローグ(開かれた対話)という言葉はチラッと聞いたことがあるだけで、フィンランドで生まれた精神療法とは知らなかった。 話し手が悩みを話し、それについて聞き手が意見交換をする。それに話し手は耳を傾ける。話し手のこの体験が不思議でやってみないと分からない感じという感想をみんなが言っていて、とても興味深かった。一体どんな感じなのだろう。 そして、著者の横道さんが運営している「ゆくゆく!」の運営の仕方が誠実で、いろいろな試行錯誤のうえでより良くしようという姿勢も、なんだか身に染みた。運営側も「悩める当事者仲間」というのも、ルールがしっかりしていることも参加する側には、きっとありがたいことだろうなと思う。 いろんな場所でいろんな人が、より良く生きるために動いている。
 読書会@coffee caraway@caraway2025年6月25日読み終わった実際に自分も参加してるような気分になりつつメンバーの考えやルールが分かり、 しかもそれは毎回の積み重ねで更新されてる、現在進行形の取組と分かる… 淡々と進むようで物語も感じられ、驚きと共に読了!
読書会@coffee caraway@caraway2025年6月25日読み終わった実際に自分も参加してるような気分になりつつメンバーの考えやルールが分かり、 しかもそれは毎回の積み重ねで更新されてる、現在進行形の取組と分かる… 淡々と進むようで物語も感じられ、驚きと共に読了! きよ@kiyomune2025年4月27日読み終わった先日オープンダイアログのワークショップに参加し、もう少し学んでみたくなったので、なんとなしに購入。 ワークショップのカウンセラーさんが、「対話は混沌を生む(綺麗に真理を掴み取るものではない)」と仰っていたことを、ぼんやり思い出しつつ、各話を読む。 二重傍線部「対話のツボ」ならびに、スタッフミーティングのくだりで、ちょっとした気づきやテクニックを得ることができて面白い。
きよ@kiyomune2025年4月27日読み終わった先日オープンダイアログのワークショップに参加し、もう少し学んでみたくなったので、なんとなしに購入。 ワークショップのカウンセラーさんが、「対話は混沌を生む(綺麗に真理を掴み取るものではない)」と仰っていたことを、ぼんやり思い出しつつ、各話を読む。 二重傍線部「対話のツボ」ならびに、スタッフミーティングのくだりで、ちょっとした気づきやテクニックを得ることができて面白い。


- さみ@futatabi2025年4月1日読んでる1章 給料の高い仕事が「良い」仕事(行為)ではないのだなと改めて。ところで、『それで君の声はどこにあるんだ?』と続けて読んだことで、こうして本を読んでは知見をありがたがるばかりで交流の閉じている自分の立ち位置と行き着くところについて考えている。


 高尾清貴@kiyotakao2025年3月1日読み始めたポリフォニー(多声性)というと、一般にハーモニーのイメージを持たれがちなんですよね。調和してハモっている状態。でもそれはホモフォニー(等声性)や「モノフォニー」(単声性)と同じく避けなければならないものなんです。ハーモニーでなく、モノフォニーでもなく、ホモフォニーでもなく、ポリフオニーというわけです。
高尾清貴@kiyotakao2025年3月1日読み始めたポリフォニー(多声性)というと、一般にハーモニーのイメージを持たれがちなんですよね。調和してハモっている状態。でもそれはホモフォニー(等声性)や「モノフォニー」(単声性)と同じく避けなければならないものなんです。ハーモニーでなく、モノフォニーでもなく、ホモフォニーでもなく、ポリフオニーというわけです。