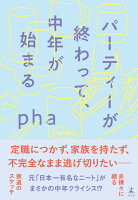さみ
@futatabi
自由
- 2026年2月21日
 友達じゃないかもしれないひらりさ,上坂あゆ美読んでる「生と死」パートの上坂さんの、人生で自分の選んでいないものはそれが自分なのではなくて自分の乗り物に過ぎない、という考えになるほど〜〜!と思っている。肉体は魂の容器でしかない、とは考えるようになっていたけど肉体だけではなく、名前も、ちょっと概念だけ借用させていただくことで考えようによってほかにもいろいろ適用できそうだから、それで乗り切れそうなものを乗り切ろうかな。
友達じゃないかもしれないひらりさ,上坂あゆ美読んでる「生と死」パートの上坂さんの、人生で自分の選んでいないものはそれが自分なのではなくて自分の乗り物に過ぎない、という考えになるほど〜〜!と思っている。肉体は魂の容器でしかない、とは考えるようになっていたけど肉体だけではなく、名前も、ちょっと概念だけ借用させていただくことで考えようによってほかにもいろいろ適用できそうだから、それで乗り切れそうなものを乗り切ろうかな。 - 2026年2月20日
 世界の力関係がわかる本千々和泰明読んでる第三章の第一次世界大戦の起こりまで。皇太子暗殺でなぜ世界大戦に……とわからないまま世界史の授業が過ぎていったので、背景が理解できてなるほど〜と思うとともに、軍事侵略という発想を捨てられないかぎりまたいつでも起こり得るのだろうなあということがかんたんにわかってしまう。そこにどんな善意がしきつめられていたとしても暴力がすべてを台無しにする。
世界の力関係がわかる本千々和泰明読んでる第三章の第一次世界大戦の起こりまで。皇太子暗殺でなぜ世界大戦に……とわからないまま世界史の授業が過ぎていったので、背景が理解できてなるほど〜と思うとともに、軍事侵略という発想を捨てられないかぎりまたいつでも起こり得るのだろうなあということがかんたんにわかってしまう。そこにどんな善意がしきつめられていたとしても暴力がすべてを台無しにする。 - 2026年2月15日
 資本主義を半分捨てる青木真兵読んでるたぶんもう何年もこういう本を読みたいなあと思ってきて、今このタイミングがいちばん効いて浸透するなあというときに読めている。自分にとってのちょうどよさを見つける難しさも、そこに常に対向があることも、バランスを考えることがつきまとうこともずっと真摯に添えられていて、現実感を失わずに夢中になれている感じ。ちゃんと栄養になっている。ちくまプリマー新書はほんとうにありがたい……
資本主義を半分捨てる青木真兵読んでるたぶんもう何年もこういう本を読みたいなあと思ってきて、今このタイミングがいちばん効いて浸透するなあというときに読めている。自分にとってのちょうどよさを見つける難しさも、そこに常に対向があることも、バランスを考えることがつきまとうこともずっと真摯に添えられていて、現実感を失わずに夢中になれている感じ。ちゃんと栄養になっている。ちくまプリマー新書はほんとうにありがたい…… - 2026年2月15日
 私の幸福論福田恆存読んでる書店員さんにご紹介いただいて! 「教養について」の章、「人文的なものを好みながら仕事になると人文的なふるまいができない」という自分のおなやみに効いている。「たんに知っているだけで教養ではない」ということです。振り回すことと使いこなすことの大きな隔たりが突き付けられる!
私の幸福論福田恆存読んでる書店員さんにご紹介いただいて! 「教養について」の章、「人文的なものを好みながら仕事になると人文的なふるまいができない」という自分のおなやみに効いている。「たんに知っているだけで教養ではない」ということです。振り回すことと使いこなすことの大きな隔たりが突き付けられる! - 2026年2月7日
 渇愛宇都宮直子読み終わった二つ、しばらく考えそうなことがあった。 ひとつは神についてのこと。「りりちゃんは、誰かの“神”になってくれる人だった。でも、ヲタ同士が連帯することは危うく、難しかった。」とあって、りりちゃんが不特定多数の誰かにとっての神になろうとしたのか神にさせられてしまったのかわからないけど(他者の求める像を提供しようとするという話が繰り返し出ていたから、求めに応じたのがそのような形になっていったというのはありそう)、現代の人々というか人間の性質なのか、神のような存在を作りたがるのはなんなのだろう。信仰に基づいた行動の、そうでない主体的?な動きと比べたときの心理的な負担の低さがあるのだろうか。星占いもそれに近いのかなあ。りりちゃんが彼女を崇めた人たちにとって神である瞬間があったのは間違いなくて、神であり続けることと背を向けられることの、決定的な違いはどこで生まれるのだろう。逮捕がなければ神のままだったのか、神としてあり続けるには何か条件があったのか。 もうひとつ、終盤でりりちゃんについての製作予定だった映画の監督が、ホストクラブでの賞賛や被害者がりりちゃんに求めた恋愛を、コミュニケーションの努力を省略して得ようとする成果だという話をしていた。その省略は楽をしたい欲求というよりは、自分一人で向かったものでもなく、焦らされて、急いだ(そのつもりがなくても)結果のものだという気がしている。自己顕示欲というよりもっと外に向けた承認欲求みたいなもので、社会に作られたものだというふうに感じる。焦らせてくる社会は、コミュニケーションの努力の過程が踏みにじられる社会でもある。 「社会問題」とはいうけれど、ほんとうに社会が個人の在り方を規定してくるんだよなあと。だから他人のことなのに興味をもってしまうのだと思うし、となると逆に自分は何にまったく興味がなく、それは個人の問題だろうと片付けてしまえるのかも気になってきて、書いているうちにノンフィクション読みたい熱を高められている……!
渇愛宇都宮直子読み終わった二つ、しばらく考えそうなことがあった。 ひとつは神についてのこと。「りりちゃんは、誰かの“神”になってくれる人だった。でも、ヲタ同士が連帯することは危うく、難しかった。」とあって、りりちゃんが不特定多数の誰かにとっての神になろうとしたのか神にさせられてしまったのかわからないけど(他者の求める像を提供しようとするという話が繰り返し出ていたから、求めに応じたのがそのような形になっていったというのはありそう)、現代の人々というか人間の性質なのか、神のような存在を作りたがるのはなんなのだろう。信仰に基づいた行動の、そうでない主体的?な動きと比べたときの心理的な負担の低さがあるのだろうか。星占いもそれに近いのかなあ。りりちゃんが彼女を崇めた人たちにとって神である瞬間があったのは間違いなくて、神であり続けることと背を向けられることの、決定的な違いはどこで生まれるのだろう。逮捕がなければ神のままだったのか、神としてあり続けるには何か条件があったのか。 もうひとつ、終盤でりりちゃんについての製作予定だった映画の監督が、ホストクラブでの賞賛や被害者がりりちゃんに求めた恋愛を、コミュニケーションの努力を省略して得ようとする成果だという話をしていた。その省略は楽をしたい欲求というよりは、自分一人で向かったものでもなく、焦らされて、急いだ(そのつもりがなくても)結果のものだという気がしている。自己顕示欲というよりもっと外に向けた承認欲求みたいなもので、社会に作られたものだというふうに感じる。焦らせてくる社会は、コミュニケーションの努力の過程が踏みにじられる社会でもある。 「社会問題」とはいうけれど、ほんとうに社会が個人の在り方を規定してくるんだよなあと。だから他人のことなのに興味をもってしまうのだと思うし、となると逆に自分は何にまったく興味がなく、それは個人の問題だろうと片付けてしまえるのかも気になってきて、書いているうちにノンフィクション読みたい熱を高められている……! - 2026年2月4日
 そいつはほんとに敵なのか碇雪恵読んでる@ UNITÉ(ユニテ)私は色々な「そいつ」を敵だと思いすぎなので買った。「自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(準備編)」まで読んだところで仕事に戻る。「実践編」、満を持して読みたい。ちょうど最近YouTubeの「たむともストリート」をよく見ていて、自分だったらすぐピリつきを出してしまうであろうところを、相手の話を聞いてから応答するスタイルが良いなあと思っていた。ちょうど正月にも親族一同に悪態をついたばかり。
そいつはほんとに敵なのか碇雪恵読んでる@ UNITÉ(ユニテ)私は色々な「そいつ」を敵だと思いすぎなので買った。「自分が支持しない政党に投票した人に会いに行く(準備編)」まで読んだところで仕事に戻る。「実践編」、満を持して読みたい。ちょうど最近YouTubeの「たむともストリート」をよく見ていて、自分だったらすぐピリつきを出してしまうであろうところを、相手の話を聞いてから応答するスタイルが良いなあと思っていた。ちょうど正月にも親族一同に悪態をついたばかり。 - 2026年2月3日
 ひとつにならない横道誠読んでる通勤の行きはphaさんの本をしずかに、帰りは頭ががちゃがちゃしちゃっているのだけどこの本はリズム合う感じがして読む、というのが今週のルーティンになりつつある。ありがたい。
ひとつにならない横道誠読んでる通勤の行きはphaさんの本をしずかに、帰りは頭ががちゃがちゃしちゃっているのだけどこの本はリズム合う感じがして読む、というのが今週のルーティンになりつつある。ありがたい。 - 2026年2月3日
- 2026年1月25日
 友達じゃないかもしれないひらりさ,上坂あゆ美読んでる@ ウレシカいつか読みそうと思いながらなかなか買っていなかったのだけど、友達と行ったお店で見つけて、どんなやりとりがあったか忘れたけど友達と見つけたいまがこの本を持ち帰るタイミングなんじゃないかと思い、予定外?に購入。こういう入荷のしかたはたのしい。友達が編みものをしてくれている間にソファでごろごろしながら読んだ。本によい思い出が付与された。ひとりでもそれを思い出しつつ読んでいる。こんなにふたりの、それぞれの個人的なものというより「ふたりの」話を読んでしまってよいのかと戸惑いながら読んでいる。嘘がゆるされていないようで緊張感がある。それと同時に、嘘をつかずにほんとうのことだけ取り出して見せられる相手がいるのはすごくうれしいことでもあるだろうなと。 最近よく怒ってしまうので、「怪物とAI」での「人間は自分がもっとも気をつけていることを蔑ろにする他者に対して怒りを感じるようにできているのではないか」という提起に納得(よりすなでもこんな話題があったような)。自分では気をつけなきゃと思っていることがあまりにも多く、それがいつまでたっても自然なふるまいではなく「気をつけてあえてやっていること」のままだから「人々、気にしなさすぎ!!」というキレかたをしてしまうのだと思う。それを「まあいっか」と思えるまでのルートは果たしてあるのか。逆に私が何を気にしていないかをばしばし指摘してくれ(と頼んだらしてくれ)るのは友達なのだろう。そういえばタイトルはどのように回収されていくのか。
友達じゃないかもしれないひらりさ,上坂あゆ美読んでる@ ウレシカいつか読みそうと思いながらなかなか買っていなかったのだけど、友達と行ったお店で見つけて、どんなやりとりがあったか忘れたけど友達と見つけたいまがこの本を持ち帰るタイミングなんじゃないかと思い、予定外?に購入。こういう入荷のしかたはたのしい。友達が編みものをしてくれている間にソファでごろごろしながら読んだ。本によい思い出が付与された。ひとりでもそれを思い出しつつ読んでいる。こんなにふたりの、それぞれの個人的なものというより「ふたりの」話を読んでしまってよいのかと戸惑いながら読んでいる。嘘がゆるされていないようで緊張感がある。それと同時に、嘘をつかずにほんとうのことだけ取り出して見せられる相手がいるのはすごくうれしいことでもあるだろうなと。 最近よく怒ってしまうので、「怪物とAI」での「人間は自分がもっとも気をつけていることを蔑ろにする他者に対して怒りを感じるようにできているのではないか」という提起に納得(よりすなでもこんな話題があったような)。自分では気をつけなきゃと思っていることがあまりにも多く、それがいつまでたっても自然なふるまいではなく「気をつけてあえてやっていること」のままだから「人々、気にしなさすぎ!!」というキレかたをしてしまうのだと思う。それを「まあいっか」と思えるまでのルートは果たしてあるのか。逆に私が何を気にしていないかをばしばし指摘してくれ(と頼んだらしてくれ)るのは友達なのだろう。そういえばタイトルはどのように回収されていくのか。 - 2026年1月23日
 終点のあの子 (文春文庫)柚木麻子読んでるとてもだいじな本。映画を観たので、帰りに読むためにあらたに買って行った。おなじ本を、あるとわかっていてもういちど買うのはこれがはじめてになった。時間のゆるすかぎり、1編めと4篇めを読んだ。はじめて読んだ高3のときの自分が、どんなに衝撃を受けて、自由な気持ちになったかすぐに思い出せた。よく昔にすきだった映像作品を観返したときに「あのときとは感性や倫理観がずいぶん変わってしまった」とぼんやりすることがあるけど、『終点のあの子』は今のわたしにとってもだいじなままで、この本をだいじに思った過去の自分は、数少ない「自分がみとめている自分」であるかもしれないなあとも思った。改めて読むと、短編なのもあってひとつひとつの展開がぐいぐいと速い。でも行間が性急に感じない、こちら側に読みをあずけすぎではと思うこともない。最近よく漫画や映画に(小説をあまり読まないからそうというだけ)速い、速い、とおいてけぼりにされていたけれど、この速さは心地よい……また十年経ってこの本を思い出すときには、はじめて読んでからのことだけじゃなくて、今日のことも思い出せたらいい。
終点のあの子 (文春文庫)柚木麻子読んでるとてもだいじな本。映画を観たので、帰りに読むためにあらたに買って行った。おなじ本を、あるとわかっていてもういちど買うのはこれがはじめてになった。時間のゆるすかぎり、1編めと4篇めを読んだ。はじめて読んだ高3のときの自分が、どんなに衝撃を受けて、自由な気持ちになったかすぐに思い出せた。よく昔にすきだった映像作品を観返したときに「あのときとは感性や倫理観がずいぶん変わってしまった」とぼんやりすることがあるけど、『終点のあの子』は今のわたしにとってもだいじなままで、この本をだいじに思った過去の自分は、数少ない「自分がみとめている自分」であるかもしれないなあとも思った。改めて読むと、短編なのもあってひとつひとつの展開がぐいぐいと速い。でも行間が性急に感じない、こちら側に読みをあずけすぎではと思うこともない。最近よく漫画や映画に(小説をあまり読まないからそうというだけ)速い、速い、とおいてけぼりにされていたけれど、この速さは心地よい……また十年経ってこの本を思い出すときには、はじめて読んでからのことだけじゃなくて、今日のことも思い出せたらいい。 - 2026年1月21日
- 2026年1月19日
 読み終わったおもしろかったー 新聞はとくに若い世代に読まれていない、性質の違うデジタル記事は対応しているが……という部分で 「社会に広く情報を伝えていくことを仕事としている私たちは、「新聞と相いれないもの」といってデジタルに背を向け続けることはできない。 なぜなら、読者に説明文で「知識」と「教訓」を届けることももちろん大切だが、紙の新聞読者が年々減り続ける現状では、デジタル読者にも社会で共有すべき情報、ニュースを届けていかなければ、報道機関の役割を果たしたことにならないから」 と書かれていて、そうかー役割を果たすためにすべきことをきちんと考えねばならないなあと思った。 と、この後に続く文章がまとまらなくて打っては消し……脳の疲労……をしていた中でも読み通せたのが著者の実践の答えなのだろうなあ。あーよかった読める、という積み重ねがひとを読書から離さないことも勇気を差し出すこともある
読み終わったおもしろかったー 新聞はとくに若い世代に読まれていない、性質の違うデジタル記事は対応しているが……という部分で 「社会に広く情報を伝えていくことを仕事としている私たちは、「新聞と相いれないもの」といってデジタルに背を向け続けることはできない。 なぜなら、読者に説明文で「知識」と「教訓」を届けることももちろん大切だが、紙の新聞読者が年々減り続ける現状では、デジタル読者にも社会で共有すべき情報、ニュースを届けていかなければ、報道機関の役割を果たしたことにならないから」 と書かれていて、そうかー役割を果たすためにすべきことをきちんと考えねばならないなあと思った。 と、この後に続く文章がまとまらなくて打っては消し……脳の疲労……をしていた中でも読み通せたのが著者の実践の答えなのだろうなあ。あーよかった読める、という積み重ねがひとを読書から離さないことも勇気を差し出すこともある - 2026年1月11日
 性的であるとはどのようなことか難波優輝読んでる第二部の途中まで読んだ。 本書でいう「えっちなもの」への自分の「えっち判断」を(わたしの場合は)公にしたくないのは、きわめてパーソナルなものを外側から悪用される可能性を警戒している、悪用されうる社会だと思っているからかなと思った。 性的な広告が、とくに女性は性の対象である(でしかない)かのような規範を再生産しうるというのはその通りだなあ危ないなあと思いながら自分の中で整理できていなかった。大体のことは単体の話をしていない、それに連なる再生産の話をしている。性的なものにしてもえっちなものにしても、その論のなかで身体の接触の話になっていくと嫌悪感がわいてくるのは、性別的に容易く性の対象とされる社会にい続けていることで作られていった防衛本能みたいなものなのだろうなということも思った。なんかこういうときに自意識過剰だろみたいなフレーズが渦巻くことがあるが、わたしはお前個人とではなく社会の中で生きているんだよと呆れた気持ちになる
性的であるとはどのようなことか難波優輝読んでる第二部の途中まで読んだ。 本書でいう「えっちなもの」への自分の「えっち判断」を(わたしの場合は)公にしたくないのは、きわめてパーソナルなものを外側から悪用される可能性を警戒している、悪用されうる社会だと思っているからかなと思った。 性的な広告が、とくに女性は性の対象である(でしかない)かのような規範を再生産しうるというのはその通りだなあ危ないなあと思いながら自分の中で整理できていなかった。大体のことは単体の話をしていない、それに連なる再生産の話をしている。性的なものにしてもえっちなものにしても、その論のなかで身体の接触の話になっていくと嫌悪感がわいてくるのは、性別的に容易く性の対象とされる社会にい続けていることで作られていった防衛本能みたいなものなのだろうなということも思った。なんかこういうときに自意識過剰だろみたいなフレーズが渦巻くことがあるが、わたしはお前個人とではなく社会の中で生きているんだよと呆れた気持ちになる - 2025年12月29日
 優しい去勢のために松浦理英子読み終わった「異性の生理をわかったふりをしないのは結構なことである。けれども、遠慮深すぎるのもどうか。「わからない」と安直に決め込めるほどわからないものなのだろうか。最終的には肉体的性別に由来する差異が厳然とあるにせよ、現段階では男女ともかなり手前の地点でわかろうとする努力を放棄しているのではないか。もっとわかり得ると考えても決して異性に対して無礼ではないだろう。」など。身体って最も身近でまちがいなく自分のものなのに、所有物感もなければ(遠隔操作している感じ)マニュアルがあまり細分化されてないし、なぞの存在だよな〜と改めて。自分がこれのことをどうしたいのかはまだよくわかっていない。 本読むのすき。書かれていることについて、書いたひととお話している気分になれる。おびやかされない。過剰に神経を過敏にしない。差し出したいことばをゆっくり考えられる。安全な空気のなかに身を置くことができる。あなたの話をもっと聞きたい、とやすらかな気持ちで思える。 と、読みながら思った。今まで「本読むの好きなんですか?」と訊かれるとなんかもごもごしていたけど、ごく自然体に。自分の生まれていない時代について書かれているし、取り上げられている作品群はほとんど知らないし(でも偶然今朝支度しながら聴いていたYouTubeの番組で言及されている映画の話が出てきて、これだよ〜人生!とか思った)、やっぱり今とは空気や環境が違って同意しかねることも書かれているし、でも、小さいときからわたしがずっと探していたのはきっとこういう本のことだったよね、と確信もした。この本を読みながらやった〜!とはしゃいでいる大学生の自分も想像された。そんな読書をしていた。 そして、本たちに守られたいとも思った。ので、本は人を守るちからもあるのか〜と思いいたった。そもそもこの本を読むことにしたのは『男性解放批評序説』で言及があったからだった。防御力を高められてうれしい。
優しい去勢のために松浦理英子読み終わった「異性の生理をわかったふりをしないのは結構なことである。けれども、遠慮深すぎるのもどうか。「わからない」と安直に決め込めるほどわからないものなのだろうか。最終的には肉体的性別に由来する差異が厳然とあるにせよ、現段階では男女ともかなり手前の地点でわかろうとする努力を放棄しているのではないか。もっとわかり得ると考えても決して異性に対して無礼ではないだろう。」など。身体って最も身近でまちがいなく自分のものなのに、所有物感もなければ(遠隔操作している感じ)マニュアルがあまり細分化されてないし、なぞの存在だよな〜と改めて。自分がこれのことをどうしたいのかはまだよくわかっていない。 本読むのすき。書かれていることについて、書いたひととお話している気分になれる。おびやかされない。過剰に神経を過敏にしない。差し出したいことばをゆっくり考えられる。安全な空気のなかに身を置くことができる。あなたの話をもっと聞きたい、とやすらかな気持ちで思える。 と、読みながら思った。今まで「本読むの好きなんですか?」と訊かれるとなんかもごもごしていたけど、ごく自然体に。自分の生まれていない時代について書かれているし、取り上げられている作品群はほとんど知らないし(でも偶然今朝支度しながら聴いていたYouTubeの番組で言及されている映画の話が出てきて、これだよ〜人生!とか思った)、やっぱり今とは空気や環境が違って同意しかねることも書かれているし、でも、小さいときからわたしがずっと探していたのはきっとこういう本のことだったよね、と確信もした。この本を読みながらやった〜!とはしゃいでいる大学生の自分も想像された。そんな読書をしていた。 そして、本たちに守られたいとも思った。ので、本は人を守るちからもあるのか〜と思いいたった。そもそもこの本を読むことにしたのは『男性解放批評序説』で言及があったからだった。防御力を高められてうれしい。 - 2025年12月20日
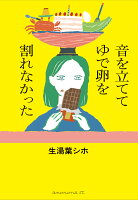 ⾳を⽴ててゆで卵を割れなかった生湯葉シホ読んでる起き抜けに読む。よいかんじに目覚めたり目覚めなかったりしたときに、ほかの何をするよりも先に「あれ読もう」とぼやぼやした頭でも思える本に会えるのはうれしい。そういえばここ数年くらい、ひとの「思ったけど言わなかったこと」「行動の選択肢にあったけどしなかったこと」に興味をもっていたので、であればこのエッセイはうってつけなわけだった。それにしても、読みはじめたときにも思ったのだけど、小説を読んでいるみたいな心地になることがある。そんなエッセイは初めてな気がする。
⾳を⽴ててゆで卵を割れなかった生湯葉シホ読んでる起き抜けに読む。よいかんじに目覚めたり目覚めなかったりしたときに、ほかの何をするよりも先に「あれ読もう」とぼやぼやした頭でも思える本に会えるのはうれしい。そういえばここ数年くらい、ひとの「思ったけど言わなかったこと」「行動の選択肢にあったけどしなかったこと」に興味をもっていたので、であればこのエッセイはうってつけなわけだった。それにしても、読みはじめたときにも思ったのだけど、小説を読んでいるみたいな心地になることがある。そんなエッセイは初めてな気がする。 - 2025年12月18日
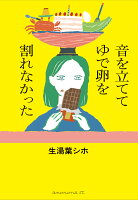 ⾳を⽴ててゆで卵を割れなかった生湯葉シホ読み始めた@ 本屋イトマイついに買った……読むべきな気配がつよく発せられながらどうして読むのをぼんやりためらっていたのか、それを予想していたわけではないのに読みはじめたらすっかりわかってしまった。自分、こうなのかという。生態系がおそらく近いところにあって。 自分のいつもの内心の右往左往ぶりは、それが動きというか、思考にしても移動みたいなもので残らないからぎり耐えてこられたけど、文に残るとすさまじいなと思った。別にわたしが書かれているわけではないですが。そもそも普段文を書くということをしていないので計り知れないけど、この思考のウォータースライダーみたいなものを文章にする勇気、ものすごいのではないかという気がする。メロンを腐らせるくだり、あまりにも流れがそのままだった。自分への嫌悪を筆で上回るさまを読むという体験ができてなぞの感動が押し寄せつつ、わたしはハックとしてくだものをもらうことになったらその場でカットしてもらうようにしはじめたなあそういえば(なんか1マスすすんだ!)と思ってそれを書きながら、いつも自分でカットしないところが最悪だなと思った。
⾳を⽴ててゆで卵を割れなかった生湯葉シホ読み始めた@ 本屋イトマイついに買った……読むべきな気配がつよく発せられながらどうして読むのをぼんやりためらっていたのか、それを予想していたわけではないのに読みはじめたらすっかりわかってしまった。自分、こうなのかという。生態系がおそらく近いところにあって。 自分のいつもの内心の右往左往ぶりは、それが動きというか、思考にしても移動みたいなもので残らないからぎり耐えてこられたけど、文に残るとすさまじいなと思った。別にわたしが書かれているわけではないですが。そもそも普段文を書くということをしていないので計り知れないけど、この思考のウォータースライダーみたいなものを文章にする勇気、ものすごいのではないかという気がする。メロンを腐らせるくだり、あまりにも流れがそのままだった。自分への嫌悪を筆で上回るさまを読むという体験ができてなぞの感動が押し寄せつつ、わたしはハックとしてくだものをもらうことになったらその場でカットしてもらうようにしはじめたなあそういえば(なんか1マスすすんだ!)と思ってそれを書きながら、いつも自分でカットしないところが最悪だなと思った。 - 2025年12月17日
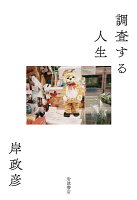 調査する人生岸政彦読んでる1章まで 「離れてしまった人たちの人生がどこかにあって、それは一つひとつ理解可能な行為の選択を繰り返しながらお互いに離れてしまったので、それを相互に理解できるようなものを書きたいです」 「精度が粗いことを書くと、暴力をまったく理解できなかったり、あるいは振り子が逆に振れて、美化したり、ロマンティックな話になってしまう」 「理解するってね、どこかで情状酌量してしまうんですよ」
調査する人生岸政彦読んでる1章まで 「離れてしまった人たちの人生がどこかにあって、それは一つひとつ理解可能な行為の選択を繰り返しながらお互いに離れてしまったので、それを相互に理解できるようなものを書きたいです」 「精度が粗いことを書くと、暴力をまったく理解できなかったり、あるいは振り子が逆に振れて、美化したり、ロマンティックな話になってしまう」 「理解するってね、どこかで情状酌量してしまうんですよ」 - 2025年12月6日
 なぜ人は締め切りを守れないのか難波優輝読んでる1章まで 「直線的なマジョリティの時間」を過ごせないことで代わりのようになくなっているのであろう空の時間 『虚弱に生きる』とつながるところがありそう、と思いながら読みすすめている 数年前に「なんか人生進んでないな?」と思ったけど、「人生が進む」という考え方もまた何かに支配されている
なぜ人は締め切りを守れないのか難波優輝読んでる1章まで 「直線的なマジョリティの時間」を過ごせないことで代わりのようになくなっているのであろう空の時間 『虚弱に生きる』とつながるところがありそう、と思いながら読みすすめている 数年前に「なんか人生進んでないな?」と思ったけど、「人生が進む」という考え方もまた何かに支配されている - 2025年12月2日
 かけないひび橋本亮二読み終わった@ 曲線読んだら、自分、もう全然バランスがとれていないのではないかと気づい(てしまっ)た。ぱきぱき「仕事」を消化したいのと、話すべきひととゆっくり会話を重ねたいの、すべてが早く過ぎ去って終わってほしいのと、ひとつひとつを書きとめて読めるようにしておきたいしそのために時間を丁重にあつかいたいの。手足がこの4つに拘束されていて、処刑みたいにそれがいきものに繋がれており、なにかのはずみでかれらが走り出したらああ〜っとなる、みたいなイメージが浮かぶ。ここしばらくそのどれかの感情が急に勢いよく引っぱってくるかんじで、でもどれもはっきりと同居している感情なので、こまりはてていた。ということがわかった。 なぜ読むことによって自分がこまっていることがわかったのかわからず、救いをもとめて買うことにしたわけでもなく、なぜ気づくことになったんだ……?とぼんやりしたまま数時間経っている。きれいでよいことで締めたいわけではないけど、棚で偶然見つけることができてよかったなあとおもっている。
かけないひび橋本亮二読み終わった@ 曲線読んだら、自分、もう全然バランスがとれていないのではないかと気づい(てしまっ)た。ぱきぱき「仕事」を消化したいのと、話すべきひととゆっくり会話を重ねたいの、すべてが早く過ぎ去って終わってほしいのと、ひとつひとつを書きとめて読めるようにしておきたいしそのために時間を丁重にあつかいたいの。手足がこの4つに拘束されていて、処刑みたいにそれがいきものに繋がれており、なにかのはずみでかれらが走り出したらああ〜っとなる、みたいなイメージが浮かぶ。ここしばらくそのどれかの感情が急に勢いよく引っぱってくるかんじで、でもどれもはっきりと同居している感情なので、こまりはてていた。ということがわかった。 なぜ読むことによって自分がこまっていることがわかったのかわからず、救いをもとめて買うことにしたわけでもなく、なぜ気づくことになったんだ……?とぼんやりしたまま数時間経っている。きれいでよいことで締めたいわけではないけど、棚で偶然見つけることができてよかったなあとおもっている。 - 2025年12月2日
 季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト読んでる今日は小沼理さん。おでんたべながら。ずっと読んでいたい。会ったことのないひとの過去の日記をずっと読んでいたいという感情、なんなんだ?
季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト読んでる今日は小沼理さん。おでんたべながら。ずっと読んでいたい。会ったことのないひとの過去の日記をずっと読んでいたいという感情、なんなんだ?
読み込み中...