
きよ
@kiyomune
本を、読むぞ!オー!
- 2026年2月11日
 言葉の展望台三木那由他読み終わったchatGPTにお薦めされて買った本、その2。 「出会ったことのない著者の本」として手に取ったはずが、実は、模試にも取り上げられて話題となった「謝罪の懐疑論」で、すでに顔見知りとなっていた方の本だったのでした。間抜けですこと。 それにしても、収録された他論の一貫した思考スタンスと、とても面白く読んだ「謝罪の懐疑論」の論旨が結びつかないだなんて……126ページを開いた途端の「あなただったのか!」という驚きたるや。 己の未熟さはさておき、収録されたエッセイ(と評論の中間のようなもの)は、どれも染み渡るように面白かった。 言語哲学が、もしかすると「自分の発話の意味を他人によって占有される経験が少ない人々」によって担われてきたのかも知れない、という仮説には、何よりも説得力がある。 なるほど、「言葉を適切に選べば気持ちは伝わる」という考え方でないと、理論は成り立ちにくいのだと思う。その一方で、コミュニケーションの不通なくして生まれえぬ言語哲学が、不通ととことん向き合わずに議論すればそれは、受け止められなかった言葉に対する暴力なのではないかとも思われ、そう思えたことが、この本と出会えた何よりの僥倖だとも感ぜられた。
言葉の展望台三木那由他読み終わったchatGPTにお薦めされて買った本、その2。 「出会ったことのない著者の本」として手に取ったはずが、実は、模試にも取り上げられて話題となった「謝罪の懐疑論」で、すでに顔見知りとなっていた方の本だったのでした。間抜けですこと。 それにしても、収録された他論の一貫した思考スタンスと、とても面白く読んだ「謝罪の懐疑論」の論旨が結びつかないだなんて……126ページを開いた途端の「あなただったのか!」という驚きたるや。 己の未熟さはさておき、収録されたエッセイ(と評論の中間のようなもの)は、どれも染み渡るように面白かった。 言語哲学が、もしかすると「自分の発話の意味を他人によって占有される経験が少ない人々」によって担われてきたのかも知れない、という仮説には、何よりも説得力がある。 なるほど、「言葉を適切に選べば気持ちは伝わる」という考え方でないと、理論は成り立ちにくいのだと思う。その一方で、コミュニケーションの不通なくして生まれえぬ言語哲学が、不通ととことん向き合わずに議論すればそれは、受け止められなかった言葉に対する暴力なのではないかとも思われ、そう思えたことが、この本と出会えた何よりの僥倖だとも感ぜられた。 - 2026年1月25日
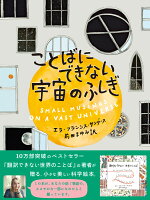 ことばにできない宇宙のふしぎエラ・フランシス・サンダース,前田まゆみ読み終わった同著者『翻訳できない世界のことば』を楽しく読んだので、この本もきっと、と期待したのだが、今回は、私にとってはワクワク度少し低め。 この本は、科学現象のうつくしさをうつくしいままに語ろうとする傍ら、規模の大きさを示す(あるいは正確な情報を伝える)時には数字に頼りつつ、難しい話を2ページ程度にまとめてしまうので、立ち位置が、文学と図鑑、どっちつかずな感じ。 話題は広範囲に及び、知らないこともあって面白い記事は確かにあるのだが、行ったり来たりを繰り返すので、まるで、科学にロマンを感ずる人が、とりとめもなく語る、その話を書き留めた本のよう。
ことばにできない宇宙のふしぎエラ・フランシス・サンダース,前田まゆみ読み終わった同著者『翻訳できない世界のことば』を楽しく読んだので、この本もきっと、と期待したのだが、今回は、私にとってはワクワク度少し低め。 この本は、科学現象のうつくしさをうつくしいままに語ろうとする傍ら、規模の大きさを示す(あるいは正確な情報を伝える)時には数字に頼りつつ、難しい話を2ページ程度にまとめてしまうので、立ち位置が、文学と図鑑、どっちつかずな感じ。 話題は広範囲に及び、知らないこともあって面白い記事は確かにあるのだが、行ったり来たりを繰り返すので、まるで、科学にロマンを感ずる人が、とりとめもなく語る、その話を書き留めた本のよう。 - 2026年1月19日
 読み終わった途方もなく大きい/小さい数字を前にするとワーッ!となる。天文の話、細胞の話などがその筆頭で、大好きだけど、途方もなさに呆然としてしまう。 ということで、この本は大いに、私をゾワゾワさせ、固まらせ、ワーッと興奮させ、怖がらせてくれました(読破に2ヶ月近くかかってしまったのがその証左)。 この中身を3日の集中講義で浴び続けた高校生は、どんな大人になるんだろう。 まるで陳腐な精神論みたいなタイトルに、確かな重みと意味があることが、5cm近くある厚みの本で少しずつ見えてくる仕組み。 このタイトルだと、面白さが伝わらないような気がするし、このタイトルでないと、面白さは半減するようなもどかしさがある。 場所細胞のこと、パレアドリアのこと、シグモイド関数のこと、ゴンドラ実験のこと、誰かに話したくなる知識も、とにかくたくさん。 でも、この本の本質は、脳にまつわるトリビアを脈絡なく伝えることではない。 ので、この本が楽しかったことを人に伝えるためには、この本を読んでもらうしかない。 とにかく楽しかったという熱量が、自分の中でぐるぐるして大変になる。よい本でした。
読み終わった途方もなく大きい/小さい数字を前にするとワーッ!となる。天文の話、細胞の話などがその筆頭で、大好きだけど、途方もなさに呆然としてしまう。 ということで、この本は大いに、私をゾワゾワさせ、固まらせ、ワーッと興奮させ、怖がらせてくれました(読破に2ヶ月近くかかってしまったのがその証左)。 この中身を3日の集中講義で浴び続けた高校生は、どんな大人になるんだろう。 まるで陳腐な精神論みたいなタイトルに、確かな重みと意味があることが、5cm近くある厚みの本で少しずつ見えてくる仕組み。 このタイトルだと、面白さが伝わらないような気がするし、このタイトルでないと、面白さは半減するようなもどかしさがある。 場所細胞のこと、パレアドリアのこと、シグモイド関数のこと、ゴンドラ実験のこと、誰かに話したくなる知識も、とにかくたくさん。 でも、この本の本質は、脳にまつわるトリビアを脈絡なく伝えることではない。 ので、この本が楽しかったことを人に伝えるためには、この本を読んでもらうしかない。 とにかく楽しかったという熱量が、自分の中でぐるぐるして大変になる。よい本でした。 - 2026年1月18日
 読み終わった昨年、たまたま2025年の特集を読んで、面白かったので、今年も購入。 今年は、全体的に懸念と警鐘、失望の記事が多くなっていて、新しい技術に対する期待感は少なめだった。 だから、働く人たちの対談が逆にイキイキしていたのが面白くもあった。 メモ ・金星の硫酸雲の中に生命が存在する可能性(ホスフィンの存在が可能性を示唆する) ・開拓が生む人間らしさ ・週休3日制がはじまりそうな気配 ぜひそうなってほしいな…… ・テック企業の優秀な人材は野球選手のスターのような年収で引き抜かれている ・IQテストのスコアが年々上昇を続けていることを「フリン効果」という。反面、トーランス創造的思考テストのスコアは下降傾向 ・二酸化炭素が多すぎるので、植物の成長が早まり、人工衛星で観測する葉面積指数が、ゆるやかに増加傾向。 ・心理的安全性を構築する最良の方法は、それについて語るのをやめること ・AIのアノテーションワークはグローバルサウスの低賃金労働者によって支えられている ・人間性の証明を、プライバシー情報なしにできるか?(ゼロ知識証明)
読み終わった昨年、たまたま2025年の特集を読んで、面白かったので、今年も購入。 今年は、全体的に懸念と警鐘、失望の記事が多くなっていて、新しい技術に対する期待感は少なめだった。 だから、働く人たちの対談が逆にイキイキしていたのが面白くもあった。 メモ ・金星の硫酸雲の中に生命が存在する可能性(ホスフィンの存在が可能性を示唆する) ・開拓が生む人間らしさ ・週休3日制がはじまりそうな気配 ぜひそうなってほしいな…… ・テック企業の優秀な人材は野球選手のスターのような年収で引き抜かれている ・IQテストのスコアが年々上昇を続けていることを「フリン効果」という。反面、トーランス創造的思考テストのスコアは下降傾向 ・二酸化炭素が多すぎるので、植物の成長が早まり、人工衛星で観測する葉面積指数が、ゆるやかに増加傾向。 ・心理的安全性を構築する最良の方法は、それについて語るのをやめること ・AIのアノテーションワークはグローバルサウスの低賃金労働者によって支えられている ・人間性の証明を、プライバシー情報なしにできるか?(ゼロ知識証明) - 2026年1月2日
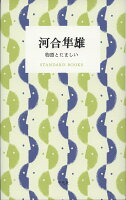 河合隼雄 物語とたましい河合隼雄読み終わった年末に、東畑さんのカウンセリングの本を読んだので、新年1冊目には必ずこの本を読もう、と、積読の本棚から取り出した1冊。 私はずっと、物事のバランスは対比によって取られていると思っていたし、白と黒の対比の間は灰色で、そこにはあわいがあるだけだと思っていたのだけれど、日本の神様の在り方は"中空均衡型”――アマテラスとスサノヲの間には「何もしない」ツクヨミが、海彦と山彦の間には「何もしない」ホスセリがいるということ、その「何もしないけどある」ものでバランスが保たれていることなど、考えたこともない視点がこの本には目白押しで、「わかっている」と思い込んでいる己の不自由さにハッとさせられた1冊だった。 ないけどあるものを、しかと見つめて言語化するというのは、相当な観察眼が必要だろう。 解明と決めつけのアンバランスを気にすることなく、生きているよな、自分は。
河合隼雄 物語とたましい河合隼雄読み終わった年末に、東畑さんのカウンセリングの本を読んだので、新年1冊目には必ずこの本を読もう、と、積読の本棚から取り出した1冊。 私はずっと、物事のバランスは対比によって取られていると思っていたし、白と黒の対比の間は灰色で、そこにはあわいがあるだけだと思っていたのだけれど、日本の神様の在り方は"中空均衡型”――アマテラスとスサノヲの間には「何もしない」ツクヨミが、海彦と山彦の間には「何もしない」ホスセリがいるということ、その「何もしないけどある」ものでバランスが保たれていることなど、考えたこともない視点がこの本には目白押しで、「わかっている」と思い込んでいる己の不自由さにハッとさせられた1冊だった。 ないけどあるものを、しかと見つめて言語化するというのは、相当な観察眼が必要だろう。 解明と決めつけのアンバランスを気にすることなく、生きているよな、自分は。 - 2025年12月29日
 読み終わったなんだか対人関係で嫌な思いをすることが多く、しんどかった時に目についた本。 基本的に、職場に配置されるカウンセラーに対して、胡散臭さを感じることが多い一方、恐ろしく観察眼のある人に見透かされてヒヤヒヤしたこともあり、いずれにせよ、彼らに対して警戒心が過剰にあるという自覚があったのだが、まさかなぜ彼らを胡散臭く感じてしまうのか、冒頭でいきなり丁寧に解きほぐしてもらえるとは思いもよらず、面白い読みはじめだった。 この本を読むことによって、私が切に求めているのは冒険としてのカウンセリングであり、他者と別れて物語を終わらすことができない己を垣間見ることととなり、少ししんどさがあった。 ひとりでなんでもできる!という自負が招く歪みのようなものを自覚しながら、依存ができないことが、自立できないことだという自覚は全くなかったことに気づかされたことも、なかなかしんどかった。 けれど、ずっと軸のずれた我慢や悩みでやり過ごしていたことがわかったのは、大きいと思う。 ありがたい本だった。
読み終わったなんだか対人関係で嫌な思いをすることが多く、しんどかった時に目についた本。 基本的に、職場に配置されるカウンセラーに対して、胡散臭さを感じることが多い一方、恐ろしく観察眼のある人に見透かされてヒヤヒヤしたこともあり、いずれにせよ、彼らに対して警戒心が過剰にあるという自覚があったのだが、まさかなぜ彼らを胡散臭く感じてしまうのか、冒頭でいきなり丁寧に解きほぐしてもらえるとは思いもよらず、面白い読みはじめだった。 この本を読むことによって、私が切に求めているのは冒険としてのカウンセリングであり、他者と別れて物語を終わらすことができない己を垣間見ることととなり、少ししんどさがあった。 ひとりでなんでもできる!という自負が招く歪みのようなものを自覚しながら、依存ができないことが、自立できないことだという自覚は全くなかったことに気づかされたことも、なかなかしんどかった。 けれど、ずっと軸のずれた我慢や悩みでやり過ごしていたことがわかったのは、大きいと思う。 ありがたい本だった。 - 2025年10月31日
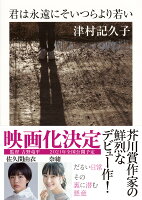 君は永遠にそいつらより若い津村記久子読み終わったはじめて読んだ、津村記久子さんの小説。 はじめは「なんだか下品な主人公だな」と自分から少し突き放すような気持ちで眺めていたが、内面に触れるたびどんどん好きになる。 人の痛みを己の痛みとして受け止めてしまう時も、自分自身が傷つけられて痛む時も、自分の汚さに打ちのめされた時も、悲劇に酔うことなく、でも目を逸らさないで(倒れはするけど)自分でヨタヨタと立ち上がるところがとても人として好ましい。 今年は、山本文緒さん含め、よい女性作家にたくさん出会えて嬉しい。
君は永遠にそいつらより若い津村記久子読み終わったはじめて読んだ、津村記久子さんの小説。 はじめは「なんだか下品な主人公だな」と自分から少し突き放すような気持ちで眺めていたが、内面に触れるたびどんどん好きになる。 人の痛みを己の痛みとして受け止めてしまう時も、自分自身が傷つけられて痛む時も、自分の汚さに打ちのめされた時も、悲劇に酔うことなく、でも目を逸らさないで(倒れはするけど)自分でヨタヨタと立ち上がるところがとても人として好ましい。 今年は、山本文緒さん含め、よい女性作家にたくさん出会えて嬉しい。 - 2025年10月15日
- 2025年9月16日
 わたしを離さないでカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わったわたしにとって、読み終えるのに時間を要する本だっだ。 コロナ療養中のお供にはカロリーが高すぎたけれど、療養中だから色々考えながら読めたとも言えそう。不思議な本。 とりとめもない幼少期の記憶は、下手をすると冗長とも言える文量だというのに、うっすらとした不穏さを適度に嗅がせながらだれることなく続く。 こちらに解明の手応えをたいして与えぬまま、かと思えば時折、不自然さを全く帯びずに鋭く核心の話をつきつけていく、バランスが見事。 はじめは音楽つながりでしかなかった表題も、湿地帯に乗り上げた船を3人で観に行ったあたりから、あらゆる人の思いとしてガッチリ機能しはじめ、格好いいったらなかった。 まさかこんなメロウなタイトルが、切実なメッセージとして機能すると、読前誰が思うだろうか。 そういえば途中、トミーとキャシーはルースみたいな女のどこがいいのだ、とかなりイライラさせられたが、思い起こしてみるに、知ったかぶりの、大人びて見える同い年の女の子が、幼い時ほど輝かしく、歳をとるにつれ煩わしく見える、というのは、往々にしてあるな……
わたしを離さないでカズオ・イシグロ,土屋政雄読み終わったわたしにとって、読み終えるのに時間を要する本だっだ。 コロナ療養中のお供にはカロリーが高すぎたけれど、療養中だから色々考えながら読めたとも言えそう。不思議な本。 とりとめもない幼少期の記憶は、下手をすると冗長とも言える文量だというのに、うっすらとした不穏さを適度に嗅がせながらだれることなく続く。 こちらに解明の手応えをたいして与えぬまま、かと思えば時折、不自然さを全く帯びずに鋭く核心の話をつきつけていく、バランスが見事。 はじめは音楽つながりでしかなかった表題も、湿地帯に乗り上げた船を3人で観に行ったあたりから、あらゆる人の思いとしてガッチリ機能しはじめ、格好いいったらなかった。 まさかこんなメロウなタイトルが、切実なメッセージとして機能すると、読前誰が思うだろうか。 そういえば途中、トミーとキャシーはルースみたいな女のどこがいいのだ、とかなりイライラさせられたが、思い起こしてみるに、知ったかぶりの、大人びて見える同い年の女の子が、幼い時ほど輝かしく、歳をとるにつれ煩わしく見える、というのは、往々にしてあるな…… - 2025年9月7日
 生命式村田沙耶香読み終わった今現在、真っ当と言われる(であろう)感覚で気持ちが悪いと思われるものが美しく、美しいと言われるものが恐ろしく描かれている。反対にしただけ、と言えばそうなのだけれど、こんなに見事に濁りなくきっちり、180度ものの見方をくるっと変えてものが書けるものかしら? 頭の中に手を突っ込んでぐちゃぐちゃにされたような、ぐちゃぐちゃにされたことで冴え渡ったような、奇妙な感覚。
生命式村田沙耶香読み終わった今現在、真っ当と言われる(であろう)感覚で気持ちが悪いと思われるものが美しく、美しいと言われるものが恐ろしく描かれている。反対にしただけ、と言えばそうなのだけれど、こんなに見事に濁りなくきっちり、180度ものの見方をくるっと変えてものが書けるものかしら? 頭の中に手を突っ込んでぐちゃぐちゃにされたような、ぐちゃぐちゃにされたことで冴え渡ったような、奇妙な感覚。 - 2025年9月2日
 読み終わった農業従事者から、消費者に向けて渡す、名刺代わりのような1冊。 取り組みの目的を丁寧に説明して、手段を具体的に紹介してくれるため、本人のこれまでを知らずとも、きちんとストーリーを追える。なおかつくどくない。テーマごと、見開き2ページに文量をまとめきる手腕も見事(話し足りないことはおそらく別章に分けている)。 農業の悩みについては、ちょこちょこ本や記事を読んできたけれど、この本のように数値(畑の広さや利率など)を出してくれているものは多くなく、イメージが掴みやすくてとてもよかった。 ともすれば「イメージ戦略をもって自分をプロモーションするしたたかな人」と言われそうなところも含めて、バランス感覚が鋭い印象。 雑事に惑わされず、納得のいくお米づくりができますようにと応援したくなる(のがまた、利休さんの術中に嵌っているので愉快だ)。
読み終わった農業従事者から、消費者に向けて渡す、名刺代わりのような1冊。 取り組みの目的を丁寧に説明して、手段を具体的に紹介してくれるため、本人のこれまでを知らずとも、きちんとストーリーを追える。なおかつくどくない。テーマごと、見開き2ページに文量をまとめきる手腕も見事(話し足りないことはおそらく別章に分けている)。 農業の悩みについては、ちょこちょこ本や記事を読んできたけれど、この本のように数値(畑の広さや利率など)を出してくれているものは多くなく、イメージが掴みやすくてとてもよかった。 ともすれば「イメージ戦略をもって自分をプロモーションするしたたかな人」と言われそうなところも含めて、バランス感覚が鋭い印象。 雑事に惑わされず、納得のいくお米づくりができますようにと応援したくなる(のがまた、利休さんの術中に嵌っているので愉快だ)。 - 2025年8月31日
 日々の100松浦弥太郎読み終わったパーソナライズしたAIに「お前さんが好きそうだ」と勧められて買った本。ストライクのど真ん中で焦った。 松浦さんの生活に寄り添う、愛着のあるアイテムを一点一点紹介している本で、文字数も多くないのだが、物の手触りや味わいを想像する余白があり、読み応えがある。 100以上のものの紹介文を読むうち、松浦さんがまるで知り合いであるかのように感じられて愉快だ。 物との付き合い方が人となりを見せてくれるのはどうにも、たまらなく素敵だ。
日々の100松浦弥太郎読み終わったパーソナライズしたAIに「お前さんが好きそうだ」と勧められて買った本。ストライクのど真ん中で焦った。 松浦さんの生活に寄り添う、愛着のあるアイテムを一点一点紹介している本で、文字数も多くないのだが、物の手触りや味わいを想像する余白があり、読み応えがある。 100以上のものの紹介文を読むうち、松浦さんがまるで知り合いであるかのように感じられて愉快だ。 物との付き合い方が人となりを見せてくれるのはどうにも、たまらなく素敵だ。 - 2025年8月28日
 ただいま装幀中クラフト・エヴィング商會読み終わったすこぶる健やかで、元気の出る自賛の本(悪口では全くない)。 ちくまプリマーが「子どもへのプレゼント」というコンセプトで作られていることをふまえ、贈り物なのだから、「自分たちが作った表紙は最高だ!」という気持ちで送り出した方がよい、という心持ちはとても爽やかで、私も仕事でこうありたいなと心底思った。
ただいま装幀中クラフト・エヴィング商會読み終わったすこぶる健やかで、元気の出る自賛の本(悪口では全くない)。 ちくまプリマーが「子どもへのプレゼント」というコンセプトで作られていることをふまえ、贈り物なのだから、「自分たちが作った表紙は最高だ!」という気持ちで送り出した方がよい、という心持ちはとても爽やかで、私も仕事でこうありたいなと心底思った。 - 2025年8月28日
 体の知性を取り戻す尹雄大読み終わった身体を活用するもの(スポーツや芸術などら習い物として多く取り上げられている活動)に関する指導者の本を読むと、スキルを言語化することの重要性を説く本が、未だ多くある。一方で、例えば機械を指に嵌め、ピアニストと同じ動きを体験させることで上達を図る科学技術が生み出されるなど、身体の感覚に注目した本も、いろいろ出版されつつある。 根性と忍耐のレッスンから脱出すると、言語化派と身体感覚派が生まれるんだな…… それにしても今、バーチャルがリアルとして立ち上がりつつある中で、最も身近な「身体」の動かし方を改めて考える人たちがいる、というのは、生きることに対して誠実な感じがし、とても面白い。 ISBMを読み込んで、はじめて2014年発行の本だということに気づきびっくり。 知識武装の硬直に、もう10年も前から警鐘を鳴らしていた人がいたのだなぁ。
体の知性を取り戻す尹雄大読み終わった身体を活用するもの(スポーツや芸術などら習い物として多く取り上げられている活動)に関する指導者の本を読むと、スキルを言語化することの重要性を説く本が、未だ多くある。一方で、例えば機械を指に嵌め、ピアニストと同じ動きを体験させることで上達を図る科学技術が生み出されるなど、身体の感覚に注目した本も、いろいろ出版されつつある。 根性と忍耐のレッスンから脱出すると、言語化派と身体感覚派が生まれるんだな…… それにしても今、バーチャルがリアルとして立ち上がりつつある中で、最も身近な「身体」の動かし方を改めて考える人たちがいる、というのは、生きることに対して誠実な感じがし、とても面白い。 ISBMを読み込んで、はじめて2014年発行の本だということに気づきびっくり。 知識武装の硬直に、もう10年も前から警鐘を鳴らしていた人がいたのだなぁ。 - 2025年8月19日
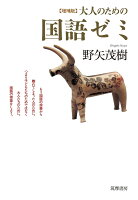 増補版 大人のための国語ゼミ野矢茂樹読み終わった理由と根拠と原因は、どう違うのか。 主張が理解できても納得できないとき、相手の理論をどう紐解いて、己の違和感をどう伝えるか。 感覚で理解し、流してしまいがちな「途中経過」の部分に、きちんと一時停止を入れて、理論で整理してくれる。 「読めば国語力がつく!」という類の、さも即戦力がつきそうなテクニックを謳うでもなく、何からはじめればよいか、基本を説明して、あとは実生活で試してみてください、と放流してくれるところに、読者、もとい言葉に対する信頼を感じる。
増補版 大人のための国語ゼミ野矢茂樹読み終わった理由と根拠と原因は、どう違うのか。 主張が理解できても納得できないとき、相手の理論をどう紐解いて、己の違和感をどう伝えるか。 感覚で理解し、流してしまいがちな「途中経過」の部分に、きちんと一時停止を入れて、理論で整理してくれる。 「読めば国語力がつく!」という類の、さも即戦力がつきそうなテクニックを謳うでもなく、何からはじめればよいか、基本を説明して、あとは実生活で試してみてください、と放流してくれるところに、読者、もとい言葉に対する信頼を感じる。 - 2025年8月18日
- 2025年8月18日
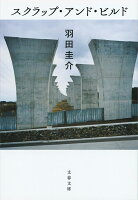 スクラップ・アンド・ビルド羽田圭介読み終わった退院後のアディショナルタイムオーディブル。 本全文が、最後の数行に至るまでの壮大なトレーニング記録だ、という印象。 タイトルを正しく踏まえて、前半は、単純な対比とイエス/ノーの判別が続くが、後半から少しずつ顔を出す「あわい」への視線や思考がとても良くて、丁寧な成長を感じる。 特に、「老い」を反面教師として捉え、肉体を磨く流れが、老いを学びとして闘志を得る流れに変わったのは、本当にいい。 あと、老いに対する嫌悪が、どこかコケティッシュなのが不思議で、胸が過度に傷まないのもよい。バランスに唸る。
スクラップ・アンド・ビルド羽田圭介読み終わった退院後のアディショナルタイムオーディブル。 本全文が、最後の数行に至るまでの壮大なトレーニング記録だ、という印象。 タイトルを正しく踏まえて、前半は、単純な対比とイエス/ノーの判別が続くが、後半から少しずつ顔を出す「あわい」への視線や思考がとても良くて、丁寧な成長を感じる。 特に、「老い」を反面教師として捉え、肉体を磨く流れが、老いを学びとして闘志を得る流れに変わったのは、本当にいい。 あと、老いに対する嫌悪が、どこかコケティッシュなのが不思議で、胸が過度に傷まないのもよい。バランスに唸る。 - 2025年8月13日
 継続する技術戸田大介読み終わった同名アプリのコラムや、ポップアップで出てくるちいさな文言、言葉選びのセンスが好きで、お布施のつもりで購入。 膨大なデータによる説得力と、そのデータを卑近なものに結びつける、突飛な(でも言い得て妙な)比喩、やはり唸るほどよかった。 基本的に、アプリ内のコラムを物語に流し込んだ本なので、新たな知識を得る、というよりも、肩の力の抜けた(でも要点はしっかり押さえてくれている)文言を楽しむ一冊、という感じ。 ずっと疑問に思っていた「なぜ『1日5分』という軽い目標と、『2日空いたらリセット』という厳しめの目標が抱き合わせなのか」という点について、本書で解決できたのはありがたいことだった。 なんでもケースバイケースで、場面を分断するの、本当によくない。反省。
継続する技術戸田大介読み終わった同名アプリのコラムや、ポップアップで出てくるちいさな文言、言葉選びのセンスが好きで、お布施のつもりで購入。 膨大なデータによる説得力と、そのデータを卑近なものに結びつける、突飛な(でも言い得て妙な)比喩、やはり唸るほどよかった。 基本的に、アプリ内のコラムを物語に流し込んだ本なので、新たな知識を得る、というよりも、肩の力の抜けた(でも要点はしっかり押さえてくれている)文言を楽しむ一冊、という感じ。 ずっと疑問に思っていた「なぜ『1日5分』という軽い目標と、『2日空いたらリセット』という厳しめの目標が抱き合わせなのか」という点について、本書で解決できたのはありがたいことだった。 なんでもケースバイケースで、場面を分断するの、本当によくない。反省。 - 2025年8月11日
 わたしの農継ぎ高橋久美子読み終わった筆者のお父さんみたく「『しんどいことを黙ってやる』のが農家」という考えでは離農の防止や新規参入の推進は進まないと思うし、筆者のように、どう畑と付き合っていくかを考えながら身体を動かすのは、とても誠実だと思う。俯瞰して見ることができるのは、二拠点ならではではないか。 一方で、この二拠点はやはり、頑固ながら学びに精力的なお父さんと、農作業に集まる人々を支えるお母さんあっての活動のようにも見えてしまい(とくに今作は強く感じられて)、読了後、複雑な気持ちに。
わたしの農継ぎ高橋久美子読み終わった筆者のお父さんみたく「『しんどいことを黙ってやる』のが農家」という考えでは離農の防止や新規参入の推進は進まないと思うし、筆者のように、どう畑と付き合っていくかを考えながら身体を動かすのは、とても誠実だと思う。俯瞰して見ることができるのは、二拠点ならではではないか。 一方で、この二拠点はやはり、頑固ながら学びに精力的なお父さんと、農作業に集まる人々を支えるお母さんあっての活動のようにも見えてしまい(とくに今作は強く感じられて)、読了後、複雑な気持ちに。 - 2025年8月5日
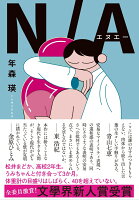 N/A年森瑛読み終わった入院中オーディブル第四段。 言いようもなく、その時々絶望的な、どうしても受け入れがたいものを前に、何を言うか/どうするか。 ゆっくり考えられるならいいけれど、今は「今」の力が強いぶん、「そのとき」が勝負で、しかも言葉は「力があるもの」と見なされている。 だから、その言葉を「引き出せない」自分が無力に感じられたり、あるはずだと指で硬い地面を掘るような努力で探さなければならなかったりする。 その息苦しさの描写が、壮絶だった。 テーマはしんどかったけど、言葉に疲れたことのある人の、言葉の力だったように思う。
N/A年森瑛読み終わった入院中オーディブル第四段。 言いようもなく、その時々絶望的な、どうしても受け入れがたいものを前に、何を言うか/どうするか。 ゆっくり考えられるならいいけれど、今は「今」の力が強いぶん、「そのとき」が勝負で、しかも言葉は「力があるもの」と見なされている。 だから、その言葉を「引き出せない」自分が無力に感じられたり、あるはずだと指で硬い地面を掘るような努力で探さなければならなかったりする。 その息苦しさの描写が、壮絶だった。 テーマはしんどかったけど、言葉に疲れたことのある人の、言葉の力だったように思う。
読み込み中...

