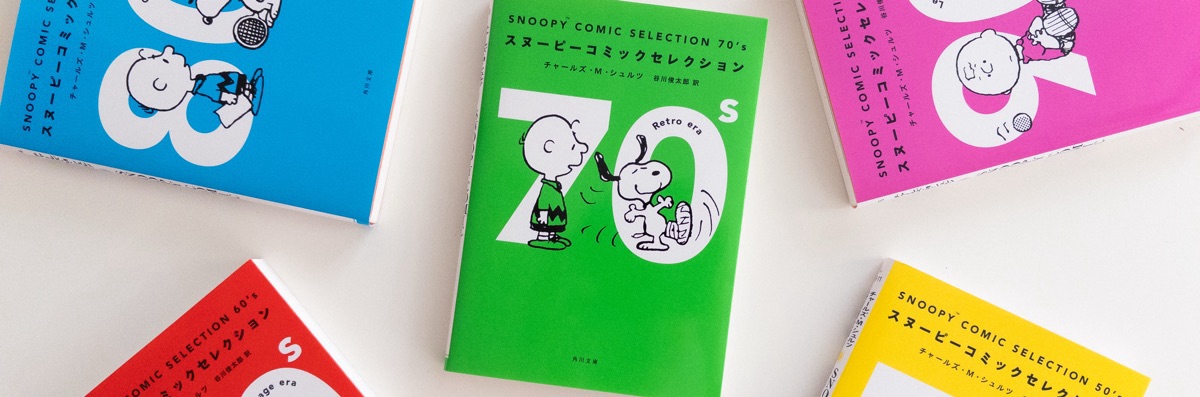

120
@120
働いているのでなぜか本が読めない。
ななめ読みしかしていない本についても堂々と語っていきたい。
- 2026年2月24日
 心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学ニック・チェイター,長谷川珈,高橋達二買った内面など存在せず、表層しかないという話。 アンディ・クラークの理論を、別の面から補完してくれそうな気がする。
心はこうして創られる 「即興する脳」の心理学ニック・チェイター,長谷川珈,高橋達二買った内面など存在せず、表層しかないという話。 アンディ・クラークの理論を、別の面から補完してくれそうな気がする。 - 2026年2月21日
 読み終わった批評とは何かを考える本であり、鑑賞する行為そのものについて明らかにしていく本でもある。 議論の土台を整える導入部分となる3章までで、すでにかなり面白い。本題となる4章から、議論は複雑化してくるが、初学者にも分かりやすくクリアに書かれている。各章もコンパクトにまとめられているし、何より章のタイトルが端的で、かなり読みやすいと思う。 最終章の「批評の意義は判断の柔軟性を養うことにある」には全面的に同意するし、批評や芸術に触れることにそれなりのリソースを費やしている身としては、勇気づけられる内容でもあった。 少し前に音楽評論界隈で話題になった、「内在的批評 vs 外在的批評」みたいな話も、1950年代にはすでに議論されていることも分かる。 (検索してみたところ、この話題に筆者もnoteで応答していて、もっとも説得力があった) エリック・サティ、フレデリック・ショパン、マルセル・デュシャン、「悪魔のいけにえ」、「チェンソーマン」、「OK Computer」などなど、例示される固有名詞を追うのも楽しい。
読み終わった批評とは何かを考える本であり、鑑賞する行為そのものについて明らかにしていく本でもある。 議論の土台を整える導入部分となる3章までで、すでにかなり面白い。本題となる4章から、議論は複雑化してくるが、初学者にも分かりやすくクリアに書かれている。各章もコンパクトにまとめられているし、何より章のタイトルが端的で、かなり読みやすいと思う。 最終章の「批評の意義は判断の柔軟性を養うことにある」には全面的に同意するし、批評や芸術に触れることにそれなりのリソースを費やしている身としては、勇気づけられる内容でもあった。 少し前に音楽評論界隈で話題になった、「内在的批評 vs 外在的批評」みたいな話も、1950年代にはすでに議論されていることも分かる。 (検索してみたところ、この話題に筆者もnoteで応答していて、もっとも説得力があった) エリック・サティ、フレデリック・ショパン、マルセル・デュシャン、「悪魔のいけにえ」、「チェンソーマン」、「OK Computer」などなど、例示される固有名詞を追うのも楽しい。 - 2026年2月19日
- 2026年2月19日
- 2026年2月19日
- 2026年2月8日
- 2026年2月8日
- 2026年2月8日
 デヴィッド・ボウイ 増補新版野中モモ読み終わった後年から後追いした身からすると、スタイルの変遷が分かりにくく感じていたボウイについて、その時々での背景が伝わってきて分かりやすい。 コンパクトで読みやすいが、しかし濃密な情報量。 アルバム単位で、時代を追って聞き返したくなった。 それにしても、大スターのイメージしかないボウイにも、なかなか花開かない下積み時代があったのか……と驚く。 94年に早くもインターネットの公式サイトを立ち上げ、98年にはプロバイダ事業(加入すると@davidbowie.comのメールアドレスが取得できる)まで行っていたというエピソードも面白い。
デヴィッド・ボウイ 増補新版野中モモ読み終わった後年から後追いした身からすると、スタイルの変遷が分かりにくく感じていたボウイについて、その時々での背景が伝わってきて分かりやすい。 コンパクトで読みやすいが、しかし濃密な情報量。 アルバム単位で、時代を追って聞き返したくなった。 それにしても、大スターのイメージしかないボウイにも、なかなか花開かない下積み時代があったのか……と驚く。 94年に早くもインターネットの公式サイトを立ち上げ、98年にはプロバイダ事業(加入すると@davidbowie.comのメールアドレスが取得できる)まで行っていたというエピソードも面白い。 - 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月7日
- 2026年2月1日
 インフレの時代渡辺努読み終わった買った黒田日銀が10年間かけて行った異次元緩和などの金融政策でも実現できなかったデフレ脱却だが、別の理由(パンデミックとプーチン大統領)によって日本でもインフレが始まり、早4年。いま重要なのは物価の抑制ではなく、賃金の上昇。 貨幣自体、「そこに価値がある」という共同幻想によって成り立つし、インフレも「インフレになる」とみんなが信じることで成り立つ。 デフレ時代を長く生きてきたので、今のインフレにまだ慣れないのだが、そんなことも言ってられない。 ああ、自分の仕事を頑張らねば。
インフレの時代渡辺努読み終わった買った黒田日銀が10年間かけて行った異次元緩和などの金融政策でも実現できなかったデフレ脱却だが、別の理由(パンデミックとプーチン大統領)によって日本でもインフレが始まり、早4年。いま重要なのは物価の抑制ではなく、賃金の上昇。 貨幣自体、「そこに価値がある」という共同幻想によって成り立つし、インフレも「インフレになる」とみんなが信じることで成り立つ。 デフレ時代を長く生きてきたので、今のインフレにまだ慣れないのだが、そんなことも言ってられない。 ああ、自分の仕事を頑張らねば。
読み込み中...














