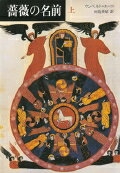た
@Yxodrei
ふつつかものですが
どうぞよろしくおねがいします。
- 2026年2月6日
 きらきらひかる江國香織読み終わった
きらきらひかる江國香織読み終わった - 2026年1月31日
 人のセックスを笑うな山崎ナオコーラ読み終わった
人のセックスを笑うな山崎ナオコーラ読み終わった - 2025年11月25日
- 2025年10月8日
- 2025年9月22日
- 2025年7月21日
- 2025年7月18日
- 2025年7月18日
 四つの署名アーサー・コナン・ドイル,駒月雅子読み終わった読書メモ(そういえば投稿していなかった!) 『緋色の研究』に続く長編第二作。今回もとても面白かった。不気味な館、謎の手紙、そしてテムズ川でのボートチェイス!緩急のある展開が絶妙で、まるで一本の映画を見終えたような満足感があった。 物語の構成も、前作よりぐっと洗練されている印象。事件を追うミステリ部分と、人間模様の描写が自然に絡み合っていて、読んでいて飽きがこない。 特に今回は、語り手ワトスンの描写がいつにも増して魅力的だった。依頼人モースタン嬢に恋し、浮き立ったり落ち込んだり、内心で大騒ぎしているワトスンが、とても人間味にあふれていて愛らしい。一方で、ホームズはいつも通り冷静沈着。まるで計算機のような男と、感情豊かな語り手とのコントラストが改めて鮮やかに際立っていた。 ふたりの関係性そのものが、このシリーズの最大の魅力かもしれない。 犯人の描写も印象的だ。 復讐に生涯をかけ、その果てに逮捕されながらも、どこか満ち足りたような表情を浮かべる人物には、哀愁と異質さが混じっていて、読後まで心に残る。動機の是非はともかくとして、“復讐を終えてしまった者の静けさ”には、不思議な魅力があった。
四つの署名アーサー・コナン・ドイル,駒月雅子読み終わった読書メモ(そういえば投稿していなかった!) 『緋色の研究』に続く長編第二作。今回もとても面白かった。不気味な館、謎の手紙、そしてテムズ川でのボートチェイス!緩急のある展開が絶妙で、まるで一本の映画を見終えたような満足感があった。 物語の構成も、前作よりぐっと洗練されている印象。事件を追うミステリ部分と、人間模様の描写が自然に絡み合っていて、読んでいて飽きがこない。 特に今回は、語り手ワトスンの描写がいつにも増して魅力的だった。依頼人モースタン嬢に恋し、浮き立ったり落ち込んだり、内心で大騒ぎしているワトスンが、とても人間味にあふれていて愛らしい。一方で、ホームズはいつも通り冷静沈着。まるで計算機のような男と、感情豊かな語り手とのコントラストが改めて鮮やかに際立っていた。 ふたりの関係性そのものが、このシリーズの最大の魅力かもしれない。 犯人の描写も印象的だ。 復讐に生涯をかけ、その果てに逮捕されながらも、どこか満ち足りたような表情を浮かべる人物には、哀愁と異質さが混じっていて、読後まで心に残る。動機の是非はともかくとして、“復讐を終えてしまった者の静けさ”には、不思議な魅力があった。 - 2025年7月17日
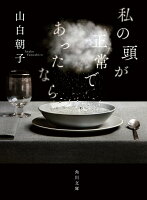 私の頭が正常であったなら山白朝子読みたい
私の頭が正常であったなら山白朝子読みたい - 2025年6月25日
- 2025年6月24日
- 2025年6月20日
- 2025年6月5日
- 2025年6月4日
- 2025年6月1日
 ポルトガルの海 増補版フェルナンド・ペソア,Fernando Pessoa,池上ミネ夫,池上岑夫わたしはペソア詩のなかでも、アルベルト・カエイロのものが特に好きだ。 『なにであれ存在すれば それだけで完全なのだ』
ポルトガルの海 増補版フェルナンド・ペソア,Fernando Pessoa,池上ミネ夫,池上岑夫わたしはペソア詩のなかでも、アルベルト・カエイロのものが特に好きだ。 『なにであれ存在すれば それだけで完全なのだ』 - 2025年5月13日
- 2025年4月24日
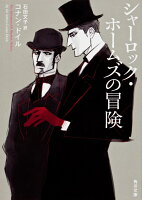 シャーロック・ホームズの冒険えすとえむ,コナン・ドイル,石田文子読み終わった感想わたしにとって、初ホームズとなった本! 全12編の短編集。どの話も端的で無駄がなく、それでいて読後にはさまざまな余韻が残る。起承転結が明快で、テンポ良く読めるのが嬉しい。 本書で描かれるのは、名探偵ホームズと、冷静な観察者としても優れたワトスン。彼らの関係は、いわゆる「探偵と助手」というより、才気煥発な変人と、それに振り回されつつも見守る良識人という印象に近い。読み進めるうちに、互いの尊敬と信頼が少しずつ滲み出してきて、気づけば「あれ、思っていたより仲良いな……」とニヤニヤしてしまった。 なかでも、ワトスンという語り手の絶妙さにだんだんと惹かれていった。 彼は決して無力な傍観者ではない。適度に推測し、考え、迷い、驚き、そして記録する。読者の代弁者として、非常にバランスが良い。 何より、ミステリとしての構造美を損なわず、かつホームズが切り捨てがちな、“人間性”をしっかり描いている。その距離感と感性の絶妙なバランスが、わたしはとても好きだ。 特に印象深かった話は『五つのオレンジの種』
シャーロック・ホームズの冒険えすとえむ,コナン・ドイル,石田文子読み終わった感想わたしにとって、初ホームズとなった本! 全12編の短編集。どの話も端的で無駄がなく、それでいて読後にはさまざまな余韻が残る。起承転結が明快で、テンポ良く読めるのが嬉しい。 本書で描かれるのは、名探偵ホームズと、冷静な観察者としても優れたワトスン。彼らの関係は、いわゆる「探偵と助手」というより、才気煥発な変人と、それに振り回されつつも見守る良識人という印象に近い。読み進めるうちに、互いの尊敬と信頼が少しずつ滲み出してきて、気づけば「あれ、思っていたより仲良いな……」とニヤニヤしてしまった。 なかでも、ワトスンという語り手の絶妙さにだんだんと惹かれていった。 彼は決して無力な傍観者ではない。適度に推測し、考え、迷い、驚き、そして記録する。読者の代弁者として、非常にバランスが良い。 何より、ミステリとしての構造美を損なわず、かつホームズが切り捨てがちな、“人間性”をしっかり描いている。その距離感と感性の絶妙なバランスが、わたしはとても好きだ。 特に印象深かった話は『五つのオレンジの種』 - 2025年4月17日
 ラ・ロシュフコー箴言集ラ・ロシュフコー,F.,二宮フサ感想読み始めた読み始めた。箴言という名の鋭い短刀で、情熱だの愛だの、そういうきらきらした外装をすぱっと切り裂き、その下に潜んでいた自己愛や虚栄をえぐりだしてくる感覚。辛辣。もはや痛快だ。おもしろい。 心当たりがあってぎくりとするものや、そういう人いるよね〜と思わず頷きたくなるもの、それは今の時代ではアウトかも…なもの、いろんな箴言があって楽しい。 『83. 人びとが友情と名付けたものは、単なる付き合い、利益の折り合い、親切のやりとりに過ぎない。所詮それは、自己愛が常に何か得をしようと目論んでいる取引きでしかないのである。』 『149. 称賛を固辞するのはもう一度褒めてほしいということである。』 『397. われわれは、自分は完全無欠で敵には長所が全くない、と全面的に言いきる勇気は持ち合わせないが、しかし部分的にはそう思い込んでいる節がなくもない。』
ラ・ロシュフコー箴言集ラ・ロシュフコー,F.,二宮フサ感想読み始めた読み始めた。箴言という名の鋭い短刀で、情熱だの愛だの、そういうきらきらした外装をすぱっと切り裂き、その下に潜んでいた自己愛や虚栄をえぐりだしてくる感覚。辛辣。もはや痛快だ。おもしろい。 心当たりがあってぎくりとするものや、そういう人いるよね〜と思わず頷きたくなるもの、それは今の時代ではアウトかも…なもの、いろんな箴言があって楽しい。 『83. 人びとが友情と名付けたものは、単なる付き合い、利益の折り合い、親切のやりとりに過ぎない。所詮それは、自己愛が常に何か得をしようと目論んでいる取引きでしかないのである。』 『149. 称賛を固辞するのはもう一度褒めてほしいということである。』 『397. われわれは、自分は完全無欠で敵には長所が全くない、と全面的に言いきる勇気は持ち合わせないが、しかし部分的にはそう思い込んでいる節がなくもない。』 - 2025年4月17日
 インド夜想曲 (白水Uブックス 99 海外小説の誘惑)アントニオ・タブッキ,アントーニョ・タブッキ,須賀敦子かつて読んだ感想失踪した友人を探して、インドを旅する男の12の夜の物語、と聞けばミステリーのようだが、これはむしろ「見つからないこと」を描いた物語だ。 夜のインド、不眠の旅、影のような記憶、すれ違う人々。現実と夢のあわいを彷徨うような不思議な感覚。 美と醜、喧騒と静寂、光と影、明瞭と曖昧……相反するものが綯い交ぜになって共存している。混沌がどこか心地いい。 夜の時間のみが描かれるのも好きだ。昼の風景がほとんど登場しないことで、現実感が希薄になり、まるで不眠の夜に記憶を反芻しているような、夢と現実の境界がぼやける感覚に陥る。 物語は12の夜の“抜粋集”のような構成。 作中のセリフに「引伸すと、コンテクストが本物でなくなる。〔……〕抜粋集にはご用心。」とあるが、私はこの“ご用心すべき断片性”に魅かれた。読者はこの抜粋集を自由に解釈し、想像を膨らませる事ができる。抜粋集にはご用心。しかしそれを楽しむのもまた一興だ。 読了後の余韻は、夢から目覚めたときの感覚に似ている。 「あれは何だったんだろう?」と思いながらも、妙に印象に残る。言葉にできない何かが引っかかり、また読み返したくなる。そして、また違う読み方をして、新たな迷宮へと迷い込む。 それが、この物語の誘いであり、魅力なのだと思う。
インド夜想曲 (白水Uブックス 99 海外小説の誘惑)アントニオ・タブッキ,アントーニョ・タブッキ,須賀敦子かつて読んだ感想失踪した友人を探して、インドを旅する男の12の夜の物語、と聞けばミステリーのようだが、これはむしろ「見つからないこと」を描いた物語だ。 夜のインド、不眠の旅、影のような記憶、すれ違う人々。現実と夢のあわいを彷徨うような不思議な感覚。 美と醜、喧騒と静寂、光と影、明瞭と曖昧……相反するものが綯い交ぜになって共存している。混沌がどこか心地いい。 夜の時間のみが描かれるのも好きだ。昼の風景がほとんど登場しないことで、現実感が希薄になり、まるで不眠の夜に記憶を反芻しているような、夢と現実の境界がぼやける感覚に陥る。 物語は12の夜の“抜粋集”のような構成。 作中のセリフに「引伸すと、コンテクストが本物でなくなる。〔……〕抜粋集にはご用心。」とあるが、私はこの“ご用心すべき断片性”に魅かれた。読者はこの抜粋集を自由に解釈し、想像を膨らませる事ができる。抜粋集にはご用心。しかしそれを楽しむのもまた一興だ。 読了後の余韻は、夢から目覚めたときの感覚に似ている。 「あれは何だったんだろう?」と思いながらも、妙に印象に残る。言葉にできない何かが引っかかり、また読み返したくなる。そして、また違う読み方をして、新たな迷宮へと迷い込む。 それが、この物語の誘いであり、魅力なのだと思う。 - 2025年4月17日
読み込み中...