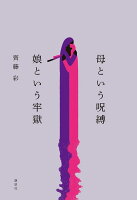くりこ
@kurikomone
三度の飯より本が好き。
生き延びるための読書。
- 2026年2月15日
 寛容多田富雄読みたい
寛容多田富雄読みたい - 2026年2月15日
 言葉果つるところ〈新版〉石牟礼道子,赤坂憲雄,赤坂真理,鶴見和子まだ読んでる言葉が果てる時を乗り越えるために、言葉を作り替えていく言葉が必要というお話に、心が震えた。私が思い出すのは北条民雄、ハンガン、李ことみなど絶望の淵から編み出された文学。 石牟礼さんと鶴見さんが、「言葉には丸い言葉と四角い言葉がある(丸い言葉は土着の言葉、四角い言葉は左翼の言葉)、丸い言葉を磨かないと」と話していているのを読み、大分言葉が四角い私は反省している。言葉が四角くなればなるほど自分の深いところには潜れなくなってきている。「構造」「自己決定権」「周縁化」とか使わず自分の心の奥の言葉を探れるようになりたい。それが、言葉を奪われたものの息づかいを感じることに繋がると思う。
言葉果つるところ〈新版〉石牟礼道子,赤坂憲雄,赤坂真理,鶴見和子まだ読んでる言葉が果てる時を乗り越えるために、言葉を作り替えていく言葉が必要というお話に、心が震えた。私が思い出すのは北条民雄、ハンガン、李ことみなど絶望の淵から編み出された文学。 石牟礼さんと鶴見さんが、「言葉には丸い言葉と四角い言葉がある(丸い言葉は土着の言葉、四角い言葉は左翼の言葉)、丸い言葉を磨かないと」と話していているのを読み、大分言葉が四角い私は反省している。言葉が四角くなればなるほど自分の深いところには潜れなくなってきている。「構造」「自己決定権」「周縁化」とか使わず自分の心の奥の言葉を探れるようになりたい。それが、言葉を奪われたものの息づかいを感じることに繋がると思う。 - 2026年2月15日
 わたしたちの権利の物語 第2期 奴隷制トビー・ニューサム,キャサリン・チェンバーズ,杉木志帆,松本有希子読みたい
わたしたちの権利の物語 第2期 奴隷制トビー・ニューサム,キャサリン・チェンバーズ,杉木志帆,松本有希子読みたい - 2026年2月15日
 武器としての非暴力中見真理読みたい
武器としての非暴力中見真理読みたい - 2026年2月13日
 言葉果つるところ〈新版〉石牟礼道子,赤坂憲雄,赤坂真理,鶴見和子読み始めた帯「言葉は討ち死にしてのたれ死にしていいんですよ」 「言葉果つるところに言葉が生まれる」 すごいこと書いてる!!!!!! ーーーーーーーー 最近の言語化ブームよくないよね、って話してたところだからドンピシャ。 (私は、絶望の淵に立たされた人が模索するように紡いだ言葉に酷く心を打たれる。言葉にならない状態が文学のスタート) 鶴見和子さん「言葉果てたるところから文学が出発する、そして文学は言葉果つるところに到着する、かつそこが出発点になる」 鶴見さん、石牟礼さんが、人間以外の物にまで目線を広げ、「息づかいが先にあって言葉が先にある」「息づきあっていたことをどう語りなおすか?」とお話ししているのも大変面白い!!
言葉果つるところ〈新版〉石牟礼道子,赤坂憲雄,赤坂真理,鶴見和子読み始めた帯「言葉は討ち死にしてのたれ死にしていいんですよ」 「言葉果つるところに言葉が生まれる」 すごいこと書いてる!!!!!! ーーーーーーーー 最近の言語化ブームよくないよね、って話してたところだからドンピシャ。 (私は、絶望の淵に立たされた人が模索するように紡いだ言葉に酷く心を打たれる。言葉にならない状態が文学のスタート) 鶴見和子さん「言葉果てたるところから文学が出発する、そして文学は言葉果つるところに到着する、かつそこが出発点になる」 鶴見さん、石牟礼さんが、人間以外の物にまで目線を広げ、「息づかいが先にあって言葉が先にある」「息づきあっていたことをどう語りなおすか?」とお話ししているのも大変面白い!! - 2026年2月13日
- 2026年2月12日
 シドニーの虹に誘われて李琴峰読みたい
シドニーの虹に誘われて李琴峰読みたい - 2026年2月12日
 ゆれる時代の生命倫理小林亜津子読み始めた77ページまで ちょっと簡単すぎたかなと思ったけど、卵子凍結については知らないことが沢山書いてあった。2021年に社会的卵子凍結(健康な女性が将来を見据えて卵子凍結する)が医療的卵子凍結(がん患者が治療の影響を避けるために行う)の数が、8倍以上に上ったということにぎょっとした。 きっと自民党が宗教右派と推し進めている、「産めよ増やせよ」の政策がうまくいっているのだ(ちょうど、プレコンと官製婚活がその流れ)
ゆれる時代の生命倫理小林亜津子読み始めた77ページまで ちょっと簡単すぎたかなと思ったけど、卵子凍結については知らないことが沢山書いてあった。2021年に社会的卵子凍結(健康な女性が将来を見据えて卵子凍結する)が医療的卵子凍結(がん患者が治療の影響を避けるために行う)の数が、8倍以上に上ったということにぎょっとした。 きっと自民党が宗教右派と推し進めている、「産めよ増やせよ」の政策がうまくいっているのだ(ちょうど、プレコンと官製婚活がその流れ) - 2026年2月12日
- 2026年2月12日
- 2026年2月12日
 切りとれ、あの祈る手を佐々木中読みたい
切りとれ、あの祈る手を佐々木中読みたい - 2026年2月11日
 ケアをすることの意味:病む人とともに在ることの心理学と医療人類学A.クラインマン,江口重幸読みたい
ケアをすることの意味:病む人とともに在ることの心理学と医療人類学A.クラインマン,江口重幸読みたい - 2026年2月10日
 私労働小説 ザ・シット・ジョブブレイディみかこ読みたい
私労働小説 ザ・シット・ジョブブレイディみかこ読みたい - 2026年2月10日
 自他の境界線を育てる鴻巣麻里香読みたい
自他の境界線を育てる鴻巣麻里香読みたい - 2026年2月10日
 DV・虐待加害者の実体を知るランディ・バンクロフト,高橋睦子まだ読んでるp.139まで 「相手をモノ化することによって、時間と共に虐待が酷くなる」「虐待と尊重は正反対」という指摘を見て、ある記述を思い出した。「なぜならそれは言葉にできるから 証言することと正義について」で言及されている、人は暴力を振るうために相手の姿を変えるということである(ひげをそる、髪を切らせる、同じ服を着せる)。 障害者や高齢者が虐待のリスクにさらされやすいことは、標準化された身体性と初めから姿が違うことで「モノ」として扱われやすい構造が関係しているのだろう
DV・虐待加害者の実体を知るランディ・バンクロフト,高橋睦子まだ読んでるp.139まで 「相手をモノ化することによって、時間と共に虐待が酷くなる」「虐待と尊重は正反対」という指摘を見て、ある記述を思い出した。「なぜならそれは言葉にできるから 証言することと正義について」で言及されている、人は暴力を振るうために相手の姿を変えるということである(ひげをそる、髪を切らせる、同じ服を着せる)。 障害者や高齢者が虐待のリスクにさらされやすいことは、標準化された身体性と初めから姿が違うことで「モノ」として扱われやすい構造が関係しているのだろう - 2026年2月10日
 現代思想 2021年11月号 特集=ルッキズムを考えるトミヤマユキコ,中村桃子,堀田義太郎,山田陽子,広瀬浩二郎,森山至貴,田中東子,西倉実季まだ読んでるエンハンスメントとしての美の実践 落合陽一の「身体の拡張」をはじめとしたエンハンスメントに違和感を感じていたので、批判的文脈で紹介されていたサンデルの「人間性論法」を知れたのはよかった。(私たちの能力才能は、ある程度運に左右されたもの(被贈与性)であるからこそ、自分の存在に対して完全な責任を取らなくて済んでいる。エンハンスメントが強化されれば「選べるもの」になる為責任は拡大し、社会の連帯の基盤が掘り起こされる)
現代思想 2021年11月号 特集=ルッキズムを考えるトミヤマユキコ,中村桃子,堀田義太郎,山田陽子,広瀬浩二郎,森山至貴,田中東子,西倉実季まだ読んでるエンハンスメントとしての美の実践 落合陽一の「身体の拡張」をはじめとしたエンハンスメントに違和感を感じていたので、批判的文脈で紹介されていたサンデルの「人間性論法」を知れたのはよかった。(私たちの能力才能は、ある程度運に左右されたもの(被贈与性)であるからこそ、自分の存在に対して完全な責任を取らなくて済んでいる。エンハンスメントが強化されれば「選べるもの」になる為責任は拡大し、社会の連帯の基盤が掘り起こされる) - 2026年2月8日
 現代ファシズム論山口二郎読みたい
現代ファシズム論山口二郎読みたい - 2026年2月8日
 AI・ロボットからの倫理学入門久木田水生,佐々木拓,本田康二郎,神崎宣次読み終わった読み終わった。アメリカでテック右派が勢力を伸ばしている一方、「テック左派」は出てこないことに疑問を持っていたが考えるヒントを貰った。 道徳的振る舞いをするAI、差別しないAI、プライバシーに配慮するAIを設計することにこれほどハードルが高いのだから、左派は慎重にならざるを得ないというのが理由の一つだろう(日本ではテック右派の流れではないが、AIを使って日本を成長させる「チームみらい」という新自由主義的価値観を持つ政党が出始めた。監視しとこう) 「良いも悪いもリモコン次第?」 自立型兵器の使用について。 自立型兵器の賛否について議論されているが、ピーターティールをはじめとするテック右派はすでにイスラエルで導入しているし、顔認証が出来る自律型ロボットが使用されているよう。さらにはアメリカのICEが導入するという論考を読んだことがある。(怖すぎ)。 アメリカが帝国主義時代に再度突入した今の状況を著者がどう考えるか知りたい。 近い将来ホロコースト大量虐殺や、アブグレイブ刑務所の虐待のようなことも代わりにロボットがするんだろうか 「はたらくロボット」 著者はケア労働にAIを使うことを楽観的に見すぎているのではないかと感じた。 介護業界は常に人員不足で低賃金労働を強いられている。その一番の歪を追っているのは高齢者や障碍者と言った弱い立場のものたち。環境を改善せず、AIをあてがうという事は、問題を個人化させる(認知症の高齢者の対応は「イライラする」ので、AIと話をさせる老人ホームがあるという論考をみたことがある。ここで問を反転してほしい。「イライラさせている」のは私たちの方ではないか?)。 人の抱える問題を個人化させず、社会モデルで考えることを促すようなAIは出来ないものか???
AI・ロボットからの倫理学入門久木田水生,佐々木拓,本田康二郎,神崎宣次読み終わった読み終わった。アメリカでテック右派が勢力を伸ばしている一方、「テック左派」は出てこないことに疑問を持っていたが考えるヒントを貰った。 道徳的振る舞いをするAI、差別しないAI、プライバシーに配慮するAIを設計することにこれほどハードルが高いのだから、左派は慎重にならざるを得ないというのが理由の一つだろう(日本ではテック右派の流れではないが、AIを使って日本を成長させる「チームみらい」という新自由主義的価値観を持つ政党が出始めた。監視しとこう) 「良いも悪いもリモコン次第?」 自立型兵器の使用について。 自立型兵器の賛否について議論されているが、ピーターティールをはじめとするテック右派はすでにイスラエルで導入しているし、顔認証が出来る自律型ロボットが使用されているよう。さらにはアメリカのICEが導入するという論考を読んだことがある。(怖すぎ)。 アメリカが帝国主義時代に再度突入した今の状況を著者がどう考えるか知りたい。 近い将来ホロコースト大量虐殺や、アブグレイブ刑務所の虐待のようなことも代わりにロボットがするんだろうか 「はたらくロボット」 著者はケア労働にAIを使うことを楽観的に見すぎているのではないかと感じた。 介護業界は常に人員不足で低賃金労働を強いられている。その一番の歪を追っているのは高齢者や障碍者と言った弱い立場のものたち。環境を改善せず、AIをあてがうという事は、問題を個人化させる(認知症の高齢者の対応は「イライラする」ので、AIと話をさせる老人ホームがあるという論考をみたことがある。ここで問を反転してほしい。「イライラさせている」のは私たちの方ではないか?)。 人の抱える問題を個人化させず、社会モデルで考えることを促すようなAIは出来ないものか??? - 2026年2月8日
 検証 戦争に加担した日本文学(3)チトコ=ヂュープランティス・マウゴジャタ・カロリナ,井浪真吾,佐藤織衣,孫世偉,張永嬌,木下宏一,朴光賢,朴賢率,松澤俊二,梅田径,河路由佳,白石佳和,雲龍櫻子,韓京子読みたいこんな状況でも、戦争反対を表明するアーティストたちがいることは救い。ただいよいよ、という緊張はある。 自分に何ができるか考えたい
検証 戦争に加担した日本文学(3)チトコ=ヂュープランティス・マウゴジャタ・カロリナ,井浪真吾,佐藤織衣,孫世偉,張永嬌,木下宏一,朴光賢,朴賢率,松澤俊二,梅田径,河路由佳,白石佳和,雲龍櫻子,韓京子読みたいこんな状況でも、戦争反対を表明するアーティストたちがいることは救い。ただいよいよ、という緊張はある。 自分に何ができるか考えたい - 2026年2月7日
 DV・虐待加害者の実体を知るランディ・バンクロフト,高橋睦子読み始めたp.65まで 同じ暴力のシーン一つとってもDV加害者と被害者の語りがまるで違うのは興味深く読んだ(加害者は被害者ポジションを取り自分を免責する語りをする) ただ、人を傷つける背景には、自分の被害者感情が必ずあるにもかかわらず、「DV加害者に過去の虐待の影響はない」と言い張る解説には疑問が残る。学校での全体主義的教育も人を管理下に置く身体性を身に着けるのにイチヤク買ってしまうので、虐待だけとはもちろん言い難いのだけど。 DV加害者が巧妙な手段を使って自分の味方を増やしていく解説には既視感がありゾッとした
DV・虐待加害者の実体を知るランディ・バンクロフト,高橋睦子読み始めたp.65まで 同じ暴力のシーン一つとってもDV加害者と被害者の語りがまるで違うのは興味深く読んだ(加害者は被害者ポジションを取り自分を免責する語りをする) ただ、人を傷つける背景には、自分の被害者感情が必ずあるにもかかわらず、「DV加害者に過去の虐待の影響はない」と言い張る解説には疑問が残る。学校での全体主義的教育も人を管理下に置く身体性を身に着けるのにイチヤク買ってしまうので、虐待だけとはもちろん言い難いのだけど。 DV加害者が巧妙な手段を使って自分の味方を増やしていく解説には既視感がありゾッとした
読み込み中...