
okabe
@m_okabe
- 2026年2月21日
 ねじまき鳥クロニクル 第2部村上春樹読み終わった第1部で提示された数々の謎が重なったり離れたりして、とにかく掴みどころがないが、その掴みどころのなさが物語の推進力になっている。 この小説でのマジックリアリズム表現は、トオルが現実・他者・自分自身と向き合うことを避けていることのメタファー?トオルは渡辺銀次?
ねじまき鳥クロニクル 第2部村上春樹読み終わった第1部で提示された数々の謎が重なったり離れたりして、とにかく掴みどころがないが、その掴みどころのなさが物語の推進力になっている。 この小説でのマジックリアリズム表現は、トオルが現実・他者・自分自身と向き合うことを避けていることのメタファー?トオルは渡辺銀次? - 2026年2月17日
 ねじまき鳥クロニクル 第1部村上春樹読み終わった「少尉殿、この戦争には大義もなんにもありゃしませんぜ。こいつはただの殺しあいです。そして踏みつけられるのは、結局のところ貧しい農民たちです。」(p.311) 苦手というわけでもないのだけど、あまり読まずにいた村上春樹。いざ読み始めると、その文学性とエンタメ性の絶妙なバランスに感服させられる。
ねじまき鳥クロニクル 第1部村上春樹読み終わった「少尉殿、この戦争には大義もなんにもありゃしませんぜ。こいつはただの殺しあいです。そして踏みつけられるのは、結局のところ貧しい農民たちです。」(p.311) 苦手というわけでもないのだけど、あまり読まずにいた村上春樹。いざ読み始めると、その文学性とエンタメ性の絶妙なバランスに感服させられる。 - 2026年2月14日
- 2026年2月14日
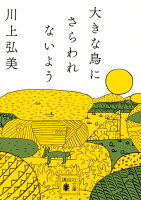 大きな鳥にさらわれないよう川上弘美読み終わった国際ブッカー賞最終候補作とのことで、興味を惹かれ読んだ。 ひとつひとつの物語が少しずつ重なり、未来の形が少しずつ浮かび上がってくる。特にラスト100ページはゾッとする快感があった。明らかにされるのは、人間がその愚かさ故に衰退し絶滅していくこと。現実でもその未来は案外すぐそこにあるように思える。
大きな鳥にさらわれないよう川上弘美読み終わった国際ブッカー賞最終候補作とのことで、興味を惹かれ読んだ。 ひとつひとつの物語が少しずつ重なり、未来の形が少しずつ浮かび上がってくる。特にラスト100ページはゾッとする快感があった。明らかにされるのは、人間がその愚かさ故に衰退し絶滅していくこと。現実でもその未来は案外すぐそこにあるように思える。 - 2026年2月12日
 環状島=トラウマの地政学 新装版宮地尚子読み終わった環状島モデルについては新書『トラウマ』で学んだので、本書は自分がいち支援者として何が出来るか、何に留意すべきかという視点で読んだ。 まずは、ミクロレベルで環状島を作ること。支援者を集めて支援の輪を作り、各々のポジションを確認しながら支援に当たる。ここで留意すべきは、支援者の加害性やマジョリティ性を批判される可能性があるということ。しかしそれを全面的な否定とは捉えず、クライエントのそばに居続けることが重要。 そして、マクロレベルで環状島を作ること。自分ひとりの活動では限界があるが、周りを見渡せば同じように活動する仲間を見つけられるはず。仲間と共に声を大きくしていくことで問題をイシュー化することができる。ここで留意すべきは、当事者の意に反して問題をイシュー化しないこと。無理矢理にそれをすることは、支援者とクライエントの間に軋轢を生み、支援を困難にしてしまう。
環状島=トラウマの地政学 新装版宮地尚子読み終わった環状島モデルについては新書『トラウマ』で学んだので、本書は自分がいち支援者として何が出来るか、何に留意すべきかという視点で読んだ。 まずは、ミクロレベルで環状島を作ること。支援者を集めて支援の輪を作り、各々のポジションを確認しながら支援に当たる。ここで留意すべきは、支援者の加害性やマジョリティ性を批判される可能性があるということ。しかしそれを全面的な否定とは捉えず、クライエントのそばに居続けることが重要。 そして、マクロレベルで環状島を作ること。自分ひとりの活動では限界があるが、周りを見渡せば同じように活動する仲間を見つけられるはず。仲間と共に声を大きくしていくことで問題をイシュー化することができる。ここで留意すべきは、当事者の意に反して問題をイシュー化しないこと。無理矢理にそれをすることは、支援者とクライエントの間に軋轢を生み、支援を困難にしてしまう。 - 2026年2月7日
 刑務所の精神科医野村俊明読み終わった「被害者の権利が護られることと加害者への支援や治療が積極的に行われることは、矛盾・対立するわけではないはずである。」(p.206) 精神疾患・発達障害や社会環境・家庭環境が要因で起こってしまう犯罪が少なからずある。刑罰を与えるだけではなく、医療・福祉と地域が連携しながら加害者支援をすることに寛容な社会であってほしい。
刑務所の精神科医野村俊明読み終わった「被害者の権利が護られることと加害者への支援や治療が積極的に行われることは、矛盾・対立するわけではないはずである。」(p.206) 精神疾患・発達障害や社会環境・家庭環境が要因で起こってしまう犯罪が少なからずある。刑罰を与えるだけではなく、医療・福祉と地域が連携しながら加害者支援をすることに寛容な社会であってほしい。 - 2026年2月6日
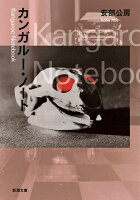 カンガルー・ノート安部公房読み終わった映画「砂の女」「他人の顔」を観て、久々に安部公房を読みたくなった。 ユーモアを持ちながら死と向き合っている小説だと思った。自分の死について真剣に考えて、死を客観視できるようにならないと、こういう小説は書けないのではないだろうか。晩年の著者は遂にその境地に達して、この小説を書いたのかもしれない。
カンガルー・ノート安部公房読み終わった映画「砂の女」「他人の顔」を観て、久々に安部公房を読みたくなった。 ユーモアを持ちながら死と向き合っている小説だと思った。自分の死について真剣に考えて、死を客観視できるようにならないと、こういう小説は書けないのではないだろうか。晩年の著者は遂にその境地に達して、この小説を書いたのかもしれない。 - 2026年2月3日
 GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる平野啓一郎×マライ・メントライン「日本社会再定義 排外主義・鬱漫画・AI」 平野氏の「今のアメリカにいると何によって国外退去になるかわからない不安がある」という言葉、町山智浩氏もラジオで同じこと言っていた。
GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる平野啓一郎×マライ・メントライン「日本社会再定義 排外主義・鬱漫画・AI」 平野氏の「今のアメリカにいると何によって国外退去になるかわからない不安がある」という言葉、町山智浩氏もラジオで同じこと言っていた。 - 2026年2月3日
 灯台へヴァージニア・ウルフ,鴻巣友季子読み終わった視点が次から次へとシームレスに移っていく。読書が普段より能動的な行為になり、小説内世界へ没入していく気持ち良さがある。 第一章、登場人物の男性性・女性性がグラデーションになっている。『自分ひとりの部屋』で触れていた、「両性具有的」な表現? 第二章、闇と風が意思を持ったかのような描写は、嵐(=WWI)の前の静けさのようでもあり、嵐そのもののようでもある。 第三章、最後にリリーがヴィジョンをつかむ描写は、ウルフが自身や未来の女性に対して願いを込めているようにも思えた。
灯台へヴァージニア・ウルフ,鴻巣友季子読み終わった視点が次から次へとシームレスに移っていく。読書が普段より能動的な行為になり、小説内世界へ没入していく気持ち良さがある。 第一章、登場人物の男性性・女性性がグラデーションになっている。『自分ひとりの部屋』で触れていた、「両性具有的」な表現? 第二章、闇と風が意思を持ったかのような描写は、嵐(=WWI)の前の静けさのようでもあり、嵐そのもののようでもある。 第三章、最後にリリーがヴィジョンをつかむ描写は、ウルフが自身や未来の女性に対して願いを込めているようにも思えた。 - 2026年1月30日
 自分ひとりの部屋(831)ヴァージニア・ウルフ,Virginia Woolf,片山亜紀読み終わった感想を書くのも野暮に思えるほど想像力豊かでキレのある文章。 「過去何世紀にもわたって、女性は鏡の役割を務めてきました。鏡には魔法の甘美な力が備わっていて、男性の姿を二倍に拡大して映してきました。(•••)少なくとも二倍は拡大された自分の姿を見ることができなかったら、判決を下すとか、原住民を文明化するとか、法律を制定するとか、本を執筆するとか、正装して宴会でスピーチを述べるとか、そんなことをどうやって続けていけるでしょうか?」
自分ひとりの部屋(831)ヴァージニア・ウルフ,Virginia Woolf,片山亜紀読み終わった感想を書くのも野暮に思えるほど想像力豊かでキレのある文章。 「過去何世紀にもわたって、女性は鏡の役割を務めてきました。鏡には魔法の甘美な力が備わっていて、男性の姿を二倍に拡大して映してきました。(•••)少なくとも二倍は拡大された自分の姿を見ることができなかったら、判決を下すとか、原住民を文明化するとか、法律を制定するとか、本を執筆するとか、正装して宴会でスピーチを述べるとか、そんなことをどうやって続けていけるでしょうか?」 - 2026年1月24日
 母親になって後悔してるオルナ・ドーナト,鹿田昌美読み終わった仕事をする中で、「あのお母さんは育児能力が低い」「愛情が足りない」「もっと子どもと向き合うべきだ」という言葉をよく耳にする。そういった言葉がいかに想像力に欠ける言葉であったか、本書を読んで改めて感じた。 「このお母さんは自分が母親に向いていないと感じているかもしれない」「母親であること以上に大切にしたいことがあるのかもしれない」と想像することが大切だと思ったし、そして母親である以前にひとりの人間であり、多くの選択肢を持った存在なのだということを忘れてはならないと思った。
母親になって後悔してるオルナ・ドーナト,鹿田昌美読み終わった仕事をする中で、「あのお母さんは育児能力が低い」「愛情が足りない」「もっと子どもと向き合うべきだ」という言葉をよく耳にする。そういった言葉がいかに想像力に欠ける言葉であったか、本書を読んで改めて感じた。 「このお母さんは自分が母親に向いていないと感じているかもしれない」「母親であること以上に大切にしたいことがあるのかもしれない」と想像することが大切だと思ったし、そして母親である以前にひとりの人間であり、多くの選択肢を持った存在なのだということを忘れてはならないと思った。 - 2026年1月23日
- 2026年1月23日
 それから夏目漱石読み終わった久々に漱石を読んだ。 文章の美しさと、会話の緊張感。代助は電車に乗って、赤い景色を見て、それからどうしたのだろう。 漱石文学において、「近代化への不安」が大きなテーマだと言われる。今作は、近代化以前の価値観と、近代化以降の価値観の衝突の物語だと思った。
それから夏目漱石読み終わった久々に漱石を読んだ。 文章の美しさと、会話の緊張感。代助は電車に乗って、赤い景色を見て、それからどうしたのだろう。 漱石文学において、「近代化への不安」が大きなテーマだと言われる。今作は、近代化以前の価値観と、近代化以降の価値観の衝突の物語だと思った。 - 2026年1月21日
 GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる間宮改衣「ルリ色のハね」 現実は残酷かもしれないけど、それがたとえ幻でも、本人の中で存在していて、幸福をもたらしてくれて、これからも生きていけるのならいいよね。
GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる間宮改衣「ルリ色のハね」 現実は残酷かもしれないけど、それがたとえ幻でも、本人の中で存在していて、幸福をもたらしてくれて、これからも生きていけるのならいいよね。 - 2026年1月18日
 黒い皮膚・白い仮面 【新装版】フランツ・ファノン,加藤晴久,海老坂武読み終わった白人に近付きたいという願いと、黒人であることの何が悪いのかという怒り、その葛藤の中で生じるアイデンティティが引き裂かれる痛み。それらを生々しく文章にぶつけている。 差別は今だになくならない。しかしファノンの哲学は、読者である私たちをも問い続ける人間たらしめる。これはファノンがこの世界に遺した希望だ。
黒い皮膚・白い仮面 【新装版】フランツ・ファノン,加藤晴久,海老坂武読み終わった白人に近付きたいという願いと、黒人であることの何が悪いのかという怒り、その葛藤の中で生じるアイデンティティが引き裂かれる痛み。それらを生々しく文章にぶつけている。 差別は今だになくならない。しかしファノンの哲学は、読者である私たちをも問い続ける人間たらしめる。これはファノンがこの世界に遺した希望だ。 - 2026年1月16日
 パワー・オブ・ザ・ドッグトーマス・サヴェージ,波多野理彩子読み終わった年始に映画を見返して、原作も読んでみようと思った。 映画と原作では、キャラクターの人物造形や後半のストーリー展開がかなり違っていた。フィルの複雑な人物造形に映画としての魅力を感じていた自分としては、原作は少し物足りなさを感じてしまったが、最後の一文の切れ味は映画以上に鋭く感じた。
パワー・オブ・ザ・ドッグトーマス・サヴェージ,波多野理彩子読み終わった年始に映画を見返して、原作も読んでみようと思った。 映画と原作では、キャラクターの人物造形や後半のストーリー展開がかなり違っていた。フィルの複雑な人物造形に映画としての魅力を感じていた自分としては、原作は少し物足りなさを感じてしまったが、最後の一文の切れ味は映画以上に鋭く感じた。 - 2026年1月15日
 傷の声齋藤塔子読み終わった自分にとっては当事者性が高く、読むのを躊躇っていたが、遂に読んだ。 「こうして私は完全にモノに成り果てた」この感覚を自分は知っている。入院した時、看護師たちは作業的に点滴を交換するだけで、ほとんど目を合わせてくれなかった。看護師たちにとって、自分は個人などではなく対象物なのだと感じた。 「私は他者と溶け合ってしまうことが多い。それは喜びであることもあれば、重荷であることもある」この感覚も知っている。ケアする側でもある自分にとって、他者の悲しみや喜びを自分事として受け取れる感受性は大切にしたいと思っている。 「いつか私も、透き通った「愛してる」がわかる日が来ますように」と綴る著者が、もうこの世にいないことが悲しい。生きていてほしかった。
傷の声齋藤塔子読み終わった自分にとっては当事者性が高く、読むのを躊躇っていたが、遂に読んだ。 「こうして私は完全にモノに成り果てた」この感覚を自分は知っている。入院した時、看護師たちは作業的に点滴を交換するだけで、ほとんど目を合わせてくれなかった。看護師たちにとって、自分は個人などではなく対象物なのだと感じた。 「私は他者と溶け合ってしまうことが多い。それは喜びであることもあれば、重荷であることもある」この感覚も知っている。ケアする側でもある自分にとって、他者の悲しみや喜びを自分事として受け取れる感受性は大切にしたいと思っている。 「いつか私も、透き通った「愛してる」がわかる日が来ますように」と綴る著者が、もうこの世にいないことが悲しい。生きていてほしかった。 - 2026年1月14日
 GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる芦沢央「父の輪郭」 「何を持っているかで、その人の輪郭が決まる」それは物に限らず、どれほどの愛を持っているかということでもある。父と母の輪郭は美しい愛。
GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる芦沢央「父の輪郭」 「何を持っているかで、その人の輪郭が決まる」それは物に限らず、どれほどの愛を持っているかということでもある。父と母の輪郭は美しい愛。 - 2026年1月12日
 GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる九段理江「Beauticide」 ビューティサイドも逆ビューティサイドも本当に起きそう。でも本当に起きたら天沼先生のゴリラ論聞けなくなるから起きてほしくない。
GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる九段理江「Beauticide」 ビューティサイドも逆ビューティサイドも本当に起きそう。でも本当に起きたら天沼先生のゴリラ論聞けなくなるから起きてほしくない。 - 2026年1月11日
 GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる高瀬隼子「ふたえ」 自分の父親がけっこうがっつりめな整形をして、しかも父親と会うのはこれが最後かもしれないとか、どういう気持ちで読めばいいんですか。
GOAT Winter 2026九段理江,小学館,山口未桜,高瀬隼子読んでる高瀬隼子「ふたえ」 自分の父親がけっこうがっつりめな整形をして、しかも父親と会うのはこれが最後かもしれないとか、どういう気持ちで読めばいいんですか。
読み込み中...

