
田口為
@naseru_taguchi
少しずつでも本が読みたいなと思い、記録をつけることにしました。のびのびと読書したいです。
- 2026年2月15日
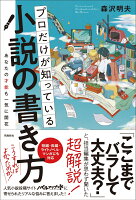 プロだけが知っている小説の書き方森沢明夫読み終わった小説の書き方をQ&A方式で述べている。描写、構成、モチベーションなど様々な角度から小説を書く方法論が書いてあるが、全体的に「オジサン構文」がすごい。ただこれは狙ってそうしている可能性もあるし、オジサン構文でも書き方について伝えたいことが書かれているなら本として間違いではない。 読んでいて辛かったのが「描写の具体例として挙げた文章が時代に合わない女性描写」「最近の書籍として挙げた本が10年以上前」であった点。作者の年齢を考えるとこうした女性キャラクター描写に違和感、嫌悪感はないのだろうし、10年前は最近という感覚もわかるが、読んでいて「作者自身に同意できない」箇所が多かった。 言っている内容は難解ではないが、問題に思う女性描写は序盤で出てくるので、読むのをそこでやめる人も出てくると思う。この本の作者の作品が好きな人向けと感じた。
プロだけが知っている小説の書き方森沢明夫読み終わった小説の書き方をQ&A方式で述べている。描写、構成、モチベーションなど様々な角度から小説を書く方法論が書いてあるが、全体的に「オジサン構文」がすごい。ただこれは狙ってそうしている可能性もあるし、オジサン構文でも書き方について伝えたいことが書かれているなら本として間違いではない。 読んでいて辛かったのが「描写の具体例として挙げた文章が時代に合わない女性描写」「最近の書籍として挙げた本が10年以上前」であった点。作者の年齢を考えるとこうした女性キャラクター描写に違和感、嫌悪感はないのだろうし、10年前は最近という感覚もわかるが、読んでいて「作者自身に同意できない」箇所が多かった。 言っている内容は難解ではないが、問題に思う女性描写は序盤で出てくるので、読むのをそこでやめる人も出てくると思う。この本の作者の作品が好きな人向けと感じた。 - 2026年2月7日
 いい感じの石ころを拾いに宮田珠己読み終わった1月に読み終わったのに、なかなか感想を書く腰が重くて、感想投稿までが長くなってしまった。 タイトル通り、著者にとっての「いい感じの石ころ」について語るエッセイである。石を拾いに行ったり、石の話を聴きに行ったり、石のイベントに行く話が収録されている。 読後感が良かった。というのも、この本はタイトルに惹かれて買ったのだ。疲れているが読書はしたい。内容理解に努める必要のない本が欲しい。そんな時に見つけたこのタイトルはまさに癒しであった。なんて難しく無さそうなタイトルなのだろう。その期待通り、疲れることなく読了できた。何故なら、著者も「いい感じの石ころは何かと聞かれると説明できないが、無理に説明しなくても良いとする」「今までいい感じと思っていなかった石がいい感じに見える。いい感じの基準がころころ変わるが、それで良いのである」というスタンスなのだ。エッセイの中に何度も著者の石ころに対する意識か出てくる。その度に「石ころを見るのに堅苦しい知識や思考は不要である」旨の文章が出てくるので、読者としても安心である。いい意味で何も考えなくて良いし、果たしてこの石ころのどこがいいのだろうか?と考えてもいい。読書は自由なものであると感じることができる本であった。 フルカラーでいい感じの石ころの写真が多数掲載されている。この本におけるいい感じの石ころとは、大きさや触った感触も含めて判断されるので、写真では「いい感じ」の全容を浴びることは叶わない。が、普段見向きしない石ころも、スポットを選べばバリエーションに富む面白いものだということはわかる。自分も日本海側の海岸に行く機会があれば、ひとつ探してみようかと思う感動があった。 緩い読書に最適な一冊である。
いい感じの石ころを拾いに宮田珠己読み終わった1月に読み終わったのに、なかなか感想を書く腰が重くて、感想投稿までが長くなってしまった。 タイトル通り、著者にとっての「いい感じの石ころ」について語るエッセイである。石を拾いに行ったり、石の話を聴きに行ったり、石のイベントに行く話が収録されている。 読後感が良かった。というのも、この本はタイトルに惹かれて買ったのだ。疲れているが読書はしたい。内容理解に努める必要のない本が欲しい。そんな時に見つけたこのタイトルはまさに癒しであった。なんて難しく無さそうなタイトルなのだろう。その期待通り、疲れることなく読了できた。何故なら、著者も「いい感じの石ころは何かと聞かれると説明できないが、無理に説明しなくても良いとする」「今までいい感じと思っていなかった石がいい感じに見える。いい感じの基準がころころ変わるが、それで良いのである」というスタンスなのだ。エッセイの中に何度も著者の石ころに対する意識か出てくる。その度に「石ころを見るのに堅苦しい知識や思考は不要である」旨の文章が出てくるので、読者としても安心である。いい意味で何も考えなくて良いし、果たしてこの石ころのどこがいいのだろうか?と考えてもいい。読書は自由なものであると感じることができる本であった。 フルカラーでいい感じの石ころの写真が多数掲載されている。この本におけるいい感じの石ころとは、大きさや触った感触も含めて判断されるので、写真では「いい感じ」の全容を浴びることは叶わない。が、普段見向きしない石ころも、スポットを選べばバリエーションに富む面白いものだということはわかる。自分も日本海側の海岸に行く機会があれば、ひとつ探してみようかと思う感動があった。 緩い読書に最適な一冊である。 - 2025年10月18日
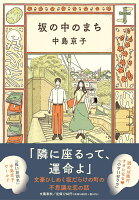 坂の中のまち中島京子借りてきた読み終わった図書館に行く夫に「何か読みたいから借りてきて欲しい」と依頼したところ、借りてきた一冊。 不思議な読後感だった。物語は、大学進学のため主人公が上京し、下宿先の女主人に挨拶するところから始まる。この女主人が非常に個性的な人物であり、私は「なるほど、主人公の大学生活に関わってくる人物なのだな」と思った。大学生活を通して変化していく主人公の話にのかと予想していた。 しかし、私の予想に反して主人公の大学生活の描写は全編を通してみるとそこまで深くはなかったと思う。本書は六話構成だが、例えば一話で出てきた大学で出会う友人は、二話以降では登場回数が減ってしまう。同様に、固有名で出てきた人物がその後出番なし、ということもちょくちょくあった。 この本は、六話分の読み切り短編集のような印象だった。もちろん主人公に変化がないわけではない。六話を通して恋をしたり、バイトをしたり、帰省をしたり、その度に色々な人に出会い、色々なことを考える。 その中で、下宿先の女主人が関係してくるのである。主人公自身も、彼女がいないところで彼女の愛読書達を思い出すなど影響を受けていく。一話一話は大学生活の中で起こる出来事を切り取り、そこに女主人も絡んでいく。 しかし、女主人の存在によって、六話を通して主人公に劇的な変化が起こるかというと、そうではないように思った。 主人公には恋人ができるのだが、その進展やすれ違いという過程も本書のメインでは内容に思った。 本書は、タイトルの通り東京の坂がメインなのだ。坂を取り巻く物語は日本に沢山ある。主人公を通して「坂」を描く作品なのだ、と思った。 読了後、淡々とした本だった、という感想だった。エピローグも登場人物達はどうなった、という一文が並ぶようなあっさりしたものだと思う。 坂はただそこにある。たまたまそこの坂に文豪が住んだり、たまたまそこの坂を舞台に物語が生まれた。そうしたことを表現しているような気がする本であった。
坂の中のまち中島京子借りてきた読み終わった図書館に行く夫に「何か読みたいから借りてきて欲しい」と依頼したところ、借りてきた一冊。 不思議な読後感だった。物語は、大学進学のため主人公が上京し、下宿先の女主人に挨拶するところから始まる。この女主人が非常に個性的な人物であり、私は「なるほど、主人公の大学生活に関わってくる人物なのだな」と思った。大学生活を通して変化していく主人公の話にのかと予想していた。 しかし、私の予想に反して主人公の大学生活の描写は全編を通してみるとそこまで深くはなかったと思う。本書は六話構成だが、例えば一話で出てきた大学で出会う友人は、二話以降では登場回数が減ってしまう。同様に、固有名で出てきた人物がその後出番なし、ということもちょくちょくあった。 この本は、六話分の読み切り短編集のような印象だった。もちろん主人公に変化がないわけではない。六話を通して恋をしたり、バイトをしたり、帰省をしたり、その度に色々な人に出会い、色々なことを考える。 その中で、下宿先の女主人が関係してくるのである。主人公自身も、彼女がいないところで彼女の愛読書達を思い出すなど影響を受けていく。一話一話は大学生活の中で起こる出来事を切り取り、そこに女主人も絡んでいく。 しかし、女主人の存在によって、六話を通して主人公に劇的な変化が起こるかというと、そうではないように思った。 主人公には恋人ができるのだが、その進展やすれ違いという過程も本書のメインでは内容に思った。 本書は、タイトルの通り東京の坂がメインなのだ。坂を取り巻く物語は日本に沢山ある。主人公を通して「坂」を描く作品なのだ、と思った。 読了後、淡々とした本だった、という感想だった。エピローグも登場人物達はどうなった、という一文が並ぶようなあっさりしたものだと思う。 坂はただそこにある。たまたまそこの坂に文豪が住んだり、たまたまそこの坂を舞台に物語が生まれた。そうしたことを表現しているような気がする本であった。 - 2025年10月16日
 残るは食欲阿川佐和子読書日記読み終わった買ったエッセイは読みやすいが、特に「食べ物」にスポットを当てたこの本は読みやすかった。 誰もが食事をする。故にテーマとして身近なのだが、私と筆者の食生活が違いすぎて、そこが面白かった。 私は子供がいる共働きであるため、食事は家なら20分以内で作れるか、外食ならファミレスとかっちり決まっている。 丁寧なお菓子作りはそもそもやる気が湧いてこない。せいぜい、ホットケーキミックスで作るバナナケーキで、混ぜてホットクックに入れてスイッチピ、である。 対して筆者は一人暮らし、でも私より年上で精神的に余裕のある大人である。お酒を楽しみ、フードプロセッサーで調理し、自分好みの食材に挑戦する筆者の食生活は、お酒は翌日を思うと控え、洗い物が手間そうな器具を使い、家族が食べないものはそもそも買わない私からすると、一言で言えば「優雅」だ。しかし一方で、筆者は時には一人分の胃袋には持て余す量の食材に悩んだりしている。私ならば、お裾分けせずとも一家で食べきることができるだろうな、などと思った。 このように、自分と違う生活をしている人の食卓を眺めるというのは面白いものだった。 いつか生活が落ち着いたら、お酒とおつまみを吟味して夜ゆっくり一杯、という時間を作りたいものである。 ところで、私はこの本で「お目もじ叶う」という表現を初めて知った。「人に会う」ことを意味するが、「女性が使うイメージ」「会う人は目上の立場」であるニュアンスを含むらしい。ということは、小説などで出てきたら、話者は女性であり、女性にとって目上の人に会うんだな、ということが読み取れるということだろう。 エッセイから思わぬ教養を得られた。読書とはやはり意外な出会いをもたらしてくれるものである。
残るは食欲阿川佐和子読書日記読み終わった買ったエッセイは読みやすいが、特に「食べ物」にスポットを当てたこの本は読みやすかった。 誰もが食事をする。故にテーマとして身近なのだが、私と筆者の食生活が違いすぎて、そこが面白かった。 私は子供がいる共働きであるため、食事は家なら20分以内で作れるか、外食ならファミレスとかっちり決まっている。 丁寧なお菓子作りはそもそもやる気が湧いてこない。せいぜい、ホットケーキミックスで作るバナナケーキで、混ぜてホットクックに入れてスイッチピ、である。 対して筆者は一人暮らし、でも私より年上で精神的に余裕のある大人である。お酒を楽しみ、フードプロセッサーで調理し、自分好みの食材に挑戦する筆者の食生活は、お酒は翌日を思うと控え、洗い物が手間そうな器具を使い、家族が食べないものはそもそも買わない私からすると、一言で言えば「優雅」だ。しかし一方で、筆者は時には一人分の胃袋には持て余す量の食材に悩んだりしている。私ならば、お裾分けせずとも一家で食べきることができるだろうな、などと思った。 このように、自分と違う生活をしている人の食卓を眺めるというのは面白いものだった。 いつか生活が落ち着いたら、お酒とおつまみを吟味して夜ゆっくり一杯、という時間を作りたいものである。 ところで、私はこの本で「お目もじ叶う」という表現を初めて知った。「人に会う」ことを意味するが、「女性が使うイメージ」「会う人は目上の立場」であるニュアンスを含むらしい。ということは、小説などで出てきたら、話者は女性であり、女性にとって目上の人に会うんだな、ということが読み取れるということだろう。 エッセイから思わぬ教養を得られた。読書とはやはり意外な出会いをもたらしてくれるものである。 - 2025年10月15日
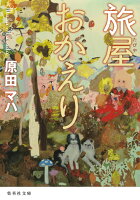 旅屋おかえり原田マハ読書日記読み終わったこの本の出会いには2つのきっかけがある。 1つは本屋。本選びの相談に乗ります、的なポップが置いてあるような地域の個人書店で購入。確か一応、店主と会話した末にこの本を選んだのだが、あまり会話は弾まず、慣れないことはするもんじゃないな、という記憶がある。 2つ目はこの本の作者である。 作者:原田マハ氏の父もまた作家で、私の実家にその父親の本がいくつかあり、読んだことがある。エッセイが面白く声を出して笑いながら読んでいたし、娘のこと(=マハ氏)もエッセイにあったと記憶している。 この本とは、出会いからして旅の途中にばったりと出会ったような、不思議な縁を感じたのだった。 こうして購入に至ったが年単位で前のこと。もはや何年前かも覚えていないが、買ったからには読まねば、と積んでいた本をようやく崩せた。 主人公崖っぷちからの逆転、波に乗る中の試練、試練には身内が関わっていて、主人公は味方を失う…からのラスト。展開自体は王道だと思う。 王道だからこそ、舞台や設定、テーマが好きなものだったので楽しく読むことができた。 特に一度解散したチームメンバー一同と再会する場面。漫画であれば別れた仲間と再会してラスボスを倒しに行くかのような熱さがあった。 また、主人公の会社の社長と社員が、それまで絶対的な味方として動いていた後の「らしくない」振る舞いや冷淡さの落差。丁寧に味方としての描写が濃かったからこそ印象的だった。 自分は旅行になかなか行かないタイプだが、それは計画を立てるのと、お金がかかると考えてしまうのと、体力がないからである。 無計画に外出して、ただ鈍行列車に揺られるような旅なら好きだ、と思う。 根本的にインドアなのと、生活の事情により旅立ってみたことはないのだが、少なくともやってみたいと前向きに感じる。 この本を読むことで、家にいながら旅の楽しさを味わうことができた。主人公にはあるミッションがあるので気ままな旅とは行かないが、かといって気を張ってクタクタ、バテバテではなく心から旅を楽しんでいる瞬間が確実にある。良い意味の緊張と非日常ならではの安らぎが良い塩梅の読後感だと思った。 ところで続編はないのだろうか。いかにもありそうだと思うのだが、自分は様々な読書体験をしたいので、シリーズがあったとしても一旦離れるつもりである。 出不精な自分には、読書が旅そのものなので、また別の場所に今は行ってみたい気分なのだ。
旅屋おかえり原田マハ読書日記読み終わったこの本の出会いには2つのきっかけがある。 1つは本屋。本選びの相談に乗ります、的なポップが置いてあるような地域の個人書店で購入。確か一応、店主と会話した末にこの本を選んだのだが、あまり会話は弾まず、慣れないことはするもんじゃないな、という記憶がある。 2つ目はこの本の作者である。 作者:原田マハ氏の父もまた作家で、私の実家にその父親の本がいくつかあり、読んだことがある。エッセイが面白く声を出して笑いながら読んでいたし、娘のこと(=マハ氏)もエッセイにあったと記憶している。 この本とは、出会いからして旅の途中にばったりと出会ったような、不思議な縁を感じたのだった。 こうして購入に至ったが年単位で前のこと。もはや何年前かも覚えていないが、買ったからには読まねば、と積んでいた本をようやく崩せた。 主人公崖っぷちからの逆転、波に乗る中の試練、試練には身内が関わっていて、主人公は味方を失う…からのラスト。展開自体は王道だと思う。 王道だからこそ、舞台や設定、テーマが好きなものだったので楽しく読むことができた。 特に一度解散したチームメンバー一同と再会する場面。漫画であれば別れた仲間と再会してラスボスを倒しに行くかのような熱さがあった。 また、主人公の会社の社長と社員が、それまで絶対的な味方として動いていた後の「らしくない」振る舞いや冷淡さの落差。丁寧に味方としての描写が濃かったからこそ印象的だった。 自分は旅行になかなか行かないタイプだが、それは計画を立てるのと、お金がかかると考えてしまうのと、体力がないからである。 無計画に外出して、ただ鈍行列車に揺られるような旅なら好きだ、と思う。 根本的にインドアなのと、生活の事情により旅立ってみたことはないのだが、少なくともやってみたいと前向きに感じる。 この本を読むことで、家にいながら旅の楽しさを味わうことができた。主人公にはあるミッションがあるので気ままな旅とは行かないが、かといって気を張ってクタクタ、バテバテではなく心から旅を楽しんでいる瞬間が確実にある。良い意味の緊張と非日常ならではの安らぎが良い塩梅の読後感だと思った。 ところで続編はないのだろうか。いかにもありそうだと思うのだが、自分は様々な読書体験をしたいので、シリーズがあったとしても一旦離れるつもりである。 出不精な自分には、読書が旅そのものなので、また別の場所に今は行ってみたい気分なのだ。 - 2025年9月15日
 休むヒント。群像編集部読書日記読み終わった「休む」をテーマにしたエッセイ集。最初の麻布競馬場さんのエッセイで笑ってしまった。この前読んだ「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の答えそのもの、全力コミットしている方だったからである。(何かに全力コミット=余暇がないので本が読めない) 「なぜ働いて〜」の本も全力コミットを否定してはいない。何かに全てを注ぐ時期はあるだろう、しかし全力コミットが人生全てになるのは違う、という話だった。 麻布競馬場さんは、全力コミットの時期にいる方なのだろう。プロフィールを見ると、まだ30代。若い。むしろ、若いうちに全力コミットしたいと思えるものに出会えて羨ましい人だ、とさえ思う。 初手から休むことが苦手、というエッセイから始まるけれど、読破して思うのは、若い人は「休み方がわからない」で、50代より上あたりになると「これが私の休み方だ」と自分の休むヒントどころか休み方の回答を持ってる人が多い、という傾向があるように思う。 エッセイの作者は業界も年代も様々で、それだけでも読んでいて楽しい。私は声優の斉藤壮馬さんの名前があったから購入したのだが、作家業以外の方だとぼる塾の酒寄さんというお笑いの方などもいて、幅広い。 旅行なり近所の散歩なり、場所を変えることを休みとする人は多い。知らない土地へ行くことにあまり興味がない、海外なんてむしろ疲れないか?という私だが、他の人の旅行の話を読むのは楽しい。作者は楽しくて旅行に行くのだから、文章からもその喜びが伝わってくるから、自分の好みに関わらず、「休む」エッセイを読むのは面白かった。 さて、休むヒントを得られたのか、というと「休みだと思えば休みだ」という感想なので、一応ヒントを得られたと言えるだろう。 この本を読むと、休みとは人それぞれ。休み方をまだ知らない、わからない人もいる。自分の休みは自分で自信を持てればそれが休みで良いのである。住めば都、と同じなのではないか。 まだ自分で「これが休みだ」と自信を持って言える「休み」はないと思うが、読んでなんとなく気が楽になった一冊である。
休むヒント。群像編集部読書日記読み終わった「休む」をテーマにしたエッセイ集。最初の麻布競馬場さんのエッセイで笑ってしまった。この前読んだ「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の答えそのもの、全力コミットしている方だったからである。(何かに全力コミット=余暇がないので本が読めない) 「なぜ働いて〜」の本も全力コミットを否定してはいない。何かに全てを注ぐ時期はあるだろう、しかし全力コミットが人生全てになるのは違う、という話だった。 麻布競馬場さんは、全力コミットの時期にいる方なのだろう。プロフィールを見ると、まだ30代。若い。むしろ、若いうちに全力コミットしたいと思えるものに出会えて羨ましい人だ、とさえ思う。 初手から休むことが苦手、というエッセイから始まるけれど、読破して思うのは、若い人は「休み方がわからない」で、50代より上あたりになると「これが私の休み方だ」と自分の休むヒントどころか休み方の回答を持ってる人が多い、という傾向があるように思う。 エッセイの作者は業界も年代も様々で、それだけでも読んでいて楽しい。私は声優の斉藤壮馬さんの名前があったから購入したのだが、作家業以外の方だとぼる塾の酒寄さんというお笑いの方などもいて、幅広い。 旅行なり近所の散歩なり、場所を変えることを休みとする人は多い。知らない土地へ行くことにあまり興味がない、海外なんてむしろ疲れないか?という私だが、他の人の旅行の話を読むのは楽しい。作者は楽しくて旅行に行くのだから、文章からもその喜びが伝わってくるから、自分の好みに関わらず、「休む」エッセイを読むのは面白かった。 さて、休むヒントを得られたのか、というと「休みだと思えば休みだ」という感想なので、一応ヒントを得られたと言えるだろう。 この本を読むと、休みとは人それぞれ。休み方をまだ知らない、わからない人もいる。自分の休みは自分で自信を持てればそれが休みで良いのである。住めば都、と同じなのではないか。 まだ自分で「これが休みだ」と自信を持って言える「休み」はないと思うが、読んでなんとなく気が楽になった一冊である。 - 2025年9月2日
 ふつうな私のゆるゆる作家生活益田ミリ読書日記読み終わった4コマのコマ割りで進むエッセイ。ゆるい読書をしたくて買ったのだけど、ちょうど良かった。 色々な編集者。そうだよね、そんな仕草をする編集者は嫌だよなあという共感。そして、そんなことを言う編集者は…あれ?益田さんは引っかからないんだ。作者の体験を通して、自分の考え、感じ方が整理されたり。 益田さんは何でもやってみる精神が旺盛で、すごいなと思った。私は新しいことをやることは好きだけど、結局元のところで安心するのが好きなのだ。 いや、元のところで戻ったとしても、前と同じ私ではないのだ。益田さんだって苦手なことをやろうとしてやめて、そこから得られたことをエッセイにしているのである。 ところでこれ、10年前の本なんですよ。 このエッセイから10年経ってから読んでも楽しい。エッセイって生活の中で何を感じたのかという話だから、いつ読んでもいいのかもしれない。 いや、例えば旅行記の類のエッセイは遠い国の話すぎて共感というか「へ、へー?」のような実感のない話として私は読むのかもしれない。 漫画なので、サクッと読めるエッセイ本。感想文を書いたら思いのほか長くなってしまった。
ふつうな私のゆるゆる作家生活益田ミリ読書日記読み終わった4コマのコマ割りで進むエッセイ。ゆるい読書をしたくて買ったのだけど、ちょうど良かった。 色々な編集者。そうだよね、そんな仕草をする編集者は嫌だよなあという共感。そして、そんなことを言う編集者は…あれ?益田さんは引っかからないんだ。作者の体験を通して、自分の考え、感じ方が整理されたり。 益田さんは何でもやってみる精神が旺盛で、すごいなと思った。私は新しいことをやることは好きだけど、結局元のところで安心するのが好きなのだ。 いや、元のところで戻ったとしても、前と同じ私ではないのだ。益田さんだって苦手なことをやろうとしてやめて、そこから得られたことをエッセイにしているのである。 ところでこれ、10年前の本なんですよ。 このエッセイから10年経ってから読んでも楽しい。エッセイって生活の中で何を感じたのかという話だから、いつ読んでもいいのかもしれない。 いや、例えば旅行記の類のエッセイは遠い国の話すぎて共感というか「へ、へー?」のような実感のない話として私は読むのかもしれない。 漫画なので、サクッと読めるエッセイ本。感想文を書いたら思いのほか長くなってしまった。 - 2025年8月30日
 読書日記読み終わった買ったタイトルから期待する結論として「〇〇だから本が読めないのだ、だから△△しよう」というものなのだが、私の予想していた結論とは違ったので、新しい視点をもらったな、と思った。 結論だけ読めば「そりゃそうだよ」で終わりそうなのだが、結論に至るまでに日本人と読書の歴史を丁寧に紹介・分析してくれるので、結論がスッと頭に入ってきたのが気持ちよかった。 私の予想した結論は「頑張って時間を作ろう。そのために…」という類のもので、要は読書のやる気が足りないのだ、のような精神論が少なからず入るものであった。 だが、この本の結論はそのような根性で解決しろというものではなかった。結論は「〇〇を心がけよう」という語りかけなのだが、それは決して押し付けではないところがホッとした。そして、〇〇を心がけることで、読書のみならず、他のあらゆる「何々ができない時間」を解決することに近づくのだと思うと、救われる気持ちになる。 これは、Xなどの文章型SNSのリプに繋げた連投で読むのとは全く違う満足感だと思った。 SNSにも良い意見はある。だが、リプの連投だとどうしても一過性のものであるという感覚があり、私は「へー」「そうだよなあ」とやはり一過性の感想で終わってしまうのだ。 この本も結論だけポストの連投で読んでいたら、心に残らなかっただろう。 最初に書いたように、読書の歴史を紹介・分析を追って結論を読むことができたので、読書ならではの体験ができたと思う。
読書日記読み終わった買ったタイトルから期待する結論として「〇〇だから本が読めないのだ、だから△△しよう」というものなのだが、私の予想していた結論とは違ったので、新しい視点をもらったな、と思った。 結論だけ読めば「そりゃそうだよ」で終わりそうなのだが、結論に至るまでに日本人と読書の歴史を丁寧に紹介・分析してくれるので、結論がスッと頭に入ってきたのが気持ちよかった。 私の予想した結論は「頑張って時間を作ろう。そのために…」という類のもので、要は読書のやる気が足りないのだ、のような精神論が少なからず入るものであった。 だが、この本の結論はそのような根性で解決しろというものではなかった。結論は「〇〇を心がけよう」という語りかけなのだが、それは決して押し付けではないところがホッとした。そして、〇〇を心がけることで、読書のみならず、他のあらゆる「何々ができない時間」を解決することに近づくのだと思うと、救われる気持ちになる。 これは、Xなどの文章型SNSのリプに繋げた連投で読むのとは全く違う満足感だと思った。 SNSにも良い意見はある。だが、リプの連投だとどうしても一過性のものであるという感覚があり、私は「へー」「そうだよなあ」とやはり一過性の感想で終わってしまうのだ。 この本も結論だけポストの連投で読んでいたら、心に残らなかっただろう。 最初に書いたように、読書の歴史を紹介・分析を追って結論を読むことができたので、読書ならではの体験ができたと思う。
読み込み中...
