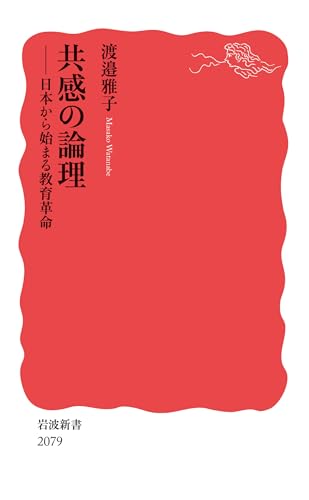ゆけまる
@yukemar_14
あまり長くない読書歴¦怖いの以外色々読みます¦スピノザ哲学¦ファンタジー¦脳科学¦進化生物学¦古典にも手を出したい¦楽しいだけの読書にしたい¦なぜ子育てをしていると本が読めなくなるのか¦18 Aug 2025~
- 2026年2月23日
 宇宙の広さを知ったサルスティーブ・スチュワート=ウィリアムズ,加藤智子借りてきたまた読みたいめーっちゃくちゃ面白い。完全に視点本。 というか視点もそうだけど、語りが抜群にうまい。男女の性差についての進化生物学上の説明、たぶん今まで読んだ関連本のなかで1番面白い。明日返却期限で読み切れなかった…から、たぶん買う。
宇宙の広さを知ったサルスティーブ・スチュワート=ウィリアムズ,加藤智子借りてきたまた読みたいめーっちゃくちゃ面白い。完全に視点本。 というか視点もそうだけど、語りが抜群にうまい。男女の性差についての進化生物学上の説明、たぶん今まで読んだ関連本のなかで1番面白い。明日返却期限で読み切れなかった…から、たぶん買う。 - 2026年2月20日
 レ・ミゼラブル 1ヴィクトル・ユーゴー,ユーゴー,V.(ヴィクトル),豊島与志雄読み終わった圧倒的筆力!物語のすじに関わるパートの引き込み方がすっごい。ぶあつい。今どきこんなに紙幅割けないよ。 前評判通り、話のすじに全然関係ないところもめっちゃ語るなぁとは思う。しかも、結構わからん感じで。 だから、こだわりがなければダイジェスト版でも十分な気はする。私は「原作読んだんだぜドヤ」って思いたいから全部読む。
レ・ミゼラブル 1ヴィクトル・ユーゴー,ユーゴー,V.(ヴィクトル),豊島与志雄読み終わった圧倒的筆力!物語のすじに関わるパートの引き込み方がすっごい。ぶあつい。今どきこんなに紙幅割けないよ。 前評判通り、話のすじに全然関係ないところもめっちゃ語るなぁとは思う。しかも、結構わからん感じで。 だから、こだわりがなければダイジェスト版でも十分な気はする。私は「原作読んだんだぜドヤ」って思いたいから全部読む。 - 2026年1月22日
 ギャツビー100年杉野健太郎気になる
ギャツビー100年杉野健太郎気になる - 2026年1月21日
 あなたはなぜ雑談が苦手なのか桜林直子気になる
あなたはなぜ雑談が苦手なのか桜林直子気になる - 2026年1月19日
 神学・政治論(下)バルーフ・ド・スピノザ,吉田量彦読み終わった上巻の読了時にも書いたけど、とにかく読みやすい訳で驚いた。普通に読める哲学書。多分、読みやすさでは方法序説を超えたと思う。 やっぱり、これは禁書なんだと思う、笑 ホッブズが「自分はこれほどの大胆さをもってものを書くことはできない」って言ったとされてる通り、普通に異端審問とかがあった時代にこんな尖ったことを書いたのほんと気骨あると思う。 「尖っている」とは言ったけど、これもあくまで当時の背景に照らしての意味合いでしかなくて、言ってること自体はすごく筋が通っているというか、納得感はすごくあった。エチカもそうだけど、振れ幅の大きさというか、熱さと冷静さを併せ持つ感じというか、一見相反するような性質を併せ持つギャップが改めて私がスピノザさんたまらんなぁって思うポイントなのかもしれないと思った。スピノザさんたまらんよ…!
神学・政治論(下)バルーフ・ド・スピノザ,吉田量彦読み終わった上巻の読了時にも書いたけど、とにかく読みやすい訳で驚いた。普通に読める哲学書。多分、読みやすさでは方法序説を超えたと思う。 やっぱり、これは禁書なんだと思う、笑 ホッブズが「自分はこれほどの大胆さをもってものを書くことはできない」って言ったとされてる通り、普通に異端審問とかがあった時代にこんな尖ったことを書いたのほんと気骨あると思う。 「尖っている」とは言ったけど、これもあくまで当時の背景に照らしての意味合いでしかなくて、言ってること自体はすごく筋が通っているというか、納得感はすごくあった。エチカもそうだけど、振れ幅の大きさというか、熱さと冷静さを併せ持つ感じというか、一見相反するような性質を併せ持つギャップが改めて私がスピノザさんたまらんなぁって思うポイントなのかもしれないと思った。スピノザさんたまらんよ…! - 2026年1月12日
 神学・政治論(上)スピノザ,バルーフ・ド・スピノザ,吉田量彦読み終わった納得の禁書 キリスト教信者でなくても、これはまぁ怒られるよねって話 それ言ったらまた怒られるよー?笑、ってニヤニヤしながら読み進めるけど、ちゃんと随所にスピノザさんらしいロジックの立て方が出てきて、エチカの理解の助けにもなるような気がした これを宗教権力が今とは比べ物にならないくらい強かった時代に、これを出版しなければ!ってなったスピノザさんほんと気骨ある あとたぶん、訳が抜群に読みやすい 普通に読める哲学書 文中の訳者補足も読みやすさにすっごく効いてて、ありがたい限り…!
神学・政治論(上)スピノザ,バルーフ・ド・スピノザ,吉田量彦読み終わった納得の禁書 キリスト教信者でなくても、これはまぁ怒られるよねって話 それ言ったらまた怒られるよー?笑、ってニヤニヤしながら読み進めるけど、ちゃんと随所にスピノザさんらしいロジックの立て方が出てきて、エチカの理解の助けにもなるような気がした これを宗教権力が今とは比べ物にならないくらい強かった時代に、これを出版しなければ!ってなったスピノザさんほんと気骨ある あとたぶん、訳が抜群に読みやすい 普通に読める哲学書 文中の訳者補足も読みやすさにすっごく効いてて、ありがたい限り…! - 2026年1月10日
 火星の人アンディ・ウィアー気になる
火星の人アンディ・ウィアー気になる - 2025年12月30日
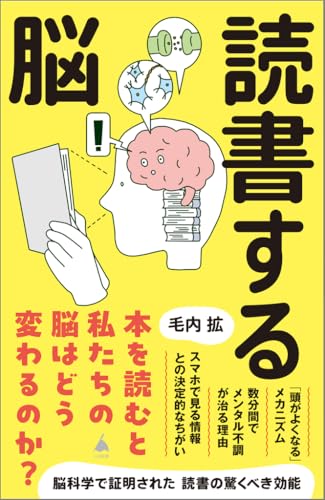 読書する脳毛内拡気になる
読書する脳毛内拡気になる - 2025年12月30日
 改訂版 プレミアムカラー国語便覧二宮美那子,本廣陽子,足立直子気になる
改訂版 プレミアムカラー国語便覧二宮美那子,本廣陽子,足立直子気になる - 2025年12月30日
 猫に学ぶジョン・グレイ,鈴木晶気になる
猫に学ぶジョン・グレイ,鈴木晶気になる - 2025年12月28日
 永遠猫の祝福清水晴木読み終わっためっっっちゃくちゃよかった。 微塵もネタバレしたくないから、あんまり書けないという… 途中までは割と普通の話かなぁとか、ちょっと横柄で人間の言葉を喋る動物モノ私好きだなぁとか思ってたけど…すごいや。ほんとに美しい。
永遠猫の祝福清水晴木読み終わっためっっっちゃくちゃよかった。 微塵もネタバレしたくないから、あんまり書けないという… 途中までは割と普通の話かなぁとか、ちょっと横柄で人間の言葉を喋る動物モノ私好きだなぁとか思ってたけど…すごいや。ほんとに美しい。 - 2025年12月24日
 世界の辺境とハードボイルド室町時代(集英社インターナショナル)清水克行,高野秀行気になる
世界の辺境とハードボイルド室町時代(集英社インターナショナル)清水克行,高野秀行気になる - 2025年12月23日
 「偶然」はどのようにあなたをつくるのかブライアン・クラース,柴田裕之読み終わった面白かった!読んでよかった。読みやすかった。最後の2章の畳み掛け方がすごい! 普段信じている世界は偶然性というノイズの除去された「童話版の現実」でしかなくて、本当の現実世界は必ずしもX→Yの明確な因果関係が支配しているわけではなくて、むしろごく僅かな偶然によって大きく変化し続ける世界。だから予測も測定も限界がある、というか限界しかない。でもだからこそ世界って面白いのかもしれない。それらをありとあらゆる分野の面白エピソード盛り盛りにして「ほいっ」と手渡してくれる本。自由意志の話とか効率化・コントロール至上主義ってどうなの?って話も混ざって、もうほんと最高。好き。
「偶然」はどのようにあなたをつくるのかブライアン・クラース,柴田裕之読み終わった面白かった!読んでよかった。読みやすかった。最後の2章の畳み掛け方がすごい! 普段信じている世界は偶然性というノイズの除去された「童話版の現実」でしかなくて、本当の現実世界は必ずしもX→Yの明確な因果関係が支配しているわけではなくて、むしろごく僅かな偶然によって大きく変化し続ける世界。だから予測も測定も限界がある、というか限界しかない。でもだからこそ世界って面白いのかもしれない。それらをありとあらゆる分野の面白エピソード盛り盛りにして「ほいっ」と手渡してくれる本。自由意志の話とか効率化・コントロール至上主義ってどうなの?って話も混ざって、もうほんと最高。好き。 - 2025年12月16日
 朝イチの「ひとり時間」が人生を変えるキム・ユジン,小笠原藤子じゅうぶん読んだ元々夜より朝派だったけど、それをばっちり言語化してくれて「そうそう!」って共感しながら読んだ。 朝派といえど早起きはツラいからね…同志みたいで嬉しかった。
朝イチの「ひとり時間」が人生を変えるキム・ユジン,小笠原藤子じゅうぶん読んだ元々夜より朝派だったけど、それをばっちり言語化してくれて「そうそう!」って共感しながら読んだ。 朝派といえど早起きはツラいからね…同志みたいで嬉しかった。 - 2025年12月13日
- 2025年12月12日
 自由は進化するダニエル・C・デネット気になる
自由は進化するダニエル・C・デネット気になる - 2025年12月12日
 ジーン・マシンヴェンカトラマン・ラマクリシュナン,大田直子,田口英樹気になる
ジーン・マシンヴェンカトラマン・ラマクリシュナン,大田直子,田口英樹気になる - 2025年12月12日
 「偶然」はどのようにあなたをつくるのかブライアン・クラース,柴田裕之気になる
「偶然」はどのようにあなたをつくるのかブライアン・クラース,柴田裕之気になる - 2025年11月28日
 カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学デイヴィッド・サダヴァ,中村千春,小松佳代子,石崎泰樹読み終わったぜんぶわかったわけじゃないけど、一応通読。 これほどまでに精巧な仕組みが生物、なんなら原核生物とかのレベルでも備わってるのほんと不思議。
カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学デイヴィッド・サダヴァ,中村千春,小松佳代子,石崎泰樹読み終わったぜんぶわかったわけじゃないけど、一応通読。 これほどまでに精巧な仕組みが生物、なんなら原核生物とかのレベルでも備わってるのほんと不思議。 - 2025年11月20日
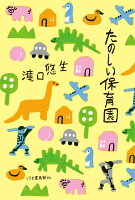 たのしい保育園滝口悠生読み終わった実体験??って思うくらい、「わかる!」「あるある!」ってなる小説だった。タイトルの通り、保育園周りの解像度がとても高い。送りの大変さとか、連絡帳のこととか、周りのお友達、その子たちのパパママとの関係性とか。それに、自分の子を大切に思う余り、子どもが傷つけられたりはたまた失うことになってしまうことを想像してしまうっていうのもすごくわかると思った。 慣れない文体で最初は戸惑ったけど、視点がポンポン変わっていくのは、なんだか実際の人間の思考の流れを追っているかのようで現実味があった。 ちょうど、ももちゃんと自分の子どもが同い年くらいのタイミングで読めたからすごく親近感、リアリティがあってよかった。これ後から読み返したら泣いちゃう気がする笑
たのしい保育園滝口悠生読み終わった実体験??って思うくらい、「わかる!」「あるある!」ってなる小説だった。タイトルの通り、保育園周りの解像度がとても高い。送りの大変さとか、連絡帳のこととか、周りのお友達、その子たちのパパママとの関係性とか。それに、自分の子を大切に思う余り、子どもが傷つけられたりはたまた失うことになってしまうことを想像してしまうっていうのもすごくわかると思った。 慣れない文体で最初は戸惑ったけど、視点がポンポン変わっていくのは、なんだか実際の人間の思考の流れを追っているかのようで現実味があった。 ちょうど、ももちゃんと自分の子どもが同い年くらいのタイミングで読めたからすごく親近感、リアリティがあってよかった。これ後から読み返したら泣いちゃう気がする笑
読み込み中...