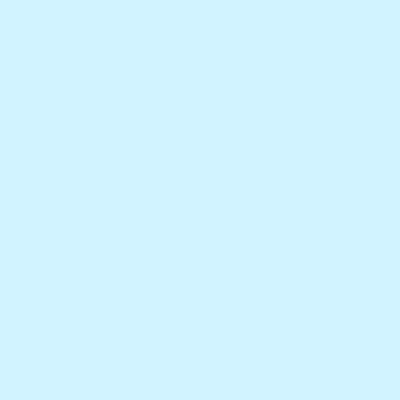責任の生成

64件の記録
 monami@kiroku_library2025年12月8日ちょっと開いた哲学に興味を持ってくれた人がいたから、安易に勧めそうになったけど、多分普段読書経験が無い人に急に与えるにはハードルが高い、気がする。 でもこれを読んで、目から100回ぐらい鱗落として欲しい。
monami@kiroku_library2025年12月8日ちょっと開いた哲学に興味を持ってくれた人がいたから、安易に勧めそうになったけど、多分普段読書経験が無い人に急に与えるにはハードルが高い、気がする。 でもこれを読んで、目から100回ぐらい鱗落として欲しい。





 ゆけまる@yukemar_142025年9月22日読み終わった借りてきた一気に読んでしまった。 自分がこれまでに読んできた複数の分野の本の内容と不意に繋がってびっくりした。読書の醍醐味って思う。 固定観念とまでは言わないけど、これまで持っていた漠然とした観念をひっくり返されるような話がいっぱいあって、でも図書館の本だから線も引けず、ページも折れず… 『中動態の世界』の話もよりよく理解できるし、スピノザ的自由についての具体例的な話があって、理解に少し近づいた気がする。 面白かった箇所全然書ききれない!とにかく面白かった。 講義録なので負荷もそれほど高くなかったのが嬉しい。ぜっったいに再読するなぁこれは。買う。
ゆけまる@yukemar_142025年9月22日読み終わった借りてきた一気に読んでしまった。 自分がこれまでに読んできた複数の分野の本の内容と不意に繋がってびっくりした。読書の醍醐味って思う。 固定観念とまでは言わないけど、これまで持っていた漠然とした観念をひっくり返されるような話がいっぱいあって、でも図書館の本だから線も引けず、ページも折れず… 『中動態の世界』の話もよりよく理解できるし、スピノザ的自由についての具体例的な話があって、理解に少し近づいた気がする。 面白かった箇所全然書ききれない!とにかく面白かった。 講義録なので負荷もそれほど高くなかったのが嬉しい。ぜっったいに再読するなぁこれは。買う。


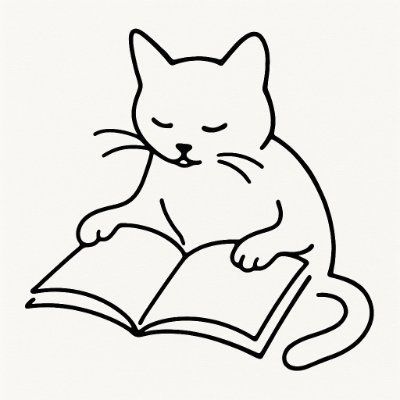
 高尾清貴@kiyotakao2025年8月14日読んでる@ 本の読める店fuzkue初台この本、面白さがすごい。 『意志が過去の切断だとしたら、覚悟というのは現在・過去・未来を自分で引き受けるということですね。』
高尾清貴@kiyotakao2025年8月14日読んでる@ 本の読める店fuzkue初台この本、面白さがすごい。 『意志が過去の切断だとしたら、覚悟というのは現在・過去・未来を自分で引き受けるということですね。』


 高尾清貴@kiyotakao2025年8月14日読み終わった@ 本の読める店fuzkue初台fuzkueで読んだこの本に、めちゃfuzkueの良さを表すフレーズ出てきた。 『アレントによれば、孤独とは思考のための条件です。私と私自身との対話、それこそが思考である。』
高尾清貴@kiyotakao2025年8月14日読み終わった@ 本の読める店fuzkue初台fuzkueで読んだこの本に、めちゃfuzkueの良さを表すフレーズ出てきた。 『アレントによれば、孤独とは思考のための条件です。私と私自身との対話、それこそが思考である。』


 橋本吉央@yoshichiha2025年6月10日読み終わった非常におもしろかった。多くの人に読んでほしい気持ち。 自分が今この瞬間にゼロから意志やモチベーションを作り出し、何かを成し遂げるというような、近代的個人の意志と自己責任論をベースにした世界の捉え方に疑問を呈すという意味で、『弱さ考』とも通ずるところがあったように思う。 社会の秩序から見て問題行為とみなされることを起こした人に対して、その人の責任を追求するということはよくあるが、実際には、その人がその行為に至った経緯には、中動態的に様々なファクターがあり、そしてそれは本人にも十分に意識されていないことが多い。そういうことを無視して、本人のその時の「意志」というものだけにフォーカスするのでは、本当の「責任」につながらないのではないか、という話は、非常に納得感がある。 個人的には、自分の身の回りでどのようにその考え方を活かせるだろうか、ということに思いを馳せている。特に、仕事をする組織の中で、なかなか思うようにパフォーマンスを出せなかったり、あるいは問題を起こしてしまうことが多かったりする人がいたような時に、当事者研究的に環境をみんなで見てみる、というアプローチができたら、変わるものは多いのではないかと感じた。本書でも言及されている通り、かなり、コストがかかるアプローチではあるので、簡単ではないけれど、そういうものの見方がある、ということだけでも頭に入れたい。
橋本吉央@yoshichiha2025年6月10日読み終わった非常におもしろかった。多くの人に読んでほしい気持ち。 自分が今この瞬間にゼロから意志やモチベーションを作り出し、何かを成し遂げるというような、近代的個人の意志と自己責任論をベースにした世界の捉え方に疑問を呈すという意味で、『弱さ考』とも通ずるところがあったように思う。 社会の秩序から見て問題行為とみなされることを起こした人に対して、その人の責任を追求するということはよくあるが、実際には、その人がその行為に至った経緯には、中動態的に様々なファクターがあり、そしてそれは本人にも十分に意識されていないことが多い。そういうことを無視して、本人のその時の「意志」というものだけにフォーカスするのでは、本当の「責任」につながらないのではないか、という話は、非常に納得感がある。 個人的には、自分の身の回りでどのようにその考え方を活かせるだろうか、ということに思いを馳せている。特に、仕事をする組織の中で、なかなか思うようにパフォーマンスを出せなかったり、あるいは問題を起こしてしまうことが多かったりする人がいたような時に、当事者研究的に環境をみんなで見てみる、というアプローチができたら、変わるものは多いのではないかと感じた。本書でも言及されている通り、かなり、コストがかかるアプローチではあるので、簡単ではないけれど、そういうものの見方がある、ということだけでも頭に入れたい。






 橋本吉央@yoshichiha2025年5月31日読んでるおもろいなー "これはどういうことかと言うと、本当は「意志」があったから責任が問われているのではないのです。責任を問うべきだと思われるケースにおいて、意志の概念によって主体に行為が帰属させられているのです。" 116
橋本吉央@yoshichiha2025年5月31日読んでるおもろいなー "これはどういうことかと言うと、本当は「意志」があったから責任が問われているのではないのです。責任を問うべきだと思われるケースにおいて、意志の概念によって主体に行為が帰属させられているのです。" 116
 pamo@pamo2025年3月17日かつて読んだ心に残る一節引用:いわゆる「非行少年」に、「なぜ薬物を使ったのか?」と聞くと、「暇だったから」と答えることがあるそうです。そうすると多くの大人はどうしても「暇だから薬物をやるなんて!」「とんでもない。けしからん‼︎」と思ってしまう。でも、大人はしばしば、少年が使う言葉の意味を取り違えます。上岡さんは、「非行少年」は単に悪ぶってそう言うのではなく、「暇」という言葉で、地獄のような苦しみを表現しているのだと。そしてそこから救われようと、いわば祈りの行為として非行に走ったのだ、と言われていました。 いっぽう國分さんは、『暇と退屈の倫理学』のなかでパスカルを引きつつ、退屈は、人間の苦しみのなかでも最も苦しい苦悩だと書かれていました。「退屈」なんてたいしたことではないと思われているが、それがしのげるのであれば、じつは人間はどんなことでもやるんだと。(p.124)
pamo@pamo2025年3月17日かつて読んだ心に残る一節引用:いわゆる「非行少年」に、「なぜ薬物を使ったのか?」と聞くと、「暇だったから」と答えることがあるそうです。そうすると多くの大人はどうしても「暇だから薬物をやるなんて!」「とんでもない。けしからん‼︎」と思ってしまう。でも、大人はしばしば、少年が使う言葉の意味を取り違えます。上岡さんは、「非行少年」は単に悪ぶってそう言うのではなく、「暇」という言葉で、地獄のような苦しみを表現しているのだと。そしてそこから救われようと、いわば祈りの行為として非行に走ったのだ、と言われていました。 いっぽう國分さんは、『暇と退屈の倫理学』のなかでパスカルを引きつつ、退屈は、人間の苦しみのなかでも最も苦しい苦悩だと書かれていました。「退屈」なんてたいしたことではないと思われているが、それがしのげるのであれば、じつは人間はどんなことでもやるんだと。(p.124)
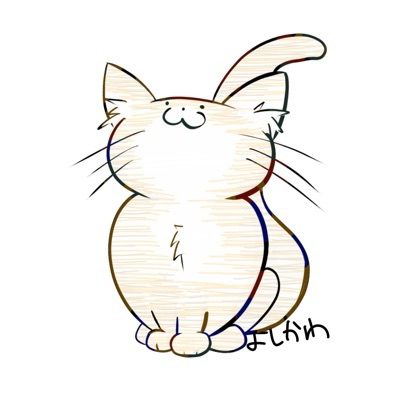
 pamo@pamo2025年3月17日かつて読んだ心に残る一節引用:古い体質の組織には、尋問の言語ですぐ個人に責任を押しつけるところがある。ところが、それとはまったく逆の「高信頼性組織研究」というのがあるのです。私はこれは自助グループにも応用できるのではないかと思っています。この「高信頼性組織」とは何か。例えば、救急医療の現場とか、航空機関連の会社とか、失敗が許されない組織のことです。彼らは本気で、組織としての失敗をゼロにするためにどうしたらいいかを探究している。その結果出てきたのが、「ジャスト・カルチャー」です。要するに、失敗を許容する、犯人探しをしない文化です。誰が悪かったのか、ということで、その人個人を罰しないという。 ただしその代わりに自分が経験したことはすべて包み隠さず話さなくてはなりません。そして、組織全体の問題として全員が受け止め、考え、応答する責任は課せられます。隠さず話すことは、失敗も含めて賞賛され、組織にとっての貴重な学習資源として受け止められる。罰すると、人は隠す。それでは、組織は失敗から学べない。だからひたすら、今日こんな失敗をしました、あんな失敗をしました、とネガティヴなことも話す、そうすると褒められる。それが「ジャスト・カルチャー」です。とても面白い逆説ですね。本気で失敗を減らしたければ、失敗を許さなければいけない。(p.413)
pamo@pamo2025年3月17日かつて読んだ心に残る一節引用:古い体質の組織には、尋問の言語ですぐ個人に責任を押しつけるところがある。ところが、それとはまったく逆の「高信頼性組織研究」というのがあるのです。私はこれは自助グループにも応用できるのではないかと思っています。この「高信頼性組織」とは何か。例えば、救急医療の現場とか、航空機関連の会社とか、失敗が許されない組織のことです。彼らは本気で、組織としての失敗をゼロにするためにどうしたらいいかを探究している。その結果出てきたのが、「ジャスト・カルチャー」です。要するに、失敗を許容する、犯人探しをしない文化です。誰が悪かったのか、ということで、その人個人を罰しないという。 ただしその代わりに自分が経験したことはすべて包み隠さず話さなくてはなりません。そして、組織全体の問題として全員が受け止め、考え、応答する責任は課せられます。隠さず話すことは、失敗も含めて賞賛され、組織にとっての貴重な学習資源として受け止められる。罰すると、人は隠す。それでは、組織は失敗から学べない。だからひたすら、今日こんな失敗をしました、あんな失敗をしました、とネガティヴなことも話す、そうすると褒められる。それが「ジャスト・カルチャー」です。とても面白い逆説ですね。本気で失敗を減らしたければ、失敗を許さなければいけない。(p.413)
 咲@mare_fecunditatis1900年1月1日読み終わった「私が全部悪かったんです。全て私の責任です。本当に、申し訳ございませんでした」 典型的な謝罪文。それは、とても閉じている。 自身の過ちを自身から切断し、他者との会話や関係修復の関わりも切断し、自己完結の形で思考停止している。 「責任を取れ」という被害側の要求はもっともだ。 その正しく強い真っ当な要求は、だがしかし、加害者を責任から遠ざける。 一度、加害行為を外在化し、自然現象のように捉える、すなわち免責すると、現象のメカニズムが次第に解明され、自分のしたことの責任を引き受けられるようになってくる。 免責による引責。 「誰もが大なり小なり傷ついた記憶を持っている。そんなわれわれ人間にとって、何もすることがなくて退屈なときが危険なのではないか。そんなときに限って、過去のトラウマ的記憶の蓋が開いてしまう。だから私たちは、その記憶を切断する、つまり記憶の蓋をもう一回閉めるために「気晴らし」をするのではないだろうか」 「過去のトラウマ的な記憶を消すためには、今ここで新たにトラウマになるような傷を自分が自分に与えるのか一番だ」 「過去を眺めることなく、未来だけを見つめて、「未来を自分の手で作るぞ」というのが意志だ。それは過去を自分から切り離そうとすることで、そうしている限り、人はものを考えることから最も遠いところにいる」 罪を償うということは、自分の過去と丁寧に向き合うことなしには成立し得ない。
咲@mare_fecunditatis1900年1月1日読み終わった「私が全部悪かったんです。全て私の責任です。本当に、申し訳ございませんでした」 典型的な謝罪文。それは、とても閉じている。 自身の過ちを自身から切断し、他者との会話や関係修復の関わりも切断し、自己完結の形で思考停止している。 「責任を取れ」という被害側の要求はもっともだ。 その正しく強い真っ当な要求は、だがしかし、加害者を責任から遠ざける。 一度、加害行為を外在化し、自然現象のように捉える、すなわち免責すると、現象のメカニズムが次第に解明され、自分のしたことの責任を引き受けられるようになってくる。 免責による引責。 「誰もが大なり小なり傷ついた記憶を持っている。そんなわれわれ人間にとって、何もすることがなくて退屈なときが危険なのではないか。そんなときに限って、過去のトラウマ的記憶の蓋が開いてしまう。だから私たちは、その記憶を切断する、つまり記憶の蓋をもう一回閉めるために「気晴らし」をするのではないだろうか」 「過去のトラウマ的な記憶を消すためには、今ここで新たにトラウマになるような傷を自分が自分に与えるのか一番だ」 「過去を眺めることなく、未来だけを見つめて、「未来を自分の手で作るぞ」というのが意志だ。それは過去を自分から切り離そうとすることで、そうしている限り、人はものを考えることから最も遠いところにいる」 罪を償うということは、自分の過去と丁寧に向き合うことなしには成立し得ない。