嫉妬論

48件の記録
 ペリー@periperiperry2025年12月31日読み終わった2025年読んだうちのベスト5に入れたい。 「嫉妬」は悪として排除されてきたが、真正面から扱ってみることで大事な視点が見えてくるのでは?というような提案だと読み取った。 いつの間にか前提になりがちな「理性」「合理性」やら、「倫理」「正義」の理論やらを考えるとき、本書のように「嫉妬」のことを考慮できているか?と問うことが、外在的な上から目線の予防策になると思った。 また、自分自身の嫉妬から目を逸らさず正面から向き合って苦しんでこそ、何か見えてくるものがあるんじゃなかろうかという、より踏み込んだ提案もあった。その点ラカンの欲望論にも通ずるなーと。 ロールズ正義論の批判的検討が特に痛快。
ペリー@periperiperry2025年12月31日読み終わった2025年読んだうちのベスト5に入れたい。 「嫉妬」は悪として排除されてきたが、真正面から扱ってみることで大事な視点が見えてくるのでは?というような提案だと読み取った。 いつの間にか前提になりがちな「理性」「合理性」やら、「倫理」「正義」の理論やらを考えるとき、本書のように「嫉妬」のことを考慮できているか?と問うことが、外在的な上から目線の予防策になると思った。 また、自分自身の嫉妬から目を逸らさず正面から向き合って苦しんでこそ、何か見えてくるものがあるんじゃなかろうかという、より踏み込んだ提案もあった。その点ラカンの欲望論にも通ずるなーと。 ロールズ正義論の批判的検討が特に痛快。



 torajiro@torajiro2025年9月5日読み終わったaudible妬み、嫉み、恨みつらみ ルサンチマン、他人の不幸は蜜の味… 私たちの社会生活において日々出会う感情だが、合理的・理性的な人間像を基本とする社会科学の主流においては自分を引き上げることよりも他人を引き下げることを望む負の感情は適切に扱うことが難しかった。 とはいえ、文学では主要なテーマの一つでもある嫉妬について、思想家たちはあれこれと論じてきた。本書ではそうした嫉妬論を概説したり、「自慢や誇示」についての思想を追って嫉妬に別の角度から輪郭を与えたりする。基本的に嫉妬は負の感情であり、良い面はほとんどないというのが、多くの思想家たちに共通しているところだが、最後に著者は負の感情であったとしても、嫉妬をなくすことはできないし、完全に無くしてしまえばいいものでもないと言う。嫉妬の源泉は対等性(自分とまったく異なるものに嫉妬はしない)と差異であり、この二つは民主主義の源泉でもあるからだ。民主主義の理念と嫉妬の情念は光と影のようなものとして付き合い方を考えていく必要がある。 社会の中に嫉妬を解消するための仕組みや機会を織り込むマクロレベルの対策も、ミクロレベルで一人一人が対処していく対策も(著者は半端に比較して嫉妬するのではなく、比較から無理に降りるのでもなく、徹底的に比較するのが良いと言う)、どちらもやり続けていくことが重要だという。はてさて。
torajiro@torajiro2025年9月5日読み終わったaudible妬み、嫉み、恨みつらみ ルサンチマン、他人の不幸は蜜の味… 私たちの社会生活において日々出会う感情だが、合理的・理性的な人間像を基本とする社会科学の主流においては自分を引き上げることよりも他人を引き下げることを望む負の感情は適切に扱うことが難しかった。 とはいえ、文学では主要なテーマの一つでもある嫉妬について、思想家たちはあれこれと論じてきた。本書ではそうした嫉妬論を概説したり、「自慢や誇示」についての思想を追って嫉妬に別の角度から輪郭を与えたりする。基本的に嫉妬は負の感情であり、良い面はほとんどないというのが、多くの思想家たちに共通しているところだが、最後に著者は負の感情であったとしても、嫉妬をなくすことはできないし、完全に無くしてしまえばいいものでもないと言う。嫉妬の源泉は対等性(自分とまったく異なるものに嫉妬はしない)と差異であり、この二つは民主主義の源泉でもあるからだ。民主主義の理念と嫉妬の情念は光と影のようなものとして付き合い方を考えていく必要がある。 社会の中に嫉妬を解消するための仕組みや機会を織り込むマクロレベルの対策も、ミクロレベルで一人一人が対処していく対策も(著者は半端に比較して嫉妬するのではなく、比較から無理に降りるのでもなく、徹底的に比較するのが良いと言う)、どちらもやり続けていくことが重要だという。はてさて。

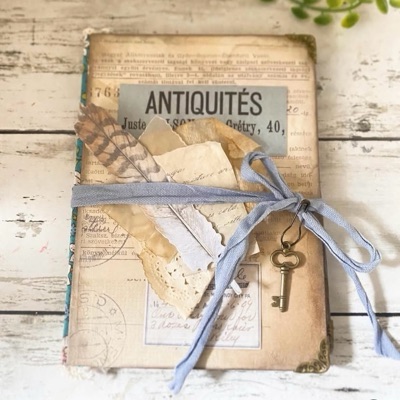
 soi@soi_i222025年8月3日読み終わった誰かに嫉妬してしまうのは自分の心が狭い、自己肯定感が低いということなのかなぁと思っていたから、まさか政治や社会生活(とりわけ民主主義)と深く関わりがあるということを知れてよかった。 「嫉妬心が完全に社会から、あるいは私たちから消え去ることはないだろう。怒りや悲しみといった人間味ある感情がそうであるように、嫉妬もまた私たち人間の条件なのだから」 嫉妬は誰もが感じることがある感情。人なら抱いてしまうものだと考えて、無理に押さえつけずに何に対してその感情を持ったのかを自分自身に問いかけながら「厄介な感情」とつきあってみよう。
soi@soi_i222025年8月3日読み終わった誰かに嫉妬してしまうのは自分の心が狭い、自己肯定感が低いということなのかなぁと思っていたから、まさか政治や社会生活(とりわけ民主主義)と深く関わりがあるということを知れてよかった。 「嫉妬心が完全に社会から、あるいは私たちから消え去ることはないだろう。怒りや悲しみといった人間味ある感情がそうであるように、嫉妬もまた私たち人間の条件なのだから」 嫉妬は誰もが感じることがある感情。人なら抱いてしまうものだと考えて、無理に押さえつけずに何に対してその感情を持ったのかを自分自身に問いかけながら「厄介な感情」とつきあってみよう。



 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月24日読み終わった他人と比較をすること。そうすることで自分の立ち位置測ることができると同時に、他人に対しての嫉妬が生じることもある。嫉妬を自覚してしまうことは本人にとってとても苦しいことだ。だからこそ嫉妬してしまうことがなくなればどんなに楽になるだろうかと悪戦苦闘してその感情を消そうとする。だけど、嫉妬と民主主義は表裏一体の双子のようなもので、嫉妬をなくすには社会構造そのものを組み立て直すしか他に方法がない。そんな社会の仕組みを変えるなんてことは一個人にはできないから、自分の中で飼い慣らすしかない。嫉妬という後ろ暗い感情を逆手に取り成長の糧にする術を身につける。そうして嫉妬と上手く付き合っていくことが最善なのかもしれない。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月24日読み終わった他人と比較をすること。そうすることで自分の立ち位置測ることができると同時に、他人に対しての嫉妬が生じることもある。嫉妬を自覚してしまうことは本人にとってとても苦しいことだ。だからこそ嫉妬してしまうことがなくなればどんなに楽になるだろうかと悪戦苦闘してその感情を消そうとする。だけど、嫉妬と民主主義は表裏一体の双子のようなもので、嫉妬をなくすには社会構造そのものを組み立て直すしか他に方法がない。そんな社会の仕組みを変えるなんてことは一個人にはできないから、自分の中で飼い慣らすしかない。嫉妬という後ろ暗い感情を逆手に取り成長の糧にする術を身につける。そうして嫉妬と上手く付き合っていくことが最善なのかもしれない。
 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月24日読んでる『私は誰の何に嫉妬しているのか、なぜ彼や彼女に嫉妬してしまうのか。これは翻って、私がどういう人間であるか、私は誰と自分を比べているのか、私はどんな準拠集団のなかに自分を見出しているかを教えてくれるだろう。』 ●メリトクラシー 能力による支配を正当化するイデオロギー。多くの場合、能力の有無や成績の出来不出来によって人々に格差を承認させる考え方。 『比較をやめられないならあえて徹底してみること、逆説的ではあるが、これだけが嫉妬という怪物を宥める確実な方法であるように思われる。』 インターネットの普及により自分と他人の生活を絶えず比較するようになってしまったが、見えている部分は他人の生活の一部分にすぎないということを念頭に置き、それが他人のリアルな生活全部と思い込まないように気をつける。そして、徹底的に比較するようにと言う。比較をしない、自分は自分、みたいな言説が世の中には蔓延っているから、この考え方はすごく新鮮だった。確かに切り取られた生活の一部を見て、それが他人の全部だと考えるのは些か乱暴かもしれない。比較するなら比較するで比較対象者を全面的に見る、そのような習慣をつけるようにしていきたい。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月24日読んでる『私は誰の何に嫉妬しているのか、なぜ彼や彼女に嫉妬してしまうのか。これは翻って、私がどういう人間であるか、私は誰と自分を比べているのか、私はどんな準拠集団のなかに自分を見出しているかを教えてくれるだろう。』 ●メリトクラシー 能力による支配を正当化するイデオロギー。多くの場合、能力の有無や成績の出来不出来によって人々に格差を承認させる考え方。 『比較をやめられないならあえて徹底してみること、逆説的ではあるが、これだけが嫉妬という怪物を宥める確実な方法であるように思われる。』 インターネットの普及により自分と他人の生活を絶えず比較するようになってしまったが、見えている部分は他人の生活の一部分にすぎないということを念頭に置き、それが他人のリアルな生活全部と思い込まないように気をつける。そして、徹底的に比較するようにと言う。比較をしない、自分は自分、みたいな言説が世の中には蔓延っているから、この考え方はすごく新鮮だった。確かに切り取られた生活の一部を見て、それが他人の全部だと考えるのは些か乱暴かもしれない。比較するなら比較するで比較対象者を全面的に見る、そのような習慣をつけるようにしていきたい。

 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月23日読んでる『キルケゴールの考えでは、革命の時代が情熱的な時代、感激に満ち満ちた時代であったのに対し、「現代は本質的に分別の時代、反省の時代、情熱のない時代であり、束の間の感激にぱっと燃え上がっても、やがて小賢しく無感動の状態におさまってしまうといった時代」である。』 『嫉妬者が才能のある者や傑出した者の足を引っ張ることで、すべての人を凡人並みにしてしまうような状態を指している。キルケゴールにとって、これほどつまらない時代はないというわけだ。』 つまらない時代…かぁ…そしたらそのつまらない時代に生まれ落ちた者たちはどう生きていけば良いのだろうか? ●メガロサミア(優越願望) 自分の優越性を認めさせようとする欲望 ●アイソサミア(対等願望) 他人と対等なものとして認められたいという欲望 『優越願望が地下に潜伏し、対等願望が幅をきかせているのが現代の民主社会の特徴なのだ。』 平等を叫べば叫ぶほどほんの小さな差異が嫉妬の誘因となってしまう。突出した芽は摘まれてしまう。嫉妬は民主主義と同じ土壌から生まれた双子のようなものと言うので、どうにか上手く付き合っていくしかなさそうだ。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月23日読んでる『キルケゴールの考えでは、革命の時代が情熱的な時代、感激に満ち満ちた時代であったのに対し、「現代は本質的に分別の時代、反省の時代、情熱のない時代であり、束の間の感激にぱっと燃え上がっても、やがて小賢しく無感動の状態におさまってしまうといった時代」である。』 『嫉妬者が才能のある者や傑出した者の足を引っ張ることで、すべての人を凡人並みにしてしまうような状態を指している。キルケゴールにとって、これほどつまらない時代はないというわけだ。』 つまらない時代…かぁ…そしたらそのつまらない時代に生まれ落ちた者たちはどう生きていけば良いのだろうか? ●メガロサミア(優越願望) 自分の優越性を認めさせようとする欲望 ●アイソサミア(対等願望) 他人と対等なものとして認められたいという欲望 『優越願望が地下に潜伏し、対等願望が幅をきかせているのが現代の民主社会の特徴なのだ。』 平等を叫べば叫ぶほどほんの小さな差異が嫉妬の誘因となってしまう。突出した芽は摘まれてしまう。嫉妬は民主主義と同じ土壌から生まれた双子のようなものと言うので、どうにか上手く付き合っていくしかなさそうだ。 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月23日読んでる「陶片追放は刑罰ではなく、嫉妬心の慰撫・軽減である。嫉妬心というものは頭角を現わす者の頭を抑えつけることに快哉を叫び、そのむしゃくしゃをこのような公的剝奪という形に現わして発散させる」 (『プルタルコス英雄伝』 プルタルコス) 『嫉妬は正義や公正さに自らを偽装し、相手を「引き下げる」ことで自分を慰める。』 人を貶めることで自分を慰めるなんて、人間ってなんだか悲しい生き物だなと思った。平等を叫び、均したら均したでほんの少しの差異が嫉妬の誘因になり得る。もはや感情を排するしか嫉妬を無くすことはできないのではとすら思ってしまう…。 『「見込みのある人生」、つまり人生がうまくいっていると感じられるためには、その人が「どこかに向かっている」、前進しているという感覚(ハージはこれを「想像的な移動性」と呼んでいる)が不可欠であるという。』 どこかで聞いたような…と思ったら「移動と階級」にて引用されていた。 自分の人生を歩む的な言葉が自分には響きやすいのかもしれない。 『簡単に言えば、人生のコマを順調に前に進めている感覚と言ってもいいかもしれない。』
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月23日読んでる「陶片追放は刑罰ではなく、嫉妬心の慰撫・軽減である。嫉妬心というものは頭角を現わす者の頭を抑えつけることに快哉を叫び、そのむしゃくしゃをこのような公的剝奪という形に現わして発散させる」 (『プルタルコス英雄伝』 プルタルコス) 『嫉妬は正義や公正さに自らを偽装し、相手を「引き下げる」ことで自分を慰める。』 人を貶めることで自分を慰めるなんて、人間ってなんだか悲しい生き物だなと思った。平等を叫び、均したら均したでほんの少しの差異が嫉妬の誘因になり得る。もはや感情を排するしか嫉妬を無くすことはできないのではとすら思ってしまう…。 『「見込みのある人生」、つまり人生がうまくいっていると感じられるためには、その人が「どこかに向かっている」、前進しているという感覚(ハージはこれを「想像的な移動性」と呼んでいる)が不可欠であるという。』 どこかで聞いたような…と思ったら「移動と階級」にて引用されていた。 自分の人生を歩む的な言葉が自分には響きやすいのかもしれない。 『簡単に言えば、人生のコマを順調に前に進めている感覚と言ってもいいかもしれない。』 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月22日読んでる『たとえコミュニズムが人々の経済状況や暮らし向きを均すことに成功したとしても、嫉妬はまた別の差異へと憑依する。そしてそれは以前よりはるかに陰鬱で、危ういものになるかもしれないということなのだ。』 抑え込めば抑え込むほど反動が大きくなるということか。しかもはるかに陰鬱で危ういものになる可能性があるという。嫉妬とはどこまでも厄介な感情だなと思った。 ただ、次章にて、 『嫉妬の両義性を示すことで、この感情との付き合い方の常識を根本から揺さぶることを目指したい。』 とのことなので、どんなことが提示されるのかわくわくしている。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月22日読んでる『たとえコミュニズムが人々の経済状況や暮らし向きを均すことに成功したとしても、嫉妬はまた別の差異へと憑依する。そしてそれは以前よりはるかに陰鬱で、危ういものになるかもしれないということなのだ。』 抑え込めば抑え込むほど反動が大きくなるということか。しかもはるかに陰鬱で危ういものになる可能性があるという。嫉妬とはどこまでも厄介な感情だなと思った。 ただ、次章にて、 『嫉妬の両義性を示すことで、この感情との付き合い方の常識を根本から揺さぶることを目指したい。』 とのことなので、どんなことが提示されるのかわくわくしている。
 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月15日読んでる『私たちはたとえ自分に利得があったとしても、他人の幸福に我慢できない。いやむしろ、隣人の不幸のためなら、すすんで自分の利益を差し出すことさえある。』 →引用:あるスロヴェニアの農夫の物語 『農夫は善良な魔女からこう言われる。「なんでも望みを叶えてやろう。でも言っておくが、お前の隣人には同じことを二倍叶えてやるぞ」。農夫は一瞬考えてから、悪賢そうな微笑を浮かべ、魔女に言う。「おれの眼をひとつ取ってくれ」。』 えぇぇ…こわぁ…。人間って恐ろしい。 自分の望みが叶えられる場面でさえ、隣人の方が幸福になることを許さず、共に地獄へ引きずり落とすことを選ぶってこと…? 確かに同じ場面に遭遇したとしたら、自分の二倍も叶えてもらえるなんて!という嫉みが生じてしまうかもしれないなと思った。 『羨望の解決のためにはもはや無関心しかないかのようだ。』 もうもはや人間が人間らしさを失ってしまう…。それほどまでに嫉妬というものは人間の感性とか感情とかに直結してしまっており切っても切り離せないものなのだと痛感する。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月15日読んでる『私たちはたとえ自分に利得があったとしても、他人の幸福に我慢できない。いやむしろ、隣人の不幸のためなら、すすんで自分の利益を差し出すことさえある。』 →引用:あるスロヴェニアの農夫の物語 『農夫は善良な魔女からこう言われる。「なんでも望みを叶えてやろう。でも言っておくが、お前の隣人には同じことを二倍叶えてやるぞ」。農夫は一瞬考えてから、悪賢そうな微笑を浮かべ、魔女に言う。「おれの眼をひとつ取ってくれ」。』 えぇぇ…こわぁ…。人間って恐ろしい。 自分の望みが叶えられる場面でさえ、隣人の方が幸福になることを許さず、共に地獄へ引きずり落とすことを選ぶってこと…? 確かに同じ場面に遭遇したとしたら、自分の二倍も叶えてもらえるなんて!という嫉みが生じてしまうかもしれないなと思った。 『羨望の解決のためにはもはや無関心しかないかのようだ。』 もうもはや人間が人間らしさを失ってしまう…。それほどまでに嫉妬というものは人間の感性とか感情とかに直結してしまっており切っても切り離せないものなのだと痛感する。

 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月14日読んでる『浪費は身の丈にかなったものであれば美徳になるが、行き過ぎると途端に示威的なものになる。美徳と悪徳の境界はきわめて曖昧であり、徳の傍にはつねに悪徳が控えていると言ってよい。』 『そもそも「贅沢」(luxury)という言葉は、ラテン語の二つの名詞に由来する。その二つとは「官能、華美、華やかさを意味するluxusと放縦、不節制、浪費を意味するluxuria」であり、この両義性には、贅沢そのものは好ましいとしても、度を過ぎるとたちまち悪徳になってしまうといった特徴がよく現れている。』 やっぱり何事もほどほどが大切。 『かつて「持つ者」は「持たざる者」からの嫉妬を恐れ、富や成功を隠す傾向にあったが、ソーシャルメディアの時代にあって人々は自身の幸福をもはや隠そうとはしない。それどころか、自身の幸福を過剰に繕い、実態以上に見せることすらある。』 SNS疲れという言葉を聞いたことがある。友人はこんなにも充実した生活を送っているのに…と惨めな気持ちに陥る。ソーシャルメディアが活発化するに伴い、見せる部分と見せない部分の境界が曖昧になった。息をつく暇もなくいつも競争に晒されているようなものなのだから、それは疲れるのも当然かと思った。 また、現代の生きづらさの要因として、この境界が曖昧になったことで、自分という人間を必要以上に大きく見せようとしてしまい、現実との乖離が生まれる点も挙げられるのではないかと思った。 だからこそ、アナと雪の女王の「ありのまま」も現代人に響いた。 だけど、他人からの評価で塗り固めた自分を選んできた人はどのように自分を再構築したらいいのだろう?
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月14日読んでる『浪費は身の丈にかなったものであれば美徳になるが、行き過ぎると途端に示威的なものになる。美徳と悪徳の境界はきわめて曖昧であり、徳の傍にはつねに悪徳が控えていると言ってよい。』 『そもそも「贅沢」(luxury)という言葉は、ラテン語の二つの名詞に由来する。その二つとは「官能、華美、華やかさを意味するluxusと放縦、不節制、浪費を意味するluxuria」であり、この両義性には、贅沢そのものは好ましいとしても、度を過ぎるとたちまち悪徳になってしまうといった特徴がよく現れている。』 やっぱり何事もほどほどが大切。 『かつて「持つ者」は「持たざる者」からの嫉妬を恐れ、富や成功を隠す傾向にあったが、ソーシャルメディアの時代にあって人々は自身の幸福をもはや隠そうとはしない。それどころか、自身の幸福を過剰に繕い、実態以上に見せることすらある。』 SNS疲れという言葉を聞いたことがある。友人はこんなにも充実した生活を送っているのに…と惨めな気持ちに陥る。ソーシャルメディアが活発化するに伴い、見せる部分と見せない部分の境界が曖昧になった。息をつく暇もなくいつも競争に晒されているようなものなのだから、それは疲れるのも当然かと思った。 また、現代の生きづらさの要因として、この境界が曖昧になったことで、自分という人間を必要以上に大きく見せようとしてしまい、現実との乖離が生まれる点も挙げられるのではないかと思った。 だからこそ、アナと雪の女王の「ありのまま」も現代人に響いた。 だけど、他人からの評価で塗り固めた自分を選んできた人はどのように自分を再構築したらいいのだろう? ちょこれーと*@5_ogd2025年7月14日読んでる「人間として存在するうえで、私自身のものである仕方というものが存在するのである。私は自らの人生を、他人の人生の模倣によってではなく、こういう仕方で生きることを求められるのである。」 自分の人生を歩む。誰かの模倣ではなく。 自己を確立しないとできないこと。 自分で考えずに人の意見に乗っかってここまで来てしまったから、とっても難しい。 共感と言うと聞こえが良いけれど。 空っぽだって認めたくなくて、相手が求めてそうなそれらしい回答用意して、本当の自分ってなんなんだろうなんていつも考えていた。だからこそ同窓生たちがどんどん先に歩いて行くのを見て、同じところを進んでいたはずなのにと、羨望という正の感情ではなく嫉妬という負の感情の方が生じてしまうのかもしれない。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月14日読んでる「人間として存在するうえで、私自身のものである仕方というものが存在するのである。私は自らの人生を、他人の人生の模倣によってではなく、こういう仕方で生きることを求められるのである。」 自分の人生を歩む。誰かの模倣ではなく。 自己を確立しないとできないこと。 自分で考えずに人の意見に乗っかってここまで来てしまったから、とっても難しい。 共感と言うと聞こえが良いけれど。 空っぽだって認めたくなくて、相手が求めてそうなそれらしい回答用意して、本当の自分ってなんなんだろうなんていつも考えていた。だからこそ同窓生たちがどんどん先に歩いて行くのを見て、同じところを進んでいたはずなのにと、羨望という正の感情ではなく嫉妬という負の感情の方が生じてしまうのかもしれない。
 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月12日読んでる■「非 - 嫉妬の政治」の可能性とは-マーサ・ヌスバウム 『ヌスバウムの議論に特徴的なことは、嫉妬を「恐れ(fear)」と結びつけて考察していることだ。恐れとは「是が非でも持っておく必要のあるものを持っていないという恐れ」のことである。こうした不安や無力感から、人は他人とのゼロサム的な競争へと駆り立てられてしまうのだ。』 ●ゼロサム:合計するとゼロになること。一方の利益が他方の損失になること。 ■正真正銘の悪徳-福澤諭吉の「怨望」論 『福澤は、嫉妬感情を「怨望」(これは英語の“envy”の響きを残す優れた翻訳であると思う)と呼び、これを厳しく評価している。』 ・吝嗇(りんしょく) →一般にケチなことを意味しているが、計画的に金銭を貯めこむことそれ自体はなんら問題あることでないし、場合によっては倹約的であると評価される ・奢侈(しゃし)≒贅沢 →快適な暮らしを求める人間の本性にかなっており、美徳であるとさえ言える。 『怨望だけはこの両義性の法則にしたがわない。人間とは様々に不徳を致すものではあるけれども、「その交際に害あるものは怨望より大なるはなし。」それは正真正銘の悪徳、「衆悪の母」、「人間最大の禍」であるほかない。』 一般的に良くないとされる性質でも、考え方次第では良いこともある。ただし、怨望については例外で正真正銘の悪徳だという。 他人に対して攻撃的になったりその怨望(envy)が緩和されない場合は自身の身を滅ぼす可能性もある故か。 その感情が競争心を駆り立て互いの成長の糧になる、とプラスに働くのであれば話はまた別なのかもしれないが。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月12日読んでる■「非 - 嫉妬の政治」の可能性とは-マーサ・ヌスバウム 『ヌスバウムの議論に特徴的なことは、嫉妬を「恐れ(fear)」と結びつけて考察していることだ。恐れとは「是が非でも持っておく必要のあるものを持っていないという恐れ」のことである。こうした不安や無力感から、人は他人とのゼロサム的な競争へと駆り立てられてしまうのだ。』 ●ゼロサム:合計するとゼロになること。一方の利益が他方の損失になること。 ■正真正銘の悪徳-福澤諭吉の「怨望」論 『福澤は、嫉妬感情を「怨望」(これは英語の“envy”の響きを残す優れた翻訳であると思う)と呼び、これを厳しく評価している。』 ・吝嗇(りんしょく) →一般にケチなことを意味しているが、計画的に金銭を貯めこむことそれ自体はなんら問題あることでないし、場合によっては倹約的であると評価される ・奢侈(しゃし)≒贅沢 →快適な暮らしを求める人間の本性にかなっており、美徳であるとさえ言える。 『怨望だけはこの両義性の法則にしたがわない。人間とは様々に不徳を致すものではあるけれども、「その交際に害あるものは怨望より大なるはなし。」それは正真正銘の悪徳、「衆悪の母」、「人間最大の禍」であるほかない。』 一般的に良くないとされる性質でも、考え方次第では良いこともある。ただし、怨望については例外で正真正銘の悪徳だという。 他人に対して攻撃的になったりその怨望(envy)が緩和されない場合は自身の身を滅ぼす可能性もある故か。 その感情が競争心を駆り立て互いの成長の糧になる、とプラスに働くのであれば話はまた別なのかもしれないが。
 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月12日読んでる■嫉妬は平均を目指す-三木清の嫉妬論 『嫉妬者は「平均」よりも高く逸脱するものを低めようとするのであって、これが愛と大きく異なる点である。愛はより高いものに憧れるのがつねであるから。』 やっぱり嫉妬は対象者を引きずり下ろすことを求めるものらしい。同じような感情なんだろうけど羨望だと輝かしく聞こえが良いのに。 『興味深く思えるのは、そうした承認に対するあくなき欲求が、誇示や自慢によってはなんら解決されているようには見えないことだ。まるで喉の渇きを癒やそうとして海水をがぶ飲みするように、誇示者はますます承認に飢えているように見える。』 『誰かに自らの幸福や成功を誇示し、妬みをかき立ててはじめて欲望は成就する。欲望にはつねにそうした他者の介在がある。』 『賞賛とは他人から受け取るべきもので、それを自分で自分に与えることは正しくない。自画自賛は良識に反するものであり、だからこそ私たちはそれをとても苦痛に感じるわけだ。』 羨望の的になることで初めて承認欲求は満たされるということか。例えば、何か入手困難なものを持っていて、それを人に自慢をして羨ましがられることで承認欲求は満たされる。だけど、自慢した先の相手も持っていた場合は?羨望の的ではなくなり特別感も薄れてしまう。そうするとまた別のところに承認欲求を満たす何かを求めるように追い縋る…なんてことになったらいつまでも経ってもずっと苦しい。 誇示はする方もされる方も下手をするとお互いに苦い思いをするだけなのでは?と思った。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月12日読んでる■嫉妬は平均を目指す-三木清の嫉妬論 『嫉妬者は「平均」よりも高く逸脱するものを低めようとするのであって、これが愛と大きく異なる点である。愛はより高いものに憧れるのがつねであるから。』 やっぱり嫉妬は対象者を引きずり下ろすことを求めるものらしい。同じような感情なんだろうけど羨望だと輝かしく聞こえが良いのに。 『興味深く思えるのは、そうした承認に対するあくなき欲求が、誇示や自慢によってはなんら解決されているようには見えないことだ。まるで喉の渇きを癒やそうとして海水をがぶ飲みするように、誇示者はますます承認に飢えているように見える。』 『誰かに自らの幸福や成功を誇示し、妬みをかき立ててはじめて欲望は成就する。欲望にはつねにそうした他者の介在がある。』 『賞賛とは他人から受け取るべきもので、それを自分で自分に与えることは正しくない。自画自賛は良識に反するものであり、だからこそ私たちはそれをとても苦痛に感じるわけだ。』 羨望の的になることで初めて承認欲求は満たされるということか。例えば、何か入手困難なものを持っていて、それを人に自慢をして羨ましがられることで承認欲求は満たされる。だけど、自慢した先の相手も持っていた場合は?羨望の的ではなくなり特別感も薄れてしまう。そうするとまた別のところに承認欲求を満たす何かを求めるように追い縋る…なんてことになったらいつまでも経ってもずっと苦しい。 誇示はする方もされる方も下手をするとお互いに苦い思いをするだけなのでは?と思った。 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月10日読んでる■劣位者への嫉妬-デイヴィッド・ヒューム 『まず一般に、劣っている者との比較は優位者に快楽や安心感を与える。人は他人との比較によってのみ、自分の優位な状況を確認することができる。』 『優位者は、最初、劣位者との比較から快楽を受け取るが、しかし劣位者の相対的な上昇は優位者の快楽を減じてしまうため、これを不快に感じるのである。』 ■人間嫉妬起原論-ジャン=ジャック・ルソー ●自己愛:一つの自然的な感情であって、これがすべての動物をその自己保存に注意させ、また、人間においては理性によって憐れみによって変容されて、人間愛と美徳とを生み出す。 ●自尊心:社会のなかで生れる相対的で、人為的な感情にすぎず、それは各個人に自己を他の誰よりも重んじるようにしむけ、人々に互いに行なうあらゆる悪を思いつかせるとともに、名誉の真の厳選なのである。 『嫉妬は社会の誕生と時を同じくして生まれたのである。』 ■嫉妬のチームプレイ-ショーペンハウアー 「あらゆる種類の個々の傑出した人物に対して、凡庸者どもが申し合わせなど抜きに暗黙裡にとり結び、いたるところで栄えている同盟の塊」 結託して対象者を引きずり下ろそうとする行為は、優位者に対する嫉妬感情の集積である。また、自分も抜きん出た場合は同じ目に遭うというお互いへの牽制にもなる。 なんであの子が選ばれるの!?許せない!引きずり下ろしてやる!…みたいな? こういう行動って正直あんまり理解ができないのよね。群衆という大勢多数に加勢して対象者への攻撃の大義名分を得て偉ぶって何になるの?嫉妬による結託って文明の衰退を引き起こすと思う。足の引っ張り合い。 人にされて嫌だって事を人にしてはいけないって教わらなかったのかしら。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月10日読んでる■劣位者への嫉妬-デイヴィッド・ヒューム 『まず一般に、劣っている者との比較は優位者に快楽や安心感を与える。人は他人との比較によってのみ、自分の優位な状況を確認することができる。』 『優位者は、最初、劣位者との比較から快楽を受け取るが、しかし劣位者の相対的な上昇は優位者の快楽を減じてしまうため、これを不快に感じるのである。』 ■人間嫉妬起原論-ジャン=ジャック・ルソー ●自己愛:一つの自然的な感情であって、これがすべての動物をその自己保存に注意させ、また、人間においては理性によって憐れみによって変容されて、人間愛と美徳とを生み出す。 ●自尊心:社会のなかで生れる相対的で、人為的な感情にすぎず、それは各個人に自己を他の誰よりも重んじるようにしむけ、人々に互いに行なうあらゆる悪を思いつかせるとともに、名誉の真の厳選なのである。 『嫉妬は社会の誕生と時を同じくして生まれたのである。』 ■嫉妬のチームプレイ-ショーペンハウアー 「あらゆる種類の個々の傑出した人物に対して、凡庸者どもが申し合わせなど抜きに暗黙裡にとり結び、いたるところで栄えている同盟の塊」 結託して対象者を引きずり下ろそうとする行為は、優位者に対する嫉妬感情の集積である。また、自分も抜きん出た場合は同じ目に遭うというお互いへの牽制にもなる。 なんであの子が選ばれるの!?許せない!引きずり下ろしてやる!…みたいな? こういう行動って正直あんまり理解ができないのよね。群衆という大勢多数に加勢して対象者への攻撃の大義名分を得て偉ぶって何になるの?嫉妬による結託って文明の衰退を引き起こすと思う。足の引っ張り合い。 人にされて嫌だって事を人にしてはいけないって教わらなかったのかしら。

 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月9日読んでる■嫉妬・背恩・シャーデンフロイデ-イマニュエル・カント 「人間愛とは正反対の人間憎悪の悪徳」:嫉妬、背恩、シャーデンフロイデ ➡︎「嫌悪すべき一群」これらはいずれも公然と示されるものではなく、密かなもの、卑劣なものである 『カントは嫉妬を「他人の幸福が自分の幸福を少しも損なうわけではないのに、他人の幸福をみるのに苦痛を伴うという性癖」と定義していた。』 ■教養人の嫉妬-バーナード・マンデヴィル →合理主義や理性主義が優勢であった時代に、人間を理性よりも情念に突き動かされる存在として描き出したことで知られる。 『「真に良識のある人間がなぜほかの者ほどねたまないかという理由は、馬鹿者や愚か者よりもためらわずに自分を、賛美しているからである」。だとすると、自分の価値を確信することのできない人間、いわば自信を持てない人間は、どれだけ成功しても、あるいは相手よりも優位な立場に立ったとしても、たえず嫉妬感情に振り回られ続けるということになるのだろう。』 自分の価値を確信すること。自信を持つこと。それができたら、真の良識者になれるだけでなく嫉妬感情に振り回されずにすむ。賛美。 自分に価値なんてあるのだろうか?最近そんなことばかり考えている。人伝に友人の近況を聞いて、なんで自分もそんな風になれなかったんだろうと考えてしまう。そんなことになんの意味もないのに。分かっているのに分かっていない。 人生一度どこかで失墜してしまったらもう修復なんて不可能で価値なんて消失してしまうものではないのか。なんて分かったようなことばかり考えている。今からでも再起は可能なのでしょうか。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月9日読んでる■嫉妬・背恩・シャーデンフロイデ-イマニュエル・カント 「人間愛とは正反対の人間憎悪の悪徳」:嫉妬、背恩、シャーデンフロイデ ➡︎「嫌悪すべき一群」これらはいずれも公然と示されるものではなく、密かなもの、卑劣なものである 『カントは嫉妬を「他人の幸福が自分の幸福を少しも損なうわけではないのに、他人の幸福をみるのに苦痛を伴うという性癖」と定義していた。』 ■教養人の嫉妬-バーナード・マンデヴィル →合理主義や理性主義が優勢であった時代に、人間を理性よりも情念に突き動かされる存在として描き出したことで知られる。 『「真に良識のある人間がなぜほかの者ほどねたまないかという理由は、馬鹿者や愚か者よりもためらわずに自分を、賛美しているからである」。だとすると、自分の価値を確信することのできない人間、いわば自信を持てない人間は、どれだけ成功しても、あるいは相手よりも優位な立場に立ったとしても、たえず嫉妬感情に振り回られ続けるということになるのだろう。』 自分の価値を確信すること。自信を持つこと。それができたら、真の良識者になれるだけでなく嫉妬感情に振り回されずにすむ。賛美。 自分に価値なんてあるのだろうか?最近そんなことばかり考えている。人伝に友人の近況を聞いて、なんで自分もそんな風になれなかったんだろうと考えてしまう。そんなことになんの意味もないのに。分かっているのに分かっていない。 人生一度どこかで失墜してしまったらもう修復なんて不可能で価値なんて消失してしまうものではないのか。なんて分かったようなことばかり考えている。今からでも再起は可能なのでしょうか。

 ちょこれーと*@5_ogd2025年7月9日読んでる■嫉妬と憎しみ-プルタルコス 『憎しみはその対象である人物が悪い人間であることを必要とするが、妬みはただ幸福を目にするだけで生じる。また、憎しみには限度があるが、妬みには限りがない点も重要である。』 ■嫉妬と愛-トマス・アクィナス 『嫉妬が隣人の善についての苦痛であるのに対し、愛は同じ善についての喜びなのである。』 ■嫉妬の効用?-フランシス・ベーコン 「嫉妬はさまよい歩く情念であって、街路をうろついて家にじっとしていない」 「妬みは最も執拗な長つづきする感情である」 妬み、嫉妬は本当に厄介だ。同じものを根源にしても少しの違いで愛が嫉妬へ転じることもあるし、しかも際限がなく執拗に長続きする感情だという。 嫉妬と愛が紙一重ならば、嫉妬から愛に転じることもあるのか…?と考えてみたけれど、ほぼ可能性がないに等しい気がする。 まれに少女漫画とかでひとりの人を取り合うライバルだったけど意気投合して仲良しに!みたいな展開になるものもあるにはあるけれど…。 現実的にあり得るのかな?実際どちらかと言えばきっぱり関わりを断つという結果になりそうな気がする。それか妬み続けるか。
ちょこれーと*@5_ogd2025年7月9日読んでる■嫉妬と憎しみ-プルタルコス 『憎しみはその対象である人物が悪い人間であることを必要とするが、妬みはただ幸福を目にするだけで生じる。また、憎しみには限度があるが、妬みには限りがない点も重要である。』 ■嫉妬と愛-トマス・アクィナス 『嫉妬が隣人の善についての苦痛であるのに対し、愛は同じ善についての喜びなのである。』 ■嫉妬の効用?-フランシス・ベーコン 「嫉妬はさまよい歩く情念であって、街路をうろついて家にじっとしていない」 「妬みは最も執拗な長つづきする感情である」 妬み、嫉妬は本当に厄介だ。同じものを根源にしても少しの違いで愛が嫉妬へ転じることもあるし、しかも際限がなく執拗に長続きする感情だという。 嫉妬と愛が紙一重ならば、嫉妬から愛に転じることもあるのか…?と考えてみたけれど、ほぼ可能性がないに等しい気がする。 まれに少女漫画とかでひとりの人を取り合うライバルだったけど意気投合して仲良しに!みたいな展開になるものもあるにはあるけれど…。 現実的にあり得るのかな?実際どちらかと言えばきっぱり関わりを断つという結果になりそうな気がする。それか妬み続けるか。 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月17日読んでる■快楽と苦痛の混合-プラトン 『妬みは確かに魂の苦痛ではあるものの、他方で、隣人が害悪を被れば、妬みは快楽をもたらすこともある。』 ■嫉妬者の戦略分析-イソクラテス 『大衆が見せる「平等主義的な嫉妬(egalitarian envy)」は、優れたものを破滅させようとする悪しきものでしかない。』 無知で本当にお恥ずかしながら、この本でイソクラテスという哲学者を初めて知った。 『プラトン的な教養が厳密な学知を基礎づける「数学的教養」であったのに対し、イソクラテスのそれはいわば「文学的・修辞的教養」であった。』 「言葉を練磨し育成することこそ人間が最も人間らしくなる方途である、イソクラテスがアテナイ人に勧めるのは、このような、言論を人間形成の中核とする教養理念」 -廣川洋一『イソクラテスの修辞学校』より- 言葉を磨くことで人間らしさも磨かれていくということ…!?文学的教養…すごく気になる。 哲学系の書物、言葉が難しくて挫折しがちだけど…。出典の本、チェックしてみようかな。
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月17日読んでる■快楽と苦痛の混合-プラトン 『妬みは確かに魂の苦痛ではあるものの、他方で、隣人が害悪を被れば、妬みは快楽をもたらすこともある。』 ■嫉妬者の戦略分析-イソクラテス 『大衆が見せる「平等主義的な嫉妬(egalitarian envy)」は、優れたものを破滅させようとする悪しきものでしかない。』 無知で本当にお恥ずかしながら、この本でイソクラテスという哲学者を初めて知った。 『プラトン的な教養が厳密な学知を基礎づける「数学的教養」であったのに対し、イソクラテスのそれはいわば「文学的・修辞的教養」であった。』 「言葉を練磨し育成することこそ人間が最も人間らしくなる方途である、イソクラテスがアテナイ人に勧めるのは、このような、言論を人間形成の中核とする教養理念」 -廣川洋一『イソクラテスの修辞学校』より- 言葉を磨くことで人間らしさも磨かれていくということ…!?文学的教養…すごく気になる。 哲学系の書物、言葉が難しくて挫折しがちだけど…。出典の本、チェックしてみようかな。


 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月16日読んでる税金の話になったぞと思ったけど、よくよく考えたら著者様政治学者の方だったわ…。 多く稼ぐ者は稼ぎが少ない人よりも多く税を支払うのは当然。私もそう思っていた。 だけど本来得られるはずだった分を税に取られてしまうのは稼いでいる人もそうじゃない人も一緒。 『累進課税とは貧しい人々が成功者の足を引っ張り、自らの嫉妬心を慰める、そうした卑しい税制なのである。しかも、累進においては、多数派は少数派に対し、限度のない負担を求めることが可能になる』 ひぇぇ…。最近観た映画の感想で「なんで多数派は少数派を排除したがるんだろう?」とか考えていたばっかりなのに。 『移動と階級』でも、誰がお金持ちかも不平等のひとつだって言ってたのに。 多数派という立場に甘んじて少数派を無意識に差別的に考えていたのかもしれない。 一度根付いてしまった考えはなかなか覆せないな。 この多様性の時代においてはもう、常識なんてものはないのかもしれないと思った。 柔軟に考えられるようになりたい。
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月16日読んでる税金の話になったぞと思ったけど、よくよく考えたら著者様政治学者の方だったわ…。 多く稼ぐ者は稼ぎが少ない人よりも多く税を支払うのは当然。私もそう思っていた。 だけど本来得られるはずだった分を税に取られてしまうのは稼いでいる人もそうじゃない人も一緒。 『累進課税とは貧しい人々が成功者の足を引っ張り、自らの嫉妬心を慰める、そうした卑しい税制なのである。しかも、累進においては、多数派は少数派に対し、限度のない負担を求めることが可能になる』 ひぇぇ…。最近観た映画の感想で「なんで多数派は少数派を排除したがるんだろう?」とか考えていたばっかりなのに。 『移動と階級』でも、誰がお金持ちかも不平等のひとつだって言ってたのに。 多数派という立場に甘んじて少数派を無意識に差別的に考えていたのかもしれない。 一度根付いてしまった考えはなかなか覆せないな。 この多様性の時代においてはもう、常識なんてものはないのかもしれないと思った。 柔軟に考えられるようになりたい。 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月6日読んでる『嫉妬心についてあれこれ考えるのはあまり愉快なことではない。人間のドロドロした感情を見つめること自体がときに心苦しいばかりでなく、どうしてもその過程で、認めたくない、日頃考えないようにしている自らの暗い部分を覗き込むことになるからだ。』 普段目を背けている、後ろ暗い感情に焦点を当てること。そうすることで自分は何を得たいんだろう?自問自答しながら読み進めている。 『嫉妬は自らを偽装する。』 『誰かへの嫉妬を認めることは、同時にその人物に対する劣等感を認めることにもなるのだ。これは当人の自尊心を大いに傷つけるものであり、なかなか受け入れがたいことだろう。』 誰でも自分の中に負の感情が渦巻いていることを認めたくない。 その感情に向き合うことで自分はどうなりたいのだろう? ●嫉妬とジェラシーの違い比較 『嫉妬(envy)』 →「欠如」にかかわる≒「獲得」 『ジェラシー(jealousy) →「喪失」にかかわる≒「保持」
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月6日読んでる『嫉妬心についてあれこれ考えるのはあまり愉快なことではない。人間のドロドロした感情を見つめること自体がときに心苦しいばかりでなく、どうしてもその過程で、認めたくない、日頃考えないようにしている自らの暗い部分を覗き込むことになるからだ。』 普段目を背けている、後ろ暗い感情に焦点を当てること。そうすることで自分は何を得たいんだろう?自問自答しながら読み進めている。 『嫉妬は自らを偽装する。』 『誰かへの嫉妬を認めることは、同時にその人物に対する劣等感を認めることにもなるのだ。これは当人の自尊心を大いに傷つけるものであり、なかなか受け入れがたいことだろう。』 誰でも自分の中に負の感情が渦巻いていることを認めたくない。 その感情に向き合うことで自分はどうなりたいのだろう? ●嫉妬とジェラシーの違い比較 『嫉妬(envy)』 →「欠如」にかかわる≒「獲得」 『ジェラシー(jealousy) →「喪失」にかかわる≒「保持」 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月5日読んでる『神とも動物とも異なる「人間味」というものがあるとすれば、それはこうした不合理さにあるに違いない。その意味で、本書が目指すのは一つの「人間学」でもある。』 人間味。なるほど。 人を人たらしめるのは嫉妬という感情、人間の本質を知る為には嫉妬感情を理解する必要があるのかもしれない。 『嫉妬のモデルが女性であるのも、おそらく何らかのジェンダー的なバイアスがあるように思われる(日本語の嫉妬という語も「おんなへん」である!)』 本当だ!確かに女って人が持っているものを羨むことが多いような気が…。隣の芝生は青く見える、みたいな? 『嫉妬にはまったくもってプラスになるところがなく、何一つ取り柄がない。同じ七つの大罪に数えられる怠惰や憤怒にさえ、社会的には何かしらポジティブなところがなくはない。たとえば、怠惰は私たちの疲れを癒すことがあるし、怒りもまた私たちを勇気ある行動へと奮い立たせることがある。』 ふむふむ。考え方次第では七つの大罪だとしても良い点があるらしい。 じゃあ嫉妬は…何の為に生じる感情なんだ?
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月5日読んでる『神とも動物とも異なる「人間味」というものがあるとすれば、それはこうした不合理さにあるに違いない。その意味で、本書が目指すのは一つの「人間学」でもある。』 人間味。なるほど。 人を人たらしめるのは嫉妬という感情、人間の本質を知る為には嫉妬感情を理解する必要があるのかもしれない。 『嫉妬のモデルが女性であるのも、おそらく何らかのジェンダー的なバイアスがあるように思われる(日本語の嫉妬という語も「おんなへん」である!)』 本当だ!確かに女って人が持っているものを羨むことが多いような気が…。隣の芝生は青く見える、みたいな? 『嫉妬にはまったくもってプラスになるところがなく、何一つ取り柄がない。同じ七つの大罪に数えられる怠惰や憤怒にさえ、社会的には何かしらポジティブなところがなくはない。たとえば、怠惰は私たちの疲れを癒すことがあるし、怒りもまた私たちを勇気ある行動へと奮い立たせることがある。』 ふむふむ。考え方次第では七つの大罪だとしても良い点があるらしい。 じゃあ嫉妬は…何の為に生じる感情なんだ?
 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月5日読んでる★ルサンチマン:怨恨、遺恨、復讐感情 一般的に『嫉妬』という感情は忌み嫌われる、嫌厭されるもの。ただし、ずっとその感情を見て見ぬふりをして発散しないままにしておくと、この恐ろしいルサンチマンの原因になりうるらしい。えー、こわいこわい!
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月5日読んでる★ルサンチマン:怨恨、遺恨、復讐感情 一般的に『嫉妬』という感情は忌み嫌われる、嫌厭されるもの。ただし、ずっとその感情を見て見ぬふりをして発散しないままにしておくと、この恐ろしいルサンチマンの原因になりうるらしい。えー、こわいこわい!
 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月5日読んでる『憧憬の場合、私たちは自分が持っていない才能や容姿などを持つ誰かにあこがれの感情を抱き、自分もそれを手に入れられるよう努力するだろう。』 『自分をより高みへと引き上げるのではなく、むしろ他人の足を引っ張ることで溜飲を下げる、これこそ嫉妬が邪悪であるとされるゆえんだろう。』 嫉妬にも良性と悪性があるらしい。ただし良性嫉妬と言うよりも、憧憬と表現した方が輝かしく未来のために努力する姿を想像できる気がする。 (悪性)嫉妬でも、考えようによっては憧憬(良性嫉妬)、自分を成長させる一助になる可能性もある。発想の転換。 『私たちは他人と比較することではじめて、自分のアイデンティティを形成したり、社会における自らの立ち位置を確認することができる。その意味で比較することそれ自体にいいも悪いもない。』 『私たちはたえず上と下を見ながら、自分の立ち位置をはかる悲しい生き物なのである。』 人と自分を比べない。自分の中に負の感情が生じてしまうから。だけど、人は自分の立ち位置を確認する為に比較せざるを得ないのかもしれない。ナンテコッタ。
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月5日読んでる『憧憬の場合、私たちは自分が持っていない才能や容姿などを持つ誰かにあこがれの感情を抱き、自分もそれを手に入れられるよう努力するだろう。』 『自分をより高みへと引き上げるのではなく、むしろ他人の足を引っ張ることで溜飲を下げる、これこそ嫉妬が邪悪であるとされるゆえんだろう。』 嫉妬にも良性と悪性があるらしい。ただし良性嫉妬と言うよりも、憧憬と表現した方が輝かしく未来のために努力する姿を想像できる気がする。 (悪性)嫉妬でも、考えようによっては憧憬(良性嫉妬)、自分を成長させる一助になる可能性もある。発想の転換。 『私たちは他人と比較することではじめて、自分のアイデンティティを形成したり、社会における自らの立ち位置を確認することができる。その意味で比較することそれ自体にいいも悪いもない。』 『私たちはたえず上と下を見ながら、自分の立ち位置をはかる悲しい生き物なのである。』 人と自分を比べない。自分の中に負の感情が生じてしまうから。だけど、人は自分の立ち位置を確認する為に比較せざるを得ないのかもしれない。ナンテコッタ。 ちょこれーと*@5_ogd2025年6月4日買った買った!やっと! この本を見つけたのがmagma booksさんだったから、買うなら絶対ここでと決めていた。 帯にある「羨ましい」の文字が目に入って気にはなっていたけど、副題に「民主社会の」云々って書いてあるのが難しそう…と思ってしまいなかなか手が出なかった。 買おうと決めたのは、最近本を読もうが映画を観ようが、「こんな性格だったらよかったのに」とか「理解してくれる人がいていいな」とかそんなことばかり考えてしまい、そういう言葉が浮かぶたびにこの本を思い出していたため。 明日から読む。楽しみ。
ちょこれーと*@5_ogd2025年6月4日買った買った!やっと! この本を見つけたのがmagma booksさんだったから、買うなら絶対ここでと決めていた。 帯にある「羨ましい」の文字が目に入って気にはなっていたけど、副題に「民主社会の」云々って書いてあるのが難しそう…と思ってしまいなかなか手が出なかった。 買おうと決めたのは、最近本を読もうが映画を観ようが、「こんな性格だったらよかったのに」とか「理解してくれる人がいていいな」とかそんなことばかり考えてしまい、そういう言葉が浮かぶたびにこの本を思い出していたため。 明日から読む。楽しみ。
 ちょこれーと*@5_ogd2025年5月18日気になる自分が持っていないものを人が持ち合わせていると『嫉妬』する。「いいな」「羨ましいな」と思う。すごく気にはなったけど買うのを躊躇ってしまった。『嫉妬』って、なかなか自分では認めたくない感情だから。でも、気づいてしまった。小説とか漫画とかを読んだ後に感じる空しさの正体。 これは『嫉妬』だったんだと。
ちょこれーと*@5_ogd2025年5月18日気になる自分が持っていないものを人が持ち合わせていると『嫉妬』する。「いいな」「羨ましいな」と思う。すごく気にはなったけど買うのを躊躇ってしまった。『嫉妬』って、なかなか自分では認めたくない感情だから。でも、気づいてしまった。小説とか漫画とかを読んだ後に感じる空しさの正体。 これは『嫉妬』だったんだと。

 yoshi@yoshi2025年4月6日読み終わった再読した嫉妬は面倒な感情である。話題にしにくいし、自分の嫉妬感情を認めにくい側面もある。でも誰でも持っている感情であるし、そこには負の面以外もある。うまく付き合っていくしかないこの感情について多面的に論じたよい本だった。
yoshi@yoshi2025年4月6日読み終わった再読した嫉妬は面倒な感情である。話題にしにくいし、自分の嫉妬感情を認めにくい側面もある。でも誰でも持っている感情であるし、そこには負の面以外もある。うまく付き合っていくしかないこの感情について多面的に論じたよい本だった。











