
ちょこれーと*
@5_ogd
自分の思考整理用。
自分の中で生まれた考えとか想いとかって、
泡のようにどんどん消えてしまうものだから。
- 2025年10月20日
 秒速5センチメートル the novel新海誠,鈴木史子読んでる『記憶とは、なぜこんなにも、不在のかたちをしているのだろう。 思い出すのは、たしかに一緒に過ごした出来事だ。それなのに、今も色濃く残っているのは、喪失の感情だ。 言えなかった言葉。伝えられなかった気持ち。叶わなかった約束。 つまり、続かなかった時間のほうだった。 埋まらない空白は、焦燥と苦みに変わり、今に流れ込んでくる。』 『どうしたら、人は喪失と折り合いをつけられるのか。』 『偶然は、実は偶然ではない。無数の分岐の上に成り立つ、限りなく必然に近いもの。』 『何かになりたい、というより、ただどこかへ向かいたかったのだ。 確かな未来なんて描けないまま、それでも、ここではないどこか遠くへ進んでいたかった。止まったような時間のなかで、距離だけが前に進める気がしていた。距離が、未来に近づくための唯一の手がかりに思えた。』 『僕はいつも、過去の手触りや、未来の光にばかり気を取られて、肝心の「今」をどこか置き去りにしてしまう。』 いつでも「今」という時間を大事にできない。 過去への後悔や未来への焦燥に気を取られて、枷をはめられたかのように足取りが重い。行き先も定まらない中、ただただ日常という時間を浪費していく。あの頃に感じていた光をいつどのようにして見失っていったのか。この喪失感をどう埋めていったら良いのか。ずっとその答えを探すように生きている。
秒速5センチメートル the novel新海誠,鈴木史子読んでる『記憶とは、なぜこんなにも、不在のかたちをしているのだろう。 思い出すのは、たしかに一緒に過ごした出来事だ。それなのに、今も色濃く残っているのは、喪失の感情だ。 言えなかった言葉。伝えられなかった気持ち。叶わなかった約束。 つまり、続かなかった時間のほうだった。 埋まらない空白は、焦燥と苦みに変わり、今に流れ込んでくる。』 『どうしたら、人は喪失と折り合いをつけられるのか。』 『偶然は、実は偶然ではない。無数の分岐の上に成り立つ、限りなく必然に近いもの。』 『何かになりたい、というより、ただどこかへ向かいたかったのだ。 確かな未来なんて描けないまま、それでも、ここではないどこか遠くへ進んでいたかった。止まったような時間のなかで、距離だけが前に進める気がしていた。距離が、未来に近づくための唯一の手がかりに思えた。』 『僕はいつも、過去の手触りや、未来の光にばかり気を取られて、肝心の「今」をどこか置き去りにしてしまう。』 いつでも「今」という時間を大事にできない。 過去への後悔や未来への焦燥に気を取られて、枷をはめられたかのように足取りが重い。行き先も定まらない中、ただただ日常という時間を浪費していく。あの頃に感じていた光をいつどのようにして見失っていったのか。この喪失感をどう埋めていったら良いのか。ずっとその答えを探すように生きている。 - 2025年10月17日
 秒速5センチメートル the novel新海誠,鈴木史子読み始めた『人生は進んでいる。あの頃はそう信じていた。でも、大人になってからは違う。次の扉がどこにあるかも、その開き方も、自分で探さなければならない。』 『今の自分はその延長線上に立っているのだろうか。』 『日々は忙しく進んでいく一方で、自分の足で前に進んでいる実感が、どこかで薄れていた。』 ずっと自分だけが同じ場所で足踏みをしているような焦燥感。ただただ進み続ける時間の中で自分だけ、川の真ん中にぽつんと佇む岩のように、取り残されている感覚。時間を共に過ごしてきた同窓生達がとても遠くを歩いているような気がする。そう感じるようになったのはいつからだろうか。 毎日通勤電車に揺られて仕事をして帰ってきて布団に倒れ込む。その繰り返しの中でだんだんと感情の起伏が平坦になり心が摩耗していく。確かにあの頃の道から延びた先にいるのが自分のはずなのに、記憶の中の自分が今とは比べものにならないほど輝いて見えるのはどうしてなんだろう。
秒速5センチメートル the novel新海誠,鈴木史子読み始めた『人生は進んでいる。あの頃はそう信じていた。でも、大人になってからは違う。次の扉がどこにあるかも、その開き方も、自分で探さなければならない。』 『今の自分はその延長線上に立っているのだろうか。』 『日々は忙しく進んでいく一方で、自分の足で前に進んでいる実感が、どこかで薄れていた。』 ずっと自分だけが同じ場所で足踏みをしているような焦燥感。ただただ進み続ける時間の中で自分だけ、川の真ん中にぽつんと佇む岩のように、取り残されている感覚。時間を共に過ごしてきた同窓生達がとても遠くを歩いているような気がする。そう感じるようになったのはいつからだろうか。 毎日通勤電車に揺られて仕事をして帰ってきて布団に倒れ込む。その繰り返しの中でだんだんと感情の起伏が平坦になり心が摩耗していく。確かにあの頃の道から延びた先にいるのが自分のはずなのに、記憶の中の自分が今とは比べものにならないほど輝いて見えるのはどうしてなんだろう。 - 2025年10月6日
 平場の月朝倉かすみ読み終わった久しぶりの読書。 こちらは映画館で観た予告で『大人のラブストーリー』というところ、また、映画verの紫みがかった装丁の美しさに惹かれて読み始めた。 端的に言うと、主人公である青砥の日記を覗き見ているようなお話だと思った。想い出としてサラッと出てきたやり取りが、後からまたこんな場面での会話だったと詳細が明らかになる。前の方のページに戻って確認してまた次のページを読み進める…人生を振り返るような心地の読書体験だった。 当たり前にまた会えるはずだった1年後の約束の日。日常というものがどれだけ儚く脆く崩れやすいものかという尊さを物語る。 人生歩みを進めていれば人に見せたくない面、触れられたくない過去が誰にだってある。自分だけじゃない。そういったものも抱えて生きていくしかない。これから先を生きる為の道標になってくれるようなお話。 結末としては悲恋だけれど、これは平場に暮らす自分たちの現実、それを投影した物語なのだと痛感した。
平場の月朝倉かすみ読み終わった久しぶりの読書。 こちらは映画館で観た予告で『大人のラブストーリー』というところ、また、映画verの紫みがかった装丁の美しさに惹かれて読み始めた。 端的に言うと、主人公である青砥の日記を覗き見ているようなお話だと思った。想い出としてサラッと出てきたやり取りが、後からまたこんな場面での会話だったと詳細が明らかになる。前の方のページに戻って確認してまた次のページを読み進める…人生を振り返るような心地の読書体験だった。 当たり前にまた会えるはずだった1年後の約束の日。日常というものがどれだけ儚く脆く崩れやすいものかという尊さを物語る。 人生歩みを進めていれば人に見せたくない面、触れられたくない過去が誰にだってある。自分だけじゃない。そういったものも抱えて生きていくしかない。これから先を生きる為の道標になってくれるようなお話。 結末としては悲恋だけれど、これは平場に暮らす自分たちの現実、それを投影した物語なのだと痛感した。 - 2025年9月29日
 平場の月朝倉かすみ読み始めた「家に帰って用事を足してるうちにチー坊効果が薄れていって、ときどき『ちょうどよくしあわせだ』と感じた自分が実におめでたい人物だと思えてくることがあってね。布団に入るころには、もしやり直せるとしたら何歳に戻りたいとかさ、そこそこ本気で考えちゃうんだ。空想であそぶ時間は愉しくないこともないけど、なんだろうなあ、いま抱えてるちょっとした煩わしさが寄り集まって、雨雲みたいに広がって、湿気ったきもちになってたりするんだよ」
平場の月朝倉かすみ読み始めた「家に帰って用事を足してるうちにチー坊効果が薄れていって、ときどき『ちょうどよくしあわせだ』と感じた自分が実におめでたい人物だと思えてくることがあってね。布団に入るころには、もしやり直せるとしたら何歳に戻りたいとかさ、そこそこ本気で考えちゃうんだ。空想であそぶ時間は愉しくないこともないけど、なんだろうなあ、いま抱えてるちょっとした煩わしさが寄り集まって、雨雲みたいに広がって、湿気ったきもちになってたりするんだよ」 - 2025年9月23日
 覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読んでる『道半ばで倒れたとき、これが自分の人生だったって、笑いながら言える』。そんな生き方してみたい。 その為にはやっぱり、自分の中にある不安から目を逸らさないこと。見て見ぬ振りをしないこと。向き合って克服する努力をすること。
覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読んでる『道半ばで倒れたとき、これが自分の人生だったって、笑いながら言える』。そんな生き方してみたい。 その為にはやっぱり、自分の中にある不安から目を逸らさないこと。見て見ぬ振りをしないこと。向き合って克服する努力をすること。 - 2025年9月23日
 覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将また読み始めた『心を疲れさせないためには、余計なものを求めないことです。』 某動画配信サービスの30日間無料体験で毎日貪るようにアニメを観た。無料とは言え時間を使って観るわけだから何かを得られる期間にしたい。そう思いながら観ていたのだが、途中でふとなんでこの作品を観たいのか?と、以前こちらの本で読んだ『どんな気持ちを感じたいのか』という一文が思い起こされた。 「自分の本当にしたいこと」ってなんだろう? この答えが見つかれば、必然的に自分に必要なものを選択できるようになる。だけれど、他人の意見を自分の意見と混同し、地に足がついていない根無草のような状態。本当にしたいことは埋もれて見えなくなっている。心の声に耳を傾けるように意識を向け、自分というものを掘り起こせるようにしていきたい。
覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将また読み始めた『心を疲れさせないためには、余計なものを求めないことです。』 某動画配信サービスの30日間無料体験で毎日貪るようにアニメを観た。無料とは言え時間を使って観るわけだから何かを得られる期間にしたい。そう思いながら観ていたのだが、途中でふとなんでこの作品を観たいのか?と、以前こちらの本で読んだ『どんな気持ちを感じたいのか』という一文が思い起こされた。 「自分の本当にしたいこと」ってなんだろう? この答えが見つかれば、必然的に自分に必要なものを選択できるようになる。だけれど、他人の意見を自分の意見と混同し、地に足がついていない根無草のような状態。本当にしたいことは埋もれて見えなくなっている。心の声に耳を傾けるように意識を向け、自分というものを掘り起こせるようにしていきたい。 - 2025年8月20日
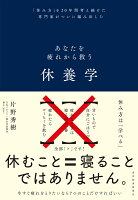 休養学片野秀樹読んでる■ATP(アデノシン三リン酸) …傷ついた細胞を修復するためのエネルギー →脂質・タンパク質・糖質(炭水化物)の三大栄養素からつくられるが、ビタミン・ミネラルなどの補酵素がなければ変換されない。 『疲労回復のためには、いわゆるバランスのよい食事をとることが大事』 『痛み・発熱・疲労は、体の異常を知らせる三大生体アラート』
休養学片野秀樹読んでる■ATP(アデノシン三リン酸) …傷ついた細胞を修復するためのエネルギー →脂質・タンパク質・糖質(炭水化物)の三大栄養素からつくられるが、ビタミン・ミネラルなどの補酵素がなければ変換されない。 『疲労回復のためには、いわゆるバランスのよい食事をとることが大事』 『痛み・発熱・疲労は、体の異常を知らせる三大生体アラート』 - 2025年8月20日
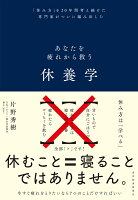 休養学片野秀樹また読み始めた■プレゼンティーズム(Presenteeism) →疾病就業。頭痛や胃腸の不調、軽度のうつ、花粉症などのアレルギー症といった「つらくても無理をすれば出社できる程度の疾病」。 ■アブセンティーズム(Absenteeism) →病欠。プレゼンティーズムの状態がさらに進んで、出社できない状態。 『グーグル翻訳で「お疲れさま」を英語に翻訳してみると、「Thank you for your hard work.」と出ます。直訳すると、重労働をしてくれてありがとう、というような意味です。』 ★日本疲労学会による疲労の定義 「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態である」 『考えてみれば、われわれビジネスパーソンもアスリートのようなものです。やらなければいけない仕事や家事があり、育児や介護など、人それぞれ果たさなければいけない責任があります。』 言われてみればその通りだと思った。しかもアスリートとは違いわれわれにはトレーナーはついていない。自分自身が自分のことに目を配り、オーバートレーニング症候群に陥らないよう的確に疲労を解消していくことが求められる。 ■オーバートレーニング症候群 →疲労が回復していない、パフォーマンスが低下した状態でも休まずにトレーニングを続け、どんどんパフォーマンスが下がる負のスパイラルのこと。
休養学片野秀樹また読み始めた■プレゼンティーズム(Presenteeism) →疾病就業。頭痛や胃腸の不調、軽度のうつ、花粉症などのアレルギー症といった「つらくても無理をすれば出社できる程度の疾病」。 ■アブセンティーズム(Absenteeism) →病欠。プレゼンティーズムの状態がさらに進んで、出社できない状態。 『グーグル翻訳で「お疲れさま」を英語に翻訳してみると、「Thank you for your hard work.」と出ます。直訳すると、重労働をしてくれてありがとう、というような意味です。』 ★日本疲労学会による疲労の定義 「過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態である」 『考えてみれば、われわれビジネスパーソンもアスリートのようなものです。やらなければいけない仕事や家事があり、育児や介護など、人それぞれ果たさなければいけない責任があります。』 言われてみればその通りだと思った。しかもアスリートとは違いわれわれにはトレーナーはついていない。自分自身が自分のことに目を配り、オーバートレーニング症候群に陥らないよう的確に疲労を解消していくことが求められる。 ■オーバートレーニング症候群 →疲労が回復していない、パフォーマンスが低下した状態でも休まずにトレーニングを続け、どんどんパフォーマンスが下がる負のスパイラルのこと。 - 2025年8月19日
 覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読んでる『大事なことは、 なにを、どう手に入れるかではなく、 どんな気持ちを感じたいかなのです。』 『まずは自分が今いるところからはじめましょう。人生の喜びを十分に味わうために。』 よくよく考えるとこれまでずっと人の顔色ばかり窺って行動してきた。人に言われたからやる、人に止められたからやめる。自分の意志で決めたことはあっただろうか。 どんな気持ちを感じたいか。自分の行動を決めるのに十分すぎる言葉。だけれど、根無し草のように生きてきた者にとってはなかなかの難題。 だからこそ、今ここからはじめようと思う。自分はどうしたい?どうなりたい?問いを積み重ねて丁寧にもがきながら再構築していこう。
覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読んでる『大事なことは、 なにを、どう手に入れるかではなく、 どんな気持ちを感じたいかなのです。』 『まずは自分が今いるところからはじめましょう。人生の喜びを十分に味わうために。』 よくよく考えるとこれまでずっと人の顔色ばかり窺って行動してきた。人に言われたからやる、人に止められたからやめる。自分の意志で決めたことはあっただろうか。 どんな気持ちを感じたいか。自分の行動を決めるのに十分すぎる言葉。だけれど、根無し草のように生きてきた者にとってはなかなかの難題。 だからこそ、今ここからはじめようと思う。自分はどうしたい?どうなりたい?問いを積み重ねて丁寧にもがきながら再構築していこう。 - 2025年8月19日
 覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読んでる『やろうと思ったときに、なにかきっかけとなる行動を起こす。それができない人は、いつになってもはじめることができない。』 ドキリとした。まさに自分のことだ。 いつもいつも今の自分は未来の自分に希望を押しつける。やらないといけないことを先延ばしに、見て見ぬふりをして向き合おうともしない。逃避だと分かりながらも逃げ続けてばかりで、理想を妄想で終わらせてしまう。 不安、だからかもしれない。沢山情報を集めて沢山比較した中から選び抜いたもの、努力してその道に進めたところで理不尽にも道を断たれた。そんな経験則から、努力したところで無駄だと。最初から何も起こさなければ絶望することもない。諦念。それでいいのか? 『大切なのは、不安をなくすことではない。いかに早く、多くの失敗を重ねることができるか。そして「未来はいくらでも自分の手で生み出すことができる」という自信を、休むことなく生み続けることなのである。』 不安を払拭することなんてきっとできない。失敗から学び、体勢を立て直し、また挑戦する。そうすることでしか道は拓けない。未来は自分の手で生み出すことができる。前をむき続けるのはとてもしんどいことでもあるけれど、少しは頑張ってみようかなと思える力強い言葉だった。
覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読んでる『やろうと思ったときに、なにかきっかけとなる行動を起こす。それができない人は、いつになってもはじめることができない。』 ドキリとした。まさに自分のことだ。 いつもいつも今の自分は未来の自分に希望を押しつける。やらないといけないことを先延ばしに、見て見ぬふりをして向き合おうともしない。逃避だと分かりながらも逃げ続けてばかりで、理想を妄想で終わらせてしまう。 不安、だからかもしれない。沢山情報を集めて沢山比較した中から選び抜いたもの、努力してその道に進めたところで理不尽にも道を断たれた。そんな経験則から、努力したところで無駄だと。最初から何も起こさなければ絶望することもない。諦念。それでいいのか? 『大切なのは、不安をなくすことではない。いかに早く、多くの失敗を重ねることができるか。そして「未来はいくらでも自分の手で生み出すことができる」という自信を、休むことなく生み続けることなのである。』 不安を払拭することなんてきっとできない。失敗から学び、体勢を立て直し、また挑戦する。そうすることでしか道は拓けない。未来は自分の手で生み出すことができる。前をむき続けるのはとてもしんどいことでもあるけれど、少しは頑張ってみようかなと思える力強い言葉だった。 - 2025年8月18日
 覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読み始めた電車の広告で『吉田松陰』という名前を目にして興味を引かれた。 まずプロローグからだけでも、吉田松陰という人物がどういった人物なのかがありありと伝わってくる。 黒船来航時御年25歳。その若さにして西洋への対抗策を考え、敵わないと思い至るや否や外国から学ぶことを選ぶ。 その覚悟と好奇心の異常ぶりには西洋人たちも恐れを覚えたそうだ。 『今ここで海を渡ることが禁じられているのは、たかだか江戸の250年の常識に過ぎない。今回の事件は、日本の今後3000年の歴史にかかわることだ。くだらない常識に縛られ、日本が沈むのを傍観することは我慢ならなかった。』 密航により故郷長州藩(現在の山口県)萩にて牢獄されるが、その中でも囚人たちを弟子にして一人ひとりの才能を見つけることに心血を注ぐ。 仮釈放された後はかの有名な松下村塾を開き、数多くの豪傑たちを世に輩出することとなる。そこで教えた期間はわずか2年半だという。 『教育は、知識だけを伝えても意味はない。 教える者の生き方が、学ぶ者を感化して、はじめてその成果が得られる。』 「教える、というようなことはできませんが、ともに勉強しましょう」 その後、老中暗殺を目論んだことから投獄、安政の大獄にて30歳という若さでこの世を去る。 なんというすごい人だろうと思った。たったの5年でこれだけの激動の人生を歩んだ偉人。こんなすごい人が残した思想の真髄を味わうことができる、なんて贅沢なんだろう!じっくり身にしていきたい。 ■安政の大獄 …1858〜1859年(安政5〜6年)、幕府の政策に反対した大名・公家・学者ら100余名が処罰、処刑された弾圧事件のこと。その後、大老・井伊直弼への批判が高まり1860年桜田門外によって暗殺される。
覚悟の磨き方 超訳 吉田松陰池田貴将読み始めた電車の広告で『吉田松陰』という名前を目にして興味を引かれた。 まずプロローグからだけでも、吉田松陰という人物がどういった人物なのかがありありと伝わってくる。 黒船来航時御年25歳。その若さにして西洋への対抗策を考え、敵わないと思い至るや否や外国から学ぶことを選ぶ。 その覚悟と好奇心の異常ぶりには西洋人たちも恐れを覚えたそうだ。 『今ここで海を渡ることが禁じられているのは、たかだか江戸の250年の常識に過ぎない。今回の事件は、日本の今後3000年の歴史にかかわることだ。くだらない常識に縛られ、日本が沈むのを傍観することは我慢ならなかった。』 密航により故郷長州藩(現在の山口県)萩にて牢獄されるが、その中でも囚人たちを弟子にして一人ひとりの才能を見つけることに心血を注ぐ。 仮釈放された後はかの有名な松下村塾を開き、数多くの豪傑たちを世に輩出することとなる。そこで教えた期間はわずか2年半だという。 『教育は、知識だけを伝えても意味はない。 教える者の生き方が、学ぶ者を感化して、はじめてその成果が得られる。』 「教える、というようなことはできませんが、ともに勉強しましょう」 その後、老中暗殺を目論んだことから投獄、安政の大獄にて30歳という若さでこの世を去る。 なんというすごい人だろうと思った。たったの5年でこれだけの激動の人生を歩んだ偉人。こんなすごい人が残した思想の真髄を味わうことができる、なんて贅沢なんだろう!じっくり身にしていきたい。 ■安政の大獄 …1858〜1859年(安政5〜6年)、幕府の政策に反対した大名・公家・学者ら100余名が処罰、処刑された弾圧事件のこと。その後、大老・井伊直弼への批判が高まり1860年桜田門外によって暗殺される。 - 2025年8月18日
 あの夏のキミを探して汐見夏衛読み終わった「どんなにつらいことでも、かならず終わる日がくるわ。だからね、おたがい、がんばりましょうね」 『好きなものを好きでいた気持ちを、失いたくなかった。また好きになりたかった。』 『伝えたい気持ちを、ちゃんと伝える大切さを。悪い状況のままで放置せずに、ちゃんと行動を起こすことの大切さを。』 汐見先生が戦後八十年に合わせて、小学校中学年でも読みやすいようにと書かれた作品。 思い出のマーニーを彷彿とさせる、戦時中に十三歳だったキミちゃんと現代の十三歳である陽和が裏山で巡り会う、不思議な十日間の物語。 人の幸不幸は比べられるものではないし、時代が違えば価値観や様々なものに対する重みも変わり、比べることなんてできないけれど。 一世紀も経っていない時代に、いま自分が生きているこの国は戦争をしていた。 未来を夢見ていたであろうたくさんの若い人たちが命を落としていった時代。 もちろん今の時代は今の時代で苦しみの内容は全然別ものだし、話せば分かり合えるなんて生微温いものでもない。 学びたくても学べず国の指揮下で働かざるを得ない子どもたちが今の時代でもいる。 そのことは心に留めておかなくてはいけない事実だと思う。
あの夏のキミを探して汐見夏衛読み終わった「どんなにつらいことでも、かならず終わる日がくるわ。だからね、おたがい、がんばりましょうね」 『好きなものを好きでいた気持ちを、失いたくなかった。また好きになりたかった。』 『伝えたい気持ちを、ちゃんと伝える大切さを。悪い状況のままで放置せずに、ちゃんと行動を起こすことの大切さを。』 汐見先生が戦後八十年に合わせて、小学校中学年でも読みやすいようにと書かれた作品。 思い出のマーニーを彷彿とさせる、戦時中に十三歳だったキミちゃんと現代の十三歳である陽和が裏山で巡り会う、不思議な十日間の物語。 人の幸不幸は比べられるものではないし、時代が違えば価値観や様々なものに対する重みも変わり、比べることなんてできないけれど。 一世紀も経っていない時代に、いま自分が生きているこの国は戦争をしていた。 未来を夢見ていたであろうたくさんの若い人たちが命を落としていった時代。 もちろん今の時代は今の時代で苦しみの内容は全然別ものだし、話せば分かり合えるなんて生微温いものでもない。 学びたくても学べず国の指揮下で働かざるを得ない子どもたちが今の時代でもいる。 そのことは心に留めておかなくてはいけない事実だと思う。 - 2025年8月14日
 あの夏のキミを探して汐見夏衛買った雑誌の広告にて汐見先生の最新作とのことで。表紙がすごく綺麗…と思ったら、前々から目を惹かれることが多いふすいさんのイラストだった。友人と会う予定がありたまたま池袋に行った際、ジュンク堂本店にサイン本があるとの情報を得て、これは手に入れなくては!と思い購入。
あの夏のキミを探して汐見夏衛買った雑誌の広告にて汐見先生の最新作とのことで。表紙がすごく綺麗…と思ったら、前々から目を惹かれることが多いふすいさんのイラストだった。友人と会う予定がありたまたま池袋に行った際、ジュンク堂本店にサイン本があるとの情報を得て、これは手に入れなくては!と思い購入。 - 2025年8月13日
 あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。あんよ,汐見夏衛読み終わった『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』。先日の金曜ロードショーでの特報にて続編の方も映画化が決まったとのことで再読。 「どんなに必死に自分の考えを訴えても、ちっとも分かってもらえなかったりする。おんなじ言葉を使ってても、それまでの環境とか生き方とかが違うと、まるで外国語みたいに伝わらないこともある」 『戦争なんて、病気だ。心の病気だ。 敵に勝つことより、名誉より、土地や資源より、人の命が一番大切だということ、そんな当たり前のことさえ分からなくなってしまう病気なんだ。』 「誰かからもらった優しさを、またほかの人に渡す。自分が優しくされたぶん、ほかの人に優しくする。そうやって恩送りの連鎖ができたら、どんどん優しい世界になっていくだろうなって、なんだか嬉しくなった」 『周りのことも、社会のことも、なにも気にせずに、自分の気持ちを正直に口にできるというのは、平和な世の中だからこそなんだ。』 平和を願った人たちが繋いでくれたこの時代をこの命を大事に。そしてこれから生きていく世代に繋いでいかなくてはいけない。 百合が現代に戻ってからのお話。タイムスリップものを観るといつも、周りにいた親しい人たちは現代に戻ったらみんな過去の人で亡くなっている、そんな悲しい現実の中でどうやって生きていくのだろう?と思っていた。(そして私はみんなと泣くポイントがずれている) 戦争の時代では結ばれなかったふたりが生まれ変わってまた巡り会う。もちろん一筋縄にはいかず紆余曲折あるけれど最終的に結ばれるハッピーエンドでロマンチックなお話。 …なのだけど、なんかもやもやうーんとなってしまうのは何故だろう…。 前作は戦時中の描写に重きを置いている印象が強かったけれど、本作は恋愛恋愛してると言うか…まぁケータイ小説だもんなぁ、という感じがした。中高生が戦争について考えるきっかけにはなると思う。 前作も映画化に際して設定など変わっている点が多々あったので、続報も楽しみに追うことにする。
あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。あんよ,汐見夏衛読み終わった『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』。先日の金曜ロードショーでの特報にて続編の方も映画化が決まったとのことで再読。 「どんなに必死に自分の考えを訴えても、ちっとも分かってもらえなかったりする。おんなじ言葉を使ってても、それまでの環境とか生き方とかが違うと、まるで外国語みたいに伝わらないこともある」 『戦争なんて、病気だ。心の病気だ。 敵に勝つことより、名誉より、土地や資源より、人の命が一番大切だということ、そんな当たり前のことさえ分からなくなってしまう病気なんだ。』 「誰かからもらった優しさを、またほかの人に渡す。自分が優しくされたぶん、ほかの人に優しくする。そうやって恩送りの連鎖ができたら、どんどん優しい世界になっていくだろうなって、なんだか嬉しくなった」 『周りのことも、社会のことも、なにも気にせずに、自分の気持ちを正直に口にできるというのは、平和な世の中だからこそなんだ。』 平和を願った人たちが繋いでくれたこの時代をこの命を大事に。そしてこれから生きていく世代に繋いでいかなくてはいけない。 百合が現代に戻ってからのお話。タイムスリップものを観るといつも、周りにいた親しい人たちは現代に戻ったらみんな過去の人で亡くなっている、そんな悲しい現実の中でどうやって生きていくのだろう?と思っていた。(そして私はみんなと泣くポイントがずれている) 戦争の時代では結ばれなかったふたりが生まれ変わってまた巡り会う。もちろん一筋縄にはいかず紆余曲折あるけれど最終的に結ばれるハッピーエンドでロマンチックなお話。 …なのだけど、なんかもやもやうーんとなってしまうのは何故だろう…。 前作は戦時中の描写に重きを置いている印象が強かったけれど、本作は恋愛恋愛してると言うか…まぁケータイ小説だもんなぁ、という感じがした。中高生が戦争について考えるきっかけにはなると思う。 前作も映画化に際して設定など変わっている点が多々あったので、続報も楽しみに追うことにする。 - 2025年8月12日
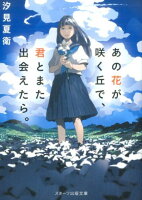 読み終わった『誰にだって、自分の意志で生きる権利があるのに。誰にだって、生きたいと願う権利があるのに。この時代では、そんな当然の権利も認められていないんだ。』 『当たり前のような「またね」の言葉。未来が来ることを、こんな時代でも、人々は信じて疑わない。いや、違うかな。言葉の上だけでも信じていたいのかも。そうじゃないと、生きていけない。』 『ここが、彼らの守ろうとした世界だ。 これが、彼らが自らの命を犠牲にしてまで叶えようとした平和だ。』 この夏は戦後80年だそうだ。テレビで耳にして知った。自分がこれまで生きてきた国のことなのになんて恥ずかしいことなんだと思う。 いま現在の平和はたくさんの犠牲の上に成り立っている、戦争の時代には生きたくても生きられない人がたくさんいたのだという事実をつけつけられる。 平和は当たり前のことではない。 毎日を大事に大事に生きていかなくてはいけないと痛感させられる。 日々の様々なことに忙殺されて投げやりになりそうになった時にはこの作品に立ち返ろう、とそう思う。
読み終わった『誰にだって、自分の意志で生きる権利があるのに。誰にだって、生きたいと願う権利があるのに。この時代では、そんな当然の権利も認められていないんだ。』 『当たり前のような「またね」の言葉。未来が来ることを、こんな時代でも、人々は信じて疑わない。いや、違うかな。言葉の上だけでも信じていたいのかも。そうじゃないと、生きていけない。』 『ここが、彼らの守ろうとした世界だ。 これが、彼らが自らの命を犠牲にしてまで叶えようとした平和だ。』 この夏は戦後80年だそうだ。テレビで耳にして知った。自分がこれまで生きてきた国のことなのになんて恥ずかしいことなんだと思う。 いま現在の平和はたくさんの犠牲の上に成り立っている、戦争の時代には生きたくても生きられない人がたくさんいたのだという事実をつけつけられる。 平和は当たり前のことではない。 毎日を大事に大事に生きていかなくてはいけないと痛感させられる。 日々の様々なことに忙殺されて投げやりになりそうになった時にはこの作品に立ち返ろう、とそう思う。 - 2025年8月9日
- 2025年8月8日
 移動と階級伊藤将人読み終わったついに読み終わってしまった。よく見たら5/22発売。発売日当日に手に入れたから、ずいぶんと長く旅をしてきたなと思う。 「行きたい場所に、いつでも行けますか?」そんな問いから始まる本書。この問いから思い起こした私の最初の答えは「ノー」だった。 学生の頃は望めばどこへだって行ける、何にだってなれるという展望があった。 社会人になってからは規範と言うか社会性と言うか、色々なしがらみが纏わりついて身動きが取りづらくなってしまった。元々体力もそんなにないから疲労も相まって余計に動きたくなくない。 そんな鬱々とした毎日を過ごしている中で、のんびりのんびりと読み進めてきた。 自分には関係がないと見てみぬふりをしていた格差の問題、旅行と嫉妬感情、移動と気候変動といった一見何の関係も無さそうなものの関連性。様々なものは繋がっているのだと認識したらすごくわくわくした。それと同時に複雑に絡み合っているからこそ問題に対する解決の糸口を見つけることの難しさも突きつけられる。 『移動とは、社会的で、政治的で、経済的なものである。』 この社会という枠組みの中で生きている以上、誰もが例外なく当事者である。 そして、最後にもう一度冒頭と同じく「行きたい場所に、いつでも行けますか?」と問われる。読み終えた後の私の答えは見つけられていない。この問いについての答えはずっと考え続けないといけない、人生において一生の宿題なのかもしれないなと思う。
移動と階級伊藤将人読み終わったついに読み終わってしまった。よく見たら5/22発売。発売日当日に手に入れたから、ずいぶんと長く旅をしてきたなと思う。 「行きたい場所に、いつでも行けますか?」そんな問いから始まる本書。この問いから思い起こした私の最初の答えは「ノー」だった。 学生の頃は望めばどこへだって行ける、何にだってなれるという展望があった。 社会人になってからは規範と言うか社会性と言うか、色々なしがらみが纏わりついて身動きが取りづらくなってしまった。元々体力もそんなにないから疲労も相まって余計に動きたくなくない。 そんな鬱々とした毎日を過ごしている中で、のんびりのんびりと読み進めてきた。 自分には関係がないと見てみぬふりをしていた格差の問題、旅行と嫉妬感情、移動と気候変動といった一見何の関係も無さそうなものの関連性。様々なものは繋がっているのだと認識したらすごくわくわくした。それと同時に複雑に絡み合っているからこそ問題に対する解決の糸口を見つけることの難しさも突きつけられる。 『移動とは、社会的で、政治的で、経済的なものである。』 この社会という枠組みの中で生きている以上、誰もが例外なく当事者である。 そして、最後にもう一度冒頭と同じく「行きたい場所に、いつでも行けますか?」と問われる。読み終えた後の私の答えは見つけられていない。この問いについての答えはずっと考え続けないといけない、人生において一生の宿題なのかもしれないなと思う。 - 2025年8月8日
 移動と階級伊藤将人読んでる■ジェンダー主流化 →事業計画から予算編成、調査、設計、実施、分析評価まで、公共政策や事業のすべての工程にジェンダーの観点を制度的に統合する手法とプロセス ■インターセクショナリティ →階級や経済格差、ジェンダー、人種、セクシュアリティ、能力、居住地域、民族、宗教、年齢、国家、市民権など、複数のカテゴリーが相互に影響しあいながら格差や排除、不平等、差別とそれを生じさせる構造をつくりだしていることを理解するための言葉であり、分析ツールである。 ≒個人の中にあるさまざまな特性の重なりに焦点を当てる見方 『移動せずに好きな場所に留まることも大事な権利であり、蔑ろにすべきではないし、そこでの暮らしは非合理だというのも間違いである。人には人の合理性がある。』 なんだかすごい感動してしまった。人には人の合理性がある。うん、いい言葉。人には理解されないことだとしても人それぞれ持っているものがある。心に留めておきたいと思う。
移動と階級伊藤将人読んでる■ジェンダー主流化 →事業計画から予算編成、調査、設計、実施、分析評価まで、公共政策や事業のすべての工程にジェンダーの観点を制度的に統合する手法とプロセス ■インターセクショナリティ →階級や経済格差、ジェンダー、人種、セクシュアリティ、能力、居住地域、民族、宗教、年齢、国家、市民権など、複数のカテゴリーが相互に影響しあいながら格差や排除、不平等、差別とそれを生じさせる構造をつくりだしていることを理解するための言葉であり、分析ツールである。 ≒個人の中にあるさまざまな特性の重なりに焦点を当てる見方 『移動せずに好きな場所に留まることも大事な権利であり、蔑ろにすべきではないし、そこでの暮らしは非合理だというのも間違いである。人には人の合理性がある。』 なんだかすごい感動してしまった。人には人の合理性がある。うん、いい言葉。人には理解されないことだとしても人それぞれ持っているものがある。心に留めておきたいと思う。 - 2025年8月7日
 移動と階級伊藤将人読んでる『人やモノ、情報、資本、文化などさまざまなものが今、まさにこの瞬間も動いており、移動によってこの世界は成り立っている。移動が止まれば世界が止まる、地球の自転が止まれば、この世界にあるものは吹っ飛び、大混乱に陥るように。』 『移動とは社会的で、政治的で、経済的なものである。』 『年収がいくらで、どんな性別で、どこに住んでいて、どんな働き方をしていて、どんな家族構成なのか。そんな誰もがもっている個々人の特徴が、移動をめぐる差異を生み出し、固定化し、ひいては再生産しているのである。』 移動と言うと人がどこかへ行くことを想像しがちだけれど、人以外の情報や物流などもまた移動である。日常生活に埋もれて当たり前と考えてしまいがちなこと。 『社会学という分野には、社会問題とはそこに常に存在するのではなく、人々が社会問題だと認識してはじめて社会問題となり、存在するようになるという考え方がある。』 誰かが叫ばないと誰かの目に留まらないと社会問題として存在すらしていないことになってしまう。また、同じ話を聞いても人それぞれ受け止め方は違う。問題だと感じない人もいるかもしれない。どう問題を提起するか、そのことも課題のひとつかもしれない。
移動と階級伊藤将人読んでる『人やモノ、情報、資本、文化などさまざまなものが今、まさにこの瞬間も動いており、移動によってこの世界は成り立っている。移動が止まれば世界が止まる、地球の自転が止まれば、この世界にあるものは吹っ飛び、大混乱に陥るように。』 『移動とは社会的で、政治的で、経済的なものである。』 『年収がいくらで、どんな性別で、どこに住んでいて、どんな働き方をしていて、どんな家族構成なのか。そんな誰もがもっている個々人の特徴が、移動をめぐる差異を生み出し、固定化し、ひいては再生産しているのである。』 移動と言うと人がどこかへ行くことを想像しがちだけれど、人以外の情報や物流などもまた移動である。日常生活に埋もれて当たり前と考えてしまいがちなこと。 『社会学という分野には、社会問題とはそこに常に存在するのではなく、人々が社会問題だと認識してはじめて社会問題となり、存在するようになるという考え方がある。』 誰かが叫ばないと誰かの目に留まらないと社会問題として存在すらしていないことになってしまう。また、同じ話を聞いても人それぞれ受け止め方は違う。問題だと感じない人もいるかもしれない。どう問題を提起するか、そのことも課題のひとつかもしれない。 - 2025年8月6日
 おもいで金平糖 5持田あき読み終わった過去に戻ってやり直したい。誰でも一度は考えたことがあると思う。でももし戻ったところで今よりも状況が悪くなったらどうしたら良いのだろう? 大好きな持田あき先生の8年振りのおもいで金平糖。内容はもちろんのこと、最後の最後に手紙のように記された言葉の結び『振り返らず進め』が効いてしまった。 タイムスリップができてしまったとしても、結局は今ここにいる自分より状況が良くなるなんてことは、もしかしたらないのかもしれない。生きていることなんて辛いことばっかりだし、明日なんて見えないことだって多々ある。だけど、もしかしたら最悪だらけのパターンの中で少しはマシな道を進んできたのかもしれない。どうせ過去を変えることはできないのだし、変えられる、これからの未来のことを考えてみようか。そう、思った。
おもいで金平糖 5持田あき読み終わった過去に戻ってやり直したい。誰でも一度は考えたことがあると思う。でももし戻ったところで今よりも状況が悪くなったらどうしたら良いのだろう? 大好きな持田あき先生の8年振りのおもいで金平糖。内容はもちろんのこと、最後の最後に手紙のように記された言葉の結び『振り返らず進め』が効いてしまった。 タイムスリップができてしまったとしても、結局は今ここにいる自分より状況が良くなるなんてことは、もしかしたらないのかもしれない。生きていることなんて辛いことばっかりだし、明日なんて見えないことだって多々ある。だけど、もしかしたら最悪だらけのパターンの中で少しはマシな道を進んできたのかもしれない。どうせ過去を変えることはできないのだし、変えられる、これからの未来のことを考えてみようか。そう、思った。
読み込み中...