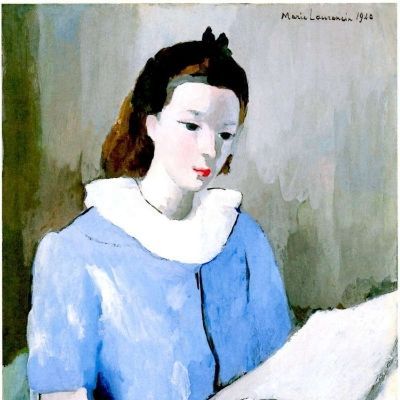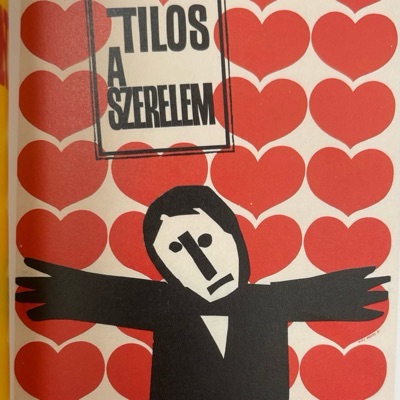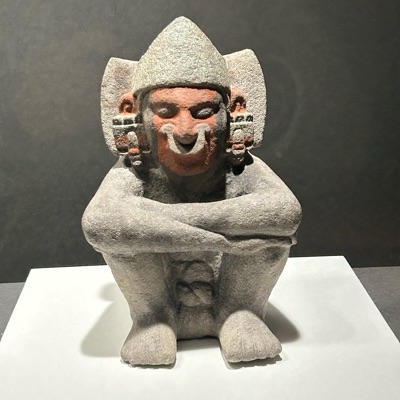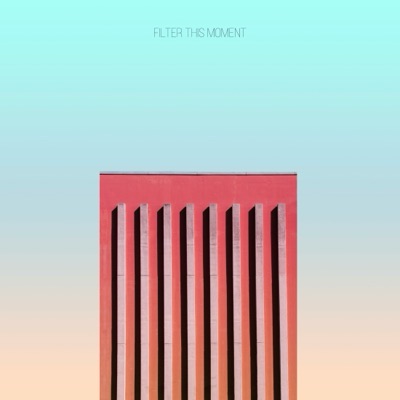ダーウィンの呪い
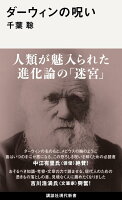
27件の記録
 蔭山@kie_doors2025年12月30日読み終わったダーウィンといえば進化論、ガラパゴス、自然選択…と大変貧しいキーワードしか思い浮かばなかったけど、この本を読んで統計学などの数学分野の発展、優生学の発展からナチスの所業を経ての衰退など、ダーウィンの意思を超えた、もはや「呪い」を受けているとも言える後世の人間の行いの数々を概観できた。
蔭山@kie_doors2025年12月30日読み終わったダーウィンといえば進化論、ガラパゴス、自然選択…と大変貧しいキーワードしか思い浮かばなかったけど、この本を読んで統計学などの数学分野の発展、優生学の発展からナチスの所業を経ての衰退など、ダーウィンの意思を超えた、もはや「呪い」を受けているとも言える後世の人間の行いの数々を概観できた。
 torajiro@torajiro2025年7月15日読み終わったaudibleダーウィンが示したことと社会に流布している進化論的イメージや進化論的比喩の差が大きいかということは吉川浩満『理不尽な進化』でも読んでいたが、ダーウィンの進化論の名の下に「ダーウィンが言っていた」という呪いの言葉でいかに誤った認識が広まり、社会に代償さまざまな悲劇が起こってきたか、その歴史や経緯緻密に構成した内容で良かった。特に後半の優生学については知らなかったことも多かったので読んで本当に良かった。排外主義が拡大したり、生物学遺伝学その他の学問的技術的発展、AIを始めとした他分野の発展など、様々な文脈からいつでも優生学的な論理や帰結に戻ってしまう危険性がとても大きいことがよくわかる。終盤の方「事実(である)から規範(べき)への飛躍があってはならない(「人間は歴史的に常に競争してきた」という事実があったからといって競争すべきと結論付けてはいけないし、「人間は協力行動や利他志向を持っている」が事実だとしてもそこから一足飛びにそうあるべきという規範を導いてはいけない)」は進化学や遺伝学分野のみならず社会のいろいろな場面で注意しなければならないシンプルだけど重要な指摘だと感じる。
torajiro@torajiro2025年7月15日読み終わったaudibleダーウィンが示したことと社会に流布している進化論的イメージや進化論的比喩の差が大きいかということは吉川浩満『理不尽な進化』でも読んでいたが、ダーウィンの進化論の名の下に「ダーウィンが言っていた」という呪いの言葉でいかに誤った認識が広まり、社会に代償さまざまな悲劇が起こってきたか、その歴史や経緯緻密に構成した内容で良かった。特に後半の優生学については知らなかったことも多かったので読んで本当に良かった。排外主義が拡大したり、生物学遺伝学その他の学問的技術的発展、AIを始めとした他分野の発展など、様々な文脈からいつでも優生学的な論理や帰結に戻ってしまう危険性がとても大きいことがよくわかる。終盤の方「事実(である)から規範(べき)への飛躍があってはならない(「人間は歴史的に常に競争してきた」という事実があったからといって競争すべきと結論付けてはいけないし、「人間は協力行動や利他志向を持っている」が事実だとしてもそこから一足飛びにそうあるべきという規範を導いてはいけない)」は進化学や遺伝学分野のみならず社会のいろいろな場面で注意しなければならないシンプルだけど重要な指摘だと感じる。
 モヘンジョ・パロ@mohenjoparo2025年4月11日読み終わった「ダーウィンが言っているから」と大義名分を掲げて人々を扇動することの愚かしさを追求している “ダーウィンはそんなことは言ってない” そして後半の大部分を、優生学を事例に挙げてその批判に割き、筆者の主張が補強されている われわれ人間は、いかに不完全で矛盾に満ちた存在であるかということを認め、その中でおかした過ちを修正していきながら少しずつ、自分たちにとっての善を積み上げていくことを続けていくのみである
モヘンジョ・パロ@mohenjoparo2025年4月11日読み終わった「ダーウィンが言っているから」と大義名分を掲げて人々を扇動することの愚かしさを追求している “ダーウィンはそんなことは言ってない” そして後半の大部分を、優生学を事例に挙げてその批判に割き、筆者の主張が補強されている われわれ人間は、いかに不完全で矛盾に満ちた存在であるかということを認め、その中でおかした過ちを修正していきながら少しずつ、自分たちにとっての善を積み上げていくことを続けていくのみである オルソル@heiwakinen2025年3月30日かつて読んだダーウィンによる進化論の提唱は自然淘汰や適者生存のビジョンを世に広め、それは格差社会を肯定する根拠となった。しかし、実際は古代ギリシャの時代から同等の思想は存在しており、進化論はそれにお墨付きを与えたに過ぎない。つまり、優生学をはじめとする生物学的進歩の思想は、古来より人間の内にある極めて素朴な差別の原理なのだ。優劣を人間が決定した時点で、それは自然科学ではない。過去、民族を進歩させるために個人を犠牲にした優生学は、現在、親が子に能力を授けたいという個人の自由や権利として、新たな復活の兆しを見せている。
オルソル@heiwakinen2025年3月30日かつて読んだダーウィンによる進化論の提唱は自然淘汰や適者生存のビジョンを世に広め、それは格差社会を肯定する根拠となった。しかし、実際は古代ギリシャの時代から同等の思想は存在しており、進化論はそれにお墨付きを与えたに過ぎない。つまり、優生学をはじめとする生物学的進歩の思想は、古来より人間の内にある極めて素朴な差別の原理なのだ。優劣を人間が決定した時点で、それは自然科学ではない。過去、民族を進歩させるために個人を犠牲にした優生学は、現在、親が子に能力を授けたいという個人の自由や権利として、新たな復活の兆しを見せている。