

モヘンジョ・パロ
@mohenjoparo
我が家にある本は一生をかけてもすべてを読み終えることができないことがすでにわかっている
- 2026年2月20日
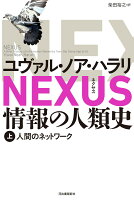 NEXUS 情報の人類史 上ユヴァル・ノア・ハラリ,柴田裕之読み終わった上巻を読み終わった。情報とは何か?から、一貫したテーマである「物語」を軸にしたホモ・サピエンスの繁栄。文章、官僚制、宗教と科学、民主主義と全体主義といった切り口で議論が展開された 後半のスターリン政権の歴史についての話は、直前まで読んでいたこともあり、また、現代史に明るくないこともあり衝撃を受けた。人類の歴史においては全体主義は敗れたが、人類 vs デジタルの行為者の構図になったときに果たして同じことが成り立つだろうか?という問題提起をして下巻へ続く……
NEXUS 情報の人類史 上ユヴァル・ノア・ハラリ,柴田裕之読み終わった上巻を読み終わった。情報とは何か?から、一貫したテーマである「物語」を軸にしたホモ・サピエンスの繁栄。文章、官僚制、宗教と科学、民主主義と全体主義といった切り口で議論が展開された 後半のスターリン政権の歴史についての話は、直前まで読んでいたこともあり、また、現代史に明るくないこともあり衝撃を受けた。人類の歴史においては全体主義は敗れたが、人類 vs デジタルの行為者の構図になったときに果たして同じことが成り立つだろうか?という問題提起をして下巻へ続く…… - 2026年2月15日
 子どものおしゃれにどう向き合う?鈴木公啓読み終わった子どもも大きくなってきてそろそろおしゃれに興味を持ち出すだろうというときの心構えとして読んでおこうと思った おしゃれにまつわるさまざまな親の心配事と実態を有効なアンケート調査、インタビュー調査によって明らかにしている 印象通りのこともあるし意外なこともあるが、定量的な結果として吟味できるのが本書の価値と言える また、心構えについても有益なアドバイスを得られた。こういう調査を続けている筆者からのメッセージも説得力がある 子どもがおしゃれに夢中になる頃には自分の常識はいったん伏せ、今の社会や子どもの周囲の環境とその関わり方にしっかり向き合って対話をしていけるような関係性を作っていきたい
子どものおしゃれにどう向き合う?鈴木公啓読み終わった子どもも大きくなってきてそろそろおしゃれに興味を持ち出すだろうというときの心構えとして読んでおこうと思った おしゃれにまつわるさまざまな親の心配事と実態を有効なアンケート調査、インタビュー調査によって明らかにしている 印象通りのこともあるし意外なこともあるが、定量的な結果として吟味できるのが本書の価値と言える また、心構えについても有益なアドバイスを得られた。こういう調査を続けている筆者からのメッセージも説得力がある 子どもがおしゃれに夢中になる頃には自分の常識はいったん伏せ、今の社会や子どもの周囲の環境とその関わり方にしっかり向き合って対話をしていけるような関係性を作っていきたい - 2026年1月15日
 読み終わった西田宗千佳氏の最近の著書ということで購入して読んでみた 著者はガジェットやインターネットコンテンツに関するわかりやすいコラムを日々執筆しており、そういった各種メディアや X などの発信もいつもチェックしている この本も、そういったオンラインの情報を見ていれば大体が知っている内容ではあるが、タイムラインを眺めて流れていってしまうものは知識として定着しづらい。こういった体系的なまとめをさらっておくのも時には重要だ 自分はスマホのテクノロジーには興味はあるが、マーケティングやキャリアとの関係性といったところはあまり追っていない。だからここで知ることができて良かった また、なぜ日本のティーンズはここまで iPhone のシェアが高いのがなどの筆者の考えも、切り口が面白いなと思って読んだ
読み終わった西田宗千佳氏の最近の著書ということで購入して読んでみた 著者はガジェットやインターネットコンテンツに関するわかりやすいコラムを日々執筆しており、そういった各種メディアや X などの発信もいつもチェックしている この本も、そういったオンラインの情報を見ていれば大体が知っている内容ではあるが、タイムラインを眺めて流れていってしまうものは知識として定着しづらい。こういった体系的なまとめをさらっておくのも時には重要だ 自分はスマホのテクノロジーには興味はあるが、マーケティングやキャリアとの関係性といったところはあまり追っていない。だからここで知ることができて良かった また、なぜ日本のティーンズはここまで iPhone のシェアが高いのがなどの筆者の考えも、切り口が面白いなと思って読んだ - 2026年1月10日
- 2026年1月5日
 読み終わったSF でよくある設定、たとえばコールドスリープだとか電脳化だとか脳機能の拡張だとかを、 SF 好きの医師が考察する空想科学読本 もちろんこの手の言説は、条件付きで可能とか、近い将来ボトルネックが解消されるようなことがあれば可能とか、そういう話になってしまうのだが、ここから学べることもかなりある SF の世界がもう実現できる、なんて眉唾物の噂話なんかは一度立ち止まって考えられるようになるかも知れない。それっぽいこと言っているけど人間の脳のつくり的におかしいよな、とか、その技術はこの技術が無いと成立しないのにそれについては何も言ってないのはおかしいな、とか、その辺の肌感覚がわかるだけでもこの本を読んだ価値はあった また、種本として面白い SF 作品がたくさん紹介されている。古典から映画・漫画・アニメまで。まだまだ読んだり観たりしていない作品もあったので、それを見る楽しみも増えた
読み終わったSF でよくある設定、たとえばコールドスリープだとか電脳化だとか脳機能の拡張だとかを、 SF 好きの医師が考察する空想科学読本 もちろんこの手の言説は、条件付きで可能とか、近い将来ボトルネックが解消されるようなことがあれば可能とか、そういう話になってしまうのだが、ここから学べることもかなりある SF の世界がもう実現できる、なんて眉唾物の噂話なんかは一度立ち止まって考えられるようになるかも知れない。それっぽいこと言っているけど人間の脳のつくり的におかしいよな、とか、その技術はこの技術が無いと成立しないのにそれについては何も言ってないのはおかしいな、とか、その辺の肌感覚がわかるだけでもこの本を読んだ価値はあった また、種本として面白い SF 作品がたくさん紹介されている。古典から映画・漫画・アニメまで。まだまだ読んだり観たりしていない作品もあったので、それを見る楽しみも増えた - 2026年1月5日
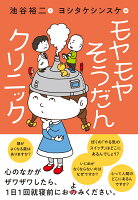 モヤモヤそうだんクリニックヨシタケ・シンスケ,池谷裕二読み終わった小学生からの素朴な疑問に脳科学者の池谷裕二先生が脳のしくみの観点から一緒に考えてこたえてくれる本 どうして勉強しなければいけないの? どうしたら自分に自信がもてるの? 死ぬって何? ゲームってやっぱりよくないの? といった、子供からいきなり質問されて答えに窮する問題に寄り添ってくれる。大人になった自分もそれを見てすっきりしたりまたモヤモヤしたり ヨシタケシンスケさんがかわいい挿絵でさらにモヤモヤを広げてくれて ( もちろん良い意味で ) 、やっぱり考え続けることが大事だよなと思ったり 低学年の子どもがいるが、もう少し大きくなったらまた一緒に読もうと思う
モヤモヤそうだんクリニックヨシタケ・シンスケ,池谷裕二読み終わった小学生からの素朴な疑問に脳科学者の池谷裕二先生が脳のしくみの観点から一緒に考えてこたえてくれる本 どうして勉強しなければいけないの? どうしたら自分に自信がもてるの? 死ぬって何? ゲームってやっぱりよくないの? といった、子供からいきなり質問されて答えに窮する問題に寄り添ってくれる。大人になった自分もそれを見てすっきりしたりまたモヤモヤしたり ヨシタケシンスケさんがかわいい挿絵でさらにモヤモヤを広げてくれて ( もちろん良い意味で ) 、やっぱり考え続けることが大事だよなと思ったり 低学年の子どもがいるが、もう少し大きくなったらまた一緒に読もうと思う - 2026年1月2日
 ニューロマンサー (ハヤカワ文庫SF)ウィリアム・ギブスン,黒丸尚読み終わったやっと読み切った!初めてのギブスン。フルボディな SF だった これがギブスンか……一年ちかくかけて隙間時間に読んできた。もはや全体像はまるで把握できず 特有の用語と表現、神出鬼没のキャラクターたち。これらが複雑に絡み合って序盤からストーリー理解の指針を失う しかし何だろう。ずっと読み続けていた。この独特の筆致を目で追っているだけで、いつの間にかこの世界へ “ジャックイン” してしまうんだ。話は理解できていない、でも自分はこの世界のあるがままをただただ目の当たりにしている、そんな錯覚に陥っていたように思える まるで壮大な叙事詩を読んでいるような、そんな感覚。それが初見のこの本を完走した正直な感想だ 面白いかつまらないかは現時点では判断できない だが今度はストーリーをちゃんと追っていきたい。用語集と人物相関図 ( 人物でないものもいるが ) と地図が必要だ
ニューロマンサー (ハヤカワ文庫SF)ウィリアム・ギブスン,黒丸尚読み終わったやっと読み切った!初めてのギブスン。フルボディな SF だった これがギブスンか……一年ちかくかけて隙間時間に読んできた。もはや全体像はまるで把握できず 特有の用語と表現、神出鬼没のキャラクターたち。これらが複雑に絡み合って序盤からストーリー理解の指針を失う しかし何だろう。ずっと読み続けていた。この独特の筆致を目で追っているだけで、いつの間にかこの世界へ “ジャックイン” してしまうんだ。話は理解できていない、でも自分はこの世界のあるがままをただただ目の当たりにしている、そんな錯覚に陥っていたように思える まるで壮大な叙事詩を読んでいるような、そんな感覚。それが初見のこの本を完走した正直な感想だ 面白いかつまらないかは現時点では判断できない だが今度はストーリーをちゃんと追っていきたい。用語集と人物相関図 ( 人物でないものもいるが ) と地図が必要だ - 2025年12月30日
 三軒茶屋星座館3 春のカリスト柴崎竜人読み終わった10 年前に三軒茶屋に住んでいたとき、地元のラジオでこのシリーズを紹介していて、駅前の当時の TSUTAYA で買った これはシリーズ 3 作目で、過去に「 1 冬のオリオン」「 2 夏のキグナス」を読んでいたが、引越しして三茶を離れ、あれこれあって続きを読めないでいた。ようやく読むことができた 1,2 は主人公の和真と三茶の「三角地帯」にある架空のプラネタリウム「星座館」にフォーカスが当たっていたが、今作では大きく話が動いた。星座館に出入りする仲間たちをフィーチャー。きな臭い事件も起きたり、登場人物たちのロマンスもあり、ハラハラしながら読み進めた この物語に花を添えるのが星座館の店主である和真によるマニアックな星座のエピソード。これは過去二作でも本作でも彼らの世界のストーリーを進めるきっかけを作っていく この続きの 「 4 秋のアンドロメダ」でシリーズ完結するのだが、彼らは無事に「答え」に辿り着けるのかどうか。本作の最後の最後で大団円と思わせて和真に掛かってくる不審な電話 すぐに 4 巻へと向かわねば……!
三軒茶屋星座館3 春のカリスト柴崎竜人読み終わった10 年前に三軒茶屋に住んでいたとき、地元のラジオでこのシリーズを紹介していて、駅前の当時の TSUTAYA で買った これはシリーズ 3 作目で、過去に「 1 冬のオリオン」「 2 夏のキグナス」を読んでいたが、引越しして三茶を離れ、あれこれあって続きを読めないでいた。ようやく読むことができた 1,2 は主人公の和真と三茶の「三角地帯」にある架空のプラネタリウム「星座館」にフォーカスが当たっていたが、今作では大きく話が動いた。星座館に出入りする仲間たちをフィーチャー。きな臭い事件も起きたり、登場人物たちのロマンスもあり、ハラハラしながら読み進めた この物語に花を添えるのが星座館の店主である和真によるマニアックな星座のエピソード。これは過去二作でも本作でも彼らの世界のストーリーを進めるきっかけを作っていく この続きの 「 4 秋のアンドロメダ」でシリーズ完結するのだが、彼らは無事に「答え」に辿り着けるのかどうか。本作の最後の最後で大団円と思わせて和真に掛かってくる不審な電話 すぐに 4 巻へと向かわねば……! - 2025年12月30日
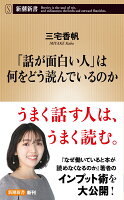 読み終わったさすがにこのタイトルは十分条件にしかならないだろうと思い、優先度は下げていたが、たまたま本屋で目に入ってしまって買ってしまい、するすると読んでしまった 本の読み方の 5 つの切り口を紹介し、それに沿って 200 近い書籍・映像作品等を実際にレビューしてみせてくれている そう、これは「話が面白くなるための方法」の解説本ではなく、三宅氏がこのフォーマットを駆使して読者をさらなる沼へと引き摺り込むためのブックガイドだったという三宅本あるある それはハウツーパートが最初の 50 ページで終わり、あとの 200 ページが全て実践編という名の沼パートという構成からも明らか ( つまりテクニックだけを知りたければ最初の 50 ページを理解できればそれで充分 ) でもターゲット読者はそれ ( 後半部分 )を期待しているところはあるのだろう。ここに紹介された本を書店で見つけたときに背中を押される力は数倍になっていることだろう。そこがこの手前味噌感溢れるタイトルを否定しきれないところなのだろうが…… 自分も何か読みたい本に渇望してきたらまたこの本を開いてみようと思う . いちおう、サブテーマ ( ? ) の方である「話が面白くなる本の読み方」の方にも触れておくと、ここで紹介されているテクニックは身につけておくとかなりコミュニケーションの幅が広がるのは間違いない どちらかというと話の面白い人は本を読む読まないに関わらずこのフォーマットを使えているように思える コミュニケーションに苦手意識がある人はここで紹介されるテクニックを意図的に用いて話してみるなどしていくとかなり見えてくる世界が変わってくるのではないだろうか 自分もコミュニケーション力を高めるために積極的に取り入れていきたい
読み終わったさすがにこのタイトルは十分条件にしかならないだろうと思い、優先度は下げていたが、たまたま本屋で目に入ってしまって買ってしまい、するすると読んでしまった 本の読み方の 5 つの切り口を紹介し、それに沿って 200 近い書籍・映像作品等を実際にレビューしてみせてくれている そう、これは「話が面白くなるための方法」の解説本ではなく、三宅氏がこのフォーマットを駆使して読者をさらなる沼へと引き摺り込むためのブックガイドだったという三宅本あるある それはハウツーパートが最初の 50 ページで終わり、あとの 200 ページが全て実践編という名の沼パートという構成からも明らか ( つまりテクニックだけを知りたければ最初の 50 ページを理解できればそれで充分 ) でもターゲット読者はそれ ( 後半部分 )を期待しているところはあるのだろう。ここに紹介された本を書店で見つけたときに背中を押される力は数倍になっていることだろう。そこがこの手前味噌感溢れるタイトルを否定しきれないところなのだろうが…… 自分も何か読みたい本に渇望してきたらまたこの本を開いてみようと思う . いちおう、サブテーマ ( ? ) の方である「話が面白くなる本の読み方」の方にも触れておくと、ここで紹介されているテクニックは身につけておくとかなりコミュニケーションの幅が広がるのは間違いない どちらかというと話の面白い人は本を読む読まないに関わらずこのフォーマットを使えているように思える コミュニケーションに苦手意識がある人はここで紹介されるテクニックを意図的に用いて話してみるなどしていくとかなり見えてくる世界が変わってくるのではないだろうか 自分もコミュニケーション力を高めるために積極的に取り入れていきたい - 2025年12月24日
 AIに勝つ数学脳ジュネイド・ムビーン,Junaid Mubeen,水谷淳読み終わったAI には無い人間の数学力とは何か?を探るために一年くらいかけて読んでいたけれど、そのわずか一年足らずの間に AI はさらに進歩してしまった。ここに書かれている人間にしかできないことも次第に AI の方が優れるものも出てきた しかしだからといって人間として考えることをやめてしまってはいけないように思う。少なくとも人間として生きたいのであれば 数学の力とは「問いを立てる力」だ。これに関して、人間は機械に束縛される必要はない
AIに勝つ数学脳ジュネイド・ムビーン,Junaid Mubeen,水谷淳読み終わったAI には無い人間の数学力とは何か?を探るために一年くらいかけて読んでいたけれど、そのわずか一年足らずの間に AI はさらに進歩してしまった。ここに書かれている人間にしかできないことも次第に AI の方が優れるものも出てきた しかしだからといって人間として考えることをやめてしまってはいけないように思う。少なくとも人間として生きたいのであれば 数学の力とは「問いを立てる力」だ。これに関して、人間は機械に束縛される必要はない - 2025年12月21日
 イン・ザ・メガチャーチ朝井リョウ読み終わった救いが……ない 主要な 3 人の登場人物全ての心情が、過去のそして今の自分のどこかの瞬間に心当たりがあり、メタな立場で読んでいても心が抉られる思いの連続だった 朝井作品は「何者」以来だったが、彼の日常を切り取る鋭さと解像度の高さにはハラハラさせられる 視野を狭めた熱狂にとらわれている間はすべてが自分の思うままになる。楽しい。視野を広げれば間違うことはないが退屈な人生。たかだか百年生きられるかどうかの人生でどういうスタンスで生きていくかは自由だが、まあ、周りの人には迷惑はかけたくないよな……と、なんかそんな感想でいいのかと思いつつたぶんそこのところなんじゃないだろうか でもこの本を読んで自分の視野の広さかあるいは狭さを何とかして知っておきたいと思った。そのためには学ぶことをやめてはいけないな
イン・ザ・メガチャーチ朝井リョウ読み終わった救いが……ない 主要な 3 人の登場人物全ての心情が、過去のそして今の自分のどこかの瞬間に心当たりがあり、メタな立場で読んでいても心が抉られる思いの連続だった 朝井作品は「何者」以来だったが、彼の日常を切り取る鋭さと解像度の高さにはハラハラさせられる 視野を狭めた熱狂にとらわれている間はすべてが自分の思うままになる。楽しい。視野を広げれば間違うことはないが退屈な人生。たかだか百年生きられるかどうかの人生でどういうスタンスで生きていくかは自由だが、まあ、周りの人には迷惑はかけたくないよな……と、なんかそんな感想でいいのかと思いつつたぶんそこのところなんじゃないだろうか でもこの本を読んで自分の視野の広さかあるいは狭さを何とかして知っておきたいと思った。そのためには学ぶことをやめてはいけないな - 2025年12月19日
 社会契約論重田園江読み終わった「リヴァイアサン」とは何か?を知りたくて。しかし社会契約論と一口に言ってもどこから手をつければいいのか途方に暮れていたところ、それに関する主要人物を紹介しつつ解説するこの新書に出会った しかし、私の理解力ではそれでも難しかった。辛うじて「自然状態」とは何かがわかった程度。ホッブズ→ヒュームときてギリギリだったがルソーの章で名誉の玉砕を遂げる。意識も朦朧としつつロールズの章を読み、満身創痍での読了となった ここに感想を書けないことが悔しい。力をつけてもう一度読みたい
社会契約論重田園江読み終わった「リヴァイアサン」とは何か?を知りたくて。しかし社会契約論と一口に言ってもどこから手をつければいいのか途方に暮れていたところ、それに関する主要人物を紹介しつつ解説するこの新書に出会った しかし、私の理解力ではそれでも難しかった。辛うじて「自然状態」とは何かがわかった程度。ホッブズ→ヒュームときてギリギリだったがルソーの章で名誉の玉砕を遂げる。意識も朦朧としつつロールズの章を読み、満身創痍での読了となった ここに感想を書けないことが悔しい。力をつけてもう一度読みたい - 2025年12月16日
 ビジュアル・シンカーの脳テンプル・グランディン,中尾ゆかり読み終わったこの世界は言語思考者が優位な世界として作られている、という主張に衝撃を受けつつも、深く頷いた 自分は言葉を操るのが苦手な部類に入る。絵に描いて説明したり、モノを用いて説明したりすることで、何とか相手に伝えられたと感じる。だがそういうことができない状況、喋ることしかできないような状況、では圧倒的に疎外感を感じることがある だがそれではこの世の中を生きていけない。だから何とかして言語能力を身につけるために努力をしてきた。本を読むこともその一環なのだと思っている 一昔前と比べて、オンラインでのやり取りが増えてきたこともあり、言葉だけでなく一緒にビジュアル的に考えを伝える機会も恵まれてきた。ビジュアルを作る方法も洗練されてきた。だから言語能力に苦手があっても、少しずつ自分をわかってもらえるチャンスが増えてきたように思える この本に出てくる事例を見るに自分はまだまだ中立なのだろう。だからより視覚思考寄りの人に相対したときには、うまくコミュニケーションが取れないかも知れない。だけど、そういう人たちにはそういう人たちにぴったりの伝え方があるのだと信じて、それを探しつつ、お互いの伝えたいことを知っていけるようにしたい
ビジュアル・シンカーの脳テンプル・グランディン,中尾ゆかり読み終わったこの世界は言語思考者が優位な世界として作られている、という主張に衝撃を受けつつも、深く頷いた 自分は言葉を操るのが苦手な部類に入る。絵に描いて説明したり、モノを用いて説明したりすることで、何とか相手に伝えられたと感じる。だがそういうことができない状況、喋ることしかできないような状況、では圧倒的に疎外感を感じることがある だがそれではこの世の中を生きていけない。だから何とかして言語能力を身につけるために努力をしてきた。本を読むこともその一環なのだと思っている 一昔前と比べて、オンラインでのやり取りが増えてきたこともあり、言葉だけでなく一緒にビジュアル的に考えを伝える機会も恵まれてきた。ビジュアルを作る方法も洗練されてきた。だから言語能力に苦手があっても、少しずつ自分をわかってもらえるチャンスが増えてきたように思える この本に出てくる事例を見るに自分はまだまだ中立なのだろう。だからより視覚思考寄りの人に相対したときには、うまくコミュニケーションが取れないかも知れない。だけど、そういう人たちにはそういう人たちにぴったりの伝え方があるのだと信じて、それを探しつつ、お互いの伝えたいことを知っていけるようにしたい - 2025年12月7日
 プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広読み終わった数ヶ月かけてちびちびと寝る前に読み、今日最後まで終えた 過去に映画「オデッセイ」を観ていたから今回のストーリー展開もとても親しみが持てる 中盤は時間をかけてかなり丁寧に積み上げていってクライマックスは一気に畳み掛けてくる怒濤の展開 読者の感情を揺さぶって揺さぶって最後はちょうど良いところに収束されてしまったという感覚 映画化されると聞いてから積読を崩して読んだので、読書中は各シーンを、映画化されるとどんな表現で見せてくれるのだろうと映像を思い浮かべつつわくわくしながら読むことができた
プロジェクト・ヘイル・メアリー 下アンディ・ウィアー,小野田和子,鷲尾直広読み終わった数ヶ月かけてちびちびと寝る前に読み、今日最後まで終えた 過去に映画「オデッセイ」を観ていたから今回のストーリー展開もとても親しみが持てる 中盤は時間をかけてかなり丁寧に積み上げていってクライマックスは一気に畳み掛けてくる怒濤の展開 読者の感情を揺さぶって揺さぶって最後はちょうど良いところに収束されてしまったという感覚 映画化されると聞いてから積読を崩して読んだので、読書中は各シーンを、映画化されるとどんな表現で見せてくれるのだろうと映像を思い浮かべつつわくわくしながら読むことができた - 2025年12月7日
- 2025年12月7日
 考察する若者たち三宅香帆読み終わったインターネットはあらゆる人々に機会の平等をもたらしたが同時に自分自身の相対値を残酷なまでに可視化してしまった。自分の人生は自分のもの、心の赴くままに時間をかけて模索していけばいいはずなのに、少しでもタイムラインが目に入ると、他人の華やかな日常と扇情的な文句の数々。そんな環境に置かれればどうしたって「正解」の選択肢を効率よく選んで生きたくなってしまうのは仕方のないことではあるのだろう そんな中で泥臭く失敗を重ねて右往左往して模索する生き方はとても勇気がいるし覚悟も必要だろう それでもできるところから始めていきたい。手に入れたものはどれだけ無駄があってもそれを全部含めて自分自身の、自分だけのものなのだから
考察する若者たち三宅香帆読み終わったインターネットはあらゆる人々に機会の平等をもたらしたが同時に自分自身の相対値を残酷なまでに可視化してしまった。自分の人生は自分のもの、心の赴くままに時間をかけて模索していけばいいはずなのに、少しでもタイムラインが目に入ると、他人の華やかな日常と扇情的な文句の数々。そんな環境に置かれればどうしたって「正解」の選択肢を効率よく選んで生きたくなってしまうのは仕方のないことではあるのだろう そんな中で泥臭く失敗を重ねて右往左往して模索する生き方はとても勇気がいるし覚悟も必要だろう それでもできるところから始めていきたい。手に入れたものはどれだけ無駄があってもそれを全部含めて自分自身の、自分だけのものなのだから - 2025年12月3日
 スラムダンク勝利学辻秀一読み終わった古い本だが、辻先生の最近の著作と読み比べても主張は変わらず、全く問題なく今現在でも通用するメンタルの持ち方を学べる。中高生も読者ターゲットにしていてとても読みやすくまとまっている。紙の書籍ならばスラムダンクの各シーンのカットが挿し込まれていてより気分を上げられる 「勝利」をテーマにしている内容だが、その意味を履き違えると自分を見失う。「勝つ」ではなく「克つ」であるということを気づかせてくれる - この本が世に出たときはバスケットボールにもっとも打ち込んでいた高校生の頃だった。なかなか成果を出せず日々悩んでいた。何でこのときに読まなかったのか。本当に悔やまれる ( その時まだスラムダンクを読んでいなかったからか……! )
スラムダンク勝利学辻秀一読み終わった古い本だが、辻先生の最近の著作と読み比べても主張は変わらず、全く問題なく今現在でも通用するメンタルの持ち方を学べる。中高生も読者ターゲットにしていてとても読みやすくまとまっている。紙の書籍ならばスラムダンクの各シーンのカットが挿し込まれていてより気分を上げられる 「勝利」をテーマにしている内容だが、その意味を履き違えると自分を見失う。「勝つ」ではなく「克つ」であるということを気づかせてくれる - この本が世に出たときはバスケットボールにもっとも打ち込んでいた高校生の頃だった。なかなか成果を出せず日々悩んでいた。何でこのときに読まなかったのか。本当に悔やまれる ( その時まだスラムダンクを読んでいなかったからか……! ) - 2025年11月20日
- 2025年11月11日
 老人と海アーネスト・ヘミングウェイ,高見浩読み終わった短い小説。確かな腕を持つが、老いてしまった漁師が一人海へ出る。淡々と情景が語られていくが、獲物と出会ってからの描写はまさに息つく間もなく、夢中になってしまった 漁に出ている数日間の描写をだけで、この老人のこれまで積み上げてきたもの、その生き様を見せつけられる 自分の中ではこの老人は完全にショーン・コネリーでキャスティングされていた
老人と海アーネスト・ヘミングウェイ,高見浩読み終わった短い小説。確かな腕を持つが、老いてしまった漁師が一人海へ出る。淡々と情景が語られていくが、獲物と出会ってからの描写はまさに息つく間もなく、夢中になってしまった 漁に出ている数日間の描写をだけで、この老人のこれまで積み上げてきたもの、その生き様を見せつけられる 自分の中ではこの老人は完全にショーン・コネリーでキャスティングされていた - 2025年10月16日
 イケズの構造(新潮文庫)入江敦彦読み終わった文芸評論家の三宅香帆さんが薄い本の紹介の中で出していたので読んでみた 各種メディア・ SNS で「京都人」の話を聞くたびに、京都に行くことが怖くなっていた今日この頃だったが、それはただの勘違いだということがわかった 人として最低限のマナーと謙虚さがあるかどうかなのだと思う 後半の、歴史上の人物たちのイケズの話、筆者の住むイギリスのイケズの話、近しい間柄でマンネリ化しないためのイケズのすすめなどは、とてもためになった イケズの達人、紫式部もシェイクスピアも、ちゃんと読んでみたくなった
イケズの構造(新潮文庫)入江敦彦読み終わった文芸評論家の三宅香帆さんが薄い本の紹介の中で出していたので読んでみた 各種メディア・ SNS で「京都人」の話を聞くたびに、京都に行くことが怖くなっていた今日この頃だったが、それはただの勘違いだということがわかった 人として最低限のマナーと謙虚さがあるかどうかなのだと思う 後半の、歴史上の人物たちのイケズの話、筆者の住むイギリスのイケズの話、近しい間柄でマンネリ化しないためのイケズのすすめなどは、とてもためになった イケズの達人、紫式部もシェイクスピアも、ちゃんと読んでみたくなった
読み込み中...


