コンヴィヴィアリティのための道具
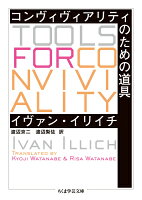
22件の記録
 調@shirabe2025年5月6日読んでる2005年刊の『「未来の学び」をデザインする』で初めて知って、最近あちこちでコンヴィヴィアリティを耳にすることが増えて、ようやく重い腰をあげて読み始めた。けど難しいので超のんびり読み進める。
調@shirabe2025年5月6日読んでる2005年刊の『「未来の学び」をデザインする』で初めて知って、最近あちこちでコンヴィヴィアリティを耳にすることが増えて、ようやく重い腰をあげて読み始めた。けど難しいので超のんびり読み進める。

 doji@doji_asgp2025年4月28日読み終わった産業化とサービス化が進む社会の中で"よりよい"ものを享受しようとすることで、自立と共生のための力が失われてしまうこと、そしてそれを取り戻すためにいまいちど道具のあり方を問い直さなくてはいけないこと。道具によって人が支配されてしまうことは、その後のケビン・ケリーにも引き継がれている考え方なので、なぜ本書がいまも重要な位置付けなのかがわかった。後半の法的な手続きと問題提起についての内容が読み下せなくてまた再読しないといけない。
doji@doji_asgp2025年4月28日読み終わった産業化とサービス化が進む社会の中で"よりよい"ものを享受しようとすることで、自立と共生のための力が失われてしまうこと、そしてそれを取り戻すためにいまいちど道具のあり方を問い直さなくてはいけないこと。道具によって人が支配されてしまうことは、その後のケビン・ケリーにも引き継がれている考え方なので、なぜ本書がいまも重要な位置付けなのかがわかった。後半の法的な手続きと問題提起についての内容が読み下せなくてまた再読しないといけない。

 tetote@tetote182025年3月7日読んでるこの手のお堅い海外論文系は特に苦手分野で開始数ページで挫折しそうになった。 そんなときはあとがきから読む。 翻訳家の意図を知り、『あ、なるほどそうやって読めば良いのね』とわかり正面から向き合わずに読むと案外すらすら進む。あえてわかりにくさを残して訳している、翻訳家さんのクールで皮肉めいた表現スキ。
tetote@tetote182025年3月7日読んでるこの手のお堅い海外論文系は特に苦手分野で開始数ページで挫折しそうになった。 そんなときはあとがきから読む。 翻訳家の意図を知り、『あ、なるほどそうやって読めば良いのね』とわかり正面から向き合わずに読むと案外すらすら進む。あえてわかりにくさを残して訳している、翻訳家さんのクールで皮肉めいた表現スキ。 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月14日読み終わったとにかくイリイチは自転車よりも速くなってしまった移動手段に対してノーと言っているようで、ちょうど『自転車』を読んでいて猛烈に自転車に乗りたくなっている私には、天啓のような1冊だったのかもしれない。しかしそれ以外のことはよくわからない後半100pほどだった。訳者あとがきを読むと渡辺京二が「既訳のものはマジで翻訳がくそだった。英語をわからない奴が翻訳したにちがいない。だから俺は30p読んで挫折したのだ(そして俺が翻訳し直すことにした)」というようなことを言っていて最高だった。しかし30p読んで挫折しかけたのは私も同じであり、そもそも冒頭30pくらいは誰が訳しても意味不明な代物だったのかもしれない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月14日読み終わったとにかくイリイチは自転車よりも速くなってしまった移動手段に対してノーと言っているようで、ちょうど『自転車』を読んでいて猛烈に自転車に乗りたくなっている私には、天啓のような1冊だったのかもしれない。しかしそれ以外のことはよくわからない後半100pほどだった。訳者あとがきを読むと渡辺京二が「既訳のものはマジで翻訳がくそだった。英語をわからない奴が翻訳したにちがいない。だから俺は30p読んで挫折したのだ(そして俺が翻訳し直すことにした)」というようなことを言っていて最高だった。しかし30p読んで挫折しかけたのは私も同じであり、そもそも冒頭30pくらいは誰が訳しても意味不明な代物だったのかもしれない。



 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月14日読んでるまだ読んでる専門家によって建てられた家が機能的な単位住宅ということにされ、自分で建てられた家には掘立て小屋という烙印がおされる。法律は建築家が署名した図面を提出できない人々に建築許可を与えないことによって、こういう定義を定着させる。人々は使用価値を生みだす力を自分自身の時間に付与する能力を奪われ、賃金のために働き、自分の稼ぎを産業的に限定された賃貸空間と交換するように強いられる。彼らはまた、家を建てながら学ぶ機会をも奪われる。(p.143) かつて小屋を建てながら学ぶ機会を得た(そしてそこで本を売った)者として、頷くほかない箇所である。我々は「家は建てられない=専門家に建ててもらう必要がある」と思っているが、そんなことはない。ということを小屋を建てたことがある者は知っている。確かにあの小屋は「掘立て」だったが、私は「いつでもあの小屋を建てられる」と思っていて、それが力の源になっている感覚はある。小屋はいつでも作れる。トランプに壊されてもまた作ればいい。小屋はほかのあらゆるものに代替可能でもある。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月14日読んでるまだ読んでる専門家によって建てられた家が機能的な単位住宅ということにされ、自分で建てられた家には掘立て小屋という烙印がおされる。法律は建築家が署名した図面を提出できない人々に建築許可を与えないことによって、こういう定義を定着させる。人々は使用価値を生みだす力を自分自身の時間に付与する能力を奪われ、賃金のために働き、自分の稼ぎを産業的に限定された賃貸空間と交換するように強いられる。彼らはまた、家を建てながら学ぶ機会をも奪われる。(p.143) かつて小屋を建てながら学ぶ機会を得た(そしてそこで本を売った)者として、頷くほかない箇所である。我々は「家は建てられない=専門家に建ててもらう必要がある」と思っているが、そんなことはない。ということを小屋を建てたことがある者は知っている。確かにあの小屋は「掘立て」だったが、私は「いつでもあの小屋を建てられる」と思っていて、それが力の源になっている感覚はある。小屋はいつでも作れる。トランプに壊されてもまた作ればいい。小屋はほかのあらゆるものに代替可能でもある。



 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月14日読んでるまだ読んでる学習が教育に変質したことは、人間の詩的能力、つまり世界に彼個人の意味を与える能力を麻痺させている。人間は、自然を奪われ、彼自身ですることを奪われ、彼が学ぶように他人が計画したことではなく、自分の欲することを学びたいという彼の深い欲求を奪われるならば、ちょうどそのぶんだけ生気を失っていく。(p.138)
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月14日読んでるまだ読んでる学習が教育に変質したことは、人間の詩的能力、つまり世界に彼個人の意味を与える能力を麻痺させている。人間は、自然を奪われ、彼自身ですることを奪われ、彼が学ぶように他人が計画したことではなく、自分の欲することを学びたいという彼の深い欲求を奪われるならば、ちょうどそのぶんだけ生気を失っていく。(p.138)
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月13日読んでるまだ読んでる今日もまた言い回しが難しく理解できないことばかりだが、とにかくいまトランプがやっていることは地球規模で壊滅的なダメージを与えることなのだ、ということがあらためて突きつけられている。イリイチがこの本を書いたのは1970年くらいだと思うのだけど。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月13日読んでるまだ読んでる今日もまた言い回しが難しく理解できないことばかりだが、とにかくいまトランプがやっていることは地球規模で壊滅的なダメージを与えることなのだ、ということがあらためて突きつけられている。イリイチがこの本を書いたのは1970年くらいだと思うのだけど。

 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月12日読んでる自立共生的道具とは、それを用いる各人に、おのれの想像力の結果として環境をゆたかなものにする最大の機会を与える道具のことである。産業主義的な道具はそれを用いる人々に対してこういう可能性を拒み、道具の考案者たちに、彼ら以外の人々の目的や期待を決定することを許す。今日の大部分の道具は自立共生的な流儀で用いることはできない。p.59 イリイチがいまのSNSを見たらまさに産業主義的道具だと思っただろう。我々は各々自由にSNSを使って楽しんでいるように思っているが、実際にはSNS企業運営者の思惑やらなんやらの中で動き回っているにすぎず、ゆえに今日の社会はできあがっている。そんな気がする。SNSを使う際にわれわれが「こう使うべきだ」と思ってしまうやりかたから、意図的に逸れていくのがいいのかもしれない。それはおそらく考案者たちの目論見に乗せられるということであり、もちろんそれがよい結果を生み出すこともあるが、道具に無自覚なまま隷従してしまうことはもっとおそろしく、個人的には避けるべきだと考えている。アナキストだから。やっとたのしくなってきた。お客さんはぜんぜんこない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月12日読んでる自立共生的道具とは、それを用いる各人に、おのれの想像力の結果として環境をゆたかなものにする最大の機会を与える道具のことである。産業主義的な道具はそれを用いる人々に対してこういう可能性を拒み、道具の考案者たちに、彼ら以外の人々の目的や期待を決定することを許す。今日の大部分の道具は自立共生的な流儀で用いることはできない。p.59 イリイチがいまのSNSを見たらまさに産業主義的道具だと思っただろう。我々は各々自由にSNSを使って楽しんでいるように思っているが、実際にはSNS企業運営者の思惑やらなんやらの中で動き回っているにすぎず、ゆえに今日の社会はできあがっている。そんな気がする。SNSを使う際にわれわれが「こう使うべきだ」と思ってしまうやりかたから、意図的に逸れていくのがいいのかもしれない。それはおそらく考案者たちの目論見に乗せられるということであり、もちろんそれがよい結果を生み出すこともあるが、道具に無自覚なまま隷従してしまうことはもっとおそろしく、個人的には避けるべきだと考えている。アナキストだから。やっとたのしくなってきた。お客さんはぜんぜんこない。


 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月12日読み始めたなにもやる気が起きないがゆえになぜか長期間放置されていた本が手にとられてしまう。難しくて読めないであろうことがわかっていたからこその放置だったはずなのに、やる気がないのに、読み始められてしまう。はじめにを読んだがわからない。ねむい。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月12日読み始めたなにもやる気が起きないがゆえになぜか長期間放置されていた本が手にとられてしまう。難しくて読めないであろうことがわかっていたからこその放置だったはずなのに、やる気がないのに、読み始められてしまう。はじめにを読んだがわからない。ねむい。



















