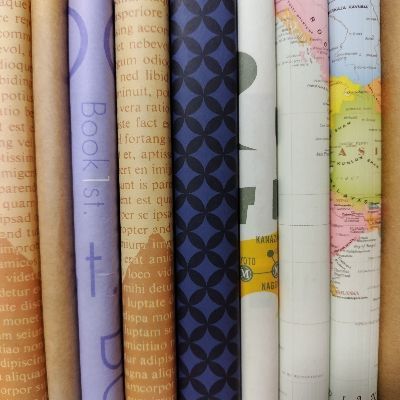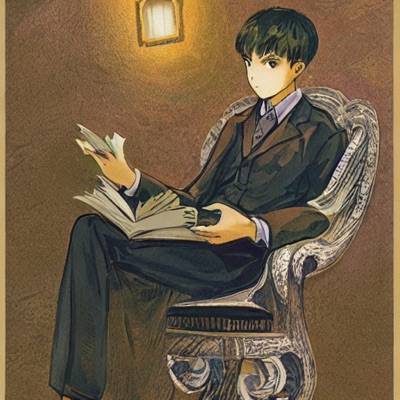プルーストとイカ

44件の記録
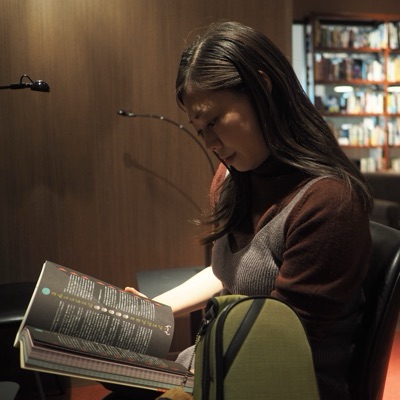 る@kaoruko2026年2月26日one of元彼が本アレルギーみたいな人で、それで「読書」「読字」に関する本をいくつか調べてたときに見つけたもののまだ読めてなかった本。脳実質のどこで何がなされてて、みたいな説明が専門的すぎて斜め読みしたところも多いけどめちゃくちゃ面白かった。最近自分が中毒のように本読みまくってる理由もなんとなくはっきりしたかな。慢性的にさみしいけど生身の人間と関わるの下手すぎるし本の中に逃げて自己との対話もしとくかーみたいな。でも結局人肌恋しさで本読んでるだけのことはあってこれ読んでる最中もどんどんさみしさが蓄積していって、ノンフィクションむり〜早く人間が出てくる小説読まないと死んじゃう〜ってなって、大急ぎで最後読み進めてしまった。世も末。
る@kaoruko2026年2月26日one of元彼が本アレルギーみたいな人で、それで「読書」「読字」に関する本をいくつか調べてたときに見つけたもののまだ読めてなかった本。脳実質のどこで何がなされてて、みたいな説明が専門的すぎて斜め読みしたところも多いけどめちゃくちゃ面白かった。最近自分が中毒のように本読みまくってる理由もなんとなくはっきりしたかな。慢性的にさみしいけど生身の人間と関わるの下手すぎるし本の中に逃げて自己との対話もしとくかーみたいな。でも結局人肌恋しさで本読んでるだけのことはあってこれ読んでる最中もどんどんさみしさが蓄積していって、ノンフィクションむり〜早く人間が出てくる小説読まないと死んじゃう〜ってなって、大急ぎで最後読み進めてしまった。世も末。

 Rika@ri_books_2026年1月28日読み終わった心に残る一節「読むことは私たちの人生を変える。そして、私たちの人生も読むことを変えるのである。」 (p.238) 「自分の思考を明確に表現しようと苦労したことがある者はみな、書くという純粋な努力によって自分の考えが形を変えていくことを、経験から知っている。」 (p.115)
Rika@ri_books_2026年1月28日読み終わった心に残る一節「読むことは私たちの人生を変える。そして、私たちの人生も読むことを変えるのである。」 (p.238) 「自分の思考を明確に表現しようと苦労したことがある者はみな、書くという純粋な努力によって自分の考えが形を変えていくことを、経験から知っている。」 (p.115)



 ふるえ@furu_furu2026年1月19日読んでるこれまで脳の仕組みとか、生物的な特徴について話を読み聞きするとどこか他人のような、自分に備わっているものなのに実感がなかったけれどなんとなく過去の体験や今読書している時の実感に追いつくような気がして、ようやっと脳を自分の中に感じる。この集中している具合が目の前の本で書かれていることなのかという実感。読書、文字を読むことについて人間はどのように認知して処理しているのか。文字を読むことについても興味深いけれど、言葉を生み出す、目の前にあるものや感情に言葉を当てはめる処理はどうなされるのかも気になる。それも文字を読む時や頭の中で思い浮かべるのと同じなのだろうか。
ふるえ@furu_furu2026年1月19日読んでるこれまで脳の仕組みとか、生物的な特徴について話を読み聞きするとどこか他人のような、自分に備わっているものなのに実感がなかったけれどなんとなく過去の体験や今読書している時の実感に追いつくような気がして、ようやっと脳を自分の中に感じる。この集中している具合が目の前の本で書かれていることなのかという実感。読書、文字を読むことについて人間はどのように認知して処理しているのか。文字を読むことについても興味深いけれど、言葉を生み出す、目の前にあるものや感情に言葉を当てはめる処理はどうなされるのかも気になる。それも文字を読む時や頭の中で思い浮かべるのと同じなのだろうか。



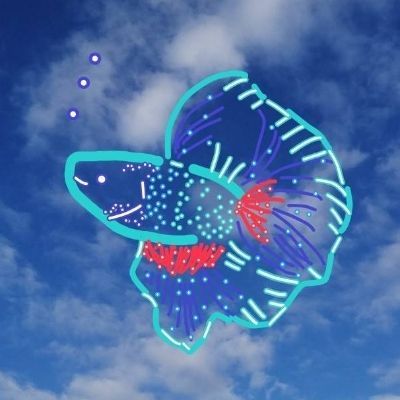
 めめん堂@memendo_tokachi2025年11月16日読み終わったインターネットの次の波、生成AIが、読字を脅かす(もしかすると再興させる)ものとして押し寄せてくるタイミングでこれを読んでよかった。読字メカニズムについての内容を、自分も読字メカニズムによって読んでいるという入れ子構造に少し酔う
めめん堂@memendo_tokachi2025年11月16日読み終わったインターネットの次の波、生成AIが、読字を脅かす(もしかすると再興させる)ものとして押し寄せてくるタイミングでこれを読んでよかった。読字メカニズムについての内容を、自分も読字メカニズムによって読んでいるという入れ子構造に少し酔う

 たま子@tama_co_co2025年6月6日読んでるYの文字のなんと絵のように美しいことか、なんと無限の意味を秘めていることか、あなたは気付いているだろうか? その木もY、二本の道がぶつかる所もY、注ぎあう二本の川、ロバの頭と雄牛の頭、脚付のグラス、茎の上に咲き誇るユリの花、両腕を差し伸べる物乞い、どれもYだ。人間が考え出したさまざまな文字の要素を成している万物に、同じことが言える。ーヴィクトル・ユーゴー この引用を読んですっかり満足したので、仕事にもどる。
たま子@tama_co_co2025年6月6日読んでるYの文字のなんと絵のように美しいことか、なんと無限の意味を秘めていることか、あなたは気付いているだろうか? その木もY、二本の道がぶつかる所もY、注ぎあう二本の川、ロバの頭と雄牛の頭、脚付のグラス、茎の上に咲き誇るユリの花、両腕を差し伸べる物乞い、どれもYだ。人間が考え出したさまざまな文字の要素を成している万物に、同じことが言える。ーヴィクトル・ユーゴー この引用を読んですっかり満足したので、仕事にもどる。









 いま@mayonakayom222025年5月18日読み終わった今井むつみさんの本で紹介されていた本、やっと読了。 子供が文字を読み始める時、脳ではどんな変化が起きているか、熟達した読み手の脳では何が起きているか。 今並行して読んでいる本は運動によりニューロンの結びつきの準備ができるといったことが書いてあるのでそれも繋がって面白い。 何を読むか、どのように読むかによって独自の熟達度は変わる、という部分で引用してあったヘルマン•ヘッセの言葉が印象的。 「もの思う人には、一人一人の詩人が綴る一行一行が、数年ごとに新しい違った顔を見せ、異なる響きを呼び覚ます•この読書という経験の素晴らしくも不可思議なこと、それは、目を肥やし、感受性を高め、連想力を豊かに持って読書することを学ぶほどに、あらゆる思考とあらゆる詩の独自性と個性と正確な限界とがはっきりと見えてくることだ。」 同じ本を読んでもその時々で自分の解釈は奥行きが出る、そこから思考が羽ばたく。 その再現性のなさが読書の楽しさであり尽きない面白さだと感じる。 著者自身の子がディスレクシアであるという当事者性からの二項対立ではない書き方や、全ての子供がもつ可能性を育みたいという姿勢も、今時よくある何歳までに〇〇、のような書き振りとは違っていて良かった。
いま@mayonakayom222025年5月18日読み終わった今井むつみさんの本で紹介されていた本、やっと読了。 子供が文字を読み始める時、脳ではどんな変化が起きているか、熟達した読み手の脳では何が起きているか。 今並行して読んでいる本は運動によりニューロンの結びつきの準備ができるといったことが書いてあるのでそれも繋がって面白い。 何を読むか、どのように読むかによって独自の熟達度は変わる、という部分で引用してあったヘルマン•ヘッセの言葉が印象的。 「もの思う人には、一人一人の詩人が綴る一行一行が、数年ごとに新しい違った顔を見せ、異なる響きを呼び覚ます•この読書という経験の素晴らしくも不可思議なこと、それは、目を肥やし、感受性を高め、連想力を豊かに持って読書することを学ぶほどに、あらゆる思考とあらゆる詩の独自性と個性と正確な限界とがはっきりと見えてくることだ。」 同じ本を読んでもその時々で自分の解釈は奥行きが出る、そこから思考が羽ばたく。 その再現性のなさが読書の楽しさであり尽きない面白さだと感じる。 著者自身の子がディスレクシアであるという当事者性からの二項対立ではない書き方や、全ての子供がもつ可能性を育みたいという姿勢も、今時よくある何歳までに〇〇、のような書き振りとは違っていて良かった。




 たま子@tama_co_co2025年5月7日読み始めた@ 自宅「文字を読むというのは、ニューロンの面から言っても、知能の面から言っても、まわり道をする行為であって、文章から目に直接飛び込んでくるメッセージ同様、読む者の推論と思考という気まぐれなまわり道によっても深みを増すものなのだ。」p34 読字は脳を変化させる最良の媒体なのだということが、生物学的・認知的側面に主眼を置いて語られていく。読書中の「思考の脱線」について、脳の発展という面から見れば、書かれた文章と無関係な思考に到達することこそが読書の目標なのだという話からはじまり、非常におもしろい。今まで感覚的に、脱線する読書ってたのしいと思っていたものが、どうやら脳的にもよいらしい。ほうほうなるほどと分かったり分からなかったりしながら読んでいる。
たま子@tama_co_co2025年5月7日読み始めた@ 自宅「文字を読むというのは、ニューロンの面から言っても、知能の面から言っても、まわり道をする行為であって、文章から目に直接飛び込んでくるメッセージ同様、読む者の推論と思考という気まぐれなまわり道によっても深みを増すものなのだ。」p34 読字は脳を変化させる最良の媒体なのだということが、生物学的・認知的側面に主眼を置いて語られていく。読書中の「思考の脱線」について、脳の発展という面から見れば、書かれた文章と無関係な思考に到達することこそが読書の目標なのだという話からはじまり、非常におもしろい。今まで感覚的に、脱線する読書ってたのしいと思っていたものが、どうやら脳的にもよいらしい。ほうほうなるほどと分かったり分からなかったりしながら読んでいる。









 小鳥美月@k_d_m_book2025年2月25日気になる『あの本、読みました?』で一色さゆりさんが紹介していた本。読字に関する最良図書として「マーゴット・マレク賞」を受賞した言語好きには堪らない1冊だそう。
小鳥美月@k_d_m_book2025年2月25日気になる『あの本、読みました?』で一色さゆりさんが紹介していた本。読字に関する最良図書として「マーゴット・マレク賞」を受賞した言語好きには堪らない1冊だそう。
 Bruno@macchoca2023年11月27日読み終わった読むとは、思考の最も繊細な創造行為。 文字を追うたび、僕らの脳は新たな回路をつくり、 他者の意識を借りて未知の世界を歩くことができる。 その過程で、読むことは単なる情報処理ではなく、 「考える」という人間の本質に深く結びついた 営みであることに気づかされる。 テクノロジーが思考を代替しつつある今こそ、 時間をかけて、 読むという行為がもたらす“内的対話”を取り戻さないといけない。 脳は文字を読むことで時間を生み、思索を深める。 この「読む脳」の進化こそ、 人間が人間であり続けるための道なのかもしれない。
Bruno@macchoca2023年11月27日読み終わった読むとは、思考の最も繊細な創造行為。 文字を追うたび、僕らの脳は新たな回路をつくり、 他者の意識を借りて未知の世界を歩くことができる。 その過程で、読むことは単なる情報処理ではなく、 「考える」という人間の本質に深く結びついた 営みであることに気づかされる。 テクノロジーが思考を代替しつつある今こそ、 時間をかけて、 読むという行為がもたらす“内的対話”を取り戻さないといけない。 脳は文字を読むことで時間を生み、思索を深める。 この「読む脳」の進化こそ、 人間が人間であり続けるための道なのかもしれない。



 彼らは読みつづけた@findareading1900年1月1日かつて読んだ*読書で見つけた「読書(する人)」* 《読むことは私たちの人生を変える。そして、私たちの人生も読むことを変えるのである。》 — メアリアン・ウルフ著/小松淳子訳『プルーストとイカ―読書は脳をどのように変えるのか?―』(2017年7月第8刷、インターシフト)
彼らは読みつづけた@findareading1900年1月1日かつて読んだ*読書で見つけた「読書(する人)」* 《読むことは私たちの人生を変える。そして、私たちの人生も読むことを変えるのである。》 — メアリアン・ウルフ著/小松淳子訳『プルーストとイカ―読書は脳をどのように変えるのか?―』(2017年7月第8刷、インターシフト)