

ばるーん
@ballo____on
- 2026年2月21日
 小銭をかぞえる (文春文庫)西村賢太読んでる
小銭をかぞえる (文春文庫)西村賢太読んでる - 2026年2月20日
 見るまえに跳べ大江健三郎読んでる
見るまえに跳べ大江健三郎読んでる - 2026年2月18日
- 2026年2月17日
- 2026年2月15日
 共に明るい井戸川射子読んでる「池の中の」も素晴らしかった。 全編において自然と人工が深く関わっている。細かな認識がやはり光っているのに、小説全体としてすごく面白い。 本作はある出来事をきっかけに初めましての雑談からは想像だにしなかったものが語り出され、それが誰の傷をも形あるものに閉じ込めてしまわない実感を伴い共振する。内と外、有機物と無機物、登場人物と読者の傷や空洞が交換される。
共に明るい井戸川射子読んでる「池の中の」も素晴らしかった。 全編において自然と人工が深く関わっている。細かな認識がやはり光っているのに、小説全体としてすごく面白い。 本作はある出来事をきっかけに初めましての雑談からは想像だにしなかったものが語り出され、それが誰の傷をも形あるものに閉じ込めてしまわない実感を伴い共振する。内と外、有機物と無機物、登場人物と読者の傷や空洞が交換される。 - 2026年2月14日
 共に明るい井戸川射子読んでる「素晴らしく幸福で豊かな」を読んだ。 全編に漂う否定感が印象深い。「ナミビアの砂漠」を想起した。日常や人間関係を描く小説には必須の細部があまりにも光りすぎているし、それが小説の完成度を押し上げている。常識も狂気もユーモアもアイロニーをかきまぜて動物の生と死の周辺が描かれていた。
共に明るい井戸川射子読んでる「素晴らしく幸福で豊かな」を読んだ。 全編に漂う否定感が印象深い。「ナミビアの砂漠」を想起した。日常や人間関係を描く小説には必須の細部があまりにも光りすぎているし、それが小説の完成度を押し上げている。常識も狂気もユーモアもアイロニーをかきまぜて動物の生と死の周辺が描かれていた。 - 2026年2月8日
- 2026年2月7日
 匿名芸術家青木淳悟読み終わった「四十日と四十夜のメルヘン」を読んだ。 小説の内容(出来事)それ自体がメタ的でかつ、常に小説の書き方、自己言及に満ちた小説だと思った。 めちゃくちゃ面白かったけど、終盤近くで完全に振り落とされたから、もう一度読む、それをえんえん繰り返すような小説だし、そんな内容だとさえ言える。町屋さんの批評を楽しみに読む。
匿名芸術家青木淳悟読み終わった「四十日と四十夜のメルヘン」を読んだ。 小説の内容(出来事)それ自体がメタ的でかつ、常に小説の書き方、自己言及に満ちた小説だと思った。 めちゃくちゃ面白かったけど、終盤近くで完全に振り落とされたから、もう一度読む、それをえんえん繰り返すような小説だし、そんな内容だとさえ言える。町屋さんの批評を楽しみに読む。 - 2026年2月5日
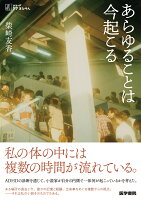 あらゆることは今起こる柴崎友香読み終わった柴崎作品における身体性・世界認識からくる文章が好きで、でもそれとわかちがたく結びついているであろう小説の技術について考えたくなった。 短編「糸」の読解にも資する箇所もあったようなも気もし嬉しかった。まだまだ読んでない作品があるから読んでいきたい。
あらゆることは今起こる柴崎友香読み終わった柴崎作品における身体性・世界認識からくる文章が好きで、でもそれとわかちがたく結びついているであろう小説の技術について考えたくなった。 短編「糸」の読解にも資する箇所もあったようなも気もし嬉しかった。まだまだ読んでない作品があるから読んでいきたい。 - 2026年1月27日
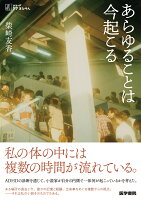 あらゆることは今起こる柴崎友香読み始めた
あらゆることは今起こる柴崎友香読み始めた - 2026年1月27日
 共に明るい井戸川射子読んでる「野鳥園」もよかった。二つの家族の子と母の雑談の一回性(関係は続くけれど)。エレクトーン。ごく小さな、ささやかな慎み深い群れの話だと思った。良い意味の人工、仮の居場所的な。
共に明るい井戸川射子読んでる「野鳥園」もよかった。二つの家族の子と母の雑談の一回性(関係は続くけれど)。エレクトーン。ごく小さな、ささやかな慎み深い群れの話だと思った。良い意味の人工、仮の居場所的な。 - 2026年1月25日
 共に明るい井戸川射子読んでる読み始めた表題を読んだ。 「私今からつらい話をしますね」と早朝のバスの車内に向かって一方的に語り出す女と同乗した複数人のそれぞれの認識が描かれる。 うつ伏せにして圧迫しながらでないと溢れ出すもの、その語りがバスの移動とともに、空間の内外の風景、カーテンと身体の境目を共にしていく。 境目から産まれた息子の失った指の境目の「遠目からだと、少し歪んで膨らむ直線」――欠を補うそれぞれの生が持つ境目は、「共に(痛くて)明るい」。 トンネルの端に置き去りにされている大きなもの。風で花が枝から逃げようとする。虹色のカーテン。併走する赤紫色の軽自動車。イオン……。 小説全体のトーンが、溢れて出そうなものを抑えて、それでもなお滲む何かで貫かれている。 一方的な他者の痛みに風景のように寄り添えるか。というお話だったと思う。 最後にすごい一文。 「座席のすみずみまでとはいかないが、くい込むように陽が当たりみんな、何て明るい。」
共に明るい井戸川射子読んでる読み始めた表題を読んだ。 「私今からつらい話をしますね」と早朝のバスの車内に向かって一方的に語り出す女と同乗した複数人のそれぞれの認識が描かれる。 うつ伏せにして圧迫しながらでないと溢れ出すもの、その語りがバスの移動とともに、空間の内外の風景、カーテンと身体の境目を共にしていく。 境目から産まれた息子の失った指の境目の「遠目からだと、少し歪んで膨らむ直線」――欠を補うそれぞれの生が持つ境目は、「共に(痛くて)明るい」。 トンネルの端に置き去りにされている大きなもの。風で花が枝から逃げようとする。虹色のカーテン。併走する赤紫色の軽自動車。イオン……。 小説全体のトーンが、溢れて出そうなものを抑えて、それでもなお滲む何かで貫かれている。 一方的な他者の痛みに風景のように寄り添えるか。というお話だったと思う。 最後にすごい一文。 「座席のすみずみまでとはいかないが、くい込むように陽が当たりみんな、何て明るい。」 - 2026年1月25日
- 2026年1月25日
- 2026年1月18日
- 2026年1月18日
 自由対談中村文則読んでる藤沢周さんが対談の最後に「書くとは世界と刺し違えることだろう」って言ってて、らしすぎて唸った。 話題に出た『第二列の男』『武曲』、中村さんの『あなたが消えた夜に』も読みたい。 あと、対談冒頭にちらっと松浦寿輝さんの作品名出てくるけど、「虹」じゃなくて「虻」が正しくない?
自由対談中村文則読んでる藤沢周さんが対談の最後に「書くとは世界と刺し違えることだろう」って言ってて、らしすぎて唸った。 話題に出た『第二列の男』『武曲』、中村さんの『あなたが消えた夜に』も読みたい。 あと、対談冒頭にちらっと松浦寿輝さんの作品名出てくるけど、「虹」じゃなくて「虻」が正しくない? - 2026年1月15日
- 2026年1月11日
- 2026年1月11日
- 2026年1月8日
 YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み終わった全編とんでもない覚悟で書かれていた。 長岡は自分の主義主張が非現実だってわかるけど!けど…!みたいな人だと思った。前半の人物像が、見事に逸脱していく過程で、だんだん自分の正しさを、どこかで絶対的に「正しい」と信じきってる感が露呈していく。 というか、長岡だけじゃないけど、前半部分にあった価値判断の基準があれば己を否応なく疑ってしまえそうな気もするのに!とか思うけど、それはずらされる。各人物にあるずらしが小説としての面白さになっていた。 この小説に求めることじゃないけど、本当の意味でのディスコミュニケーションがなさすぎる。わかりあえないことがわかりあえすぎている。主張のある/なしをわかりあえすぎている。みんな対話が不自然なぐらい上手すぎる。
YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み終わった全編とんでもない覚悟で書かれていた。 長岡は自分の主義主張が非現実だってわかるけど!けど…!みたいな人だと思った。前半の人物像が、見事に逸脱していく過程で、だんだん自分の正しさを、どこかで絶対的に「正しい」と信じきってる感が露呈していく。 というか、長岡だけじゃないけど、前半部分にあった価値判断の基準があれば己を否応なく疑ってしまえそうな気もするのに!とか思うけど、それはずらされる。各人物にあるずらしが小説としての面白さになっていた。 この小説に求めることじゃないけど、本当の意味でのディスコミュニケーションがなさすぎる。わかりあえないことがわかりあえすぎている。主張のある/なしをわかりあえすぎている。みんな対話が不自然なぐらい上手すぎる。
読み込み中...





