

ミオReads
@hanamio03
家とスマホに無限の積ん読を築きつつ図書館通いの円環に囚われしオタク。
- 2026年1月22日
 虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった大寒波の雪に閉じ込められている間に読んだ。 わたしは平均並みには体力がある女だと思うが、近親者に虚弱がいるので何か参考にならないだろうかと思ったのが手を伸ばしたきっかけだ。実際「眼鏡をかける」「体力をつけるための体力をつける準備をする」などは実に参考になった。 しかし筆者も作中で言っていたように、程度は違えど加齢による体力低下という面では分かりあえる気がした。 『創作や表現における「才能が枯れる」「感性が鈍る」などと言われる現象も、加齢に伴う体力低下が最大の原因なのではないかと思う。単純に脳のパフォーマンスも下がるので、インプット・アウトプットともに効率も質も下がり、結果的に才能や感性と呼ばれるものが衰えたと感じられるのではないか。』 膝を打ち、じゃあどうするかというと、結局筋トレしかないのである。希望の話だ。 すごい本だったと思う。試行錯誤を経たノウハウに終始しない。自己探求と自己分析。自分はどう生き、どうありたいのか。自分の欲求を逸らさず見つめ、残酷なまでにソリッドな取捨選択をする。人生の話だ。 著者が己と己のいきかたを受け入れるまでの孤独が、あまりにもせつない。 『私の普通じゃなさに私自身も周りも困っていて、なぜ喋らないのかと散々問いただしておきながら、障害だと言うと慌てて私の普通な部分を探して強調し、普通じゃない部分は都合良く個性として扱おうとする。』 分かって欲しい。分かって欲しい。苦しみや存在を分かって欲しい。切実すぎる原初の渇望。人がバズってよかったと、ほぼ初めて思った気がする。孤独を理解してくれる人がいたのだから。 人は自分しか生きられない。理解は他人からしか得られない。アンビバレントな、けれどとても素直に届く、淡々とした語り口の、人生の話。よい本でした。
虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった大寒波の雪に閉じ込められている間に読んだ。 わたしは平均並みには体力がある女だと思うが、近親者に虚弱がいるので何か参考にならないだろうかと思ったのが手を伸ばしたきっかけだ。実際「眼鏡をかける」「体力をつけるための体力をつける準備をする」などは実に参考になった。 しかし筆者も作中で言っていたように、程度は違えど加齢による体力低下という面では分かりあえる気がした。 『創作や表現における「才能が枯れる」「感性が鈍る」などと言われる現象も、加齢に伴う体力低下が最大の原因なのではないかと思う。単純に脳のパフォーマンスも下がるので、インプット・アウトプットともに効率も質も下がり、結果的に才能や感性と呼ばれるものが衰えたと感じられるのではないか。』 膝を打ち、じゃあどうするかというと、結局筋トレしかないのである。希望の話だ。 すごい本だったと思う。試行錯誤を経たノウハウに終始しない。自己探求と自己分析。自分はどう生き、どうありたいのか。自分の欲求を逸らさず見つめ、残酷なまでにソリッドな取捨選択をする。人生の話だ。 著者が己と己のいきかたを受け入れるまでの孤独が、あまりにもせつない。 『私の普通じゃなさに私自身も周りも困っていて、なぜ喋らないのかと散々問いただしておきながら、障害だと言うと慌てて私の普通な部分を探して強調し、普通じゃない部分は都合良く個性として扱おうとする。』 分かって欲しい。分かって欲しい。苦しみや存在を分かって欲しい。切実すぎる原初の渇望。人がバズってよかったと、ほぼ初めて思った気がする。孤独を理解してくれる人がいたのだから。 人は自分しか生きられない。理解は他人からしか得られない。アンビバレントな、けれどとても素直に届く、淡々とした語り口の、人生の話。よい本でした。 - 2025年12月20日
 世界99 下村田沙耶香読み終わった世界が壊れ(そしてリセットされ)こっちの世界と全然違うように見え始めたこと、空子の傍から男性性が減ったこと(そしてそれは空子が年を重ね『賞味期限』を過ぎたから)、主にその2点で上巻より怖さが減った?慣れた?こっちが麻痺してきた?読み手さえ記憶や感覚をリセットされてしまった??? けど「白藤さんって、差別しないためならなんでもするんだ」とか「ピョコルンじゃなくてもセックスしてもらえるぐらいかわいい」とか、時々指先まで悴むような怖さの手触りに目が覚める。なのに、繰り返し、本当に繰り返し同じ事を何度も描写されて(奏の現状描写なんか特に顕著)また感覚を麻痺させられる。 世界の自殺、自我の喪失、人類補完計画…それっぽい言葉はいくらでもあるけど、でもこれはやはり「怖さ」のエンタメだなと思う。あー怖い、怖い怖い、この怖さを「怖い」と思ったまま、怖さを楽しもう、楽しめる側でいよう、そういう世界であり続けるように勤めよう…………でもそれもまた、白藤さんの末路なんだろうか。 すごい話だった。村田沙耶香さんの本、初めてだったけど、他のも読もうと思います。絶望して楽しみたい。
世界99 下村田沙耶香読み終わった世界が壊れ(そしてリセットされ)こっちの世界と全然違うように見え始めたこと、空子の傍から男性性が減ったこと(そしてそれは空子が年を重ね『賞味期限』を過ぎたから)、主にその2点で上巻より怖さが減った?慣れた?こっちが麻痺してきた?読み手さえ記憶や感覚をリセットされてしまった??? けど「白藤さんって、差別しないためならなんでもするんだ」とか「ピョコルンじゃなくてもセックスしてもらえるぐらいかわいい」とか、時々指先まで悴むような怖さの手触りに目が覚める。なのに、繰り返し、本当に繰り返し同じ事を何度も描写されて(奏の現状描写なんか特に顕著)また感覚を麻痺させられる。 世界の自殺、自我の喪失、人類補完計画…それっぽい言葉はいくらでもあるけど、でもこれはやはり「怖さ」のエンタメだなと思う。あー怖い、怖い怖い、この怖さを「怖い」と思ったまま、怖さを楽しもう、楽しめる側でいよう、そういう世界であり続けるように勤めよう…………でもそれもまた、白藤さんの末路なんだろうか。 すごい話だった。村田沙耶香さんの本、初めてだったけど、他のも読もうと思います。絶望して楽しみたい。 - 2025年11月29日
 皇后の碧阿部智里読み終わったファンタジーの取っつきにくさは、まるで違う世界体系に突然放り込まれることだと思う。理解できない謎の世界の話がいきなり始まって、何がなんだか分からないまま、こっちに一切おもねることなく、向こうの常識のみで話が進んでいく。おかげで序盤は3回ほど寝落ちしたのだが、一度世界のとば口を掴むと、こっちの世界のことなんか全部忘れて没入していけるのが気持ちがいい。知性と世界の豊かな広がりを感じさせてくれる。 決して悪人ではなく、聡明で慈悲深い賢人の「見る世界」が違うことによるいかんともしがたい相互断絶と、それでも生きていくしかない諦念、けれどその諦念は賢さや広い視野、平たく生きていこうという不断の信念でしかたどり着けない境地である…みたいなことが、この筆者の真髄じゃないかと思う。精霊や宝石、後宮の華々しさ、煌びやかさをこれでもかと描写しながら(宝石の輝きを飲むという美しさよ!)根底にある怒りみたいなものがブレないのとか。 続くのかな?というより続かないともったいないなと思う。書かれていない物語があまりに多すぎる。そういう「書かれていない物語」はそのままでもいいのかもしれないけど、八咫烏シリーズを知ってる身としては、絶っっっっっ対、面白くすさまじく広がっていく確信があるから、よろしくね、という気持ち。特設サイトもイラストも気合い入りまくってたから期待してていいんだと思うけど〜。 11月、忙しすぎて何も読めずに終わるかと思った。よかった。
皇后の碧阿部智里読み終わったファンタジーの取っつきにくさは、まるで違う世界体系に突然放り込まれることだと思う。理解できない謎の世界の話がいきなり始まって、何がなんだか分からないまま、こっちに一切おもねることなく、向こうの常識のみで話が進んでいく。おかげで序盤は3回ほど寝落ちしたのだが、一度世界のとば口を掴むと、こっちの世界のことなんか全部忘れて没入していけるのが気持ちがいい。知性と世界の豊かな広がりを感じさせてくれる。 決して悪人ではなく、聡明で慈悲深い賢人の「見る世界」が違うことによるいかんともしがたい相互断絶と、それでも生きていくしかない諦念、けれどその諦念は賢さや広い視野、平たく生きていこうという不断の信念でしかたどり着けない境地である…みたいなことが、この筆者の真髄じゃないかと思う。精霊や宝石、後宮の華々しさ、煌びやかさをこれでもかと描写しながら(宝石の輝きを飲むという美しさよ!)根底にある怒りみたいなものがブレないのとか。 続くのかな?というより続かないともったいないなと思う。書かれていない物語があまりに多すぎる。そういう「書かれていない物語」はそのままでもいいのかもしれないけど、八咫烏シリーズを知ってる身としては、絶っっっっっ対、面白くすさまじく広がっていく確信があるから、よろしくね、という気持ち。特設サイトもイラストも気合い入りまくってたから期待してていいんだと思うけど〜。 11月、忙しすぎて何も読めずに終わるかと思った。よかった。 - 2025年10月14日
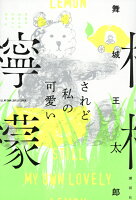 されど私の可愛い檸檬舞城王太郎読み終わった家族の話を思うとき、いつかマツコ・デラックスがテレビで言っていた「家族だからこそ言えないし、どうにもできないことってあるじゃない?」というような言葉を思い出す。あれほど賢く、世界の真理を見通しては、的確に言葉を紡いでいるような人にも支配できないものが家族なんだな…と空恐ろしくなるのだが、その言葉を読んでる間中、何度となく思い出した。 これが家族じゃなかったら、多分もっと早く、もっと手短に、もっと鋭く終わりにできた。家族だからできない。家族だからしない。家制度なんてクソだなと思うのに、結局家に捕らわれてることにむしゃくしゃしたり、むしゃくしゃしながらも本気で恐れて読んだ。戦慄。まさしく。姉が怒りによる目に見えないし知覚しにくい支配を始めること、血の繋がらぬ義兄には何もたどり着けていないこと、その絶望と安堵。義母の無神経過ぎる態度や言葉、それに対抗しようとする己の浅はかさと奮闘。豹変した妻と怯える娘は何もかもが怖くて泣きそうになる。話のまるで通じない異星人のような男。次々に壊されていくのに本人は気付けず知覚できず、結局できた家族のせいで苦手な決断を下せるようになる。怖かった。ほんとに怪談のようだった。 「君と一緒にいるとまともになれる気がする」 「けど、私、あんたのそういう問題をどうにかするたの道具とかじゃないんだけど?」 これに心底納得できるのに言動が「正しく」出力されない。でも「正しさ」って? コンプラに引っかかる? 引っかかりはする。けどだけど、そういうことじゃない。 ああこれが、どうにもできないことかもしれない、と思って、また一つ身震いする。
されど私の可愛い檸檬舞城王太郎読み終わった家族の話を思うとき、いつかマツコ・デラックスがテレビで言っていた「家族だからこそ言えないし、どうにもできないことってあるじゃない?」というような言葉を思い出す。あれほど賢く、世界の真理を見通しては、的確に言葉を紡いでいるような人にも支配できないものが家族なんだな…と空恐ろしくなるのだが、その言葉を読んでる間中、何度となく思い出した。 これが家族じゃなかったら、多分もっと早く、もっと手短に、もっと鋭く終わりにできた。家族だからできない。家族だからしない。家制度なんてクソだなと思うのに、結局家に捕らわれてることにむしゃくしゃしたり、むしゃくしゃしながらも本気で恐れて読んだ。戦慄。まさしく。姉が怒りによる目に見えないし知覚しにくい支配を始めること、血の繋がらぬ義兄には何もたどり着けていないこと、その絶望と安堵。義母の無神経過ぎる態度や言葉、それに対抗しようとする己の浅はかさと奮闘。豹変した妻と怯える娘は何もかもが怖くて泣きそうになる。話のまるで通じない異星人のような男。次々に壊されていくのに本人は気付けず知覚できず、結局できた家族のせいで苦手な決断を下せるようになる。怖かった。ほんとに怪談のようだった。 「君と一緒にいるとまともになれる気がする」 「けど、私、あんたのそういう問題をどうにかするたの道具とかじゃないんだけど?」 これに心底納得できるのに言動が「正しく」出力されない。でも「正しさ」って? コンプラに引っかかる? 引っかかりはする。けどだけど、そういうことじゃない。 ああこれが、どうにもできないことかもしれない、と思って、また一つ身震いする。 - 2025年10月13日
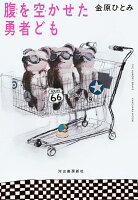 腹を空かせた勇者ども金原ひとみ読み終わったぐわーーーーーーー!という、言葉にならない衝動がドコドコ湧き上がってきてそのエネルギーに心臓を三倍速で脈打たされるみたいな、もうめちゃくちゃに面白かった。子供だ。子供だけど、こんなにありのままに子供なの、その子供の心が文章に、物語になってることにずっと痺れていた。 「自分の母親がこんなママだったらマジで面倒臭くて耐えられない」「自分の母親がこんなママだったら成立していた対話が唸るほどあったんだろう」とママが出てくるたび子供の心で思ったし(そしてご飯がマジでおいしそうすぎる)、「自分の父親がこんなパパだったら感覚の遠さや共感のなさに憤りと諦めがあっただろう」「自分の父親がこんなパパだったらトンチンカンだろうとやっぱり対話はあったし支配はなかったんだろう」と子供の心で思った。 もういい大人なので物語に大人と子供が出てきたら9割大人に感情移入しちゃう今、ずっと子供の心で楽しめたり自由を求めたりできたのが楽しかったなぁ。だってあの質感。「パパはわたしが今小学生って言っても信じそうだけど、ママはわたしのブラのサイズを把握してるし生理周期もなんとなく把握してる」という差違の生々しさに膝を打ちすぎて本当に気持ちがよかった。ああ面白かった。面白かったな〜!!!!
腹を空かせた勇者ども金原ひとみ読み終わったぐわーーーーーーー!という、言葉にならない衝動がドコドコ湧き上がってきてそのエネルギーに心臓を三倍速で脈打たされるみたいな、もうめちゃくちゃに面白かった。子供だ。子供だけど、こんなにありのままに子供なの、その子供の心が文章に、物語になってることにずっと痺れていた。 「自分の母親がこんなママだったらマジで面倒臭くて耐えられない」「自分の母親がこんなママだったら成立していた対話が唸るほどあったんだろう」とママが出てくるたび子供の心で思ったし(そしてご飯がマジでおいしそうすぎる)、「自分の父親がこんなパパだったら感覚の遠さや共感のなさに憤りと諦めがあっただろう」「自分の父親がこんなパパだったらトンチンカンだろうとやっぱり対話はあったし支配はなかったんだろう」と子供の心で思った。 もういい大人なので物語に大人と子供が出てきたら9割大人に感情移入しちゃう今、ずっと子供の心で楽しめたり自由を求めたりできたのが楽しかったなぁ。だってあの質感。「パパはわたしが今小学生って言っても信じそうだけど、ママはわたしのブラのサイズを把握してるし生理周期もなんとなく把握してる」という差違の生々しさに膝を打ちすぎて本当に気持ちがよかった。ああ面白かった。面白かったな〜!!!! - 2025年10月9日
 モモミヒャエル・エンデ,Michael Ende,大島かおり読み終わった子供時代に読まなかった児童文学について、「子どもの頃に読みたかった」と「大人になった今だからこそ理解できる話だ」が感想の二大巨頭になりがちで、「モモ」を大人になった今初めて読んでいたわたしもご多分に漏れず思ったのだが、最後まで夢中で読んだ結論として「読書の価値は理解力の多寡ではかるものでもないし、面白い物語はいつ読んでも面白い」である。あ〜面白かった。 風刺は現代にも突き刺さるし、今確かに考えるべき・立ち止まるべきこともたくさんあった。心に刻んでおきたい金言もたくさんあった。 でもわたしは「時間どろぼうの灰色の男たち超怖いよ〜〜〜〜」「チョコレートとはちみつのパンわたしも食べたい〜〜〜」「モモみたいにジジやベッポや子供たちや大人たちに好かれたいし、おまえ一人なんだよと世界の命運をたくされてみたい〜〜〜〜」という物語への耽溺でもって楽しみたいな〜なんて思っちゃう。大人の中にも子どもはずっといて、その子どもはいつ児童文学に触れたって子どもの気持ちで楽しんでくれるんだから、感受性も捨てたもんじゃないね。 その上で大人のわたしは、どうしても覚えておきたいセリフがあった。 「あたしの友だちも?ほんとうにそんなことをしてもらいたかったのかしら?」 「してもらいたいかどうかなんて、問題にされやしなかったさ。」 「子どもには、そういうことに発言権はないんだ」 絶対に、忘れちゃいけない。
モモミヒャエル・エンデ,Michael Ende,大島かおり読み終わった子供時代に読まなかった児童文学について、「子どもの頃に読みたかった」と「大人になった今だからこそ理解できる話だ」が感想の二大巨頭になりがちで、「モモ」を大人になった今初めて読んでいたわたしもご多分に漏れず思ったのだが、最後まで夢中で読んだ結論として「読書の価値は理解力の多寡ではかるものでもないし、面白い物語はいつ読んでも面白い」である。あ〜面白かった。 風刺は現代にも突き刺さるし、今確かに考えるべき・立ち止まるべきこともたくさんあった。心に刻んでおきたい金言もたくさんあった。 でもわたしは「時間どろぼうの灰色の男たち超怖いよ〜〜〜〜」「チョコレートとはちみつのパンわたしも食べたい〜〜〜」「モモみたいにジジやベッポや子供たちや大人たちに好かれたいし、おまえ一人なんだよと世界の命運をたくされてみたい〜〜〜〜」という物語への耽溺でもって楽しみたいな〜なんて思っちゃう。大人の中にも子どもはずっといて、その子どもはいつ児童文学に触れたって子どもの気持ちで楽しんでくれるんだから、感受性も捨てたもんじゃないね。 その上で大人のわたしは、どうしても覚えておきたいセリフがあった。 「あたしの友だちも?ほんとうにそんなことをしてもらいたかったのかしら?」 「してもらいたいかどうかなんて、問題にされやしなかったさ。」 「子どもには、そういうことに発言権はないんだ」 絶対に、忘れちゃいけない。 - 2025年10月8日
 こどもを野に放て! AI時代に活きる知性の育て方中村桂子,春山慶彦,池澤夏樹,養老孟司読み終わったYAMAP創業者の春山さんと、名だたる著名人との対談。「こどもを」と銘打ってあるし「『赤ちゃん、かわいいな』の目を授けられている」からも分かるように子どもを自然に、山に触れさせて、知の体験をしよう、とは書かれているんだけど、基本的には人間の話なので、大人もきちんと対象です。 「ああすれば、こうなる」方式 「勉強すればなんでも頭に入ると思い込みすぎ」 「思い通りにならないことや余白と向き合う」 「あらゆることに『予測と制御』が可能だと思ってる」 ちょっと自分に必要かもしれない、この考えをやめたい・抜け出したいけどどうしたもんか? と最近思っていたことが、賢人たちの知性と言葉でこれでもかと語られていた。こういう巡り合わせは、見つけたい!と思っても見つかるものではなく、いろんな分野に枝葉を伸ばして遠回りして、無駄なこともして、それでたまたま巡り合えたり合えなかったりする、まさしくこの本に書かれていることだなと感じる。 自分を幸せにするには世界が幸せになってないと無理だよ。引用は宮沢賢治にも至るのだが、その精神そのままに、YAMAPとヤマレコが共同で、ユーザーたちと集めた登山道のデータを国土地理院に還元した話は、すごく胸打たれた。池澤夏樹が「そのデータを彼らは受け取りましたか?」と尋ねた思慮や、結論を聞いて褒めてくれたことを含めて。 あとは「歩くことって気持ちいい」という話。二足歩行は脳を使う運動であり(転びやすいから)、人間の弱さゆえに進歩した形(両手に物を持ち、遠くまで移動できるように)という原初の話なんかも随所にちりばめられながらも、 「(山登りの)最初の2.3時間は身体の中にいわば灰汁がたまってる感じなので、すごくキツいんですよ。それを越えると、だんだん楽しくなってきます」 という根源の喜びの話もあって、うんうん、とにっこりしながら読んだ。楽しいね。歩きたいね。 追記というか「いろんな分野に枝葉を伸ばしてたまたまつながる」の話につながるように、ちょうど今、ミヒャエル・エンデの「モモ」も一緒に借りて来ていた。対談の中で出てきていたのだ。面白い〜と思いながら、次は「モモ」を読もうと思う。
こどもを野に放て! AI時代に活きる知性の育て方中村桂子,春山慶彦,池澤夏樹,養老孟司読み終わったYAMAP創業者の春山さんと、名だたる著名人との対談。「こどもを」と銘打ってあるし「『赤ちゃん、かわいいな』の目を授けられている」からも分かるように子どもを自然に、山に触れさせて、知の体験をしよう、とは書かれているんだけど、基本的には人間の話なので、大人もきちんと対象です。 「ああすれば、こうなる」方式 「勉強すればなんでも頭に入ると思い込みすぎ」 「思い通りにならないことや余白と向き合う」 「あらゆることに『予測と制御』が可能だと思ってる」 ちょっと自分に必要かもしれない、この考えをやめたい・抜け出したいけどどうしたもんか? と最近思っていたことが、賢人たちの知性と言葉でこれでもかと語られていた。こういう巡り合わせは、見つけたい!と思っても見つかるものではなく、いろんな分野に枝葉を伸ばして遠回りして、無駄なこともして、それでたまたま巡り合えたり合えなかったりする、まさしくこの本に書かれていることだなと感じる。 自分を幸せにするには世界が幸せになってないと無理だよ。引用は宮沢賢治にも至るのだが、その精神そのままに、YAMAPとヤマレコが共同で、ユーザーたちと集めた登山道のデータを国土地理院に還元した話は、すごく胸打たれた。池澤夏樹が「そのデータを彼らは受け取りましたか?」と尋ねた思慮や、結論を聞いて褒めてくれたことを含めて。 あとは「歩くことって気持ちいい」という話。二足歩行は脳を使う運動であり(転びやすいから)、人間の弱さゆえに進歩した形(両手に物を持ち、遠くまで移動できるように)という原初の話なんかも随所にちりばめられながらも、 「(山登りの)最初の2.3時間は身体の中にいわば灰汁がたまってる感じなので、すごくキツいんですよ。それを越えると、だんだん楽しくなってきます」 という根源の喜びの話もあって、うんうん、とにっこりしながら読んだ。楽しいね。歩きたいね。 追記というか「いろんな分野に枝葉を伸ばしてたまたまつながる」の話につながるように、ちょうど今、ミヒャエル・エンデの「モモ」も一緒に借りて来ていた。対談の中で出てきていたのだ。面白い〜と思いながら、次は「モモ」を読もうと思う。 - 2025年10月4日
- 2025年10月3日
- 2025年10月3日
- 2025年9月30日
 読み終わった「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」知りたくて借りたのに、読む時間を捻出できないまま返却期限が来てしまう…きっとそういう姿勢がだめだということが書いてあるんだろうな…とメソメソしていたら、すでに読んだ友人から「多分、割と結論として真逆のことが書いてある」と教えられた。 なので返却期限当日にざっと読んだ。読めるじゃん!と思いながら。そして面白い〜!と満喫しながら。 「せっかく読むんだから読書ノートも書きながら、一文も無駄にせず知識として入手したい」なんていう姿勢でいるから読む始められんのだな、まあとりあえず読まずに返すより読んで返した方が得だろ、みたいな思考に返却当日なったため読めたのだが、まさにそういうことが書いてあって半笑い、のち、軽く「にわか」で読んでよかったなと思った。 学びたいし賢くもなりたいし人生を楽に生きたいし社会を切り離して自分の世界に生きたくもあるけど、そういう気持ちは腹の底にいるけど、そういうの「まあとりあえず読むか」からの「わ〜面白い〜」をやってるときは見えなくなってるし「わ〜面白い〜」はほんとうに気持ちがいい。 返却期限にヒイヒイしちゃうけど、また何か図書館で借りてこよ。ここも、円本並べて満足するような記録の仕方じゃなくて、もっとカジュアルに使いたいね。
読み終わった「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」知りたくて借りたのに、読む時間を捻出できないまま返却期限が来てしまう…きっとそういう姿勢がだめだということが書いてあるんだろうな…とメソメソしていたら、すでに読んだ友人から「多分、割と結論として真逆のことが書いてある」と教えられた。 なので返却期限当日にざっと読んだ。読めるじゃん!と思いながら。そして面白い〜!と満喫しながら。 「せっかく読むんだから読書ノートも書きながら、一文も無駄にせず知識として入手したい」なんていう姿勢でいるから読む始められんのだな、まあとりあえず読まずに返すより読んで返した方が得だろ、みたいな思考に返却当日なったため読めたのだが、まさにそういうことが書いてあって半笑い、のち、軽く「にわか」で読んでよかったなと思った。 学びたいし賢くもなりたいし人生を楽に生きたいし社会を切り離して自分の世界に生きたくもあるけど、そういう気持ちは腹の底にいるけど、そういうの「まあとりあえず読むか」からの「わ〜面白い〜」をやってるときは見えなくなってるし「わ〜面白い〜」はほんとうに気持ちがいい。 返却期限にヒイヒイしちゃうけど、また何か図書館で借りてこよ。ここも、円本並べて満足するような記録の仕方じゃなくて、もっとカジュアルに使いたいね。 - 2025年9月24日
 今日からはじめる山登りじゅごん大輔読み終わった「インドア出不精オタクが何年か越しで登山に興味を持って始めてみたら…」という、多分この先もこれ以上シンクロする登山入門書はないだろうな…という本。 動きやすい格好で綿100Tシャツにジーンズ履いたり、オタクのグッズコレクター癖に火が付いてあれこれギアを探ってみては「沼…楽しい…」となったり、ひいこらしてる割には「もうやめる」とならなかったり。「登山はタイミング」のタイミングの感覚がかなり近いところで始めたんだろうなと思う。 体力・スキル的に似た辺りから選んでる山も分かる分かるって感じだし、コースタイムより遅れるのも、重課金オタクがパーティーに参戦するのも、ああ、ああ馴染んだ肌感…とまあ、オタクの親和性はあったんだけど、それよりなにより。 5年経っても飽きてないんだって。 わたしも、めちゃくちゃ楽しく山遊びしてる今でも、いつか登山ブームが去って飽きちゃうのかな、まあそれも仕方ないけどね、とほんのり思い続けているので、希望の星がひとつ、胸に宿ったなと思えた。感謝。
今日からはじめる山登りじゅごん大輔読み終わった「インドア出不精オタクが何年か越しで登山に興味を持って始めてみたら…」という、多分この先もこれ以上シンクロする登山入門書はないだろうな…という本。 動きやすい格好で綿100Tシャツにジーンズ履いたり、オタクのグッズコレクター癖に火が付いてあれこれギアを探ってみては「沼…楽しい…」となったり、ひいこらしてる割には「もうやめる」とならなかったり。「登山はタイミング」のタイミングの感覚がかなり近いところで始めたんだろうなと思う。 体力・スキル的に似た辺りから選んでる山も分かる分かるって感じだし、コースタイムより遅れるのも、重課金オタクがパーティーに参戦するのも、ああ、ああ馴染んだ肌感…とまあ、オタクの親和性はあったんだけど、それよりなにより。 5年経っても飽きてないんだって。 わたしも、めちゃくちゃ楽しく山遊びしてる今でも、いつか登山ブームが去って飽きちゃうのかな、まあそれも仕方ないけどね、とほんのり思い続けているので、希望の星がひとつ、胸に宿ったなと思えた。感謝。 - 2025年9月8日
 世界99 上村田沙耶香読み終わった今年触れた物語の中でダントツで恐ろしい。 被害者であり加害者である、という読み手が持っているだろう共感と嫌悪を、グロテスクファンタジーという手法で「やや」ずらす。さながらレイヤーをずるりとずらされたみたいな世界観。けれど、その下には自分がいる世界が変わらず、なんならずらしたせいでより一層くっきりと透けて見えて、それがまた怖くてたまらない。世界99。被害者側だけに立つことを絶対に許してくれない。 「どうだ?便利だったものが、意志をもつのって、すっごくむかついて、面倒で、厄介で、できることなら目を瞑りたいだろ?お前らはさ、俺たちを、まるで極悪人みたいに、指差して、自分は被害者だから清らかだ、みたいな顔してたけどさ?同じだったろ?便利なものが現れたら、あっさり使ったろ?どこかおかしくても、目を瞑って、便利さの中で考えることなんかやめたろ?それがさ、お前らの正体なんだよ。人間ってものの正体なんだよ」 これを、自分は被害者側だとだけ信じ込めたら幸せだろうか。きっとそんなことはない。被害者だと信じ込んでいるから、「記憶を手術」しているから、本気で辛いし怒っているし、自分の加害性には欠片も気付けない。それが恐ろしい。 世界99は、被害者側だけに立つことを許してくれないので、親切なのかもしれない…なんてことはなく、それこそピョコルンのようにただそこにあるだけ。人間に都合のいいように、そこにあるだけ。ああ恐ろしい。恐ろしくて、もう何も聞きたくない気がするのに、絶対にこの世界の末路を知りたい。下巻も楽しみです。
世界99 上村田沙耶香読み終わった今年触れた物語の中でダントツで恐ろしい。 被害者であり加害者である、という読み手が持っているだろう共感と嫌悪を、グロテスクファンタジーという手法で「やや」ずらす。さながらレイヤーをずるりとずらされたみたいな世界観。けれど、その下には自分がいる世界が変わらず、なんならずらしたせいでより一層くっきりと透けて見えて、それがまた怖くてたまらない。世界99。被害者側だけに立つことを絶対に許してくれない。 「どうだ?便利だったものが、意志をもつのって、すっごくむかついて、面倒で、厄介で、できることなら目を瞑りたいだろ?お前らはさ、俺たちを、まるで極悪人みたいに、指差して、自分は被害者だから清らかだ、みたいな顔してたけどさ?同じだったろ?便利なものが現れたら、あっさり使ったろ?どこかおかしくても、目を瞑って、便利さの中で考えることなんかやめたろ?それがさ、お前らの正体なんだよ。人間ってものの正体なんだよ」 これを、自分は被害者側だとだけ信じ込めたら幸せだろうか。きっとそんなことはない。被害者だと信じ込んでいるから、「記憶を手術」しているから、本気で辛いし怒っているし、自分の加害性には欠片も気付けない。それが恐ろしい。 世界99は、被害者側だけに立つことを許してくれないので、親切なのかもしれない…なんてことはなく、それこそピョコルンのようにただそこにあるだけ。人間に都合のいいように、そこにあるだけ。ああ恐ろしい。恐ろしくて、もう何も聞きたくない気がするのに、絶対にこの世界の末路を知りたい。下巻も楽しみです。 - 2025年9月5日
 「好き」を言語化する技術三宅香帆読み終わった「頭の中の妄想をそのまま抽出できる機械があればいいのに~」という二次創作界隈では定期的に回る願望は、「まあ、実際可能になっても、そのまま抽出した妄想って面白くないんだよね」とまとめるまでが一連の流れになっている。少なくとも、わたしの近辺では血の通った常識となっている。その「頭の中の妄想」を【核】と呼び、核を包む「工夫」のことを【好きの言語化】と定義しているのが……この本の前提だ。これは絶望ではなく救いの話だ。工夫さえすれば面白くなるし、伝わりやすくなる。 伝えたい人に伝えたいことを伝える。シンプルにそれだけを追求してある本なので、技術的に目新しいことは特にない。あくまでも推しについての妄想を10万字越えの文章にするのが趣味です! みたいな推しの押し売りオタクにとっての目新しさなので「推しの魅力を伝えてみたいけどどうしたらいいのかな?」という方にはオススメだ。 それと、「自分」について最近まったく深掘りしていないな、という人。 こっちはわたしも当てはまるので、どちらかというと「好き」を言語化する技術より、そこに至る思考の方が有意義な本だった。ちょうど、思考を言語化するための筋力が落ちていると感じていた。ネガティブ・ケイパビリティ。なんでもすぐ検索したりおすすめ欄を流し見したりして「分かった」気になる悪い癖。早々の利益を求めてしまう悪癖。ここから抜け出したいと思っていたタイミングで読めてよかった。 頭の中の妄想をそのまま抽出したいとは思わないけれど、そもそもとして今、頭の中に抽出したい妄想を広げられてもいない。「推しの魅力を伝えることは自分の人生を愛するということ」という言葉にあらためて納得する。頭の中の筋力が衰え弛んでいる人生は退屈で怠惰で他者にも自分にも無関心で、良い悪い以前に、シンプルに愛せない。愛せないのはつまらない。わたしがわたしの人生を愛するには、自分の力で手で、自分の好きを言語化していくことが不可欠で、そうした方が人生楽しい方に転んでいくと思うので、楽しい方に広げていきたい。
「好き」を言語化する技術三宅香帆読み終わった「頭の中の妄想をそのまま抽出できる機械があればいいのに~」という二次創作界隈では定期的に回る願望は、「まあ、実際可能になっても、そのまま抽出した妄想って面白くないんだよね」とまとめるまでが一連の流れになっている。少なくとも、わたしの近辺では血の通った常識となっている。その「頭の中の妄想」を【核】と呼び、核を包む「工夫」のことを【好きの言語化】と定義しているのが……この本の前提だ。これは絶望ではなく救いの話だ。工夫さえすれば面白くなるし、伝わりやすくなる。 伝えたい人に伝えたいことを伝える。シンプルにそれだけを追求してある本なので、技術的に目新しいことは特にない。あくまでも推しについての妄想を10万字越えの文章にするのが趣味です! みたいな推しの押し売りオタクにとっての目新しさなので「推しの魅力を伝えてみたいけどどうしたらいいのかな?」という方にはオススメだ。 それと、「自分」について最近まったく深掘りしていないな、という人。 こっちはわたしも当てはまるので、どちらかというと「好き」を言語化する技術より、そこに至る思考の方が有意義な本だった。ちょうど、思考を言語化するための筋力が落ちていると感じていた。ネガティブ・ケイパビリティ。なんでもすぐ検索したりおすすめ欄を流し見したりして「分かった」気になる悪い癖。早々の利益を求めてしまう悪癖。ここから抜け出したいと思っていたタイミングで読めてよかった。 頭の中の妄想をそのまま抽出したいとは思わないけれど、そもそもとして今、頭の中に抽出したい妄想を広げられてもいない。「推しの魅力を伝えることは自分の人生を愛するということ」という言葉にあらためて納得する。頭の中の筋力が衰え弛んでいる人生は退屈で怠惰で他者にも自分にも無関心で、良い悪い以前に、シンプルに愛せない。愛せないのはつまらない。わたしがわたしの人生を愛するには、自分の力で手で、自分の好きを言語化していくことが不可欠で、そうした方が人生楽しい方に転んでいくと思うので、楽しい方に広げていきたい。 - 2025年8月14日
 黒部源流 山小屋料理人やまとけいこ読み終わった登山について思考を深めていると、他者とつながること・コミュニケーションを取って理解を深め合うこと・自分以外を思いやること・喜んでもらいたいと願うこと…みたいな、そういう、道徳としては当たり前でも自分の弱さゆえにおざなりになりがちな、根源的な尊さをあらためて学べるし「そうなりたい」と素直に思える、と思う。山小屋を営む人のしなやかな倫理観。山に生きる人たちの優しさは知恵と道徳に裏付けされていると思う。格好良いし、憧れるね。
黒部源流 山小屋料理人やまとけいこ読み終わった登山について思考を深めていると、他者とつながること・コミュニケーションを取って理解を深め合うこと・自分以外を思いやること・喜んでもらいたいと願うこと…みたいな、そういう、道徳としては当たり前でも自分の弱さゆえにおざなりになりがちな、根源的な尊さをあらためて学べるし「そうなりたい」と素直に思える、と思う。山小屋を営む人のしなやかな倫理観。山に生きる人たちの優しさは知恵と道徳に裏付けされていると思う。格好良いし、憧れるね。 - 2025年8月14日
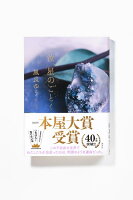 汝、星のごとく凪良ゆう読み終わったAudibleで、深夜の高速道路を走っている間に聞き終えた。Audibleは自分が読みたい速度と合わないなと感じるときもあるんだけど、この物語を真夏の、夜明けに向かう移動する箱の中で聞けたのはかなり得難い経験と感動になったと思う。 好きな男のために人生を誤りたい。 なんという自由だろう。そこに至るまでの壮絶な人生を思い、指先までじんわりと痺れた。そこに至るまでの壮絶な人生、その積み重ねがあったからこそ、自由として誤ることができた。 羨ましく思う。辛く先が見えない苦しい溢れそうな生活の果てに自由になったこと、仕事があること、人に出会えたこと、愛があったこと…色々あるけれど、そういうことではなく、そういう要素の羅列ではなく、辿り着ける人になっていけたこと、それが羨ましいのかもしれない。
汝、星のごとく凪良ゆう読み終わったAudibleで、深夜の高速道路を走っている間に聞き終えた。Audibleは自分が読みたい速度と合わないなと感じるときもあるんだけど、この物語を真夏の、夜明けに向かう移動する箱の中で聞けたのはかなり得難い経験と感動になったと思う。 好きな男のために人生を誤りたい。 なんという自由だろう。そこに至るまでの壮絶な人生を思い、指先までじんわりと痺れた。そこに至るまでの壮絶な人生、その積み重ねがあったからこそ、自由として誤ることができた。 羨ましく思う。辛く先が見えない苦しい溢れそうな生活の果てに自由になったこと、仕事があること、人に出会えたこと、愛があったこと…色々あるけれど、そういうことではなく、そういう要素の羅列ではなく、辿り着ける人になっていけたこと、それが羨ましいのかもしれない。 - 2025年7月21日
 正欲朝井リョウ読み終わったAudibleで3か月近くかけて聞ききった(途中他の本を読んだり色々していた時間が多かった)。 文体が今風だからAudibleで聞くには聞きやすいんだけど、わたしだったらここは流し読みするな〜という文章もずっと聞いてなきゃいけないのがしんどい小説だったな。あと、小説の技法的にも多分字で読んだ方が面白かったかもしれない。でもAudibleだから最後までたどり着けた気もするので、それはそれ。 読後感(読んでないけど)は悪くなかった。「あそこでわたしが止めなかったから、まだ生きていられているのかもしれない」という締めが。誰とも繋がれていなかったんだろう生きていた結果のフジワラサトルの結末と比較して、特に。
正欲朝井リョウ読み終わったAudibleで3か月近くかけて聞ききった(途中他の本を読んだり色々していた時間が多かった)。 文体が今風だからAudibleで聞くには聞きやすいんだけど、わたしだったらここは流し読みするな〜という文章もずっと聞いてなきゃいけないのがしんどい小説だったな。あと、小説の技法的にも多分字で読んだ方が面白かったかもしれない。でもAudibleだから最後までたどり着けた気もするので、それはそれ。 読後感(読んでないけど)は悪くなかった。「あそこでわたしが止めなかったから、まだ生きていられているのかもしれない」という締めが。誰とも繋がれていなかったんだろう生きていた結果のフジワラサトルの結末と比較して、特に。 - 2025年7月15日
 読み終わったお、お、おもしろ〜〜〜(1日ぶり2回目)。 「た、たる〜!」の部分はなくなってきて、これは行動によって状況が変わってきたからなんだけど、マインの精神的未熟さが際だってきて、それは甘ったれて自分のしたいこと以上に周囲を顧みてこなかったツケだから、それだけの話だとかなりきつい。けど、多分、多分この物語はそうはならないだろう信頼があるので、その信頼を担保に読み進めている。未熟!愚か!という感覚自体、新卒社会人を見てる気分なのかもしれない…と思えば見守るのが道理だと思うし、そう思わせてくれる力は偉大。 合本読み終わっちゃったけど、この先はまだ貸し出しされてて予約の順番回ってくるの結構先になりそうなので、なろうで読んじゃうか、村上海賊の娘にもどるか悩む…。無限に読んじゃって普通に寝不足なので…。
読み終わったお、お、おもしろ〜〜〜(1日ぶり2回目)。 「た、たる〜!」の部分はなくなってきて、これは行動によって状況が変わってきたからなんだけど、マインの精神的未熟さが際だってきて、それは甘ったれて自分のしたいこと以上に周囲を顧みてこなかったツケだから、それだけの話だとかなりきつい。けど、多分、多分この物語はそうはならないだろう信頼があるので、その信頼を担保に読み進めている。未熟!愚か!という感覚自体、新卒社会人を見てる気分なのかもしれない…と思えば見守るのが道理だと思うし、そう思わせてくれる力は偉大。 合本読み終わっちゃったけど、この先はまだ貸し出しされてて予約の順番回ってくるの結構先になりそうなので、なろうで読んじゃうか、村上海賊の娘にもどるか悩む…。無限に読んじゃって普通に寝不足なので…。 - 2025年7月14日
- 2025年7月13日
 読み終わった図書館の電子書籍、借りに行くことも返しに行く必要もない上に、まだ存在をあまり知られていないため紙の本より早く予約の順番が回ってくる!すごすぎ!でもまだそんなに蔵書がないので「読みたい本」ではなく図書館の電子書籍にありそうな本…」という本末転倒な探し方をして辿り着いたのがかの有名な「本好き」である。 「長いけど面白い」「面白いけど長い」という前情報以外知らずに読み始め、なるほどこれは大いなる序章なんだろうな…という予感がヒシヒシとしている。面白い。序盤、たるいな〜と思うところはあるんだけど「とはいえ確かにそんな何もかもご都合主義的に話うまくすすまんよな」と勝手に納得しながら読み進められるので、その時点で相当面白いんだろうな〜〜からエピローグまで来て面白さが一気に加速する。エピローグで加速するのは「読み手の視点・感覚に近い高さのキャラクターが高位置でその高さについて話し合っている」からで、これこそが序盤のたるいな〜のすくい上げなんだな、と腑に落ちる瞬間の気持ちよさすごいっすね。 おもしろ〜! 合本なので引き続き読みます。
読み終わった図書館の電子書籍、借りに行くことも返しに行く必要もない上に、まだ存在をあまり知られていないため紙の本より早く予約の順番が回ってくる!すごすぎ!でもまだそんなに蔵書がないので「読みたい本」ではなく図書館の電子書籍にありそうな本…」という本末転倒な探し方をして辿り着いたのがかの有名な「本好き」である。 「長いけど面白い」「面白いけど長い」という前情報以外知らずに読み始め、なるほどこれは大いなる序章なんだろうな…という予感がヒシヒシとしている。面白い。序盤、たるいな〜と思うところはあるんだけど「とはいえ確かにそんな何もかもご都合主義的に話うまくすすまんよな」と勝手に納得しながら読み進められるので、その時点で相当面白いんだろうな〜〜からエピローグまで来て面白さが一気に加速する。エピローグで加速するのは「読み手の視点・感覚に近い高さのキャラクターが高位置でその高さについて話し合っている」からで、これこそが序盤のたるいな〜のすくい上げなんだな、と腑に落ちる瞬間の気持ちよさすごいっすね。 おもしろ〜! 合本なので引き続き読みます。
読み込み中...



