

かちゃん
@kazumi22wo
- 2025年4月9日
 反共と愛国藤生明気になる
反共と愛国藤生明気になる - 2025年3月20日
 私たちは何を捨てているのか井出留美読んでる第5章「気候変動とほころんだ食料システム」読了。この章が読みたくて、この本を購入。 食品ロス•ほころんだ食品システムが気候変動に与える影響の大きさがよく分かった。 ①食品ロスから排出される温室効果ガスの量が、自動車から排出される温室効果ガスの量とほぼ変わらないこと ②温室効果ガスの3分の1は食料システムが排出源であること には驚き。食品ロスの削減は誰もが今すぐ取り組めることだし、費用対効果が極めて高い解決策であるとのことなので、明日から意識して取り組みたい。 また、生産者の方の多くが、燃料肥料や飼料の値上がりを価格に転嫁できておらず、経営を続けられない現状に追いやられていることも今回初めて知った。改めて、生産者の方に連帯の意を示すためにも、3/30の令和の百姓一揆に参加できればと思った。 最後に、印象に残った一文。 「本来は食料システムに関わる生産管理から小売にいたるまでのすべてのセクションが円滑に価格転嫁をおこない、商品の価値に見合った価格に変更し、それがきちんと賃上げにつながる経済•社会の仕組みこそが必要なのではないだろうか。もちろん、すべての人が食料を入手できるような社会保障制度が整っていることが前提であることはいうまでもない。」(p197)
私たちは何を捨てているのか井出留美読んでる第5章「気候変動とほころんだ食料システム」読了。この章が読みたくて、この本を購入。 食品ロス•ほころんだ食品システムが気候変動に与える影響の大きさがよく分かった。 ①食品ロスから排出される温室効果ガスの量が、自動車から排出される温室効果ガスの量とほぼ変わらないこと ②温室効果ガスの3分の1は食料システムが排出源であること には驚き。食品ロスの削減は誰もが今すぐ取り組めることだし、費用対効果が極めて高い解決策であるとのことなので、明日から意識して取り組みたい。 また、生産者の方の多くが、燃料肥料や飼料の値上がりを価格に転嫁できておらず、経営を続けられない現状に追いやられていることも今回初めて知った。改めて、生産者の方に連帯の意を示すためにも、3/30の令和の百姓一揆に参加できればと思った。 最後に、印象に残った一文。 「本来は食料システムに関わる生産管理から小売にいたるまでのすべてのセクションが円滑に価格転嫁をおこない、商品の価値に見合った価格に変更し、それがきちんと賃上げにつながる経済•社会の仕組みこそが必要なのではないだろうか。もちろん、すべての人が食料を入手できるような社会保障制度が整っていることが前提であることはいうまでもない。」(p197) - 2025年3月18日
 あいまいさに耐える佐藤卓己気になる読みたい
あいまいさに耐える佐藤卓己気になる読みたい - 2025年3月18日
 メディアと私たち中島岳志,堤未果読んでる第2章 サイード『イスラム報道』 中島岳志 読了。 「イスラムの解釈の背後には、個々の学者や知識人の直面する選択がある。知性を権力に奉仕させるのか、あるいは、批判や一般社会や倫理観に奉仕させるのかということだ。」
メディアと私たち中島岳志,堤未果読んでる第2章 サイード『イスラム報道』 中島岳志 読了。 「イスラムの解釈の背後には、個々の学者や知識人の直面する選択がある。知性を権力に奉仕させるのか、あるいは、批判や一般社会や倫理観に奉仕させるのかということだ。」 - 2025年3月17日
- 2025年3月16日
 メディアと私たち中島岳志,堤未果読んでる第4章 オーウェル『1984年』高橋源一郎 読了。 句読点さんをはじめ、様々な方が現代を『1984年』に描かれているディストピアにたとえていることから、すっと読まねばと思っていた。今回簡単なあらすじを知っただけでも、思い当たることが沢山あって、かなりゾクッとしてしまった。 個人的に興味深かったのはセックスについての記述。『1984年』では、愛•快楽をともなわない子作りのためのセックスのみがセックスとして認められ、それ以外のすべては「性犯罪」として見なされる。性の意味を「生殖」にのみ限定することがディストピアとして描かれていることは、ひとつの大きなポイントであると思う。 わたしたち人間の性には本来、「生殖としての性」にとどまらない多様な意味、側面、要素があるのだと信じたい。
メディアと私たち中島岳志,堤未果読んでる第4章 オーウェル『1984年』高橋源一郎 読了。 句読点さんをはじめ、様々な方が現代を『1984年』に描かれているディストピアにたとえていることから、すっと読まねばと思っていた。今回簡単なあらすじを知っただけでも、思い当たることが沢山あって、かなりゾクッとしてしまった。 個人的に興味深かったのはセックスについての記述。『1984年』では、愛•快楽をともなわない子作りのためのセックスのみがセックスとして認められ、それ以外のすべては「性犯罪」として見なされる。性の意味を「生殖」にのみ限定することがディストピアとして描かれていることは、ひとつの大きなポイントであると思う。 わたしたち人間の性には本来、「生殖としての性」にとどまらない多様な意味、側面、要素があるのだと信じたい。 - 2025年3月16日
 私たちは何を捨てているのか井出留美読んでる2章まで読了。筆者の食品ロスに対する強い課題意識と利己的な消費者への怒りが伝わってくる。食品ロスを減らすための各国の様々な取り組みについて知ることができ、勉強になる。また、「消費者としての責任」についても深く考えさせられる。 近年あらゆる食品が値上がりをしており、特に米価に関しては価格が下がるのか否かといった消費者側からの視点でのみ報じられがち。それに対して筆者は「食品価格の適正化と困窮者支援の問題は分けて考えたほうがいいのではないだろうか」と。確かにその通り。
私たちは何を捨てているのか井出留美読んでる2章まで読了。筆者の食品ロスに対する強い課題意識と利己的な消費者への怒りが伝わってくる。食品ロスを減らすための各国の様々な取り組みについて知ることができ、勉強になる。また、「消費者としての責任」についても深く考えさせられる。 近年あらゆる食品が値上がりをしており、特に米価に関しては価格が下がるのか否かといった消費者側からの視点でのみ報じられがち。それに対して筆者は「食品価格の適正化と困窮者支援の問題は分けて考えたほうがいいのではないだろうか」と。確かにその通り。 - 2025年3月10日
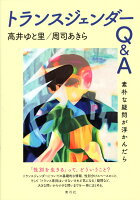 トランスジェンダーQ&A周司あきら,高井ゆと里読んでる
トランスジェンダーQ&A周司あきら,高井ゆと里読んでる - 2025年3月9日
- 2025年3月6日
 メディアと私たち中島岳志,堤未果読んでる
メディアと私たち中島岳志,堤未果読んでる - 2025年3月6日
 ファシズムの教室田野大輔読み終わった兵庫県知事選で起きたことや、加速する排外主義運動、ヘイトスピーチの背景にあるものが、この本を通してよく見えたような気がします。 この本の巻末には、①ファシズム的な運動に対して「ファシズムはいけない」と理性に訴えるだけでは不充分で、むしろそれが逆効果にもなりうること、 ②むしろ私たちがすべきは、ファシズムが私たちを惹きつける要因を知り、その感情に積極的に介入することで、過激化の危険性を摘んでいくこと、だと書かれています。 そのために、田野さんは実際に甲南大学で10年以上「ファシズムの教室」という実践を積まれており、この本にはその詳細な記録があります。 ここ最近は随分と仕事にも順応してきたつもりでいたけれど、職場で日々感じる違和感をやり過ごし、権威に服従し、責任からの解放感に包まれていただけかもしれないなぁと、なんだか納得してしまいました。 この本で繰り返し出てくる「行動の責任」、私にとってのそれはなんなのか、考え続けたいです。
ファシズムの教室田野大輔読み終わった兵庫県知事選で起きたことや、加速する排外主義運動、ヘイトスピーチの背景にあるものが、この本を通してよく見えたような気がします。 この本の巻末には、①ファシズム的な運動に対して「ファシズムはいけない」と理性に訴えるだけでは不充分で、むしろそれが逆効果にもなりうること、 ②むしろ私たちがすべきは、ファシズムが私たちを惹きつける要因を知り、その感情に積極的に介入することで、過激化の危険性を摘んでいくこと、だと書かれています。 そのために、田野さんは実際に甲南大学で10年以上「ファシズムの教室」という実践を積まれており、この本にはその詳細な記録があります。 ここ最近は随分と仕事にも順応してきたつもりでいたけれど、職場で日々感じる違和感をやり過ごし、権威に服従し、責任からの解放感に包まれていただけかもしれないなぁと、なんだか納得してしまいました。 この本で繰り返し出てくる「行動の責任」、私にとってのそれはなんなのか、考え続けたいです。 - 2025年3月6日
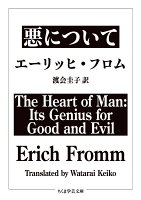 悪についてエーリッヒ・フロム,渡会圭子読んでる
悪についてエーリッヒ・フロム,渡会圭子読んでる - 2025年3月6日
 台湾の本音野嶋剛読んでる台湾とえいば2019年にアジア初の同性婚を認める法律が施行されるなど、先進的で民主的なイメージを持っていたが、施行前に行われた世論調査では、法律施行に賛成の割合はわずか37.4%だったという事実に驚き。若年を支持層とする民進党が政権を握っていたからこそ、同性婚特別法が施行できたそう。 一方で日本は65%もの人が同性婚に賛成しているのに、同性婚に反対する立場を取り続けている自民党が政権を握り続けているため、法制化が実現しない。 「日本の若者たちは選挙に興味がない。その理由はどうせ自分の意見が通らないとあきらめているから、といわれます。でも、どうでしょう。あきらめているからこそ、政権は票田である老人層が喜ぶ政策ばかり取り入れて、若い世代の未来に希望が見えなくなる。この閉塞感を打ち消したいなら、選挙で願いを叶えるしかないのではないでしょうか。」という筆者の言葉が胸に響く。 また筆者によると、台湾のコロナ禍における対応の速さや、政権交代が起こりやすい点、東日本大震災の際に日本へ寄せられた巨額な義援金な背景には、「一つの関心ごとに対して突き進む、ワン・イシューの国」という台湾の特質があるという。歴史、文化、さまざまな角度から台湾を知ることができる良書。
台湾の本音野嶋剛読んでる台湾とえいば2019年にアジア初の同性婚を認める法律が施行されるなど、先進的で民主的なイメージを持っていたが、施行前に行われた世論調査では、法律施行に賛成の割合はわずか37.4%だったという事実に驚き。若年を支持層とする民進党が政権を握っていたからこそ、同性婚特別法が施行できたそう。 一方で日本は65%もの人が同性婚に賛成しているのに、同性婚に反対する立場を取り続けている自民党が政権を握り続けているため、法制化が実現しない。 「日本の若者たちは選挙に興味がない。その理由はどうせ自分の意見が通らないとあきらめているから、といわれます。でも、どうでしょう。あきらめているからこそ、政権は票田である老人層が喜ぶ政策ばかり取り入れて、若い世代の未来に希望が見えなくなる。この閉塞感を打ち消したいなら、選挙で願いを叶えるしかないのではないでしょうか。」という筆者の言葉が胸に響く。 また筆者によると、台湾のコロナ禍における対応の速さや、政権交代が起こりやすい点、東日本大震災の際に日本へ寄せられた巨額な義援金な背景には、「一つの関心ごとに対して突き進む、ワン・イシューの国」という台湾の特質があるという。歴史、文化、さまざまな角度から台湾を知ることができる良書。 - 2024年10月23日
 韓国の味『中くらいの友だち』編集部かつて読んだ
韓国の味『中くらいの友だち』編集部かつて読んだ - 2024年10月2日
 増補新版 韓国文学の中心にあるもの斎藤真理子かつて読んだ
増補新版 韓国文学の中心にあるもの斎藤真理子かつて読んだ
読み込み中...
![世界2025年4月号[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ANrAbNAEL._SL500_.jpg)
