仲嶺真
@nihsenimakan
- 2026年2月20日
 文化が違えば,心も違う?北山忍読み終わった本書のテーマを一言で言うなら、多様性の本質とは何か?である。ここでの議論は以下の三点に要約できる。 (1)現代の文化の多様性を理解するためには、過去数千年、ことによると数万年、あるいはそれ以上にわたる生態条件、生活環境、移住移民といった要因を考慮に入れる必要がある。 (2)こうした時間軸の中で多様性を考えると、そこには自ずと人類共通の基盤が立ち現れる。 (3)このように考えることによって、真の相互理解が可能になる。 p.ⅱ
文化が違えば,心も違う?北山忍読み終わった本書のテーマを一言で言うなら、多様性の本質とは何か?である。ここでの議論は以下の三点に要約できる。 (1)現代の文化の多様性を理解するためには、過去数千年、ことによると数万年、あるいはそれ以上にわたる生態条件、生活環境、移住移民といった要因を考慮に入れる必要がある。 (2)こうした時間軸の中で多様性を考えると、そこには自ずと人類共通の基盤が立ち現れる。 (3)このように考えることによって、真の相互理解が可能になる。 p.ⅱ - 2026年2月9日
 日本近代科学史村上陽一郎読み終わったしたがって、表面的な体裁を見れば、本書は、時代の推移をほぼ忠実に追って書かれた、日本における西欧科学受容の小通史という形をとってはいるが、記述の中心点は、あくまで、日本文化の特質を、西欧科学という踏み絵を使って考えていこうとするところにある。pp.4-5
日本近代科学史村上陽一郎読み終わったしたがって、表面的な体裁を見れば、本書は、時代の推移をほぼ忠実に追って書かれた、日本における西欧科学受容の小通史という形をとってはいるが、記述の中心点は、あくまで、日本文化の特質を、西欧科学という踏み絵を使って考えていこうとするところにある。pp.4-5 - 2026年1月24日
- 2026年1月21日
 テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。ヤニス・バルファキス,斎藤幸平,関美和読み終わったせっかちな読者のために、あらかじめおことわりしておこう。テクノ封建制についての説明は第三章まで出てこない。私の書くことを理解してもらうにはまず、ここ数十年における資本主義の驚くべき変容を振り返る必要がある。それが第二章だ。本の冒頭にはテクノ封建制の話はまったく出てこない。第一章では、私の父が金属片とヘシオドスの叙事詩の助けを借りなが ら、六歳だった私にテクノロジーと人間の複雑な関係と、資本主義の本質をどのように説明してくれたかを書いた。この教えが、その後に続くすべての考えの原則を導く出発点になった。 そして結論へと導いてくれたのもまた、一九九三年に父が私に投げかけた一見単純な問いだった。だから、ここからは父への手紙という形でしたためることにする。この本は、父の大切な問いに答えようとする私の試みである。pp.8-9
テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。ヤニス・バルファキス,斎藤幸平,関美和読み終わったせっかちな読者のために、あらかじめおことわりしておこう。テクノ封建制についての説明は第三章まで出てこない。私の書くことを理解してもらうにはまず、ここ数十年における資本主義の驚くべき変容を振り返る必要がある。それが第二章だ。本の冒頭にはテクノ封建制の話はまったく出てこない。第一章では、私の父が金属片とヘシオドスの叙事詩の助けを借りなが ら、六歳だった私にテクノロジーと人間の複雑な関係と、資本主義の本質をどのように説明してくれたかを書いた。この教えが、その後に続くすべての考えの原則を導く出発点になった。 そして結論へと導いてくれたのもまた、一九九三年に父が私に投げかけた一見単純な問いだった。だから、ここからは父への手紙という形でしたためることにする。この本は、父の大切な問いに答えようとする私の試みである。pp.8-9 - 2026年1月19日
- 2026年1月13日
 正欲朝井リョウ読み終わった自分が想像できる“多様性”だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよなー。息子が不登校になった検事・啓喜。初めての恋に気づく女子大生・八重子。ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。ある事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり始める。だがその繋がりは、“多様性を尊重する時代”にとって、ひどく不都合なものだった。読む前の自分には戻れない、気迫の長編小説。
正欲朝井リョウ読み終わった自分が想像できる“多様性”だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよなー。息子が不登校になった検事・啓喜。初めての恋に気づく女子大生・八重子。ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。ある事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり始める。だがその繋がりは、“多様性を尊重する時代”にとって、ひどく不都合なものだった。読む前の自分には戻れない、気迫の長編小説。 - 2026年1月11日
- 2026年1月10日
 学習の生態学福島真人読み終わった全体としての章構成は、前半と後半の大きく二つに分かれる。前半(第I部)は、理論的考察が中心であり、学習をめぐる認知科学、計算主義的アプローチと、より社会科学的なアプローチ(状況的学習論)などの理論的アプローチの射程と限界を、様々な理論的、現実的な舞台を中心に批判・検討し、更に学習理論のミクロとマクロをつなぐ新たな理論的試論としての学習の実験的領域という理論的枠組みを呈示することを試みている。 後半(第工部)は、より具体的、民族誌的な記述・分析が主体となるが、特に後半で強調されるのは、具体的な探求の対象としての組織のレベルである。とりわけリスキーなテクノロジーによって構成されている組織という具体的テーマが新たに加わる。ここで民族誌的に取り扱われるのは、いくつかのタイプの医療組織であるが、この背景にあるのは、軍艦や原子力発電所などについて詳細な分析を行った高信頼性組織研究という分野である。学習と思考というテーマは、後半では、リスク、テクノロジー、科学的知識、そして組織といった具体的文脈と織りあわされることになる。p.005-006
学習の生態学福島真人読み終わった全体としての章構成は、前半と後半の大きく二つに分かれる。前半(第I部)は、理論的考察が中心であり、学習をめぐる認知科学、計算主義的アプローチと、より社会科学的なアプローチ(状況的学習論)などの理論的アプローチの射程と限界を、様々な理論的、現実的な舞台を中心に批判・検討し、更に学習理論のミクロとマクロをつなぐ新たな理論的試論としての学習の実験的領域という理論的枠組みを呈示することを試みている。 後半(第工部)は、より具体的、民族誌的な記述・分析が主体となるが、特に後半で強調されるのは、具体的な探求の対象としての組織のレベルである。とりわけリスキーなテクノロジーによって構成されている組織という具体的テーマが新たに加わる。ここで民族誌的に取り扱われるのは、いくつかのタイプの医療組織であるが、この背景にあるのは、軍艦や原子力発電所などについて詳細な分析を行った高信頼性組織研究という分野である。学習と思考というテーマは、後半では、リスク、テクノロジー、科学的知識、そして組織といった具体的文脈と織りあわされることになる。p.005-006 - 2026年1月2日
 市民の科学 (講談社学術文庫 2228)高木仁三郎読み終わった市民の視点(あるいは立場)に立った科学ーいわば「市民の科学」ということが可能だろうか、それによって現代科学技術の根本にある歪みのようなものに「科学」の場から異議を唱えることが可能だろうか。そのことは長い間私をずっととらえてきたことだが、最近の情勢は、あらためて私自身に向けてその問いを発する必要を示しているように思われる。そこで、なによりも自分の営みの問題として、この科学と市民の問題を考えてみたいというのが、本書のねらいである。p.12
市民の科学 (講談社学術文庫 2228)高木仁三郎読み終わった市民の視点(あるいは立場)に立った科学ーいわば「市民の科学」ということが可能だろうか、それによって現代科学技術の根本にある歪みのようなものに「科学」の場から異議を唱えることが可能だろうか。そのことは長い間私をずっととらえてきたことだが、最近の情勢は、あらためて私自身に向けてその問いを発する必要を示しているように思われる。そこで、なによりも自分の営みの問題として、この科学と市民の問題を考えてみたいというのが、本書のねらいである。p.12 - 2026年1月1日
- 2025年12月28日
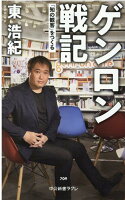 ゲンロン戦記東浩紀読み終わったでもいまは、当時の考えがまちがいだったとわかっています。これから順に語っていきますが、会社の本体はむしろ事務にあります。研究成果でも作品でもなんでもいいですが、「商品」は事務がしっかりしないと生み出せません。研究者やクリエイターだけが重要で事務はしょせん補助だというような発想は、結果的に手痛いしっぺ返しを食らうことになります。p.32
ゲンロン戦記東浩紀読み終わったでもいまは、当時の考えがまちがいだったとわかっています。これから順に語っていきますが、会社の本体はむしろ事務にあります。研究成果でも作品でもなんでもいいですが、「商品」は事務がしっかりしないと生み出せません。研究者やクリエイターだけが重要で事務はしょせん補助だというような発想は、結果的に手痛いしっぺ返しを食らうことになります。p.32 - 2025年12月26日
- 2025年12月17日
- 2025年12月9日
 ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い一〇分間の大激論の謎ジョン・エーディナウ,デヴィッド・エドモンズ,二木麻里読み終わった一九四六年十月二十五日、金曜の晩、ケンブリッジ大学のモラル・サイエンス・クラブは定例の会合をひらいていた。これは哲学の教授と学生たちが毎週おこなっていた討論会である。メンバーはいつもどおり夜八時半に、キングズカレッジのギブズ棟にあるつづき部屋、日階段の3号室にあつまった。p.11
ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い一〇分間の大激論の謎ジョン・エーディナウ,デヴィッド・エドモンズ,二木麻里読み終わった一九四六年十月二十五日、金曜の晩、ケンブリッジ大学のモラル・サイエンス・クラブは定例の会合をひらいていた。これは哲学の教授と学生たちが毎週おこなっていた討論会である。メンバーはいつもどおり夜八時半に、キングズカレッジのギブズ棟にあるつづき部屋、日階段の3号室にあつまった。p.11 - 2025年12月6日
- 2025年11月27日
 構造と力浅田彰読み終わった「序に代えて」では、本書の執筆にあたっての姿勢を明らかにするとともに、本書全体の論理の雛型を提示する。 第I部では、構造主義とポスト構造主義をひとつの一貫したパースペクティヴの中で論理的に再構成し、現在の理論的フロンティアの位置を確定する。 第口部では、第I部で提示したパースペクティヴをさらに内在的に理解すべく、構造主義のリミットと目されるラカンの理論に定位して詳しい分析を行ない、その後、新しい理論家たち、とりわけドゥルーズ"ガタリが、どのようにしてそれを乗りこえていくかを検討しながら、ポスト構造主義の理路を探っていく。 from 本書
構造と力浅田彰読み終わった「序に代えて」では、本書の執筆にあたっての姿勢を明らかにするとともに、本書全体の論理の雛型を提示する。 第I部では、構造主義とポスト構造主義をひとつの一貫したパースペクティヴの中で論理的に再構成し、現在の理論的フロンティアの位置を確定する。 第口部では、第I部で提示したパースペクティヴをさらに内在的に理解すべく、構造主義のリミットと目されるラカンの理論に定位して詳しい分析を行ない、その後、新しい理論家たち、とりわけドゥルーズ"ガタリが、どのようにしてそれを乗りこえていくかを検討しながら、ポスト構造主義の理路を探っていく。 from 本書 - 2025年11月25日
 科学としての心理学ゾルタン・ディエネス,清河幸子,石井敬子読み終わった本書の目的は、統計的推測の概念的基礎を含む科学哲学の問題のうち、心理学的研究の実践に直接関係するものを取り上げることである。p.i
科学としての心理学ゾルタン・ディエネス,清河幸子,石井敬子読み終わった本書の目的は、統計的推測の概念的基礎を含む科学哲学の問題のうち、心理学的研究の実践に直接関係するものを取り上げることである。p.i - 2025年11月14日
 組織と人を動かす科学的に正しいホメ方伊達洋駆,黒住嶺読み終わったホメ言葉は、ほんの些細なフレーズであっても、相手の未来を変えることができます。その力をどうやって正しく発揮するか!それこそが本書が問いかけるテーマです。ページをめくるうちに、きっと「ホメる」ことへの見方が変わるでしょう。この1冊が皆さんの日常に小さな変化と前向きな空気をもたらし、人と組織の新たなステップへとつながることを願っています。p.6
組織と人を動かす科学的に正しいホメ方伊達洋駆,黒住嶺読み終わったホメ言葉は、ほんの些細なフレーズであっても、相手の未来を変えることができます。その力をどうやって正しく発揮するか!それこそが本書が問いかけるテーマです。ページをめくるうちに、きっと「ホメる」ことへの見方が変わるでしょう。この1冊が皆さんの日常に小さな変化と前向きな空気をもたらし、人と組織の新たなステップへとつながることを願っています。p.6 - 2025年11月14日
 生活史の方法岸政彦読み終わったただ、この本では、生活史を聞いて書くうえでの、技術的なことを含めたさまざまなことが書かれていますが、本書はいわゆる「マニュアル本」ではありません。聞き取りは誰でもできるのです。マニュアルなんか必要ありません。聞き取りをめぐるさまざまなことを書いて、それをきっかけに、他者の話を聞くということについて考えてみたい。この本はそんな本です。p.24
生活史の方法岸政彦読み終わったただ、この本では、生活史を聞いて書くうえでの、技術的なことを含めたさまざまなことが書かれていますが、本書はいわゆる「マニュアル本」ではありません。聞き取りは誰でもできるのです。マニュアルなんか必要ありません。聞き取りをめぐるさまざまなことを書いて、それをきっかけに、他者の話を聞くということについて考えてみたい。この本はそんな本です。p.24 - 2025年11月11日
読み込み中...







