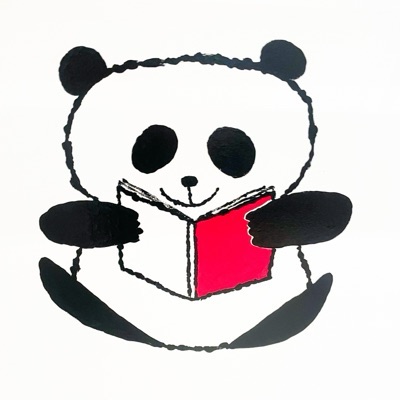会話を哲学する

72件の記録
 ゆ。@XtVq42025年12月30日読み終わったコミュニケーションとマニピュレーションについて書かれている本。 会話で作られるお互いの約束事がコミュニケーション、マニピュレーションは会話じゃないところで起きてるもの。それを使えば人を操ることができる。約束事の形成を避けつつ聞き手をコントロールするのがマニピュレーション。
ゆ。@XtVq42025年12月30日読み終わったコミュニケーションとマニピュレーションについて書かれている本。 会話で作られるお互いの約束事がコミュニケーション、マニピュレーションは会話じゃないところで起きてるもの。それを使えば人を操ることができる。約束事の形成を避けつつ聞き手をコントロールするのがマニピュレーション。 ちっちゃいねこ図書館@gjmajt1002025年12月10日1コミュニケーションとマニピュレーション 2わかり切ったことをそれでも言う 3間違っているとわかっていても 4伝わらないからこそ言えること 5すれ違うコミュニケーション 6本心を潜ませる 7操るための言葉
ちっちゃいねこ図書館@gjmajt1002025年12月10日1コミュニケーションとマニピュレーション 2わかり切ったことをそれでも言う 3間違っているとわかっていても 4伝わらないからこそ言えること 5すれ違うコミュニケーション 6本心を潜ませる 7操るための言葉
 がみ@ottoto-dameda2025年12月9日読み終わったラムちゃんとあたるくんのかわいい帯に惹かれて読んだ。 漫画や小説など、フィクション作品が例として多く取り上げられているが、5章や7章で相手の地位や属性によってコミュニケーションがねじ曲げられる例や、言葉の責任を負わないままに相手の思考を誘導する例など、現実にも深く関係のある会話の問題について触れられているのが興味深かった。 明らかに悪意を匂わせているのに、「そんなこと一言も言っていない」と逃げ道を用意するような会話について言語化されていて、そういうずるい話し方あるよな〜!と得心がいった。
がみ@ottoto-dameda2025年12月9日読み終わったラムちゃんとあたるくんのかわいい帯に惹かれて読んだ。 漫画や小説など、フィクション作品が例として多く取り上げられているが、5章や7章で相手の地位や属性によってコミュニケーションがねじ曲げられる例や、言葉の責任を負わないままに相手の思考を誘導する例など、現実にも深く関係のある会話の問題について触れられているのが興味深かった。 明らかに悪意を匂わせているのに、「そんなこと一言も言っていない」と逃げ道を用意するような会話について言語化されていて、そういうずるい話し方あるよな〜!と得心がいった。
 rkm @ 𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗂𝗌 💙@rkm172025年12月3日買った読み終わった読書メモフィクション小説や漫画・映画・ゲームなどのコンテンツを題材にして意図と会話における約束事がどのような作用を起こすと、どう互いに影響を与えるものなのか、考えられうるあらゆる事例を用いており、漫画ならば該当ページが掲載されてる。 権利の問題を考えてもこれってすごいよ。コンテンツガイドとしても秀逸。 自分に向けた言葉でも会話として「約束事」が成立してしまうので…という観点から失敗しているコミュニケーションだからこそ上手く使われている例が書かれている第4章とかとにかくすごいです。こんなふうに考えたことはなかった。 やるせない悩みのある方、悩んでいるかもしれない誰かの味方になりたいと思う方は参考にできるかも。だから三木那由他さんの御本って心がやさしいんだなあ… ここ数ヶ月で読んだなかでは、私のものごとのとらえ方を変えたかもしれない本ナンバーワンかもしれません。
rkm @ 𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗂𝗌 💙@rkm172025年12月3日買った読み終わった読書メモフィクション小説や漫画・映画・ゲームなどのコンテンツを題材にして意図と会話における約束事がどのような作用を起こすと、どう互いに影響を与えるものなのか、考えられうるあらゆる事例を用いており、漫画ならば該当ページが掲載されてる。 権利の問題を考えてもこれってすごいよ。コンテンツガイドとしても秀逸。 自分に向けた言葉でも会話として「約束事」が成立してしまうので…という観点から失敗しているコミュニケーションだからこそ上手く使われている例が書かれている第4章とかとにかくすごいです。こんなふうに考えたことはなかった。 やるせない悩みのある方、悩んでいるかもしれない誰かの味方になりたいと思う方は参考にできるかも。だから三木那由他さんの御本って心がやさしいんだなあ… ここ数ヶ月で読んだなかでは、私のものごとのとらえ方を変えたかもしれない本ナンバーワンかもしれません。
 きりんモリモリ@tantakadance2025年11月12日買った読んでる会話についてコミュニケーションとマニピュレーションという二つの要素に分けて考えている本。コミュニケーションは約束ごと、マニピュレーションは企みのようなもの。この2つのグラデーションというか、ねじれというかいろんな合わさり方によって会話って面白くなってるんだな。 私は会話の醍醐味を他者であることによるズレに見出してるのだが、それはどう整理されるのかあまり理解できてない、全然別のことかも?
きりんモリモリ@tantakadance2025年11月12日買った読んでる会話についてコミュニケーションとマニピュレーションという二つの要素に分けて考えている本。コミュニケーションは約束ごと、マニピュレーションは企みのようなもの。この2つのグラデーションというか、ねじれというかいろんな合わさり方によって会話って面白くなってるんだな。 私は会話の醍醐味を他者であることによるズレに見出してるのだが、それはどう整理されるのかあまり理解できてない、全然別のことかも?




 -ゞ-@bunkobonsuki2025年10月27日コミュニケーション。それは相互理解のための会話であり、人を操作する営みでもある。 本書では、情報をバケツリレーのように伝達する「バケツリレー方式」のコミュニケーション観を批判し、一つの会話にいくつもの異なる営みが含まれている「約束事の形成方式」のコミュニケーション観を確立する。 本文では各章に会話の例として漫画を取り上げている。そのため、漫画のワンシーンの解説としても読むことができる。言語のトピックは身近でありながら難解に陥りやすいが、例題が漫画のため最後まで読みやすかった。
-ゞ-@bunkobonsuki2025年10月27日コミュニケーション。それは相互理解のための会話であり、人を操作する営みでもある。 本書では、情報をバケツリレーのように伝達する「バケツリレー方式」のコミュニケーション観を批判し、一つの会話にいくつもの異なる営みが含まれている「約束事の形成方式」のコミュニケーション観を確立する。 本文では各章に会話の例として漫画を取り上げている。そのため、漫画のワンシーンの解説としても読むことができる。言語のトピックは身近でありながら難解に陥りやすいが、例題が漫画のため最後まで読みやすかった。

- 仲嶺真@nihsenimakan2025年9月23日読み終わったpp.5-7 第一章では、コミュニケーションとマニピュレーションという概念について説明しています。全体の下準備となる章です。いずれの概念も私自身で定義したかたちで用いるので、以降の章の話がよくわからなくなったら、ここに戻ってもらうといいかもしれません。 第二章から第五章では、コミュニケーションを主に扱います。そのうち最初の三つの章では、よくあるコミュニケーション観ではうまく捉えられない奇妙なやり取りをたくさんのフイクション作品から紹介し、そこでいったい何が起きているのかを私の立場から解説しています。順番に述べると、第二章ではもうわかり切っていることをあえてコミュニケートするという例を扱い、第三章では間違っているとわかっていることをあえてコミュニケートするという例を扱い、第四章ではコミュニケーションにならないとわかっているからこそ、つまり伝わらないとわかっているからこそなされる発話を扱います。 第五章ではそれまでの章とは違い、コミュニケーションがすれ違った場合に話し手と聞き手のあいだでどういった交渉がなされるのかといったことをフィクションの例を手掛かりに論じ、そのなかでどのように暴力が起こりうるのかを述べています。いま現在の私の関心は特にこの第五章で語っているような事象にあるのですが、それはつまりほかの章で話していることに比べると現在進行形で考えている側面が強いということでもあって、この章の内容はいまの私の考えのスケッチのようなものになっているかと思います。 第六章と第七章では、会話においてなされつつあるコミュニケーションとは異なる営みとしてマニュピレーションに目を向け、いかにしてそれが会話のなかで展開されるのかを論じています。第六章は本心をコミュニケーションにおいては伝えず、マニピュレーションを介して知らせるという例を取り上げています。第七章では、マニピュレーションを介して話し手が聞き手を自分の望む方向へと誘導する例を論じています。

 torajiro@torajiro2025年9月14日読み終わったaudibleコミュニケーションは話し手と聞き手との間に約束事を形成するものであり、マニピュレーションは聞き手を話し手の意図通りに操作することであり、両者は区別される必要がある。この両者の様々なズレやバリエーションについて漫画や小説などのフィクション作品における会話を題材に解説していく。素晴らしくわかりやすかった。この本を読むことで実際の会話におけるコミュニケーションやマニピュレーションについてもアンテナを貼ることができるようになるし、小説や漫画の読解力を上げることもできるように思います。 それにしても『鋼の錬金術師』はおしゃれなマニピュレーションの宝庫だな。本書で取り上げられてたところ以外にもたくさん思い浮かんだ。
torajiro@torajiro2025年9月14日読み終わったaudibleコミュニケーションは話し手と聞き手との間に約束事を形成するものであり、マニピュレーションは聞き手を話し手の意図通りに操作することであり、両者は区別される必要がある。この両者の様々なズレやバリエーションについて漫画や小説などのフィクション作品における会話を題材に解説していく。素晴らしくわかりやすかった。この本を読むことで実際の会話におけるコミュニケーションやマニピュレーションについてもアンテナを貼ることができるようになるし、小説や漫画の読解力を上げることもできるように思います。 それにしても『鋼の錬金術師』はおしゃれなマニピュレーションの宝庫だな。本書で取り上げられてたところ以外にもたくさん思い浮かんだ。

 柳 風歌@ryuya_ymgs2025年6月17日読み終わった実世界のケース(検証・分析する目的で再現されたものでない)へ、容易に当てはめることができる理論を可能な限りわかりやすく言語化している。 フィクションにおける会話の例をメインに用いていることから、以降で鑑賞するフィクションの見方が変わる、影響力の高い学びだった。
柳 風歌@ryuya_ymgs2025年6月17日読み終わった実世界のケース(検証・分析する目的で再現されたものでない)へ、容易に当てはめることができる理論を可能な限りわかりやすく言語化している。 フィクションにおける会話の例をメインに用いていることから、以降で鑑賞するフィクションの見方が変わる、影響力の高い学びだった。