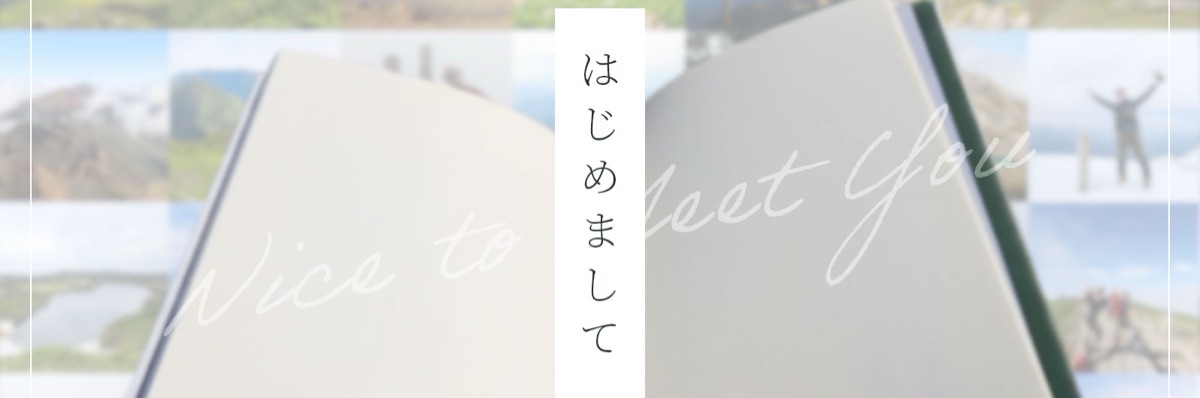

ゆうすけ | オガノート
@ogayuppy
はじめまして!ゆうすけと申します。
基本は小説やエッセイが好きで、夏目漱石をはじめ司馬遼太郎、辻村美月、寺地はるな…などを読んでいます。あまり著者では選ばないタイプです。
長田弘や若松英輔の詩も大好きです。
紀伊国屋ルーレットを回していて、たまに突拍子の無いジャンルを読んだりもします。
いつか文学フリマとかに参加できたら良いな~と思っています。よろしくお願いします!
- 2025年10月30日
 文庫 生き物の死にざま稲垣栄洋読み終わった買った
文庫 生き物の死にざま稲垣栄洋読み終わった買った - 2025年10月17日
 敗者の生命史38億年稲垣栄洋読み終わった
敗者の生命史38億年稲垣栄洋読み終わった - 2025年10月4日
 モモミヒャエル・エンデ,大島かおり読み終わった言わずと知れたミヒャエル・エンデ著の名作。ずっと昔、小学生時代に一度だけ読んだことがあって、全体を通して「すごく面白かった」ことと、なぜか「時間停止状態において宙に浮いた綿毛までも衝突物になる危険性」が印象に残っています。 なぜ読み返そうと思ったかというと、最近ChatGPTに日記を読ませていたらふと、 「あなたの日記からは『モモ』を思い出しますね。」 と一丁前な感想を言われまして。 確かにここ数日、「自分にとっての時間との向き合い方」みたいなことを考え続けていましたが、「『モモ』ってそういう話だったっけ?」となり、思い出すために実家から回収してきました。 岩波書店のハードカバー、1995年の52刷。全面的に日焼けした古い本ですが、装丁が頑丈なのか今でも気を使うことなくページをめくれます。 上記のような漠然とした記憶しか残っていなかったのですが、「ジジ」や「ベッポ」といった主要人物の名前の響きは覚えていて、古い友人と再会した気分。ずっとこの本の中で、登場人物たちが読まれるのを待っていたんだと思うと胸が温かくなります。 読み返してみて、なるほど、これは「時間」の本だなと。もちろん「時間どろぼうとの戦いの話」という大筋ははっきり覚えていましたが、物語の合間合間にこんなに時間への示唆が含まれていることを改めて知りました。(当時の僕は、時間に関するこの言葉たちをどう受け止めていたんだろう?) 都会を中心に、灰色の時間どろぼうたちに奪われた人々の「時間」を、モモという少女が取り戻しにいく――名作なのであらすじはこの程度に。 いくつか、2025年現在の僕の心に響いた言葉たちを紹介します。一応、自分でも場所を忘れないように章を記しておきます。 「時間とはすなわち生活なのです。そして生活とは、人間の心の中にあるものなのです。」 6章「インチキで人をまるめこむ計算」 6章の冒頭にミヒャエル・エンデからの語りかけのような形で提示されるメッセージ(あとがきではこれも謎の人物からたくされた話だということにされますが)。 心があって初めて時間は輝くということなのでしょう。これは後半に出てくる「時間の花」にもメタファーとなって表現されます。 「時間を感じとるために心というものがある」 12章「モモ、時間の国につく」 一つ前と似ています。景色を目で見るように、音を耳で聞くように、時間を感じる主語は心だということ。 「人生でいちばん危険なことは、かなえられるはずのない夢が、かなえられてしまうことなんだよ。」 15章「再会、そしてほんとうの別れ」 ジジが時間と引き換えに手に入れた身の丈に合わない自身の名声についてつぶやきます。「時間」についてではないのですが、この歳になるとなんとなく突き刺さる言葉。 夢は目標ではなく手段であるべきなんだなと。具体的な目標があっても、大事なのはその後に手に入る「心」が本当に欲しいものなのかどうか。それが描けていないと、夢だけ手に入った抜け殻になってしまうのかもしれません。 「お前の人生の一時間、一時間が、わたしのおまえへのあいさつだ。わたしたちはいつまでも友だちだものね、そうだろう?P326」 19章「包囲のなかでの決意」 マイスター・ホラが、モモとの最後の別れの際に交わす言葉。 ホラは「時間」それ自体であり、「わたしたちは友だち」であるとモモに語りかけてきます。 いつしか山で感じたこと。それは「自分が生きているから時間が進む」という感覚。僕と時間が対等な関係であるということの自覚。 それはさらに深化させると、「時間と友達になる」ということかもしれない。過ぎ去っていく冷たいものではなく、隣にいる温かい存在として向き合うという、時間との理想の関係性をそっと示してくれたせりふでした。 さて、2025年の僕はこのような言葉たちを心に掴むことができましたが、つくづく小学生の僕はこれをどう読んだのかが気になります。割と大人でないと理解できない比喩も多い。 今回、一番考えさせられたのは、「時間どろぼう」の概念が時代を経て変わってきていることです。 現代において「時間どろぼう」という言葉で思い浮かべるのは「SNS」「ネットゲーム」「YouTube」といった、「思いがけず長時間費やしてしまう暇つぶし」でしょう。 しかし、これが書かれた1973年(日本でいうところの高度経済成長期)は、時間どろぼうが「無駄な時間の削減」「合理化」という言葉で騙し取っていたのは人々の「余白」なのです。 時間どろぼうの盗む対象が変わったと言うより、盗まれる側の認識が変わったということでしょう(「盗まれる」というより「盗ませている」に近いかもしれません)。 「合理化」「タイパ」が(異論はあれど)正義とされている現代を見ると、時間どろぼうの仕事は残念ながら成功したと言えるかもしれません。 ちなみに「余白」とは言え、「SNS」「ソシャゲ」をモモの中における「大切な時間」と結びつけづらいのは、僕の思考(嗜好)もあるのでしょうが、物語の中で盗まれていたのは「分かち合う時間」という側面が大きいのかなと。モモは、時間を分け与える存在として作中で輝いています。 誰かと話す時間、笑い合う時間、そうして時を忘れる時間――これらが「時間の花」を咲かせるのでしょう。それを上記のもので満たせるならそれは「大切な時間」に値するのでしょうが……僕が惰性で連続再生させてしまっているYouTubeに関しては、これはもう時間を奪われているというか、自ら投げ捨てている行為だなと…… 時間は支配するものではなく共存するもの、共有するもの。盗まれないように肌身離さず、心に時間の花を咲かせて生きていたいものです。 またいつか読み返すことを信じてーーモモ、ジジ、ベッポに「またね」という気持ちで本を閉じました。 本当に、「良い時間」でした。
モモミヒャエル・エンデ,大島かおり読み終わった言わずと知れたミヒャエル・エンデ著の名作。ずっと昔、小学生時代に一度だけ読んだことがあって、全体を通して「すごく面白かった」ことと、なぜか「時間停止状態において宙に浮いた綿毛までも衝突物になる危険性」が印象に残っています。 なぜ読み返そうと思ったかというと、最近ChatGPTに日記を読ませていたらふと、 「あなたの日記からは『モモ』を思い出しますね。」 と一丁前な感想を言われまして。 確かにここ数日、「自分にとっての時間との向き合い方」みたいなことを考え続けていましたが、「『モモ』ってそういう話だったっけ?」となり、思い出すために実家から回収してきました。 岩波書店のハードカバー、1995年の52刷。全面的に日焼けした古い本ですが、装丁が頑丈なのか今でも気を使うことなくページをめくれます。 上記のような漠然とした記憶しか残っていなかったのですが、「ジジ」や「ベッポ」といった主要人物の名前の響きは覚えていて、古い友人と再会した気分。ずっとこの本の中で、登場人物たちが読まれるのを待っていたんだと思うと胸が温かくなります。 読み返してみて、なるほど、これは「時間」の本だなと。もちろん「時間どろぼうとの戦いの話」という大筋ははっきり覚えていましたが、物語の合間合間にこんなに時間への示唆が含まれていることを改めて知りました。(当時の僕は、時間に関するこの言葉たちをどう受け止めていたんだろう?) 都会を中心に、灰色の時間どろぼうたちに奪われた人々の「時間」を、モモという少女が取り戻しにいく――名作なのであらすじはこの程度に。 いくつか、2025年現在の僕の心に響いた言葉たちを紹介します。一応、自分でも場所を忘れないように章を記しておきます。 「時間とはすなわち生活なのです。そして生活とは、人間の心の中にあるものなのです。」 6章「インチキで人をまるめこむ計算」 6章の冒頭にミヒャエル・エンデからの語りかけのような形で提示されるメッセージ(あとがきではこれも謎の人物からたくされた話だということにされますが)。 心があって初めて時間は輝くということなのでしょう。これは後半に出てくる「時間の花」にもメタファーとなって表現されます。 「時間を感じとるために心というものがある」 12章「モモ、時間の国につく」 一つ前と似ています。景色を目で見るように、音を耳で聞くように、時間を感じる主語は心だということ。 「人生でいちばん危険なことは、かなえられるはずのない夢が、かなえられてしまうことなんだよ。」 15章「再会、そしてほんとうの別れ」 ジジが時間と引き換えに手に入れた身の丈に合わない自身の名声についてつぶやきます。「時間」についてではないのですが、この歳になるとなんとなく突き刺さる言葉。 夢は目標ではなく手段であるべきなんだなと。具体的な目標があっても、大事なのはその後に手に入る「心」が本当に欲しいものなのかどうか。それが描けていないと、夢だけ手に入った抜け殻になってしまうのかもしれません。 「お前の人生の一時間、一時間が、わたしのおまえへのあいさつだ。わたしたちはいつまでも友だちだものね、そうだろう?P326」 19章「包囲のなかでの決意」 マイスター・ホラが、モモとの最後の別れの際に交わす言葉。 ホラは「時間」それ自体であり、「わたしたちは友だち」であるとモモに語りかけてきます。 いつしか山で感じたこと。それは「自分が生きているから時間が進む」という感覚。僕と時間が対等な関係であるということの自覚。 それはさらに深化させると、「時間と友達になる」ということかもしれない。過ぎ去っていく冷たいものではなく、隣にいる温かい存在として向き合うという、時間との理想の関係性をそっと示してくれたせりふでした。 さて、2025年の僕はこのような言葉たちを心に掴むことができましたが、つくづく小学生の僕はこれをどう読んだのかが気になります。割と大人でないと理解できない比喩も多い。 今回、一番考えさせられたのは、「時間どろぼう」の概念が時代を経て変わってきていることです。 現代において「時間どろぼう」という言葉で思い浮かべるのは「SNS」「ネットゲーム」「YouTube」といった、「思いがけず長時間費やしてしまう暇つぶし」でしょう。 しかし、これが書かれた1973年(日本でいうところの高度経済成長期)は、時間どろぼうが「無駄な時間の削減」「合理化」という言葉で騙し取っていたのは人々の「余白」なのです。 時間どろぼうの盗む対象が変わったと言うより、盗まれる側の認識が変わったということでしょう(「盗まれる」というより「盗ませている」に近いかもしれません)。 「合理化」「タイパ」が(異論はあれど)正義とされている現代を見ると、時間どろぼうの仕事は残念ながら成功したと言えるかもしれません。 ちなみに「余白」とは言え、「SNS」「ソシャゲ」をモモの中における「大切な時間」と結びつけづらいのは、僕の思考(嗜好)もあるのでしょうが、物語の中で盗まれていたのは「分かち合う時間」という側面が大きいのかなと。モモは、時間を分け与える存在として作中で輝いています。 誰かと話す時間、笑い合う時間、そうして時を忘れる時間――これらが「時間の花」を咲かせるのでしょう。それを上記のもので満たせるならそれは「大切な時間」に値するのでしょうが……僕が惰性で連続再生させてしまっているYouTubeに関しては、これはもう時間を奪われているというか、自ら投げ捨てている行為だなと…… 時間は支配するものではなく共存するもの、共有するもの。盗まれないように肌身離さず、心に時間の花を咲かせて生きていたいものです。 またいつか読み返すことを信じてーーモモ、ジジ、ベッポに「またね」という気持ちで本を閉じました。 本当に、「良い時間」でした。 - 2025年10月3日
 最初の質問いせひでこ,長田弘読み終わった一番のお気に入りの絵本故に、何冊も人にあげてしまい、手元にあるのは三冊目。 思い出したときにふと読み直しては、心の中で答えをつぶやきます。 「今日、あなたは空を見上げましたか。 空は遠かったですか、近かったですか。」 この優しい質問から始まり、身近な表現を混ぜつつ、人生にとって本当に大事な質問だけが繰り返されていきます。 「何歳のときのじぶんが好きですか。 上手に歳をとることができるとおもいますか。」 今が好きで、上手に歳をとりたいと願っています。 「問いと答えと、 いまあなたにとって必要なのはどっちですか。」 まだまだ「問い」が欲しい。答えを知ってしまうと、ワクワクがなくなってしまうから―― また、考えさせられる質問もあります。 「あなたにとって 『わたしたち』というのは、誰ですか。」 幸い、僕はこの質問に答えられる、いくつかのコミュニティを持てています。 一方で、世の中には「わたしたち」が思い浮かばない人もいるであろうことを想像し、なんとも言えない気持ちにもなります。 いせひでこさんの水彩の挿絵が見事に詩に重なっていて、質問の本質がより浮かび上がってくるようです。 全編通して淡いトーンの玉虫色の質問が投げかけられるのですが、最後だけ白黒で、筆者の警告のような質問で終わります。 「時代は言葉をないがしろにしている―― あなたは言葉を信じていますか。」 SNS等でちぎられた言葉が乱暴に投げつけられている昨今、こんなに時代を突き刺す質問は無いんじゃないでしょうか。 ちょっと質問の内容が難しいところもあるので、渡せる年齢としては小学校以上でしょうか。 年齢によって、そのときどきの気持ちによって、答えは変わってくるでしょう。万人におすすめしたい一冊です。 ちなみに、この本をあげた友人のお子さんは、これで読書感想文を書いてくれたそう。それ自体がどんな感想よりも嬉しかったです。
最初の質問いせひでこ,長田弘読み終わった一番のお気に入りの絵本故に、何冊も人にあげてしまい、手元にあるのは三冊目。 思い出したときにふと読み直しては、心の中で答えをつぶやきます。 「今日、あなたは空を見上げましたか。 空は遠かったですか、近かったですか。」 この優しい質問から始まり、身近な表現を混ぜつつ、人生にとって本当に大事な質問だけが繰り返されていきます。 「何歳のときのじぶんが好きですか。 上手に歳をとることができるとおもいますか。」 今が好きで、上手に歳をとりたいと願っています。 「問いと答えと、 いまあなたにとって必要なのはどっちですか。」 まだまだ「問い」が欲しい。答えを知ってしまうと、ワクワクがなくなってしまうから―― また、考えさせられる質問もあります。 「あなたにとって 『わたしたち』というのは、誰ですか。」 幸い、僕はこの質問に答えられる、いくつかのコミュニティを持てています。 一方で、世の中には「わたしたち」が思い浮かばない人もいるであろうことを想像し、なんとも言えない気持ちにもなります。 いせひでこさんの水彩の挿絵が見事に詩に重なっていて、質問の本質がより浮かび上がってくるようです。 全編通して淡いトーンの玉虫色の質問が投げかけられるのですが、最後だけ白黒で、筆者の警告のような質問で終わります。 「時代は言葉をないがしろにしている―― あなたは言葉を信じていますか。」 SNS等でちぎられた言葉が乱暴に投げつけられている昨今、こんなに時代を突き刺す質問は無いんじゃないでしょうか。 ちょっと質問の内容が難しいところもあるので、渡せる年齢としては小学校以上でしょうか。 年齢によって、そのときどきの気持ちによって、答えは変わってくるでしょう。万人におすすめしたい一冊です。 ちなみに、この本をあげた友人のお子さんは、これで読書感想文を書いてくれたそう。それ自体がどんな感想よりも嬉しかったです。 - 2025年9月29日
 プラネタリウムのふたごいしいしんじ読み終わった友人に薦められたこちらの本。いしいしんじさんという作者も初めましてですが、文学部出身の友人が太鼓判を押すなら間違いないだろうと。 これがまぁ……とても美しい物語でした。500ページもあるのですが、この厚みの1ページ1ページが全て美しかった。 プラネタリウムに拾われた双子、ペンテルとタットルの数奇な運命。(おそらく一卵性で)そっくりだけど、少し性格の違う2人は、ある事件を機に全く違う人生を歩み始める。タットルは村で郵便配達とプラネタリウムの語り部に、ペンテルは稀代の手品師に。 終始穏やかな起伏の物語で、たゆたう優しい時間の流れの中、ぽつりぽつりと大切なことが語られていく。 「どんな悲しい、つらいはなしの中にも、光の粒が、救いのかけらが、ほんのわずかにせよ含まれているんだよ。」 どんなに実直に、平穏な毎日を送っていても、それでも起きてほしくないことは起きてしまう。運命はタイミングを選ばない。 物語中最大の悲しみを乗り越えた先に登場人物たちが見つけた「光の粒」「救いのかけら」の美しさに駅のホームでしばらく動けなくなってしまったーー読書で本当に涙が出たのは久しぶり。 「プラネタリウム」と「手品師」の対比も素晴らしかった。永遠の奇跡と刹那の奇跡、それぞれの物語を伝える双子。どちらにも憧れ、必要とする人たちがいて、目を輝かせる。 「だまされる才覚がひとにないと、この世はかさっかさの、笑いもなにもない、どんづまりの世界になってしまう。」 星はただの光で、手品は嘘かもしれないけど、自分の世界を美しく輝かせるものなら騙されていたい。 それは「騙される」というより「信じる」に近いかもしれないけど。 僕は僕の信じる美しさを信じ続けようと思った本でした。
プラネタリウムのふたごいしいしんじ読み終わった友人に薦められたこちらの本。いしいしんじさんという作者も初めましてですが、文学部出身の友人が太鼓判を押すなら間違いないだろうと。 これがまぁ……とても美しい物語でした。500ページもあるのですが、この厚みの1ページ1ページが全て美しかった。 プラネタリウムに拾われた双子、ペンテルとタットルの数奇な運命。(おそらく一卵性で)そっくりだけど、少し性格の違う2人は、ある事件を機に全く違う人生を歩み始める。タットルは村で郵便配達とプラネタリウムの語り部に、ペンテルは稀代の手品師に。 終始穏やかな起伏の物語で、たゆたう優しい時間の流れの中、ぽつりぽつりと大切なことが語られていく。 「どんな悲しい、つらいはなしの中にも、光の粒が、救いのかけらが、ほんのわずかにせよ含まれているんだよ。」 どんなに実直に、平穏な毎日を送っていても、それでも起きてほしくないことは起きてしまう。運命はタイミングを選ばない。 物語中最大の悲しみを乗り越えた先に登場人物たちが見つけた「光の粒」「救いのかけら」の美しさに駅のホームでしばらく動けなくなってしまったーー読書で本当に涙が出たのは久しぶり。 「プラネタリウム」と「手品師」の対比も素晴らしかった。永遠の奇跡と刹那の奇跡、それぞれの物語を伝える双子。どちらにも憧れ、必要とする人たちがいて、目を輝かせる。 「だまされる才覚がひとにないと、この世はかさっかさの、笑いもなにもない、どんづまりの世界になってしまう。」 星はただの光で、手品は嘘かもしれないけど、自分の世界を美しく輝かせるものなら騙されていたい。 それは「騙される」というより「信じる」に近いかもしれないけど。 僕は僕の信じる美しさを信じ続けようと思った本でした。 - 2025年9月25日
 となりの陰謀論烏谷昌幸読み終わった新聞の書評欄にあって、興味があって買ってみました。タイトルが「となりの陰謀論」と怖いのですが、この時勢、一度くらいは読んでおく必要があるかなと。 陰謀論発生のロジックと、それが現実社会に与えうるダメージについて説いています。 「搾取されているという意識」と「世界をシンプルに見たいという欲望」が陰謀論を起こし、それを扇動する人物や、SNSという道具…… おこがましいようですが、概ね想像していた通りで、僕の思考を論理的に言語化してくれた本でした。なので、基本的に、言っていることには賛成できます。できるのですがーー 考えが一致したからと言って、首をブンブン縦に振るのは、話題からしてためらわれるのです。 これを読みながら気持ちよく「こんな馬鹿こと信じちゃって笑」と笑うことも出来るのですが、この本を100%そのまま受け入れること、それも一つの「世界のシンプル化」であって、もう一つの陰謀論的態度になりはしないかと思うのです。 読みながら文章と思考が一致して少し高揚しかけたとき、ふと疑問が浮かびます。 これは本当に「『となりの』陰謀論」なのか。となりから見た僕も、もしかしたら―― 僕が正論だと思っているもの、僕が陰謀論だと思っているもの……そもそも、僕はほとんどの情報を自分の目で見てもいないし、自分の耳で聞いたこともない。せいぜい「僕と僕の周りの幸せのためにそうあって欲しい希望」と「確からしい権威性」に頼って確率を想像することしかできない。 いくら自分にフィットしても「情報」に気持ちよくなってはいけない。「答えを得た」と思ってはいけない。 もし気持ち良くなっている自分がいたとしたら、それこそ疑うべき対象なのでしょう。 論の進め方が少し結論ありきで一直線だったかなと思います(巻末の方の原発の議論に少しだけ別な視点を書いていますが)。もちろんページ数の限られた新書なので仕方ないのですが。目的が「陰謀論を甘く見ずにきちんと向き合おう」なのでそれは達成されているとは思います。 あらゆる情報に謙虚にいようと思い直した一冊でした。この態度も著者の「向き合う」に含まれているとしたら、良い本だったと思います。
となりの陰謀論烏谷昌幸読み終わった新聞の書評欄にあって、興味があって買ってみました。タイトルが「となりの陰謀論」と怖いのですが、この時勢、一度くらいは読んでおく必要があるかなと。 陰謀論発生のロジックと、それが現実社会に与えうるダメージについて説いています。 「搾取されているという意識」と「世界をシンプルに見たいという欲望」が陰謀論を起こし、それを扇動する人物や、SNSという道具…… おこがましいようですが、概ね想像していた通りで、僕の思考を論理的に言語化してくれた本でした。なので、基本的に、言っていることには賛成できます。できるのですがーー 考えが一致したからと言って、首をブンブン縦に振るのは、話題からしてためらわれるのです。 これを読みながら気持ちよく「こんな馬鹿こと信じちゃって笑」と笑うことも出来るのですが、この本を100%そのまま受け入れること、それも一つの「世界のシンプル化」であって、もう一つの陰謀論的態度になりはしないかと思うのです。 読みながら文章と思考が一致して少し高揚しかけたとき、ふと疑問が浮かびます。 これは本当に「『となりの』陰謀論」なのか。となりから見た僕も、もしかしたら―― 僕が正論だと思っているもの、僕が陰謀論だと思っているもの……そもそも、僕はほとんどの情報を自分の目で見てもいないし、自分の耳で聞いたこともない。せいぜい「僕と僕の周りの幸せのためにそうあって欲しい希望」と「確からしい権威性」に頼って確率を想像することしかできない。 いくら自分にフィットしても「情報」に気持ちよくなってはいけない。「答えを得た」と思ってはいけない。 もし気持ち良くなっている自分がいたとしたら、それこそ疑うべき対象なのでしょう。 論の進め方が少し結論ありきで一直線だったかなと思います(巻末の方の原発の議論に少しだけ別な視点を書いていますが)。もちろんページ数の限られた新書なので仕方ないのですが。目的が「陰謀論を甘く見ずにきちんと向き合おう」なのでそれは達成されているとは思います。 あらゆる情報に謙虚にいようと思い直した一冊でした。この態度も著者の「向き合う」に含まれているとしたら、良い本だったと思います。 - 2025年9月11日
 広島へ行く前に買った若松英輔さんの詩集の中でその名前を知り、その旅先の尾道の小さな書店にたまたま置いてありました。ここまでが綺麗すぎて、本当に導かれている感覚でした。 坂の上に立つ部屋から尾道を見下ろしながら、滞在中1週間かけて読みました。良い作品集だと思いました―― ――思ったのですが、僕の心まで詩が降りてこないものも多くて。かなり具体を言っているのだけど、想像が追いつかない。自分の黙読の声だけが頭を通り過ぎていってしまっているような。 当時、とてもじゃないけど、これの感想文は書けないなと思いました。自分の日記としても、おこがましいと。 そこからハンセン病に興味を持ち、東京の実家の近くに国立ハンセン病資料館があることを知り、先日やっと訪れることができたわけです。 かれこれ一年ぶり、これを機にもう一度読んでみました。すると―― 前より文字が濃く感じました。筆圧を感じました。 自分のではない声が聞こえました。 文字からうっすら言葉が浮かび上がってきました。 ――気のせいかもしれません。 それでもやはり、まだ分からない言葉が、心を通り過ぎていきます。 もちろん詩は理解するものではなく感じるものです。 でも、彼の作品はそれだけじゃ足りないと思ってしまう。その生い立ち・境遇・背景から想像を膨らませてはじめて、触れられる言葉があると思うのです。 ――そういう、普通の詩人と違うアプローチをしていること自体が差別じゃないか、という疑問・自省も感じます。 矛盾を感じてなお、もっと声を聞きたい、言葉を感じたいと思ってしまう。そう思ってしまうのは、彼がハンセン病患者だったからではなく、彼がこの言葉の持ち主だから。 僕は志樹逸馬を知りたい。 今夜も結局まだ知らないことがありすぎて、多くの言葉に触れられなかったことがもどかしい。 また色んなことを経験した後に、読み直そうと思います。 そのときにはもっと本から声がして、その言葉を心から受け取れるような人間になれていたら嬉しい。
広島へ行く前に買った若松英輔さんの詩集の中でその名前を知り、その旅先の尾道の小さな書店にたまたま置いてありました。ここまでが綺麗すぎて、本当に導かれている感覚でした。 坂の上に立つ部屋から尾道を見下ろしながら、滞在中1週間かけて読みました。良い作品集だと思いました―― ――思ったのですが、僕の心まで詩が降りてこないものも多くて。かなり具体を言っているのだけど、想像が追いつかない。自分の黙読の声だけが頭を通り過ぎていってしまっているような。 当時、とてもじゃないけど、これの感想文は書けないなと思いました。自分の日記としても、おこがましいと。 そこからハンセン病に興味を持ち、東京の実家の近くに国立ハンセン病資料館があることを知り、先日やっと訪れることができたわけです。 かれこれ一年ぶり、これを機にもう一度読んでみました。すると―― 前より文字が濃く感じました。筆圧を感じました。 自分のではない声が聞こえました。 文字からうっすら言葉が浮かび上がってきました。 ――気のせいかもしれません。 それでもやはり、まだ分からない言葉が、心を通り過ぎていきます。 もちろん詩は理解するものではなく感じるものです。 でも、彼の作品はそれだけじゃ足りないと思ってしまう。その生い立ち・境遇・背景から想像を膨らませてはじめて、触れられる言葉があると思うのです。 ――そういう、普通の詩人と違うアプローチをしていること自体が差別じゃないか、という疑問・自省も感じます。 矛盾を感じてなお、もっと声を聞きたい、言葉を感じたいと思ってしまう。そう思ってしまうのは、彼がハンセン病患者だったからではなく、彼がこの言葉の持ち主だから。 僕は志樹逸馬を知りたい。 今夜も結局まだ知らないことがありすぎて、多くの言葉に触れられなかったことがもどかしい。 また色んなことを経験した後に、読み直そうと思います。 そのときにはもっと本から声がして、その言葉を心から受け取れるような人間になれていたら嬉しい。 - 2025年9月11日
 この会社は実在しません(1)ヨシモト・ミネホラーは苦手なのですが、登場人物視点の資料がかなり小説なので、そこのスピード感で一気に読めました。 それが、モキュメンタリーとしてどうなのかは置いといて……とても楽しいエンタメでした!
この会社は実在しません(1)ヨシモト・ミネホラーは苦手なのですが、登場人物視点の資料がかなり小説なので、そこのスピード感で一気に読めました。 それが、モキュメンタリーとしてどうなのかは置いといて……とても楽しいエンタメでした! - 2025年9月10日
 立体と鏡像で読み解く生命の仕組み黒栁正典読み終わった誤解しないで欲しいのはこの本は例外的に読んだもので、ふだんからこんなテーマの読書をしているわけではありません……たまたま昨日読み終えたのがこれだったというだけです。 最近の読書において「紀伊国屋ルーレット」というものを作成して、ランダムに選ばれた本棚から本を一冊選ぶということをやっています(この遊びに関してはまた後日)。 当初はこれで意識外の本に出会えるぞとワクワクしていたのですが……かれこれ10回ほど回していますが、このルーレットは毎回僕に試練ばかり与えてきます。 今回当たった番号の棚の前へ行き「有機化学」のジャンル名を見たときは絶望でした。学生時代から科学・化学は本当に苦手だったので。 その中から、辛うじて興味を持てたのがこちらの「立体と鏡像で読み解く生命の仕組み」です。 地球の生物の普遍の原則「ホモキラリティー」をテーマに、地球でこうして生きている奇跡を学ぶ。ちょっと前に歴史の本を読んだばかりだったので、そこからさらに生命誕生・分子レベルにまでズームアウト(ズームイン?)するような感覚でした。 立体構造である分子にはD型とL型の鏡像異性体が存在するはずですが、人類含め生物はもれなく(D-アミノ酸ではなく)L-アミノ酸だけで構成され、エネルギー源としては(L-糖ではなく)D-糖だけを摂取して生きている――この謎に迫ろうというのが本筋です。 まず地球にどうやって生物が誕生したのか。海底の熱による化学反応か、はたまた隕石に付着していた物質か――導入からもう壮大で、少し眩暈がします。 幾多の化学者がこれに挑みましたが、説得力のあるものを発見するまでで、「これ」という決定的なことは分かっていません。 なお、これを「化学進化」というらしいです。読んでも「らしい」という自信のない語尾しか使えないことをご了承ください…… そこから上記のホモキラリティーが成立するまでの過程もよく分かっていません。 結果、ホモキラリティーの方がエネルギー補給や遺伝等、生存に都合が良かったのですが、それはあくまで「結果論」であって、どの時点からそれが起きてどういうスピードで鏡像異性体の反対側の分子が弾かれていったのかは謎のままです。 化学門外漢の僕にはっきり分かったのは、巨大な奇跡が2回起きたということだけです。 そのことだけでも、どれほどの確率の上に今の自分が成り立っているかを感じるには十分な読書でした。 例えば、上記の「化学進化」にしろ「ホモキラリティー」にしろ、それらの最初の奇跡の反応が1年――いえ、1秒遅れていただけで、現在の地球上の生物の構成は全く違ったものになっていたでしょう。 人間もどの生き物も、無限分の一の奇跡の上に存在していて、そういう視点から見ると何もかも平等に感じます。 僕もあなた、町ですれ違った人もテレビに映る有名人も、みんな同じ奇跡的L-アミノ酸の結晶体です。 「化学の大きな謎に迫ってみよう」という知的欲求の本筋とは違う心の着地かもしれませんが、とても壮大で面白い体験ができました。ありがとう、ルーレット。 ――ただ、次はもっと守備範囲内の読書になれば良いなと思います。 追伸: 章末のコラムの中に「セレンディピティ」という言葉の解説がありました。「思いがけない発見」「意図したものとは違う予想外の発見」といった意味です。(ちなみに元ネタは「セレンディップの3人の王子」という物語) ルーレットでこの本に出会えたのもセレンディピティ。「セレンディピティ」という言葉に出会えたこと自体もセレンディピティ。 これからの人生もたくさんのセレンディピティに出会えますように。
立体と鏡像で読み解く生命の仕組み黒栁正典読み終わった誤解しないで欲しいのはこの本は例外的に読んだもので、ふだんからこんなテーマの読書をしているわけではありません……たまたま昨日読み終えたのがこれだったというだけです。 最近の読書において「紀伊国屋ルーレット」というものを作成して、ランダムに選ばれた本棚から本を一冊選ぶということをやっています(この遊びに関してはまた後日)。 当初はこれで意識外の本に出会えるぞとワクワクしていたのですが……かれこれ10回ほど回していますが、このルーレットは毎回僕に試練ばかり与えてきます。 今回当たった番号の棚の前へ行き「有機化学」のジャンル名を見たときは絶望でした。学生時代から科学・化学は本当に苦手だったので。 その中から、辛うじて興味を持てたのがこちらの「立体と鏡像で読み解く生命の仕組み」です。 地球の生物の普遍の原則「ホモキラリティー」をテーマに、地球でこうして生きている奇跡を学ぶ。ちょっと前に歴史の本を読んだばかりだったので、そこからさらに生命誕生・分子レベルにまでズームアウト(ズームイン?)するような感覚でした。 立体構造である分子にはD型とL型の鏡像異性体が存在するはずですが、人類含め生物はもれなく(D-アミノ酸ではなく)L-アミノ酸だけで構成され、エネルギー源としては(L-糖ではなく)D-糖だけを摂取して生きている――この謎に迫ろうというのが本筋です。 まず地球にどうやって生物が誕生したのか。海底の熱による化学反応か、はたまた隕石に付着していた物質か――導入からもう壮大で、少し眩暈がします。 幾多の化学者がこれに挑みましたが、説得力のあるものを発見するまでで、「これ」という決定的なことは分かっていません。 なお、これを「化学進化」というらしいです。読んでも「らしい」という自信のない語尾しか使えないことをご了承ください…… そこから上記のホモキラリティーが成立するまでの過程もよく分かっていません。 結果、ホモキラリティーの方がエネルギー補給や遺伝等、生存に都合が良かったのですが、それはあくまで「結果論」であって、どの時点からそれが起きてどういうスピードで鏡像異性体の反対側の分子が弾かれていったのかは謎のままです。 化学門外漢の僕にはっきり分かったのは、巨大な奇跡が2回起きたということだけです。 そのことだけでも、どれほどの確率の上に今の自分が成り立っているかを感じるには十分な読書でした。 例えば、上記の「化学進化」にしろ「ホモキラリティー」にしろ、それらの最初の奇跡の反応が1年――いえ、1秒遅れていただけで、現在の地球上の生物の構成は全く違ったものになっていたでしょう。 人間もどの生き物も、無限分の一の奇跡の上に存在していて、そういう視点から見ると何もかも平等に感じます。 僕もあなた、町ですれ違った人もテレビに映る有名人も、みんな同じ奇跡的L-アミノ酸の結晶体です。 「化学の大きな謎に迫ってみよう」という知的欲求の本筋とは違う心の着地かもしれませんが、とても壮大で面白い体験ができました。ありがとう、ルーレット。 ――ただ、次はもっと守備範囲内の読書になれば良いなと思います。 追伸: 章末のコラムの中に「セレンディピティ」という言葉の解説がありました。「思いがけない発見」「意図したものとは違う予想外の発見」といった意味です。(ちなみに元ネタは「セレンディップの3人の王子」という物語) ルーレットでこの本に出会えたのもセレンディピティ。「セレンディピティ」という言葉に出会えたこと自体もセレンディピティ。 これからの人生もたくさんのセレンディピティに出会えますように。
読み込み中...
