りょう
@ryozy
- 2026年2月1日
 ブレイクショットの軌跡逢坂冬馬読み終わった読み始めた今年一冊目の小説。昨年該当なしだった直木賞の候補作品だったはず。 まだ途中なのでどこに落ち着くのかまったく想像できないけれど、先へ先へと読み進めてしまう展開。登場人物も場面も多いけれど、それぞれのエピソードが映像のように目の前に立ち上がる描写が秀逸。 読み終えた時にまた印象が変わるのかもしれないけれど、まずは途中の備忘録として。 〈読了後〉 最終盤で、群像で展開されていた話がすべてつながる。 最後になってそれまで点線だったものがつながり、この本自体が「ブレイクショットの軌跡」を読者に辿らせる仕掛けだったと気づかされた。 「ブレイクショット」は、ビリヤードの9ボールの最初の一打であり、本作では重要なアイテムであり仕掛けとなっている車の名前だ。 偶然とも必然とも言える世界で僕たちは生きている。 まぐれといえばまぐれだし、実力といえば実力。 その境界のグラデーションの中で、本作の登場人物たちもまた生きている。 身近な誰にでも感情移入できるわけもないのと同じように、この登場人物たちにも必ずしも共感できるわけではない。けれど、同じ世界線を生きていることは分かる。だからこそ、より生々しく感じられるのかもしれない。 本当にすべてがフィクションなのか。いや、そうでもないかもしれないことを、作者が隠そうとしていないところが数カ所感じ取れる。 読書中の疾走感といい、読後のさわやかさといい、一級のエンターテイメントだと思う。映像化は、しないでおいてほしい。
ブレイクショットの軌跡逢坂冬馬読み終わった読み始めた今年一冊目の小説。昨年該当なしだった直木賞の候補作品だったはず。 まだ途中なのでどこに落ち着くのかまったく想像できないけれど、先へ先へと読み進めてしまう展開。登場人物も場面も多いけれど、それぞれのエピソードが映像のように目の前に立ち上がる描写が秀逸。 読み終えた時にまた印象が変わるのかもしれないけれど、まずは途中の備忘録として。 〈読了後〉 最終盤で、群像で展開されていた話がすべてつながる。 最後になってそれまで点線だったものがつながり、この本自体が「ブレイクショットの軌跡」を読者に辿らせる仕掛けだったと気づかされた。 「ブレイクショット」は、ビリヤードの9ボールの最初の一打であり、本作では重要なアイテムであり仕掛けとなっている車の名前だ。 偶然とも必然とも言える世界で僕たちは生きている。 まぐれといえばまぐれだし、実力といえば実力。 その境界のグラデーションの中で、本作の登場人物たちもまた生きている。 身近な誰にでも感情移入できるわけもないのと同じように、この登場人物たちにも必ずしも共感できるわけではない。けれど、同じ世界線を生きていることは分かる。だからこそ、より生々しく感じられるのかもしれない。 本当にすべてがフィクションなのか。いや、そうでもないかもしれないことを、作者が隠そうとしていないところが数カ所感じ取れる。 読書中の疾走感といい、読後のさわやかさといい、一級のエンターテイメントだと思う。映像化は、しないでおいてほしい。 - 2026年1月29日
 「風の谷」という希望安宅和人まだ読んでる
「風の谷」という希望安宅和人まだ読んでる - 2025年6月22日
 すべての音に祝福を白石美雪読み終わった
すべての音に祝福を白石美雪読み終わった - 2025年6月20日
 東大ファッション論集中講義平芳裕子読み終わった
東大ファッション論集中講義平芳裕子読み終わった - 2025年6月4日
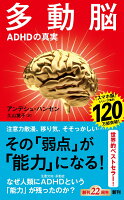 多動脳アンデシュ・ハンセン,久山葉子読み終わった
多動脳アンデシュ・ハンセン,久山葉子読み終わった - 2025年5月24日
 旅屋おかえり (集英社文庫)原田マハ読み終わった
旅屋おかえり (集英社文庫)原田マハ読み終わった - 2025年5月24日
 北大路魯山人 (下巻)白崎秀雄読み終わった
北大路魯山人 (下巻)白崎秀雄読み終わった - 2025年5月13日
 北大路魯山人(上巻)白崎秀雄読み終わった
北大路魯山人(上巻)白崎秀雄読み終わった - 2025年5月5日
 青を泳ぐ。杉谷麻衣読み終わった
青を泳ぐ。杉谷麻衣読み終わった - 2025年5月3日
 古事記(下)次田真幸読み終わった今月下旬に山陰に出かけるので、ながらく積読だったシリーズを手に取った。上中下巻に分かれており、なじみのある話や登場人物で、比較的読みやすいのは上巻。 出雲の黄泉比良坂など、初めて知る地名が多く、旅の途中で立ち寄ってみたくなった。 現代のコンプライアンスに当てはめると、古代の神々のふるまいは映像化できそうにないので、やはり本で読むのが一番かも。
古事記(下)次田真幸読み終わった今月下旬に山陰に出かけるので、ながらく積読だったシリーズを手に取った。上中下巻に分かれており、なじみのある話や登場人物で、比較的読みやすいのは上巻。 出雲の黄泉比良坂など、初めて知る地名が多く、旅の途中で立ち寄ってみたくなった。 現代のコンプライアンスに当てはめると、古代の神々のふるまいは映像化できそうにないので、やはり本で読むのが一番かも。 - 2025年5月3日
 古事記(中)次田真幸読み終わった
古事記(中)次田真幸読み終わった - 2025年5月3日
- 2025年5月3日
- 2025年5月3日
 知性の限界高橋昌一郎読み終わった
知性の限界高橋昌一郎読み終わった - 2025年4月30日
 ものがたりの余白ミヒャエル・エンデ,田村都志夫読み終わったエンデと、翻訳者で友人の田村都志夫との座談を書き起こした本。対話、というよりもエンデの語りに主眼がある。 前半は書くことについて。『モモ』の作者であるエンデが、物語というものをどのように考えていたのか。興味深い話がつづく。 白眉は最後半の「死について」だろうか。精神世界について深入りした部分は理解がまだ追いつかないので、すこし時間を置いて再読したい。 『モモ』を、あらためて読み直したくなった。
ものがたりの余白ミヒャエル・エンデ,田村都志夫読み終わったエンデと、翻訳者で友人の田村都志夫との座談を書き起こした本。対話、というよりもエンデの語りに主眼がある。 前半は書くことについて。『モモ』の作者であるエンデが、物語というものをどのように考えていたのか。興味深い話がつづく。 白眉は最後半の「死について」だろうか。精神世界について深入りした部分は理解がまだ追いつかないので、すこし時間を置いて再読したい。 『モモ』を、あらためて読み直したくなった。 - 2025年4月29日
- 2025年4月28日
 デジタル・ミニマリスト スマホに依存しない生き方カル・ニューポート,池田真紀子読み終わったいつのまにか、スマホを手にしている時間が長くなっていることが気になっていた。 依存症とまでは自覚していないけれど、「スマホに依存しない生き方」の副題に惹かれて購入。結果、本当に読後の「生き方」が変わるかもしれない。そんな読書体験になった。 本書では、まずソーシャルメディアについて、「常時つながっていることと引き換えに、自覚のないまま法外な代償を支払っている」と指摘する。 たしかに、身に覚えがある。 そこで、デジタルテクノロジーを使う時間を大幅に減らす、「デジタルミニマリスト」への道を説くわけだけれど、これは一時的にデジタル断ちをする「デジタルデトックス」とは異なる。もっと根本的に、自身の生き方、哲学を再確認することで、これまでソーシャルメディア企業に無意識のうちに奉じていた自分の時間を取り戻そうというものだ。 それは「孤独」ー自分の思考が他者のインプットから切り離された意識の状態ーを取り戻すことでもある。 デジタルミニマリストへの道は、デジタル断ちが目的なのではなく、自身の生き方への手段なのだった。 読み終えて、さっそくスマホからいくつものアプリを削除した。SNSで「いいね」をするのを止め(本書で勧められている)てみた。 代わりに本を読む時間が増え、書き物をする余裕ができた。 SNS以前に戻しただけのようにも思うけれど、まずはここから。時間が経つほどに、これまでと違った成果が出るような気がしている。
デジタル・ミニマリスト スマホに依存しない生き方カル・ニューポート,池田真紀子読み終わったいつのまにか、スマホを手にしている時間が長くなっていることが気になっていた。 依存症とまでは自覚していないけれど、「スマホに依存しない生き方」の副題に惹かれて購入。結果、本当に読後の「生き方」が変わるかもしれない。そんな読書体験になった。 本書では、まずソーシャルメディアについて、「常時つながっていることと引き換えに、自覚のないまま法外な代償を支払っている」と指摘する。 たしかに、身に覚えがある。 そこで、デジタルテクノロジーを使う時間を大幅に減らす、「デジタルミニマリスト」への道を説くわけだけれど、これは一時的にデジタル断ちをする「デジタルデトックス」とは異なる。もっと根本的に、自身の生き方、哲学を再確認することで、これまでソーシャルメディア企業に無意識のうちに奉じていた自分の時間を取り戻そうというものだ。 それは「孤独」ー自分の思考が他者のインプットから切り離された意識の状態ーを取り戻すことでもある。 デジタルミニマリストへの道は、デジタル断ちが目的なのではなく、自身の生き方への手段なのだった。 読み終えて、さっそくスマホからいくつものアプリを削除した。SNSで「いいね」をするのを止め(本書で勧められている)てみた。 代わりに本を読む時間が増え、書き物をする余裕ができた。 SNS以前に戻しただけのようにも思うけれど、まずはここから。時間が経つほどに、これまでと違った成果が出るような気がしている。 - 2025年4月24日
- 2025年4月23日
 読み終わった来月、山陰を訪れることになった。 鳥取・島根には3日間ほど滞在する。せっかくなので、こうした機会でもなければなかなか読めない『古事記』に予習がてら手をのばしたりしている。 足立美術館や出雲大社、石見銀山など、行ってみたいところをリストアップしていくうちに思い出したのが、司馬遼太郎の『街道をゆく』シリーズだ。 本書で描かれるのは鳥取県東部の因幡と西部の伯耆。知らなかった地名が次々と出てくるので、この機会に辿ってみたい道が増えてくる。 「低い山々が堤のようにこの小型の湖をかこみ、池中には七つの小島がうかんで、昔噺(むかしばなし)のなかの王国に入ってきたようにうつくしい」 リストはもういっぱいなのだけれど、こんな描写をされる風景には足を運んでみたくなってしまう。旅の時期が1985年5月ということなので、ちょうど40年後の風景を追うことになりそうだ。 聖地巡礼といえば、そうかもしれない。
読み終わった来月、山陰を訪れることになった。 鳥取・島根には3日間ほど滞在する。せっかくなので、こうした機会でもなければなかなか読めない『古事記』に予習がてら手をのばしたりしている。 足立美術館や出雲大社、石見銀山など、行ってみたいところをリストアップしていくうちに思い出したのが、司馬遼太郎の『街道をゆく』シリーズだ。 本書で描かれるのは鳥取県東部の因幡と西部の伯耆。知らなかった地名が次々と出てくるので、この機会に辿ってみたい道が増えてくる。 「低い山々が堤のようにこの小型の湖をかこみ、池中には七つの小島がうかんで、昔噺(むかしばなし)のなかの王国に入ってきたようにうつくしい」 リストはもういっぱいなのだけれど、こんな描写をされる風景には足を運んでみたくなってしまう。旅の時期が1985年5月ということなので、ちょうど40年後の風景を追うことになりそうだ。 聖地巡礼といえば、そうかもしれない。 - 2025年4月20日
 「謙虚な人」の作戦帳ジル・チャン,中村加代子読み終わった前作『「静かな人」の戦略書』の著者による本。 目立つことに抵抗がある人が、表に出ることが良しとされる社会でどのように考え、行動するとよいのか。そのヒントが紹介されている。 本書の一つ一つの指針はもちろん、「インポスター症候群」あるいは「ニセモノ思考」になびきがちな、自分のような人が少なくないことを知れたことが、この先の行動を起こす場面で背中を押してくれるような気がする。 YouTubeに、著者のインタビュー動画もいくつかあった。合わせて見ると、さらに理解がすすみそうだ。
「謙虚な人」の作戦帳ジル・チャン,中村加代子読み終わった前作『「静かな人」の戦略書』の著者による本。 目立つことに抵抗がある人が、表に出ることが良しとされる社会でどのように考え、行動するとよいのか。そのヒントが紹介されている。 本書の一つ一つの指針はもちろん、「インポスター症候群」あるいは「ニセモノ思考」になびきがちな、自分のような人が少なくないことを知れたことが、この先の行動を起こす場面で背中を押してくれるような気がする。 YouTubeに、著者のインタビュー動画もいくつかあった。合わせて見ると、さらに理解がすすみそうだ。
読み込み中...

