
たまお
@tamao
たまお/齊藤珠美
- 2026年1月7日
 文化の窮状ジェイムズ・クリフォード,太田好信読んでる生成の文脈を把握するため。 途中のみ飛ばしながら読む 前半:マリノフスキーはじめさまざまなエスノグラフィーを批判的に読み解く。 後半:裁判の傍聴。 例えば伝統的な民族が、伝統的な衣装を使わず、現代的なものを身に着けていることで、伝統的な民族と認められないこと。 大学図書館にて借りる
文化の窮状ジェイムズ・クリフォード,太田好信読んでる生成の文脈を把握するため。 途中のみ飛ばしながら読む 前半:マリノフスキーはじめさまざまなエスノグラフィーを批判的に読み解く。 後半:裁判の傍聴。 例えば伝統的な民族が、伝統的な衣装を使わず、現代的なものを身に着けていることで、伝統的な民族と認められないこと。 大学図書館にて借りる - 2026年1月7日
 分解の哲学藤原辰史読んでる
分解の哲学藤原辰史読んでる - 2026年1月7日
 社会学の基本 デュルケームの論点中島道男,デュルケーム/デュルケーム学派研究会,小川伸彦,山田陽子,岡崎宏樹読んでる途中まで デュルケムの思想を、いくつかの書籍をまたいで、前後の社会学者と比較しながら解説しているためわかりやすい 大学図書館にて借りる
社会学の基本 デュルケームの論点中島道男,デュルケーム/デュルケーム学派研究会,小川伸彦,山田陽子,岡崎宏樹読んでる途中まで デュルケムの思想を、いくつかの書籍をまたいで、前後の社会学者と比較しながら解説しているためわかりやすい 大学図書館にて借りる - 2025年4月24日
 草の花福永武彦読みたい
草の花福永武彦読みたい - 2025年4月24日
 社会学入門佐藤哲彦,盛山和夫,金明秀,難波功士買った読み始めた社会学の専門書購読をする必要があるのだが、自分に基本的な社会学の知識が不足していることに気がつき、慌てて探した買いました。 いくつか初心者向けの入門書はあったが、いちばんしっかり紹介しているのがこちらだと感じた。イラストなどは使わずテキストでしっかり解説してくれているのも選んだポイント。 ジェンダー、公共性、階層、地域社会、福祉、貧困、犯罪…などなど、社会学の必須の概念を、それぞれの簡単な経緯を踏まえて書かれているのでとてもよい。 また、重要な語句は英語の表記もあるのでありがたい。 300ページごえとすこし重めではあるけれども、ふわっと覚えても後で困ることが多いので、しっかり読んである程度噛み砕いておけると色々と後の自分の研究や、議論の土台として活かせそうだと思う。
社会学入門佐藤哲彦,盛山和夫,金明秀,難波功士買った読み始めた社会学の専門書購読をする必要があるのだが、自分に基本的な社会学の知識が不足していることに気がつき、慌てて探した買いました。 いくつか初心者向けの入門書はあったが、いちばんしっかり紹介しているのがこちらだと感じた。イラストなどは使わずテキストでしっかり解説してくれているのも選んだポイント。 ジェンダー、公共性、階層、地域社会、福祉、貧困、犯罪…などなど、社会学の必須の概念を、それぞれの簡単な経緯を踏まえて書かれているのでとてもよい。 また、重要な語句は英語の表記もあるのでありがたい。 300ページごえとすこし重めではあるけれども、ふわっと覚えても後で困ることが多いので、しっかり読んである程度噛み砕いておけると色々と後の自分の研究や、議論の土台として活かせそうだと思う。 - 2025年4月24日
- 2025年4月22日
 チーズの世界史木榑博読んでる読み始めた半分ぐらい読んだが、とても面白い。 世界史に出てきた、『ポエニ戦争」『ゲルマン人の大移動』『太陽王』みたいな、聞いたことけどなんか忘れちゃったな…みたいなキーワードが、色んなチーズと共に次々と登場してくる。楽しい。 チーズが栄養価が高く、保存が効くので戦争の常備食とされていたという話は「なるほどな」と納得。 フランスの王様とチーズ伝説みたいなのが色々あって、王子の怪我が治ったとか、チーズの皮の部分を王様がとりのぞいてたらそこを食べろと言われたとか。 びっくりしたのがロックフォールチーズは今もロックフォール=シュル=スールゾン村の洞窟でつくられているという話。洞窟というのがにわかに信じられなくて(ごめんなさい)、調べてみたのだがAOC制度で守られているので本当だった。すごいー! 洞窟、いつか見に行ってみたいなあ。 半分ぐらい読んで、これから3章で東方パートになるようです。こちらも楽しみ。 新書ならではで、わかりやすく、読みやすい。
チーズの世界史木榑博読んでる読み始めた半分ぐらい読んだが、とても面白い。 世界史に出てきた、『ポエニ戦争」『ゲルマン人の大移動』『太陽王』みたいな、聞いたことけどなんか忘れちゃったな…みたいなキーワードが、色んなチーズと共に次々と登場してくる。楽しい。 チーズが栄養価が高く、保存が効くので戦争の常備食とされていたという話は「なるほどな」と納得。 フランスの王様とチーズ伝説みたいなのが色々あって、王子の怪我が治ったとか、チーズの皮の部分を王様がとりのぞいてたらそこを食べろと言われたとか。 びっくりしたのがロックフォールチーズは今もロックフォール=シュル=スールゾン村の洞窟でつくられているという話。洞窟というのがにわかに信じられなくて(ごめんなさい)、調べてみたのだがAOC制度で守られているので本当だった。すごいー! 洞窟、いつか見に行ってみたいなあ。 半分ぐらい読んで、これから3章で東方パートになるようです。こちらも楽しみ。 新書ならではで、わかりやすく、読みやすい。 - 2025年4月6日
 甘さと権力シドニー・W・ミンツ,和田光弘,川北稔読み終わった資本主義がどうやって誕生したのか、 その誕生の裏では何が進行していたのか。 『砂糖』というひとつのモノを軸とし、 ◎生産ー中南米のサトウキビ生産者 ◎消費ー砂糖入紅茶を飲むイギリスの労働者階級 具体的な時代、場所をとりあげながら、世界的に流通する商品がわたしたちの生産と消費をどう変えたのかを読み解く名作だと思う。 ミンツはアメリカの人類学者で、実際にプエルト・リコのサトウキビ農園で働いた経験がある。この本ではその現場の話はほぼ出てこない。それにより、ここで語られていることが砂糖に限らずさまざまなモノ、世界的に流通する商品にあてはまることを考えさせられた。
甘さと権力シドニー・W・ミンツ,和田光弘,川北稔読み終わった資本主義がどうやって誕生したのか、 その誕生の裏では何が進行していたのか。 『砂糖』というひとつのモノを軸とし、 ◎生産ー中南米のサトウキビ生産者 ◎消費ー砂糖入紅茶を飲むイギリスの労働者階級 具体的な時代、場所をとりあげながら、世界的に流通する商品がわたしたちの生産と消費をどう変えたのかを読み解く名作だと思う。 ミンツはアメリカの人類学者で、実際にプエルト・リコのサトウキビ農園で働いた経験がある。この本ではその現場の話はほぼ出てこない。それにより、ここで語られていることが砂糖に限らずさまざまなモノ、世界的に流通する商品にあてはまることを考えさせられた。 - 2025年3月9日
 聞き書ふるさとの家庭料理(1)農山漁村文化協会ちょっと開いたふるさとの家庭料理 第1巻「すし なれすし」。現代すしと言えば握り寿司がイメージされるが、全国の押しずし、まぜすし、なれずしは魚や山菜や漬物などその地域の産物が使われている。見ているだけで、四季の山や海、日本列島の多種多様な風土がイメージされる。離れた場所で似たような寿司があるのもおもしろいが、これは海路で伝わったものかもしれない。混ぜすしにフォーカスするのも面白そうだ。
聞き書ふるさとの家庭料理(1)農山漁村文化協会ちょっと開いたふるさとの家庭料理 第1巻「すし なれすし」。現代すしと言えば握り寿司がイメージされるが、全国の押しずし、まぜすし、なれずしは魚や山菜や漬物などその地域の産物が使われている。見ているだけで、四季の山や海、日本列島の多種多様な風土がイメージされる。離れた場所で似たような寿司があるのもおもしろいが、これは海路で伝わったものかもしれない。混ぜすしにフォーカスするのも面白そうだ。 - 2025年3月7日
 マンゴーと手榴弾岸政彦気になる
マンゴーと手榴弾岸政彦気になる - 2025年3月7日
 なぜふつうに食べられないのか磯野真穂買った
なぜふつうに食べられないのか磯野真穂買った - 2025年3月7日
 アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?カトリーン・キラス=マルサル,高橋璃子まだ読んでるタイトルが面白いなと思って(あんまり中身を見ずに)買った。パラパラ読みしたところ。料理や家事の担い手の話かと思ったのだが、フェミニズムの視点を取り入れた経済の話だった。これはネタバレになるかもなのたが、アダム・スミスの夕食を作ったのは、アダム・スミスのお母さんらしい。こういう歴史上見えない女性の存在というのは、ヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』にもあったので面白いなと感じた。もうちょっとパラ読みする予定。
アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?カトリーン・キラス=マルサル,高橋璃子まだ読んでるタイトルが面白いなと思って(あんまり中身を見ずに)買った。パラパラ読みしたところ。料理や家事の担い手の話かと思ったのだが、フェミニズムの視点を取り入れた経済の話だった。これはネタバレになるかもなのたが、アダム・スミスの夕食を作ったのは、アダム・スミスのお母さんらしい。こういう歴史上見えない女性の存在というのは、ヴァージニア・ウルフの『自分ひとりの部屋』にもあったので面白いなと感じた。もうちょっとパラ読みする予定。 - 2025年3月7日
 儀礼の過程ヴィクター・W・ターナー,冨倉光雄まだ読んでる3分の2まで読んだところ。 中央アフリカのンデンブ族の儀式を中心に、構造と対立するリミナリティとコムニタスのあり方を定義したところまで。 次の4章では、コムニタスの概念をアフリカを離れて、中世ヨーロッパの修道会や15世紀インドの宗教活動にも当てはめて検討することになるようだ。
儀礼の過程ヴィクター・W・ターナー,冨倉光雄まだ読んでる3分の2まで読んだところ。 中央アフリカのンデンブ族の儀式を中心に、構造と対立するリミナリティとコムニタスのあり方を定義したところまで。 次の4章では、コムニタスの概念をアフリカを離れて、中世ヨーロッパの修道会や15世紀インドの宗教活動にも当てはめて検討することになるようだ。 - 2025年3月6日
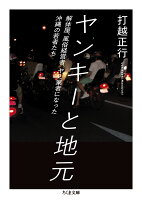 ヤンキーと地元打越正行読み終わった閉ざされた沖縄の地元コミュニティで、理不尽にも思えるルールや習慣に添いながら、ときに抗いながら生きる若者たち。丹念に拾いあげられた言葉のひとつひとつから、それぞれの選択と生活がナマの手触りをもって伝わってきた。 暴走族、セクキャバ、建設会社…例えば先輩・後輩の上下関係や暴力には、今の一般的な社会規範ではあり得ないことだろう。しかし筆者はけして批判的な目線を持ち込まず、どのような背景や力学で暴力がふるわれ、ふるわれた側はそれをどう受け止めているのかを記述している。 これは筆者である打越さんが、"パシリ"という立場をとって、暴走族の若者たちのあとを原付で追いかけながら、長年実践したフィールドワークで得られたものである。 登場する人物はけして美化されてはいない。また置かれている過酷な環境でもあるが、それぞれの人生がこの先が気になるほど、葛藤やそのなかで行われる選択は、実感を持って描かれていた。
ヤンキーと地元打越正行読み終わった閉ざされた沖縄の地元コミュニティで、理不尽にも思えるルールや習慣に添いながら、ときに抗いながら生きる若者たち。丹念に拾いあげられた言葉のひとつひとつから、それぞれの選択と生活がナマの手触りをもって伝わってきた。 暴走族、セクキャバ、建設会社…例えば先輩・後輩の上下関係や暴力には、今の一般的な社会規範ではあり得ないことだろう。しかし筆者はけして批判的な目線を持ち込まず、どのような背景や力学で暴力がふるわれ、ふるわれた側はそれをどう受け止めているのかを記述している。 これは筆者である打越さんが、"パシリ"という立場をとって、暴走族の若者たちのあとを原付で追いかけながら、長年実践したフィールドワークで得られたものである。 登場する人物はけして美化されてはいない。また置かれている過酷な環境でもあるが、それぞれの人生がこの先が気になるほど、葛藤やそのなかで行われる選択は、実感を持って描かれていた。 - 2025年1月31日
 食べるアネマリー・モル読み終わった学び!共食について考えて、先生のおすすめで読んだ。 自分にとってかなり思考の転換となった本。哲学的領域にも踏み込んだ、専門性が高い本であるが、食べるということの受け取り方は個人的に感覚としてしっくりくるところが多く、すっと読むことができた。 存在論的に、自分自身のの体験をある種のフィールドワークと扱って、食べることをとらえなおしている。 さらにはそこから「ある」「知る」「かかわる」といった行為のあり方を問い直す。
食べるアネマリー・モル読み終わった学び!共食について考えて、先生のおすすめで読んだ。 自分にとってかなり思考の転換となった本。哲学的領域にも踏み込んだ、専門性が高い本であるが、食べるということの受け取り方は個人的に感覚としてしっくりくるところが多く、すっと読むことができた。 存在論的に、自分自身のの体験をある種のフィールドワークと扱って、食べることをとらえなおしている。 さらにはそこから「ある」「知る」「かかわる」といった行為のあり方を問い直す。
読み込み中...

