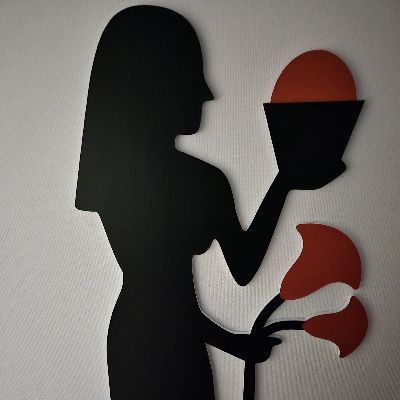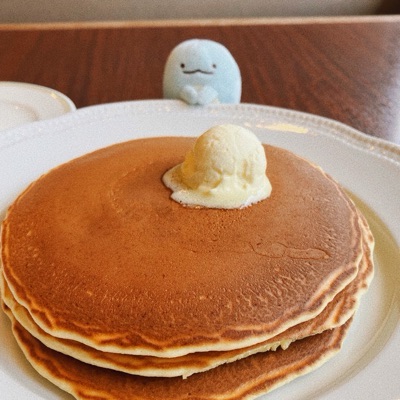ケアしケアされ、生きていく

31件の記録
 🪁@empowered_tako2025年7月19日かつて読んだ思い出した@ ファミレス「差別してない」と言いながら差別を正当化している政党の集会が昨日あって、抗議目的で行った。友人が誘ってくれて行くことができたのだが、ほんとうに嫌な場だった。疲れた。でも行っておいてよかったとも思う。 全員でげんなりしながら別の町に移動し、ファミレスであれこれ話した。その中で「迷惑かけるな」という圧、の話になった。「他人に迷惑をかけてはいけない」という圧があるよね。それがどんどん強化されていって呪いのようになっている。呪いの結果には障害者差別だってあるし、何かに声をあげること自体への反感もある。使う言葉や文化や振る舞いの違う人々が悪に見えてしまっているのも呪い起因かもしれない。前に『ケアしケアされ、生きていく』を読んでいたので、そういう見方をしている。 何らかの属性を持っている人らがなぜ悪に見えてしまうのか。その根っこには「素朴な不安」があるのかもしれない。だとしたら、その不安がケアされていない状態であることも問題なのかも。専門家がデータを引用しながら誤りを指摘することもめちゃ大事だけど、もしかするとそれだけでは不安が置き去りになっていてケアされていないんじゃないか…? とも考えている。
🪁@empowered_tako2025年7月19日かつて読んだ思い出した@ ファミレス「差別してない」と言いながら差別を正当化している政党の集会が昨日あって、抗議目的で行った。友人が誘ってくれて行くことができたのだが、ほんとうに嫌な場だった。疲れた。でも行っておいてよかったとも思う。 全員でげんなりしながら別の町に移動し、ファミレスであれこれ話した。その中で「迷惑かけるな」という圧、の話になった。「他人に迷惑をかけてはいけない」という圧があるよね。それがどんどん強化されていって呪いのようになっている。呪いの結果には障害者差別だってあるし、何かに声をあげること自体への反感もある。使う言葉や文化や振る舞いの違う人々が悪に見えてしまっているのも呪い起因かもしれない。前に『ケアしケアされ、生きていく』を読んでいたので、そういう見方をしている。 何らかの属性を持っている人らがなぜ悪に見えてしまうのか。その根っこには「素朴な不安」があるのかもしれない。だとしたら、その不安がケアされていない状態であることも問題なのかも。専門家がデータを引用しながら誤りを指摘することもめちゃ大事だけど、もしかするとそれだけでは不安が置き去りになっていてケアされていないんじゃないか…? とも考えている。




 橋本吉央@yoshichiha2025年5月7日読み終わったabout-nessとwith-ness。特にケアの文脈では、社会的弱者の抱える課題を、支援者が全て十全に解決できるわけではない。その前提で、with-nessの姿勢で、あなたの目の前の問題、あるいはあなたの辛さを一緒に考えるよ、という姿勢を示すことにも、大きな意味がある。 「尊厳の自立」と、生活史的にその人の生き様の意味をつなげていく、というところは、障害児者、特に重症心身障害児者福祉のキーワードでもあるかもしれない、と思った。 子育ての観点でも、読んでおくと良いのではと思う。子どもを意思表明の主体者として尊重することとはどういうことか、ということを、著者の実体験も踏まえてわかりやすく書いてくれている。 引用されている本が結構気になって、興味が広がる。積読が増えそう・・・
橋本吉央@yoshichiha2025年5月7日読み終わったabout-nessとwith-ness。特にケアの文脈では、社会的弱者の抱える課題を、支援者が全て十全に解決できるわけではない。その前提で、with-nessの姿勢で、あなたの目の前の問題、あるいはあなたの辛さを一緒に考えるよ、という姿勢を示すことにも、大きな意味がある。 「尊厳の自立」と、生活史的にその人の生き様の意味をつなげていく、というところは、障害児者、特に重症心身障害児者福祉のキーワードでもあるかもしれない、と思った。 子育ての観点でも、読んでおくと良いのではと思う。子どもを意思表明の主体者として尊重することとはどういうことか、ということを、著者の実体験も踏まえてわかりやすく書いてくれている。 引用されている本が結構気になって、興味が広がる。積読が増えそう・・・